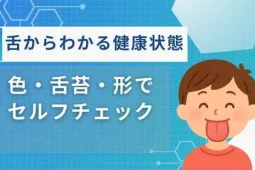食欲が止まらないのは病気のサイン?よくある疾患と対処法を紹介
公開日:2021.02.16 スタッフ ブログ 健康「最近、いくら食べてもお腹が空く」「間食がやめられない」などのお悩みを抱えていませんか?
一時的なストレスや睡眠不足が原因となることもありますが、実は食欲の異常が病気のサインであるケースもあります。
本記事では、食欲が止まらなくなる生理的な要因から、注意が必要な疾患、具体的な対処法や予防策までわかりやすく解説します。
「ただの食べ過ぎ」で片付けず、自分の体からのサインに気づくためのヒントとして、ぜひ参考にしてください。
目次
食欲が止まらない人によくある生理的な原因
「食欲が止まらない」と感じる場合、その背景には病気だけでなく、生理的な要因が関わっていることが多いです。
ここでは、日常的によく見られる生理的な原因について以下の4つを解説します。
- ストレス過多
- 睡眠不足・疲れの蓄積
- 糖質の摂りすぎ
- 糖質依存(生理前)|女性の場合
ストレス過多
ストレスを感じると、自律神経のバランスが乱れ、食欲をコントロールするホルモンの分泌に影響を及ぼします。
とくにストレスが長期化すると、脳が「快楽物質」であるドーパミンやセロトニンを得ようとし、高カロリーな食べ物を求める傾向が強まります。
「ストレス太り」という言葉があるように、無意識に間食や過食を繰り返すことで太ってしまう場合もあるのです。
睡眠不足・疲れの蓄積
睡眠不足は、食欲を刺激するホルモン「グレリン」の分泌を増やし、食欲を抑えるホルモン「レプチン」の分泌を減少させるといわれています。
その結果、満腹感を感じにくくなり、必要以上に食べてしまうことがあるのです。
また、慢性的な疲労も脳の判断力を鈍らせ、誤って「エネルギーを補給しなければ」と錯覚し食欲が過剰に高まる原因となります。
糖質の摂りすぎ
糖質を多く含む食品を頻繁に摂取すると、血糖値が急上昇・急降下しやすくなるため、空腹感が生じやすくなります。
とくに白米やパン、スイーツなどの精製された炭水化物は、血糖値の変動が激しく、短時間で再び強い空腹を感じる悪循環を生み出します。
このような食生活が続くと、常に「もっと食べたい」と感じる状態が続きやすくなるため、糖質制限などの手段を取ることが望ましいです。
糖質依存(生理前)|女性の場合
女性の場合、月経前にプロゲステロンというホルモンの分泌が増加し、体が栄養を蓄えようとするはたらきが強くなります。
これにより、普段よりも食欲が増す傾向があります。とくに甘いものや脂っこいものを欲しやすくなるのは、この影響です。
これは自然な身体の反応ではありますが、月経前の体調変化を理解しておくことで、過食を防ぐ意識づけにもつながります。
しばらく食欲が止まらないのは病気かも?考えられる疾患
一時的な生理的要因ではなく、数週間以上にわたって食欲が止まらない状態が続いている場合、何か疾患が隠れている可能性があります。
以下では、食欲異常と関係する代表的な疾患を紹介します。
- 2型糖尿病
- 甲状腺機能亢進症(バセドウ病)
- うつ病・双極性障害
- 過食障害(BED)
- 睡眠時無呼吸症候群
- クッシング症候群
2型糖尿病
2型糖尿病では、インスリンの効きが悪くなる「インスリン抵抗性」や、インスリンの分泌不足が起きることで、血糖値のコントロールが難しくなります。その結果、細胞に十分なエネルギーが届かず、常に空腹を感じてしまうのです。
さらに、血糖値が不安定になると満腹感を司るホルモンバランスも乱れやすく、食べてもすぐに空腹になる悪循環に陥ることがあります。
甲状腺機能亢進症(バセドウ病)
甲状腺ホルモンが過剰に分泌される甲状腺機能亢進症(代表的な疾患がバセドウ病)にかかると、身体の代謝を異常に高めるため、エネルギー消費が激しくなります。
エネルギー消費が過剰になることで、強い空腹感とともに、食べてもすぐにお腹が空く状態になるのです。
さらに症状が悪化すると、動悸、手の震え、汗が止まらない、体重減少などが見られる場合もあり、早期での医療機関の受診が推奨されます。
うつ病・双極性障害
うつ病や双極性障害などの気分障害では、脳内の神経伝達物質(セロトニンやドーパミンなど)の異常により、食欲のコントロールにも影響を及ぼすことが多いです。
とくにうつ病では「過食」または「拒食」のどちらかに偏ることがあり、ストレスや不安の反動で食欲が止まらなくなることもあります。
また、双極性障害では、躁状態の際に衝動的な過食が見られるケースもあります。気分が高まっているときには食べ過ぎる一方で、気分の落ち込みと同時に拒食状態になる場合もあるので、注意が必要です。
過食障害(BED)
過食障害の一種であるBED(Binge Eating Disorder:むちゃ食い障害)は、短時間に大量の食べ物を摂取する行為自体を止められないのが特徴です。
多くの場合、精神的ストレスや感情のコントロールの困難さが引き金となります。
過食の後に強い罪悪感を抱く人も多く、本人の意思だけでは改善が難しいため、専門機関への相談が推奨されます。
睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に何度も呼吸が止まり、十分な休息が得られない状態が続く疾患です。
SASにより睡眠の質が大きく低下すると、食欲を増進させるホルモン「グレリン」が増加し、逆に食欲を抑制する「レプチン」が減少することがわかっています。
結果として、必要以上に食べたくなる状態が続き、体重増加や生活習慣病のリスクも高まります。いびきがひどい、日中に強い眠気を感じるといった症状がある方は、早めに検査を受けるのがおすすめです。
クッシング症候群
クッシング症候群は、副腎から分泌されるホルモン「コルチゾール」が過剰に分泌されることによって起こる疾患です。コルチゾールはストレスに対抗するはたらきがありますが、過剰に分泌されると代謝や血糖値のコントロールに異常をきたし、強い食欲や脂肪の蓄積を引き起こします。
特徴的な症状として、顔が丸くなる(ムーンフェイス)、体幹部の肥満、皮膚の弱化、筋力低下などがあります。自己判断が難しいため、気になる症状があれば内分泌科を受診するのがおすすめです。
食欲が止まらない病気や後遺症へ|再生医療という選択肢
食欲が止まらない症状がしばらく続く場合は、速やかに医療機関へ相談するのがおすすめです。とくに糖尿病、甲状腺機能異常、精神的な要因など、専門医による検査が早期発見と適切な治療につながります。
病気が特定できたら、標準的な治療(薬物療法やホルモン療法など)を優先しましょう。
また、糖尿病の治療には、再生医療も選択肢の一つとなります。たとえば、幹細胞やiPS細胞を用いた研究では、摂食や睡眠をつかさどる神経回路の再構築に可能性が示されています。
もし食欲異常に向けた病気や後遺症の治療として、再生医療を検討したい方はリペアセルクリニックへご相談ください。ささいなお悩みやご希望に寄り添いながら、適切な治療法をご提案いたします。
まずは当院へお気軽にお問い合わせください。
\無料相談受付中/
食欲が止まらない状態を予防する方法
日常生活の中で、食欲の異常を未然に防ぐ方法はいくつかあります。
ここでは、誰でもすぐに実践できる生活習慣改善のポイントを紹介します。
- 1日3食を決めた時間によく噛んで食べる
- 散歩をはじめ適度に運動する習慣をつける
- 睡眠時間をしっかり確保する
- 食欲を抑えるツボを押す
1日3食を決めた時間によく噛んで食べる
食事を規則正しく摂ることは、体内時計(概日リズム)を整え、ホルモン分泌の安定にもつながります。
また、1口あたり30回以上を目安によく噛んで食べれば、脳の満腹中枢が刺激され、過剰な食欲を抑えられます。
早食いは血糖値の急上昇や消化不良の原因にもなるため、「ゆっくり食べる」習慣を意識するのが大切です。
散歩をはじめ適度に運動する習慣をつける
軽い有酸素運動は、食欲を適切にコントロールするホルモンバランスを整えるだけでなく、ストレス解消や睡眠の質向上にもつながります。
取り組む運動の具体例は、1日20分程度のウォーキングを週3以上取り入れる、1回あたり15分~30分のストレッチを就寝前に行うなどです。
また、運動によって筋肉量が維持されると、基礎代謝も高まり、脂肪の蓄積を予防できます。激しい運動でなくても、まずは歩くこと・伸ばすことなどから習慣化してみましょう。
睡眠時間をしっかり確保する
睡眠不足は食欲を増進させるグレリンを増やし、食欲抑制ホルモンであるレプチンを減少させます。そのため、食欲を抑えるには睡眠時間の確保も重要です。
なお、理想的な睡眠時間は7〜8時間とされており、年代によっても適正時間は変化するといわれています。また、睡眠は時間だけでなく、質を高めることも大切です。
まずは夜遅くのスマートフォン使用やカフェイン摂取を避け、寝る前にリラックスできる環境づくりから意識しましょう。
食欲を抑えるツボを押す
東洋医学では、特定のツボを刺激することで自律神経のバランスを整え、過剰な食欲を抑える効果が期待できるとされています。代表的な食欲を抑えるツボは以下の通りです。
| ツボの名前 | 概要 |
|---|---|
| 飢点(きてん) | 耳の前方にあるツボ。過食予防に効果的。 |
| 足三里(あしさんり) | ひざ下の外側。胃腸のはたらきを整える。 |
毎日数分、軽く押すことで食欲が安定しやすくなります。ただし、効果には個人差があるため、体調に合わせてツボを刺激しましょう。
まとめ|食欲が止まらない原因によって適切に対処しましょう
食欲が止まらない状態には、ストレスや生活習慣の乱れなどの一時的な要因のほか、糖尿病や甲状腺機能障害、精神疾患、睡眠障害も関与します。
放置すると生活習慣病や肥満のリスクが高まり、健康を損ねることも多いです。
思い当たる原因がある場合はまず生活習慣を見直し、それでも改善しない場合は医療機関を受診しましょう。
必要に応じて、再生医療などの新しい選択肢も視野に入れつつ、自分の身体と丁寧に向き合うことが、長期的な健康への第一歩です。
\無料オンライン診断実施中!/