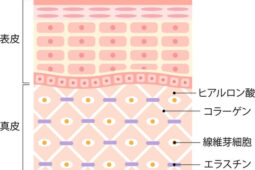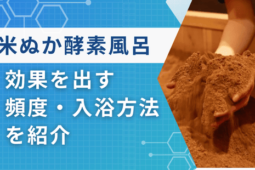医療コミュニケーションとは?安心して医療を受けるためのポイント
公開日:2021.05.18 スタッフ ブログ 豆知識「病院で先生に上手く症状を伝えられない」
「説明を聞いても、専門用語ばかりでよくわからない」
診療中の限られた時間で、上手く自分の思いを伝えられない経験を持つ人もいるでしょう。
患者様と医療従事者が信頼関係を築き、安心して医療を受けるには、医療コミュニケーションが欠かせません。
この記事では、医療コミュニケーションの重要性について解説します。患者様自身ができることや医療従事者に求められるスキルも紹介するので、より良い医療を受けられるよう、参考にしてください。
目次
医療コミュニケーションとは?
医療コミュニケーションとは、医療従事者と患者様の間だけでなく、医療従事者間で行われる情報のやり取りを指します。
診療や治療方針・検査結果の説明だけでなく、患者様の不安や希望を汲み取り信頼関係を築くのが目的です。医療現場では、単に医学的な情報を伝えるだけでなく、相手の理解度や心理状態に配慮したやり取りが求められます。
患者様が安心して医療を受けたり、主体性を持って治療に参加したりするには、質の高い医療コミュニケーションが欠かせません。
コミュニケーションが円滑に行われると、患者様は自身の状態を正確に理解し、納得した上で治療を選択できます。医療従事者にとっても、患者様の情報を深く理解し、より適切な医療を提供するための重要な基盤となるでしょう。
医療コミュニケーション不足で起こりうる問題点
医療コミュニケーションが不足していると、患者様との関係性や医療の質にさまざまな悪影響が生じます。単なる情報のやり取りが不十分であるだけでなく、信頼や安心感が損なわれることによって、治療そのものにも悪影響が及びます。
医療コミュニケーション不足によって、具体的にどのような問題が起こりうるのか詳しくみていきましょう。
患者様との信頼関係が崩れる
医療コミュニケーションが不足すると、患者様は医療従事者に対して不信感を抱きやすくなります。
たとえば、以下の状況では患者様の信頼を得るのは難しいでしょう。
- 医師からの説明が一方的である
- 患者様の質問や訴えに対して丁寧に向き合わない
患者様が医療従事者を信頼できなくなると、治療に対するモチベーションの低下や、医療機関への不満につながる可能性があります。信頼関係の崩壊は、患者様の治療効果にも悪影響を及ぼすため、医療コミュニケーションは信頼関係を築く上で非常に重要です。
診断や治療計画に誤解が生じる
コミュニケーションが不十分なまま診察が進むと、患者様が自分の症状や悩みを正確に伝えられないため、医師側の診断や治療計画に誤解が生じかねません。
たとえば、医師の説明が専門用語ばかりで理解しにくい場合、患者様は治療方針を誤って解釈してしまうリスクがあるのも事実です。誤解したまま治療を開始すると、想定外の副作用や不安が生じやすく、継続的な通院や服薬にも悪影響が出る可能性もあります。
医療チームの連携が上手く取れない
医療コミュニケーション不足は、医療チーム内の連携にも悪影響を及ぼします。
医師・看護師・薬剤師など、医療従事者間で患者様の情報が十分に共有されない場合、各専門分野からの視点が活かされません。治療方針の決定やケアの実施において認識のずれが生じる可能性があります。
具体例として考えられる状況は、以下の通りです。
- 医師から看護師への指示が正確に伝わっていない
- 看護師が気づいた患者様の状態変化が医師に報告されていない
医療チーム内での連携が上手く取れないと、適切なタイミングで必要な医療を提供できなくなるケースがあります。医療チームが上手く連携し、患者様に質の高い医療を提供するには、日頃からの活発なコミュニケーションが重要です。
症状や悩みを具体的に伝える
診察時は、以下の項目を参考に症状や悩みを具体的に伝えるのが大切です。
- いつから症状が出ているのか
- どのような症状なのか
- 症状の程度はどれくらいか
「なんとなく具合が悪い」のように曖昧な伝え方では、医師が正確な情報を把握できません。たとえば「昨日の夕食後から、お腹の右側がズキズキと痛む」と、具体的な症状や発症時期・程度などを詳しく伝えましょう。
また、症状に伴う不安や日常生活での困りごとなども伝えられると、医師はより患者様の状況を理解し、適切な診断や治療につなげられます。
医師の説明をメモする
医師から病状や治療法の説明を受けた際には、可能な範囲でメモを取るのがおすすめです。1度の説明だけでは、内容をすべて理解するのが難しい場面もあります。
メモを取ると、後から内容を振り返られるだけでなく、理解を深められます。なかでも、メモを取る項目としておすすめなのは、以下の項目です。
- 病名
- 薬の名前
- 検査内容
- 治療の流れ
もし、メモを取る時間がない場合は、家族や付き添いの人に同席してもらい、一緒に聞いてもらうのも良いでしょう。事前に、メモを取っても良いか医師に確認しておくのも大切です。
わからないことは質問する
診察中に医師の説明が理解できなかったときは、放置せず、質問するのが大切です。
専門用語が多くて理解できない場合や、治療法についてもっと詳しく知りたい場合など「こんなことを聞いても良いのかな」と遠慮する必要はありません。
納得のいかないまま治療が始まってしまうと、不安が大きくなり、治療へのモチベーションも薄れてしまいます。理解できていないと伝えられると、誤解や不安を防ぎ、医療への信頼感も高まります。
医師は患者様が理解できるように説明する義務があります。また、患者様が積極的に質問する行動は、より良い医療につながる大切な行動です。
自分の考えや希望を伝える
治療方針について、患者様自身の考えや希望があれば、遠慮せずに医師へ伝えましょう。たとえば「手術は避けたい」「できるだけ早く仕事に復帰したい」など、患者様の価値観やライフスタイルによって、望む治療法は異なります。
自分の考えや希望が伝わると、医師は患者様の意志を考慮した上で、より患者様に合った治療計画を立てられます。
医学的な観点から希望通りにならないケースもありますが、まずは自分の気持ちを伝えるのが大切です。患者様が主体性を持って治療に参加できると、満足度の高い医療につながるでしょう。
当院「リペアセルクリニック」では、メールによる無料相談も受け付けております。「受診すべきか悩んでいる」「治療方法について聞いてみたい」などお気軽にご相談ください。
\まずは当院にお問い合わせください/
医療を受ける際のコミュニケーションで大切なこと
安心して医療を受けるには、患者様自身もコミュニケーションに関わるのが重要です。自身の状態を正確に伝え、医師の説明をしっかり理解するなどで、より良い医療につながります。
ここでは、患者様が医療を受ける際のコミュニケーションで大切なことを紹介するので、参考にしてください。
医療従事者に必要なコミュニケーション能力
患者様が安心して医療を受け、治療に積極的に参加するためには、医療従事者側のコミュニケーション能力が欠かせません。単に医学的な知識を伝えるだけでなく、患者様の気持ちに寄り添い、信頼関係を築くためのスキルが求められます。
医療従事者が身につけるべき重要なコミュニケーション能力を詳しくみていきましょう。
アクティブリスニング
アクティブリスニングとは、患者様の言葉に注意深く耳を傾けるだけでなく、背景にある感情や意図を理解しようとする姿勢です。単に話を聞くだけでなく、相槌を打ったり質問したりすると、患者様に対して「あなたの話を真剣に聞いています」とメッセージを伝えられます。
また、患者様の言葉を要約して確認できると誤解を防ぎ、より深く理解できます。
アクティブリスニングは、患者様との信頼関係を築き、安心して自分の気持ちや症状を話せる環境を作る上で、非常に重要なスキルです。
エンパシー
エンパシーとは、患者様の立場になって考え、感情や状況に対する共感する能力です。
当院では、病気や怪我で不安を感じている患者様に寄り添って適切な言葉をお掛けし、愛情深い態度で対応いただくよう努めています。結果として、お互いに信頼関係を築け、心理的な安心感を提供できればと考えています。
エンパシーを示す行動は、患者様との間に心のつながりを築き、信頼関係を深める上で非常に重要です。
非言語コミュニケーション
非言語コミュニケーションとは、言葉以外の手段で情報を伝える方法を指します。言葉に加えて、表情や身振り手振り・目線や接する際の姿勢なども非言語コミュニケーションの手段です。
医療従事者の温かい笑顔や優しい眼差しは、患者様に安心感を与えます。逆に、不安そうな表情や冷たい態度は、患者様に不信感を与えてしまう可能性があります。
また、患者様の非言語的なサインを読み取るのも重要です。たとえば、顔をしかめている場合は痛みを訴えている可能性がありますし、視線を合わせない場合は何かを遠慮しているのかもしれません。
非言語コミュニケーションは、当院へ来院される患者様に対して、限られた時間で症状の辛さや、想いを把握するのに役立つと考えています。
患者様の症状や想いを引き出すために行う質問の基本は「5W1H」です。
|
コミュニケーションで大切な「5W1H」について ①Who(誰が) ➡️ 対象となるお客様 ②What(何を) ➡️ 質問の主題 ③When(いつ) ➡️ いつ起こったことか ④Where(どこで)➡️ 周囲の状況・環境 ⑤Why(どうして)➡️ 原因・理由 + ⑥How(どのように)➡️原因・理由を踏まえての対策 |
当院では「5W1H」を基本とした患者様に合った具体的な質問を実施しています。安全な治療のご提供と、安心して治療を受けていただけるように笑顔で看護サービスを提供できるように努めて参ります。
|
医療現場のコミュニケーション ・お客様の病歴 ・いつ頃から痛みや症状が出現したのか ・現在の痛み ・病状の状況 ・辛さの度合い ・症状など |
当院へお越しいただいた患者様に対して、私たちが日ごろ意識している「5WH」を利用したコミュニケーションについて記しました。
言葉だけでなく、非言語的な要素にも注意を払い、患者様とのより良いコミュニケーションを目指せるよう心がけております。
まとめ|医療コミュニケーションは患者様との信頼関係を築く重要なスキル
医療コミュニケーションは患者様と医療従事者間だけでなく、医療チーム間で行われる情報交換であり、医療現場において欠かせない手段です。
不足すると信頼関係の崩壊、診断や治療の誤解、チーム連携の不調を招きかねません。
患者様自身も症状を具体的に伝えたり、わからないことは質問するなどの行動が大切です。医療従事者は、アクティブリスニングやエンパシー(共感)など活用が、患者様との良好なコミュニケーションを築くための大切なポイントになります。
質の高い医療コミュニケーションは、患者様との信頼関係を築き、より良い医療の提供につながる重要なスキルといえるでしょう。
当院「リペアセルクリニック」では、患者様の症状や体調についての情報を正確に受け止められるよう適切な対応を行い、共感や理解を得て信頼関係を築ければと考えています。
気になる症状がありましたら、お気軽にご相談ください。
\まずは当院にお問い合わせください/
▼紹介