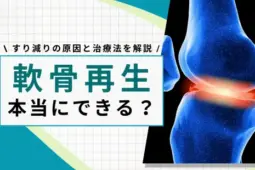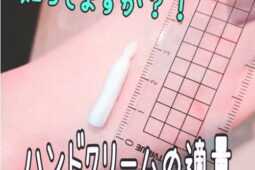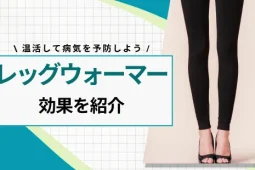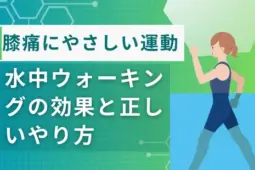【油の黄金比】オメガ3とオメガ6の「理想的なバランス」知っていますか?
公開日:2021.10.08 スタッフ ブログ 健康 豆知識
前回は、油は決して悪者ではなく、私たちの体にとって「非常に大切な栄養素」であるというお話をしました。特に「オメガ3・6・9」と呼ばれる油は、美容と健康の強い味方でしたね。
でも、ここでひとつ重要な落とし穴があります。
「体に良い油なら、何も気にせずどんどん摂ればいい」……実は、これは間違いなんです。
今回は、オメガオイルの効果を最大限に引き出すために知っておきたい、オメガ3とオメガ6の「摂取バランス(割合)」についてお話しします。
ただ摂るだけではもったいない!
賢く健康になるための「油の黄金比」をマスターしましょう。
目次
オメガ3とオメガ6は「正反対」の働きをする?
私たちが食事から必ず摂らなければならない「必須脂肪酸」。
これには、以下の2種類がありました。
| 1. オメガ3脂肪酸(エゴマ油、アマニ油、青魚など) 2. オメガ6脂肪酸(サラダ油、ゴマ油、大豆油など) |
どちらも体内で作ることができないため、食べ物から摂る必要があります。
しかし最近の研究で、この2つの油は、体内でお互いに「正反対の働き」をしていることが分かってきました。
分かりやすく言うと、体の防御反応(免疫)における「アクセル」と「ブレーキ」の関係です。
オメガ6は「アクセル」:戦う力
オメガ6は、体内に侵入した病原菌と戦うために白血球を活性化させたり、怪我をした箇所の血を止めたりする働きがあります。つまり、体を守るためにあえて「炎症」を起こす、アクセルの役割です。
オメガ3は「ブレーキ」:鎮める力
逆にオメガ3は、過剰になった白血球の働きを抑制し、炎症を抑える働きがあります。アレルギー症状を緩和したり、血液をサラサラにしたりする、ブレーキの役割です。
車もアクセルとブレーキの両方が揃って初めて安全に走れるように、私たちの体もこの2つの油がバランスよく存在して初めて、健康を維持できるのです。
目指すべき黄金比は「1:4」
では、具体的にどのくらいの割合で摂ればいいのでしょうか?
厚生労働省の推奨などを加味した、理想的なバランスはずばりこれです。
| 理想の割合 = オメガ3 : オメガ6 = 1 : 4 |
オメガ3が「1」に対して、オメガ6は「4」程度。このバランスが保たれているとき、私たちの体は最も調子が良いと言われています。
現代人のバランスは崩壊している!?
しかし、現代の日本人の食生活を調査すると、その割合はなんと「1 : 10」とも「1 : 20」とも言われています。
圧倒的に「オメガ6」を摂りすぎている状態です。
オメガ6(サラダ油や加工食品など)も必要な油ではありますが、比率が極端に増えすぎると、体のあちこちで「炎症(アクセル)」が効きっぱなしの状態になります。
これが、アレルギー症状の悪化や動脈硬化、生活習慣病のリスクを高める原因になってしまうのです。
バランスを整えるコツは「オメガ3」を意識すること
「大変!じゃあ今日からオメガ6を減らさなきゃ!」
そう思った方も多いはず。でも、外食や市販のお惣菜、スナック菓子など、現代の食事にはオメガ6がたっぷり使われており、これを極端に減らすのはなかなか難しいのが現実です。
そこで提案したいのが、「オメガ6を減らす」ことよりも、「オメガ3を増やす」ことに集中する作戦です!
今の食事スタイルは大きく変えず、意識的にオメガ3をプラスすることで、バランスを「1:10」から理想の「1:4」に近づけていきましょう。
今日からできるオメガ3チャージ
積極的に摂りたいのは、以下の食材やオイルです。
| 青魚を食べる | イワシ、サンマ、サバ、アジなどの青魚には、良質なオメガ3(DHA・EPA)がたっぷり。お刺身なら熱で油が壊れることもないので最高です。 |
| 「生オイル」を活用する | エゴマ油やアマニ油を1本常備しておきましょう。これらは熱に弱いので、加熱調理には使いません。 出来上がったサラダにドレッシングとしてかけたり、お味噌汁や納豆、コーヒーなどに小さじ1杯入れたりするだけでOKです。 |
まとめ:賢いバランスで健康を守ろう
オメガ3とオメガ6、どちらも私たちには欠かせない大切な油です。
重要なのは「偏らないこと」。
| オメガ3(魚、アマニ油) | 意識して積極的に摂る! |
| オメガ6(サラダ油、加工食品) | 無意識に摂れているので、摂りすぎに注意。 |
このイメージを持つだけで、あなたの細胞レベルでの健康状態が変わってくるはずです。
ぜひ今日のご飯から、「あ、これはオメガ3かな?」と意識してみてくださいね!