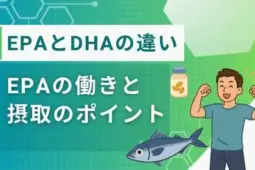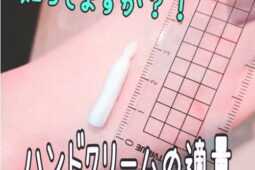食欲が止まらない原因とは|病気のリスクや対処法を解説
公開日:2021.02.16 スタッフ ブログ 健康「急に食欲が止まらない」「いくら食べても満足できない」と感じることはありませんか?
一時的な体調の変化やストレスが原因の場合もありますが、背後に重大な病気が隠れている可能性もあります。
放っておくと、糖尿病や摂食障害などの深刻な健康問題につながることもあり、注意が必要です。
本記事では、食欲が止まらない原因や考えられる病気、放置によるリスク、効果的な対処法をわかりやすく解説します。
なお、食欲が止まらない原因の一つである糖尿病に対しては、再生医療による治療という選択肢もあります。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施していますので、ぜひご登録ください。
目次
食欲が止まらない原因
食欲が止まらない原因は、ただの「食べ過ぎ」ではなく、体や心の状態が関係しているケースが少なくありません。
ここでは、疲れ・ストレスや不眠、満腹中枢の異常、生理との関係など主要な原因をわかりやすく解説します。
疲れ・ストレスが溜まっている
強いストレスや疲労が長く続くと、心が不安定な状態になり、「エモーショナルイーティング(感情による過食)」が起こる場合があります。
たとえば、仕事のプレッシャーや人間関係の悩み、不安が続くと、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が増え、甘いもの・脂っこいものを求める欲求が強くなるケースがあるのです。
また、満腹かどうかの判断が鈍くなり、心が満たされていないという「心理的な空腹」を埋めようとする傾向も出てきます。
睡眠が不足している
十分な睡眠が取れずに体内のホルモンバランスが乱れるのも、食欲が止まらない原因のひとつです。
睡眠不足により、空腹感を促す「グレリン」が多く分泌され、満腹感を伝える「レプチン」が減少するとされています。
普通なら満腹を感じる場面でも「まだ食べたい」と感じやすくなるわけです。
さらに、睡眠不足は判断力や衝動抑制をつかさどる脳の前頭前野の働きが弱くなるため、「食べたい」という欲求を理性的に抑えにくくなります。
栄養不足になっている
体が必要とする栄養素が不足していると、身体は足りない分を補おうとして食欲を強く働かせます。
たとえば、偏った食事や過度なダイエットで十分に栄養を取らないと、血糖値の乱高下が起こって「お腹が空いた」と感じる脳への信号が強まります。
その結果、食欲を止められない状態になるわけです。
とくに、エネルギー源となる糖質や体をつくるタンパク質が不足していると、甘いものや炭水化物などを無意識に欲するようになる傾向があります。
満腹中枢に異常をきたしている
人は、胃や腸の状態や血糖値、ホルモンからの信号を脳が受け取ることで「もうお腹いっぱい」と感じます。
この仕組みをつかさどるのが「満腹中枢」です。
満腹中枢の働きがうまくいかないと、いくら食べても満足できない場合があります。
たとえば、食欲抑制ホルモンがうまく作用しない「レプチン抵抗性」という状態では、脂肪が増えて満腹ホルモンのレプチンが多く分泌されても、脳がその信号を適切に受け取れなくなり、満腹感を感じにくくなるのです。
さらに、脳の視床下部という食欲をコントロールする部分の異常や、生まれつきの病気によって満腹中枢自体が弱っている場合もあります。
女性の場合は生理が関係している
女性の場合は、生理前に卵巣で作られる女性ホルモンの一種である「プロゲステロン」の分泌が増え、女性ホルモンの「エストロゲン」の量が変わることで、身体が栄養やエネルギーを蓄えようとする働きが強まります。
その結果、甘いものや脂肪分、塩分などを欲することが多くなるのです。
さらに、ホルモンの変動は血糖値の変動やセロトニンの分泌の変化も引き起こし、気分が不安定になったり、食欲を抑えにくくなったりする場合もあります。
食欲が増えて止まらないのは病気の可能性も
日常的に「とてもお腹が空いている」「食べてもすぐにまた食べたくなる」という状態が続くなら、単なるストレスや生活習慣だけでなく、何らかの病気が原因かもしれません。
ここでは、食欲が止まらないときに疑われる代表的な疾患について解説します。
過食性障害
過食性障害とは、空腹や栄養不足とは無関係に、衝動的に多く食べすぎてしまうのを繰り返す精神疾患です。
食べる量や速さ・タイミングなどを自分でコントロールできないのが特徴で、罪悪感・自己嫌悪を伴うケースも少なくありません。
過食性障害では食べ物を前にすると我慢できず、「食べ始めたら止まらない」「空腹でなくてもつい食べてしまう」などの症状が見られます。
とくに、生活の質が低下するほど精神的な負担が大きくなるケースには要注意です。
神経性過食症
神経性過食症は、過食後に体重増加を防ぐために嘔吐・下剤・過度の運動などの代償行為を伴う摂食障害の一種です。
過食性障害と異なり、見た目や体重に対する強い不安や恐怖を避けるための行動が取られます。
過食行為が頻繁であることや代償行為の有無、体重に対する心理的影響などが診断のポイントです。
食欲が止められない状況が精神的な苦痛を伴いつつ繰り返されているなら、神経性過食症の可能性があります。
2型糖尿病
血糖をコントロールするインスリンが働かなくなる「2型糖尿病」にかかると、血中の糖分が細胞にうまく取り込まれない場合があります。
その結果、体はエネルギー不足を感じ、より多く食べたがる状態になるケースがあるのです。
食欲が止まらないのに体重が減る、または体調が安定しない状態が続くなら、診察・血糖検査を受けましょう。
甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)
甲状腺機能亢進症とは、首の前にある甲状腺からホルモンが過剰に分泌される病気です。
甲状腺ホルモンは体の代謝を調整する働きを持っており、出すぎると新陳代謝が必要以上に活発になります。
その結果、体が多くのエネルギーを消費するため、それを補おうとして強い食欲が出てしまう場合があるのです。
しかし、いくら食べても代謝によるエネルギー消費が食事による摂取を上回るため、食欲があるのに体重が減っていきます。
また、大量の汗をかく、心臓がドキドキする、手が震えるなど日常生活に支障をきたすケースもあります。
うつ病・双極性障害
うつ病や双極性障害とは、「気分障害」とも呼ばれている精神疾患群です。
とくに、双極性障害の躁状態や一部のうつ病、もしくは非定型うつ病の期間に過食傾向が見られることが知られています。
食べる行為が気分の浮き沈みと連動していたり、悲しさ・空虚感を紛らわすために食べるようになったりする傾向もあります。
クッシング症候群
クッシング症候群は、「コルチゾール」というホルモンが過剰に分泌され続けることで発症する内分泌疾患です。
たとえば、次のような症状があります。
- 食欲が異常に増す
- 体重が急増する
- 顔が丸くなる
- 腹部が出る
- 皮膚が薄くなる
- 骨が弱くなる
- 疲労感や脱力感が強くなる
また、高血圧・血糖値上昇・月経異常なども合併するケースがあるため、とくに複数の異常が見られる場合は注意が必要です。
食欲が止まらないのを放置するとどうなる?
食欲が止まらない状態を放置しておくと、身体と精神にさまざまな悪影響が現れ、生活の質が大きく損なわれる可能性があります。
ここでは、食欲が止まらない状態を放置した際に生じるリスクを解説します。
糖尿病を患う
食欲が止まらずに過食を続けていると、カロリーや糖質の摂取が過剰になり、体重が増加して肥満の状態に陥ります。
肥満が進行すると、血糖を調整するホルモンであるインスリンの効きが悪くなる「インスリン抵抗性」が生じやすくなり、2型糖尿病を発症する場合があるのです。
糖尿病になると、血糖値が慢性的に高い状態が続き、以下のような症状が現れるケースがあります。
- 視力低下を招く網膜症
- 腎機能が低下する糖尿病性腎症
- 手足のしびれや痛みを引き起こす神経障害
さらに高血糖状態が続けば、動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞といった重大な循環器疾患にもつながる可能性があります。
過食の放置は、糖尿病を含む深刻な生活習慣病のリスクを高める可能性があるのです。
以下の記事では、糖尿病の初期症状などについて解説しています。
逆流性食道炎になる
食欲が止まらずに過食を続けていると、胃の中に常に大量の食べ物が溜まり、腹圧が高まる状態が続きます。
胃と食道の境目にある括約筋の働きが弱まって胃酸が食道へ逆流しやすくなり、炎症を起こす「逆流性食道炎」を発症する可能性が高まるのです。
逆流性食道炎を放置すると、胸やけや呑酸などの不快な症状が慢性化するだけでなく、食道潰瘍や食道狭窄、さらには前がん状態であるバレット食道に進行する恐れもあります。
摂食障害になる
食欲が止まらない状態が長く続いてしまうと、過食性障害や神経性過食症といった摂食障害に進むケースがあります。
症状によって体への影響はさまざまで、嘔吐や下剤の乱用を伴う場合には体内のカリウムが不足し、不整脈などの危険が高まります。
一方、極端に体重が減る神経性やせ症では、無月経や骨粗しょう症といったホルモンや骨に関わる症状が生じます。
また、「食べすぎてしまった」という自己嫌悪を繰り返すことで抑うつや不安が強まり、心身ともに生活へ大きな支障をきたす恐れがあるため、早めの対処が大切です。
食欲が止まらない場合の対処法
食欲が止まらないなら、まず原因を理解してからの適切な対策が重要です。
ここでは、食欲が止まらないときの対処法をいくつかご紹介します。
しっかり睡眠時間を確保する
睡眠不足は、食欲を制御するホルモンのバランスを乱します。
眠りが浅い、また時間が短いときに食欲が強くなる傾向があるため注意が必要です。
たとえば、就寝前にスマートフォンの使用を避ける、寝る前の環境を整えて静かで暗くする、寝る時間と起きる時間を一定にするなどの方法で対処しましょう。
適度に運動する
定期的な運動は、食欲の調整に役立ちます。
軽いウォーキングやストレッチ、ヨガなどは気分を安定させるだけでなく、満腹感を感じやすくするための体内の代謝やホルモン機能を改善するとされています。
たとえば、歩数を増やすなど日常の活動量を上げることで、体重オーバーやBMIの改善が可能です。
ただし、体に負担が大きい過度な運動は避け、毎日続けやすい軽い運動を習慣にしましょう。
ゆっくり食べる
食事をゆっくり食べることは、満腹中枢を十分に働かせるために重要です。
口に入れてからよく噛むと、脳が「もう十分だ」という信号を受け取りやすくなります。
早食いや「ながら食べ」は、満腹を感じる前に多く食べてしまう原因になるため注意しましょう。
テレビを見ながら、スマホを触りながらではなく、食事の時間に集中してください。
また、野菜を先に食べるなど順番を工夫すると、血糖値の急上昇を抑えるのにも有効です。
1回の食事量を減らす
1回の食事で食べる量を減らし、回数を分けることも有用です。
たとえば、3食のうち1食を少なめにして間食や軽めのものを追加すると、空腹の波が小さくなって過剰な食欲が抑えられます。
また、タンパク質・食物繊維・脂質などをバランスよく組み合わせれば、満腹感が持続しやすいとされています。
ただし、急激に量を減らしすぎると反動で食べ過ぎてしまうので、無理のない範囲で減らしましょう。
ツボを押す
強い食欲が襲ってきたときには、ツボを使って気を紛らわせたり、自律神経を整えたりする方法があります。
適切に圧をかけてマッサージすることで、胃の調子が整ったり、ストレスが和らいだりする効果が期待できます。
ただし、食欲が止まらないときの医学的な有効性は確立されていない点に留意しておきましょう。
病院を受診する
さまざまな工夫をこらしても食欲が止まらない、コントロールできない場合には専門医の診察を受けましょう。
身体のホルモン異常や精神的な要因が背景にあるケースが多いため、内科・精神科などを受診してください。
医師に相談すれば、薬物療法や心理療法・栄養指導などの専門的なアプローチが可能になり、重症化や合併症の予防につながります。
まとめ|食欲が止まらないのは病気のサインかも?医療機関の受診を検討しよう
急に食欲が止まらなくなったとき、「つい食べ過ぎてしまった」と軽く考えて放置するのは危険です。
原因がストレスや生活習慣の乱れによる一時的なものであれば、睡眠・運動・食事の見直しで改善できる場合もあります。
しかし、ホルモンバランスの異常や摂食障害、糖尿病などの病気が隠れている可能性もあるため、異変が長引く場合は要注意です。
自己判断で我慢を続けるのではなく原因を見極めたうえで、睡眠時間の確保や適度な運動、ゆっくり食べるなどを習慣化して早めに対処してください。
また、食欲が止まらないことで生活に支障が出ているなら、早めに医療機関を受診しましょう。
なお、当院「リペアセルクリニック」では、公式LINEにて再生医療に関する情報や簡易オンライン診断を実施していますので、ぜひご利用ください。
\無料オンライン診断実施中!/
食欲が止まらないに関するよくある質問
食欲が止まらない場合に処方される薬はありますか?
食欲が止まらない場合、医療機関では薬による治療がおこなわれるケースがあります。
代表的な薬は「サノレックス(一般名:マジンドール)」で、厚生労働省に肥満症治療薬として承認されている食欲抑制剤です。
おもに高度肥満症の患者に対して、食事療法や運動療法だけでは十分な効果が得られないときの補助として処方されます。
ただし、服用には健康状態などに厳格な基準があるほか、副作用や依存性のリスクもあるため、医師の指導が必要です。
自己判断での使用は危険なので避けてください。
更年期に食欲が止まらない場合があるのは何故ですか?
更年期に食欲が止まらなくなるのは、おもに女性ホルモンの変化が関係しています。
卵巣から分泌される女性ホルモンの一種「エストロゲン」の分泌が減少すると、食欲を抑えるホルモンのバランスが崩れやすくなり、満腹感を得にくくなる場合があるのです。
また、ホルモンの影響で自律神経が乱れ、ストレスや不眠が生じることで「感情による食欲(エモーショナルイーティング)」が起こりやすくなります。
加えて、更年期には筋肉量の減少や代謝の低下も重なるため、体がエネルギー不足を感じて無意識のうちに食欲が増してしまうケースも少なくありません。
女性の更年期障害については、以下の記事でも詳しく取り上げています。
食欲が止まらないで太るとどんな健康リスクがありますか?
食べ過ぎによる体重増加は、糖尿病・高血圧・脂質異常症などの生活習慣病を招きます。
また、心筋梗塞や脳卒中といった重大な疾患のリスクも高まるため、早期の体重管理が重要です。
夏でも食欲が止まらないことはありますか?
夏は、冷房による自律神経の乱れや水分不足、冷たいものの摂り過ぎで胃腸機能が低下し、逆に食欲が増す場合があります。
冷え対策をおこなうほか、バランスのよい食事も大切です。
男性で食欲が止まらない理由は何ですか?
男性の過剰な食欲はストレスや睡眠不足、栄養バランスの乱れがおもな原因です。
生活習慣を整えると、食欲をコントロールしやすくなります。