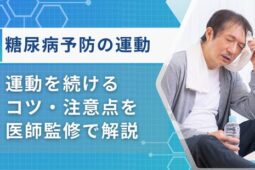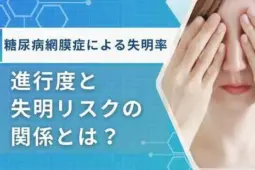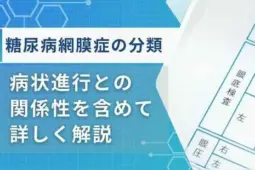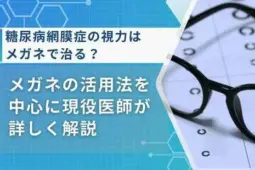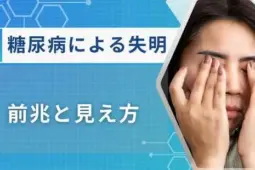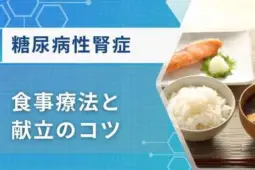- 糖尿病
- 内科疾患
糖尿病は1型と2型どちらが多い?治療法・それぞれの違いを解説

厚生労働省の調査によると、2019年時点で20歳以上のうち、糖尿病が強く疑われる人は約1,196万人。
予備軍も含めると、実に2,000万人以上が糖尿病リスクを抱えていることがわかっています。
それだけ多くの人が悩む病気ですが、「糖尿病」と一口にいっても、実は「1型」と「2型」の2つのタイプがあるのをご存知でしょうか。
今回は、糖尿病について「1型糖尿病」「2型糖尿病」それぞれの違いや特徴、治療法についてわかりやすくご紹介します。
目次
糖尿病は1型より2型の方が多い
糖尿病には1型と2型の2種類がありますが、実際に患者数が多いのは2型糖尿病です。
厚生労働省の2023年「患者調査」によると、現在治療を受けている糖尿病患者は全国で約552万人。
そのうち2型糖尿病の人は約364万人にのぼり、全体の65%以上を占めています。(参考1)
いっぽうで、1型糖尿病の患者数は約12万人とされ、全体の中ではごくわずかです。
さらに、「その他の糖尿病」に分類されている約176万人の多くも、実際には2型に含まれる可能性が高いため、糖尿病の9割以上が2型と考えられています。
2型糖尿病は、中高年以降に発症しやすく、生活習慣が深く関係しているのが特徴です。
それに対して1型糖尿病は、自己免疫の異常などが原因とされ、年齢に関係なく発症するものの、子どもや若者で多く見られる傾向があります。
1型糖尿病とは?原因や症状を詳しく解説
1型糖尿病は、膵臓のランゲルハンス島という部分にあるβ細胞が壊され、その結果、血糖を下げる役割があるインスリンを作り出せずに高血糖の状態が続く疾患です。
糖尿病全体のうち、1型は約5%程度と少数派ですが、先天的な体質や遺伝的素因が関与しているとされ、生活習慣とは関係なく若い人を中心に幅広い年齢で発症します。
1型糖尿病の主な原因とは?
1型糖尿病でなぜβ細胞が壊れるのかは現時点では判明していませんが、免疫反応が正しく働かず、自分の細胞にもかかわらず、外部から侵入しようとしてきた細菌・ウイルスなどの有害物質などと間違って攻撃してしまう、自己免疫反応がかかわっていると考えられています。
そのため、生活習慣病が大きな原因である2型糖尿病とは異なり、注射によってインスリンを補う必要があります。
1型糖尿病の3つのタイプ(劇症・急性・緩徐進行)
β細胞の破壊は一般的には進行性で、病気が進行すると、ほとんどインスリンを出せなくなります。
1型糖尿病は、β細胞が破壊される進行スピードによって、下記のように分類されます。
劇症1型糖尿病
発症から1週間程度でインスリン依存状態になるタイプです。
そのため、すぐにインスリンを補充しなければ、糖尿病の急性合併症である「糖尿病ケトアシドーシス」となり重症になる可能性があります。
急性発症1糖尿病
1型糖尿病で最も頻度の高いタイプで、糖尿病の症状が出てから数ヶ月でインスリン依存状態になります。
人によっては、発症したすぐ後であれば、一時的に残っている自己のインスリン効果がある場合もありますが、長続きせず、その後は再びインスリン治療が必要です。
緩徐進行(かんじょしんこう)1型糖尿病
半年~数年と比較的ゆっくりとインスリン分泌が低下していくタイプです。
発症した最初は、2型糖尿病と同じようにインスリン注射を使わなくても血糖値を抑えることができます。
しかし、途中で血液検査の結果から、実は緩徐進行1型糖尿病だったと判明する場合が多くあります。
1型糖尿病の治療方法
1型糖尿病は、原則としてインスリン療法が必要です。
また原因として、生活習慣の乱れということはありませんが、薬物療法だけでは、重度の低血糖になる可能性があるため、2型糖尿病と同じように食事・運動習慣に注意します。
1型糖尿病の食事療法
基本的に食べてはいけない物はありません。
1人ずつ生活スタイル・インスリン治療法が違うため、普段の食事方法については、主治医・管理栄養士としっかり話し合うことが重要です。
また、炭水化物は食後の血糖値の上昇に大きくかかわります。
そのため、炭水化物を調整する方法である「カーボ(炭水化物)カウント」をおこない、食事の炭水化物量に合わせてインスリンの量を調節する。
もしくは、インスリン治療に合わせて食事の炭水化物の量を調節すると血糖値が安定しやすくなります。
1型糖尿病の運動療法
重い合併症がなく、血糖値が落ち着いていれば、運動の制限はありません。
実際に、プロのスポーツ選手も存在します。
しかし、運動する際は、低血糖に注意が必要なため、インスリン療法や補食を調整します。
どのような方法が推奨されるかは、1人ずつ異なるため、主治医の先生と相談して決めることが重要です。
\まずは当院にお問い合わせください/
2型糖尿病とは?原因と3つのリスク
2型糖尿病は、糖尿病の中で最も多く、いわゆる「生活習慣病」として知られています。
膵臓から分泌されるインスリンの働きが悪くなったり、十分に作られなくなることで、血糖値が高い状態が続く病気です。
原因は1つではなく、遺伝的な体質に加えて、加齢や生活習慣の乱れがきっかけとなって発症する、後天的な疾患としての側面が強いのが特徴です。
食生活の乱れや運動不足などの生活習慣が深く関係していると言われています。
2型糖尿病の原因
「糖尿病=生活習慣の問題」と思われがちですが、それだけではありません。
2型糖尿病は、遺伝的な体質と生活習慣が積み重なって発症するケースが多いのが特徴です。
たとえば、家族に糖尿病の人がいると、体質的に血糖値が上がりやすいことがあり、そこに運動不足や過食、ストレスなどが加わることで発症のリスクが高まります。
空腹感や口の渇き、頻尿、視界のかすみなどの初期症状が現れたら、早めの検査が大切です。
2型糖尿病の3つのリスク(肥満・遺伝・生活習慣)
2型糖尿病の発症には、以下のようなリスクが深く関わっています。
- 肥満・内臓脂肪の蓄積
体重が増えるとインスリンの効きが悪くなり、血糖値が下がりにくくなります。 - 遺伝的な体質
親や兄弟に糖尿病の人がいると、発症のリスクが高くなります。 - 不規則な生活習慣
運動不足や食べすぎ、夜遅い食事、ストレスなどがインスリンの分泌・作用に悪影響を与えます。
これらの要素が重なることで、発症リスクが高まるため、普段から生活を見直すことが予防にもつながります。
2型糖尿病の治療方法
2型糖尿病の治療には、大きく分けて「食事療法」「運動療法」「薬物療法」があります。
中でも、食事と運動による生活習慣の見直しは、治療の基本とされています。
特に初期の段階では、食事と運動だけで血糖値を安定させられることもあるため、医師の指導のもと、できるだけ早く生活改善に取り組むことが重要です。
薬物療法が必要になる場合もありますが、今回は特に「食事療法」と「運動療法」について詳しく解説していきます。
2型糖尿病の食事療法
2型糖尿病の管理において、食事の工夫はとても大切です。
基本は、栄養バランスの取れた食事を心がけること。
糖質の摂りすぎを避けつつ、主食・主菜・副菜の3つをしっかり揃えるよう意識しましょう。
また、食べ方もポイントです。
「ゆっくりよく噛んで食べる」「夜遅くに食事をしない」といった食習慣の見直しも血糖コントロールに役立ちます。
さらに、1日に必要なカロリーを把握することも大切で、適正な摂取カロリーは、以下の式でおおよそ求められます。
標準体重(kg)=身長(m)×身長(m)×22
必要エネルギー量=標準体重 × 身体活動量(25〜30程度)
計算例)
たとえば、身長160cm・軽めの活動量の人なら、
1.6×1.6×22=56.3kg(標準体重)
56.3×25~30=1407~1689kcal/日が目安です。
炭水化物:50~60%
たんぱく質:15~20%
脂質:20~25%
数字ばかりで難しく感じるかもしれませんが、医師や管理栄養士と相談しながら、自分に合った食事スタイルを見つけていくことが大切です。
2型糖尿病の運動療法
運動は、2型糖尿病の改善に欠かせない習慣のひとつです。
体重の管理や心肺機能の向上だけでなく、血糖値を下げる効果やインスリンの働きを助ける効果も期待できます。
特に2型糖尿病の人は、食事療法と運動療法を組み合わせることで、より血糖コントロールが安定しやすくなると言われています。
運動の種類には主に2つあります。
- 有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、水泳など)
- レジスタンス運動(筋トレなど)
糖尿病への運動療法は、ダンベルなどを使用して筋肉に負荷をかけるレジスタンス運動より、歩行やジョギング、水泳などの全身運動にあたる有酸素運動のほうがインスリンの働きがよくなるため、糖尿病の管理に適しています。
運動の目標として、1日20~60分程度の運動をできれば毎日、もしくは週3回以上。
合計で週150分以上を目指すと効果的です。
また、可能であれば週に2~3回程度、有酸素運動とともにレジスタンス運動を組み合わせることで、体力や筋力アップにもつながります。
\まずは当院にお問い合わせください/
その他の糖尿病
糖尿病は「1型」と「2型」だけではなく、実はその他のタイプもあります。
たとえば、妊娠中に発症する「妊娠糖尿病」や、薬の副作用・病気などが原因で起こる「二次性糖尿病」などがあります。
妊娠糖尿病
妊娠中に一時的に血糖値が高くなるタイプで、出産後には自然と治ることも多いですが、将来的に2型糖尿病になるリスクがあるため注意が必要です。
二次性糖尿病
ステロイド薬の長期使用や、ホルモン異常、膵臓の病気などが原因で起こる糖尿病です。
原因となる病気や薬を見直すことが、改善のポイントになります。
これらの糖尿病も早期発見と治療がとても大切です。
いつもと違う体調の変化があれば、放置せずに病院で相談するようにしましょう。
まとめ|生活習慣を整えて糖尿病を予防しよう
糖尿病には「1型糖尿病」と「2型糖尿病」の2つのタイプがあります。
1型糖尿病は自己免疫反応によって膵臓のβ細胞が破壊され、インスリンを生成できなくなる疾患です。主に先天的な要素が強く、急性発症型や緩徐進行型などがあり、治療にはインスリン補充が必要となります。
一方、2型糖尿病は生活習慣の乱れや遺伝的要因により膵臓のインスリン分泌が低下する疾患で、「生活習慣病」としても知られています。治療は食事療法や運動療法が中心となり、適切な体重管理と運動が重要です。
どちらのタイプでも共通して大切なのは生活習慣を整えることです。バランスのとれた食事と適度な運動を習慣づけることで血糖値を安定させやすくなります。
また、信頼できる主治医との相談や定期的な健康診断も欠かせません。糖尿病の予防や治療法に悩んでいる方も、まずはできることから少しずつ始めてみましょう。
当院では、糖尿病に対する再生医療を提供しております。再生医療に関する詳細は、以下のページをご覧ください。

糖尿病のお悩みに対する新しい治療法があります。
(文献1)
日本生活習慣病予防協会「糖尿病で治療を受けている総患者数は、552万3,000人 令和5年(2023)「患者調査の概況」より」
https://seikatsusyukanbyo.com/statistics/2025/010845.php(最終アクセス:2025年4月27日)