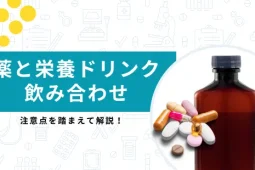【油の基礎知識】オメガ3・6・9の違いとは?健康に必要な「体に良い油」の選び方
公開日:2021.03.02 スタッフ ブログ 健康 豆知識
「油(脂質)」と聞くと、皆さんはどんなイメージを持ちますか?
ダイエット中の方なら、「太るから敵!」「できるだけ避けるべきもの」と思ってしまいがちですよね。
でも実は、油(脂肪)は、私たちが生きていくために欠かせない炭水化物やタンパク質に並ぶ「3大栄養素」のひとつなんです。
もちろん摂り過ぎれば肥満や生活習慣病の原因になりますが、逆に控え過ぎてしまうと、免疫力が下がったり、お肌がカサカサに乾燥してしまったりと、美容と健康に悪影響を及ぼすこともあります。
大切なのは「油を断つこと」ではなく、「体に良い油を選んで摂ること」。
最近よく耳にする「オメガ3・6・9系オイル」。
これらが一体どんな油で、私たちの体にどう良いのか、スーパーでどの油を選べばいいのか、わかりやすくお話ししていきますね。
目次
まずは基本!油は「固まるか、サラサラか」で分かれる
油について詳しくなるための第一歩は、大きく2つの種類があることを知ることから始まります。
少し専門的な言葉になりますが、「飽和脂肪酸(ほうわしぼうさん)」と「不飽和脂肪酸(ふほうわしぼうさん)」という言葉、聞いたことはありませんか?
名前は覚えなくても大丈夫。「常温で固まるか、液体のままか」というイメージを持つだけでOKです!
常温で固まる「飽和脂肪酸」
バターやラード(豚の脂)、牛脂、ココナッツオイルなどがこれにあたります。
冷蔵庫に入れたり、冬場の寒い部屋に置いたりすると白く固まりますよね? 肉類や乳製品など、動物性の脂肪に多く含まれるのが特徴です。
エネルギーとして大切ですが、摂り過ぎると悪玉(LDL)コレステロールを増やし、血液ドロドロの原因になってしまうことも。体内で作ることもできる油なので、現代の食生活では「意識して控える」くらいでちょうど良いかもしれません。
常温でサラサラな「不飽和脂肪酸」
今回の主役はこちらです!
オリーブオイルやゴマ油、魚の油など、植物や魚に含まれる油のこと。これらは低い温度でも固まりにくく、常温では常にサラサラとした液体です。
この「サラサラした油」の中に、健康のカギを握る「オメガ3・6・9」が含まれているんです。
体内で作れない?重要なのは「必須脂肪酸」かどうか
さて、ここからが本題です。
同じ植物性のサラサラした油でも、「オメガ3」「オメガ6」「オメガ9」のどれに分類されるかで、体への働きかけが全く違います。
ここで一番のポイントになるのが、「自分の体の中で作れるか、作れないか」という点です。
人間が体内で作り出すことができない油のことを「必須脂肪酸」と呼びます。
「必須」という名前の通り、「食事から必ず摂らなければならない、生きていくために必要な油」という意味です。
では、それぞれのオイルの特徴を見ていきましょう。
【オメガ9系】加熱に強い万能選手(オレイン酸)
| 代表的な油:オリーブオイル、アボカドオイル、米油など |
オリーブオイルに代表されるオメガ9系(オレイン酸)は、実は体内で作り出すことができるため、「必須脂肪酸」ではありません。でも、健康効果は抜群です。
最大の特徴は「酸化しにくい(熱に強い)」こと。
加熱調理に使っても油が劣化しにくいので、炒め物など普段のお料理にとても使いやすいんです。
さらに嬉しいのが、善玉(HDL)コレステロールは下げずに、悪玉(LDL)コレステロールだけを下げてくれる働きがあること。腸の働きを活発にして便秘予防にも役立つと言われているので、毎日の食卓のメインオイルとしておすすめです。
【オメガ6系】摂りすぎに注意したい必須脂肪酸(リノール酸)
| 代表的な油:サラダ油、ゴマ油、コーン油、グレープシードオイルなど |
こちらは体内で作ることができない「必須脂肪酸」です。
「じゃあ、たくさん摂らなきゃ!」と思うかもしれませんが、実はちょっと注意が必要な油なんです。
オメガ6系(リノール酸)は、コレステロール値を下げる効果がある一方で、摂りすぎるとアレルギーや炎症を悪化させたり、動脈硬化のリスクを高めたりすると言われています。
現代の食生活では、加工食品や外食、スナック菓子などにこのオメガ6系の油が多く使われているため、知らず知らずのうちに「過剰摂取」になりがち。
「意識して摂る」というよりは、「質の良いものを選んで、摂りすぎないように気をつける」というスタンスが正解です。
【オメガ3系】現代人に一番足りない油(α-リノレン酸)
| 代表的な油:アマニ油、エゴマ油、青魚(DHA・EPA)など |
今、最も注目されているのがこのオメガ3系です。
オメガ6と同じく体内で作れない「必須脂肪酸」ですが、こちらは現代人に圧倒的に不足していると言われています。
オメガ3には、血中の中性脂肪を減らして血液をサラサラにしたり、脳の働きを助けたり、アレルギーなどの炎症を抑えたりと、素晴らしい効果がたくさん!
ただし、非常にデリケートで熱に弱いという弱点があります。
加熱調理には向かないので、ドレッシングとしてサラダにかけたり、お味噌汁や納豆に食べる直前に回しかけたりと、「生のまま」食べるのがコツです。
まとめ:油の特徴を知って使い分けよう
いかがでしたか?
油といっても、「控えるべき油」もあれば、「積極的に摂るべき油」もあることがお分かりいただけたでしょうか。
| オメガ9(オリーブ油など) | 加熱料理に使いやすく、悪玉コレステロール対策に。 |
| オメガ6(サラダ油など) | 体に必須だけど、摂りすぎには注意。 |
| オメガ3(アマニ油・青魚) | 現代人に不足しがち。熱を加えず生で積極的に! |
スーパーにズラーッと並ぶ油の棚を見たときは、ぜひこの話を思い出して、目的に合わせた「体に良い油」を手に取ってみてくださいね。
「よし、じゃあ体に良いオメガ3をボトルで飲もう!」
……と思った方、ちょっと待ってください! 実は油の摂り方には、健康効果を最大にするための「黄金比」があるんです。
次回は、知らないと損をする「オメガオイルの摂取割合(バランス)」について、詳しくお話ししますね。
▼次は、知っておきたいオメガ油の「摂取割合」について!