
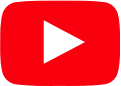
動画でみるインタビュー
実際に当院で治療を受けられた患者さんによるインタビュー動画です。
患者さまのインタビュー

膝にまつわる症例紹介
具体的な症例紹介を解説しています。
リペア幹細胞プラス【分化誘導】痛み10段階中10が4に!靴下が履ける日常を取り戻した!変形性股関節症 50代 女性
靴下を履ける日常を取り戻した50代女性の股関節・膝関節再生治療 「靴下を履くことすら、こんなに辛いなんて」──約1年前から左股関節と左膝の強い痛みに悩まされてきた50代女性の患者様。痛みは10段階中10という最も強いレベルに達し、跛行しながらの歩行を余儀なくされていました。"リペア幹細胞プラス"(分化誘導)と"リペア幹細胞"、PRP療法を組み合わせた治療により、痛みは10段階中4まで軽減し、靴下の着脱ができる日常を取り戻すことができました。 治療前の状態 約1年前から左股関節に痛みを感じ始め、整形外科で変形性股関節症と診断された 左膝にも痛みが広がり、靴下の着脱、靴紐結び、足の爪切りといった基本動作が困難に 跛行がみられ、左下肢の筋力低下が顕著な状態 医師からは手術を10年後の目安と告げられたが、日常生活への支障が大きく当院へご相談 患者様は約1年前に左股関節の違和感を覚え、やがて痛みが強くなり整形外科を受診されました。変形性股関節症(進行期)と診断され、さらに左膝にも痛みが広がったことで日常生活に大きな支障をきたすようになりました。 整形外科では「手術は10年後が目安」と言われましたが、靴下を履くことすら困難な状態では10年も待てないというお気持ちから、手術に頼らない治療法を求めて当院へご来院されました。 "リペア幹細胞"とリペアセルクリニックの特長 レントゲン所見 レントゲンにて股関節・膝関節ともに関節の狭小化を認めます。 <治療内容>左股関節・左膝に"リペア幹細胞プラス"(分化誘導)1回、"リペア幹細胞"1回、計2億個投与+PRP 左股関節と左膝に"リペア幹細胞プラス"(分化誘導)を1回、"リペア幹細胞"を1回、計2億個を投与しました。あわせてPRP療法も2回実施し、組織の修復環境を整えました。手術や入院の必要はなく、関節を温存したまま治療を進めることができました。 治療後の変化 左股関節の痛みが10段階中10から4へ大幅に軽減 左膝の痛みも10段階中10から4へ改善 靴下の着脱が可能になり、日常動作の制限が大幅に軽減 跛行も改善傾向にあり、左下肢の筋力が徐々に回復 治療を経て、左股関節・左膝ともに痛みが10段階中10から4まで軽減しました。強い痛みのために困難だった靴下の着脱や足の爪切りといった基本動作が可能になり、日常生活の質が大きく向上しています。 治療前は「手術まで10年も我慢しなければならないのか」という不安を抱えておられましたが、手術に頼らず痛みを軽減できたことで、日常を取り戻す希望が見えてきました。跛行も改善傾向にあり、今後さらなる回復が期待されます。組織の再生・修復を促したことで、このような改善が実現しました。"リペア幹細胞"は投与後1年間にわたって効果を発揮し続けるため、さらなる改善も期待できます。
-
ひざ関節の症例
-
股関節の症例
-
関節の症例
-
幹細胞治療の症例
-
PRP治療の症例
“リペア幹細胞” 痛み10段階中10が3に!高齢でも諦めなくてよかった!左変形性膝関節症 80代 女性
人工関節を回避し、痛みのない日常を取り戻した80代女性の膝関節再生治療 「この年齢で本当に効果があるのでしょうか」——そんな不安を抱えながら来院された80代女性の患者様。末期の左変形性膝関節症と診断され、痛みは10段階中10という深刻な状態でした。"リペア幹細胞"による治療後、痛みは10段階中3まで大幅に軽減。高齢であっても再生医療による改善の可能性が示された症例でさらなる改善にも期待が持てる状況です。 治療前の状態 3か月前から左膝に痛みが出現し、水も溜まって腫れてきた 近くの整形外科で末期の変形性膝関節症と診断された 水を抜いてヒアルロン酸注射や痛み止めの内服を試みたが効果を感じなかった 痛みは10段階中10で、保険診療での選択肢は人工関節のみと告げられた 患者様は3か月前から誘因なく左膝の痛みに悩まされるようになりました。近くの整形外科を受診したところ、末期の変形性膝関節症と診断されました。水を抜いてヒアルロン酸注射を行い、痛み止めの内服による保存的加療を続けましたが、効果を感じられなかったそうです。 保険診療の範囲では人工関節しか選択肢がありませんでしたが、高齢であるためリスクが高く躊躇されていました。「この年齢で幹細胞治療の効果は見込めるのだろうか」という不安を抱えながらも、再生医療に希望を託して当院を受診されました。 "リペア幹細胞"とリペアセルクリニックの特長 レントゲン所見 レントゲンにて左膝関節の狭小化を認めます <治療内容>左膝に5000万個の"リペア幹細胞"を1回投与 左膝に5000万個の"リペア幹細胞"を1回投与しました。手術や入院の必要はなく、高齢の患者様でも身体への負担を最小限に抑えながら治療を進めることができました。 治療後の変化 初回投与から3か月後に効果を実感 痛みは10段階中10から3へ大幅に軽減 高齢でも効果が得られることを実感し、不安が解消された 今後さらに2回の投与を受けることを決意された 初回投与から3か月後、左膝の痛みは10段階中10から3へと大幅に軽減しました。末期の変形性膝関節症で、かつ高齢であっても、当院の"リペア幹細胞"であれば十分な除痛効果が得られることを実感していただけました。 治療前は「この年齢で効果があるのか」と不安を抱えていらっしゃいましたが、実際に痛みの軽減を体験されたことでその不安は解消されました。患者様は効果を確信され、今後さらに2回の"リペア幹細胞"投与を受けることを決意されています。高齢のためリスクを考えて人工関節を躊躇されている方にも、再生医療という選択肢があることを示す症例となりました。"リペア幹細胞"は投与後1年間にわたって効果を発揮し続けるため、さらなる改善も期待できます。
-
ひざ関節の症例
-
関節の症例
-
幹細胞治療の症例
リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中6が1に!テニス復帰も夢じゃない! 両変形性ひざ関節症 60代 女性
テニス復帰への希望を取り戻した60代女性の両膝再生治療 「このまま大好きなテニスを諦めなければならないのか…」。5年間、両膝の痛みに悩まされてきた60代女性の患者様。ヒアルロン酸注射を2週間に1度継続しても改善せず、右膝は10段階中6の痛みを抱えていらっしゃいました。"リペア幹細胞プラス"(分化誘導)による治療を受けた結果、右膝の痛みは6から1へ、左膝は0へと改善。小走りも可能になり、テニス復帰への希望が見えてきました。 治療前の状態 約5年前から右膝に痛みが出現し、その後左膝にも広がる 両変形性ひざ関節症と診断され、痛みは右膝6、左膝2(10段階評価) ヒアルロン酸注射を2週間に1度継続するも改善せず 長年続けてきたテニスの継続が困難となり、諦めかけていた 患者様は長年テニスを楽しんでこられましたが、関節への負担が大きく、体格的にも膝へのストレスが強い状況でした。右下肢には筋力低下があり、過去に2回の肉離れを経験されています。ヒアルロン酸注射を続けても痛みは一向に改善せず、大好きなテニスを諦めなければならないのかと不安を感じていらっしゃいました。 ヒアルロン酸注射は変形性膝関節症の保存療法として広く行われていますが、軟骨そのものを再生させる効果には限界があります。注射を続けても改善しない場合、次の選択肢は人工関節手術となりますが、術後はテニスのような激しいスポーツの継続は難しくなります。手術を避けながらテニスを続けたいという患者様の願いに応えるため、"リペア幹細胞プラス"(分化誘導)による再生医療をご提案しました。 "リペア幹細胞"とリペアセルクリニックの特長 当院では、独自の培養技術で増やした幹細胞を"リペア幹細胞"、さらに骨への分化誘導を施した幹細胞を"リペア幹細胞プラス"と呼んでいます。 "リペア幹細胞プラス"は、培養過程で骨になるよう誘導因子を加えることで作られます。この幹細胞を傷んだ関節に投与すると、軟骨の土台となる軟骨下骨を効率よく再生させ、最終的には軟骨自体の再生も促進させることができるのです。 MRI・レントゲン所見 レントゲンにて関節の狭小化を認めます。 <治療内容>両膝に"リペア幹細胞プラス"(分化誘導)を2回、"リペア幹細胞"を1回、計2億個投与+PRP 両膝に"リペア幹細胞プラス"(分化誘導)を2回、"リペア幹細胞"を1回、計2億個を3回にわたり投与しました。また、治療開始時にはPRP療法も併用し、両膝に2ccずつ投与しました。手術や入院の必要はなく、膝関節の組織を温存したまま治療を進めることができました。 治療後の変化 1回目投与後、右膝の痛みが6から4へ改善 2回目投与後は旅行にも行けるほど回復 3回目投与後、右膝の痛みは1、左膝は0へと大幅に改善 小走りも可能となり、日常生活動作が大きく向上 治療開始後、1回目の投与では右膝の痛みが6から4へと軽減しました。投与後に一時的な膝の腫脹が見られましたが、これは"リペア幹細胞"が活発に働いている反応とも言えます。リハビリを経て改善した後は順調に回復され、2回目投与後には旅行にも出かけられるまでになりました。3回目投与後には右膝の痛みが1、左膝は0へと改善し、小走りも可能な状態まで回復されています。 治療前は「テニスを諦めなければならないのか」と不安を抱えていらっしゃいましたが、現在はしゃがみ込みや立ち上がり動作も楽になり、痛みのない日常生活を取り戻されました。手術をせずに自分の細胞で治すという選択が、患者様の希望を叶える結果となりました。
-
ひざ関節の症例
-
関節の症例
-
幹細胞治療の症例
-
PRP治療の症例
“リペア幹細胞” 右膝痛み4が0に完全消失!快適な歩行を取り戻した!両膝変形性関節症 70代 女性
痛みのない快適な歩行を取り戻した70代女性の両膝再生治療 突然の右膝激痛で歩行困難となり、さらに3年間続く左膝の痛みにも悩まされていた70代女性の患者様。両膝変形性関節症と右膝半月板損傷の診断を受け、他院でヒアルロン酸注射や関節液除去を試みましたが十分な改善は得られませんでした。当院での"リペア幹細胞"治療により、右膝の痛みは4から0へ完全消失。左膝も追加治療後に痛み0となり、手術を回避しながら快適な日常生活を取り戻されました。 治療前の状態 右膝の突然の激痛で歩行困難に MRI検査で右膝半月板損傷と診断、痛みVAS4 左膝は3年前から痛み、初期〜中期の変形性膝関節症 他院でのヒアルロン酸注射・関節液除去も効果不十分 患者様は、突然右膝に激痛が走り、歩行困難な状態となりました。MRI検査で半月板損傷と診断され、他院でヒアルロン酸注射や関節液除去を繰り返し実施されましたが、十分な改善は得られませんでした。左膝も3年前から慢性的な痛みがあり、初期から中期の変形性膝関節症と診断されていました。 半月板損傷を伴う変形性膝関節症では、ヒアルロン酸注射や関節液除去による症状緩和には限界があります。高齢者の場合、手術に伴うリスクも高くなるため、患者様は手術を避けながら痛みを根本から改善できる治療法を探されていました。 "リペア幹細胞"とリペアセルクリニックの特長 MRI・レントゲン所見 レントゲンにて左膝関節の狭小化を認めます。右膝関節は半月板の損傷が認められます <治療内容>計1億5,000万個の"リペア幹細胞"を両膝へ投与 脂肪採取とPRP投与から治療を開始し、計1億5,000万個の"リペア幹細胞"を両膝へ投与しました。左膝の軽度再発に対しては、追加治療を実施しました。 治療後の変化 "リペア幹細胞"を複数回投与 治療3か月後、右膝の痛みが4から2に改善 治療1年後、右膝の痛みが完全消失、左膝は追加治療後に痛み0 両膝とも痛みがなくなり、快適な日常生活を送れるように 治療開始から3か月後には右膝の痛みが4から2へ改善し、1年後には完全に消失しました。左膝は経過中に軽度の再発がみられたため追加治療を行い、その後は両膝とも痛み0を維持されています。 治療前は「歩くたびに右膝に激痛が走り、日常生活もままならなかった」という患者様でしたが、現在は「右膝の激痛が嘘のように消え、歩くのが楽になりました」と笑顔でお話しくださっています。手術を回避しながら、両膝の痛みから解放された生活を取り戻されました。
-
ひざ関節の症例
-
関節の症例
-
幹細胞治療の症例
-
PRP治療の症例
“リペア幹細胞” 10年悩んだ両膝の痛みから解放 両変形性膝関節症 60代女性
痛み10段階中5が1に!10年悩んだ両膝の痛みから解放 10年間両膝の痛みに苦しみ、立っていることも辛くなって人工関節を勧められていた60代の患者様。“リペア幹細胞”によって痛みが劇的に軽減しました。両膝とも10段階中5だった痛みが1まで改善し、人工関節を回避してアクティブな活動を続けられるようになったのです。 まだまだ元気に動きたいと願っていた患者様が、このような回復を実現できたのは、いったいどのような治療だったのでしょうか。 治療前の状態 10年前から両膝関節痛に悩む 痛み止めを飲みながら過ごしてきた 最近では立っていることも辛い 痛みは両膝とも10段階中5で人工関節を勧められる この患者様は、10年前からの両膝関節痛のため受診していただきました。当時、近くの整形外科で変形性膝関節症と診断されたそうです。以後、痛み止めを飲みながら過ごしてきましたが、最近では立っていることも辛くなってしまいました。レントゲンを再度撮影すると、軟骨のすり減りが進行しており、医師から人工関節を勧められました。まだまだアクティブな活動を続けたい患者様は人工関節を躊躇し、軟骨を再生させる方法を探され、幹細胞治療に辿り着いて当院を受診されました。 一旦人工関節になると、耐用性の問題から活動的に動き回ることができなくなりますし、膝の可動域の制限も出てしまいます。入院期間、合併症のリスク、術後の痛みなども懸念されます。 “リペア幹細胞”とリペアセルクリニックの特長 詳細については、こちらで当院独自の再生医療の特徴を紹介しています。 リペアセルクリニックは「膝の痛み」に特化した再生医療専門クリニックです。手術・入院をしない新たな治療【再生医療】を提供しております。 レントゲン所見 レントゲンにて関節の狭小化を認めます。 <治療内容>両膝に“リペア幹細胞”1億個を3回投与+PRP 両膝に“リペア幹細胞”1億個を3回投与いたしました。 治療後の変化 両膝の痛みが10段階中5から1へ劇的に改善 立っていることが辛かった状態から解放 人工関節を回避してアクティブな活動を継続 10年間の悩みから解放 最終投与後には両膝とも投与前10段階中5だった痛みが1まで軽減しました。“リペア幹細胞”が両膝の軟骨欠損部位に直接働きかけ、投与する度に一層ずつ軟骨が再生されていったことで、このような素晴らしい改善が実現したのです。10年間痛み止めを飲みながら耐えてきた痛みから解放され、人工関節を回避してアクティブな活動を続けられるようになりました。 この劇的な改善について、専門医のとし先生が詳しく解説しています。実際の治療の流れや、なぜ人工関節を回避できたのか、動画でご覧ください。 https://youtu.be/wmPCWC2pVeI?si=3aEPROMFQvrRscAZ 変形性膝関節症で人工関節を回避したい方、まだまだアクティブな活動を続けたい方に、当院の再生医療は新たな可能性を提供します。膝の痛みでお悩みの方はぜひ一度、当院へご相談ください。 当院独自の“リペア幹細胞”、そして国内で珍しい分化誘導技術を用いた“リペア幹細胞プラス”で、『次世代の再生医療』を提供します。 <治療費> 関節1部位 幹細胞数 ( 2500万個~1億個) 投与回数( 1回 )132万円( 税込 )/2500万個 分化誘導( 1回 )55万円( 税込 ) PRP治療 16.5万円(税込) <起こりうる副作用> 脂肪採取部の内出血や創部感染、傷跡などが起こることがあります。 症状によりMRIやCTなどの検査を受けて頂く事があります。 ※こちらでご紹介している症例は一部の患者様です。掲載以外の症例も多数ございます。ご自身の症状については、お気軽にご相談ください。 変形性膝関節症の再生医療についてはこちらで詳しく説明しています。↓ 再生医療医師監修:黄金勲矢
-
ひざ関節の症例
-
関節の症例
-
幹細胞治療の症例
-
PRP治療の症例
“リペア幹細胞” 痛み10段階中6が1になりテニス復帰! 左膝半月板損傷 60代女性
痛み10段階中6が1に!テニスのプレー中も痛みなし! 左膝の痛みのため、趣味のテニスを1年間諦めかけていた60代の患者様。“リペア幹細胞”の投与によって痛みがほぼ消失し、週3〜4回のテニスを痛みなく楽しめるようになりました。毎月水を抜いてヒアルロン酸注射を受けても改善せず、関節鏡手術も視野に入れていたにもかかわらず、わずか半年で「プレー中は痛みなく楽しめています」とのお声をいただきました。 いったいどのような治療で、このような素晴らしい回復を実現できたのでしょうか。 治療前の状態 テニス後に左膝が腫れて痛みが出る 毎月の穿刺とヒアルロン酸注射も効果なし 歩き始めや階段昇降でも痛みを感じる 痛みの程度は10段階中6で悪化傾向 この患者様は、趣味でテニスをされていましたが、1年前からテニスをした後に左膝が腫れて痛みが出るようになりました。整形外科で左膝半月板損傷と診断され、1か月に1回、穿刺して水を抜いてはヒアルロン酸注射を受けていましたが、効果はあまり感じられませんでした。現在は、テニス以外でも歩き始めや階段昇降で痛みを感じるようになり、悪化してきていると心配されて、当院を受診されました。 半月板損傷の手術では、半月板の損傷が激しくて縫合できない場合や、血行のない半月板辺縁の断裂の場合には、半月板の損傷した部分が切除されてしまいます。半月板を切除すると膝のクッションがなくなるため、軟骨のすり減りが加速してしまいます。実際、半月板切除後10年後を調査すると、一般の方で3割が、スポーツ選手では7割が変形性関節症に進行してしまうのです。テニスをされているようなアクティブな方は、変形性関節症に進行する可能性が高いと考えられます。 “リペア幹細胞”とリペアセルクリニックの特長 詳細については、こちらで当院独自の再生医療の特徴を紹介しています。 リペアセルクリニックは「半月板損傷」に特化した再生医療専門クリニックです。手術・入院をしない新たな治療【再生医療】を提供しております。 MRI所見 MRIにて内側半月板の損傷を認めます。 <治療内容>左膝に“リペア幹細胞”5000万個を1回投与+PRP 左膝に“リペア幹細胞”5000万個を1回投与いたしました。 治療後の変化 痛みが10段階中6から1へ劇的に改善 投与後わずか半年で効果を実感 週3〜4回テニスを痛みなく楽しめるように 「プレー中は痛みなく楽しめています」 投与から半年後には、投与前10段階中6だった左膝の痛みが、1まで劇的に軽減しました。従来の手術は症状緩和を目的とした対症療法ですが、幹細胞治療は半月板組織の再生による根本的な治療です。患者様からは「週3〜4回テニスをしていますが、プレー中は痛みなく楽しめています」とのお声をいただきました。なお、冷凍せず培養された生き生きした幹細胞でなければ、このような良い成績はみられないでしょう。 この治療法の画期的な点は、従来必要とされていた長期入院や過酷なリハビリテーション、そして行動制限のための固定期間が一切不要であることです。半月板損傷と診断された方で、痛みを取りつつ半月板を修復して将来の軟骨のすり減りを予防したい方に、当院の再生医療は新たな可能性を提供します。手術による半月板切除を避け、アクティブな生活を続けることができます。半月板損傷でお悩みの方はぜひ、当院へカウンセリングへお越しください。 国内で珍しい、最新の『分化誘導技術』を用い、当院は『次世代の再生医療』による治療を提供します。 <治療費> 関節1部位 幹細胞数 ( 2500万個~1億個) 投与回数( 1回 )132万円( 税込 )/2500万個 分化誘導( 1回 )55万円( 税込 ) PRP治療 16.5万円(税込) <起こりうる副作用> 脂肪採取部の内出血や創部感染、傷跡などが起こることがあります。 症状によりMRIやCTなどの検査を受けて頂く事があります。 ※こちらでご紹介している症例は一部の患者様です。掲載以外の症例も多数ございます。ご自身の症状については、お気軽にご相談ください。 半月板損傷の再生医療についてはこちらで詳しく説明しています。↓ 再生医療医師監修:黄金勲矢
-
ひざ関節の症例
-
半月板の症例
-
幹細胞治療の症例
-
PRP治療の症例

新着コンテンツ
-
X脚を治すストレッチや筋トレを紹介|原因タイプ別の改善メニューと続けるコツ
X脚は日本人に多くみられる脚の形状の一つで、外見上のコンプレックスにとどまらず、膝痛や腰痛といった身体的な不調を引き起こす可能性があります。 「この脚の形は自分で改善できるのだろうか」「どんなストレッチを行えばいいのだろう」などの疑問を抱えている方は少なくないでしょう。 結論からお伝えすると、X脚の多くは後天的な要因が大きいため、セルフケアによって改善を目指せます。 本記事では、X脚のセルフチェック方法から、原因別のストレッチ・筋力トレーニング、さらに日常生活で意識したい姿勢や歩き方のポイントまで徹底解説します。また、今日から自宅で始められるメニューを紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。 なお、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。膝や股関節の痛みでお悩みの方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。 X脚を治す簡単ストレッチ5選 X脚の改善を目指す上で、まず取り組みたいのが「硬くなった筋肉の柔軟性を回復させること」です。 X脚の傾向がある方は、太ももの内側にある内転筋群(ないてんきんぐん)や外側の大腿筋膜張筋(だいたいきんまくちょうきん)、もも裏のハムストリングスといった筋肉が過度に緊張している場合が多いとされています。 ここでは、自宅で無理なく取り組める5つのストレッチを紹介します。 内転筋(内もも)ストレッチ 大腿筋膜張筋(太ももの外側)ストレッチ ハムストリングス(もも裏)ストレッチ 股関節のねじれを整える外旋ストレッチ ふくらはぎ・足首のストレッチ それぞれのストレッチ手順を具体的に解説します。 1. 内転筋(内もも)ストレッチ X脚の傾向がある方は、太ももの内側にある「内転筋」が硬くなりやすい傾向にあります。内転筋の緊張は、膝を内側に引っ張る力として作用するため、柔軟性を保つことがX脚改善の基本です。 ここでは、開脚姿勢で行うシンプルなストレッチを紹介します。具体的な手順は、以下を参考にしてください。 床に座り、脚を大きく左右に開く 背筋をまっすぐに伸ばしたまま、体の前の床に手をつける ゆっくりと息を吐きながら、おへそを前へ突き出すようなイメージで上半身を前に傾ける 内ももに心地良い伸びを感じるところで動きを止め、30秒間その姿勢をキープする 時間が経ったら、ゆっくりと上体を起こして元の姿勢に戻る 上記ストレッチは、1回あたり30秒キープ×2〜3セットを目安に行ってください。 なお、上体を倒すときに背中が丸まらないよう、股関節から折り曲げる意識を持ちましょう。また、膝を無理に床へ押しつける必要はありません。「心地よい」と感じる範囲で行ってください。 2. 大腿筋膜張筋(太ももの外側)ストレッチ 太ももの外側に位置する大腿筋膜張筋が硬くなると、股関節の左右バランスが崩れ、X脚を助長する原因になり得ます。以下の手順で、しっかりと大腿筋膜張筋をストレッチしましょう。 仰向けに寝た状態で両膝を立てる 片方の足首を反対側の膝の上に乗せ、数字の「4」のような形を作る その姿勢のまま、乗せた脚の方向へゆっくり倒していく 心地良い伸びを感じるポイントで止め、30秒間キープする 反対側の脚も同様に行う 上記ストレッチの1回あたりの目安は、左右各30秒キープ×2セットです。 なお、脚を倒した際に、反対側の肩が床から浮いてしまわないよう意識してください。また、呼吸を止めず、体全体をリラックスさせた状態を保つことも大切です。 3. ハムストリングス(もも裏)ストレッチ もも裏の筋肉群であるハムストリングスが硬くなると、骨盤が後方に傾く「骨盤後傾(こつばんこうけい)」の状態を招きやすくなります。とくに長時間のデスクワークが多い方は、ハムストリングスが硬くなりやすい傾向にあります。意識的にストレッチしましょう。 具体的な手順は以下のとおりです。 仰向けに寝た状態で、片方の膝を両手で抱え、胸のほうへ引き寄せる 太ももとお腹をしっかり密着させたまま、膝をゆっくり天井方向へ伸ばしていく もも裏に伸びを感じたところで10~20秒間キープする ゆっくりと膝を曲げ、元の姿勢に戻す 反対側の脚も同じように繰り返す 上記ストレッチの1回あたりの目安は、左右各5回×2セットです。 なお、膝を伸ばす過程で、太ももとお腹が離れないよう意識することがポイントです。膝が完全に伸びきらなくても問題ありません。 もも裏にしっかりと伸びを感じられていれば、十分にストレッチの役割を果たしています。 4. 股関節のねじれを整える外旋ストレッチ X脚の根本的な原因の一つに、股関節が内側方向にねじれる「内旋(ないせん)」状態が挙げられます。内旋状態を解消するために、股関節を外側に開く「外旋」の動きを取り入れるストレッチが重要です。 具体的な手順は、以下を参考にしてください。 床にあぐらをかくように座り、両方の足裏を合わせる 両手を体の前の床につき、背筋をすっと伸ばす 息を吐きながら、背中を丸めずに股関節から上体をゆっくり前へ倒す お尻の奥や股関節の外側に心地良い伸びを感じるところで動きを止める その姿勢を20〜30秒キープし、ゆっくりと体を起こす 上記ストレッチの1回あたりの目安は、20〜30秒キープ×3セットです。 なお、背中を丸めて倒すのではなく、おへそを床に近づけていくイメージで股関節を起点に動かすのがコツです。膝に痛みが出る場合は無理をせず、痛みのない範囲にとどめてください。 5. ふくらはぎ・足首のストレッチ 足首の動きが硬くなると、歩行時の衝撃をうまく分散できず、膝や股関節に負担がかかることがあります。脚全体のバランスを整えるためには、足元の柔軟性にも目を向けることが大切です。 具体的なストレッチの手順は以下のとおりです。 壁の正面に立ち、両手を壁について体を支える 片足を大きく一歩後ろに引く 後ろ足のかかとを床から離さないよう注意しながら、膝を伸ばして20~30秒キープ 次に前の膝をゆっくり曲げた状態で20~30秒キープ 反対の足も同様に行う 上記ストレッチの1回あたりの目安は、左右各20〜30秒キープ×2〜3セットです。 なお、後ろ足のかかとが床から浮かないよう、常に意識しましょう。また、つま先の向きはまっすぐ正面を保つようにしてください。 X脚を治す簡単筋トレ2選 ストレッチで筋肉の柔軟性を取り戻したら、弱くなった筋肉のトレーニングも大切です。 とくに、お尻の側面にある「中殿筋(ちゅうでんきん)」は、股関節を安定させる重要な筋肉です。この筋肉が弱っていると、歩行時に膝が内側へぶれやすくなり、X脚が悪化する原因となりかねません。 ここでは、自宅で無理なく取り組める2つの筋力トレーニングを紹介します。 クラムシェル(お尻のインナーマッスル) 正しいフォームでのスクワット それぞれ詳しく解説します。 1. クラムシェル(お尻のインナーマッスル) X脚の改善には、硬くなった筋肉をほぐすストレッチと、弱った部分を強化する筋力トレーニングの両輪が欠かせません。クラムシェルは、股関節の安定に大きく関わる中殿筋をターゲットに鍛えられます。 具体的な手順は、以下を参考にしてください。 体を横向きにして寝て、下側の腕で頭を支える 両膝を軽く曲げ、左右のかかとを揃える かかとを合わせたまま、上側の膝だけをゆっくり持ち上げる お尻の横の筋肉がキュッと収縮する位置まで上げたら、2〜3秒間静止する ゆっくりと膝を下ろし、元の位置へ戻す 反対側も同様に繰り返す クラムシェルの1回あたりの目安は、左右各15回×2セットです。 また、クラムシェル中は動作中に骨盤が前後にぐらつかないよう、上半身をしっかり固定しましょう。意識をお尻の横に集中させ、膝を開く際に体が後方へ傾かないよう注意してください。 2. 正しいフォームでのスクワット スクワットは、下半身全体をバランスよく鍛えられるトレーニングの基本種目です。ただし、X脚の傾向がある方は動作中に膝が内側に入ってしまう「ニーイン(knee-in)」が起こりやすいため、正しいフォームの習得が何よりも大切になります。 具体的な手順は以下のとおりです。 両足を肩幅程度に開き、つま先をやや外側に向ける 背筋をまっすぐ保ったまま、両腕を前方に伸ばすか胸の前で組む 椅子に腰掛けるイメージで、お尻を後方へ引きながらゆっくり腰を落としていく 太ももが床と平行になる深さが理想だが、難しい場合は無理のない範囲で止める 膝が内側に入らないこと、膝がつま先より極端に前へ出ないことを確認しながら、ゆっくりと元の姿勢に戻る スクワットの1回あたりの目安は、10〜15回×2〜3セットです。 なお、スクワットで最も注意したいのが、動作を通じて「膝とつま先の向きを常に揃える」ことです。可能であれば鏡を横に置き、フォームを修正しながら取り組むと、安全かつ効率よく筋力を高められます。 X脚になる4つの原因と今日からできる予防法 X脚とは、両膝が接する一方で、内くるぶし同士が離れてしまう脚の形状を指します。見た目の問題だけでなく、膝や股関節への偏った負担が蓄積し、将来的な不調につながる可能性もあるため、原因を理解した上で早めのケアが重要です。 ここでは、X脚を引き起こす主な4つの原因と、それぞれに対する予防策を紹介いたします。 日常の姿勢(立ち方や座り方) 歩き方の癖 お尻や太ももの筋力低下 骨盤の歪みと股関節の内旋 それぞれ詳しく解説します。 日常の姿勢(立ち方や座り方) X脚の多くは先天的なものではなく、日々の生活のなかで無意識に続けている習慣が積み重なり、後天的に形成されると考えられています。 とくに注意したいのが、以下のような座り方や立ち方の癖です。 両膝を内側に倒して座る「ぺたんこ座り」 左右どちらかに脚を流す「横座り」 足を組んで座る 片足に重心を偏らせて立つ なかでも「ぺたんこ座り」は、股関節の内旋と膝のねじれを直接的に誘発するため、とくに避けたい姿勢です。 予防策としては、椅子に座るときは「深く腰掛けて両膝を揃えること」、立つときは「左右の足に均等に体重を乗せること」を意識しましょう。日々の小さな意識の積み重ねが、X脚の改善につながる可能性があります。 歩き方の癖 普段の歩き方にも、X脚を助長するさまざまな要因が潜んでいます。以下の表で、代表的な歩き方の癖とX脚への影響を確認してみてください。 歩き方の癖 X脚への影響 内股歩き 股関節の内旋が習慣化し、歩行のたびに膝が内側へ入りやすくなる 親指側に重心が偏る歩き方 足裏全体で体を支えられず、脚全体の軸が不安定になりやすい すり足・ペタペタ歩き 足指が機能しない「浮き指」を招き、扁平足(へんぺいそく)や外反母趾(がいはんぼし)を経てX脚を悪化させるリスクがある ハイヒールの常用 体重がつま先側に集中し、足裏のアーチ構造が崩れて脚全体のバランスに悪影響を及ぼす可能性がある 正しい歩行の基本は、「かかとから着地し、足の親指で地面を蹴り出す」動きです。日頃からこの意識を持つだけでも、脚への負担は軽減されます。 お尻や太ももの筋力低下 X脚の背景には、筋肉バランスの乱れが関与していることがあります。生活習慣や運動量の変化などにより、お尻や太ももの筋力が低下すると、脚のラインに影響が及ぶ可能性があるのです。 とくに、股関節の安定に欠かせない中殿筋(ちゅうでんきん)が弱くなると、歩行時に体重を十分に支えきれず、膝が内側へぶれやすくなることがあります。 改善を目指す上では、ストレッチで筋肉をゆるめるアプローチと、筋力トレーニングで支える力を高めるアプローチの両方を意識することが大切です。 本記事で紹介したクラムシェルやスクワットを日常に取り入れ、無理のない範囲で継続しましょう。 骨盤の歪みと股関節の内旋 骨盤に歪みが生じると、股関節の位置関係が崩れ、X脚につながることがあります。 骨盤の歪みは、デスクワークや長時間の運転など同じ姿勢が続く場面だけでなく、片足重心や足を組む癖といった日常の何気ない動作からも生じるものです。また、X脚だけでなく腰痛や肩こりなど、全身のさまざまな不調の原因にもなり得るため、日常的なケアが欠かせません。 予防策としては、以下を意識してみてください。 椅子に座る際は骨盤を立て、左右均等に体重を乗せる 足を組む・横座りなど、骨盤が傾く姿勢を避ける 定期的にストレッチを行い、骨盤周りの柔軟性を保つ 骨盤周りの柔軟性と安定性を維持し、X脚改善を目指しましょう。 痛みを伴うX脚には再生医療という選択肢 痛みを伴うX脚は、関節疾患が影響している場合があります。 なお、変形性股関節症(へんけいせいこかんせつしょう)や変形性膝関節症(へんけいせいひざかんせつしょう)の進行過程でX脚がみられる場合もあれば、もともとのX脚が関節への負担を高め、変形を助長するケースもあります。 痛みや機能障害がある場合は、脚の形だけでなく、原因となっている関節への対応が重要です。再生医療であれば、入院の必要がなく、体への負担にも配慮しながら改善を目指せるため、選択肢の一つとして検討してみてください。 具体的な治療の流れについては、以下の症例紹介ページをご覧ください。 まとめ|X脚を治すストレッチを継続して改善を目指そう X脚のセルフケアは、1日5分程度のストレッチからでも始められます。しかし、何よりも大切なのは継続です。長年の生活習慣で形成された脚の癖は、短期間で劇的に変わるものではありません。 改善へのアプローチは2つの柱で成り立っています。一つはストレッチによって硬くなった筋肉の柔軟性を取り戻すこと、もう一つは筋トレで正しい脚のラインを支える筋力を養うことです。 また、普段の立ち方や歩き方、座り方といった無意識の癖を見直すと、セルフケアの成果をより大きなものにできます。 なお、ストレッチや筋トレ中に痛みを感じた場合は、無理をせず医療機関に相談してください。痛みの原因によっては、専門的な診断や治療が必要なケースもあります。 当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。膝や股関節の痛みでお悩みの方は、ぜひ一度ご登録ください。 X脚を治すストレッチに関するよくある質問 即効性のあるX脚の治し方はある? 残念ながら、X脚を短期間で劇的に改善できるような特効薬は存在しません。X脚は長年にわたる生活習慣や体の使い方の癖が積み重なって形成されたものであり、その改善にも相応の時間と継続的な取り組みが必要です。 なお、医療用インソール(靴の中敷き)の使用で、歩行時の足裏の接地バランスを整え、膝への負担を分散できる場合があります。ただし、インソールは形を根本的に変えるものではなく、あくまで補助的な手段です。 「即効性」を求めるよりも、正しい知識に基づいたケアをコツコツと積み重ねながら改善を目指しましょう。 子どものX脚は成長とともに自然に治る? 子どもの脚の形は、成長の段階に応じて変化するのが一般的です。多くの場合、3歳頃からX脚の傾向がみられ始めますが、これは「生理的X脚」と呼ばれる発達過程の自然な変化であり、7〜8歳頃までに自然とまっすぐな脚に成長していくとされています。(文献1) そのため、幼児期のX脚については過度に心配する必要はありません。 ただし、以下のようなサインがみられる場合は、小児整形外科などの医療機関に相談しましょう。 8歳を過ぎてもX脚の傾向が改善しない 左右の脚で変形の度合いに明らかな差がある 子どもが膝の痛みを頻繁に訴えている こうした場合は、生理的なものではなく「なんらかの病的要因」が隠れている可能性も考えられます。早めに医療機関を受診しましょう。 参考文献 (文献1) 「O脚・X脚」|日本整形外科学会 症状・病気をしらべる
-
前十字靱帯断裂後のサッカー選手の復帰はいつ?受傷の原因や放置するリスクを解説
「前十字靱帯を断裂したサッカー選手はいつ復帰できる?」 「放置したままにするとどうなる?」 「適切な治療方法やリハビリスケジュールを知りたい」 前十字靱帯断裂後のスポーツ復帰の目安は平均8カ月後です。ただし、ケガの程度や手術の方法などによって目安は異なります。 本記事では、前十字靱帯断裂に関する以下のことをサッカーに焦点を当てて解説します。 受傷の原因 放置するリスク 治療方法 リハビリスケジュール 復帰の目安 予防エクササイズ 再断裂のリスクを下げるための評価方法についても解説しています。サッカーにおける前十字靱帯断裂について、理解を深めるために本記事を参考にしてください。 なお、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。 スポーツ外傷でお悩みの方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。 サッカーは前十字靱帯断裂が多いスポーツ サッカーは以下のような特性があることから、前十字靱帯断裂が多いスポーツです。 プレイ中に900回前後の方向転換に加えて、さまざまな動作を繰り返す 急激な加速や減速、別方向への加速など緩急が激しい キックやトラップなど片足立ちになる場面が多い 受傷する男女比は女性に多い傾向です。前十字靱帯を損傷した有名なサッカー選手には、元日本代表の城彰二選手や小野伸二選手などが挙げられます。 サッカー選手によくある前十字靱帯断裂の受傷の原因 サッカーでは、以下のようなプレイにより前十字靱帯断裂を受傷することが多いです。 ディフェンス時のプレッシング動作 ボールに対するキック動作 ジャンプからの着地 受傷状況には、接触プレーと非接触プレーがあります。接触プレーでは「相手からタックルが入った」「ジャンプの着地時に相手の足が絡んだ」などの状況で受傷する場合があります。 一方、非接触プレーでは「急に方向転換をしたとき」「ジャンプの着地時に足をひねった」などの状況です。接触プレーよりも、非接触プレーのほうが受傷する割合が多いとの報告があります。(文献1) 前十字靱帯断裂後の症状と放置するリスク 前十字靱帯を断裂した直後は「ブチッ」と切れたような音や、膝が外れたような感覚が現れます。この状態は、前十字靱帯に緊張がない状態です。 この状態のままだと、スポーツの動作だけでなく日常生活の動作でも「ガクッ」と膝くずれのような現象が生じるようになります。さらに放置していると、関節の中にある半月板や軟骨を損傷してしまうおそれがあり、変形性膝関節症を引き起こしてしまうリスクがあります。 変形性膝関節症は高齢者に多い病気です。しかし、前十字靱帯の断裂や損傷により、若い人でも引き起こすことがあります。 サッカー選手における前十字靱帯断裂の治療方法 前十字靱帯断裂が自然治癒することはほぼありません。そのため、多くの場合に再建術という手術療法を行う必要があります。再建術とは、自分の体にある腱を採取して断裂部位に移植する治療方法です。とくに前十字靱帯断裂を受傷したサッカー選手は、運動能力を回復させるためにも再建術が必要です。 再建術には、以下のようにいくつか種類があります。 ハムストリング腱を用いた再建術 骨付き膝蓋腱を用いた再建術 以下では再建術の一例を解説します。 ハムストリング腱を用いた再建術 再建術の中で最も多く用いられる、膝のハムストリング腱を用いた方法です。 ハムストリング腱を用いて行われる関節鏡視下再建術では、切開は最小にでき、合併症も少ないとされています。術後の経過も安定しており、有効な手術療法として確立しています。 骨付き膝蓋腱を用いた再建術 膝の骨付きの腱を用いた再建術です。復帰を目指すアスリートや膝の安定性を重視する場合、また再建術後に再断裂した場合などに適応となることがあります。 膝の骨付きの腱を用いるメリットは、腱の移植後、骨癒合(こつゆごう:骨がくっ付くこと)までの期間が短く、腱が固定するのが早いことです。 また、正常の前十字靱帯より強い引っ張り強度があるとされています。主なデメリットとしては、傷が大きく術後早期の痛みが強いことです。加えて、腱を採取した部位の骨折や感染、断裂のリスクなどが高まってしまいます。 自身の細胞を用いた再生医療 前十字靱帯断裂の治療において、再生医療も選択肢の1つです。再生医療とは、患者様自身の細胞を用いて、体の自然治癒力を高める治療方法です。 再生医療には、主に幹細胞治療とPRP療法の二つがあります。 幹細胞治療は、自己の幹細胞を採取・培養して患部に投与する治療法です。一方、PRP療法は、自己の血液から血小板を濃縮した液体を作製し、患部に注射する治療法です。血小板に含まれる成長因子などには、組織の修復を促し、炎症を抑える働きがあります。 再生医療は前十字靱帯断裂だけなく、半月板損傷やテニス肘、ゴルフ肘など、さまざまなスポーツ外傷に活用されています。 前十字靱帯再建後のサッカー選手のリハビリスケジュール 前十字靱帯再建後のサッカー選手のリハビリスケジュールの一例は、以下の通りです。 時期 リハビリメニュー 手術翌日 足関節運動 1〜2週目〜 足上げ(股関節屈曲)、足の横上げ(股関節外転)、足の後ろ上げ(股関節伸展) 3週目〜 膝の伸展運動、静止スケーティング 5週目〜 レッグカール、ハーフスクワット 7週目〜 静止自転車、カーフレイズ、踏み台昇降 9週目〜 膝伸展運動、階段昇降、速歩 13週目〜 ハーフスクワット、片足スクワット、レッグプレス、レッグカール、水中歩行 以上のように経過に応じて徐々にリハビリの強度を上げていきます。ただし、以上のリハビリの時期はあくまでも一例です。手術の方法や状態によって異なります。 また、時期に応じて膝の可動域やかけてもよい体重などの制限があります。医師の指示通りにリハビリを進めてください。 前十字靱帯断裂を受傷したサッカー選手の復帰目安 前十字靱帯断裂後に再建術を実施したサッカー選手の競技復帰の目安は、平均8カ月後です。(文献2)個人差があり5〜12カ月と幅があります。再建術後の再断裂のリスクは、2年以内が最も高いとされています。(文献3) そのため、期間よりも以下のような機能にもとづいた復帰の判断が重要です。 片足ジャンプの左右差が10%未満 健康な方の脚と比較して筋肉の出力が90%を超える ケガをした脚に不安感がない 復帰を焦らず経過に応じたリハビリを進めていきましょう。 サッカー選手が前十字靱帯断裂を予防するエクササイズ サッカーの外傷や障害予防プログラムとして「FIFA11+」が推奨されています。 例えば、以下のようなエクササイズを動画で紹介しています。 ベンチスタティック サンドイッチスタティック スクワット+トゥレイズ ここでは、エクササイズの一例の詳細を解説します。 ベンチスタティック ベンチスタティックは体幹の筋肉を強化するエクササイズです。体幹の筋肉を強化するとあらゆる動きの安定性の向上につながります。 ベンチスタティックの手順は以下の通りです。 うつ伏せになる 脇を閉じて前腕が地面に付くようにする 肘は肩の真下にする 足先と前腕で体を持ち上げる 上体、骨盤、脚を上げて頭から脚を一直線にする この体勢を20〜30秒間維持します。頭を後ろに反らしたり、背中が丸まったりしないように注意してください。3セットを目安に行いましょう。 サンドイッチスタティック サンドイッチスタティックは、体幹の側面の筋力を強化するエクササイズです。体幹の側面の筋肉を強化すると、横方向への動きや回転動作の安定性の向上につながります。 サンドイッチスタティックの手順は以下の通りです。 横向きに寝て下側の膝を90°に曲げる 下側の前腕と脚で体を支える 肘は肩の真下にする 骨盤と上側の脚を上げる 上側の肩、骨盤、脚を一直線にする この体勢を20〜30秒間維持します。肩と骨盤を前後に傾けないようにしてください。両側を各3セットずつ行いましょう。 スクワット+トゥレイズ スクワット+トゥレイズは、ハムストリングや下腿の筋肉の強化に加えて、膝や足首の動きのコントロール能力の向上を期待できます。 両足を肩幅に合わせてまっすぐ立ち、両手を腰に当てる ゆっくりと腰を下ろし、膝が90°になるまで曲げる そこから上体、股関節、膝を伸ばして立位に戻していく 膝が完全に伸びたらつま先立ちになる 再びゆっくりと曲げていく この動作を30秒間続けます。膝を内側に入れず、頭を後ろに反らさないようにしてください。2セットを目安に行いましょう。 まとめ|前十字靱帯再建後は復帰を焦らずリハビリに取り組もう サッカーはプレイ内容の特性上、前十字靱帯断裂を受傷しやすいスポーツです。接触プレーよりも「急に方向転換をしたとき」「ジャンプの着地時に足をひねった」などの非接触プレーのほうが、受傷原因として多いと報告があります。 復帰までの期間は平均8カ月ほどです。再建術後2年以内は再断裂のリスクが高いといわれています。再断裂のリスクを下げるためには、両足の筋力や機能の左右差がほとんどなくなるまで、リハビリに取り組むことが重要です。焦らずに医師やリハビリスタッフと相談しながら、回復の時期に応じたリハビリを行いましょう。 前十字靱帯断裂などスポーツ外傷の治療方法として、再生医療という選択肢もあります。再生医療について詳しくは、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEをご確認ください。 サッカーにおける前十字靱帯断裂に関するよくある質問 前十字靱帯断裂したままスポーツは可能? 前十字靱帯を断裂したままのスポーツは困難であり危険です。 関節の安定性が損なわれており容易に膝くずれが起きてしまうためです。適切な治療を受け、医師の許可が出てからスポーツを再開しましょう。 前十字靱帯断裂したらサッカーは引退? 前十字靱帯断裂が必ずしも引退につながるわけではありません。 適切な治療とリハビリにより復帰しているサッカー選手はいます。 参考文献 (文献1) 膝前十字靱帯損傷のリハビリテーション|中外医学社 (文献2) Jリーグ選手の膝前十字靱帯再建後の復帰について~膝最大伸展位での移植腱固定による靱帯再建術~|日本臨床スポーツ医学会誌 (文献3) 前十字靱帯断裂〜スポーツ復帰までの道のり〜|佐賀大学医学部附属病院
-
前十字靭帯断裂とは|症状・原因・手術をしないリスクまで現役医師が解説
前十字靭帯は損傷率が高い靭帯で、断裂するとスポーツだけでなく日常生活にも支障をきたす可能性があります。断裂した場合、自然治癒は難しいため、違和感を覚えた際は早めの受診が大切です。 本記事では、前十字靭帯断裂の概要や原因、症状について解説します。治療法や予防策もまとめているので、前十字靭帯断裂の疑いがある方は、ぜひ参考にしてください。 また、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。 前十字靭帯断裂に関する気になる症状が見られる方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。 前十字靭帯断裂とは 前十字靭帯断裂とは、大腿骨(だいたいこつ)とす脛骨(けいこつ)をつなぐ靭帯が部分的または完全に断裂する疾患です。前十字靭帯には膝を安定する役割があり、正常に機能することでジャンプや方向転換などが可能になります。 前十字靭帯が断裂すると膝関節が不安定になるため、ジャンプやひねる動作に加えて、歩行や走行にも支障をきたします。膝の外傷の中でも、前十字靭帯は損傷率が高い靭帯であり、好発年齢は15歳~45歳です。(文献1) 前十字靭帯は主にスポーツ選手に多い疾患で、断裂した場合、自然治癒は難しいため手術が必要になります。 なお、膝には前だけでなく後ろにも十字靭帯が存在しています。前と後ろ、どちらかが機能しなければ人は膝を安定して動かせません。前と後ろどちらの十字靭帯が断裂しているのか知るためには、医療機関で診断を受ける必要があります。 前十字靭帯断裂と損傷の違い 前十字靭帯の断裂と損傷では、治療法や回復期間が異なります。損傷は、前十字靭帯の一部が伸びていたり切れたりしている状態です。損傷といっても、程度は軽度から重度までさまざまで、場合によっては手術が必要になります。 対して、断裂とは前十字靭帯が部分的もしくは完全に切れてつながっていない状態です。断裂すると靭帯の機能が失われるため、膝の関節が不安定になり、運動だけでなく日常生活にも支障をきたします。前十字靭帯の断裂と損傷いずれの症状が見られた場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。 前十字靭帯断裂の症状 前十字靭帯を断裂した場合、症状は損傷の程度によって異なります。 主な症状は、以下の通りです。 状態 主な症状 受傷直後 膝のズレ・ひねった感じがする 膝の中でプツッという音が聞こえる 膝内部に血液が溜まり、膝が腫れ上がる 立ち上がれないほど強い痛みが生じる 膝崩れが起こる 断裂した場合 強い痛みが生じる 膝が腫れ上がる 膝の曲げ伸ばしができなくなる 立ったり歩いたりできなくなる 膝崩れを繰り返す 安静時も痛む場合がある 前十字靭帯を断裂した場合、時間が経つと痛みが治まる場合もあります。しかし、時間の経過とともに、膝が不安定になり運動や生活をしている中で膝が崩れるような「膝崩れ」が起こる場合があります。 前十字靭帯断裂の原因 前十字靭帯が断裂する原因はさまざまで、スポーツ中に受傷するだけではありません。主な原因には、以下の3つが考えられます。 サッカーやバスケなどで行う動作 スポーツや交通事故による衝突 ホルモンバランスによる影響 それぞれの原因について、以下で詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。 サッカーやバスケなどで行う動作 前十字靭帯断裂はジャンプや方向転換、着地時など、非接触によって発生します。前十字靭帯に強い力が加わることで断裂します。 前十字靭帯が断裂する原因となる具体的な動きは、以下のとおりです。 サッカーでドリブルをしている途中、急に方向転換する 相手をかわすために不安定な姿勢のまま方向転換する フェイクを入れるために急停止する リバウンドやブロック、スパイクの際にジャンプする ターンの際に膝をねじる サッカーやバスケなどのスポーツをしている場合、前十字靭帯が断裂する可能性があります。 スポーツや交通事故による衝突 前十字靭帯は、接触時に断裂する場合があります。ラグビーや柔道など、相手との接触があるコンタクトスポーツや交通事故も、前十字靭帯が断裂する原因の1つです。 前十字靭帯が断裂する原因となる具体的な動きは、以下のとおりです。 ラグビーでタックル・スクラムを行う ラグビーやアメリカンフットボールでブロックを行う 柔道で投げ技や受け身を行う 車と衝突する いずれも接触により膝に負担がかかるため、前十字靭帯が断裂する場合があります。 ホルモンバランスによる影響 前十字靭帯が断裂する原因には、女性ホルモンバランスの乱れも挙げられます。前十字靭帯の損傷は、男性に比べて女性の受傷率が2〜8倍ほど高いことが報告されています。(文献1)靭帯はコラーゲン繊維が密集して構成されているため、コラーゲン合成が欠かせません。 女性ホルモンの一つであるエストロゲンの値が高いと、コラーゲン形成や線維芽細胞増殖が減少し、靭帯や関節が不安定になります。(文献2)そのため、女性は前十字靭帯断裂のリスクが生じやすい傾向にあります。 前十字靭帯断裂で手術をしないとどうなる?放置するリスク 前十字靭帯断裂は、自然治癒が困難であり、放置すると再断裂のリスクが高くなります。また、放置により膝の関節が不安定化し、半月板損傷や変形性膝関節症になる可能性があります。 半月板損傷は膝の軟骨が損傷する疾患で、変形性関節症は膝関節が変形する疾患です。前十字靭帯を断裂した場合は、これらの二次的な障害を防ぐためにも、適切な治療の検討が重要です。 前十字靭帯断裂における全治までの期間 前十字靭帯断裂の場合、手術やリハビリが必要なため全治期間は8〜10カ月ほどかかります。手術を行う場合、4〜7日ほどの入院が必要です。 また、術後は移植した腱が負担に耐えられるようになるまでには3カ月程度かかります。それまでは激しい運動を避けなければなりません。再発を予防するためにも、医師や理学療法士などの指導を受けながら適切な治療を行いましょう。 前十字靭帯断裂の治療法 前十字靭帯を断裂した場合、適切な治療を受けることが大切です。主な治療法には、以下の3つが挙げられます。 保存療法 手術療法 再生医療 ここでは、各治療法について紹介するので、ぜひ参考にしてください。 保存療法 前十字靭帯断裂の場合、手術しなければ症状回復は困難です。しかし、年齢によっては手術の負担を考慮し、保存療法で症状のコントロールを目指す場合があります。 前十字靭帯断裂時の保存療法は、以下のとおりです。 可動域訓練・大腿四頭筋訓練などの運動療法 電気療法や温熱療法などの物理療法 サポーター・支柱付き装具を使用した装具療法 内服薬や外用薬などの薬物療法 保存療法で十分な効果が得られない場合や、競技復帰を目指す場合は、手術治療を検討します。 手術療法 手術は、患者自身の身体の他部分から腱を採取し、前十字靭帯の代わりとして移植する再建術が行われます。基本的には、膝に小さな穴を数か所開けて、そこから膝関節鏡や手術器具を挿入します。 手術後は手術した部分がしびれたり、感覚が鈍くなったりする場合があるほか、可動域制限が起こる可能性があるため、決められた範囲内のリハビリが大切です。なお、状態にもよりますが、一般的には術後2日目から本格的にリハビリが開始されます。 再生医療 再生医療は、前十字靭帯断裂の治療法の1つです。当院リペアセルクリニックでは、自己脂肪由来の幹細胞を用いた治療が行われます。 幹細胞治療とは、自身の身体から採取した幹細胞を外部で増殖させ、所定の量に達したら再び身体に戻す治療法です。幹細胞を採取する際は、おへその横からごくわずかな脂肪を採取するため、身体への負担を最小限に抑えられます。 幹細胞治療は入院・手術を必要とせず日帰りの施術が可能なため、治療期間の短縮が期待できます。手術せず治療を受けたい場合に、再生医療はおすすめです。 前十字靭帯断裂の予防策 前十字靭帯断裂をした場合、治療に時間がかかるため引き起こさないよう予防が大切です。予防法には、膝関節の安定性を高めるトレーニングが必要になります。 大腿四頭筋(だいたいしとうきん)や太ももの裏側の筋肉となるハムストリングス、ふくらはぎの筋肉が膝関節を支えているため、トレーニングで鍛えましょう。 前十字靭帯断裂の予防策としては、以下のトレーニングが効果的です。 スクワット ランジ ストレッチ バランストレーニング トレーニングは無理のない範囲で行うことが重要です。前十字靭帯断裂のリスクを軽減するためにも、膝関節の安定性を高めるトレーニングを実施しましょう。 前十字靭帯断裂の悪化を防ぐためには早めの受診が重要 前十字靭帯断裂は主にスポーツ選手が引き起こす疾患で、自然治癒するのは難しいため治療が必要になります。主な原因にはスポーツのほか、交通事故やホルモンバランスも挙げられます。 手術をしないで放置すると、スポーツ活動だけでなく、日常生活に支障をきたすため、疑いがある場合は早めの受診が重要です。 治療法には手術のほか、再生医療もあるため、自分にあった方法で前十字靭帯断裂の症状回復を目指しましょう。 当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。前十字靭帯断裂について気になる症状が見られる方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。 前十字靭帯断裂に関するよくある質問 前十字靭帯断裂でスポーツ・立ち仕事復帰までの期間はどのくらいですか? 前十字靭帯断裂の場合、スポーツ復帰は術後6カ月〜1年が目安です。無理をすると、再断裂や半月板損傷のリスクが高まるため注意しなければなりません。 復帰までの期間には個人差があるため、医師と相談しつつリハビリを行い、早期復帰を目指しましょう。 また、仕事復帰はデスクワークや軽作業の場合で1カ月ほどが目安です。立ち仕事や重いものを運ぶ場合、復帰までには3カ月ほどかかるケースもあります。 前十字靭帯断裂で歩けるまでの期間はどのくらいですか? 前十字靭帯断裂の手術をした場合、松葉杖を使用すれば手術翌日から歩けます。松葉杖なしで歩けるようになるまでには、2週間〜1カ月ほどが目安です。 また、膝の不安定さに懸念がある場合は、サポーターを使用するケースもあります。したがって、日常生活に戻るまでには、早くても2週間ほど時間を要する点を理解しておきましょう。 前十字靭帯断裂は術後に再断裂の可能性がありますか? 前十字靭帯断裂の手術をしたからといって、必ずしも再断裂しないとは言い切れません。前十字靭帯は一度断裂すると膝の不安定感が強いため、手術後も再断裂の可能性があります。 とくに、術後6カ月〜1年は再断裂に注意が必要です。再断裂しないためにも、膝関節を安定させるトレーニングを無理のない範囲で行うことが大切です。 参考文献 文献1 日本臨床スポーツ医学会誌|当院の膝前十字靱帯損傷症例における受傷状況の調査 文献2 J-STAGE|A Greater Reduction of Anterior Cruciate Ligament Elasticity in Women Compared to Men as a Result of Delayed Onset Muscle Soreness
-
【医師監修】腸脛靭帯炎(ランナー膝)とは|症状・原因・治し方からセルフケアまで解説
「膝の外側が痛くて走れない」「腸脛靭帯炎が疑われるもののどう対処すれば良いのかわからない」といった悩みを抱える方もいるでしょう。腸脛靭帯炎(ランナー膝)は、膝の外側にある腸脛靭帯が炎症を起こすことで痛みが生じるスポーツ障害の一つです。悪化すると歩行や階段昇降でも痛みが出るため、適切な治療が欠かせません。 今回は、腸脛靭帯炎の症状や原因、治し方などをわかりやすく解説します。腸脛靭帯炎のときにやってはいけないことやセルフケアについてもまとめているので、膝の痛みでお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。 当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。気になる症状がある方は、ぜひ公式LINEにご登録ください。 腸脛靭帯炎(ランナー膝)とは 腸脛靭帯炎は、太ももの外側を走る「腸脛靭帯」が炎症を起こすことで痛みが生じる疾患です。腸脛靭帯は骨盤からすねの骨までをつなぐ靭帯で、膝の曲げ伸ばしを支える役割があります。 腸脛靭帯炎は長距離ランナーやマラソン愛好者など、繰り返し膝を曲げ伸ばしする動作を行う人に多く見られ、走行中やランニング後に痛みが出やすい点が特徴です。このような背景から、「ランナー膝」とも呼ばれています。 腸脛靭帯炎(ランナー膝)の症状 腸脛靭帯炎の主な症状は膝の外側の痛みです。そのほか、特徴的な症状には次のようなものがあります。 走行中やランニング後に膝の外側がズキッと痛む 階段の昇降や膝の曲げ伸ばし動作で痛みが増す 歩行時に膝の外側に張りや違和感を感じる 膝の外側を押すと鋭い痛みが走ることがある 初期段階では軽い違和感で済むことが多いものの、痛みを我慢して走り続けると炎症が悪化し、歩行にも支障が出るほど重症化するケースもあります。そのため、腸脛靭帯炎が疑われる場合は、早めの休息と適切な対処が必要です。 関連記事:ランナー膝の治し方は?やってはいけないことや膝の外側の痛みのチェック方法も解説 腸脛靭帯炎(ランナー膝)の原因 腸脛靭帯炎は、膝の曲げ伸ばしを繰り返すことで腸脛靭帯と大腿骨の外側がこすれ続けることが主な原因です。こすれる回数が増えるほど摩擦が大きくなり、炎症が生じやすくなります。 腸脛靭帯炎の発症リスクを高める要因には以下のようなものがあります。 長距離ランニング 坂道走行などの負荷の高いトレーニング アスファルトなど硬い路面での練習 O脚や偏平足などの問題 太ももや股関節の筋力不足 クッション性が低い靴の使用 など これらの要因が重なると炎症を起こしやすくなるため、トレーニング環境の見直しや適切なシューズ選びなどをして、膝への負担を減らすことが重要です。 腸脛靭帯炎(ランナー膝)のときにやってはいけないこと 腸脛靭帯炎は、間違った対処をすると回復に時間がかかるだけではなく、慢性化につながる可能性があります。そのため、腸脛靭帯炎のときは以下のような行動に注意しましょう。 強い痛みがある状態でランニングを続ける 長時間立ち仕事をする 長時間同じ姿勢を維持する 急な方向転換やジャンプ動作をする 痛む箇所を強く押す 必要以上にストレッチを行う 摩耗した靴を履いて走行する 炎症がある時期は安静を優先し、痛みを悪化させる行動を避けることが早期改善につながります。無理を続けると症状が長引くだけでなく、再発の恐れもあるため注意が必要です。膝の外側に痛みが生じたら運動を中止し、早めに医療機関を受診しましょう。 腸脛靭帯炎(ランナー膝)の治し方 腸脛靭帯炎は、早期の治療と再発予防が大切です。代表的な治療法は保存療法・手術療法・再生医療の3つで、症状の程度や治療目的に応じて選択されます。ここでは、それぞれの治療法を紹介するので、ぜひ参考にしてください。 保存療法 保存療法は、腸脛靭帯炎の治療で最も一般的な治療法です。 腸脛靭帯炎の保存的治療は、腸脛靭帯の緊張を和らげるストレッチや、筋力強化などの理学療法を組み合わせて行うのが基本です。また、必要に応じて、超音波や電気刺激などの物理療法を併用して痛みを軽減します。 なお、痛みが強い場合には、消炎鎮痛薬やステロイド注射を使用するケースもあります。治療の継続によって炎症を抑え、症状を改善して運動復帰を目指します。 手術療法 手術療法は、数カ月保存療法を継続しても症状が改善しない重度の腸脛靭帯炎に限り検討されます。腸脛靭帯炎の手術では、腸脛靭帯の一部を切除し、骨との摩擦を減らすことで炎症の原因を取り除きます。 ただし、腸脛靭帯炎は保存療法で改善するケースが多く、手術はあくまで最終手段です。手術後にはリハビリが必要になるため、回復までの時間も考慮して慎重に判断されます。 再生医療 腸脛靭帯炎の治療法として、再生医療が注目されています。主にPRP療法(多血小板血漿注射)や幹細胞治療などが用いられ、自己細胞を炎症部位や損傷部位に注入して組織の修復を促します。 再生医療は手術をせずに回復を目指せる点が特徴です。そのため、ほかの治療法で十分な効果が得られていない方や手術を避けたい方の選択肢となります。ただし、再生医療は保険適用外の治療も多いため、専門医との十分な相談が不可欠です。 当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。腸脛靭帯炎の治療法についてお悩みの方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。 腸脛靭帯炎(ランナー膝)を早く治すためのセルフケア 腸脛靭帯炎は治療と並行して自宅でできるセルフケアを取り入れると、より早い改善が期待できます。ここでは、腸脛靭帯炎のセルフケア方法を紹介するので、ぜひ参考にしてください。 ストレッチでほぐして負担を軽減する 腸脛靭帯炎を早く治すためには、ストレッチでほぐして膝への負担を軽減することが大切です。ただし、痛みが強い時期に無理なストレッチをすると症状が悪化する可能性があるため、炎症が落ち着いてから行いましょう。 腸脛靭帯炎のセルフケアにおすすめのストレッチは、以下の4種類です。 ストレッチ名 方法 期待できる効果 フォワードフォールド 直立して左足を右足の後ろに交差させる 腰を前に倒し、左わき腹が伸びる位置で手を床につく その姿勢で2〜3秒キープする 元の姿勢に戻る 太もも裏・お尻・腰を伸ばす ラテラルストレッチ 壁や椅子に片手を添えて体を安定させる 壁側の足を後ろに引き、反対側の足と交差させる 壁に向かって腰を寄せ、壁側の腰まわりをしっかり伸ばす 元の姿勢に戻る 体の側面・太もも外側を重点的にほぐす 4の字ストレッチ 仰向けに寝て膝を立て、足を腰幅より少し広めに開く 右足首を左膝に乗せて「4の字」を作る 組んだ足で反対側の膝をゆっくり床方向へ押し下げる 元の姿勢に戻る お尻・股関節をほぐす タオルを使ったストレッチ 床に座り、タオルを片足にかける そのまま仰向けになり、タオルをかけた足をまっすぐ天井へ伸ばす 反対側の足のかかとが床についたままになっているか確認する 持ち上げた足をゆっくりと体の反対側へ倒して伸ばす 腸脛靭帯周辺を伸ばす これらのストレッチを日常的に取り入れることで、腸脛靭帯への負担が減り、再発予防につながります。 痛みを早く取るために、痛みがあるうちにストレッチをすることは厳禁です。かえって痛みが再発する可能性が高いです。ストレッチは走った時の痛みがないことを確認し、再発予防にストレッチを取り入れるという意識で行いましょう。 テーピングやサポーターで膝の安定性を高める 腸脛靭帯炎の改善には、テーピングやサポーターの使用もおすすめです。テーピングやサポーターを使って膝の安定性を高めると、ランニング時の摩擦や負荷を軽減しやすくなります。 テーピングは貼り方によってサポートの強さや位置を細かく調整できるため、症状に合わせやすい反面、正しく巻くには知識や練習が必要です。一方で、サポーターは着脱が簡単で初心者でも手軽に使える点が魅力です。そのため、運動時だけではなく、日常生活でも利用しやすいでしょう。 症状の程度や運動量に合わせて、ご自身に合った方法を選ぶようにしてください。 自分に合った靴を選ぶ 足に合わない靴を履いていると膝に余分な負荷がかかり、腸脛靭帯炎を引き起こす原因になりかねません。そのため、靴選びは予防・改善の上における重要なポイントです。具体的には、以下のポイントを確認して靴選びをしましょう。 つま先に適度な余裕があるか かかとがしっかり固定されるか クッション性が十分か 自分の足型(扁平足・ハイアーチなど)に合っているか 腸脛靭帯炎は自分に合った靴に変えるだけで症状が改善するケースもあります。また、日頃からソールが極端にすり減っていないか靴の状態をチェックして早めの対策に努めましょう。 関連記事:腸脛靭帯炎を早く治す方法は?やってはいけないことや何日で治るか解説【医師解説】 腸脛靭帯炎(ランナー膝)を早く治すためにも早期治療に取り組もう 腸脛靭帯炎を早く治すためには、初期の段階で適切な対処を行うことが重要です。 腸脛靭帯炎は、膝の違和感や軽い痛みの段階でランニングを中止し、ストレッチや筋力強化などのケアを行うことで、比較的早期の改善が期待できます。しかし、痛みを無視して走り続けたり、無理にトレーニングを継続すると炎症が悪化し、慢性化して回復までに長い時間がかかります。 腸脛靭帯炎からの早期回復を目指すためにも、症状が現れた時点で早めに医療機関を受診するようにしてください。 当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。気になる症状がある方は、ぜひ公式LINEにご登録ください。 腸脛靭帯炎(ランナー膝)に関するよくある質問 腸脛靭帯炎がなかなか治らないのはなぜですか? 腸脛靭帯炎が治りにくいのは、多くの場合、使いすぎによる炎症が長期間続いているためです。痛みを我慢して走り続けたり、長時間同じ姿勢で過ごしたりすることで組織の回復が追いつかず、炎症が慢性化しやすくなります。 また、足に合わない靴の使用や筋力のアンバランスの乱れといった根本原因が改善されないことも回復を遅らせる要因です。腸脛靭帯炎がなかなか治らない場合は、原因を見極めて適切に対処する必要があります。 腸脛靭帯炎は走りながら治せますか? 腸脛靭帯炎の治療は安静が基本です。そのため、痛みを感じる段階でのランニングは推奨できません。 治療の進行度によっては軽めのジョギングを再開できる場合もありますが、歩行や階段昇降など日常動作で痛みがないか確認してから、無理のない範囲で行いましょう。 関連記事:ランニングによる膝外側の痛み|ランナー膝(腸脛靭帯炎)の直し方や予防法について解説

膝の痛みにまつわるQ&A
<骨切り術のメリット>
骨入り術という手術のメリットは、何より自分本来の関節を残すことができることです。骨が癒合(接着、固着に至る)すれば活動制限もなくなり、QOL(日常生活の質)の向上はもちろん、スポーツなどを行うことも可能になります。
また、人工関節への置換術と違い、金属を体内に残すことがありません。そのため脱臼や、将来訪れる人工関節の寿命に際する再手術という心配がありません。
<骨切り術のデメリット>
手術後、入院とリハビリを合わせて長期にわたる療養期間が必要になります。(個人差はありますが、約6ヶ月程)その間、骨が癒合するまでの間は、激しい動きや負荷のかかる動作は控えていただく事となります。
また手術という性格上、身体にメスを入れることとなり、合併症を含めた手術上のリスクが発生します。もちろん身体に負担をかけることは否めません。何より治療においては、仕事や家庭生活を長期間、離れる必要があり、その点が大きなデメリットになるでしょう。
ジャンプ動作の多い競技によく見られる症状です。
膝蓋骨の内側に引っ張られる感覚があり、膝関節を動かすと痛みが出ることがあります。
膝関節の内側と大腿骨の間にある滑膜ヒダの張り出している部分が膝蓋骨と大腿骨の間に挟み込まれ、膝関節を動かしたときに膝蓋骨の内側に引っかかりを感じ痛みが生じます。
これをタナ障害と言い、膝関節に慢性的に負担をかけることで、タナが厚くなったり硬くなったりすることで挟み込まれて症状を引き起こします。
主に太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)がストレッチ不足になっていることが主因と言えますが、先天的に膝蓋骨の形の悪い人や膝蓋腱が長い方も症状を引き起こす可能性が高いと言えます。引っかかりや痛みが生じた状態を長期間放置していると、安静時や起立時でさえも重苦しさが残り疼痛が持続します。そこまで放っておくと、運動パフォーマンスにも支障を来します。
ただ、膝の内側が痛むときは必ずしもタナ障害だとは言い切れません。痛みの原因がタナではなく膝蓋骨や軟骨などに見られることもあります。訴える症状とタナとの関連性を十分に精査する事が必要となります。
その点からも診断では必ずMRI検査を受けましょう。
但し、ほとんどの患者様が、タナ障害で手術に至る人は少ないようですが、まずは疼痛になる運動を回避し、大腿四頭筋の強化やストレッチをすること。
また、痛み止めの服用や温熱療法(熱感があるときは冷却療法)を施し、それでも痛みが引かないときには関節内にステロイド注射を打ち様子を見ます。これらの対処でも改善されない場合や物理的にタナが大きくて引っかかりが強く膝が伸びない場合は他の部位に影響を及ぼすこともあるので手術療法を選択します。
当院では、再生医療のP R P療法を用いて痛みのある膝関節に投与する事で患部の症状を改善する事が可能です。
整形外科で行われている治療方法は、投薬・注射・リハビリ等が一般的では有りますが。どちらの治療方法も一時的に症状の緩和や関節の変形・組織の修復を完全に行う事は難しいです。
結果的には、症状の軽快が、見られない場合は手術の提案になる事が多く見られます。
その為、手術を避けたい患者様の治療法が対処療法になってしまい、根本的な治療の提案と選択肢を広げていく為には、再生医療が非常に有用であると言えます。
手術以外の選択をお考えであれば、一度ご相談頂ければと思います。
変形性膝関節症には、重症度や進行度を示すグレード(ステージ)分類(Ⅰ~Ⅳ)が主にレントゲン画像を見ることで分類することができます。
グレードⅠ:
大きな変化はないが、変形性膝関節症が疑われる状態
グレードⅡ:
膝関節の隙間に僅かな狭小が見られる状態。(25%以下)骨の変化は無いが、僅かに骨の棘(骨棘)が見られる事がある。
グレードⅢ:
膝関節の隙間が半分以上に狭小した状態。(50~70%)骨棘の形成や骨硬化がはっきりと見られる。
グレードⅣ:
膝関節の隙間が75%以上狭小した状態となり、消失の場合もある。大きな骨棘と骨の変化が大きく見られる。
通常の診察では、レントゲンやM R Iで確定診断を行なっていきますが、一定期間、ヒアルロン酸注射など、同じ治療方法を継続して経過を診ていき、変化が見られない場合は定期的なチェックを行った後、手術の治療を選択される場合がほとんどです。
痛みが変わらないのであれば、現在治療されている方法の見直しを行う為にも主治医にご相談されると良いと考えます。
一方、再生医療での幹細胞治療では、すり減った軟骨を再生させる効果を期待できる事から、膝関節のクッション性を高める事により痛みの原因を緩和させる事が出来る治療となっており手術以外の可能性を秘めた治療となっています。
一度ご相談頂ければと思います。
歩行で痛いのであれば膝関節に何らかの原因が考えられます。
再生医療は様々な膝痛にも対応でき、痛みをとる可能性が高い治療法となっております。
ただし、今悩んでおられる膝関節の症状がどのようなもので、どういう状態か診断する必要があります。
一度ご相談を承りますのでお気軽にお問い合わせください。
少しずつ症状が進行しているように思います。
膝の痛みの原因の多くは変形性膝関節症と診断される事が多いです。
軟骨が徐々に減ってしまう事で、膝関節のクッション性が減少し、変形が進んでしまいます。その様な状態が進むと、手術も視野に入れなければなりません。
今気になっておられるのであれば、関節が痛みとしてSOSを出しているのかも知れません。一度受診されてはいかがでしょうか。
問診にて詳しく情報をまとめ、治療法を提案させていただきます。
再生医療が可能であるか判断するためにも、受診をお勧めいたします。










