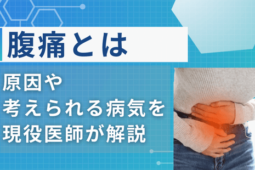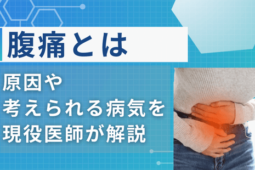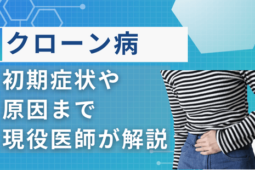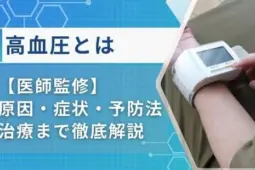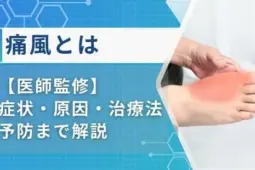- 内科疾患
- 内科疾患、その他
大腸がんの初期症状とおならの変化|早期に気づくチェックポイントとは
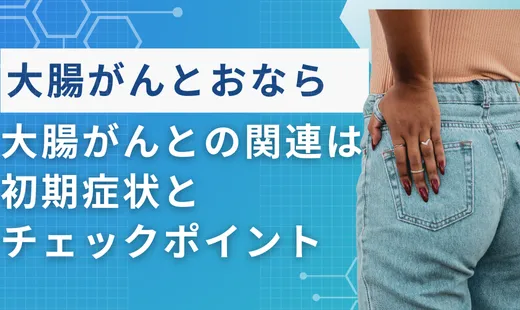
大腸がんは年間約15万5千人が新たに診断される日本人に多いがんで、とくに女性のがん死亡原因第1位です。
早期発見が生存率を大きく左右しますが、初期症状はほとんどなく、進行してから気づくケースも少なくありません。
こうした中「おならの異変が大腸がんの初期症状の一つである可能性」が注目されています。おならは誰にでも起こる生理現象ですが、その回数や臭いの変化が体の不調を反映することがあります。
本記事では大腸がん初期症状とおならの関連性について、危険なおならと正常なおならの違いを含めて解説します。
また、おなら以外の大腸がん初期症状についてもわかりやすく説明し、早期発見のためのポイントを紹介します。異変に気づいた際に自己判断せず医療機関を受診する重要性についても触れますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
大腸がん初期症状と「おなら」の関連性
大腸がんの初期症状としておならの状態変化が挙げられることがあります。実際、「おならの頻度が増えた」「おならの臭いが強烈になった」「おならの際に腹痛を伴う」といった変化が見られる場合には注意が必要です。
大腸がんがあると腸内の環境に変化が生じ、以下のような理由でおならに異常が現れる可能性があります。
| 腸内の変化 | 説明 |
|---|---|
| 腸内にガスが溜まりやすくなる |
大腸内に腫瘍ができると腸の通り道が部分的に狭くなり、食べ物の消化やガスの排出がスムーズに行かなくなります。 結果として腸内にガスが溜まり、おならの回数が増える原因となります。 |
| 腸内細菌のバランス変化 |
腫瘍から分泌される代謝産物や腫瘍の存在そのものが腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう:腸内の細菌バランス)に影響を与えることがあります。 その影響でガスの成分が変わり、おならの臭いが以前より異常に強くなることがあります。 |
| 腸の運動変化 |
腫瘍による刺激で腸の蠕動運動(ぜんどううんどう:腸が内容物を送り出す動き)が乱れることも指摘されています。 その結果、お腹がゴロゴロ鳴ったりガスが頻繁に発生します。とくに腹痛を伴うおならが続く場合は腸内でなんらかの異変が起きているサインかもしれません。 |
もっとも、おならの変化だけで大腸がんと断定はできません。おならの臭い・回数は食生活や体調によっても日常的に変動します。たとえば芋類や豆類を多く食べればおならの回数は増えますし、肉や卵を多く摂れば硫黄のような強い臭いになることもあります。
重要なのは「普段と比べて明らかに異常なおならが続くかどうか」です。次の項で危険なおならと正常なおならの違いを整理しますが、おならの異変に気づいたときは他の初期症状がないかも確認し、少しでも思い当たることがあれば早めに医療機関で相談してみましょう。
危険なおならと正常なおならの違いについて
| おならの種類 | 説明 |
|---|---|
| 正常なおならの範囲 |
健康な人でも1日に数回~十数回程度のおならは出ます。臭いも食事内容によって強くなることがありますが、一時的なものがほとんどです。 お腹が張って苦しくなるようなこともなく、ガスは自然に排出されます。 |
| 注意すべき異常なおなら |
以前と比べて急におならの回数が増えたり、逆にまったくおならが出なくなったりする場合は腸内異常の兆候です。 また、臭いが異常に強烈(腐敗臭や卵が腐ったような硫黄臭)になった状態が続くのも要注意です。 さらに、おならに腹痛や腹部の張りを伴う場合も正常ではありません。これらの変化が見られるときは、単なる食生活の問題ではなく消化器の病気(大腸がんを含む)の可能性を考えて早めに受診しましょう。 |
普段のおならと比べて明らかにおかしいと思われるおならの特徴を押さえておきましょう。一般的なおなら(正常範囲)と、大腸がんなど病的な原因が疑われるおならとで何が違うのかを比較します。
上記のような危険なおならに該当する場合でも、それだけですぐ大腸がんと決めつけることはできません。ただし、おならの異常に加えて後述するような他の症状がみられる場合は、大腸がんの初期症状として現れている可能性があります。
おならと他の症状、両方の異変が重なったときは早期発見のチャンスでもあるため、自己判断せず医療機関で検査を受けることが大切です。
おなら以外の大腸がん初期症状
大腸がんは初期には自覚症状がほとんどありませんが、腫瘍がある程度大きくなってくると徐々に体の変化が現れ始めます。(文献2)
代表的な初期症状としては、血便、排便習慣の変化(便秘・下痢)、便が細くなる(便の狭小化)、残便感、貧血、腹痛、嘔吐などが挙げられます。
これらはいずれも大腸がん以外の病気でも起こり得る症状ですが、複数の症状が重なっている場合や、明らかにいつもと違う状態が続く場合には注意が必要です。以下にそれぞれの症状について、具体的にどのような様子か説明します。
血便
血便(けつべん)とは、便に血液が混じる症状です。大腸がんができると腫瘍表面の血管が傷つきやすくなり、便が通過する際に出血して便に血が付着することがあります。血便の特徴として、出血カ所が肛門に近いほど鮮やかな赤色になりやすい傾向があります。
直腸やS状結腸(大腸の一番下の部分)にがんがある場合は鮮血が混じりやすく、上行結腸(右側の大腸)など上流にある場合は暗めの色になることもあります。
少量の血便だと痔(じ)かな?と放置してしまう人もいますが、痔と大腸がんの見分けは自己判断ができません。とくに40代以降で血便が続く場合は痔の持病があっても油断せず、一度大腸内視鏡検査などで確認しましょう。
便秘、下痢
便秘や下痢が続く、あるいは便秘と下痢を繰り返すのも大腸がんの初期にみられることがあります。腫瘍が腸内にできると腸の動き(ぜん動運動)が乱れたり、腸管が狭くなることで便通リズムが狂いやすくなります。
その結果、頑固な便秘になったり、下痢が増えたりします。特徴的なのは、便秘と下痢を交互に繰り返すパターンです。腸に便が溜まって便秘になった後、下痢で一気に出る場合、腸内に通過障害が発生している可能性があります。
普段は便秘をしないのに急に便秘が続くようになった、下痢をする頻度が増えた、あるいは以前と比べて明らかに排便の習慣が変わった場合、大腸の異常を疑ってみましょう。
食生活の変化やストレスでも一時的に便通は変わりますが、原因に心当たりがないのに数週間以上そうした状態が続くなら念のため検査を受けることをおすすめします。
便の狭小化
便の狭小化(きょうさいか)とは、便が細くなる症状です。腸内を通る便の太さが腫瘍によって物理的に制限されるため、鉛筆のように細い便が出ることがあります。
とくに直腸やS状結腸など大腸の下部にがんがある場合、便が形作られる段階で細く絞られてしまうため、狭いリボン状の便が続くことがあります。
「最近、便が細長くなった」「いつもより便の径が明らかに細い」と感じたら注意が必要です。便の狭小化自体は他の要因でも起こりますが、従来との明らかな変化は見逃さないようにしましょう。
便秘・下痢の項目で述べた便通異常とあわせて、便の形状変化も大腸がん初期のサインの一つです。
残便感
残便感(ざんべんかん)とは、排便した後にまだ腸に便が残っているように感じる症状です。大腸がんが直腸付近にできると、腫瘍が物理的に邪魔をしたり肛門付近を刺激したりするため、トイレに行ってもまだ出し切れていない感じが続くことがあります。
残便感は便秘や過敏性腸症候群などでも起こるため、それ単体では判断が難しい症状です。しかし残便感が長く続く場合や、残便感とともに便に血が混じる・お腹が痛いといった他の症状がある場合は、大腸がんの疑いも考慮する必要があります。
一度排便してもすぐまたトイレに行きたくなる、いつもお腹に何か溜まっている感じがする、といった状態が続けば医療機関で相談しましょう。
貧血
大腸がんによる貧血(ひんけつ)は、腫瘍からの慢性的な出血が原因で起こります。便に目に見える血が出ていなくても、少しずつ出血していると体内の鉄分が失われていき、鉄欠乏性貧血になります。貧血になるとめまいや立ちくらみ、疲れやすさ、動悸、顔色が青白くなるなどの症状が現れます。
日常的に疲労感が強かったり、階段を上っただけで動悸・息切れがしたりする場合、血液検査で貧血が判明することがあります。とくに中高年で原因不明の貧血が見つかった場合、大腸を含む消化管からの出血が疑われます。
女性の場合は月経など他の要因もありますが、長引く貧血症状があるときは一度消化器の検査(便潜血検査や内視鏡検査)を受けましょう。
腹痛
腹痛(ふくつう)も大腸がんがある程度進行すると出てくることがあります。
腫瘍が大きくなり腸の中が狭くなると便の通過に支障が出るため、腸が詰まったような張った痛みや差し込むような痛みを感じますが、とくに下行結腸やS状結腸など便が固形になってから通る下部の大腸にがんがある場合、腸閉塞(ちょうへいそく:腸の詰まり)を起こしやすく、強い腹痛が起こりやすいとされています。
一方、上行結腸(右腹側)など大腸の右側にがんがある場合、内容物が液状のまま通過するため比較的痛みは出にくいとも言われます。
痛みの有無はがんの場所によって異なりますが、お腹の痛みが慢性的に続く場合や、便通と関連して腹痛が起きる場合は精密検査を受けることを検討しましょう。
嘔吐
一見関係なさそうな嘔吐(おうと)も、大腸がんの症状として起こることがあります。これは主に腸閉塞(腸がふさがった状態)に陥った場合に見られる症状です。腫瘍が腸管をふさぐほど大きくなると、食べ物や消化物が先に進めず行き場を失ってしまいます。
その結果、腸の内容物が逆流して嘔吐を引き起こすことがあります。ひどい場合には便のような臭いの嘔吐(吐物が腸の内容物)になるケースもあり、これは緊急手術が必要な状態です。大腸がんの初期段階で嘔吐まで生じることは稀ですが、腹痛や膨満感がひどく吐き気を催す場合には注意が必要です。
とくに食事とは関係なく繰り返し吐き気・嘔吐が起こる場合、消化管のどこかに閉塞が起きている可能性があります。放置すると脱水や深刻な状態に陥るため、早急に医療機関を受診してください。
以上のように、大腸がんが進行し始めるとさまざまな症状が現れます。ただし繰り返しになりますが、初期の大腸がんでは目立った症状が出ないことが多い点に注意が必要です。
「なんとなく調子が悪いけど病院に行くほどではないかな…」と思っているうちに見過ごしてしまうケースもあります。少しでもおかしいと感じる症状があれば、無理に楽観せず専門医に相談しましょう。
大腸がんを早期発見するためのポイント
大腸がんから身を守るには、早期発見・早期治療が何より重要です。早期であれば大腸がんは高い確率で完治が可能で、内視鏡による日帰り手術で治療できるケースも多くあります。
そのため、症状が出揃ってからではなく症状が軽微なうち、あるいは症状がない段階で発見が理想です。
早期発見のために心がけたいポイントとして、日頃からのセルフチェックと定期的ながん検診の受診があります。以下に具体的に解説します。
初期症状チェックリスト|該当したら医療機関へ
まずは自分で気をつけたい初期症状のセルフチェックです。次のような症状に心当たりがある場合は要注意です。当てはまる項目が一つでもあれば、一度消化器科など専門医療機関で相談してみましょう。とくに複数当てはまる場合は放置しないでください。
- 便に血液や粘液が混じる、黒っぽい便が出る(血便・下血がある)
- おならの臭いが急に強くなった、おならの回数が急に増えた
- 便秘と下痢を繰り返すようになり、排便のリズムが乱れている
- 便が細くなった、最近出る便の量が減ったと感じる
- トイレに行ってもまだ出し切れていない感じ(残便感)がある
- 腹痛やお腹の張りが慢性的に続いている
- めまい・立ちくらみなど貧血症状が見られる
- 原因不明の体重減少がこの数カ月でみられる
- 食欲不振が継続している
こうした症状は大腸がん以外でも起こり得ますが、年齢が高くなってから現れた場合や症状が長引いている場合は大腸がんの可能性も考えて早めに検査を受けることをおすすめします。様子を見ようと放置せず、まずは専門のクリニックで相談しましょう。
とくに血便は重要なサインですし、おならの異常も軽視しない方が良いポイントです。おかしいと思った時点で消化器内科を受診すれば、万が一がんであっても早期に発見できる可能性が高まります。
大腸がん検診を受ける
自覚症状の有無にかかわらず、定期的に大腸がん検診を受けることも早期発見には欠かせません。日本では現在、40歳以上の方は年に1回、大腸がん検診(便潜血検査)を受けることが推奨されています。(文献1)
便潜血検査とは便の中に血液が混じっていないか調べる検査です。検査の結果、陽性(便に血が混じっている疑い)となった場合には、精密検査として大腸内視鏡検査(大腸カメラ)を行います。大腸がん検診は自治体の健康診断などでも実施されており、症状がないうちに検診を受けましょう。
大腸がんは早期であれば症状がない場合が多く、検診によって早期に発見し治療すると大腸がんで亡くなるリスクを大きく下げられます。(文献1)
実際、大腸がんは早期に発見できれば高い確率で治癒可能ながんです。
内視鏡検査でポリープや早期がんが見つかった場合、その場で切除して日帰りで治療を完了できるケースも多数あります。逆に言えば、検診を受けずに症状が出るまで放置してしまうと、発見時には進行して手術が大がかりになる・完治が難しくなるといったリスクが高まります。
とくに40代以上の方は忙しくても年に一度は大腸がん検診を受ける習慣を持ちましょう。また、ポリープが見つかった場合は医師の指示に従い定期的なフォローを受けることも大切です。
まとめ|初期症状のチェックや検診で大腸がんを早期発見しよう
大腸がんは早期には目立った症状が出にくい病気ですが、おならの異常や便通の変化など日常のサインを見逃さないことが早期発見につながります。「最近おならの様子がおかしい」「腹痛や血便が続いている」など、少しでも気になる初期症状がある場合は自己判断せず消化器の専門医に相談が重要です。
血便・便秘や下痢の反復・便の狭小化・残便感・貧血症状・腹痛・嘔吐など、大腸がんの疑いを示す症状はいくつかあります。これらの初期症状チェックを日頃から意識し、該当する症状があれば早めに医療機関を受診しましょう。
また、症状がなくても定期的に大腸がん検診を受けることが最大の防御策となります。幸い、大腸がんは早期に発見し適切に治療すれば怖がる必要はありません。違和感を感じたタイミングで勇気を出して専門クリニックを受診すれば、万が一大腸がんであっても早期のうちに治療でき、あなたの健康と命を守ることにつながります。
なお、当院「リペアセルクリニック」では、がん予防を目的として「免疫細胞療法」を行っております。
免疫細胞療法について詳しくは、以下のページをご覧ください。

再⽣医療で免疫⼒を⾼めることができる時代です。
参考文献
(文献1) 国立がん研究センター がん情報サービス「大腸がん検診について」https://ganjoho.jp/public/pre_scr/screening/colon.html .2024年9月20日.(最終アクセス:2025年4月22日)
(文献2) 国立がん研究センター がん情報サービス「大腸がん検診について」https://ganjoho.jp/public/cancer/colon/print.html .2024年9月20日.(最終アクセス:2025年3月24日)