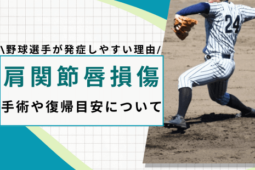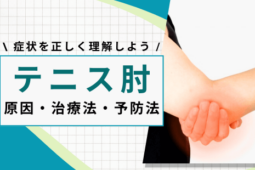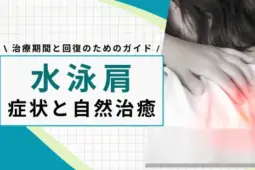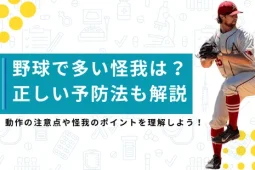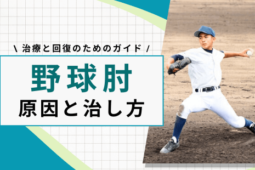- 上肢(腕の障害)
- スポーツ外傷
【医師監修】上腕二頭筋断裂とは|治し方や断裂後の生活を紹介

上腕二頭筋にこれまでにない違和感がある
腕に力が入らず、困っている
その症状、もしかしたら上腕二頭筋断裂かも知れません。
上腕二頭筋断裂は、上腕二頭筋腱長頭腱が損傷し、腕を動かすなどの動作に支障が出る症状です。
スポーツや日常生活で腕を酷使する方がなりやすい症状であり、放っておくと重症化する恐れがあります。
本記事では以下について解説します。
- 上腕二頭筋断裂について
- 上腕二頭筋断裂の診断方法
- 上腕二頭筋断裂の原因
- 上腕二頭筋断裂の治し方
- 断裂後の生活で気を付けるべきこと
上腕二頭筋断裂は正しい知識を身につけ、適切な処置と治療を受けることで改善できます。
腕に違和感がある方は、ぜひ最後まで読み進めてみてください。
上腕二頭筋断裂とは
上腕二頭筋断裂の症状は、肩や肘の近くの強い違和感です。
肩関節で肩甲骨につながる2本の腱と、肘で腕の骨の1本(橈骨)につながる1本の腱が重いものを持つ行為などで損傷し、上腕二頭筋断裂が引き起こされます。
上腕二頭筋断裂は部分的な断裂もあれば、完全に断裂してしまい、腱が骨から完全に離れることもあります。
また、肘から骨が離れることで、腕を特定の方向に動かすことが困難になります。
腱の断裂が部分的なものであれば、患部を動かすことはできるものの、無理な酷使で腱の断裂状態が悪化し、完全に断裂する可能性もあるので注意が必要です。(文献1)
上腕二頭筋断裂の診断方法
| 診断方法 | 内容 |
|---|---|
| 問診 | 受傷時の状況、違和感のある部位や程度、日常生活での支障などを確認します。 |
| 視診・触診 | 腕の腫れや変形(ポパイサイン)圧痛の有無などを確認します。 |
| 理学検査 | 腕の可動域や筋力、動作中の違和感の有無などを確認します。 |
| 画像検査 | レントゲン、超音波検査、MRIなどで腱の状態を確認します。 |
| 血液検査 | 通常は不要ですが、感染症などが疑われる場合には行われることがあります。 |
上腕二頭筋断裂の診断方法は以下の5つです。
- 問診
- 視診・触診
- 理学検査
- 画像検査
- 血液検査
上腕二頭筋断裂の診断は、検査を総合的に判断して行われます。検査の内容について解説します。
問診
| 診断項目 | 医師が確認する項目 | 患者が伝えること |
|---|---|---|
| 断裂時の状況 | いつ、どのような状況で受傷したか(重い物を持ち上げた、スポーツ中に強い負荷がかかったなど) | いつどこで何をしている時に違和感があったなど、詳細に伝える |
| 症状 | 腕のどこに違和感があるか。腕を曲げる、持ち上げるのが辛くないか | 腕のどこに違和感を感じるか。力を入れたり腕を曲げたりすると辛いかどうか |
| 既往歴 | 過去に肩や腕に違和感があったか。過去に治療や服用している薬がないかなど | 過去に肩や腕に怪我を負ったかの有無。現在の健康状態や服用している薬があれば、漏れなく伝える |
(文献1) 問診では断裂時の状況や症状、既往歴などを医師が確認します。断裂時の状況や症状をできるだけ細かく伝えることが大切です。
過去に腕や肩を怪我したことのある方は、その旨を伝えましょう。また、現在服用している薬も忘れずに伝えましょう。
問診の情報を元に医師は視診や触診を行い、必要に応じて画像検査などを実施します。
正確に状況や症状を伝えることで診断や治療精度の向上が期待できます。
また問診の段階で少しでも気になることがあれば、遠慮なく医師に相談しましょう。
視診・触診
| 診察項目 | 確認事項 | ポイント |
|---|---|---|
| 上腕の形状 | 力こぶの形が変わっていないか(ポパイ徴候) | 通常、断裂すると上腕の筋肉が下方にずれる |
| 圧痛の有無 | 腱の走行に沿って押したときに違和感があるか | 圧痛があると部分断裂の可能性が高い |
| 筋力テスト | 腕に力を入れたときの筋力が低下していないか | 筋力の低下が見られる場合、腱が完全に切れている可能性がある |
(文献1)
視診・触診では、医師が患部の外観を確認します。上腕の形状などが変形していないかの有無や、色の変化を視診します。
腱の走行に沿って押したときに違和感や、筋力テストでいつもより力が入らない場合は腱が切れている可能性が高いです。
視診・触診で上腕二頭筋長頭腱の有無を確認し、適切な治療方針を定めます。
理学検査
| テスト名 | 目的 | 方法 | 結果の見方 |
|---|---|---|---|
| ルーズテスト | 上腕二頭筋腱の安定性を評価 | 腕を外旋しながら肘を曲げ伸ばし、安定性を確認 | 異常な動きや引っかかりがあれば腱の不安定性を示唆 |
| フックテスト | 上腕二頭筋腱の完全断裂を評価 | 肘を90度に曲げた状態で、指を使って腱を引っ掛けられるか確認(文献2) | 違和感がある場合、炎症や部分断裂の可能性がある |
| バイセプス・スクイズ・テスト | 上腕二頭筋腱の完全断裂を評価 | 肘を90度に曲げた状態で上腕を両側から圧迫し、筋収縮を確認 | 筋収縮がなければ腱が完全に断裂している可能性がある |
| スピードテスト | 上腕二頭筋腱の炎症を評価 | 腕を前方に伸ばした状態で抵抗をかけながら挙上し、違和感を確認 | 違和感がある場合、炎症や部分断裂の可能性がある |
上腕二頭筋腱の症状に対して、どのテストを行うかは医療機関によって異なるものの、大枠は症状の確認です。
結果を医師が確認し、異常や違和感があれば、上腕二頭筋腱と診断される可能性があります。
画像検査
| 検査名 | 目的 | 特徴 | 適したケース |
|---|---|---|---|
| 超音波検査 | 腱の断裂や炎症を確認 | リアルタイムで腱の損傷を確認しつつ、動かしながら評価 | 簡易的な診断や、動作による変化を評価したいとき |
| MRI検査 | 腱や周囲組織の状態を詳細に評価 | 腱だけでなく、関節や周囲の軟部組織も詳細に確認可能 | より詳細な評価が必要な場合や手術の判断をする場合 |
(文献1)
上腕二頭筋腱の画像検査では、主にMRI検査と超音波検査が行われます。MRI検査では腱の断裂だけでなく、周囲の組織の状態を確認できます。
一方、超音波検査では腱の損傷や程度を視覚化する方法です。腕を動かしながらでも断裂の位置や大きさを正確に把握できます。
血液検査
血液検査は、必要に応じて行われます。腱断裂の直接的な診断では行いません。
感染症の有無や炎症反応、健康状態などを確認するために用いられます。
上腕二頭筋断裂の原因
| 原因 | どんなときに起こりやすい? |
|---|---|
| 加齢による腱の変性・脆弱化 | 年齢とともに腱が弱くなり、ちょっとした力でも切れやすくなる |
| スポーツなどの反復的な使用 | 野球やテニスなど、腕をよく使うスポーツで繰り返し負荷がかかったとき |
| 転倒や直接的な衝撃での外傷 | 転んだり、ぶつけたりして、強い力が腕にかかったとき |
| 腱板損傷などの肩の疾患 | 肩の他の部分が傷んでいると、上腕二頭筋に負担がかかりやすくなり、発症しやすくなる |
| ステロイド薬の長期使用 | 薬の影響で腱が弱くなることがある(文献3) |
上腕二頭筋断裂の原因は、加齢やスポーツなどで発生した外傷です。上腕二頭筋断裂の原因について解説します。
加齢による腱の変性・脆弱化
上腕二頭筋の腱は年齢とともに強度が弱まり摩耗しやすくなるため、発症リスクが上がります。
腱や筋肉の柔軟性を維持するために、日頃から軽いストレッチや適度な運動が大切です。
スポーツなどの反復的な使用
スポーツが原因で上腕二頭筋断裂は発症します。とくに腕を酷使するスポーツである野球やテニスなどは腕に負担がかかりやすく、発症リスクが高いです。
また、工場作業や土木作業で重いものを運ぶのが日常になっている人も、腕に負荷がかかりやすく、断裂の原因になります。
スポーツや重労働を行う前は適切な準備運動を行い、腱や筋肉を慣らしておくことが大切です。
転倒や直接的などの外傷
| 処置名 | 説明 | ポイント |
|---|---|---|
| Rest(安静) | 患部を動かさずに安静にし、さらなる損傷を防ぐ | 無理に動かさず、適切な休息を取る |
| Ice(冷却) | 氷や冷却パックを当て、炎症や腫れを抑える(1回20分目安) | 冷やしすぎに注意し、直接皮膚に当てないようにする |
| Compression(圧迫) | 包帯などで適度に圧迫し、腫れを最小限に抑える | 強く締めすぎず、血流が悪くならないようにする |
| Elevation(挙上) | 患部を心臓より高く持ち上げ、血流をコントロールして腫れを防ぐ | 横になってクッションを使うと楽に挙上できる |
転倒した際に腕を地面につけたり重いものを押さえたりすると、腱に負荷がかかります。とくに急な負荷だった場合、断裂する可能性があります。
もし転倒や重いものを持ち上げ、腕に負荷がかかってしまった場合は、RICE処置:Rest(安静)・Ice(冷却)・Compression(圧迫)・Elevation(挙上)を行いましょう。
ただし、RICE処置はあくまでも応急処置のため、違和感が続く場合は自己判断せず、速やかに医療機関を受診しましょう。(文献1)
腱板損傷などの肩の疾患
| メカニズム | 影響 |
|---|---|
| 肩関節の不安定性 | 腱板が損傷すると、肩関節の安定性が低下し、上腕二頭筋腱がずれやすくなる |
| 腱の摩擦と炎症 | 腱が周囲の組織と摩擦しやすくなり、炎症が生じる |
| 血流の低下 | 血流が低下すると、腱の修復能力が落ち、断裂しやすくなる |
腱板損傷などの肩の疾患で、上腕二頭筋断裂が引き起こされます。
腱板の中でも棘上筋腱は上腕二頭筋腱のすぐ上に位置します。そのため、棘上筋腱の断裂は上腕二頭筋腱の断裂に直接的な影響を与える可能性もあります。(文献1)
慢性化すると腱の脆弱化が進行し、断裂の危険性が高まります。対策として、過度な負荷や無理なトレーニングは控えましょう。
ステロイド薬の長期使用
2024年1月更新の患者向薬品ガイド資料7Pによると、ステロイド薬であるプレドニン錠 5mgの副作用として、腱断裂が自覚症状とて現れることが記載されています。(文献3)
患者向薬品ガイド資料では、ステロイド薬の使用による腱組織の脆弱化などが指摘されています。
ステロイド薬については以下の記事で詳しく解説しています。
上腕二頭筋断裂の治し方
| 上腕二頭筋断裂の治療法の選択 | |||
|---|---|---|---|
| 対象者 | 推奨される治療法 | メリット | 適した人 |
| 腕を酷使しない人 | 保存療法 | リハビリやサポーターで日常生活に支障が出にくい | 腕を強く使う必要がない人 |
| 力仕事やスポーツをする人 | 手術療法 | 筋力が回復し、腕の動きが元通りに近づく | 仕事やスポーツで腕をしっかり使う人 |
上腕二頭筋断裂の治し方は、主に保存療法と手術療法です。保存療法と手術療法について解説します。
保存療法
| 保存療法の方法 | 内容 |
|---|---|
| 安静 | 患部を安静に保ち、過度な負荷を避ける |
| 冷却 | 患部を冷却し、腫れや炎症を抑える |
| 薬物療法 | 鎮痛剤や抗炎症薬を使用して、違和感を緩和する |
| リハビリテーション | 腕に抱える違和感が改善次第、筋力の回復を目指す |
保存療法が選択されるケースとしては主に腕を治療する時間があり、腕を酷使しない人の場合です。
保存療法のメリットは、日常生活に支障が出にくいことです。
しかし、ポパイサイン(断裂した後にできる力こぶのような変形)が肘を曲げた際に生じることが理由で、手術療法を選択するケースもあります。
手術療法(縫合・再建手術)
| 手術の種類 | 概要 | 手術を行うケース | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 腱の縫合(再接着手術) | 切れた腱を元の位置に戻し、縫合して再接着する | 完全断裂の場合 | 腱を強固に固定し、機能回復が期待できる |
| 内視鏡を使った手術(関節鏡手術) | 内視鏡を使い、小さな切開で腱を修復 | 腱の切れ目が深い場所にあるときや、体の負担を減らしたいとき | 傷口が小さく、回復が早い |
| 再建手術(腱移行術) | 失われた腱を他の筋肉や腱で再建する | 長期間放置された断裂や、大きく腱が失われた場合 | なくなった腱を補える |
| 腱の転移(筋腱移行術) | 他の筋肉を移植し、上腕二頭筋の機能を補う | 上腕二頭筋の腱がなく、再建も難しいとき | 筋肉の力を利用して、腕の機能を回復させる |
保存療法で改善せず、症状が重度の場合は手術療法が必要です。手術は肘関節や肩関節の機能を回復させるのが目的です。
手術の方法は腱の切れ方や、症状によって異なるため、医師の判断で行われます。手術後は医師の指導のもと、リハビリで症状改善を目指します。
手術を受ける際にわからないことや、不安なことは遠慮せず医師に質問しましょう。
断裂後の生活で気を付けるべきこと
断裂後の生活で気を付けるべきことを解説します。
上腕二頭筋断裂を起こした際は腕に負担のかかる動作は控え、無理のない範囲でリハビリを行いましょう。
腕に負担のかかる動作は控える
上腕二頭筋断裂を発症した後は、腕に負荷のかかる動作は控えることが大切です。腕に負荷がかかることで、症状悪化や回復が遅くなる可能性があります。
リハビリやトレーニングを行う際は、急な負荷は避けるようにしましょう。
無理のない範囲でリハビリを行う
| リハビリの段階 | 主な目的 | リハビリ内容 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 手術直後(行なっている場合)〜数週間 | 腱の保護と炎症の軽減 | ギプスやサポーターで固定し、過度な動きを避ける | 無理な動きはせず、医師の指示に従う |
| 数週間〜1カ月 | 関節の可動域を広げる | 軽いストレッチや他動運動で可動域を広げる | 腕に違和感を強く感じる場合は無理をせず、徐々に動かす |
| 1〜3カ月 | 筋力の回復を促す | ゴムバンドや軽いダンベルを使った筋力トレーニング | 急に負荷を増やさず、段階的に強度を上げる |
| 3カ月以降 | 通常の動作やスポーツ復帰 | 日常生活動作やスポーツ向けの実践的な運動を行う | 症状改善を焦らず、継続的にトレーニングを行う |
上腕二頭筋断裂の治療としてリハビリは有効です。リハビリを行う際は自己判断ではなく、医師の指導のもと、行うことが大切です。
リハビリは焦らず、炎症や違和感などを考慮して行います。いきなり腕を動かすのではなく、段階ごとに腕を慣らしていきます。
症状改善を焦ると、無意識のうちに腕に負担をかけてしまうことがあるため、焦らずリハビリに取り組みましょう。
スポーツや仕事への復帰は医師と相談する
上腕二頭筋を断裂した後、無理に復帰すると再断裂や回復が遅くなる恐れがあります。
上腕二頭筋断裂の症状や回復のスピードには個人差があり、医師は患者に合わせた復帰計画を立てて指導します。
自己判断で復帰や無理をしてしまうと、腱の再断裂だけでなく、肩関節周囲の他の組織を損傷する恐れがあるので、復帰時期は医師と相談しましょう。
またスポーツや仕事に復帰する際は、軽い運動から徐々に慣らしましょう。
食事に気をつける
| 栄養素 | 役割 | 推奨される食材 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 筋肉や腱の修復を促進する | 肉、魚、卵、大豆製品 (豆腐、納豆) |
| カルシウムとビタミンD | 骨の健康を維持し、腱の強化をサポートする | 乳製品(牛乳、チーズ)魚介類(鮭、いわし) |
| ビタミンC | コラーゲンの合成を助け、組織の修復を促進する | 果物(オレンジ、キウイ)野菜(パプリカ、ブロッコリー) |
| オメガ-3脂肪酸 | 炎症を抑え、回復をサポートする | 魚油(サバ、マグロ)ナッツ類(アーモンド、クルミ) |
上腕二頭筋断裂後は症状改善に向けて、食事にも気を付ける必要があります。
栄養素の摂取は大切ですが、極端に食事が偏らないよう注意しましょう。
上腕二頭筋断裂の疑いがある場合は早めの受診を
上腕二頭筋断裂の疑いがある場合は早めの受診が大切です。上腕二頭筋断裂は発見が遅れると回復が遅れ、重症化する恐れがあります。
また、上腕二頭筋断裂と診断された後も無理はせず、医師の診断のもとリハビリや復帰を行いましょう。
上腕二頭筋断裂が数カ月経過しても改善しない場合は、当院「リペアセルクリニック」にご相談ください。再生医療を活用し腱の構造的な修復だけでなく、機能的な回復も促します。
改善しない上腕二頭筋断裂でお悩みの方は「メール相談」もしくは「オンラインカウンセリング」にてお気軽にお問い合わせください。
\無料オンライン診断実施中!/
参考文献
Danielle Campagne, (2023)Biceps Tendon Tears,MSD MANUAL,Reviewed/Revised Jul 2023,
https://www.msdmanuals.com/home/injuries-and-poisoning/sprains-and-other-soft-tissue-injuries/biceps-tendon-tears(最終アクセス:2025年3月11日)
Danielle Campagne, et al. (2023),Biceps Tendon Tears,MSD MANUALProfessionalVersion,Reviewed/Revised Jul 2023
https://www.msdmanuals.com/professional/injuries-poisoning/sprains-and-other-soft-tissue-injuries/biceps-tendon-tears(Accessed:2025-03-11)
「プレドニン錠 5mg」『患者向医薬品ガイド』,pp.1-10, 2024年
https://www.info.pmda.go.jp/downfiles/guide/ph/343018_2456001F1310_4_00G.pdf(最終アクセス:2025年3月11日)
Carl R Freeman, et al.(2023),Nonoperative treatment of distal biceps tendon ruptures compared with a historical control group,PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19797566/(Accessed:2025-03-11)
Simon P Lalehzarian, et al.(2022),Management of proximal biceps tendon pathology,PubMed
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8771414/(Accessed:2025-03-11)
中川拓也ほか,「遠位上腕二頭筋腱断裂における術後早期理学療法後の長期経過─術後 3 年間の症例検討─」『JPTA』.pp1-1,
https://www.jstage.jst.go.jp/article/cjpt/2011/0/2011_Cb0503/_pdf/-char/ja(最終アクセス:2025年3月11日)