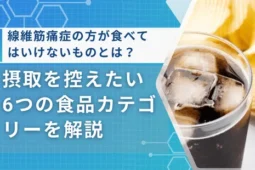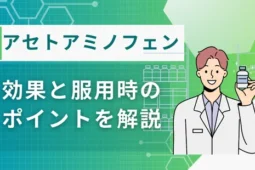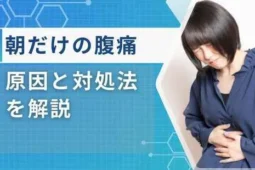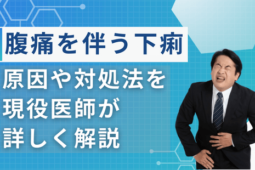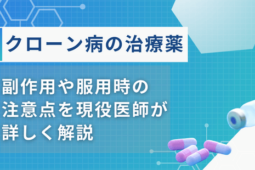- 内科疾患
- 内科疾患、その他
自己免疫疾患の原因にストレスは関係ある?知っておきたい発症メカニズムと対策を解説
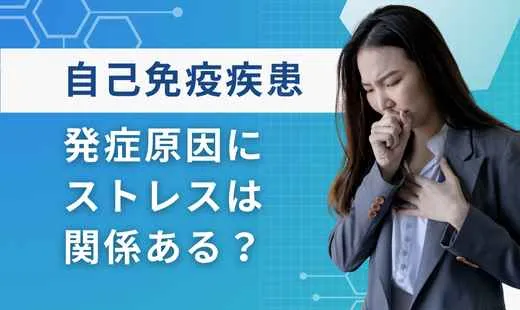
自己免疫疾患は、いまだにはっきりとした原因がわかっていない病気が多く、診断された方の多くが不安を抱えています。
「もしかしてストレスが原因?」「自分の生活に問題があったの?」と自分を責めてしまう人も少なくありません。
この記事では、自己免疫疾患の基本から原因に関する最新の考え方、そしてストレスとの関係についてわかりやすく解説します。
毎日の生活でできるストレスケアについても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
自己免疫疾患の基礎知識
自己免疫疾患とは、本来なら外敵から体を守るはずの免疫システムが、誤って自分自身の細胞や組織を「敵」と認識して攻撃してしまう病気です。つまり、私たちの体を守るべき免疫が、逆に自分自身に向かってしまう状態を指します。
免疫システムの誤作動によって、体内では慢性的な炎症反応が引き起こされ、さまざまな臓器や組織に障害が生じるようになります。症状や重症度は疾患によって大きく異なり、軽い体調不良から、日常生活に支障をきたす重症な状態、さらには命に関わるケースまで幅広く存在するのです。
発症の仕組みは完全には解明されていませんが、遺伝的要因、環境要因、ホルモンバランスの乱れなど、複数の要素が関与していると考えられています。
代表的な自己免疫疾患には、以下のような病気があります。
- バセドウ病
- 関節リウマチ
- 橋本甲状腺炎
- 1型糖尿病
- 全身性エリテマトーデス
- 血管炎
- アジソン病
- 多発性筋炎
- シェーグレン症候群
- 進行性の全身性強皮症
- 糸球体腎炎
これらの疾患は、現代の医療でも完全な治癒が難しい場合が多いものの、早期発見と適切な治療により、症状の進行を抑えたり、生活の質を維持したりすることが可能です。
近年では新しい治療薬も登場し、より多くの患者様が日常生活を大切にしながら治療を続けられるようになっています。疾患への理解を深め、早めの対応を心がけることで、日常生活を送れるようになるでしょう。
【関連記事】
自己免疫疾患とは?原因・症状・代表的な病気をわかりやすく解説
関節リウマチの初期症状は?チェックリスト付きで現役医師が解説
自己免疫疾患の原因はストレスだけじゃない!
自己免疫疾患の発症メカニズムは複雑で、単一の原因ではなく複数の要因が組み合わさって発症すると考えられています。ストレスも一因ですが、それだけではありません。以下の要因が考えられます。
遺伝的な要因
自己免疫疾患には遺伝的な素因が大きく関わっています。家族に自己免疫疾患の患者がいる場合、ほかの家族も同様の、あるいは別の自己免疫疾患を発症するリスクが高まることが研究で示されています。特定の遺伝子変異が免疫系の調節機能に影響を与え、自己免疫反応を起こしやすくする体質を作ると考えられるのです。
ただし、遺伝的要因があるからといって必ず発症するわけではありません。同じ遺伝子を持つ一卵性双生児でも、片方だけが発症するケースも多く見られます。つまり遺伝は「発症しやすさ」を決める要因の一つに過ぎず、他の環境要因との相互作用が重要です。
環境要因
環境要因は自己免疫疾患の発症や進行に大きく関係します。特定のウイルスや細菌感染が免疫系を刺激し、その後の免疫反応の誤作動につながるケースです。
EBウイルス感染後に多発性硬化症や全身性エリテマトーデス(SLE)のリスクが高まることや、紫外線を過度に浴びることは、全身性エリテマトーデス(SLE)などの悪化要因と言われています。
喫煙も多くの自己免疫疾患のリスク因子として知られており、可能なら禁煙することをおすすめします。
ホルモンバランスや性差
自己免疫疾患の多くは女性の発症率が圧倒的に高く、その背景にはホルモンバランスの影響が考えられています。エストロゲンなど女性ホルモンは免疫系の活性化に関わる一方、テストステロンなど男性ホルモンには免疫反応を抑制する効果があるとされています。
思春期、妊娠期、産後、更年期など、女性のライフステージにおけるホルモン変動期に発症や症状変化が見られることも特徴的です。妊娠中に症状が改善する疾患がある一方、産後に症状が悪化したり発症したりする疾患もあり、ホルモンの複雑な影響が示唆されています。
ストレスと自己免疫疾患の関係
自己免疫疾患とストレスには複雑な関連性があります。近年の研究では、ストレスが免疫機能に影響を与え、自己免疫疾患の発症や悪化に関係する可能性が示されています。ストレスと免疫機能の関係性を正しく理解しておきましょう。
ストレスが免疫システムに与える影響
ストレスを感じると、人の体では以下のような変化が起こります。
- 交感神経が活性化する
- アドレナリンやノルアドレナリンなどのストレスホルモンが分泌される
- コルチゾールの分泌が増え、免疫系に影響を与える
- 長期的なストレスで免疫システムのバランスが崩れる
- 慢性的な炎症が進行し、自己免疫反応のリスクが高まる
これらの変化は短期的には体を守りますが、長期間続くと問題が生じます。コルチゾールが長期間多い状態では、免疫機能を抑制する一方で炎症を促進し、このバランスの崩れが自己免疫反応を誘発しやすくします。
また、ストレスは睡眠や食生活にも悪影響を与え、間接的にも免疫機能を低下させます。心身の健康を保つためには、日常的なストレス対策が大切です。
ストレスが「引き金」になることもある
強い精神的ショックや、長く続くストレスの後に自己免疫疾患が現れることがあります。また、すでに病気がある人では症状が悪くなることもあります。
たとえば、関節リウマチや全身性エリテマトーデスなどの患者様の多くが、発症前に大きなライフイベントや精神的ストレスを経験していたことを挙げています。
これは、ストレスによって遺伝的素因が「表面化」するものと考えられるでしょう。自己免疫疾患の素因をもともと持っていたとしても、通常の生活では発症しない場合が多いのですが、強いストレスを受けたことで発症に至る可能性が高まるのです。
慢性的なストレスによって免疫の働きが乱れ、自分の体を攻撃する抗体が作られやすくなるため、病気が進行する原因になる可能性があると指摘されています。こうした背景からも、心身のストレスマネジメントは、自己免疫疾患の予防や症状コントロールにおいて非常に重要な要素といえるでしょう。
ストレスだけが原因ではない
ストレスは自己免疫疾患の発症や悪化において重要な要素の一つですが、それ単独で病気の原因になるわけではありません。
自己免疫疾患は典型的な「多因子疾患」とされ、遺伝的素因、環境因子、感染症、ホルモンバランスの変化など、さまざまな要因が複雑に絡み合って発症に至ります。ストレスはその中の一因にすぎず、必ずしも決定的な要素ではないのです。
患者様がこのことを理解するのは非常に重要です。「ストレスをためたから病気になった」と自分を責めるのではなく、複数の要因が重なった結果であると冷静に受け止めることが、前向きな治療への第一歩となります。
治療においても、ストレス管理は大切な柱ですが、それだけで完結するわけではありません。医学的な治療、適切な薬物療法、栄養バランスの取れた食事、十分な休養や運動など、生活全体を見直す総合的なアプローチが必要です。治療とセルフケアの両輪で症状のコントロールを目指していきましょう。
自己免疫疾患を防ぐストレスをためない方法
自己免疫疾患の予防や症状コントロールにおいて、ストレス管理は重要な要素の一つです。日常生活の中で無理なく続けられるストレス対策を取り入れ、心身のバランスを整えることが大切です。
自律神経や生活リズムを整える
日常生活でできるストレス対策として、以下の方法を取り入れてみましょう。
- 深呼吸や瞑想などのリラクゼーション法を実践する
- 趣味や好きなことに没頭する時間を確保する
- 規則正しい生活リズムを維持する
- 適度な運動を取り入れる
- バランスの取れた食事を心がける
- 質の良い睡眠をとる(就寝前のスマートフォン使用を控える)
自律神経のバランスを整えることは、ストレスに強い体づくりの基本です。朝起きた時や寝る前に5分間の深呼吸をするだけでも、リラックス効果が得られます。
また、音楽を聴く、読書をするなど、楽しい活動に集中する時間を意識的に作りましょう。趣味に没頭している時間は、ストレスホルモンの分泌が自然と抑えられます。
さらに、同じ時間に寝起きする習慣や適切な運動、バランスの良い食事も自律神経の安定につながります。特に質の良い睡眠は免疫機能の回復に欠かせません。
専門家との連携
自己免疫疾患を抱えている方のストレスケアは、自己流で行うよりも専門家のサポートを受けながら進めることが望ましいです。まずは主治医に現在のストレス状況や心配事を相談し、医学的見地からのアドバイスを受けましょう。
症状や状況によっては、心理カウンセラーや心療内科医など、メンタルヘルスの専門家のサポートを受けることも検討してください。認知行動療法などの心理療法は、ストレスへの対処法を学び、ネガティブな思考パターンを変えるのに効果的です。
自己免疫疾患の治療では、薬物療法による症状のコントロールと並行して、生活改善やメンタルケアをバランスよく取り入れることが大切です。患者会やオンラインコミュニティなどで同じ疾患を持つ人たちと交流するのも、精神的な支えになります。一人で抱え込まず、医療従事者や周囲の理解者と連携しながら、自分に合ったストレス管理法を見つけていきましょう。
自己免疫疾患とストレスの関係を正しく理解して、自分を守ろう
自己免疫疾患は、遺伝的要因、環境要因、ホルモンバランス、そしてストレスなど、さまざまな要素が複雑に影響し合って起こります。ストレスはその一部ですが、ストレスだけで発症するわけではありません。
大切なのは、「病気になったのは自分のせい」と自分を責めるのではなく、「自分の体と心を大切にする」という前向きな姿勢です。適切なストレス管理は症状の安定につながり、生活の質も向上します。自分のペースを尊重し、無理のない生活習慣を心がけましょう。
必要なときは周囲や専門家のサポートを求めることも大切です。小さな積み重ねが、自己免疫疾患とともに生きる上での大きな力になります。
なお、当院「リペアセルクリニック」では免疫細胞療法を提供しております。主にがん予防に関する内容ではございますが、免疫力に関して不安がある方は、以下のページもあわせてご覧ください。

再⽣医療で免疫⼒を⾼めることができる時代です。