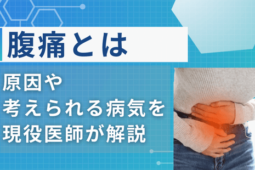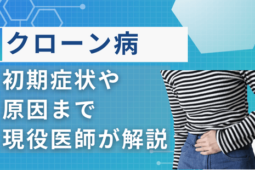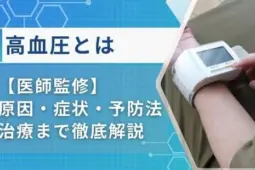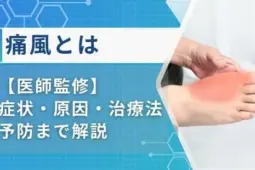- 内科疾患
- 内科疾患、その他
更年期の肩こりの原因と治し方|自宅ケア方法から治療法まで解説
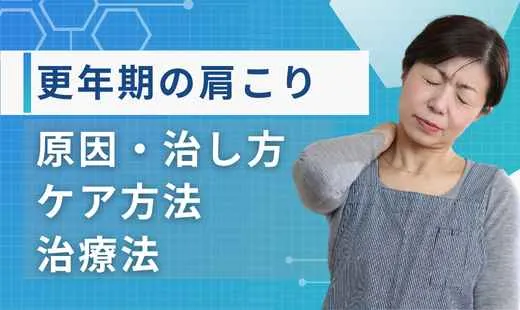
更年期に入ってから「肩こりがひどくなった」と感じる方は少なくありません。
これは主に、女性ホルモン「エストロゲン」の急激な減少によって自律神経が乱れ、筋肉の血流が悪化することが原因と考えられています。
さらに、姿勢の悪さや運動不足、ストレスなども症状を悪化させる一因です。
しかし、肩こりの根本的な原因を正しく理解し、自宅でのケアや医療機関での治療を適切に組み合わせれば、快適な日常を取り戻すことも可能です。
本記事では、更年期の肩こりが起こるメカニズムから自宅でできるケア方法、病院での治療法までわかりやすく解説します。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
ひどい肩こりの症状や再生医療について詳しく知りたい方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
更年期で肩こりがひどくなるのはなぜ?メカニズムを解説
更年期に肩こりが悪化するのは、女性ホルモン「エストロゲン」の急激な減少によって自律神経が乱れるのが主な原因です。
エストロゲンには自律神経を安定させる働きがありますが、更年期に入るとホルモンの分泌量が大きく減少します。
その結果、交感神経と副交感神経のバランスが崩れ、血管の収縮や筋肉の緊張が続きやすくなるのです。
とくに、肩や首まわりの筋肉が緊張すると血行不良が起こり、肩こりが慢性化する可能性があります。
また、加齢による筋力低下やストレスが蓄積すると、肩こりがさらに強まることも少なくありません。
更年期の肩こりは、ホルモンと神経系の変化が深く関わってひどくなるメカニズムである点を押さえておきましょう。
更年期の肩こりが起こる7つの原因
更年期に差しかかると、肩こりを訴える女性が増加します。
単なる疲労や年齢の影響だけでなく、ホルモンバランスの変化や生活習慣、自律神経の乱れなどさまざまな要因が複雑に絡み、肩こりになりやすい時期なのです。
ここでは、更年期に特有の肩こりの原因を7つに分類し、それぞれ詳しく解説します。
血流の悪化
更年期になると血流の巡りが悪くなり、肩の筋肉に十分な酸素や栄養が行き届かなくなります。
血行不良が老廃物の蓄積や筋肉の緊張を引き起こし、肩こりの症状を悪化させる原因となるのです。
さらに、冷えやすい体質も血流に悪影響を及ぼします。
血流不足が続くと肩や首の筋肉が硬直し、慢性化した痛みへと進行する恐れもあるため注意しなければなりません。
エストロゲンの減少
更年期に入って卵巣の機能が低下すると、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌が急激に減少します。
ホルモンは血管の拡張や筋肉の柔軟性の維持に深く関与しており、不足すると筋肉が硬くなりやすく、肩こりの原因となるのです。
また、骨密度や関節の状態にも影響し、身体の可動域が狭くなりやすい傾向があります。
肩こりがホルモンの変動が原因の場合、単なるマッサージでは改善しにくい点も懸念材料です。
自律神経の乱れ
更年期の肩こりは、自律神経の乱れも原因の一つです。
エストロゲンが減少して自律神経のバランスが崩れると、交感神経が過剰に優位になって血管の収縮や筋肉の緊張が起こります。
その結果、血流の悪化と相まって肩周辺の筋肉がこわばり、肩こりを引き起こしやすくなります。
また、不眠や倦怠感といった他の更年期症状と肩こりが互いに影響し合うこともあるため、体と心の両方からケアしていくことが大切です。
姿勢の悪さ
日常生活における姿勢の悪さも、更年期の肩こりを悪化させる要因となります。
たとえば、長時間のスマートフォンの使用やパソコン作業により、猫背や前傾姿勢が癖になっていると肩甲骨周辺の筋肉が常に引っ張られた状態になってしまうのです。
姿勢の悪い状態を続けると筋肉の緊張で血流が妨げられ、肩こりが慢性化します。
とくに、更年期は筋肉量の低下も重なって姿勢を支える力が弱まっているため、肩こりを感じやすくなる傾向がある点に留意しておきましょう。
ストレス
更年期は体調の変化に加え、仕事や家庭での役割の変化、将来への不安など精神的ストレスが増す時期です。
ストレスが蓄積すると交感神経が活性化し、筋肉が硬直しやすくなります。
さらに、ストレスによって不眠や疲労感が増幅されて筋肉の回復が妨げられると、肩こりが慢性化しやすくなるのです。
リラクゼーションや趣味の時間を確保し、ストレス緩和と肩こりの軽減につなげていく意識が大切です。
心のケアが、体の不調と深く結びついている点を認識しておきましょう。
運動不足
加齢とともに運動量が減ると、肩こりが起こりやすくなるため注意が必要です。
運動不足になると筋肉量の減少と柔軟性の低下が進み、血流も悪化します。
とくに肩周りの筋肉は使わないと硬くなりやすく、日常の動作だけでも疲労しやすくなるのです。
また、筋肉が弱ると正しい姿勢を維持できなくなり、肩こりを引き起こす要因になります。
定期的なストレッチや軽い運動を習慣化し、肩こり予防につなげていきましょう。
ひどい肩こりは病気の可能性も
慢性的に肩こりが続き、以下のような症状がある場合には他の疾患が関与している可能性があります。
- 痛みが強い
- 頭痛や吐き気を伴う
- 手のしびれがある
たとえば、頸椎症や椎間板ヘルニア、高血圧や内臓疾患などが肩こりの原因となるケースもあるため要注意です。
とくに、更年期は体調が変化しやすいため「更年期だから仕方ない」と自己判断せず、異常を感じたら早めに医療機関を受診しましょう。
更年期の肩こりを和らげる自宅ケア方法・治し方
更年期に入ると肩こりが慢性化し、日常生活に支障をきたすケースも少なくありません。
医療機関での治療も大切ですが、日常的なセルフケアによって症状を和らげることも十分可能です。
ここでは、自宅で簡単に取り組める更年期の肩こり対策を紹介します。
ツボ押し
肩こりに効くツボを刺激することで、血流を促進し筋肉の緊張を和らげる効果が期待できます。
正しい位置と押し方を確認した上で、毎日の習慣に取り入れてみましょう。
肩こり解消に適した主なツボには、以下のようなものがあります。
- 肩井(けんせい):首の根元と肩先との真ん中にあるツボ
- 天柱(てんちゅう):髪の毛の生え際付近で、首の太い骨の外側にあるツボ
(文献1)
指の腹でゆっくりと5秒間押すのを数回繰り返すことで、心地良い刺激となって肩まわりの筋肉がほぐれやすくなります。
ただし、強く押しすぎると逆効果になるため、心地良いと感じる程度の力加減がツボ押しのポイントです。
十分な睡眠
十分な睡眠は自律神経を整え、筋肉の回復を促すために不可欠です。
とくに、更年期にはホルモンの変化によって不眠や眠りの質が低下しやすいため、以下のような対策を心がけましょう。
- 就寝前1時間はスマートフォンを見ない
- 寝室を暗く静かに保つ
- 毎日同じ時間に寝起きする
睡眠中は筋肉が緩んで血流も改善されるため、質の高い睡眠は肩こりの軽減に直結します。
また、十分な睡眠は肩こりの軽減だけでなく、全身の健康維持にも重要です。
ぬるま湯で入浴
38〜40度程度のぬるめのお湯にゆっくりと浸かると、自律神経のバランスを整えやすくなります。
入浴によって体温が上がると血行が促進され、筋肉の緊張がほぐれやすくなるのです。
以下のポイントを意識して実践してみましょう。
- 15〜20分程度の半身浴
- 入浴剤を使用してリラックス効果をアップ
また、就寝前に入浴すると入眠しやすくなる効果もあるため、睡眠の質向上にもつながります。
患部を温める
肩こりの原因が肩まわりの血行不良である場合、外から温めると症状が改善するケースがあります。
温めることで局所の血行が促進され、筋肉の緊張を和らげる効果が期待できます。
とくに、冷房の効いた環境に長時間いると肩が冷えやすくなるため、温熱ケアは積極的に取り入れたい肩こり対策の一つです。
以下のような方法を試してみましょう。
- 蒸しタオルや温熱シートを使って肩を温める
- 冬場はカイロや温熱パッドを活用してしっかり温める
ただし、炎症を伴うような強い痛みや熱を持っている場合は、温めると逆効果になる点に留意しておきましょう。
ストレッチ
肩まわりの筋肉をやさしく動かすストレッチは、肩こりの予防と解消に効果が期待できます。
なかでも、肩甲骨周辺の筋肉をほぐすストレッチを試してみてください。
手順は以下の通りです。
1.両ひじを曲げて肩より上に上げ、手は軽く握って鎖骨のあたりに置いて腕がV字になるようにする
2.両ひじをゆっくりと後ろに引き、5秒かけて息を吐く。ひじの位置はできるだけ下げないように注意し、肩甲骨を背骨に向かって寄せる意識で強めに引き寄せる
3.肩甲骨を寄せたまま「ひじを下げてから脱力する」を5回繰り返す
(文献2)
起床時と就寝時に5回ずつ、上記の肩甲骨ストレッチを習慣にしてみましょう。デスクワークの合間などに行うのもおすすめです。
ただし、無理な動きは避け、心地よく感じる範囲でストレッチしてください。
入浴後など、身体が温まっている時間帯に行うと効果を高められます。
生活習慣の見直し
日常生活の中で、肩こりの原因となる習慣を見直す意識も大切です。
とくに、更年期に入ると日々の体調が変化しやすくなるため、規則正しい生活リズムを心がけましょう。
たとえば、以下のような点に注意してください。
- 長時間同じ姿勢を避け、1時間に一度は体を動かす
- スマートフォンやパソコンの画面を目線の高さに合わせる
- バランスの良い食事を心がける
また、カフェインやアルコールの摂取を控えると、自律神経を安定させる効果が期待できます。
これらの生活習慣の改善は、肩こりの軽減だけでなく全身の健康維持にもつながります。
更年期の肩こりの治療法
更年期の肩こりは、ホルモンバランスの変化や自律神経の乱れが主な原因であり、症状が長引く場合は医療機関での適切な治療が必要です。
ここでは、更年期の肩こりに対する代表的な治療法を2つ紹介します。
ホルモン補充療法(HRT)
ホルモン補充療法(HRT)は、更年期に減少するエストロゲンを補う治療法です。
エストロゲンの補充によって自律神経のバランスを整え、肩こりや腰痛の緩和を目指します。(文献3)
ただし、更年期障害の中でも重い症状に対して実施される治療法であり、副作用のリスクがある点に注意が必要です。
持病がある場合には、医師の診察と管理のもとで慎重に治療を行う必要があります。
漢方療法
漢方療法は、全身のバランスを整えることを目的とした治療法です。
多種多様な漢方の中から個々の体質や症状に合わせて処方され、肩こりや腰痛だけでなく疲れやすさや冷え、不眠といった更年期特有のさまざまな症状の軽減を目指します。
漢方は副作用が比較的少ないため、長期的な体調改善を目的とする方におすすめです。
また、西洋医学との併用も可能で、症状に合わせて柔軟な治療が行える点もメリットです。
更年期の肩こりだけでなく、腰痛にもお悩みの方は以下の記事もご覧ください。
まとめ|更年期に肩こりが悪化しやすい原因を理解して改善に取り組もう
更年期に肩こりが悪化しやすいのは、エストロゲンの急激な減少による自律神経の乱れや血流の悪化が主な要因です。
また、姿勢の悪さや運動不足、ストレスの蓄積なども複合的に影響しています。
肩こりの原因を正しく理解し、自宅でできるケアや生活習慣の見直しから無理なく始めてみてください。
改善が見られない場合は、ホルモン補充療法や漢方治療といった医療的なアプローチの検討も重要です。
早めの対策と継続的なケアで、更年期の肩こりを無理なく和らげていきましょう。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療に関する情報提供や簡易オンライン診断を行っております。
再生医療についての疑問や気になる症状があれば、公式LINEに登録してぜひ一度ご利用ください。
\無料オンライン診断実施中!/
参考文献
(文献1)
肩こりの解消法③ かんたんなツボ押し|大原薬品
(文献2)
肩こりにおすすめ!肩甲骨ストレッチ|沢井製薬