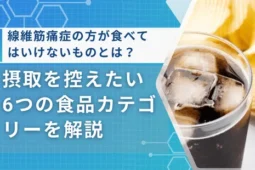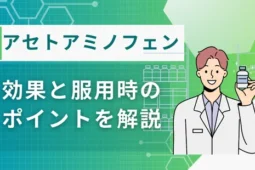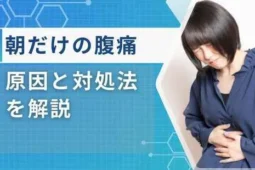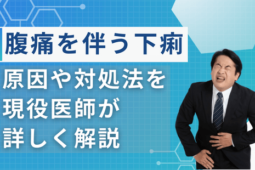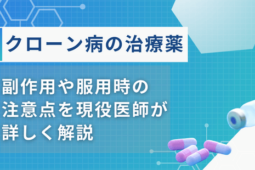- 内科疾患
- 内科疾患、その他
血友病とはどんな病気?主な症状や治療法、日常生活での注意点を解説

血友病は、生まれつき血液を固める力が弱い「先天性の出血性疾患」です。
放置すると、関節障害や日常生活への支障をきたす恐れもあります。
しかし、近年は治療法が進歩し、早期発見と適切な管理によって健常な人とほとんど変わらない生活を送ることが可能です。
本記事では、血友病の基礎知識から検査・治療法、日常生活での注意点をわかりやすく解説します。
正しい知識を身につけ、安心して向き合うための第一歩として参考にしてみてください。
なお、当院「リペアセルクリニック」では、公式LINEで情報提供と簡易オンライン診断を実施しています。
再生医療について知りたいことや不明な点があれば、ぜひご利用ください。
目次
血友病とは|出血が止まりにくくなる病気
血友病とは、血液の凝固因子が生まれつき不足または欠損しているため、出血した際に血が止まりにくくなる遺伝性の疾患です。
通常の止血機能が働かないため、軽い打撲やけがでも出血が長引く場合があります。
血友病には主に2つのタイプがあり、治療方針も異なる場合があるため、正確な診断が重要です。
血友病の種類と特徴は以下のとおりです。
- 血友病A:第VIII因子(抗血友病因子A)が欠乏しているタイプ。全体の約80%を占める。(文献1)
- 血友病B:第IX因子(抗血友病因子B)が不足しているタイプ。
血友病は先天性が大半を占めますが、まれに後天的に発症する「後天性血友病A」というタイプもあります。
自己免疫の異常により体内で凝固因子に対する抗体が作られ、血が固まらなくなるのが特徴です。
いずれにおいても、日常生活で注意が必要な疾患であり、早期の診断と適切な治療が出血のリスクを減らす鍵となります。
血友病の症状
血友病では血液が固まりにくいため、皮膚表面だけでなく体の深部でも出血が起こりやすくなります。
とくに、筋肉や関節内での出血が特徴的で、日常生活に支障をきたす場合もあるため注意が必要です。
以下に、血友病でよく見られる代表的な症状をまとめました。
| 症状の種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 筋肉内出血 | 腕や脚などの筋肉が腫れて痛む |
| 関節内出血 | 膝や肘などの関節に腫れ・熱感・痛みが出る |
| 皮下出血 | ぶつけていないのに青あざができる |
| 鼻出血・口腔内出血 | 鼻や口の中からの出血が止まりにくい |
| 手術・抜歯後の出血 | 通常よりも長時間にわたって出血が続く |
| 関節拘縮 | 出血により関節が固まり、動かしづらくなる |
また、以下のような症状が日常的に見られる場合も、血友病の可能性があるため、早めの医療機関を受診しましょう。
- 明らかな外傷がないのにあざができる
- 関節が腫れて痛み、動かしづらくなる
- 歯ぐきや鼻からの出血が長引く
- 以前より関節の可動域が狭くなってきた
症状が進行すると生活の質を大きく損なうため、早期発見と適切な管理が重要です。
血友病の検査・診断
血友病の診断では、まず血液がどれくらいの時間で固まるかを調べる「血液凝固検査」が行われます。
血が固まりにくい状態が確認された場合、さらに詳細な「凝固因子活性検査」に進み、第VIII因子または第IX因子の働きがどれほどあるかを評価し、病型と重症度を判定します。
凝固因子活性の値に応じた分類は以下の通りです。(文献2)
| 病型 | 凝固因子活性値 | 割合(目安) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 重症型 | 1%以下 | 約50~60% | 自発的出血が頻繁に起こる |
| 中等症型 | 1~5% | 約20% | 軽い打撲でも出血することがある |
| 軽症型 | 5%以上 | 約20% | 手術やけがの際に出血しやすい |
凝固因子の働きに基づいて重症度を把握することで、適切な治療方針を決定します。
とくに、重症型では無症候でも体内で出血している場合があるため、早期の診断が重要です。
血友病の治療法
血友病の治療では、不足している凝固因子を補充する「補充療法」が基本です。
重症度や出血頻度に応じて、以下の治療法を組み合わせて使い分けます。
- 定期補充療法
- 予備的補充療法
- 出血時補充療法(オンデマンド療法)
それぞれ詳しく見ていきましょう。
定期補充療法
定期補充療法は、出血が起きる前から定期的に凝固因子製剤を静脈投与する治療法です。
重症型の血友病患者様に対しての標準治療ですが、軽中等症でも予防を目的に投与するケースがあります。
製剤によって週2〜3回、または2週間に1回の注射を継続的に行うことで、関節内出血や筋肉内出血などの出血リスクを未然に防げます。
定期補充療法の最大の利点は、日常生活の質(QOL)の向上です。
出血に対する不安を軽減し、学校や職場での活動を安心して行えるようになり、とくに小児期からの早期導入が関節障害の予防につながるとされています。
予備的補充療法
予備的補充療法とはスポーツや旅行、歯科治療など、出血リスクが予測される特定の場面に限定して、事前に凝固因子製剤を投与する方法です。
重症型以外の患者様や、日常的に出血の頻度が少ない方に適しています。
必要なときだけ補充を行うため、治療の負担を軽減できるのがメリットです。
ただし、タイミングを逃すと出血を防げない可能性があるため、患者様自身や家族が状況を正確に判断しながら適切な対処が求められます。
出血時補充療法(オンデマンド療法)
出血時補充療法は、実際に出血が起きたときに凝固因子製剤を投与する方法です。
軽症型や中等症型の患者様を対象とし、出血頻度が少ない場合に選択される場合があります。
出血が確認された段階で速やかに製剤を使用することが重要で、出血の進行を最小限に抑え、症状の悪化を防ぐのが目的です。
ただし、関節や筋肉の深部出血は初期症状がわかりにくいため、早期対応が難しいという課題もあります。
血友病の方が日常生活を送る上での注意点
血友病のある方が安全に日常生活を送るためには、出血を防ぐ工夫と周囲の理解が大切です。
とくに、外傷や薬の使用、医療機関との連携など、あらかじめ注意しておくべき点を理解しておくと、万が一の際にも迅速に対応できるでしょう。
ここでは、日常生活のうえで押さえておきたい具体的なポイントを紹介します。
外傷・ケガの予防意識を持つ
血友病の方は出血が止まりにくいだけでなく、関節や筋肉内での深部出血が起きやすいため、日常生活でも以下のような予防を意識しましょう。
- 段差の多い場所や滑りやすい床では慎重に歩行する
- ひじやひざなどの関節を保護するプロテクターを活用する
- スポーツは出血リスクを考慮し、事前に医師と相談する
とくに、転倒しやすい場所では注意が必要です
予防する意識を持つように心がけて不要な出血のリスクを避け、安心して生活を送るための環境を整えましょう。
緊急時患者カードを携帯する
血友病の方は、外出時や災害・事故時に備えて「緊急時患者カード」の携帯が推奨されています。
緊急時患者カードは、血液凝固異常症の方がかかりつけ以外の医療機関を緊急で受診したり、救急車で搬送されたりした際に、医療関係者へ必要な情報を迅速かつ正確に伝えるためのカードです。
血友病の種類や使用している治療薬、投与量、かかりつけ医療機関などの情報が記載されています。
万が一の事故や意識障害などで本人が説明できない状況でも、周囲の医療関係者に正確な対応を促すことが可能です。
日常的に財布やスマートフォンケースに入れておくなど、常時携帯する習慣をつけましょう。
成人の場合は、各自治体から医療費助成の関連書類とともに、小児は患者会や製薬会社を通じて配布されています。
血友病の方でカードがまだ手元にない方は、「一般社団法人日本血液凝固異常症調査研究機構(JBDRO)」にお問い合わせください。
解熱剤・鎮痛剤の使用は避ける
血友病の方は、一般的な解熱剤や鎮痛剤の使用に注意が必要です。
とくに、アスピリンやインドメタシンなどの成分には血液を固まりにくくする作用があり、出血を助長する恐れがあります。
市販薬の中にも、これらの成分が含まれている可能性があるため、以下の点に注意しましょう。
- 解熱・鎮痛薬の購入時は、薬剤師に成分を確認する
- 医師の処方がない薬は使用しない
- 歯科や他科の受診時にも、血友病であることを必ず申告する
安全な薬物治療を行うためには自己判断を避け、医療従事者の指導のもとで薬を選びましょう。
口腔ケアを怠らない
口腔内は出血しやすい部位のひとつであり、血友病の方にとっては日々の口腔ケアがとても大切です。
虫歯や歯周病を予防すれば、歯ぐきからの出血を減らせます。
日常の歯磨きでは、以下の点に注意しましょう。
- 柔らかめの歯ブラシを使用し、歯ぐきを傷つけない
- 歯と歯ぐきの境目の汚れを丁寧に除去する
- 継続してケアを行う
定期的な歯科受診も欠かさずに、出血のリスクを最小限に抑えるよう心がけましょう。
なお、歯ぐきは適切にケアされていれば出血を抑えられますが、少量の出血が見られても問題ありません。
保育園や学校に出血が起きた際の対処法を共有する
小さい子どもの血友病患者様が安心して学校生活を送るには、保育園や学校側との情報共有が不可欠です。
以下のように、外傷や出血時の対応方法などを事前に伝えておくと、迅速かつ適切な対応が可能になります。
- 緊急時の連絡先と対応方法を文書で共有する
- 保管している凝固因子製剤の使い方を説明する
- 生活の中で注意すべき動作や活動を明確に伝える
子どもが血友病であっても、適切な治療と計画で多くの活動に参加できます。
以下のサイトのページでは、血友病の子どもを担当する先生向けに対応を説明しているので、情報共有時に参考にしてください。
まとめ|血友病は正しい知識と治療で管理できる病気
血友病は先天的に血液が固まりにくくなる疾患で、出血しやすい体質が特徴です。
完治は困難ですが、定期的な補充療法や生活上の注意によって、健常な人と変わらない生活を送れます。
早期診断と適切な治療の継続により、合併症の予防や生活の質の維持につなげていきましょう。
また、出血リスクへの理解に加え、周囲の協力や医療機関との連携も欠かせません。
なお、当院「リペアセルクリニック」では、公式LINEにて再生医療に関する情報提供と簡易オンライン診断を実施していますので、ぜひご登録ください。
\無料オンライン診断実施中!/
血友病に関してよくある質問
血友病は治りますか?
現時点で、血友病を根本的に治す治療法は確立されていません。
しかし、定期的な補充療法によって不足している凝固因子を補うことで、出血を予防し、健常な人とほとんど変わらない生活を送れます。
とくに、早期の治療開始が関節障害の予防や生活の質の維持に大きく貢献する点に留意しておきましょう。
血友病Aと血友病Bの違いはなんですか?
血友病は主に2つのタイプに分類されており、それぞれの違いは次の通りです。
- 血友病A:第VIII因子(抗血友病因子A)が欠乏しているタイプ
- 血友病B:第IX因子(抗血友病因子B)が不足しているタイプ
両者の出血症状や経過は似ていますが、治療に用いる凝固因子製剤が異なるため、正確な診断が重要です。
血友病は予防できますか?
現在のところ、血友病そのものを予防する方法は存在しません。
しかし、出血による合併症を防ぐことはできるため、以下のような早期対応が重要です。
- 出血が起きた際は、速やかに凝固因子製剤を補充する
- あざや関節痛などの初期症状を見逃さない
- とくに乳児期後半にみられる皮下出血に注意する
症状を発見した場合には、医療機関での早めの相談が重症化を防ぐための第一歩となります。
参考文献
(文献1)
Hemophilia ‒ Hematology and Oncology | Coagulation Disorders ‒ Merck Manual Professional Version|Merck Manual Professional Version