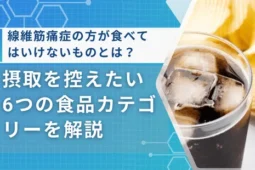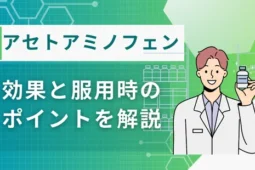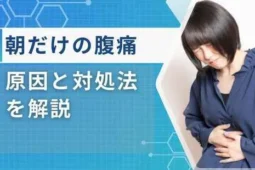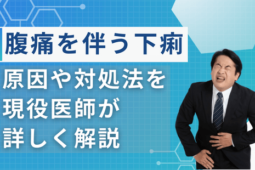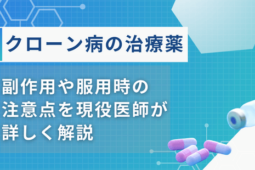- 内科疾患
- 内科疾患、その他
胃がん手術後の5つの後遺症と症状ごとの対処法をわかりやすく解説

胃がんは、日本で罹患数が多いがんのひとつです。
手術によって治療を行うケースも多いですが、術後はダンピング症候群や下痢、栄養障害、胆石症、骨粗鬆症などさまざまな後遺症が起こる可能性があります。
症状に応じて食事療法や栄養補助食品の使用、手術などが行われます。
また、近年では長く続く痛みや長期的ながん予防には再生医療といった新しい選択肢もあります。
この記事では、胃がんの症状や原因、診断や治療法の他、術後の後遺症の種類や後遺症に対する対処法、また、再生医療の可能性について詳しく解説していきます。
胃がんの手術をこれから受ける予定で術後について不安がある方、また術後後遺症でお悩みの方はぜひ参考にしてください。
胃がん手術後の後遺症に対しては、再生医療も治療選択肢の一つです。
胃がん手術後の後遺症のお悩みを今すぐ解消したい・再生医療に興味がある方は、当院「リペアセルクリニック」の電話相談までお問い合わせください。
目次
胃がん手術後の後遺症と対処法
胃がんの手術後には「胃切除後症候群」と呼ばれるさまざまな後遺症があらわれることがあります。
代表的な後遺症として、以下が挙げられます。
- ダンピング症候群
- 貧血
- 消化・吸収不良(体重減少)
- 骨粗鬆症
- 胆石症・胆嚢炎
これらの後遺症は症状の内容や程度によって対応方法が異なります。
たとえば、食事の摂り方を工夫したり、薬物療法や栄養補助食品を取り入れることで改善を目指すことが可能です。
なかには時間の経過とともに軽快するものもありますが、長引く症状は放置せずに医師へ相談することが大切です。
①ダンピング症候群
胃を切除すると食べ物を一時的にためる容量が減り、胃酸の分泌も少なくなります。
その結果、通常よりも濃い内容物が一気に腸内へ流れ込み、ダンピング症候群が起こります。
食後すぐに動悸・立ちくらみ・めまい・吐き気・発汗などが出るのを「早期ダンピング症候群」、食後2~3時間後に疲労感・失神・手の震えなどが出るのを「後期ダンピング症候群」と呼びます。
対処法
- 1時間以上かけてゆっくり食べる
- 1回の食事量を減らして1日5~6回に分けて食事する
- よく噛んでから飲み込む
- 食事中の水分摂取を減らす
②貧血
胃酸の分泌が減ることで胃からの鉄の吸収が妨げられ、胃の切除から数カ月で鉄欠乏性貧血を起こしやすくなります。
さらに数年経つと、胃の壁から分泌される内因子というビタミンB12の吸収を助ける糖たんぱく質が減り、ビタミンB12欠乏による貧血が生じることもあります。
対処法
- 鉄剤の内服
- ビタミンB12注射補充
③消化・吸収不良(体重減少)
胃酸や消化酵素の働きが低下し、さらに手術で迷走神経を切除すると消化管の動きも弱くなります。
その結果、栄養をうまく吸収できず体重が減少してしまいます。
対処法
- 一度に多く食べず、少しずつ時間をかけて食べる
- 医師や栄養士に相談しながら食事の調整を行う
- 少量で効率よく栄養が取れる補助食品を活用する
④骨粗鬆症(こつそしょうしょう)
胃を切除すると胃酸分泌の減少や腸内細菌の変化が起き、カルシウムの吸収が低下します。
その結果、骨がもろくなり骨粗鬆症のリスクが高まります。
対処法
- カルシウムやビタミンD製剤の服用
- 骨密度を上げる薬の使用
⑤胆石症・胆嚢炎
胃切除後は胆嚢の動きが弱まり、胆石ができやすくなります。
胃切除後の患者様の、2〜3割にみられます。
対処法
- 無症状の場合は経過観察
- 発作や胆嚢炎を起こした場合は治療が必要
- 根治的には胆嚢摘出術(場合によっては胃切除と同時に行うこともある)
胃がん手術後の生活と注意点|食事・仕事復帰・痛みのケア
胃がんの手術後は、後遺症だけでなく日常生活の工夫や体調管理が大切です。
食事の取り方や復職のタイミング、さらに長引く痛みやしびれへの対処について理解しておくことで、術後の生活をより快適に過ごすことができます。
ここでは、生活上のポイントを3つの観点から解説します。
食事の工夫(食べ方・避けたい食品・おすすめ食品)
手術後は胃の容量が減り、消化や吸収がスムーズにいかなくなります。
そのため、少量をゆっくり、回数を分けて食べることが基本です。
- 1日3食ではなく、5〜6回に分けて摂取する
- よく噛んでゆっくり食べる
- 食事中や直後の水分は控えめにする
避けたい食品には、高脂肪・刺激物・アルコールなどがあります。
一方で、消化に良い白身魚や豆腐、柔らかい野菜スープなどはおすすめです。
栄養士のアドバイスを受けながら、自分に合った食生活を整えると安心です。
日常生活と仕事復帰の目安
退院後すぐに無理をすると体力の回復が遅れてしまうため、段階的に日常生活に戻ることが大切です。
- 軽い散歩などから始めて体力を徐々に回復させる
- 車の運転や重い荷物の持ち運びは医師に相談してから
- 仕事復帰はデスクワークであれば数週間〜1カ月程度、肉体労働ではさらに時間がかかるケースが多い
個人差はありますが、医師の診断を受けながら無理のない復帰スケジュールを立てましょう。
痛みやしびれが長引く場合の対処
手術後に感じる痛みやしびれは、通常は時間とともに改善します。
しかし、3カ月以上続く場合は「遷延性術後痛」の可能性があります。
これは手術による神経障害や心理的要因などが関係しており、自己判断で我慢するのは危険です。
- 医療機関での適切な検査・治療を受ける
- 鎮痛薬や神経障害に対応した薬の使用
- 必要に応じてリハビリや心理的サポート
症状を早期に医師へ相談することで、回復を早めることができます。
\無料相談受付中/
胃がんとは【基礎知識】
胃がんは、胃の内壁を覆う粘膜の細胞が異常に増殖し、がん化することで発生します。
日本では比較的多くみられるがんの一つで、早期発見が治療の鍵となります。
胃がんの症状
胃がんは初期段階では自覚症状がほとんどないのが特徴です。
そのため、検診で偶然見つかるケースも多くあります。
初期無症状 進行すると
|
胃がんの原因
胃がんの発生にはいくつかの要因が関わっています。
代表的なものは次の通りです。
|
これらの要因が複合的に作用し、胃の粘膜にダメージを与えることで発症リスクが高まります。
胃がんの診断
診断には次のような検査を組み合わせて行います。
- 胃内視鏡検査(胃カメラ)
- 内視鏡で採取した組織の病理診断
- 血液検査
- CT検査
- 胃X線検査
これらを総合的に判断して確定診断がなされます。
胃がんの治療法
胃がんの治療には以下の方法があります。
- 内視鏡治療(早期がんに有効)
- 外科的手術(胃を部分的またはすべて切除)
- 化学療法(抗がん剤治療)
- 放射線療法
進行度(ステージ)に応じて適切な治療法が選ばれます。
とくに外科的手術では胃を一部またはすべて切除することが多く、その結果として「胃切除後症候群」と呼ばれる後遺症が発生する場合があります。
\無料相談受付中/
長く続く胃がん手術後の痛みと再生医療の可能性
胃がんの手術後、時間が経っても傷跡の痛みや周囲のしびれが続くことがあります。
これが3カ月以上続く場合、「遷延性術後痛」の可能性があり注意が必要です。(文献1)
遷延性術後痛の原因は複雑で、手術による神経障害だけでなく、精神的・心理的因子や遺伝的素因、生活環境などが絡み合って生じることがあります。検査をしても原因が特定できないケースも少なくありません。
手術の後遺症に対しては、再生医療という治療法があります。
当院では、再生医療の「自己脂肪由来幹細胞治療」と「PRP(多血小板血漿)療法」を行っています。
| 治療法 | 方法 | 特徴 | 所要時間・治療時間 |
|---|---|---|---|
| 自己脂肪由来幹細胞治療 | 脂肪から幹細胞を採取・培養し、点滴で投与する | 幹細胞が他の細胞に変化する「分化能」という能力を活用した治療法 |
入院・手術を必要とせず日帰りの施術が可能
|
| PRP(多血小板血漿)療法 | 血液を遠心分離して血小板を濃縮し、患部に投与 | 血小板の成長因子が持つ「炎症を抑える働き」を活用した治療法 | 入院・手術を必要とせず日帰りの施術が可能 ・採血・加工・投与(約30分~) |
長期にわたる痛みやしびれは、身体的なつらさだけでなく、気分の落ち込みやうつ状態を引き起こすこともあります。
症状が改善すると、活動範囲が広がり、精神的・社会的にも患者様の満足度が上がります。
▼実際に当院では、乳がん術後の化学療法で末梢神経が障害され、長い間足のしびれと原因不明の胃腸症状・倦怠感に悩まされていた患者様が、幹細胞治療によって改善した症例を経験しています。
また、再生医療のひとつであるNK(ナチュラルキラー)細胞免疫療法は、がんの予防に有効とされています。
自己の血液中にある免疫細胞の一種、NK細胞と呼ばれるものを血液から採取し、培養後に点滴でまた体内に戻す治療です。
当院「リペアセルクリニック」の免疫細胞療法については、以下をご覧ください。

再⽣医療で免疫⼒を⾼めることができる時代です。
まとめ|胃がん手術後の後遺症は生活習慣の工夫で改善できる
胃がんは初期に症状が出にくく、腹痛や嘔吐などの症状が出たときには手術が必要な状態になっていることも少なくありません。
手術後は胃切除後症候群と呼ばれる後遺症が生じることがあり、代表的なものにはダンピング症候群、消化・吸収不良、貧血、骨粗鬆症、胆石症などがあります。
これらの症状は、食事の摂り方を工夫したり、不足する栄養素を補ったりすることで改善を目指すことが可能です。
また、手術後に長く痛みやしびれが続く「遷延性術後痛」に悩まされる場合もあり、身体的・精神的なサポートが必要となります。
再生医療は、末梢神経障害を根本的に治療できる手立てとして注目されており、今後ますます普及していくことが予想されます。
胃がん手術後の後遺症は一人ひとり症状の現れ方が異なるため、気になる症状がある場合は早めに医師に相談し、生活習慣の工夫と適切な治療を組み合わせて改善を目指すことが大切です。
再生医療に興味がある方は、当院「リペアセルクリニック」の電話相談までお問い合わせください。
\無料相談受付中/
胃がんに関してよくある質問
胃がんは日本人に多いがんの一つであり、手術後の生活や再発の可能性など、患者様やご家族にとって気になる点は少なくありません。
ここでは、よく寄せられる質問をピックアップし、わかりやすく解説します。
胃がんの罹患者数や死亡率は他のがんと比べてどれくらい多いの?
2021年の部位別がん罹患数では、男性の胃がんは前立腺がん、大腸がん、肺がんに次いで4番目に多く、女性の胃がんは乳がん、大腸がん、肺がんに次いで4番目に位置しています。
また、2023年の部位別がん死亡数では、胃がんは肺がん、大腸がんに次いで3番目に多く、男女別でみると男性は3番目、女性は5番目という結果でした。(文献2)
胃がんは依然として日本における主要ながんの一つといえます。
若年者に多くて進行も早い胃がんの種類があるって本当?
胃がんは内視鏡やX線の所見から、以下のように分類されます。
|
この中で、びまん浸潤型(4型)にあたるスキルス性胃がんは、若年者や女性に多くみられるタイプです。
胃の壁が硬く厚くなり、進行が速く、腹膜転移が起こりやすい特徴があります。
そのため早期発見・早期治療が非常に重要です。