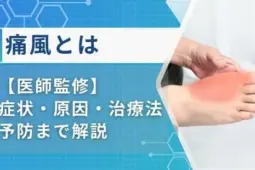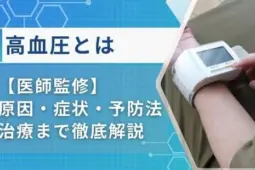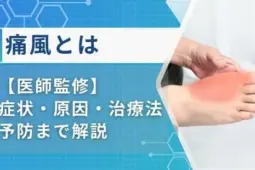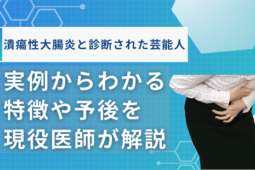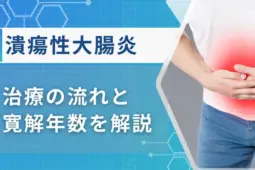- 内科疾患
- 内科疾患、その他
痛風の薬について専門医が解説|種類から副作用まで

「痛風の発作がつらくて仕事や日常生活に支障が出ている」「痛風の薬を飲んでいるけれど、副作用が心配」といったお悩みをお持ちではないでしょうか。
痛風は適切な治療を行わなければ、関節の損傷や日常生活の質の低下を招く恐れがあります。しかし、正しい薬の選択と使用法を理解し、生活習慣の改善を併せて行えば、症状の改善がより期待できます。
本記事では、痛風治療に用いられる代表的な薬剤の特徴と副作用対策、痛風予防のための生活習慣改善のポイントについて詳しく解説します。
なお、痛風は単独で発症することは少なく、糖尿病などの生活習慣病と相互に影響し合うことが知られています。そんな糖尿病に対しては再生医療という治療法もあります。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施していおります。ぜひ公式LINEにご登録ください。
痛風治療薬の種類と副作用
痛風の薬は、大きく分けて「痛風発作を抑える薬」と「尿酸値を下げる薬」の2種類があります。(文献1)
| 分類 |
目的 |
主な薬剤 |
|---|---|---|
| 痛風発作を抑える薬 | 急性の関節炎症状を抑える |
|
| 尿酸値を下げる薬 | 高尿酸血症を改善し、再発を予防する |
|
痛風発作を抑える薬(急性痛風関節炎の治療薬)
痛風発作を抑える薬として、NSAIDs、コルヒチン、ステロイド薬などが使われます。
これらは、痛風発作の予兆がある患者様や尿酸降下薬の開始初期の患者様に処方されることが多く、痛風発作の予兆(足の違和感など)がある時に服用すると、発作を予防・軽減できるとされています。
NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)
| 主な薬剤 | 特徴 | 主な副作用 |
|---|---|---|
|
|
|
NSAIDsは、痛みや発熱を伴う症状を抑える薬として広く使われており、一般的には「痛みどめ」として知られています。
痛風発作が起きてしまった患者様向けに処方されることが多く、激しい痛みや腫れを緩和する目的で処方されます。(文献2)
一方で、胃腸障害(胃粘膜病変や胃潰瘍の誘発・増悪)や腎障害を引き起こす可能性があるため注意が必要です。
また、ワーファリン(抗凝固薬)を服用中の患者様には、NSAIDsではなく、代わりにステロイド薬の処方が検討されます。
コルヒチン
| 薬剤名 | 特徴 | 主な副作用 |
|---|---|---|
|
|
|
コルヒチンは、痛風発作の予防と急性期治療の両方に用いられる薬剤です。
この薬は、炎症を引き起こす白血球の活動を抑制することで、発作を抑える効果が期待できます。
大量投与すると、吐き気や下痢などの消化器症状を引き起こす可能性があるため、少量から開始し、慎重に用量を調整する必要があります。
ステロイド薬
| 薬剤名 | 特徴 | 主な副作用 |
|---|---|---|
| ・プレドニゾロン | ・強力な抗炎症作用 ・NSAIDsやコルヒチンが使えない場合の選択肢 |
・糖尿病や感染症リスクに注意 |
ステロイド薬は、強力な抗炎症作用を持ち、重度の痛風発作に対して用いられる薬剤です。
NSAIDsやコルヒチンが使えない患者様に処方されることがあります。
しかし、長期使用によって、血糖値の上昇、感染症リスクの上昇、骨密度の低下を引き起こす可能性があります。
尿酸値を下げる薬(高尿酸血症の治療薬)
尿酸値を下げる薬は、体内での尿酸の生成を抑える「尿酸生成抑制薬」と、腎臓からの尿酸の排泄を促す「尿酸排泄促進薬」に分けられます。(文献3)
これらは、痛風発作の治療薬ではなく、体内に蓄積した尿酸を減らすことで、痛風発作の予防や腎障害の改善が期待されています。
尿酸降下薬の開始時期は、発作が落ち着いた後に検討するのが一般的です。開始時期は医師が総合的に判断します。
尿酸生成抑制薬
| 主な薬剤 | 特徴 | 主な副作用 |
|---|---|---|
|
体内での尿酸の生成を抑える |
|
尿酸生成抑制薬とは、体内で尿酸をつくるキサンチンオキシダーゼという酵素の働きを弱め、尿酸の産生を減らす薬です。
薬の選定は、副作用や合併症の有無などを考慮し、主治医が一人ひとりの状況に応じて選びます。
アロプリノール
| 薬剤名 | 特徴 | 主な副作用 |
|---|---|---|
|
|
|
アロプリノールは、体内のプリン体(DNAやRNAの材料になる物質)に似た構造を持っている薬です。
世界的に長年使用されていますが、腎機能に関連した副作用が確認されており、腎機能が低下している場合は用量を調整する必要があります。
また、免疫抑制薬であるメルカプトプリンやアザチオプリンとの併用には、減量のうえ慎重に使用する必要があります。
フェブキソスタット
| 薬剤名 | 特徴 | 主な副作用 |
|---|---|---|
|
|
|
フェブキソスタットは、プリン体の形をしていない「非プリン型」の薬で、1日1回の服用が可能です。
アロプリノールで十分な効果が得られない場合や、副作用などでアロプリノールが使えない場合に処方されます。
また、免疫抑制薬であるメルカプトプリンやアザチオプリンとの併用は禁止されています。
尿酸排泄促進薬
| 主な薬剤 | 特徴 | 主な副作用 |
|---|---|---|
|
|
|
尿酸排泄促進薬とは、腎臓で尿酸が血液に戻るのを防ぎ、尿で排出を促す薬です。尿酸を排出し、血清尿酸値を下げます。
とくに、尿酸を作りすぎているわけではなく、腎臓からの排泄が不十分な「尿酸排泄低下型」の患者様に処方されます。
ただし、尿酸を体の外に出す働きが強まると、尿路結石ができやすくなる可能性があるため、薬を飲んでいる間は十分な水分を摂り、尿量を増やすことが大切です。
必要に応じて、尿をアルカリ性に保つ薬を併用することもあります。
ベンズブロマロン
| 薬剤名 | 特徴 | 主な副作用 |
|---|---|---|
|
尿酸の再吸収を強く抑え、尿中への排泄を増やす |
|
ベンズブロマロンは、尿酸排泄促進作用は強力で、効果が比較的長く続くと報告されており、プロベネシドに代わり、広く使用されています。
とくに飲み始めの6か月は肝障害に注意が必要なため、服用初期は定期的な検査が必要です。
また、ワーファリン(抗凝固薬)など一部の薬の効き方に影響することがあるため、服用中の薬がある場合は、必ず医師・薬剤師に伝えてください。
プロベネシド
| 薬剤名 | 特徴 |
主な副作用 |
|---|---|---|
| プロベネシド |
尿酸の再吸収を抑制して排泄を促す (作用はベンズブロマロンより弱め) |
・ペニシリン系抗菌薬、メトトレキサートなどの血中濃度を上げることがある |
プロベネシドは、腎臓で尿酸が再吸収されるのを抑えることを主な作用としています。その結果、血液中の尿酸が体に蓄積しにくくなり、尿酸値の低下につながります。
また、ペニシリン系抗菌薬やメトトレキサートなど、一部の薬剤の血中濃度を上昇させる可能性があるため、併用時には注意が必要です。
一般的に用法は人によって異なります。実際の用量・回数は医師が処方するため、服用中の薬がある場合は必ず医師・薬剤師に伝えてください。
痛風の原因・症状について知りたい方は、こちらの記事も併せてお読みください。
\無料相談受付中/
痛風治療の市販薬と処方薬の違い
痛風の治療薬には、医療機関で処方されるものと、薬局で購入できる市販薬があります。市販薬は治療ではなく、症状を一時的に和らげる目的で使用される薬です。
痛風発作時の激しい痛みに対しては、市販のロキソニンなどのNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)が痛みを和らげる効果があります。
発作が続く場合は、根本原因に着目した治療が必要になります。また、市販薬を使用する際は、用法・用量を守り、適切に使用することが重要です。
過剰摂取や長期連用は副作用のリスクを高める可能性があります。市販薬を使用する前には、医師や薬剤師に相談しましょう。
痛風予防と生活習慣 – 再発防止のためにできること
薬物療法と並行して、生活習慣の改善に取り組むことが痛風の再発予防につながります。とくに食事の工夫と適度な運動習慣が重要です。
食事と生活習慣の改善
痛風の予防には、プリン体の摂取を控えてバランスの良い食事をとることが大切です。
以下のプリン体を多く含む食品は、尿酸値上昇の原因となるため、なるべく控えましょう。
| 食品カテゴリ | 主な食品 |
|---|---|
| 内臓類 | レバー(鶏・豚・牛)、あん肝、腎臓、脳など |
| 魚類 | イワシ、サンマ、カツオなどの青魚 |
| 野菜類 | マッシュルーム、ほうれん草、アスパラガスなど |
| アルコール類 | ビール、ワイン、日本酒などアルコール飲料 |
ただし、何も食べずにいると、体内脂肪の分解と尿酸排泄が滞ることで、尿酸値が上昇するケースもあります。プリン体を多く含む食品を避けながら、栄養バランスの良い食事を心がけましょう。
また、尿酸値を下げることが期待されている「低脂肪乳製品」や「無糖コーヒー」を取り入れるのもおすすめです。
【関連記事】
痛風の食事療法とは?食べてはいけないもの一覧やストレスをためない食生活改善のポイント
痛風にコーヒーはダメ?OK?尿酸値への影響と安全な飲み方を医師が解説
\無料オンライン診断実施中!/
痛風を防ぐための日常のポイント
適度な運動習慣と水分補給は、尿酸値を下げる効果が期待されています。
目安は以下の通りです。
|
項目 |
期待できる効果 | 内容 | 目安 |
|---|---|---|---|
| 有酸素運動 | 尿酸値を下げる可能性がある |
|
週3〜5回 30分〜1時間程度 |
| 水分補給 | 尿酸を多く排出しやすくなる |
|
1日に2リットル以上 ※個人差あり、医師との相談が必要 |
痛風予防のための生活習慣の改善は、薬物療法と並行して行うことで、再発防止につながります。
無理のない範囲で、生活習慣の見直しを行っていくことが大切です。
まとめ|痛風の薬・症状への理解を深めて適切な治療を選択しよう
痛風治療には「痛風発作を抑える薬」と「尿酸値を下げる薬」の2つがあり、それぞれ異なる目的で使用されます。
NSAIDsやコルヒチンは急性発作の痛みを和らげ、尿酸生成抑制薬や尿酸排泄促進薬は根本的な原因である高尿酸血症を改善します。
市販薬は一時的な症状緩和に留まるため、継続的な発作がある場合は医療機関での適切な診断と治療が必要です。
また、薬物療法と併せてプリン体を控えた食事、適度な運動、十分な水分補給など生活習慣の見直しを行うことで、痛風の再発予防と症状の改善が期待できます。
痛風は適切な治療と生活習慣の見直しによって十分にコントロール可能な疾患です。まずは医師に相談して治療計画を立て、健康的な日常生活を取り戻しましょう。
痛風の薬に関するよくある質問
痛風発作が治まったら、薬をやめてもいい?
自己判断でやめてはいけません。
痛風発作が治まっても、体内の尿酸結晶が溶けていない状態は続いています。
尿酸値を下げる薬を中断すると、再び尿酸値が上がりやすくなり、痛風発作の再発リスクが高まります。
薬を飲んでいれば、好きなものを飲食できる?
薬を飲んでいても、食事内容には注意しましょう。症状の改善には、プリン体が多く含まれる食事を避けて、栄養バランスの良い食事を摂ることが重要です。
痛風治療の基盤は、生活習慣(食事・飲酒・運動・体重管理)の見直しです。
好きなものを自由に摂る生活を続けた場合、薬の効果が不十分となり、薬剤量の増加や別の治療が必要になる可能性があります。
\無料オンライン診断実施中!/
尿酸値を下げる薬を飲み始めたら、逆に痛風発作が起きた。なぜ?
尿酸値が長く高かった方が治療を始めると、尿酸が急に下がります。その結果、関節にたまっていた尿酸の結晶が刺激されやすくなり、白血球が反応して一時的に痛みや腫れ(痛風発作)が起こることがあります。(文献4)
発作が起きても薬は中断せず、医師に相談してください。
健康食品やサプリメントで尿酸値は下がりますか?
治療の基本はあくまで「医師から処方される医薬品」と「生活習慣の改善」です。
サプリや健康食品は補助として検討する位置づけなので、利用する場合は、必ず事前に医師や薬剤師に相談してください。
痛風発作時にすぐにすべきことはある?
痛風発作が疑われる場合、まずは安静にして患部を動かさないようにしましょう。
冷却パックなどを用いて患部を冷やすことで、炎症と痛みを和らげることができる可能性があります。
また、発作時には水分を十分に摂取することが重要です。
水分をとることで尿量が増え、尿酸が体外に出やすくなることが期待されます。
参考文献
高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン 第3版|日本内科学会雑誌第109巻第8号
高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン(ダイジェスト版)|公益財団法人 痛風・尿酸財団
痛風・高尿酸血症治療のフローチャート|一般社団法人 日本動脈硬化学会
2016 updated EULAR evidence-based recommendations for the management of gout|BMJ Jornals