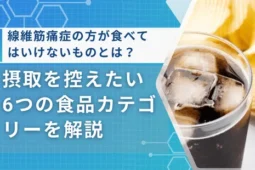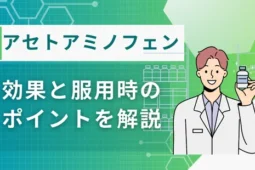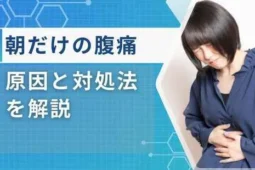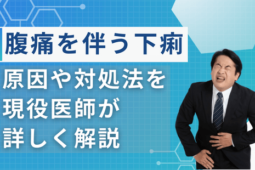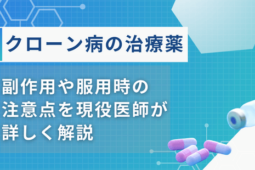- 内科疾患
- 内科疾患、その他
肺がん手術後に起こる後遺症・合併症とは?|肺がんの原因から治療法まで解説

肺がんは、日本で多く診断されるがんのひとつで、2021年の罹患数は約124,500人に上ります。
死亡数については、2023年には約75,762人と報告されており、がんによる死因の中で男女を合わせて最も多い疾患のひとつです。(文献1)
本記事では、肺がんの基礎知識から治療法までを解説した上で、手術後に起こりやすい合併症や後遺症について紹介します。
さらに、それらに対する治療や対処法、再生医療の可能性についても触れています。
手術前後の不安を抱えている方や、術後の生活に関心のある方にとって参考となる内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。
なお、肺がん手術後の後遺症に対しては、再生医療も治療選択肢の一つです。
肺がん手術後の後遺症のお悩みを今すぐ解消したい・再生医療に興味がある方は、当院「リペアセルクリニック」の電話相談までお問い合わせください。
目次
肺がん手術後の後遺症と対処法
本章では、肺がんの手術後に後遺症として残ってしまう可能性のある症状や状態について、その対処法も含めて紹介します。
呼吸のしにくさ、息苦しさ
肺がん手術後は、肺を切除したことにより肺活量が低下し、うまく呼吸できなくなったり、労作時の息切れ、息苦しさが残る可能性があります。
<対処法>
呼吸リハビリテーションを行って改善を促すなどの方法があります。
理学療法士の指導のもと、呼吸筋を鍛えるリハビリを行います。
声のかすれ、飲み込みにくさ
肺がん手術で、反回神経と呼ばれる声帯を動かす神経が影響を受けた場合に生じる可能性のある症状です。
反回神経の障害によって声帯が動かしにくくなり、声のかすれや飲み込みにくさが生じます。
まれに数カ月以上たっても症状が改善しない場合があります。
<対処法>
声のかすれが重度の場合や飲み込みにくさが強い場合には、麻痺した声帯を移動させる等、手術による治療法があります。
術後の咳や痰が続く
肺がん手術後は、肺を切除した影響や気道が刺激を受けることで、咳や痰が長く続くことがあります。
とくに痰がうまく排出できないと、肺炎などのリスクを高めるため注意が必要です。
<対処法>
咳や痰が強い場合には、吸入薬や去痰薬を用いることで症状を和らげられます。
また、水分をしっかりと摂ることも効果的です。
さらに、呼吸リハビリを取り入れることで、痰を効率よく排出する方法を学ぶことができます。
胸や背中の痛み・しびれが長引く
手術で肋骨や神経に負担がかかることで、術後に胸や背中の痛み、あるいはしびれが長期間残ることがあります。
これは「術後慢性痛」と呼ばれ、数カ月から数年にわたって続く場合もあります。
<対処法>
鎮痛薬で痛みを和らげるほか、神経ブロック注射が選択される場合もあります。
痛みによって体を動かさなくなるとさらに回復が遅れるため、無理のない範囲で体を動かし続けることが推奨されます。
体力低下・疲れやすさ
肺を切除した影響で酸素を取り込む力が弱まり、以前より疲れやすくなることがあります。
また、手術や抗がん剤治療によって筋力が落ち、体力の回復が遅れるケースも少なくありません。
<対処法>
ウォーキングなど軽い有酸素運動を取り入れたり、理学療法士の指導を受けて筋力トレーニングを行うことが効果的です。
さらに、栄養バランスのとれた食事を心がけることで体力の回復をサポートできます。
肺がん手術後の合併症とその対処法
肺がん手術後の合併症は、手術の方法や、患者様自身の体質などによっても異なります。
ここでは、一般的に想定される主な術後合併症とその対処法について挙げていきます。
肺胞瘻(はいほうろう|肺から空気が漏れる状態)
肺を切除したところから空気が漏れる合併症です。
肺がんの手術の中では約5%と比較的頻度が高い合併症です。
通常であれば手術により肺の一部が取り除かれるため、呼吸機能が低下することがあります。
<対処法>
多くの場合自然に改善しますが、まれに治らないケースがあります。
その場合には薬剤を用いて空気の漏れを止める胸膜癒着術や、再手術が必要になることがあります。
気管支断端瘻(きかんしだんたんろう|気管支の縫合部分から空気が漏れる)
一般的な肺がんの手術では、肺と気管支の一部も切除します。
その気管支を切ったところから空気が漏れてしまう合併症です。
<対処法>
起こりうる可能性は極めてまれですが、起こってしまった場合には重篤になるため、緊急手術によって閉鎖したりする必要があります。
術後肺炎(手術後に肺が炎症を起こす)
手術後に肺炎が生じ、咳、発熱、呼吸困難などがみられることがあります。
<対処法>
抗生剤を投与して治療を行います。
膿胸(のうきょう|胸に膿がたまる)
手術した側の肺の胸腔内に膿がたまる合併症です。
膿による発熱や、感染が全身にまわると敗血症をきたす恐れもあります。
<対処法>
膿が少量であれば、胸に小さな穴を開けてそこから洗浄して膿を排除します。
小さな穴からの洗浄で不十分な場合には、手術による洗浄が必要です。
いずれの場合でも抗生剤を併用して治療する必要があります。
乳び胸(にゅうびきょう|胸にリンパ液が漏れる)
手術の際に、胸管とよばれる太いリンパ管が傷つき、胸腔内にリンパ液が漏れてしまう合併症です。
<対処法>
症状が軽度であれば、脂肪分を制限した食事にすることでリンパ液の漏出を抑え、改善する可能性があります。
ただし、場合によっては再手術で漏れを塞ぐこともあります。
肺動脈血栓塞栓症(足の血栓が肺に詰まる)
手術中や手術後など、ベッドに長期間横になって下肢を動かさない状態になると、足の静脈がうっ滞して血栓が作られます。
その血栓が、立ったり歩き始めた際に肺の血管に移動して詰まることで起こる合併症で、いわゆるエコノミークラス症候群として知られています。
発生頻度は高くないものの、生じた場合には重篤で死亡する危険性もある合併症です。
<対処法>
血栓が作られるのを予防することが大切で、手術中や術後歩けるようになるまでストッキングを装着したり、下肢のマッサージを行うフットポンプを着用します。
また、血栓が生じてしまい、肺に詰まってしまうリスクが高い場合には、血液をサラサラにする抗凝固薬を投与して治療します。
反回神経麻痺(声のかすれ・飲み込みにくさにつながる神経障害)
肺の近くを走行している反回神経を手術中に傷めてしまうと、反回神経麻痺を起こす可能性があります。
この神経の障害によって、声のかすれ(嗄声)や飲み込みにくさが出る場合があります。
<対処法>
反回神経麻痺は一時的な症状であることが多く、通常数カ月程度で改善しますが、まれに回復しないケースもあります。
肺がん手術後に後遺症が残ってしまったら|再生医療について
肺がん手術後に後遺症が長く続く場合、治療の選択肢のひとつとして「再生医療」があります。
再生医療では、患者様ご自身の脂肪から採取した細胞を培養し、点滴で体内に戻す「幹細胞治療」という方法があります。
幹細胞が他の細胞へ変化する「分化能」能力を活用する治療法です。
当院「リペアセルクリニック」は再生医療を提供できる施設の1つです。
患者様自身の脂肪から幹細胞を採取・培養し、点滴する「自己脂肪由来幹細胞治療」を行っています。
自分自身の細胞を用いるため、拒絶反応やアレルギーが生じにくい方法です。
手術後の後遺症でお悩みの方は、当院「リペアセルクリニック」の電話相談までお問い合わせください。
\無料相談受付中/
肺がんの原因
肺がんの主な原因は喫煙で、発症の約7割を占めると言われています。
タバコを吸わない人に比べ、喫煙者の発症リスクは4倍以上に高まり、副流煙でも危険性は増します。
そのほか、大気汚染やアスベストの吸入、遺伝的要因なども肺がんのリスク因子です。
肺がんの症状
肺がんの初期は多くの場合無症状であり、早期に発見するのは困難です。
進行に応じて咳や痰、息切れなどがみられることがあります。
肺がんに特徴的とまではいえない症状がほとんどですが、痰に血が混じる(血痰)場合には肺がんが疑わしい可能性が高まるため、早めに医療機関を受診しましょう。
それ以外にも極端な体重低下や肩の痛み、しゃっくりなど、がんの進行によってさまざまな症状を引き起こします。
また、肺がんが転移した場所の症状が出ることがあり、脳転移による頭痛、手足の麻痺、めまい、吐き気、骨転移による痛みなどがあります。
肺がんの検査と診断
肺がんの検査は、肺がんを見つけるための検査、肺がんであることを確定する、肺がんの種類を調べる検査、治療方針を決めるために必要な検査など様々です。
肺がんを見つけるための検査
肺がんを見つけるための検査としては、画像検査が一般的です。
胸部レントゲン検査や胸部CT検査が挙げられます。
レントゲン検査は、健診や人間ドックなどでも幅広く使用されている基本的な検査です。
CTではレントゲンよりも画像で得られる情報量が豊富で、より小さな病変も見つけることが可能となります。
一方レントゲンよりも放射線被ばく量が多くなることがデメリットです。
その他、肺がんの転移を調べるのに有用なMRI検査、シンチグラフィー、PET検査などがあります。
また、血液検査の中で腫瘍マーカーと呼ばれるものがあり、この腫瘍マーカーを調べて数値が異常値を示す場合には肺がんを疑います。
ただし、このマーカーは他のがんや病気でも上昇することがあるため、この検査のみで肺がんを診断することはできません。
あくまで他の検査と合わせて総合的に判断するための材料です。
肺がんを確定する診断と治療法の検討のための検査
肺がんであることを確定させるには、がん細胞がいることを確認する必要があります。
そのためには、痰に混じったがん細胞を見つける方法(喀痰細胞診検査)や、病変を内視鏡やCTなどで確認して、組織に直接針を刺して細胞を採取して確認する方法(組織診検査)があります。
この組織を詳しく調べることで、がん細胞の存在の有無だけでなく、どういった種類の肺がんかを見分けることが可能です。
また、がんの種類によっては遺伝子検査を追加で行い、そのがんの遺伝子変異について詳しく調べることがあります。
これは、ある特定の遺伝子変異が見つかった場合、その変異に特異的に効く分子標的薬と呼ばれる治療薬を使うことで、治療効果が期待できるためです。
肺がんの治療法
肺がんの治療は大きく「手術」「化学療法」「放射線療法」の3つです。
がんの種類や進行度に応じて組み合わせて行います。
肺がんの組織型による違い
肺がんは大きく「小細胞肺がん」と「非小細胞肺がん」に分けられ、それぞれ進行のスピードや治療の方針が異なります。
小細胞肺がん(SCLC)
小細胞肺がんは進行が非常に早く、発見された際にはすでに転移してしまっているケースが多いため、化学療法や放射線療法を組み合わせて治療を行います。
非小細胞肺がん(NSCLC)
非小細胞肺がんは、小細胞肺がんに比べると進行速度は比較的ゆるやかで、早期に見つかれば手術の適応となる場合があります。
肺がんの病期と治療法について
肺がんの病期(ステージ)は、以下のように分類されます。
|
非小細胞肺がんの場合、病期によって治療法が異なります。
ⅠA期では、手術のみを行います。
ⅠBからⅢB期までは手術を行い術後に化学療法を行うのが一般的です。
ⅢA、ⅢB期で手術が不可能な場合には、放射線治療と化学療法を併用した治療法を検討します。
Ⅳ期の場合では、まず遺伝子検査によって特定の遺伝子変異の有無を確認し、有効な分子標的薬があればそれによる薬物療法を検討します。
有効な遺伝子変異がない場合には、抗がん剤を用いた化学療法を選択します。
ただし、これはあくまでも基本的な方針のため、一律にこのように決まるとは限りません。
実際には患者様ごとの状態や事情なども考慮して治療を決定していきます。
肺がんの3つの手術方法
肺がんの手術方法は、切除範囲とがんの進行度や位置、患者様自身の状態などによって異なってきます。
| 手術方法 | 説明 | 特徴・注意点 |
| 肺葉切除術 | 肺がん手術の標準的な方法。右肺3葉、左肺2葉のうち、がんのある肺葉を切除。 多くの場合、近くのリンパ節も同時に切除される。 |
最も一般的な術式。 肋骨の間から胸部を切開し、がんを含む肺の葉を取り除く。 |
|
区域切除術・楔状切除術 |
肺の一部分だけを切除する方法。 区域切除術は肺葉より小さい単位の切除、楔状切除術はさらに小さな部分を切除。 |
早期で小型のがんが対象。 胸腔鏡を用いることで小さな切開で済み、身体への負担が軽い。 再発リスクは考慮が必要。 |
| 肺全摘術 | 片側の肺をすべて切除する大きな手術。 がんが一側の肺全体や中心部に広がっている場合に選択される。 |
心肺機能への影響が大きく、体力や呼吸機能が低下している人には適応が難しい。 |
まとめ|肺がん手術後の後遺症を最小限にするための治療と生活習慣
肺がんは喫煙などを主な原因とし、早期発見が難しい病気です。
手術によって命を救える一方で、呼吸のしにくさや声のかすれといった後遺症、肺炎や血栓などの合併症が生じることがあります。
こうした症状はリハビリや生活習慣の工夫によって改善が期待でき、再生医療のような新しい治療法も注目されています。
肺がん手術後の後遺症でお悩みの方は、再生医療を行っている当院「リペアセルクリニック」へお気軽にご相談ください。
肺がん・肺がん手術後の後遺症についてよくある質問
新型タバコ(電子・加熱式)は肺がんの原因になりますか?
新型タバコは紙巻タバコに比べて害が少ないと思われがちです。
しかし実際は、含まれるニコチンの量は紙巻タバコと同等もしくはそれ以上であることもあり、タールも7割程度と言われています。
さらに、それ以外にも約70種類の発がん物質が含まれていると言われており、新型タバコも同様に肺がんのリスクとなります。
肺がんを予防する方法はありますか?
肺がんを完全に予防できる方法は現時点でありませんが、肺がんになるリスクを減らすことはできます。
まず、肺がんの最も多い原因である喫煙をしている場合には禁煙をしてください。
また、受動喫煙によっても肺がんのリスクが上がるため、タバコの煙を避けるのも大切です。
最も重要なのは肺がんの早期発見です。
予防できることは限られますが、定期的に健康診断などで胸部のレントゲン検査など、画像検査を受けるようにしてください。
肺がんが見つかったとしても大きくなる前に早期発見できれば、完治の可能性が高まります。
手術後の息苦しさはいつまで続きますか?
肺がんの手術後は、肺を切除したことによる肺活量の低下や胸の傷による痛みなどから、息苦しさがしばらく続くことがあります。
多くの場合は時間の経過とともに軽快していきますが、回復には個人差があります。
術後数か月から半年ほどで日常生活に支障がない程度に改善するケースが多いですが、広範囲の切除を行った場合や基礎疾患がある場合には、長期的に息切れが残ることもあります。
仕事復帰はいつ頃できますか?
手術の種類や切除範囲、患者様の体力や合併症の有無によって復帰時期は異なります。
一般的には、胸腔鏡手術などの負担が比較的少ない手術であれば、2〜3か月ほどで仕事に復帰できるケースもあります。
一方で、肺全摘術のように大きな手術を受けた場合は、体力回復に半年以上かかることも珍しくありません。
体を使う仕事や重労働に復帰するにはさらに時間がかかることが多いため、主治医と相談しながら段階的に復職を進めることが大切です。
(文献1)
公益財団法人|日本対がん協会