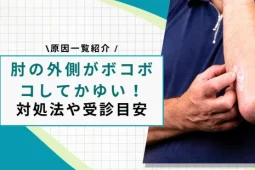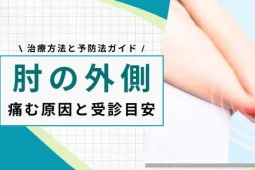- 肘関節、その他疾患
- 肘関節
肘外側側副靭帯損傷とは|症状・原因・治療法をわかりやすく解説
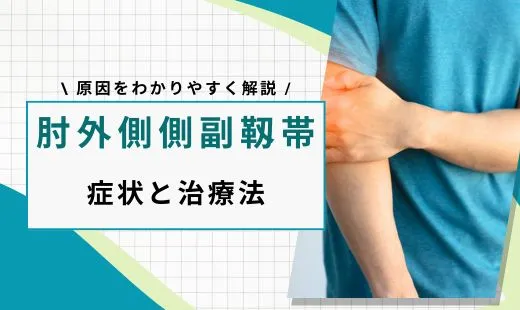
肘外側側副靭帯損傷とは、肘関節の外側にある靱帯が傷つき、痛みや不安定感が現れる状態を指します。原因や治療法がわからず、不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
本記事では肘外側側副靭帯損傷の症状や原因、治療法についてわかりやすく解説します。簡単にできるセルフチェック方法も紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
肘外側側副靭帯とは
肘外側側副靭帯(ひじがいそくそくふくじんたい)は、肘関節の外側に位置し、輪状靱帯とともに橈骨(とうこつ)を包み込むように支えている靱帯の総称です。
重いものを片手で持ち上げたり、腕をひねったりすると、肘には多方向からの負荷がかかります。肘外側側副靭帯の役割は多方向からのストレスに抵抗して肘関節を安定させることです。
なかでも、外側尺側側副靱帯(がいそくしゃくそくそくふくじんたい)は重要な部分で、肘の外側から後ろ側を支える位置にあります。外側尺側側副靱帯が損傷すると、関節が不安定になるリスクも少なくありません。
なお、靭帯損傷の原因や治療法については、以下の記事が参考になります。
肘外側側副靭帯損傷の症状
肘外側側副靭帯を損傷すると、肘だけでなく肩や腕にも痛みが広がる場合があります。とくに、肩の前側から二の腕に症状が出るケースがほとんどです。
以下で、軽度から重度までの症状を解説します。
軽度から重度までの症状
肘外側側副靭帯損傷には、靱帯が少し伸びている程度のものから、完全に断裂してしまう重度のものまでさまざまな段階があります。
以下に、主な症状の例を重症度ごとにまとめたので、参考にしてください。
|
損傷の程度 |
症状 |
|---|---|
|
軽度(靱帯が軽く伸びた状態) |
|
|
中度(靱帯が部分的に断裂している状態) |
|
|
重度(靱帯が断裂している状態) |
|
痛みの感じ方や肘の不調は人によってそれぞれ異なります。軽度の症状に見えても、自己判断せず早めに医師に相談しましょう。
自分でできる症状チェックの方法
肘の痛みや違和感が気になる方は、以下の項目をチェックしてみてください。複数当てはまる場合は、肘外側側副靭帯の損傷が起きている可能性があります。
|
症状の種類 |
具体的なチェック項目 |
|---|---|
|
動かしたときの痛み |
|
|
押したときの痛み、腫れ |
|
|
安静時の痛み |
|
|
不安定感、筋肉の異常 |
|
気になる症状が続くときや、普段の生活で不便を感じる場合は、早めに病院に行きましょう。
リペアセルクリニックでは、メール相談やオンラインカウンセリングを実施しています。肘の痛みが気になるときはお気軽にご相談ください。
\まずは当院にお問い合わせください/
肘外側側副靭帯損傷の原因
肘外側側副靭帯損傷の原因には主に以下の2つがあります。
- 転倒や外傷によるダメージ
- 肘への過度な負担
以下で、それぞれ見ていきましょう。
転倒や外傷によるダメージ
転倒した際に手をついてしまい肘に力が加わり、肘外側側副靭帯を損傷してしまうケースがあります。または、肘を直接ぶつけてしまったり、交通事故で肘に怪我を負ってしまったりして損傷するのも一例です。
事故や転倒によって靱帯が引き伸ばされ、無理なひねりが加わると損傷が生じる可能性があります。
肘に強いストレスが加わると、意図せず靱帯に大きな負担がかかるため注意が必要です。
肘への過度な負担
肘外側側副靭帯損傷の原因のもう一つは、野球やテニスなどのスポーツによる肘への過度な負担です。肘の一部分に慢性的に強い力やひねりなどの負担がかかると、靱帯を損傷してしまうケースも少なくありません。
無理なフォームでプレイを続けたり、肘を使いすぎる状態が続くと肘外側側副靭帯に負担をかけ、損傷につながる恐れがあります。
靱帯への負担を減らすために、適度な休養やセルフケアを心がけることが大切です。
肘外側側副靭帯損傷のリハビリ・治療方法
肘外側側副靭帯の損傷を治療するには主に、リハビリやギプスによる固定などの保存療法や手術療法、再生医療があります。
以下でそれぞれ詳しく解説しますので、治療法に悩んでいる方は参考にしてください。
保存療法
軽度の靱帯が軽く伸びた状態の症状があるときには、まずは保存療法で治療を行います。保存療法には冷湿布や包帯による圧迫処置、リハビリなどの方法があります。
軽度の靱帯損傷では、保存療法が選ばれることがほとんどです。
以下に、代表的な保存療法の内容をまとめました。
|
保存療法の種類 |
内容・目的 |
|---|---|
|
冷湿布 |
炎症や痛みを抑える |
|
包帯による圧迫処置 |
腫れを抑え、肘を安定させる |
|
ギプス固定 |
関節の動きを制限し、靱帯の回復を促す |
|
リハビリ |
可動域や筋力を回復させる |
いずれの方法も、医師の判断のもとで正しく治療することが大切です。
手術療法
靱帯の損傷が重度で肘関節が安定しない場合には、手術が選択されるケースがあります。保存療法では改善が難しいケースや、自然な回復が見込めない状態だと、外科的な処置が選ばれる場合も少なくありません。
手術では、切れた靱帯を縫い合わせたり、剥がれた部位を固定したりします。術後は一定期間固定して、そのあと肘の可動域、筋力を回復するためにリハビリを行うことが一般的です。
再生医療
肘外側側副靭帯の損傷では、保存療法や手術以外に再生医療と呼ばれる新しい治療法も選択肢の一つです。再生医療には、自分の脂肪から取り出した幹細胞を使って損傷した組織の回復を促す幹細胞治療や、血液を使ったPRP療法などがあります。
薬やリハビリでも効果が出にくいときに検討される治療で、手術のように体への負担が大きくない点も特徴です。
再生医療の具体的な治療法や症例については、以下のページで詳しく解説しています。

手術をしない新しい治療「再生医療」を提供しております。
また、本院ではメール相談やオンラインカウンセリングを行っております。お気軽にご相談ください。
\まずは当院にお問い合わせください/
肘外側側副靭帯損傷の診断方法
ここでは、肘外側側副靭帯損傷の診断方法について解説します。診断方法は大きく分けて下記の2つです。
- ストレステストによる診断
- 画像による診断
それぞれ、診断方法の特徴を確認しましょう。
ストレステストによる診断
損傷の診断方法の一つにストレステストがあります。ストレステストとは、肘に負荷をかけながら、靱帯がしっかり働いているか、関節が安定しているかを確認する検査です。
関節にぐらつきや不安定性が認められた場合は、靱帯損傷の可能性があると診断されます。
無理に動かすと症状を悪化させるおそれがあるため、専門医の診察を受けることが大切です。
画像による診断
肘外側側副靭帯の損傷を診断するために、主にレントゲンやストレスレントゲン、MRIの3つの画像検査が用いられます。
|
検査名 |
特徴・目的 |
|---|---|
|
レントゲン |
骨折や脱臼の有無を確認する |
|
ストレスレントゲン |
力を加えた状態で撮影し、靱帯損傷による関節の不安定性を評価する |
|
MRI |
靱帯や筋肉などの損傷を詳しく確認できる |
レントゲンでは靱帯の損傷がわかりづらく、正確に診断するのが困難なケースもあります。肘の痛みやぐらつきなどの自覚症状がある場合は、MRI検査も視野に入れて医師に相談するとよいでしょう。
肘外側側副靭帯損傷の症状や治療法を理解し適切に対応しよう
肘外側側副靭帯損傷の症状は軽度から重度まであります。痛みの度合いによって治療法も異なるため、自身の症状を正しく理解することが重要です。
症状が軽い場合は湿布や圧迫包帯の処置で緩和されるケースもありますが、自己判断せずに必要に応じて医師に相談してみてください。
肘に痛みや違和感を感じたら、無理をせず安静にし、日ごろから肘に負担をかけないように心がけましょう。