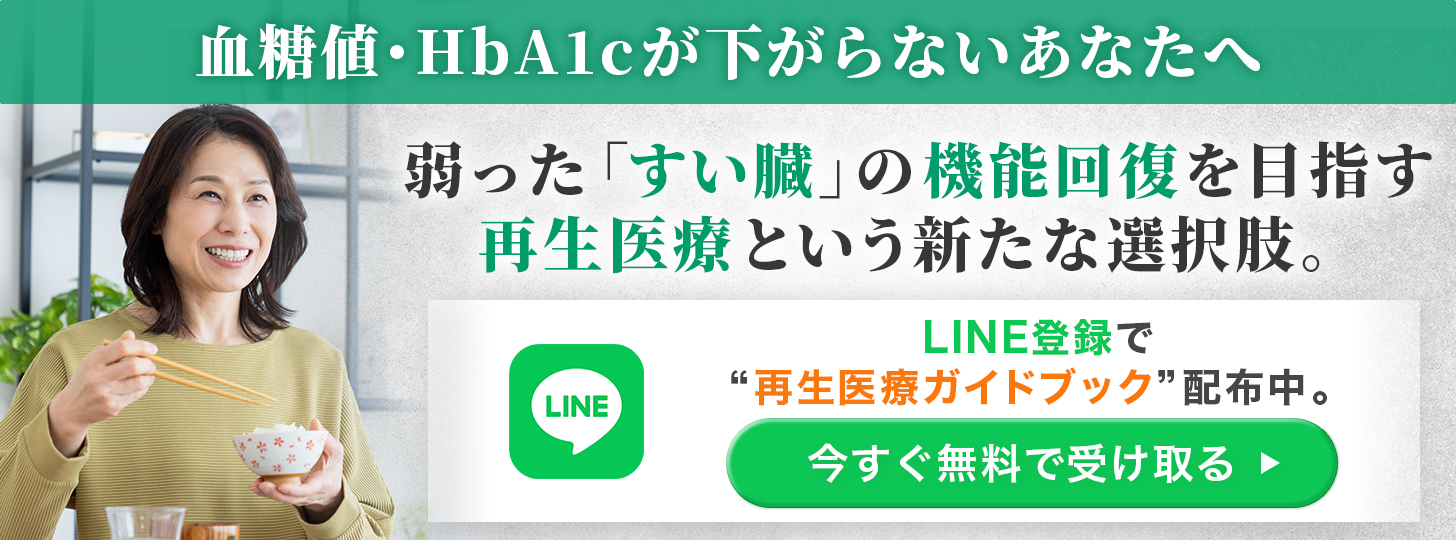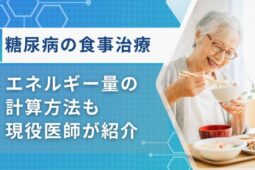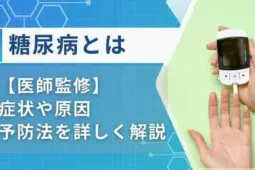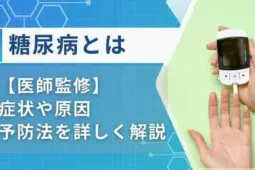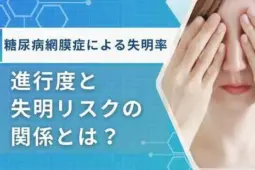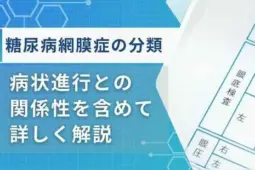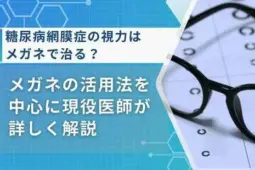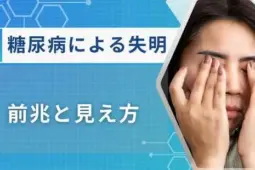- 糖尿病
- 内科疾患
糖尿病性腎症の人が知っておきたい食事療法と献立のコツ
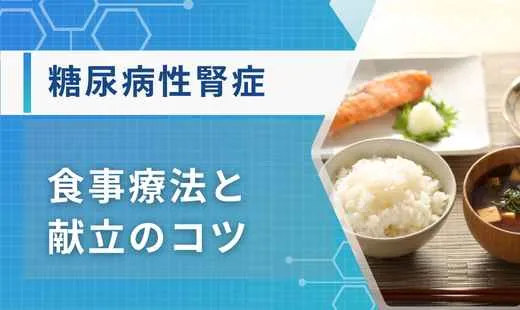
糖尿病性腎症と診断されると、「何を食べたら良いの?」「献立をどう考えれば良いの?」と戸惑う方も多いでしょう。
腎症は腎機能の低下が進むと、やがて透析が必要になるリスクがあります。しかし、早い段階から食事を管理することで進行を抑え、腎臓を守ることが可能です。
本記事では、糖尿病性腎症のリスクを理解した上で「なぜ食事療法が必要なのか」、そして「具体的に何をどう食べれば良いのか」まで、わかりやすく解説します。
日々の献立作りのコツや外食・コンビニを利用する際の工夫も紹介します。今日から実践できる食事管理のポイントをぜひ参考にしてください。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
糖尿病性腎症について気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
糖尿病性腎症の食事の具体的な献立例
糖尿病性腎症では、たんぱく質や塩分を控えつつ栄養バランスを整えることが大切です。
ここから、朝食、昼食、夕食それぞれの具体的な献立例とレシピをご紹介します。
朝食の献立例
| メニュー | 材料 |
|---|---|
| ごはん | ・低たんぱくごはん1/25 180g(1パック) |
| みそ汁(麩・ねぎ) | ・みそ 10g ・だし汁 130cc ・麩 2g ・ねぎ 25g |
| かんぴょうの炒め煮 | ・かんぴょう 5g ・にんじん 20g ・ごま油 3g ・砂糖 3g ・しょうゆ 4g ・だし汁 30cc |
| くだもの(オレンジ) | ・オレンジ 50g(1/3個) |
| 味付のり・紅茶 | ・紅茶 1パック+粉飴40g ・味付のり 2g(1袋) |
(文献1)
このメニューの栄養は、586kcal、たんぱく質18.8g、塩分2.0gでした。(文献1)
昼食の献立例
| メニュー | 材料 |
|---|---|
| ごはん | ・低たんぱくごはん1/10 180g(1パック) |
| チキンカツ | ・鶏もも皮なし 70g ・こしょう 少々 ・小麦粉 3g ・生パン粉 10g ・油 9g ・キャベツ 20g ・レモン 10g ・パセリ 2g ・ソース 5cc |
| 海草サラダ | ・サラダ用海草 25g ・きゅうり 20g ・ミニトマト 1個 ・ドレッシング 10g |
| さやえんどうの和風ソテー | ・さやえんどう 20g ・エリンギ 30g ・生しいたけ 10g ・油 3g ・塩 0.3g ・こしょう 少々 ・しょうゆ 2g |
(文献1)
チキンカツの作り方は以下のとおりです。
- 鶏肉を観音開きにし、こしょうを振って下味をつける。
- 小麦粉を水で溶いた衣をくぐらせ、次にパン粉をまぶす。
- 油でカラリと揚げたら、皿に千切りキャベツを添えて盛り付ける。
- 仕上げにレモンとパセリを飾る。
このメニューの栄養は、586kcal、たんぱく質18.8g、塩分2.0gでした。(文献1)
夕食の献立例
| メニュー | 材料 |
|---|---|
| ごはん | ・低たんぱくごはん1/10 180g(1パック) |
| さわらの照焼 | ・さわら 40g ・しょうゆ 2g ・みりん 3g ・料理酒 1g ・油 1g ・しその葉 1g(1枚) ・甘酢生姜漬 10g |
| かぼちゃの含め煮 | ・かぼちゃ 60g ・生しいたけ 20g(1枚) ・砂糖 3g ・みりん 3g ・しょうゆ 3g ・だし汁 20cc |
| マヨネーズ和え(もやし・にんじん) | ・もやし 50g ・にんじん 10g ・マヨネーズ 15g ・しょうゆ 3g ・からし 少々 |
| マクトン入り胡麻豆腐 | ・マクトンゼロパウダー 20g ・黒すりごま 1.5g ・水 50cc ・粉寒天 0.4g(1/10袋) ・生姜 2g ・しょうゆ 3cc |
(文献1)
マクトン入り胡麻豆腐の作り方は以下のとおりです。
- 鍋に水と粉寒天を入れて混ぜながら加熱し、寒天をしっかり溶かす。
- 寒天が完全に溶けたら、さらに2~3分ほど煮詰めて火を止める。
- 火を止めたら、マクトンパウダーと黒すりごまを加え、よく混ぜながら粗熱を取る。
- 粗熱が取れたタイミングで型に流し入れ、冷蔵庫で冷やし固める(熱いままだと層が分かれてしまうので注意する)。
- 型から取り出して器に盛り付け、おろし生姜を添え、しょうゆをかけていただく。
マクトンゼロパウダーは、消化吸収が良く速やかにエネルギーになる粉末油脂です。たんぱく質0gで高エネルギー(100gあたり789kcal)。どんな料理にも手軽に使え、効率的なエネルギー補給に便利です。
このメニューの栄養は、736kcal、たんぱく質12.8g、塩分2.1gでした。(文献1)
糖尿病性腎症は食事管理が重要!献立が必要な理由
糖尿病性腎症の食事療法の最大の目的は、腎不全への進行防止です。
腎臓は血液中の老廃物を排出する重要な役割を担いますが、糖尿病によって徐々にダメージを受け、機能が低下していきます。とくにたんぱく質を多く摂ると腎臓への負担が増えるため、摂取量を適切に制限し、塩分やエネルギー、カリウム、リンなども管理していかなければなりません。
食事管理を怠ると腎症が進行し、最終的には透析治療が必要になる可能性もあります。食事療法は患者様の腎症の進行度や年齢、体格、合併症の有無などによって内容が変わるため、自己判断で行うのは危険です。
医師や管理栄養士と相談しながら個別に献立を立てると、無理なく続けられ、腎機能をできるだけ長く保てます。
糖尿病性腎症の食事療法・献立のポイント
糖尿病性腎症の食事管理は、腎機能を守り進行を遅らせるための大切な治療のひとつです。
以下に、献立を考える上で知っておきたい栄養管理のポイントを解説します。
1日のエネルギー量の目安
糖尿病性腎症の食事療法では、過剰な栄養不足や肥満を防ぐために適正なエネルギー摂取が大切です。
目安は「標準体重1kgあたり約35kcal」ですが、年齢や活動量によって28〜40kcal程度と幅があります。(文献1)
エネルギーが不足すると体内のたんぱく質が分解されて腎臓に負担をかける恐れがあるため、十分に確保することが重要です。
糖尿病の血糖管理を両立させるためにも、炭水化物や脂質の質と量を調整しながら、主食・主菜・副菜をバランスよく組み合わせる工夫が必要です。
たんぱく質を制限する
腎臓の負担を減らすため、たんぱく質は「標準体重1kgあたり0.6~0.8g」に制限されるのが一般的です。(文献1)
制限量は、尿たんぱくの排泄量や血清クレアチニン値など腎症の進行度、栄養状態によって変わります。過剰なたんぱく質摂取は腎臓を酷使し、腎機能悪化を早めるリスクがあるため、食材の種類や量を慎重に選ぶ必要があります。
ただし過度な制限は栄養不良を招く恐れがあるため、低たんぱくごはんなどの特殊食品を利用したり調理法を工夫したり、美味しく無理なく続けられることが大切です。
医師や管理栄養士と連携して、自分に合った目標量を決めましょう。
塩分を制限する
高血圧や浮腫を予防・改善するために塩分制限は欠かせません。目標は1日6~7g未満ですが、高血圧やむくみが強い場合は5g以下に制限されることもあります。(文献1)
塩分の摂りすぎは血圧を上げ、腎臓の血管を痛め、病気の進行を加速させる原因になります。
以下は塩分制限のポイントです。
- 減塩調味料の活用
- だしや香辛料、酢などを使って風味を工夫する
- 外食や加工食品は塩分が多いため、成分表示を確認して選ぶ
毎日の食事を楽しみながら、無理なく続けることが大切です。
水分・カリウム・リンの摂り方
腎症が進行すると、水分やカリウム、リンの制限が必要になる場合があります。
水分はむくみや尿量を考慮して調整し、心不全の予防や血圧管理にもつながります。
カリウムは高くなりすぎると不整脈などの危険があるため、野菜や果物の種類や調理法(ゆでこぼしなど)で含有量を減らす工夫が必要です。
リンは骨からカルシウムを奪い骨粗しょう症を招くリスクがあるため、乳製品や加工食品などリンが多い食品の量を調整します。
必ず医師や管理栄養士と相談し、体調に合った食事を心がけましょう。
糖尿病性腎症に適した食材選びと調理の工夫
糖尿病性腎症の食事療法では、たんぱく質や塩分を抑えつつ満足感を得られる工夫が欠かせません。
治療用の低たんぱくごはんや調味料などを上手に取り入れると、制限内でエネルギーをしっかり確保できます。少ないたんぱく質を多く見せるために、薄切りやみじん切りにしてかさを増やしたり、味付けや盛り付けを工夫したりすることも大切です。
3食のうち1食はおかずがなくても食べられるメニューを用意し、たんぱく質量を調整する方法も有効です。
家族と同じ献立でも主菜を減らし副菜を増やすなど、うまく調整して無理なく続けることで腎機能を長く守りましょう。
外食・コンビニ・宅配弁当の選び方
糖尿病性腎症の食事療法では、自炊が理想ですが、忙しい日常では外食やコンビニ、宅配弁当を利用する機会も少なくありません。
ここからは、腎臓への負担を抑えつつ上手に選ぶコツを紹介します。
外食時の注意点
外食では塩分やたんぱく質が多くなりがちなので、自分で調節する意識が大切です。醤油やタレ、ドレッシングは別添えでもらい、使う量を減らすなどの工夫をしましょう。
カリウムやリンが多い食材を避けるため、サラダのドレッシング、乳製品、加工食品などにも注意が必要です。
主菜は肉より魚を選ぶと脂質やリンを抑えられ、腎臓への負担軽減につながります。麺類や丼ものは汁を残す、単品ではなく定食を選び副菜を増やすなど、組み合わせ方の意識も大切です。
栄養成分表示があるお店では、たんぱく質や塩分量を確認しながらメニューを決める習慣をつけ、外食を楽しみながら食事療法を続けましょう。
コンビニ利用のコツ
コンビニ食でも栄養バランスの意識が大切です。おにぎりだけ、菓子パンだけなど主食に偏らず、主菜・副菜を組み合わせて選びましょう。
サラダや煮物、焼き魚、ゆで卵などをプラスしてたんぱく質量を調整し、塩分やリンを抑えます。サンドイッチやおにぎり、ハンバーガーなどは中身の具材をチェックし、ハムやチーズなどリンや塩分が多いものは控えめにします。
以下の項目は注意するポイントです。
- 減塩表示の商品を選ぶ
- 飲み物は無糖のお茶や水を選ぶ
- 成分表示を確認してエネルギーやたんぱく質量を把握する
管理栄養士と相談しながら自分に合った選び方を身につけましょう。
宅配弁当や冷凍食の利用
自炊が難しい日や忙しいときには、腎臓病食や糖尿病食に対応した宅配弁当や冷凍食品を上手に活用するのもおすすめです。
塩分、たんぱく質、糖質などがあらかじめ管理されており、栄養バランスを整えやすいのが魅力です。自分で計算する負担を減らしつつ、適切な制限を守れるため、食事療法を無理なく続けられます。
最近はメニューの種類も豊富で、飽きずに続けられる工夫がされています。定期配送や単品購入などサービス形態も多様なので、生活スタイルや体調に合わせて選びましょう。
糖尿病性腎症には再生医療の選択肢
糖尿病性腎症に対しては、自分の脂肪から採取・培養した幹細胞を体内に投与する「再生医療」も新たな治療選択肢の一つです。患者様自身の細胞を使用するため、拒絶反応のリスクが低いのが特徴です。
しかし、糖尿病性腎症の進行を抑えるには、何よりも血糖管理が欠かせません。食事療法や薬物療法と組み合わせることで、より総合的な治療が可能になります。
将来の腎不全や透析を避けるために、再生医療についても検討してみましょう。詳しい内容は、以下をご覧ください。

糖尿病のお悩みに対する新しい治療法があります。
糖尿病性腎症の食事の献立はできることから始めよう
糖尿病性腎症の食事療法は、腎臓を守り進行を遅らせるために自分で取り組める治療法です。
しかし「完璧にやらなければ」と思いすぎるとストレスになり、続けるのが難しくなります。減塩や主菜の量を調整するなど、できることから少しずつ始めましょう。
治療用食品を活用したり、家族と同じメニューを工夫するなど、日常生活に取り入れやすい方法の選択も大切です。頑張りすぎず、続けやすい工夫を取り入れながら、医師や管理栄養士と相談し、自分に合ったペースで無理なく進めることが腎機能を長く守るポイントです。
食事管理とともに再生医療による治療をご検討の際は、ぜひ当クリニックにご相談ください。あなたに合ったサポートをご提案します。
\無料オンライン診断実施中!/
糖尿病性腎症の食事の献立におけるよくある質問
果物は食べて良いですか?
果物はビタミンや食物繊維が豊富ですが、糖分を多く含むたみ血糖値が上がりやすいため、食べすぎには注意が必要です。腎症が進行すると、果物に多く含まれるカリウムを制限する必要が出てくる場合もあります。
缶詰の果物を利用する場合はシロップをしっかり切るなどの工夫も大切です。自分に適した量や種類は、医師や管理栄養士と相談しながら確認してください。
たんぱく質を減らすと栄養不足になりませんか?
たんぱく質の制限は腎臓への負担を減らす大切な治療法です。しかし過度な制限で栄養不足にならないよう、代わりに十分なエネルギーを確保して筋肉量を維持することが重要です。
低たんぱくごはんや治療用食品を活用し、主食・副菜の組み合わせを工夫するとバランスを整えられます。管理栄養士の指導を受けながら取り組みましょう。
人工甘味料は大丈夫ですか?
一般に認可されている人工甘味料は安全性が確認されており、血糖値を上げにくいため糖尿病患者様でも上手に活用できます。飲み物やデザートに取り入れれば、甘みを楽しみながら血糖管理をしやすくなります。
ただし、商品によって甘味料の種類や量が異なるため、気になる場合は医師や管理栄養士に相談しましょう。
参考文献