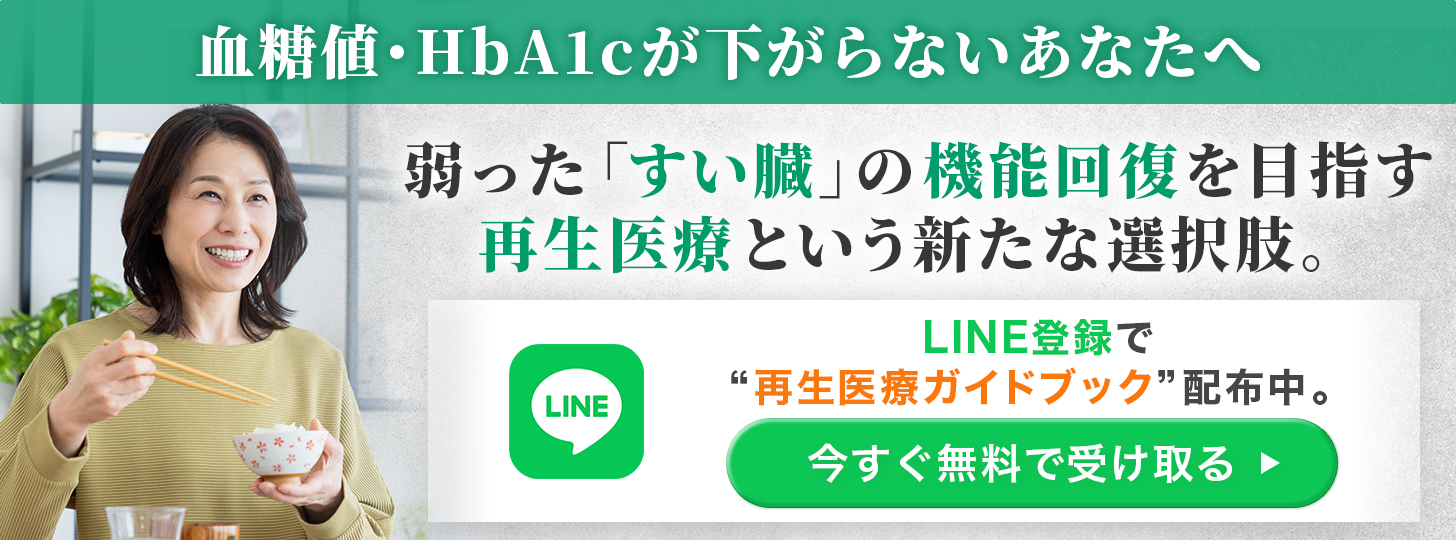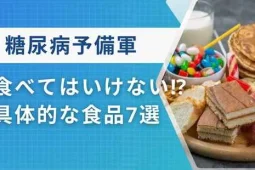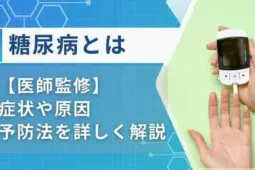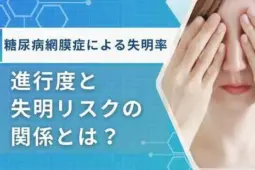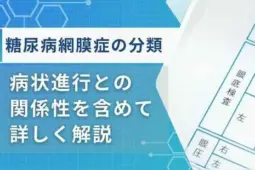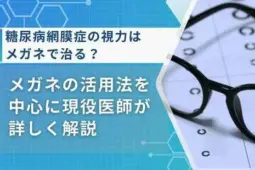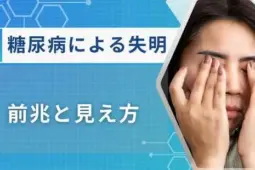- 糖尿病
- 内科疾患
【糖尿病】食事治療とエネルギー量の関係性を現役医師が解説|計算方法もあわせて紹介

糖尿病の食事療法では、食事量が多いと血糖値が上がり、少なすぎても体力が落ちてしまうため、「適正エネルギー量」がわからず悩んでいませんか。
多くの方が「何を食べるか」を考えながらも、「どのくらい食べるか」と言ったエネルギー量の管理を後回しにしがちです。
自分に合った「適正エネルギー量」を知ることで、血糖値を安定させ、無理なく改善が目指せます。
本記事では、糖尿病治療におけるエネルギー管理の基本から計算方法、メニュー作りのポイントまで医師監修で解説します。
食べる楽しみを保ちながら、血糖をコントロールしたい方は、ぜひ参考にしてください。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
糖尿病について気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
糖尿病の食事療法では「エネルギー管理」が重要
糖尿病は、薬物療法で症状が改善しても食事内容を見直さなければ、再び悪化しかねません。
糖尿病の予防・管理には、エネルギー量の適正化が血糖コントロールに役立ちます。
食事療法では、「何を、どのくらい食べるか」が大切です。
なお、本記事で紹介する食事方法は、あくまで目安となるものです。適正な食事量は人によって異なるため、より詳しく知りたい方は主治医や管理栄養士、糖尿病療養指導士に相談しましょう。
エネルギー摂取量の基準
糖尿病の食事療法では、「摂取エネルギー量(=1日に食べる総カロリー)」を適切に保つことが重要です。
摂取エネルギーが多すぎると血糖値が上がりやすくなり、薬やインスリンの効果が十分に期待できなくなります。
一方で、極端に食事量が少ないと、低血糖や筋肉量の低下を起こすリスクが高まり注意が必要です。
自分に合った「適正エネルギー量」を知ることが食事療法の基本です。
エネルギー量の目安は、目標体重に活動量に応じたエネルギー係数(25〜35kcal/kg)を掛けて算出します。
詳しい計算方法や具体的な目安については、次の項目で紹介します。
エネルギー摂取量を適切に保つことが、血糖コントロールの基本です。
適正エネルギー量により合併症予防
エネルギー摂取量を適正に保つことは、血糖コントロールに役立つだけでなく、糖尿病合併症の予防にもつながります。
過剰なエネルギー摂取は肥満につながり、インスリン抵抗性を悪化させ、動脈硬化や高血圧、脂質異常症などのリスクを高める要因です。
一方で、適正エネルギー量を維持すれば、体重増加を防ぎ、糖尿病性腎症や神経障害、網膜症など三大合併症のリスクを抑えられます。
食事療法は、健康維持のために長期的な生活改善が必要です。
エネルギー管理により、血糖値の安定だけでなく合併症のリスクを減らし、健康的な生活を送ることができます。
総エネルギー摂取量の計算方法
糖尿病を改善するためには、自分にとって適正なエネルギー量を知る必要があります。
エネルギー摂取量の目安は、計算で導くことができます。計算方法を知ることで、無理なくコントロールしましょう。
なお、1日の適性エネルギー量は年齢や性別によっても変わってきます。本記事の記載はあくまでも目安量と考えて、詳しく知りたい方は主治医、管理栄養士、糖尿病療養指導士にご相談ください。
適正エネルギー量の計算式
適正エネルギーの算出方法を紹介します。
以下、3つのステップで算出します。(文献1)
- Step1:目標体重の算出
- Step2:エネルギー係数の設定
- Step3:1日の適正エネルギー量の算出
Step1:目標体重の算出
まずは自分の目標体重を計算します。目標体重は、身長とBMI(Body Mass Index)から算出します。ご自身の身長から求められます。
目標体重(kg)=身長(m)×身長(m)×BMI(kg/m2)
※身長160cmの場合、計算式の身長は1.6mとなります。
※BMIは、体重と身長から算出される痩せや肥満度を表す体格指数です。
65歳未満の方は22kg/m2、65歳~74歳(前期高齢者)の方は22~25kg/m2、75歳以上(後期高齢者)の方は22~25kg/m2です。なお、75歳以上の方は、体格や食事量などにより個別に目標体重の設定が必要ですので、主治医や管理栄養士に相談しましょう。
Step2:エネルギー係数の設定
身体活動量と健康状態より、その人に適した摂取エネルギー量(エネルギー係数)を決定します。
エネルギー係数は、活動量や年齢、肥満の有無に応じて異なります。係数は、主治医に相談して決めましょう。
|
活動量目安 |
エネルギー係数(kcal/kg目標体重) |
|---|---|
|
デスクワークなどの軽い身体活動量の人 |
25~30 |
|
デスクワーク中心であるものの、通勤・家事、軽い運動など普通の身体活動量の人 |
30~35 |
|
力仕事、活発な運動習慣があるなど重い身体活動量の人 |
35~ |
Step3:1日の適正エネルギー量の算出
Step1の目標体重とStep2で決定したエネルギー係数を掛けた値が1日の適正エネルギー量です。
適正エネルギー量(kcal/ 日)=目標体重×エネルギー係数
年齢・活動量による目安
適正エネルギー量は、年齢や日常の活動量によって変わります。
同じ体重でも、日常生活での動き方が違えば消費エネルギー量も異なるためです。
たとえば、デスクワーク中心の人は消費エネルギーが少ないため、体重1kgあたり25〜30kcalが目安です。
一方で、通勤や家事など、軽く体を動かす機会が多い人は30〜35kcal、力仕事や定期的な運動をしている人は35kcal以上を目安に設定します。
また、高齢者など筋力低下の予防が必要な場合はエネルギー係数を大きめに、肥満により減量が必要な場合はエネルギー係数は小さめに設定します。
「自分の年齢」と「日常の活動量」「肥満の有無」によりエネルギー量を調整することが、長期的な血糖コントロールにつながります。
目安値はあくまで一般的なものですので、実際の食事量は主治医や管理栄養士の指導のもとで調整しましょう。
簡単な計算方法と活用例
1日の適正エネルギー量は、計算式「目標体重×エネルギー係数」より算出されますが、もっと簡単に知りたいという要望もあります。
おおまかにエネルギー量を求める場合、目標体重ではなく「標準体重」を基準に計算する方法があります。標準体重はBMI値を22として算出します。
標準体重(kg)=身長(m)×身長(m)×22(kg/m2)
この標準体重にエネルギー係数(25〜30kcal/kgなど)を掛けると、1日の摂取エネルギーの目安を求められます。
【たとえば身長160cm、デスクワーク中心の45歳女性の場合】
|
標準体重 : 1.6(m)×1.6(m)×22=56.3kg エネルギー係数:デスクワーク中心で「軽い身体活動量」に該当するため、エネルギー係数は25~30 kcal/kgです。ここでは中間的な値である28 kcal/kgを選択します。 1日の摂取エネルギー量:56.3(kg)×28(kcal/kg)=1576.4kcal |
この計算結果から、この方の1日の摂取エネルギー量の目安は約1600 kcalとなります。
なお、標準体重とは、統計的に「最も病気にかかりにくいとされる健康的な体重」のことで、実際の体型や年齢、筋肉量とは異なる場合があります。
そのため近年では、個々の健康状態や減量目標に応じた「目標体重」を基準にしています。
食事のエネルギー量を把握するには
算出した「1日の適正エネルギー量」は目安であり、実際にどのくらい食べているかエネルギー摂取量の把握が大切です。
しかし、すべての食品のカロリーを計算するのは現実として難しいでしょう。そこで役立つのが、「食品交換表」です。
食品交換表は、普段食べている食品を似たような栄養ごとにグループ分けし、同じグループ内で食品を交換できるようにしたツールです。
グループ内で食品を交換することで、適正なエネルギー量・栄養バランスの良い食事が摂れます。
毎日の食事をバランスよく組み立てながら、無理なくエネルギー量を管理できるようになります。(文献2)
食品交換表を活用する
糖尿病の食事療法で使われている「食品交換表」は、主食・主菜・副菜などを1単位=80kcalとして置き換えて考えるツールです。
たとえば、ご飯・パン・いも類などは同じ「炭水化物グループ」として扱い、どれを選んでも同じエネルギー量になるように調整できます。
食品交換表を使うと、献立全体のカロリーバランスを簡単に計算できるので、「ご飯を減らしてその分おかずを増やす」といった調整がしやすくなります。
書籍で販売している他、インターネットでも確認できます。農林水産省では「食事バランスガイド」として簡易版が公開されていますので、ご参照ください。(文献3)
詳しい使い方については、糖尿病専門医や管理栄養士に相談すると良いでしょう。
無理に食事を我慢するより、食品を上手に入れ替えて満足感を得るのが長く続けるコツです。
外食・コンビニでのエネルギー管理のコツ
外食やコンビニで弁当を買う際には、エネルギー表示をチェックしましょう。
最近はファミリーレストランやファストフード店などでも、メニューや公式サイトにカロリー・糖質などの栄養成分が記載されています。
弁当や惣菜を買う際も、ラベルの「エネルギー(kcal)」欄を見れば、1日の適正エネルギー量に占める割合が把握できます。
もし高カロリーな食品を選んだ場合、次の食事で野菜中心にするなどの調整が可能です。
食事の栄養素のうち、血糖値に影響を及ぼすのは炭水化物です。
炭水化物には、食後血糖値を上昇させエネルギーとなる糖質と、ほとんど消化されず血糖値の上昇を抑え、エネルギーにならない食物繊維があります。
糖尿病改善のためには、食物繊維が含まれる食品を多く摂るように心がけましょう。食物繊維の目標は、1日20g以上といわれています。
栄養バランスとメニュー作りのポイント
2型糖尿病の食事療法は、エネルギー量と各栄養素をバランスよく摂ることで、「血糖コントロール」を良好に保ちます。また、1回の食事中の糖質量が多いと食後高血糖を引き起こす可能性があるため、1日の食事をなるべく均等に3回に分けて食べるようにしましょう。
同じカロリーでも、栄養素の組み合わせによって血糖値の上がり方は変わります。
糖質・たんぱく質・脂質といった三大栄養素のバランスを整え、ビタミンや食物繊維を十分に摂ると血糖コントロールが安定します。
次に、三大栄養素の理想的なバランスと、血糖を穏やかに保つ食事の工夫を紹介します。
三大栄養素(糖質・たんぱく質・脂質)のバランス
血糖コントロール安定のためには、エネルギーのもととなる三大栄養素(糖質・たんぱく質・脂質)の割合が大切です。
バランスの良い栄養摂取量は、次の通りです。(文献1)
- 炭水化物:摂取エネルギーの40~60%
- たんぱく質:摂取エネルギーの20%まで
- 脂質:残り
炭水化物(糖質)の摂りすぎは食後血糖値の上昇を招く一方で、極端に減らすとエネルギー不足や筋肉量の減少につながるおそれがあります。
ご飯やパンなどの主食を適量にし、肉・魚・大豆製品などのたんぱく質をバランスよく取り入れましょう。
野菜・食物繊維を増やして血糖をコントロール
糖尿病改善のためには、食物繊維が含まれる食品を多く摂るように心がけましょう。
野菜やきのこ、海藻に多く含まれる「食物繊維」には、糖の吸収をゆるやかにして食後血糖値の上昇を防ぐ働きがあります。
食物繊維の摂取目標は、1日20g以上といわれています。
食物繊維を多く含む食品には、野菜(とくに根菜類)、海藻、キノコ、大豆、果物(糖質も多いので食べ過ぎに注意が必要)が挙げられるので、日々の食事に取り入れてみましょう。
また、血糖値が上がり過ぎないための食べ方を工夫できます。具体的な方法は、次のとおりです。
- ゆっくり時間をかけて食べる
- よく噛んで食べる
- 野菜を先に食べる
糖尿病治療に「再生医療」という選択肢
糖尿病治療において食事療法は基本ですが、食事療法だけでは不十分なケースもあります。
そのような場合に、新しい治療法も視野に入れると選択肢が広がります。近年では再生医療による治療も注目されています。
再生医療では、ご自身の脂肪から培養した幹細胞を投与し、膵臓や血管の再生・修復を目指します。
当院「リペアセルクリニック」で行っている再生医療については、以下の症例をご覧ください。
また、再生医療を提供する当院では、メール相談、オンラインカウンセリングを承っております。
糖尿病に関する再生医療の治療内容について詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

糖尿病のお悩みに対する新しい治療法があります。
糖尿病の食事を楽しみながらエネルギーを管理しよう
糖尿病が悪化すると全身にさまざまな合併症が生じます。しかし、食事療法を始めとする糖尿病治療を適切に行うことにより、合併症や動脈硬化の発症や悪化が防げます。
食事は毎日の生活で欠かせないものです。急激な食事制限は、ストレスにより長続きしないだけではなく、かえって症状が悪化する恐れがあります。
現在糖尿病を患っている人は、主治医や管理栄養士、糖尿病療養指導士と相談しながら、継続しやすい食事療法を進めていきましょう。
糖尿病の食事治療に関するよくある質問
糖尿病の食事療法に関するガイドラインはありますか?
糖尿病の食事療法については、日本糖尿病学会が作成した「糖尿病治療ガイドライン 2024」が公開されています。(文献4)
ガイドラインでは、血糖コントロールのための食事療法やエネルギー摂取量・炭水化物の制限などの考え方が示されています。
糖尿病の食事療法は「エネルギー管理」と「栄養バランス」を両立させることが重要とされています。
食事内容を見直す際は、ガイドラインを参考にしつつ、主治医や管理栄養士の指導を受けると安心です。
糖尿病の食事指導に関するパンフレットはありますか?
農林水産省や日本糖尿病学会などが、患者さん向けのわかりやすい資料やパンフレットを公開しています。
一般社団法人日本糖尿病学会「日本糖尿病学会がすすめる健康食スタートブック」
これらは公式サイトから無料で閲覧・ダウンロードできます。日々の食事管理に役立ててください。
また、病院やクリニックなど施設によってはパンフレットなどを用意しているところもあるので、相談してみると良いでしょう。
参考文献
日本糖尿病学会がすすめる健康食スタートブック|一般社団法人日本糖尿病学会
糖尿病治療ガイドライン 2024|一般社団法人日本糖尿病学会