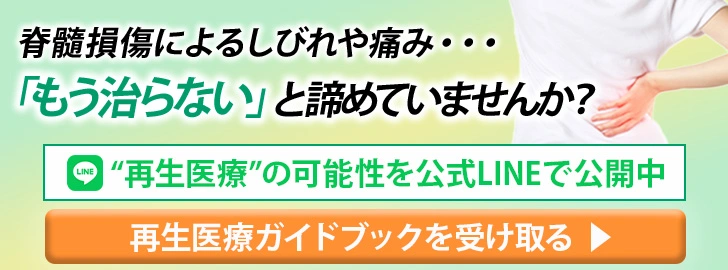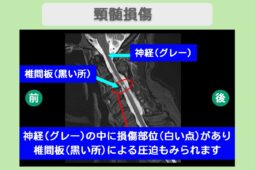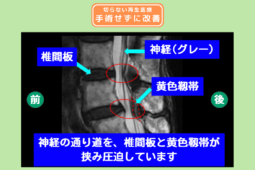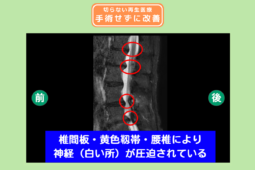- 脊椎
- 脊椎、その他疾患
【医師監修】むち打ちに効く湿布の選び方や貼り方を解説
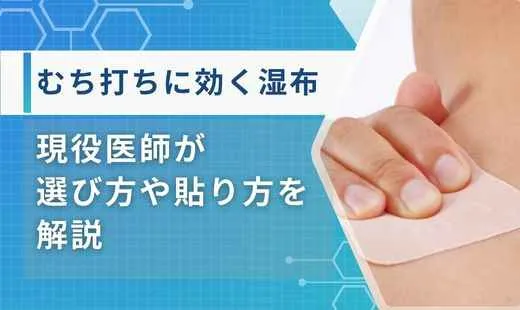
「交通事故が原因でむち打ちと診断され、湿布を処方された」
「湿布はどのように効くのだろうか?」
「早く治したいのだが、湿布で本当に治るのだろうか?」
むち打ちと診断された方の中には、このように感じている方もいると思います。
結論から申し上げますと、湿布は症状を和らげるものであり、根本的な回復のためには整形外科での治療が必要です。
本記事ではむち打ちに効く湿布や選び方、貼り方などについて解説します。
湿布を上手に活用しつつ、早い回復を目指すためにも、ぜひ最後までご覧ください。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
長期化する痛みなどお悩みの症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
むち打ちに効く湿布とは|成分と効果について
むち打ちで処方される多くの湿布には、非ステロイド性抗炎症薬が含まれています。
非ステロイド系抗炎症薬には、体内で痛みを増強させる物質「プロスタグランジン」を生成する酵素を阻害する作用があります。この作用で、痛みを和らげたり炎症を鎮めたりします。(文献1)
非ステロイド系抗炎症薬としてあげられるのは、主に以下のとおりです。
- ロキソニン
- ボルタレン
- モーラス
- インテバン
- MS温湿布
- MS冷湿布
MS温湿布と冷湿布の違いは、含まれている成分です。温湿布にはトウガラシエキスが含まれており、冷湿布にはメントールが含まれています。
むち打ちにおける湿布の効果は痛みや炎症を和らげることであり、根本的な治療は難しいといえるでしょう。
むち打ち時の湿布の選び方
湿布は主に冷湿布と温湿布の2種類に分けられており、どちらを選ぶかは、患者の状況次第です。
冷湿布には、サリチル酸メチル、メントール、ハッカ油などの冷感成分が配合されており、事故や外傷の直後で腫れや熱が著しいときに使われます。
温湿布は、血行促進や温感作用を持つトウガラシエキスや、合成トウガラシのノニル酸ワニリルアミドなどが配合されています。そのため慢性的な痛みやこりがあるときに使われることが多いものです。
自分の症状に応じた湿布を処方してもらうためにも、医師の診察時には症状を正確に伝えましょう。
市販されている湿布を購入する場合は、薬剤師や登録販売者へ相談すると良いでしょう。
むち打ちに対する正しい湿布の貼り方
むち打ちで湿布を使用するときは、痛みや腫れ、こりといった症状が強い部位に直接貼りましょう。主な部位としては、首や肩、背中の上部などがあげられます。
正しい湿布の貼り方は、主に以下のとおりです。
- 貼る前に患部を清潔にして、汗や水分を拭きとる
- 傷や湿疹などがある部分を避けて貼る
- 湿布を皮膚に密着させるために、空気を抜きながら貼る
- 必要に応じて、テープや包帯などで固定する
湿布を貼る際の注意点
湿布を長時間貼る、もしくは同じ場所に貼り続けることは避けてください。皮膚のかぶれや赤みの原因になるためです。
決められた回数以上に湿布を貼らないことも大切です。必要以上に貼り過ぎると、湿布薬の成分が皮膚から吸収されて、内服薬同様の副作用が現れる可能性があります。
ロキソニン湿布の場合、お腹の痛みや不快感、吐き気といった消化器症状や皮膚のかゆみ、むくみなどの副作用が出現した事例があります。(文献2)
湿布を貼った部分を日光(紫外線)に当てることも避けてください。光線過敏症(日光に当たることで起こる皮膚炎)と呼ばれる副作用を起こす可能性があるためです。光線過敏症では、皮膚の赤みやかゆみ、水ぶくれなどの症状が現れます。予防するためには、長袖の服を着たり、サポーターを着用したりしましょう。
副作用と思われる症状が現れた場合は、すみやかに医師や薬剤師へ相談してください。
むち打ちにおける湿布以外の治療方法
むち打ちにおける湿布以外の治療方法は、急性期と慢性期で異なります。この章では、それぞれの時期に応じた治療法を紹介します。
急性期
外傷によりむち打ち症状が出てきたときは、まず整形外科を受診しましょう。正しい診断や治療のためにも、レントゲンやCT、MRIなどの検査が必要です。
また、交通事故で損害賠償を請求する場合は、医師の診断書が必要です。(文献3)
病院受診後は、できる限り首を安静にしてください。必要に応じて、頚椎カラーを使用する場合もあります。
痛みが強い場合は、医師から処方された鎮痛剤を内服しましょう。炎症が起きている可能性もあるため、首もしくは痛みのある部分を冷やして炎症を落ち着かせてください。
患部を冷やすときは、ビニール袋や氷のうに入れた氷、もしくは冷たいタオルを患部に当てると良いでしょう。
慢性期
慢性期にも痛みが続いている場合は、鎮痛剤の内服やブロック注射などで和らげます。
慢性期では、ストレッチや筋力トレーニングなどの理学療法にくわえ、物理療法が実施される場合もあります。
物理療法としてあげられるのは、主に以下のとおりです。
- ホットパック
- 超音波療法
- 電気刺激療法
むち打ちの治療については、下記の記事でも紹介しています。あわせてご覧ください。
むち打ちは湿布と並行して医療機関での治療が必要
むち打ちで処方される湿布は、症状を和らげる対症療法の1つであり、湿布のみでは根本的な治療は難しいものです。
むち打ちは放置すると痛みが悪化したり、後遺症が残ったりする可能性もあります。そのため、医療機関で適切な治療を受けることが大切です。
痛みが長引く、痛みが強くなる、手足のしびれが出てきた、頭痛や吐き気が続くといった症状が続くときは、放置せずに再度病院を受診しましょう。
むち打ちでは、慢性的な経過をたどるケースも少なくありません。焦らず一歩ずつ回復を目指しましょう。
リペアセルクリニックでは、メール相談やオンラインカウンセリングを実施しています。湿布を貼り続けてもむち打ち症状が続くといったお悩みがある方は、お気軽にお問い合わせください。
\無料オンライン診断実施中!/
むち打ちと湿布に関するよくある質問
むち打ちでやってはいけないことは何ですか?
主に以下の4点があげられます。
- 診察を受けずに放置する
- 外傷直後に首を温める
- 外傷直後に飲酒する
- 外傷直後にマッサージを受ける
外傷後、診察を受けずに放置すると、症状の悪化や慢性化を招く、後遺症が残るといったリスクがあります。必ず医療機関を受診しましょう。
外傷直後は炎症を起こしており、温めることで悪化し、痛みが強まる可能性があります。冷やして炎症をおさえる方が望ましい状況です。
アルコールは血液循環を良くする作用があります。その結果、炎症が促進され、痛みが強まる可能性があるため、外傷直後の飲酒は避けてください。
マッサージには炎症を促進する作用があります。また、傷ついた筋肉や靱帯にさらなるダメージを与える可能性もあるため、医療機関受診後は安静にしましょう。
寝るときに湿布を貼っていても問題はありませんか?
基本的には寝るときに貼っていても問題はありません。ただし、就寝中にかゆみやヒリヒリした感覚が生じた場合は、一度はがす方が望ましいでしょう。
湿布が入っている袋には、「1日2回」「〇時間おき」など、貼る回数や間隔が記載されています。湿布を貼るときは、その指示を守りましょう。はがし忘れると、皮膚トラブルが生じる可能性があります。
参考文献