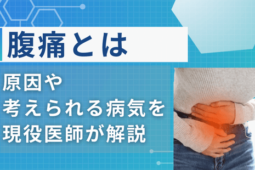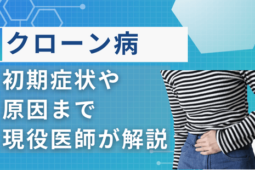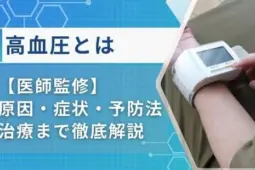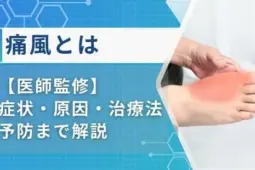- 内科疾患
- 内科疾患、その他
脂質異常症の薬は必要?コレステロールを下げる薬の種類と副作用を専門医が解説
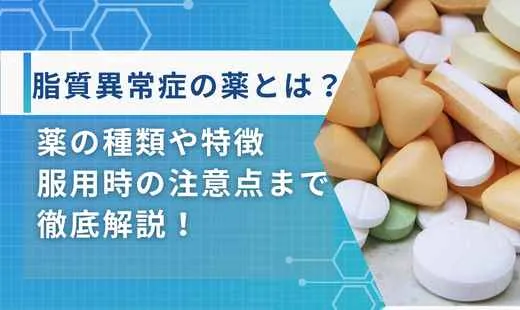
脂質異常症は、自覚症状がないため、知らず知らずのうちに進行してしまう疾患です。
しかし、そのまま放っておくと動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳梗塞などといった重篤な病気につながる可能性があります。
その一方で「どの薬を選べば良いのか」「副作用が心配」といった声も多く聞かれるのが現状です。
本記事では、脂質異常症の薬物治療について詳しく解説いたします。
薬の種類や効果、副作用のリスク、服用期間、そして薬に頼らない選択肢まで、専門医の視点からお伝えします。
ぜひ記事を最後まで読んで、脂質異常症薬への理解を深めましょう。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
脂質異常症に関連する「しびれ」などの症状についてお悩みの方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
脂質異常症とは?その診断基準と薬の必要性
まず脂質異常症がどのような状態を指すのか、その診断基準について解説します。
そして、なぜ早期の診断と適切な治療が重要なのか、放置した場合のリスクについても詳しくお伝えします。
ご自身の健康状態を正しく理解し、適切な治療につなげるための参考にしてください。
脂質異常症の診断基準について
脂質異常症とは、一定の基準値よりもLDL(悪玉)コレステロールや中性脂肪が高い、または、HDL(善玉)コレステロールが低い状態です。
脂質異常症の診断では、まず採血による血液検査でLDLコレステロール値とHDLコレステロール値、中性脂肪値の測定から行います。
採血前日は、高脂肪食や高カロリー食を控え、禁酒し、12時間以上の絶食を行った状態の採血が必要です。
これらの値が下記いずれかに該当すると「脂質異常症」と診断されます。(文献1)
- LDL(悪玉)コレステロール値が140 mg/dL以上の場合
なお、LDLコレステロールが120〜139mg/dLは境界域といわれ、糖尿病や高血圧の合併がある場合は治療が必要となることがあります。 - HDL(善玉)コレステロール値が 40 mg/dL未満の場合
- 中性脂肪が150 mg/dL以上の場合
ただし、単に数値が基準を超えればすぐに投薬するわけではありません。
診断の際には、年齢・性別・既往歴(心筋梗塞や脳卒中の経験)、家族歴(家族性高コレステロール血症の疑い)、喫煙歴、高血圧や糖尿病などの合併症も総合的に評価します。
この基準値に応じて、薬物治療のタイミングや方法が決まるので、ご自身の目標値については、医師にご相談ください。
脂質異常症治療薬の必要性と放置するリスク
脂質異常症は、自覚症状がないため、健康診断などで発見されることが多いです。
治療せずに放置すると、HDLコレステロールの減少やLDLコレステロールの増加により、動脈の壁に脂肪の塊(プラーク)を作ってこびりつき、その結果、動脈硬化になります。
動脈硬化が進行すると、心筋梗塞や狭心症、脳卒中や脳梗塞などの重篤な病気になるリスクが高まります。
脂質異常症の薬について|主要な薬剤の種類
脂質異常症の治療には、主に以下の薬が使われます。
| 薬剤の種類 | 主な効果・特徴 |
|---|---|
| スタチン系製剤 |
|
| PCSK9阻害薬 (エボロクマブ) |
|
| siRNA薬 (インクリシラン) |
|
| ベムペド酸 |
|
|
その他の脂質改善薬 |
|
スタチン系製剤
スタチン系製剤は、肝臓でコレステロールが作られる際に働く「HMG-CoA還元酵素」という酵素の働きを阻害し、体内のコレステロール合成を抑えます。
その結果、血液中のLDL(悪玉)コレステロールが減少し、動脈硬化の進行を抑える効果が期待できます。
スタチン系製剤の特徴は、その種類や服用量によってコレステロールを下げる効果の強さが異なることです。
大きく分けて「スタンダードスタチン」と、スタンダードスタチンより作用が強い「ストロングスタチン」の2種類があります。
どの種類や量を使うかは、患者様の検査結果や病気のリスク、副作用の出方などによって、医師が総合的に判断します。
これらのスタチン系製剤の多くは、1日1回の服用が可能な経口薬です。
主な副作用には、以下の症状が挙げられます。
- 筋肉痛や筋力低下
- 消化器症状(胃の不快感、吐き気、便秘)
- 発疹
- 肝機能障害
少しでも体の異変を感じたら、自己判断で薬の服用を中止せず、速やかに医師に相談してください。
PCSK9阻害薬
PCSK9阻害薬は、スタチン系製剤の服用が難しい場合、スタチン系製剤と併用で検討される薬剤です。
肝臓で作られるPCSK9タンパク質の働きを阻害することで、血管からLDLを肝臓に取り込む受け皿であるLDL受容体を増加させます。この作用によって、血中のLDL(悪玉)コレステロールを下げられます。(文献2)
PCSK9阻害薬は、スタチン系製剤では⼗分に LDLコレステロール値が低下しない方や家族性⾼コレステロール⾎症の方、冠動脈疾患、心筋梗塞、脳梗塞などの心血管疾患を経験し、再発予防が必要な方に有効な治療薬です。
日本で現在使用されているPCSK9阻害薬には、エボロクマブ(レパーサ)やアリロクマブ(プラルエント)などがあります。
投与は皮下注射で投与され、通常は2週間に1回、または月に1回の頻度で投与されます。
自宅での自己注射が可能なため、通院の負担を軽減できます。
副作用には、疼痛、紅斑、発疹などの反応を引き起こす可能性があります。副作用が出たら速やかに医師に相談してください。
siRNA薬(インクリシラン)
siRNA薬は、肝臓で産生される特定のタンパク質、PCSK9の生成を抑えることでコレステロールを低下させる薬剤です。
siRNA薬はこのPCSK9の数を減らすことで、血液中のLDLコレステロール値を下げる効果を発揮します。
以下のような患者様にsiRNA薬は有効な治療薬とされています。
- スタチン系製剤だけではLDLコレステロール値が十分に低下しない方
- 家族性高コレステロール血症の方
- すでに心臓や脳の動脈硬化疾患をお持ちでコレステロール管理が不十分な方
siRNA薬は、皮下注射で投与され、成人には初回に300mgを投与し、その後3カ月に2回目の投与を行います。
それ以降は6カ月ごとに定期的に投与されます。この薬はPCSK9阻害薬と違い、医療機関でのみ投与可能なため、自己管理による投与忘れの心配はありません。
siRNA薬の副作用には、注射した部位に疼痛、紅斑、発疹などの反応を引き起こす可能性があります。
副作用が出た場合は、速やかに医師に相談してください。
ベムペド酸
ベムペド酸は、スタチン系製剤で副作用が出たり、LDLコレステロール値の低下が不十分な場合に処方されることがある薬剤です。
作用としては、肝臓に存在するATPクエン酸リアーゼという酵素を阻害し、コレステロールの合成を抑制します。
この酵素は肝臓に多く存在する酵素で、肝臓のコレステロール合成が減ることで、血中のLDLコレステロールが下がる効果が期待できます。
1日1回の経口薬で、日本では2024年11月26日に大塚製薬が製造販売承認申請を行っており、承認されれば処方される可能性があります。(文献3)
ベムペド酸の副作用には、痛風・胆石症の発症率の上昇、血清クレアチニン・尿酸・肝酵素レベルが上昇する可能性があります。
その他の脂質改善薬(エゼチミブ、フィブラート製剤、EPA製剤、陰イオン交換樹脂)
脂質異常症の治療には、これまでにご紹介したスタチン系製剤やPCSK9阻害薬、siRNA薬以外にも、患者様の状態や脂質のタイプに合わせて、様々な薬剤が用いられます。
ここでは、その他の脂質改善薬について、その作用と特徴を解説します。
エゼチミブ(小腸コレステロールトランスポーター阻害剤)
エゼチミブは、小腸におけるコレステロールの吸収を阻害します。
その結果、血液中のLDLコレステロールや総コレステロールの濃度が低下する薬で、1日1回の経口服用薬です。
スタチン系製剤を服用できない人の治療にも使用されますが、スタチン併用でLDLコレステロール値を下げることが報告されています。
エゼチミブの主な副作用には、発疹や消化器症状(便秘、下痢、腹痛、腹部膨満、吐き気、嘔吐)などがあります。
このような症状が現れた場合は、医師に相談してください。
フィブラート系製剤
フィブラート系製剤は、中性脂肪を下げる働きがあり、LDLコレステロールを減少させるとともに、HDL(善玉)コレステロールを増やす効果も期待できる薬で、1日1回の経口服用薬です。
スタチン系製剤と併用すると副作用として、筋肉の細胞が破壊される横紋筋融解症などの症状が起こるリスクが高まります。そのため、治療上併用する場合は医師の指導のもとでの服用が重要です。
EPA製剤(イコサペント酸エチル)
EPA製剤は、血液中の中性脂肪を低下させ、血行を改善する効果があります。
EPA製剤には、サプリメントとして市販されているものと、高脂血症治療薬として処方される医療用医薬品の2種類ありますが、高脂血症治療薬として処方されるものは医師の診断と処方箋が必要です。
EPA製剤の主な副作用には、発疹や消化器症状(下痢、腹部の不快感、吐き気、嘔吐)などが報告されています。
陰イオン交換樹脂
陰イオン交換樹脂は、腸内で胆汁酸と結合して体外に排出させることで、血中コレステロール値を低下させる効果を持つ薬剤です。
スタチン系製剤が使用できない症例や併用薬として処方されてます。
陰イオン交換樹脂の主な副作用には、発疹や消化器症状(便秘、下痢、食欲不振、吐き気)があります。
飲み合わせや服用時の注意点
脂質異常症薬と他の薬や食品との飲み合わせや、日常生活で気を付けるべき点について解説します。
スタチン系製剤(アトルバスタチンとリピトール)+グレープフルーツジュース
グレープフルーツに含まれる成分が薬の分解を妨げ、血中濃度が高くなり、薬の効果が強くなりすぎてしまう可能性があります。(文献4)
グレープフルーツジュースの影響は、数日間におよぶこともあるといわれているため、薬を服用している間はグレープフルーツジュースを飲まないように注意しましょう。
同じ柑橘系の果物でも、みかんやオレンジは一緒に食べても影響を与えないと言われています。
スタチン系製剤+フィブラート系製剤
中性脂肪を下げる目的で併用されることがありますが、筋肉障害のリスクがやや高まります。(文献6)
クレアチンキナーゼ(CK:筋肉の損傷を示す検査値)測定を定期的に行い、異常があれば片方を減量・中止することもあります。
EPA製剤+抗凝固薬
EPA製剤には血液をサラサラにする作用があり、抗凝固薬(ワルファリンなど)を服用中の方は出血傾向があるので注意が必要です。出血を伴う医療行為(抜歯、外科手術など)を行う場合には医師に相談しましょう。
胆汁酸吸着樹脂と他の経口薬
胆汁酸吸着樹脂は、他の薬剤の吸収を遅延・阻害する可能性があるため、服用時間を2時間以上空ける必要があります。
服用する薬剤の種類や量によっては、さらに時間を長く空ける場合もあるため、必ず医師や薬剤師に相談しましょう。
脂質異常症の薬は一生飲み続ける?服用期間と中断の可能性
脂質異常症の薬は、多くの場合、長期的に服用を続けることが推奨されます。
しかし、必ずしも一生飲み続けなければならないわけではありません。
服用期間の目安は、患者様お一人おひとりの病状やリスク、生活習慣の改善状況によって異なります。
また、脂質異常症の原因は、家族性高コレステロール血症など遺伝的な要因を除き、食生活の偏りや運動不足、喫煙、アルコールの過剰摂取、他の疾患(糖尿病や肥満など)だといわれています。
治療の基本は生活習慣の見直しであり、薬を服用している間も食事・運動・減量・禁煙といった取り組みが欠かせません。こうした改善が進めば、薬の減量や将来的な服薬中止につながる可能性もあります。
重要なポイントとして、血液検査の結果、コレステロール値が改善しても自己判断で服用を中止しないでください。
事例をあげると、フランスの研究では、75歳以上の高齢者が予防のために服用していたスタチンを中止した場合と、継続した場合で比べると、中止した時の方が心血管イベントによる入院リスクが増加したことがわかっています。(文献5)
脂質異常症の薬に関するお悩み事はためらわずに医師へご相談ください
ここまで脂質異常症と薬の治療について紹介しました。
コレステロールの数値や薬について、疑問や不安が生まれるのは当然のことです。
脂質異常症は、放置すると心筋梗塞や脳卒中といった重大な病気につながる可能性があるため、生活習慣の改善が非常に重要です。
一方で、薬による治療も大切です。LDL(悪玉)コレステロールを下げる薬、中性脂肪を下げる薬など、薬によって効果や特徴は異なりますが、医師は患者様を診断し処方する薬を選定します。
飲み合わせによってはさらに悪化する可能性もあるため、事前に医師にどのような薬を服用しているか伝え、副作用が起きるような場合も医師に早く相談しましょう。
脂質異常症の治療は、一人で抱え込むものではありません。
不安を抱えたまま治療を続けるのは精神的な負担にもなりますので、小さなことでもためらわず、医師に相談しましょう。
参考文献
(文献1)
動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2022年版|一般社団法人日本動脈硬化学会
(文献2)
レパーサ皮下注140 mgペン 添付文書|PMDA
(文献3)
高コレステロール血症治療薬「ベムペド酸」製造販売承認申請について|大塚製薬
(文献4)
薬物間相互作用―グレープフルーツジュースとスタチン|日本臨床薬理学会誌
(文献5)
Statin discontinuation and cardiovascular events in 75-year-olds|European Heart Journal
(文献6)
Incidence of hospitalized rhabdomyolysis with statin-fibrate therapy|PubMed