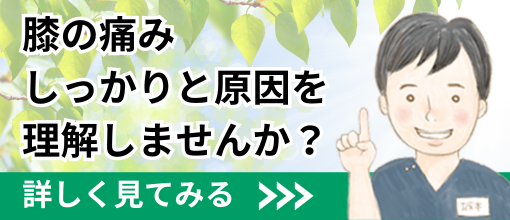-
- ひざ関節
- お皿付近に違和感
- 膝部、その他疾患
「膝が最近、ミシミシ・ジャリジャリと音がする」 「膝に聞き慣れない音がするのに痛くないのはなぜ?」 膝を曲げると音が鳴るのに、痛みを感じないことはありませんか。実際、音は気になるものの、痛みを感じないので医療機関を受診するほどではないと考える人も少なくありません。 しかし、ミシミシ・ジャリジャリという関節音は、筋肉や軟骨に変化が生じているサインの可能性があります。 関節の動きに伴う音は、加齢や筋力低下、姿勢の崩れ、軟骨のわずかな変化など、いくつかの要因が関係します。 本記事では、現役医師が膝がミシミシ・ジャリジャリする原因・治し方を解説し、考えられる疾患についても紹介します。 記事の最後には、膝のミシミシ・ジャリジャリに関するよくある質問についてまとめておりますので、ぜひ最後までご覧ください。 なお、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。 気になる症状や再生医療について詳しく知りたい方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。 膝がミシミシ・ジャリジャリするのに痛くない原因 原因 詳細 関節内の気泡や摩擦音によるもの 関節内に発生した気泡がはじける音や軟部組織同士がこすれる音 関節軟骨の擦り減りはじめによるわずかな変化 軟骨の軽度の摩耗による骨同士の接触や動きの乱れ 運動不足や筋力低下による関節の不安定性 大腿四頭筋などの筋力低下による関節のぐらつきやズレ 膝を動かしたときの音は、必ずしも異常とは限りません。違和感がなくても、関節内で軟骨や靭帯、筋肉にわずかなズレが生じている可能性があります。関節内の気泡が弾ける音や、筋肉・腱が骨にこすれる音も原因のひとつです。 加齢による軟骨の変化や筋力低下も関節の安定性を低下させ、音の原因になります。こうした現象は、日常生活に支障がなければ経過観察で問題ありません。しかし、このような音が続く、または違和感が強くなる場合には、早急に医療機関を受診しましょう。 関節内の気泡や摩擦音によるもの 内容 詳細 関節内の気泡(ガス)がはじける音 関節内の滑液に溶けている窒素や二酸化炭素が、膝の動きで気泡となり、破裂することで発生する「ポキッ」「パチッ」とした音 靭帯や腱が骨の突起を越える際の摩擦音 膝の曲げ伸ばし時に靭帯や腱が骨の出っ張りに引っかかり、動きとともに「ひっかかる・戻る」を繰り返すことで生じる摩擦音 違和感・腫れ・可動制限がなければ病的でないことが多い 生理的関節音であり、違和感や腫れ、動きの制限を伴わなければ日常的現象で経過観察が基本 膝から聞こえる音の中には、キャビテーションと呼ばれる関節内の気泡がはじけることで生じるものがあります。膝を曲げ伸ばしたときに関節内の圧力が変化し、一時的にできた気泡が破裂して、ポキポキ・ミシミシといった音が出ることがあります。 また、関節内の組織同士がこすれ合って摩擦音がすることもあり、これらの音は病気とは限らず、一時的な現象であるケースが多いです。通常であれば、心配いりません。ただし、音が出る頻度の増加や違和感、腫れなど他の症状を伴う場合は、早めに医療機関を受診しましょう。 関節軟骨の擦り減りはじめによるわずかな変化 中高年になると、膝などの関節で軟骨が徐々にすり減り始めます。初期段階では、ミシミシ・ジャリジャリといった異音や違和感のみが現れることがあります。 関節軟骨は、骨同士の動きを滑らかに保つクッションのような役割を担う組織です。加齢や日常の負荷により、軟骨表面がざらつくと、関節の動きに摩擦が生じ、異音の原因になります。軟骨には神経がないため、摩耗してもすぐに症状が出るとは限りません。 こうした異音は見過ごされがちですが、進行すると軟骨の消耗が進み、違和感・腫れ・可動域制限などの症状を引き起こすおそれがあります。 変形性膝関節症などの疾患につながる可能性もあります。そのため、早期対応が重要です。不安がある場合は、整形外科での診察を受け、関節の状態を確認することが推奨されます。 運動不足や筋力低下による関節の不安定性 加齢や運動不足でこれらの筋力が低下すると、関節の安定性が損なわれ、動作時にわずかなズレや摩擦が生じやすくなります。 とくに大腿四頭筋が弱くなると、膝蓋骨(膝のお皿)の動きが不安定になり、骨同士の摩擦によって、ミシミシ・ジャリジャリといった異音が起こりやすくなります。また、筋力の低下は関節を不安定にし、関節内に気泡が生じる一因です。 高齢になると、加齢による筋力の低下(ダイナペニア)が進行し、運動習慣がなくても膝関節の不安定性が現れやすくなります。関節の安定を保つには、継続的な筋力トレーニングや歩行などで、関節周囲の筋肉を維持・強化することが有効です。 以下の記事では、膝がポキポキなる原因について詳しく解説しております。 膝がミシミシ・ジャリジャリの治し方 治し方 詳細 膝に負担をかけない生活習慣を整える 正しい姿勢の維持・体重管理・階段や正座を避ける生活上の工夫 筋トレとストレッチで膝の動きをなめらかに保つ 大腿四頭筋やハムストリングスの強化・関節の柔軟性維持 必要に応じてサポーターやインソールを取り入れる 膝への衝撃緩和・関節のズレ防止・歩行時の安定性向上 膝のミシミシ・ジャリジャリ音は、関節の軟骨のすり減りや筋力・柔軟性の低下が原因です。体重を適正に保ち、正しい姿勢で生活することが基本です。階段の昇降や正座を避け、膝に負担をかけない工夫しましょう。 また、大腿四頭筋やハムストリングスを鍛える筋トレやストレッチで関節を支える力を向上させることも大切です。必要に応じてサポーターやインソールを使用することで、膝への負担が軽減され、歩行も安定します。 膝に負担をかけない生活習慣を整える ポイント 詳細 日常動作や習慣の見直し 長時間の立ち仕事や座りっぱなし、不適切な姿勢、合わない靴の使用による膝への負担減少 体重管理 食事や運動による適正体重の維持による関節負担軽減 休息と活動のバランス 膝の使いすぎ・動かなさすぎを避け、筋力低下の予防 環境や動作の工夫 イスや机の高さ調整、正しい姿勢や歩行、急な動作や正座回避による膝への負荷軽減 膝がミシミシ・ジャリジャリする場合、生活習慣を整えることは非常に重要です。日常生活の中で不適切な姿勢や合わない靴の使用、長時間同じ姿勢を取ることは膝関節への負担を大きくします。 体重を適正に管理することも、膝への圧力を抑え、慢性的な摩耗や変形のリスク軽減につながります。また、膝の過剰な使用や不活動は筋力バランスの乱れを招き、関節への負荷を増大させる要因です。 イスや机の高さの調整や正しい動作の習慣化など、身近な生活環境を見直すことで、膝の異音の改善や将来的な関節疾患の予防が期待されます。 筋トレとストレッチで膝の動きをなめらかに保つ ポイント 詳細 膝周囲の筋肉が関節を支え、負担を和らげる 大腿四頭筋・ハムストリングス・お尻の筋肉の強化による膝の安定化 ストレッチによる動きのなめらかさ 筋肉や腱の柔軟性向上による関節内摩擦や引っかかりの予防 継続による将来的な膝トラブルの予防 変形性膝関節症などの進行抑制・関節機能の維持 膝の異音には、筋トレとストレッチによる筋肉強化と柔軟性向上が効果的です。太もも前や裏、臀部の筋肉を鍛えると、膝関節が安定し骨同士の摩擦が減ります。 ストレッチを加えることで膝回りの筋肉や腱の柔軟性が向上し、動作時の摩擦や引っかかりも生じにくくなります。運動を継続することで、膝の健康を維持し、将来的な関節疾患の予防にもつながります。 必要に応じてサポーターやインソールを取り入れる ポイント 詳細 膝関節の安定性向上 サポーター装着による関節のぐらつき防止と動作時の安定確保 膝への衝撃や負担の軽減 インソールによる衝撃吸収と荷重分散による膝負荷の軽減 関節の保温と血行促進 保温効果による血流促進と関節可動域の改善 違和感や不安感の緩和 圧迫と固定による膝感覚の安定化の向上 正しいサイズと使用方法の選択 自分に合った製品の選定と適切な装着による効果的使用 膝のミシミシ・ジャリジャリといった違和感に対しては、サポーターやインソールの活用が有効です。サポーターは関節を外側から支えることでぐらつきを安定させ、歩行や階段昇降など日常動作の負担軽減につながります。 インソールは足元から衝撃を吸収し、膝への力を分散する働きがあります。とくにO脚傾向や足裏のアーチが崩れている方に効果的です。また、サポーターには保温作用があり、血行を促進して関節の動きをなめらかにする働きもあります。 ただし、製品は自分に合ったサイズ・素材を選び、正しい装着方法で使用することが大切です。必要に応じて医師に相談しましょう。 膝がミシミシ・ジャリジャリするのに考えられる疾患 考えられる疾患 詳細 中高年に多い膝の構造的変化による疾患(変形性膝関節症・半月板損傷) 軟骨や半月板のすり減り・損傷による骨の接触やクッション機能低下 関節リウマチ 自己免疫反応による関節包の炎症と破壊・関節変形への進行 離断性骨軟骨炎 膝関節内の骨や軟骨の一部が剥がれることで生じる関節内の不安定性 膝のミシミシ・ジャリジャリ音は、変形性膝関節症や半月板損傷、関節リウマチ、離断性骨軟骨炎などが原因となることがあります。 いずれも進行すると痛みや変形を伴い、日常生活に支障をきたすため、早期に医療機関を受診することが重要です。 中高年に多い膝の構造的変化による疾患(変形性膝関節症・半月板損傷) 原因 詳細 変形性膝関節症(軟骨のすり減り) 加齢による軟骨の摩耗と滑らかな動きの低下、骨同士の直接接触による異音発生 半月板の変性・損傷 加齢による半月板の摩耗や亀裂、膝の曲げ伸ばし時のクリック音やゴリゴリ音の発生 中高年に多い膝の異音は、加齢や負荷による軟骨や半月板の摩耗により、骨同士がこすれ合うことが原因です。 また半月板が傷つくと、膝の動きで引っかかりや異音が出やすくなります。初期は痛みが目立たず、音や違和感だけしか現れないケースも多いですが、放置すると進行しやすいため、異音が長引く場合は早めに医療機関へ相談することが重要です。 以下の記事では、構造的変化による疾患について詳しく解説しています。 【関連記事】 変形性膝関節症の治療は早期発見が鍵!初期症状を見逃さないために 半月板損傷でやってはいけないこと7選!放置するリスクや注意点について医師が解説 関節リウマチ 膝がミシミシ・ジャリジャリと鳴る原因のひとつに、関節リウマチが考えられます。関節リウマチは、自己免疫の異常によって関節内に炎症が起こる疾患で、膝を含む複数の関節に症状が現れるのが特徴です。 炎症が続くと軟骨や骨が傷み、関節の動きがスムーズでなくなり、摩擦音や違和感が生じることがあります。初期には音や違和感のみで、腫れが目立たないこともあります。 左右の関節にこわばりが出る、朝の動き始めがつらいといった症状がある場合は、早急に医療機関を受診しましょう。 以下の記事では、関節リウマチについて詳しく解説しています。 【関連記事】 膝の関節炎とリウマチの違いとは?症状と治療法などを現役医師が解説 関節リウマチの原因を医師が解説|ストレス・飲酒・性格との関係性も紹介 離断性骨軟骨炎 離断性骨軟骨炎は、膝関節内で軟骨や骨の一部がはがれ、関節内で動くことで異音や違和感が生じる疾患です。成長期の若い人に多く、初期は軽い違和感だけのこともあります。 しかし、進行するとミシミシ・ジャリジャリといった音や引っかかり、膝が動かなくなることもあります。放置すると軟骨片が関節内を遊離し、関節のロッキングや変形を引き起こすおそれがあるため、早急に医療機関を受診することが大切です。 以下の記事では、離断性骨軟骨炎について詳しく解説しています。 【関連記事】 離断性骨軟骨炎とは?主な原因や症状、治療法について解説 離断性骨軟骨炎の完治期間は?リハビリの重要性や再発予防法を解説 膝のミシミシ・ジャリジャリ音が続くなら早めに受診しよう 膝の異音が一時的なものであれば、治療は不要であるケースがほとんどです。しかし、数週間以上続く場合や頻度が増えてきた場合は、関節や軟骨に変化が起きている可能性があります。 とくに中高年では、軟骨のすり減りや炎症性疾患が背景にあることも少なくありません。音に加えて動きにくさや腫れを感じるようであれば、当院「リペアセルクリニック」へご相談ください。 当院では、膝のミシミシ・ジャリジャリ音から起こりうる関節形の疾患に対して、再生医療を選択肢の一つとしてご案内しています。再生医療は、膝の損傷した軟骨や組織の修復を促す治療法で、自己修復力を活かして、違和感の軽減や機能回復を目指します。 ご質問やご相談は、「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」で受け付けておりますので、お気軽にお申し付けください。 膝のミシミシ・ジャリジャリに関するよくある質問 膝に音がするのは一時的なものですか?自然に治ることもありますか? 膝の音が「ポキッ」「パキッ」と高く、違和感がなければ一時的な関節内の気泡によるもので、自然に治ることが多いです。 ただし、ミシミシ・ジャリジャリといった低音が続く場合は、軟骨や半月板の損傷など関節の変化が疑われます。気になる症状が続くときは整形外科での検査をおすすめします。 膝の異音は年齢のせいですか?若い人でも起こりますか? 膝の異音は年齢だけが原因ではなく、若い人にも起こることがあります。加齢による軟骨の摩耗や関節の変形はリスクですが、運動歴、体重、筋力のバランス、遺伝なども原因です。 とくにスポーツをしている若年層では、靭帯や腱の動き、成長による影響で異音が出ることもあります。一時的な音で違和感がなければ心配ないことも多いです。しかし、違和感や音が続く場合は、整形外科での受診をおすすめします。 膝ミシミシ・ジャリジャリするときはストレッチやスクワットは控えるべきでしょうか? 膝にミシミシ・ジャリジャリといった音や違和感がある場合は、無理のない範囲でストレッチを行うと関節の動きがスムーズになりやすく、太ももや膝裏の柔軟性向上に役立ちます。 一方で、スクワットは膝への負荷が大きく状態を悪化させることがあるため、控えましょう。代わりに椅子に座って足を伸ばす運動など、膝に負担をかけにくい方法がおすすめです。腫れや違和感が強い場合は早めに医療機関を受診しましょう。
2025.07.31 -
- ひざ関節
- お皿付近に違和感
- 膝部、その他疾患
「膝を捻挫して歩けるけど痛い」という方の中には、病院に行くべきか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。 結論、膝の捻挫後に歩けるけど痛い場合は、靭帯断裂など重症な可能性があります。 軽症な場合は適切な応急処置とセルフケアで早期に回復するケースもありますが、治療を受けずに放置してしまうと重症化するリスクがあります。 捻挫を放置することで、後遺症がでる場合や靭帯が完全に断裂して手術が必要になる可能性も少なくありません。 当院リペアセルクリニックでは、捻挫による痛みだけでなく「少し違和感がある」など些細なことでも無料でご相談を承っています。 「捻挫の痛みを早く治したい」「後遺症や手術は避けたい」という方は、ご自身の症状に適した治療法についてご相談ください。 ▼捻挫の早期回復に再生医療が注目 (こちらをクリックして)無料で相談しよう \お問い合わせはこちらから/ 0120-706-313 (受付時間:9:00〜18:00) 膝を捻挫して歩けるけど痛いときに考えられる原因 膝を捻挫して歩けるけど痛いときに考えられる原因として、捻挫ではなく靭帯断裂などの重症な可能性があります。 捻挫とは、膝の曲げ伸ばしを行うための「関節包」や「靭帯」が損傷してしまう外傷のことです。 しかし、捻挫と診断されるのは軽症の場合に限り、損傷度合いが強く、靭帯が完全に切れている場合「靭帯断裂」という診断になります。 捻挫だと思って痛みを我慢して放置していたら靭帯断裂だったというケースも少なくありません。 受傷後に歩行できる場合でも、適切な治療を受けなければ関節が不安定になったり、再発しやすくなる(クセがつく)可能性があります。 近年の治療では、捻挫や靭帯断裂の早期回復が目指せる治療法として、再生医療による治療が注目されています。 「膝の痛みを早く治したい」「再発のクセがつく前に治したい」という方は、ぜひお問い合わせください。 \無料相談・お問い合わせはこちら/ 0120-706-313 (受付時間:9:00〜18:00) 膝を捻挫して歩けるけど痛いときの症状 膝を捻挫すると主に以下のような症状が現れます。 受傷直後の強い痛み 内出血とむくみの発生 膝全体の腫れ 受傷直後は痛みが強いですが、機能は比較的保たれている事が多く、その後も痛みを我慢して普通に生活できる方もいます。 ですが、徐々に内出血とむくみが出てきて、膝全体が腫れてきます。 膝全体が腫れると、膝を動かす際に痛みが生じます。また、左右を比較すると動かせる範囲が狭くなる「可動域制限」がでてきます。 ひどい場合は痛みで足が地面につかないケースも。 ただし、「捻挫」であれば一時的な症状なので、数日で改善するケースが多いです。 いつまでたっても痛みが引かない、腫れがひどくなってきたという場合は「靭帯損傷」のレベルまで症状が悪化している可能性があります。注意しましょう。 以下の記事では、靭帯損傷の原因や治療法について解説しています。ぜひ参考にしてください。 「歩けるけど痛い」「膝がぐらぐらして不安定」は要注意! 「ただひねっただけだと思って様子を見ていたら、実は靭帯損傷だった。」という事例は意外に多いです。 膝には主に4つの重要な靭帯があります。 前後方向の安定性を保つ前十字靭帯・後十字靭帯、左右方向の安定性を保つ内側側副靭帯・外側側副靭帯です。これらはバスケットボールやサッカーなどのスポーツはもちろん、転倒などでも痛めるケースがあります。 「歩けるけれども痛みが続く」や「膝がぐらぐらして不安定」と感じるときは、これらの靭帯を痛めている可能性があります。 また、靭帯を痛めていると関節の中に血が溜まることが多いです。 「もしかしたら当てはまるかも」と思った場合は、自己判断せずに病院を受診しましょう。 歩けるけど痛い 膝がぐらぐらして不安定 「靭帯」や「半月板」を損傷している恐れがあります。自己判断はせず、病院を受診しましょう! また、膝のクッションや安定性を保つ役割をしている組織に半月板が存在します。半月板は左右に1つずつありますが、こちらも膝をひねって痛めた際に損傷してしまうことがあります。 年を取ると徐々にすり減って切れやすくなります。特に、高齢の方はバスの乗り降りなど少しの段差を下りただけでも半月板が切れてしまう恐れも。「ブチッ」という感覚を伴うのが特徴的です。半月板損傷は検査しないと判明せず、病院でMRIなどを撮影しなければなりません。 一口に「捻挫」と言っても、紹介したような損傷が隠れている可能性もあります。ちょっとでも違和感があるなら、病院に受診するようにしてみてください。 膝を捻挫して歩けるけど痛いときの対処法 膝をひねってしまった受傷直後は、RICE処置を行いましょう。 Rest:安静 Ice:冷やす Compression:圧迫 Elevation:挙上 スポーツはすぐに中止し、歩行もできればしない方が望ましいです。氷や保冷材などを使って膝を冷やしながら、包帯などがあれば圧迫してください。 また、寝ているときは心臓より高い位置に足をあげておくと、膝が腫れてくるのを予防できます。 しかし、自己判断での応急処置は症状を悪化させてしまうリスクもあるため、症状に適した応急処置について確認することが重要です。 当院リペアセルクリニックでも捻挫の症状に適した対処法や治療法についてご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。 膝を捻挫して歩けるけど痛いときに受けるべき診断方法は? 問診と身体診察で、どのような怪我が疑わしいのか予想がつく場合もあります。 基本的には、まずレントゲンで骨折がないかどうか確認します。レントゲンだけではわからない場合は、骨をより詳しく見るためにCT検査を行うこともあります。その後、靭帯損傷や半月板損傷が疑われる場合にはMRI撮影を実施します。 レントゲン撮影 CT検査 MRI撮影 検査の結果、手術が必要な靭帯損傷などの疑いがなければ保存療法になります。 損傷した関節包や靱帯が修復する期間は、通常3週間前後です。この期間は激しい運動や重労働などはせず、安静にしていましょう。安静を保つ目的で、一定期間添木や松葉杖・サポーターなどの使用を指定するケースもあります。 痛みが強い場合は、飲み薬や湿布を処方する場合もあります。ただし、鎮痛薬は痛みを止めるだけで治ったわけではないので、一番大事なのは膝の安静です。 そのまま通常の生活に戻れる場合は、晴れて治療終了です。しかしながら、安静にしていた影響で筋力が低下したり、動きが悪くなることがあります。 その際はリハビリテーションを実施して膝関節の機能を戻すとともに、次の怪我の予防も同時に行うことが大切です。 膝を捻挫して歩けるけど痛いときによくある質問 膝を捻挫して歩けるけど痛いときによくある質問をQ&A形式で紹介します。 膝関節を含む捻挫の予防法や対処法はありますか? 運動をされる場合は、適切なストレッチやウォーミングアップが大切です。筋肉の柔軟性を保ち、温めてしっかりと動かせる状態にしてから運動を始めることで、関節に負担がかかりにくくなります。 また、普段から下肢の筋力が衰えないように意識してトレーニングをしておくことも重要です。さらに、自分の足に合った靴を選ぶことも転倒の予防になります。 膝関節捻挫を引き起こしてからスポーツに復帰できる目安は? スポーツ復帰には、痛みがなくなっていることが大前提です。痛みがあるまま再開すると、膝をさらに痛めたり、かばって別の部位の怪我を引き起こしかねません。 一般的に、通常の捻挫であれば2〜3週間で痛みが落ち着くので、軽い運動から再開するように指導します。 膝に過度な負担をかけないよう、サポーターなどの補助具を使用することも勧められます。 膝関節捻挫は何科を受診すればよいですか? 膝関節捻挫は外傷により発症します。よって、整形外科を受診しましょう。 とはいえ、受傷した時間が深夜や早朝だと、最寄りの整形外科医が受診の時間外の場合もあるでしょう。このような場合は、整形外科のある最寄りの大きな病院に問い合わせるか、厚生労働省が推奨している「♯7119」に電話で相談してみてください。 あきらかに緊急性がない場合は当院へご相談ください。国内で10,000以上ある実績を元に、親身に対応いたします。 膝を捻挫して歩けるけど痛いときは重症の可能性あり!早めに医療機関を受診しよう この記事では、膝関節捻挫について解説しました。 膝関節捻挫は直接的・間接的な原因から発症し、受傷直後に強い痛みを伴います。病院を受診せずに痛みを我慢しその後も様子をみてしまう方も多いのが現状です。しかし、裏側に潜む靭帯や半月板の損傷も考えられます。 自己判断で無理せず、最寄りの医療機関を受診するよう心がけましょう。 従来の治療では、症状に応じて約4〜8週間の固定期間が必要ですが、先端医療である再生医療による治療で痛み症状の早期改善が期待できます。 捻挫の痛みを早く治したい方は、この機会に再生医療がどのような治療をするのかお問い合わせください。 ▼捻挫の早期回復に再生医療が注目 (こちらをクリックして)無料で相談しよう \お問い合わせはこちらから/ 0120-706-313 (受付時間:9:00〜18:00)
2023.08.28 -
- 関節リウマチ
- 内科疾患
- お皿付近に違和感
「関節リウマチになったらやってはいけないことはある?」 「関節リウマチで食べてはいけないものは?」 関節リウマチの症状を改善したくて、日常生活で何に気をつければ良いか知りたいと考えていませんか? 痛みやこわばりでつらい思いをしないで済むよう、できることがあるならやっておきたいですよね。 結論、関節リウマチとうまく付き合うために日常生活の中で避けてほしいことがあります。 本記事では、関節リウマチの患者様が避けるべき10項目を紹介します。 本記事を参考にしていただき関節リウマチの症状軽減を目指すとともに、日々の生活を快適に過ごせるように意識してみてください。 関節リウマチのしてはいけない10項目とは? 関節リウマチの患者様がしてはいけない10項目は以下の通りです。 症状を悪化させないために、紹介した10項目を避けるよう心がけてみてください。 ①砂糖や加工食品の摂りすぎ https://youtu.be/4LeBKWd3w2s?si=qFEX9A8IULDRFirM 関節リウマチの症状を悪化させる可能性がある食べものとして、以下があります。 砂糖入りの飲食物 赤身の肉 加工食品 また、不飽和脂肪酸のn-3系とn-6系の摂取するバランスが崩れることも関節リウマチの痛みと関わっているので、バランスの良い食事を意識することが大切※です。 ※出典:PMC PubMed Central 以下に根拠となる研究をご紹介します。 砂糖入りの飲食物 砂糖入りの飲みものは、以下2つの研究から関節リウマチの悪化因子であり、発症リスクを高める因子でもあることが報告されています。同時にデザートもリウマチの悪化因子だと報告があるので、注意が必要です。 217人の関節リウマチ患者を対象とした、自己申告による研究があります。20種類の食品のうち、最も関節リウマチの症状が悪化したと報告されたのは砂糖入りの炭酸飲料とデザートでした。 ※文献1:PMC PubMed Central アメリカの約19万人の女性を対象とした大規模な疫学調査では、砂糖入り炭酸飲料と関節リウマチの発症リスクの関連性を評価しています。毎日1缶程度以上の砂糖入り炭酸飲料を摂取している人は、全く飲まない、あるいは毎月1缶未満程度しか摂取しない人に比べ、リウマチ因子陽性の関節リウマチを発症するリスクが63%高いことがわかりました。 ※文献2:PMC PubMed Central 赤身の肉 関節リウマチを悪化させる可能性がある食べものとして赤身肉の報告があります。 217人の関節リウマチを有する患者を対象とした研究において「赤身肉を食べると関節リウマチの症状が悪化する」と報告した人の割合は、20種類の食品の中では高い方でした。 ※文献1:PMC PubMed Central 関節リウマチの新規患者88名とそうでない176名を比較した研究では、患者群の方が赤身肉の摂取量が高い結果でした。 ※文献3:PubMed 加工食品 加工食品の摂取量が多いと、関節リウマチ患者の心血管系疾患のリスクが高くなる可能性が報告されています。 56人の関節リウマチ患者の摂取している食品を加工レベル別に評価した結果、糖分・塩分・脂肪を多く超加工食品の摂取量が多いほど患者の心疾患リスクが上がりました。 ※文献4:SPRINGER NATURE Link 関節リウマチと食べものについてはさまざまな研究が行われていますが、いずれも摂取量の多いことが問題になっています。 関節リウマチの症状を悪化させないためにも、同じものを極端に食べすぎず、バランスの良い食事を心がけましょう。 ②激しい運動 痛みが強く出ているときは、激しい運動を避けるべきです。炎症が起きている関節に負担がかかることで、症状が悪化する場合があります。 ただし、関節の動きを良くするためにも適度な運動は推奨されています。治療を続ける中で痛みがコントロールできている場合は、適度に体を動かし、手足の筋力や関節の可動域(動かせる範囲)を維持しましょう。 関節リウマチは、関節だけでなく全身に症状が出やすい病気です。運動は無理のない範囲で行い、疲れたら休憩や昼寝など適宜休息をとりましょう。 ③体や関節を冷やす 体や関節を冷やしすぎると関節痛が強くなったり、関節が動かしづらくなったりすることがあります。 寒い季節はもちろん、夏も冷房の風が直接あたるのを避け、長袖や長ズボン、ブランケットなどで関節部位の保温を心がけましょう。温まって関節の血液の流れがよくなると、こわばりや痛みをやわらげる効果が期待できます。 ただし、関節が腫れて熱感があるときは炎症が起きている可能性もあるので、温めないようにしましょう。 ④首に負担をかける行動 関節リウマチが進行すると頚椎の炎症を起こし、頸部痛や頸部の運動制限をきたします。 過度に首に負担がかかる行動をすると、頚椎の亜脱臼を起こして脊髄神経を圧迫し、四肢の痺れや麻痺、呼吸障害が起こる可能性があるのです。 首に負担がかかる動作の一つに起居動作が挙げられます。朝はできる限りベッドから急に立ち上がらず、一度腰かけてから立つ習慣をつけましょう。朝は不用意に首を回さないようにし、首の運動は医師の診察を受けた上で行うことが重要です。 ⑤肥満 肥満だと膝や股関節などの主要な関節に過剰な負担がかかり、炎症が悪化する可能性があります。体重管理を適切に行うことで関節への負担を軽減し、症状の悪化を防ぐよう心がけましょう。 体重管理の観点からバランスの取れた食事と適度な運動が重要です。 ⑥同じ姿勢を長時間とる 同じ姿勢を長時間保つのは同じ部位に負担をかけてしまいます。定期的に姿勢を変えて、関節に負担がかかりすぎないようにしましょう。 特にデスクワークや座りっぱなしの仕事では、適度に休憩をとったり、ストレッチを行ったりすることが重要です。 ⑦重いものを持つ 関節リウマチの好発部位は、手指や手首の関節です。重いものを持つと過剰な負担をかけ、炎症や痛みを悪化させる原因となります。 日常生活では重いものを持つ機会をできるだけ避け、必要な場合は道具などを利用して負担を軽減しましょう。 症状があるとうまくものが持てないこともあるので、周囲のサポートを得るのも大切です。 ⑧正座をする 正座は膝関節に大きな負担がかかるので可能な限り避けましょう。とくに、正座を長時間続けるのは、膝や足首の可動域が制限され血行不良を招きやすいので、関節の痛みや腫れを引き起こす可能性があります。 正座を避けて椅子に座る、膝を伸ばして楽な姿勢をとるようにしましょう。 関節リウマチによる膝の関節炎について詳しく知りたい人は以下の記事もご覧ください。 ⑨喫煙をする 関節リウマチの患者様は、禁煙が勧められます。喫煙は関節リウマチの症状を悪化させるだけでなく、病気を進行させる要因になり、死亡リスクが上がる可能性も報告されています。 とくに死亡リスクに関しては、リウマチの診断後に禁煙した人は喫煙を継続した人よりも死亡リスクが低くなると報告されていました。(文献6) 今更だと思わずに、早めに禁煙に取り組みましょう。 関節リウマチと喫煙の関係性を詳しく知りたい人は以下の記事もご覧ください。 ⑩ストレスを溜める 手がこわばってものがつかみにくいなど、関節リウマチの患者様は日常生活の不自由さからストレスを感じやすいです。ストレスが溜まることで自律神経の乱れやメンタルに不調をきたしてしまうことから、健康的な生活から遠ざかる可能性があります。 リラクゼーションや適度な運動を取り入れて、ストレスを溜めないことが、関節リウマチの治療を後押ししてくれます。 関節リウマチかも?と思ったら早めに受診しよう 関節リウマチかもしれないと思ったら、早めに整形外科を受診しましょう。 関節リウマチは、進行すると関節の変形や機能障害を引き起こし、日常生活に支障をきたす病気です。始めは軽い痛みや腫れであっても、時間が経つにつれて悪化し、治療が遅れると回復しづらくなります。 関節リウマチを疑う症状として、以下のようなものがあります。 服のボタンが外しづらい びんの蓋が閉められない 床に落としたものが拾えない 朝起きたときにベッドから起き上がれない 早期に受診し適切な治療を開始すれば、薬物療法やリハビリテーションで関節の損傷を抑えつつ症状をコントロールすることが可能です。 もとに戻らないほど関節が変形してしまう前に、早めに整形外科へご相談ください。 関節リウマチではない膝の痛みは変形性膝関節症かも?詳しく知りたい人は以下の記事もご覧ください。 関節リウマチに関するよくある質問 関節リウマチに関するよくある質問をまとめて紹介します。 関節リウマチとはどんな症状ですか? 関節リウマチの症状には、関節の動かし始めがスムーズにいかない「こわばり」や腫れ・痛みなどがあります。 関節リウマチは免疫機能の異常によって骨や軟骨・関節の破壊が起こることが原因とされています。万が一「関節リウマチかも?」と思ったら早めに受診しましょう。 関節リウマチの症状について詳しく知りたい人は以下の記事もご覧ください。 関節リウマチは生物学的製剤で本当に治せますか? 生物学的製剤で効果があれば、休薬しても症状が落ち着いている状態を目指せます。 関節リウマチの原因である免疫異常の改善が期待できる上、炎症を抑える効果もあるため、進行を抑えながら症状をコントロールできます。 関節リウマチで使われる生物学的製剤について詳しく知りたい人は以下の記事もご覧ください。 関節リウマチになりやすい性格はありますか? 関節リウマチになりやすい性格は、ありません。 ただ、我慢強い性格の人は治療開始が遅れたり、神経質でストレスを感じやすい人は治療が難航したりする可能性があります。違和感があったら早めに受診し、不安があれば専門医に相談しましょう。 再生医療の幹細胞治療に関する詳細は以下をご覧下さい 関節リウマチのしてはいけない10項目を守ろう 関節リウマチの患者様には、してはいけない10項目を避けて、健康的な食事とライフスタイルを心がけましょう。 重症化すると、普段の生活もままならなくなってしまう可能性があります。 治療と並行して関節の負担を減らし、症状をコントロールできるよう、普段の生活から意識してみてください。 万が一、関節リウマチの治療をしていても膝の痛みがよくならない場合は、他の疾患が隠れているかもしれません。 再生医療が適応になる可能性がありますので、お困りの場合は当院へご相談ください。
2022.08.19 -
- 関節リウマチ
- 内科疾患
- お皿付近に違和感
関節リウマチは、関節の痛みや腫れを引き起こす慢性疾患で、日常生活に大きな影響を及ぼす場合もあります。 近年では、関節リウマチの治療法も進化し、とくに注射による薬物療法として高い効果が期待できる「生物学的製剤」の使用が広まりつつあります。 一方で、副作用についても気になるところです。 従来薬と比べてどう違うのか、どんな点に注意すべきなのかを知っておくことはとても大切です。 今回は、関節リウマチの注射治療における副作用や生物学的製剤と従来薬との違いについてわかりやすく解説していきます。 関節リウマチの注射治療の役割と主な副作用 関節リウマチは、免疫の異常によって関節が慢性的に炎症を起こす病気です。 放っておくと関節の変形や機能障害を引き起こし、日常生活にも支障をきたす可能性があります。 そのため、早期の治療と炎症のコントロールが非常に重要とされています。 関節リウマチの治療には、内服薬に加えて注射薬が使われるケースが増えてきました。 注射治療が選ばれる主な理由には、以下のような点があります。 即効性や効果の持続時間が期待できる 内服薬に比べて消化器への負担が少ない 自己注射が可能な薬もあり、通院の負担を減らせる とくに重症例や、内服薬だけでは効果が不十分な場合には、生物学的製剤やステロイド注射による治療が効果的な選択肢となります。 生物学的製剤は、免疫システムの特定の部分だけをターゲットにして炎症を抑える先進的な薬剤です。 一方、ステロイド注射は急性の炎症を素早く鎮める目的で使用され、特に痛みの強い関節に直接注入されることが多いのが特徴です。 こうした注射薬は高い治療効果が期待できる反面、副作用にも注意が必要です。 たとえば、注射部位に腫れや赤みが出ることがあり、発熱や頭痛、倦怠感などの全身症状が出る場合もあります。 副作用の出方は個人差があり、すべての人に起こるわけではありませんが、使用前には医師と十分に相談し、定期的な経過観察が欠かせません。 関節リウマチの治療で使われる生物学的薬剤とは? 関節リウマチの治療は、主に抗リウマチ薬などの従来薬が中心でしたが、近年では「生物学的製剤」と呼ばれる新しい治療薬が広く使われるようになってきました。 本章では、以下3つの項目について解説します。 生物学的製剤と従来薬との違い 生物学的製剤の種類 どのように体に作用するのか 生物学的製剤と従来薬との違い 従来薬は、免疫全体の働きを広く抑制して炎症をコントロールする薬で、内服薬を中心とした治療方法のため、効果の発現に時間がかかる傾向があります。 一方、生物学的製剤は、炎症に関与する特定の物質(サイトカイン)や細胞にピンポイントで作用するため、即効性があり、より高い効果が期待されます。 しかし、生物学的製剤は注射や点滴による投与が必要で、治療費も高額になる傾向があります。 そのため、まずは従来薬で治療を開始し、効果が不十分な場合に生物学的製剤へ切り替えるという流れが一般的です。 生物学的製剤の種類 関節リウマチの注射治療に使われる生物学的製剤には、いくつかのタイプがあり、それぞれ炎症の原因となる免疫の働きに対して、異なるアプローチで作用します。 代表的な生物学的製剤は以下の4つです。 抗TNFα抗体(インフリキシマブ、エタネルセプト、アダリムマブなど) 炎症を引き起こす「TNF-α」という物質をブロックし、関節の腫れや痛みを抑えます。 IL-6阻害薬(トシリズマブなど) 炎症に関与する「IL-6」というサイトカインの働きを抑制します。 T細胞共刺激阻害薬(アバタセプトなど) 免疫細胞同士の過剰な活性化をブロックし、炎症の連鎖を断ちます。 B細胞抑制薬(リツキシマブなど) 抗体を産生するB細胞の働きを抑えて免疫反応を和らげます。 それぞれの製剤には特徴や適応があり、患者様の病状や体質、他の合併症の有無などに応じて使い分けられます。 どのように体に作用するのか 生物学的製剤は、関節リウマチの炎症に関わる免疫反応の一部を「選択的に抑える」ことで効果を発揮します。 たとえば、関節内で過剰に分泌されるサイトカインに結合してその作用をブロックしたり、特定の免疫細胞の働きをコントロールすることで、関節の腫れや痛みを軽減します。 このような選択的な作用により、高い治療効果が得られる一方、免疫の一部を抑えるために感染症への注意が必要です。 治療を受ける際は、定期的な血液検査や医師の管理のもと、安全性にも十分配慮した継続的なフォローが行われます。 \まずは当院にお問い合わせください/ 関節リウマチ注射の副作用と生物学的製剤の注意点について 関節リウマチの注射治療として使用される生物学的製剤は、効果が高い反面、副作用や注意すべき点もあります。 ここでは、注射治療にともなう副作用やリスクについて詳しく解説します。 関節リウマチ注射のよくある副作用 関節リウマチの注射治療で比較的よくみられる副作用には、以下のようなものがあります。 注射部位の反応(発赤、腫れ、かゆみ、痛みなど) 倦怠感や軽度の発熱 頭痛、吐き気、筋肉痛 これらの副作用は、多くの場合は一時的で、自然に治ることがほとんどです。 とくに皮下注射(薬液を皮膚と筋肉の間にある皮下組織に注入する方法)の生物学的製剤では、注射部位に炎症反応が出ることがありますが、冷やすなどの対処で落ち着くこともあります。 関節リウマチ注射のまれに起こる重篤な副作用 一方で、まれではありますが、注意が必要な重篤な副作用も存在します。 代表的なものは以下の4つです。 感染症のリスク増加(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹など) アレルギー反応(アナフィラキシー):急な呼吸困難や発疹、血圧低下などを伴うことがある 肝機能障害や血液異常(肝酵素の上昇、白血球や血小板の減少) 心不全の悪化や間質性肺炎の誘発(既往がある場合) 上記の副作用は頻度こそ低いものの、早期に対応することが重要です。 症状が出た場合は、自己判断で放置せず、必ず主治医に相談しましょう。 関節リウマチ注射の副作用が出やすいタイミングやリスク要因 副作用が出やすいタイミングとしては、投与開始直後や投与変更後の数回目までがとくに注意が必要です。 初回投与では、体が薬に慣れていないため、副作用が出やすくなる傾向があります。 また、以下のようなリスク要因がある場合、副作用の出現や重症化の可能性が高まります。 高齢者 免疫力が低下している人(糖尿病や慢性疾患がある場合など) 他の免疫抑制薬を併用している場合 感染症の既往がある、または現在感染している場合 肝機能や腎機能に問題がある場合 生物学的製剤は、免疫機能に直接働きかける薬のため、「副作用が出るかも」と事前に想定しておくことが大切です。 治療開始前には十分な検査や医師との相談を行い、使用中も定期的なモニタリングを続けることで、安全に治療を継続することができます。 \まずは当院にお問い合わせください/ 関節リウマチ注射の副作用に対する予防策と対処法 関節リウマチの注射治療には高い効果が期待できますが、副作用が心配という声も少なくありません。 副作用を防ぐため、治療前には血液検査や感染症の有無を確認する検査が行われます。 肝機能や腎機能のチェック、結核やB型肝炎などの検査を通して、安全に治療を始められるよう準備が整えられます。 注射後に、注射部位の赤みやかゆみ、軽い発熱などが出ることがありますが、多くは一時的なもので心配はいりません。 ただし、息苦しさや高熱、強い倦怠感などが出た場合は、副作用の可能性もあるため、早めに医師へ相談しましょう。 また、副作用が出やすいのは治療開始初期や、薬を変えた直後のため、体調の変化を記録し、気になる症状があれば遠慮せず医師に伝えることが大切です。 事前の検査と早めの対応によって、多くの副作用は予防・軽減できます。 正しい知識と備えで、安心して注射治療に取り組みましょう。 まとめ|関節リウマチ注射の効果と副作用を正しく理解して治療に臨もう 関節リウマチの注射治療は、症状の進行を抑え、関節の機能を保つために非常に有効な手段です。 生物学的製剤の登場により、これまでコントロールが難しかった症状にも対応できるようになってきました。 一方で、副作用のリスクがあることも事実です。 しかし、治療前の適切な検査や準備、治療中の体調管理によって、多くの副作用は予防・軽減できます。 また、万が一症状が現れた場合でも、早期に対応することで重症化を防ぐことが可能です。 大切なのは、注射治療の効果と副作用の両方を正しく理解し、自分の体と向き合いながら医師と協力して治療を進めることです。不安なことがあれば、一人で抱え込まず、医師に相談しましょう。 しっかりと情報を得て備えることで、安心して治療に臨み、日常生活の質を高める一歩につながります。
2022.02.25 -
- 関節リウマチ
- 内科疾患
- お皿付近に違和感
「関節リウマチはどんな初期症状が現れる?」 「簡単に判断できるチェックリストはない?」 関節リウマチとは、免疫の異常により関節の滑膜(かつまく:関節の内側を覆う膜)などに炎症が起きる病気です。典型的な初期症状には、朝の手指のこわばりや腫れなどがあります。 本記事では、関節リウマチの主な初期症状をはじめとして以下を解説します。 進行後の症状 似た初期症状が現れる病気 主な治療方法 なりやすい人 簡易的に関節リウマチかどうかを判断する際のチェックリストも記載しています。疑われる症状が現れている方は参考にしてください。 なお、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、さまざまな病気の治療に応用されている再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。 関節リウマチの痛みに悩んでいる方は、ぜひ一度公式LINEをご利用ください。 関節リウマチの主な初期症状【チェックリスト】 関節リウマチかどうかを判断する際、以下のチェックリストが参考になります。なお、アメリカリウマチ学会(1987年)の分類基準に基づいて作成しております。(文献1) 関節リウマチの初期症状のチェックリスト 朝起きて1時間以上続く手指のこわばり 関節の腫れが3箇所以上ある 手の関節が腫れている 左右対称に関節が腫れている 上記はあくまでも簡易的なチェックリストです。診断をするためには、血液検査やレントゲン検査が必要です。いくつか当てはまる方は医療機関で詳しい検査を受けてください。 ここからは、関節リウマチの主な初期症状について詳しく解説します。 朝のこわばり|手指が動かしにくい 関節リウマチの典型的な初期症状は朝の手指のこわばりです。 具体的には以下のような症状です。 朝起きた際に手指にこわばりがあり動かしにくい 動かしにくい状態が少なくとも30分以上続く こわばりにより「ぞうきんが絞りにくい」「物を握りにくい」といった症状も現れます。 関節の腫れ|手指に腫れぼったさがある 朝のこわばりの次に目立つのは、手指の関節の腫れです。明らかに腫れているのではなく「なんとなく腫れぼったい」状態で現れることもあります。 肘や膝、肩など大きな関節に腫れが出現する場合もあります。なお、実際には関節が腫れているのではなく、関節の周囲が腫れている状態です。 関節痛|手足の小さな関節に痛みが現れる 関節の腫れと同時に痛みが現れることもあります。痛みが現れる部位は、腫れが生じている手指や肘、膝、肩などの関節です。なお、関節リウマチはこわばりや腫れ、痛みなどの症状が左右対称に現れる特徴があります。 その他の初期症状は全身のだるさや微熱などです。疑われる症状が現れている場合は、早めに医療機関を受診してください。 関節リウマチの進行後の症状 関節リウマチが進行すると骨や軟骨が壊れてしまい関節の変形が起きます。近年では関節リウマチの発症後1~2年以内に関節破壊が進行するということがわかってきています。(文献2)つまり、関節リウマチは早期発見・早期治療が重要ということです。 ここからは、関節リウマチの進行後の症状について解説します。 関節の変形 関節リウマチが進行すると関節の変形が起きます。その結果、関節の動く範囲が狭くなってしまいます。 関節の変形には以下のようなものがあります。 起こりうる関節の変形 特徴 スワンネック 手指の第2関節が反って第1関節が内側に曲がった状態 ボタンホール 手指の第2関節が内側に曲がり第1関節が反った状態 外反母趾(がいはんぼし) 足の親指の付け根が外側に曲がり、足の親指が人差し指に乗り越えた状態 その他にも、肘の外側や腰骨の上部にしこりができることがあります。 関節以外の症状 関節以外の主な症状は以下のとおりです。 疲れやすさ 脱力感 食欲低下 体重減少 関節リウマチの合併症である間質性肺炎(肺が炎症により繊維化する病気)が生じると、息切れや空咳などの症状が現れます。 関節リウマチと似た初期症状が現れる病気 関節リウマチと似た初期症状が現れる主な病気は以下のとおりです。 乾癬性関節炎(かんせんせいかんせつえん) 全身性エリテマトーデス リウマチ性多発筋痛症 それぞれの病気について詳しく解説します。 乾癬性関節炎 乾癬とは、免疫が過剰になり皮膚に炎症が起きる病気です。乾癬性関節炎とは、この乾癬に関節炎が合併した病気です。はっきりとした発症の原因は不明ですが、肥満や血縁関係の関連性が報告されています。 関節リウマチと似ている症状は、手指の関節の痛みや腫れです。第2関節に炎症が多い関節リウマチに対して、乾癬性関節炎は第1関節も炎症が起きて痛みや腫れが現れます。 特徴的な症状は以下のとおりです。 症状 特徴 皮膚症状 ・皮膚に赤みや剥がれが起きる ・剥がれた皮膚の一部が残り白くなる 爪病変 ・爪のくぼみや腫れ、肥厚(ひこう:爪が分厚くなる) ・水虫のような見た目になる 全身性エリテマトーデス 全身性エリテマトーデスとは、全身に炎症症状が現れる自己免疫疾患です。発症の原因は、遺伝や感染症、紫外線などが関連していると報告があります。関節リウマチと似ている症状は、関節の痛みや腫れです。関節リウマチとは異なり骨や軟骨の破壊は起きません。 特徴的な症状は以下のとおりです。 症状 特徴 蝶形紅斑 (ちょうけいこうはん) ・鼻から両頬にかけて蝶の羽のように現れる発疹 ・目立つ赤色が特徴でかゆみはない 円板状ループス ・顔面や頭、耳たぶなど円盤状に現れる発疹 ・かゆみはなく経過に伴い白くカサカサした状態になる 日光を浴びるとこれらの症状が出現または悪化するおそれがあります。 リウマチ性多発筋痛症 リウマチ性多発筋痛症とは慢性の炎症性の病気です。発症の原因は不明で、50歳以降の中高年に発症する傾向です。 肩や上腕、腰部、背部などに以下のような症状が現れます。 ある日突然の朝のこわばり 筋肉の痛み 関節の動きの制限 「朝に肩が30分以上こわばる」など、関節リウマチの初期症状と似ている部分があります。しかし、リウマチ性多発筋痛症は、関節リウマチと異なり大きな筋肉にこわばりや痛みが現れます。 関節リウマチの治療方法 関節リウマチの主な治療方法は以下のとおりです。 生活指導 薬物療法 再生医療 それぞれの治療方法について詳しく解説します。 生活指導 関節リウマチの治療において安静は重要です。炎症の強い関節を動かすと、痛みや腫れが悪化するおそれがあるためです。また、関節リウマチは関節だけではなく全身を消耗する病気でもあります。 以下のように休息をとり関節と全身を休めてください。 夜間睡眠は十分にとる 昼間も疲労を感じたら昼寝をする 睡眠時間がとれない場合は、例えば「午前中の家事が終わったあと」「夕食の支度に取りかかる前」などに少し横になるのも効果的です。 また、関節の痛みや腫れが落ち着いているときにかぎり、1日1回は関節を十分に動かすことも大切です。寒い時期は、関節が冷えて痛みが悪化するおそれがあります。長袖や長ズボン、ブランケットにより関節を保温しましょう。 薬物療法 関節リウマチに対する薬物療法は以下のような薬を用います。 薬の種類 特徴 抗リウマチ薬 ・原因となっている免疫の異常に作用して病気の進行を抑える ・関節リウマチの治療における第一選択の薬である 生物学的製剤 ・炎症を引き起こす物質の働きを妨げて炎症を和らげる ・抗リウマチ薬の効果が不十分である場合に使用する どちらの薬も効果が高く、症状が落ち着いている寛解(かんかい)の状態になる方も多いです。 再生医療 関節リウマチの痛みに対する治療方法の一つとして再生医療があります。再生医療とは、自己の細胞を痛みのある部位に投与して、体が持つ自然治癒力を引き出す治療方法です。 具体的な再生医療の治療方法は以下のとおりです。 再生医療の種類 詳細 幹細胞治療 (かんさいぼうちりょう) 組織の修復に関わる働きを持つ「幹細胞」を患部に投与する治療方法 PRP療法 血液中の血小板に含まれる成長因子などが持つ、炎症を抑える働きや組織修復に関与する働きを利用した治療方法 関節リウマチに対する当院の再生医療の症例については、以下を参考にしてください。 【症例解説】 関節リウマチで膝関節の痛みが取れない・40代女性 関節リウマチ・高濃度PRPで手首の痛みが激減! 関節リウマチになりやすい人 関節リウマチの原因は明確にはわかっていませんが、30代〜50代の女性に多い病気です。発症には免疫の異常が関連していると考えられていることから、遺伝子や感染症の影響により発症するのではないかと言われています。 その他には、歯周病や喫煙が関節リウマチの発症率を上げることがわかっています。関節リウマチの発症を予防するためには、日々の丁寧な歯磨き習慣や禁煙などが大切です。 まとめ|関節リウマチの初期症状を疑ったら早期に医療機関を受診しよう 関節リウマチの初期症状は朝のこわばり、関節の腫れ、関節の痛みです。とくに「朝起きた際に手指がこわばって動かしにくい」「手指に腫れぼったさがある」は、典型的な初期症状です。 放置すると骨や軟骨の破壊が進み、関節が変形してしまいます。近年では、発症後1年以内に関節破壊が進むこともわかってきています。進行を抑えるためにも疑われる症状が現れている方は、早期に医療機関を受診してください。 当院「リペアセルクリニック」では、関節リウマチに対して再生医療を行っています。気になる症状がある方は、お気軽にご相談ください。 関節リウマチの初期症状に関するよくある質問 具体的にどんな痛み? 関節リウマチは炎症を伴うため、熱を持ったような痛みが現れます。また、左右対称に現れる特徴があります。 ばね指との見分け方は? ばね指は主に指一本に起きる動作障害です。一方、関節リウマチは左右対称に複数の関節に症状が現れます。 なりやすい性格はある? 関節リウマチの患者様は、神経症や抑うつの傾向の方が多いと報告があります。しかし、関節リウマチの発症と性格の関連性を示す明確な根拠はありません。 参考文献 (文献1) 関節リウマチ|帝京大学医学部内科学講座 (文献2) 早期発見・早期治療で 食い止めろ!リウマチ|調布東山病院
2021.12.10