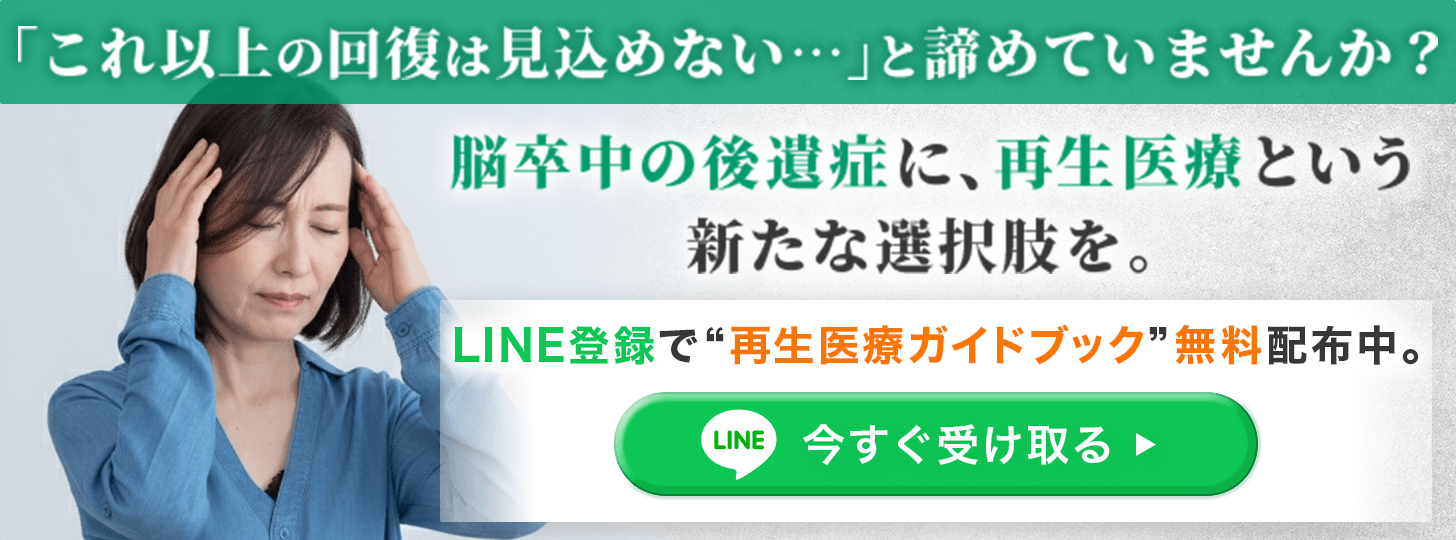- 脳卒中
- 頭部
脳卒中のリハビリで手足の麻痺を回復させ、残った機能を最大化させる方法
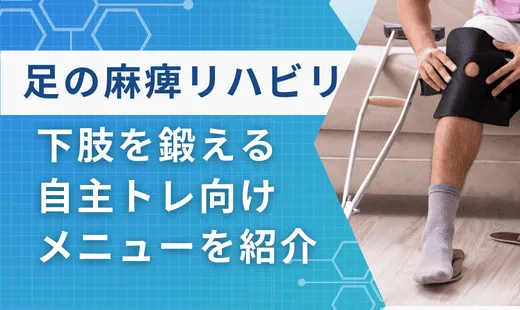
脳卒中は脳の血管が詰まったり破れたりして脳の機能が損なわれる病気の総称です。(文献1)大きく脳梗塞・脳出血・くも膜下出血の3種類に分けられ、発症すると運動障害や感覚障害など後遺症のリスクが増加します。
代表的な運動障害が手足の麻痺で、身体のいずれか片側にあらわれるのが特徴です。脳卒中の発症後早期から積極的なリハビリに取り組むと、ADL(Activities of Daily Living:日常生活動作の向上)が見込めます。
今回は脳卒中の後遺症で多く見られる足の麻痺について、リハビリのやり方を詳しくお伝えします。リハビリを始める前に知っておくべき点も解説するため、ぜひ参考にしてください。
目次
足の麻痺のリハビリは必要!早めに始めるほど回復する可能性が高まる
足の麻痺のリハビリは、早期に社会復帰するために必要です。足の麻痺が残ると歩行が困難になったり転倒危険性が高くなったりする上、社会参加の機会が失われると精神面にも悪影響を及ぼす恐れがあります。
リハビリで足の麻痺をどこまで改善できるかは症状の程度や年齢、損傷部位により異なるため一概には断言できません。しかし脳神経には可塑性があるため、早期にリハビリを開始するほど歩行機能の改善が見込めます。
足の麻痺のリハビリに取り組む目的・必要性としては筋肉の弱体化を防止したり、身体のバランス感覚を保持したり、日常生活における動作に必要な筋力を維持したりする点が挙げられます。
足の麻痺のリハビリを始める前に知っておきたいこと
足の麻痺のリハビリを始める前に、以下4つのポイントを知っておきましょう。
- 正しいフォーム(姿勢)で実施する
- 転倒・転落の対策を十分に行う
- 適度に水分補給・休憩をとる
- 痛みがある(出る)場合は無理しない
足の麻痺のリハビリに取り組む際は、正しいフォーム(姿勢)で実施するのが原則です。誤ったフォーム(姿勢)では狙った筋肉にアプローチできない上、筋肉痛や腰痛などのリスクが増加します。
リハビリを実施する際は転倒・転落への対策を十分に講じてください。自宅の部屋で行う方はリハビリのためのスペースを十分に確保し、滑りやすい物を足元に置かないようにしましょう。
導線上に不要な物を置かないようにするだけでなく、万が一の転倒に備えてすぐに壁に触れられる環境を整えることも大切です。
リハビリの実施中は水分補給と適度な休憩を欠かさず、途中で痛みが出た場合は無理をせず中断しましょう。リハビリ中に頻繁に痛みが出る方は、正しいフォーム(姿勢)で実施できているか確認する必要があります。
リハビリの初期は筋出力が低下しているため、少ない回数・時間からはじめ、慣れてきたら徐々に増やすのがポイントです。
足の麻痺のリハビリ方法|自主トレする場合
足の麻痺のリハビリ方法について、自宅で自主トレする場合に効果的な運動を以下に分けて解説します。
- ベッド上でできるリハビリ
- 座ったままできるリハビリ
- 起立してできるリハビリ
脳卒中の発症から48時間以内に離床すると、不動関連の合併症のリスクを低減できるとわかっています。(文献2)医師の許可が出たら自分にできるリハビリに取り組み、足の麻痺を少しでも軽減しましょう。
ベッド上でできるリハビリ
ベッド上でできる足の麻痺のリハビリ方法は以下の3つです。
- 片足を上げる運動
- お尻を上げる運動(ブリッジ)
- タオルを膝裏でつぶす運動
それぞれについて詳しく解説します。
片足を上げる運動
ベッド上でできるリハビリの一つが、寝た状態から片足を上げる運動です。
| 目的 | 股関節を屈曲させる際にはたらく腸腰筋を強化する |
|---|---|
| 方法 | 1.ベッドにあおむけで寝て両足を伸ばす 2.手のひらを下にしてお尻の両脇に置く 3.ひざを伸ばしたまま右足をゆっくりと上げる 4.足をあげた状態を2秒ほどキープしたらゆっくりと元に戻す 5.左右10回ずつ行う |
腸腰筋は腰の骨と太ももの骨をつなぐ筋肉で、歩行の際に太ももをあげる(股関節を屈曲させる)はたらきがあります。腸腰筋をしっかり使えると足が高く上がるため、転倒リスクを下げる効果が期待できます。
仰向けだけでなく横向きでリハビリに取り組むと、お尻の筋肉(中殿筋)が鍛えられ、歩行時に体幹(全身から四肢を除いた部分)を安定させるのに効果的です。
お尻を上げる運動(ブリッジ)
お尻を上げる運動もベッド上でできるリハビリの一つです。
| 目的 | 股関節を伸展させる際にはたらく大殿筋を強化する |
|---|---|
| 方法 | 1.ベッドにあおむけで寝て両足を伸ばす 2.手のひらを下にしてお尻の両脇に置く 3.両ひざを立ててお尻をゆっくりと上げる 4.2秒ほど姿勢をキープしたらゆっくりと元に戻す 5.最初は10回から始め慣れてきたら回数を増やす |
大殿筋は骨盤と太ももの骨を結ぶお尻の大きな筋肉で、歩行の際に後ろ足で地面をける動作(股関節の伸展)の際にはたらきます。
大殿筋が鍛えられると地面をしっかりと蹴れるようになるため、歩行をスムーズにする効果が期待できます。お尻を上げた際に、肩から膝が一直線になるイメージで行うのがポイントです。
タオルを膝裏でつぶす運動
丸めたタオルを膝裏でつぶす運動も、足の筋肉の強化に効果的です。
| 目的 | 股関節の屈曲・膝関節の伸展の際にはたらく大腿直筋を強化する |
|---|---|
| 方法 | 1.ベッドにあおむけで寝て左ひざを立てる 2.丸めて棒状にしたタオルを右膝の下に入れる 3.右膝を伸ばし膝裏でタオルをつぶすように力を加える 4.左右10回ずつ行う |
大腿直筋は骨盤と膝下(脛骨粗面)を結ぶ筋肉で、太ももをあげたり(股関節の屈曲)、膝を伸ばしたり(膝関節の伸展)する際にはたらきます。
大腿直筋が鍛えられると膝を曲げ伸ばししやすくなるため、歩行をスムーズにする効果が期待出来ます。ベッドに座れるようであれば、両手を後ろについてリハビリしても構いません。
座ったままできるリハビリ
座ったままできる足の麻痺のリハビリ方法は以下の3つです。
- 太ももを上げる運動
- つま先を上げる運動
- 膝を閉じる運動
それぞれについて詳しく解説します。
太ももを上げる運動
椅子に座れるようになったら、太ももを上げる運動に取り組みましょう。
| 目的 | 股関節を屈曲させる際にはたらく腸腰筋を強化する |
|---|---|
| 方法 | 1.両足の裏が地面につく高さの椅子に座る 2.両手で椅子の縁をつかむ 3.右足を上げて膝を胸の方へ近づける 4.2秒ほど姿勢をキープしたらゆっくりと元に戻す 5.左右10回ずつ行う |
椅子に座り太ももを上げる運動に取り組むと、足を上げる際にはたらく腸腰筋の強化につながります。太ももをあげる際は、上半身が後ろに倒れないよう意識しましょう。
上半身が後ろに倒れると体重を利用して太ももを上げてしまうため、腸腰筋が十分に刺激されません。歩行がおぼつかない方は、ベッドの端に座ってリハビリしても構いません。
つま先を上げる運動
つま先を上げる運動は、立ったり座ったりする際に使われる筋肉を強化するのに効果的です。
| 目的 | 股関節の屈曲・膝関節の伸展の際にはたらく大腿直筋を強化する |
|---|---|
| 方法 | 1.両足の裏が地面につく高さの椅子に座る 2.両手で椅子の縁をつかむ 3.膝を伸ばしたまま右足を床と平行になるまで上げる 4.2秒ほど姿勢をキープしたらゆっくりと元に戻す 5.左右10回ずつ行う |
椅子に座りつま先を上げる運動に取り組むと、股関節を曲げて膝を伸ばす際にはたらく大腿直筋の強化につながります。つま先を上げる際は、足が床と平行になる高さまでで構いません。
足を上げる際に上半身が後ろに倒れないよう意識しましょう。上半身が後ろに倒れると体重を利用して足を上げてしまうため、大腿直筋を鍛える効果が低くなります。
膝を閉じる運動
椅子に座って膝を閉じる運動に取り組むと、骨盤が安定して歩行の際に足を上げやすくなります。
| 目的 | 股関節を屈曲したり骨盤を安定させたりするはたらきを持つ内転筋群を強化する |
|---|---|
| 方法 | 1.両足の裏が地面につく高さの椅子に座る 2.両手で椅子の縁をつかむ 3.膝の間に挟んだボールをつぶすように足を閉じる 4.2秒ほど姿勢をキープしたらゆっくりと元に戻す 5.最初は10回から始め慣れてきたら回数を増やす |
内転筋群は骨盤と太ももの骨の内側を結ぶ筋肉で、骨盤を安定させたり足を上げる際に補助的なはたらきをしたりする筋肉です。内転筋群を強化すると足が外側に広がるのを抑え、まっすぐ歩きやすくなるメリットがあります。
自宅に適当なボールがない方は、タオルを丸めたものやクッション、折りたたんだ座布団などでも代用可能です。
起立してできるリハビリ
起立できるようになったら以下3つのリハビリに取り組むのがおすすめです。
- 立ったり座ったりを繰り返す運動
- 足を後ろに蹴る運動
- 片足を横に開く運動
それぞれについて詳しく解説します。
立ったり座ったりを繰り返す運動
立ったり座ったりを繰り返す運動に取り組むと、バランスよく立つための筋力アップに効果的です。
| 目的 | 足全体の筋力強化、および麻痺側の足に体重をかけてバランスよく立つ |
|---|---|
| 方法 | 1.テーブルを前にして椅子に腰かける 2.両手をテーブルについて体重をかけ立ち上がる 3.両足に均等に体重をかけるイメージで姿勢を維持する 4.お辞儀するように上半身を前に倒しながら椅子に腰かける 5.最初は10回から始め慣れてきたら回数を増やす |
立ったり座ったりを繰り返す運動のコツは、立つときも座るときもゆっくり時間をかけることです。時間をかけることで筋肉が十分に収縮するため、効率よく筋力アップにつながります。
腕の力に頼らなくても立てるようになったら、机がない場所で椅子に座った状態から立ち上がる訓練にも取り組みましょう。ただし、転倒に備えて壁の近くで行うなど工夫してください。
足を後ろに蹴る運動
足を後ろに蹴る運動を繰り返すと、歩行の際に足で地面をしっかり蹴れるようになります。
| 目的 | 股関節を伸展させる際にはたらく大殿筋を強化する |
|---|---|
| 方法 | 1.立った状態で椅子の背もたれや机の縁に両手を置く 2.膝を伸ばしたまま右足を大きく後ろに蹴る 3.右足を後ろに下げた姿勢を2秒ほどキープしてゆっくりと元に戻す 4.左右10回ずつ行う |
足を後ろに蹴る運動は地面をける際にはたらく大殿筋を鍛えるリハビリのため、素早く行う必要はありません。できるだけゆっくり行い、お尻の筋肉に効いていることを意識するのがポイントです。
足を後ろに下げるときは、上半身が前に倒れないよう意識しましょう。上半身が前に倒れると反動で足を後ろに下げてしまうため、大殿筋に十分な負荷がかからなくなります。
片足を横に開く運動
片足を横に開く運動を繰り返すと、骨盤を安定させるための筋力アップが期待できます。
| 目的 | 骨盤を安定させる際にはたらく中殿筋を強化する |
|---|---|
| 方法 | 1.立った状態で椅子の背もたれや机の縁に両手を置く 2.膝を伸ばしたまま右足を大きく左側に開く 3.足を開いた姿勢を2秒ほどキープしてゆっくりと元に戻す 4.左右10回ずつ行う |
片足を横に開く運動も素早く行うのではなく、できるだけ時間をかけてゆっくり取り組むのがポイントです。足を開く際は上半身が左右に傾かないよう意識しましょう。
上半身が左右に傾くと反動で足を振り上げてしまうため、十分に中殿筋が刺激されなくなります。つま先を外側に開かず真っすぐ前に向けると、より効率的に中殿筋を刺激できます。
足の麻痺のリハビリ方法|病院のリハビリテーション室で実施する場合
足の麻痺のリハビリは、病院のリハビリテーション室で実施する場合もあります。脳卒中の発症直後は集中治療室で過ごしますが、車いすに座れるようになると一般病棟へ移るのが一般的です。
一般病棟でベッドサイドでのリハビリに取り組んだ後、立ったり座ったりするための筋力が付いてきたら、リハビリテーション室で歩行機能を回復させるためのリハビリを実施します。
リハビリテーション室で取り組む歩行機能の回復に向けたリハビリ方法は、以下の通りです。
- 立つ訓練に取り組む
- 手すりを用いた歩行練習に移る
- 杖を使って歩く練習を開始する
リハビリテーション室では最初に両足でバランスよく立つための訓練に取り組み、立位が安定して保持できるようになれば手すりを用いた歩行練習に移ります。歩容が安定してきたら、杖を使って歩けるようになるためのリハビリに取り組みます。
脳卒中の発症に伴う歩行障害の程度は個人によりさまざまです。作業療法士が一人ひとりに適したプログラムを作成し、回復度合いを見ながら運動強度を強めていきます。
足の麻痺はリハビリしても後遺症が出る可能性はある
脳卒中の発症後から速やかにリハビリに取り組むと、歩行障害の改善が期待できます。実際に脳卒中を発症した方のおよそ3人に2人は、リハビリによる自立歩行が可能です。(文献3)
しかし、現在の医療技術で脳卒中の発症に伴う感覚麻痺を完全に治すことは難しく、足の麻痺のリハビリに取り組んでも、後遺症が出る可能性は否定できません。実際、18歳から65歳までの発症者では、3割以上に中等度以上の後遺症が残るとされています。(文献4)
具体的な後遺症の例としては運動麻痺や感覚麻痺、失語症、高次機能障害、嚥下障害、排尿障害、認知症、うつなどが挙げられます。
脳卒中による後遺症のリスクを少しでも低減するため、発症後の早い段階から適切な治療およびリハビリに取り組むことが重要です。
\まずは当院にお問い合わせください/
足の麻痺の治療には再生医療をご検討ください
近年、足の麻痺の治療法の一つとして、再生医療が挙げられるようになりました。
足の麻痺に対する再生医療の具体的な手順は以下の通りです。
- 脳卒中患者の血液を採取する
- 同様に脂肪を採取する
- 幹細胞を培養する
- 脳卒中患者に幹細胞を投与する
再生医療に関しても、治療を始めるタイミングが早ければ早いほど良い結果が見込めます。
当院リペアセルクリニックでは、脳卒中による足の麻痺の治療にも用いられる再生医療を扱っておりますので、ご興味のある方はぜひ一度ご相談ください。

脳卒中のお悩みに対する新しい治療法があります。
まとめ|足の麻痺のリハビリは早期からコツコツ進めるのがポイント
脳卒中の発症後に見られる代表的な運動障害が手足の麻痺ですが、発症後の早期から積極的なリハビリに取り組むと、ADL(Activities of Daily Living:日常生活動作の向上)が見込めます。
実際に脳卒中を発症した方のおよそ3人に2人が、適切な治療およびリハビリによって自立歩行が可能になるとわかっています。
脳卒中の累積再発率は初回発症後から5年で約35%とされていますが、再生医療により損傷した血管が修復されると、将来の脳卒中の再発を予防できる点もメリットの1つです。(文献5)
リペアセルクリニックでは、足の麻痺に対する再生療法に関するご相談を受け付けています。患者様の症状に応じて期待できる効果を丁寧にご説明しますので、お気軽にお問い合わせください。
\まずは当院にお問い合わせください/
参考文献
(文献1)
東京都保健医療局「脳卒中とは」
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/siryou25-2(最終アクセス:2025年4月17日)
(文献2)
理学療法学「脳卒中患者に対する発症後48時間以内の規律と定義した早期離床導入の効果」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/rigaku/advpub/0/advpub_11753/_pdf(最終アクセス:2025年4月16日)
(文献3)
理学療法科学「脳卒中片麻痺患者における下肢感覚障害が歩行が自立するまでの期間の長さに及ぼす影響」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/rika/38/6/38_456/_pdf/-char/en(最終アクセス:2025年4月17日)
(文献4)
厚生労働省「脳卒中患者(18-65歳)の予後」
https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/18/backdata/01-01-02-06.html(最終アクセス:2025年4月17日)
(文献5)
厚生労働省「脳卒中の回復期・維持期の診療提供体制の考え方」
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/5_4.pdf(最終アクセス:2025年4月17日)