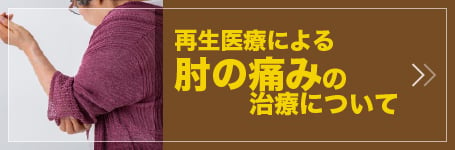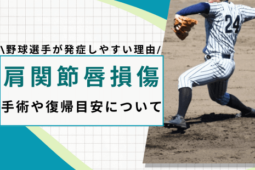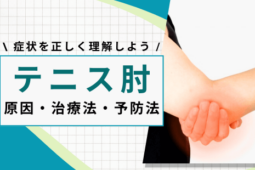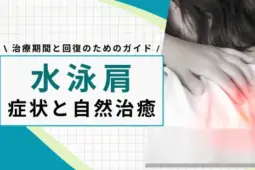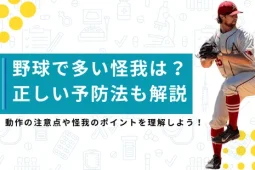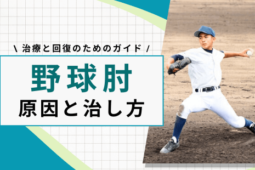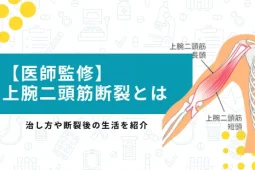- 肘関節
- 野球肘
- 上肢(腕の障害)
- スポーツ外傷
野球肘におすすめなストレッチ5選!症状の改善や原因について解説

野球肘は、5人に一人が発症する、ありふれたスポーツ障害のひとつです。主に投球練習や登板回数の過多が原因で発症します。
症状が重い場合は選手生命が縮んでしまうことも。理解を深め、予防や症状改善を図るのが重要です。
本記事では野球肘の症状改善や予防のためのストレッチ方法などを解説します。
目次
野球肘の症状改善・予防におすすめなストレッチ5選
肘の関節や靭帯を守るため、動かす前に準備が大切です。
野球肘を予防するには、プレー前に関節をしっかり伸ばすストレッチをおこないましょう。
スポーツの前後にストレッチをしっかりおこなうことは大切ですが、肘周りのストレッチだけで安心していてはいけません。
野球肘の予防には、肘の関節だけでなく、全身の柔軟性を上げることが重要だからです。
そこで以下に野球肘の予防に効果的なストレッチをご紹介します。
手首・肘の内側を伸ばすストレッチ
片手をまっすぐ前に伸ばします。
この時、手の甲は天井を向き、手首と腕が90度になるようにします。
そして、伸ばしている手と反対の手で、指先を体の方に引き寄せましょう。
次の動作は、そのまま手のひらを反時計回りに180度回転させ、手の甲が地面を向くようにします。
そのまま手のひらを机などの平らなところに着け、ゆっくりと体重をかけていきます。
肩・肩甲骨をほぐすストレッチ
まず、指先を肩に添えましょう。(右肩には右手、左肩には左手を添える)
肘で円を描くように大きく回す動作を繰り返します。
前に10回、後ろに10回程度回しながら肩と肩甲骨を意識してストレッチしていきましょう。
投球動作では、肩にも大きな負担がかかります。
肩甲骨周りの可動域を広げることは、きれいな投球フォームを作ることにもつながります。
肩回りを伸ばすストレッチ
胸の前で、自身の腕(肘から手の平まで)をくっつけます
この時点で窮屈に感じる方は、肩甲骨回りや、肩の筋肉が固い状態です。
肘を胸の高さまで引き上げることが可能な場合は、肘が90度、脇下も90度の状態になります。(難しい場合は角度が狭くなっても構いません。)
その姿勢から、腕を後ろへ引き、胸を張る状態を作ります。
胸を張ったらそのまま10秒キープしましょう。
その後、再び胸の前で手のひらから肘をくっつけていきます。
この動きを5セット繰り返しましょう。
胸の前で腕をくっつける際は肩甲骨が離れる感覚を、腕を後ろに引く際は、肩甲骨が背骨を挟むような感覚を掴みながらおこなってください。
体幹と下半身のストレッチ
体幹と下半身の柔軟性を高めると、肘への負担が大幅に減ります。以下のストレッチに取り組みましょう。
1. 両足を肩幅の1.5倍程度開く
2. 膝を120度ほど曲げる
3. 膝の内側に両手を置く
4. 左肩を、右方向にひねる
5. 10秒キープする
6. 右肩を、左方向にひねる
7. 10秒キープする
8. 5に戻る
4から8回を1セットとして、2セットほどおこないましょう。
肩をひねるとき、膝が動かないようにすると、ストレッチ感を得やすくなります。
また、腰は不自然に落としすぎないようにしましょう。
体幹と股関節のストレッチ
両足を股関節から開いた状態で床に座ります。
まず、左膝を折り曲げ、左足の裏側が右足の内ももに着く姿勢を取りましょう。(右足は伸ばしたままの状態です。)
右足のつま先をしっかり天井に向け、体側を伸ばしながら左手を右足のつま先へ向かって伸ばします。
左側の体側と、右足の裏側からふくらはぎにストレッチを感じていれば正しく伸ばせています。
この状態を10秒キープし、反対も同じように行いましょう。
左右それぞれ2セットずつおこなってください。
ストレッチをする時に気を付けるポイント
第一に、ストレッチの動作はゆっくりおこないましょう。
急に関節を伸ばすと、痛めてしまうこともあります。
具体的には、1つの部位を伸ばすのに10秒〜20秒程度かけるのが理想的です。
加えて、ストレッチをしてすぐに激しい動きをするのはNGです。
緊張がゆるんだ関節を急に動かすと思わぬケガにつながりますので、軽い運動をおこなってから練習を始めてください。
野球肘治療後のストレッチは専門家に相談する
ストレッチは関節の可動域を広げるために重要です。
ただし、野球肘の治療後にストレッチを始める場合は、医師の指示に従っておこなうようにしましょう。
また、リハビリにストレッチのメニューが加えられた場合、専門家の指導のもとでおこなうのも大切です。
安易な自己判断で野球肘を悪化させることがないように気を付けてください。
野球肘とは?
野球肘とは、ピッチングなど、ボールを投球する動作が原因で起こる「肘関節の損傷をまとめた呼び方」です。
投球時の痛みや違和感が代表的な症状で、軽傷であれば、安静にすれば痛みは落ち着きます。
ただし、痛みが引いたことで「肘を傷めてはいない」と勘違いし、治療が遅れ、重症化することも。
本人が気をつけるのももちろんですが、周囲が野球肘に関して警戒するのも大切です。
「肘が痛い」と感じた、もしくは選手に言われたら、野球肘を疑い、適切に対応する必要があります。
野球肘が起こる原因
野球肘は、肘に反復して過度な負担がかかることが原因で発症します。
野球のボールを投げる動作は、腕を大きく振りかぶった状態から肘の機能を使って力いっぱい投げおろすため、肘への負担が大きな動作です。
この動作を繰り返すことで肘の靱帯や軟骨に大きな負担がかかってしまいます。
野球肘の種類
野球肘には、3つの種類があります。
- 肘の外側の橈骨側の靱帯や軟骨を損傷するもの
- 肘の内側の尺骨の軟骨が損傷するもの
- 橈骨を損傷するもの
肘の内側には、骨や人体が引き離される方向に負荷がかかります。この力は関節を傷めやすく、尺骨側での野球肘を誘発します。
肘の外側と後ろ側では、骨がぶつかる方向で負荷がかかります。そのため、骨自体に損傷が起こりやすい傾向です。
野球肘の治療法
野球肘の発症後、その治療は、何よりも安静が第一です。
短くても数週間、長いと数年、野球肘と付き合いが続く可能性があります。
そのためにも、症状や違和感を感じたら、我慢せずに医師に相談しましょう。
軽症のうちから医療機関を受診し、指導を受けて重症化を防ぐことが必要です。
すでに野球肘の症状がある場合
野球肘の症状がある場合は、治療の長期化を防ぐため、早急な対応が必要です。
まずは肘を休ませて、早めに医療機関を受診しましょう。
そして、長く野球を続けるためには、肘に負担が掛かる投げ方をしていないか、指導者を交えての指導が必要です。
肘に負担が掛かるような投げ方、フォームを改善する必要があります。
治療については、スポーツ外来などがある医療機関を受診し、治療はもちろん、リハビリを含め、以後の取り組みについて指導を受けるようにしましょう。
エコー検査やレントゲンなど検査を受け状態を確認し、早期に治療を開始することが大切です。
合わせて取り組みたい野球肘の予防方法
ストレッチ以外の方法でも、以下の方法で野球肘を予防できます。
- 投球回数を減らす
- ウォームアップを入念におこなう
- フォームを改善する
チーム方針や投球スタイルとの兼ね合いもありますが、野球肘の予防を図るうえでは効果的です。
また、これらの方法は野球以外の競技に取り組む選手にも有用です。
それぞれ解説するので参考にしてください。
投球回数を減らす
投球回数を減らすことで、野球肘の発症リスクが下がります。
過度な投球練習や登板をなるべく避けましょう。
ただし、チーム方針の関係上、長いイニングを投げる必要に迫られるケースも。
その場合、十分なアイシングの実施と休養が重要です。
テニスや水泳など、やり投げなどのスポーツでも、練習頻度や負荷を減らすことで予防につながります。
ウォームアップを入念におこなう
投球前のウォームアップをより入念におこなうのも重要です。
例えば、普段のメニューに加えて、「腕を上げた状態でのキャッチボール」を追加するとよいでしょう。
腕を伸ばして投球すると、腕から肩の筋肉が刺激されます。
刺激が入ると、より高い柔軟性が発揮されます。
野球肘の予防では、体を柔らかくした上で投球するのが大切。
ストレッチとウォームアップで、十分な柔軟性を保ちましょう。
フォームを改善する
投球スタイルや球速、コントロールとの兼ね合いもありますが、フォーム改善で野球肘を予防できます。
以下のポイントを意識しましょう。
- ストライドを縮める
- リリースポイントを一定にする
- 投球時に肘が開かないようにする
ポイントをおさえると、肘に負担がかかりにくいです。
一方で、フォームを変えると球速やコントロールに影響が出るかもしれません。
その場合は指導者と、どのようなフォームを定めるか相談しましょう。
まとめ・野球肘をストレッチで予防して選手生命を伸ばす
野球の投球は全身で行うことが理想で、手だけの力で投げ続けると、野球肘発症の引き金となってしまいます。
練習前に時間をかけてストレッチを行うことで、野球肘の予防だけでなく、練習後の疲労も軽減できるでしょう。
野球肘の原因は肘の使い過ぎです。
最初から強く投げたり、いきなり投球するのではなく準備が必要です。
プレーや練習前、練習後には入念なストレッチを行うことが必要です。
練習計画に前後のストレッチを取り入れて野球肘を予防しましょう。
それでも肘の違和感がある、痛みがあるというような場合は重症化を防ぐためにも肘を安静にし、早めに医療機関を受診しましょう。
せっかくの才能ですから伸ばすためには身体の手入れが一番の練習だとご理解ください。
\無料オンライン診断実施中!/