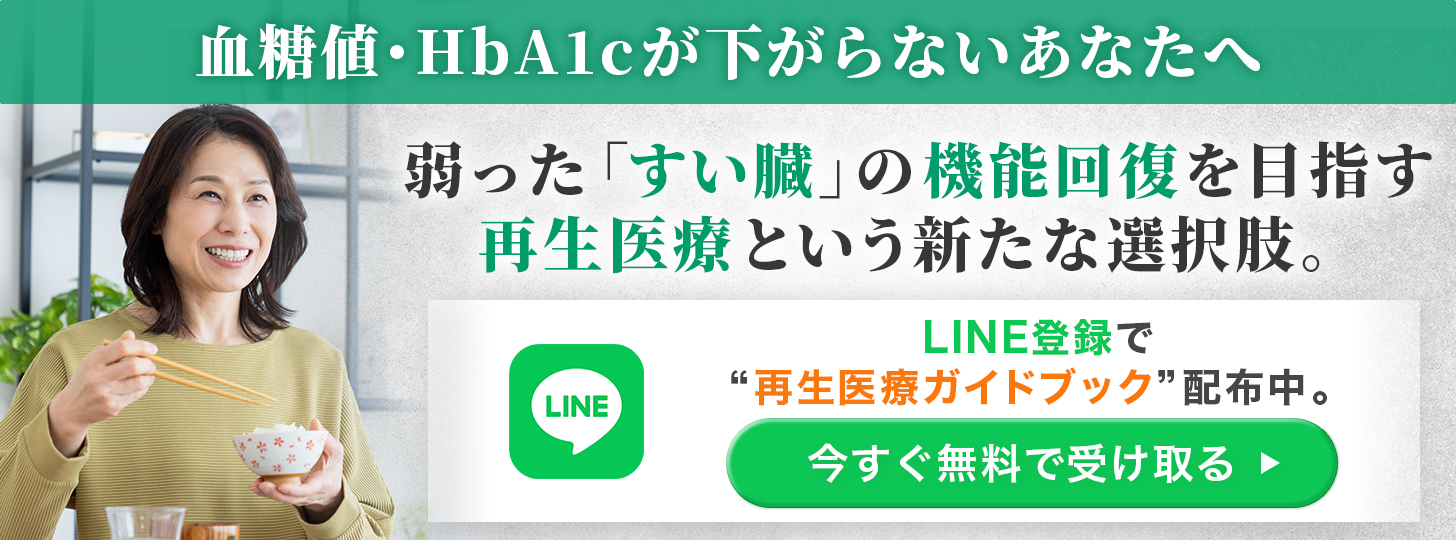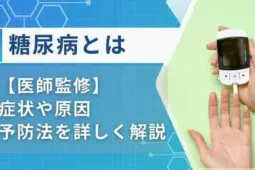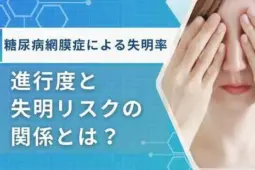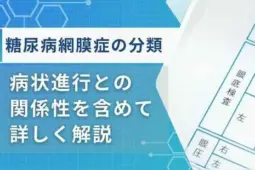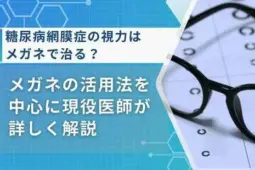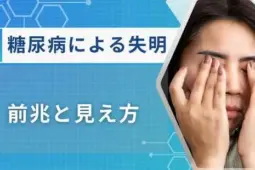- 糖尿病
- 内科疾患
空腹時の運動は糖尿病予防に逆効果!血糖値の上昇を防ぐ運動法を解説
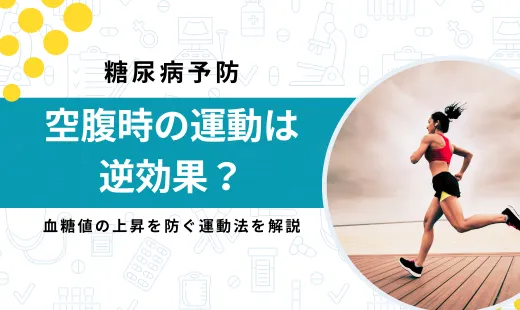
糖尿病を患っている人にとって、運動療法は効果的な改善法のひとつです。
しかし、運動のタイミングや運動量を誤ってしまうと、むしろ糖尿病を悪化させる原因になってしまう可能性があります。
この記事では、糖尿病に効果のある運動のタイミングや運動法について解説します。「今まで運動不足だったからいきなりの運動は不安」という人でもできる簡単な運動もあるため、ぜひ最後まで見てみてください。
目次
空腹時の運動が血糖値に与える影響|血糖値の急上昇、急降下を防ぐには
空腹時の運動は血糖値を不安定にしてしまうため推奨されていません。
食後の血糖値と比べると、空腹時は血糖値が低い状態です。運動を行うと血糖値は下がるため、激しい運動を行うと適正値を下回ってしまう可能性があります。
また、空腹時に運動を行った後は食事量も増えてしまうことが考えられます。食事量の増加によって血糖値の急上昇を引き起こしてしまうため、空腹時の運動は避けるべきでしょう。
現在行っている治療や体質によって注意すべきポイントが変わるため、それぞれご紹介します。
薬を飲んでいる人は空腹時の運動で低血糖を引き起こすリスクがある
現在インスリンやSU薬(スルホニル尿素薬)を飲んでいる人は、空腹時に運動を行うと低血糖を引き起こしてしまうため注意が必要です。
低血糖とは、血液中のブドウ糖が著しく少なくなった状態をいいます。糖尿病治療を行っている人によく見られる症状であり、体のだるさ、冷や汗、めまいなどを引き起こします。
空腹時血糖値が高い人は運動中に血糖値が急上昇する可能性がある
空腹時血糖値(食事を10時間以上摂らない状態での血糖値)が高い人は、運動を行うとむしろ血糖値が上がってしまう可能性があります。
食前、食後問わず、運動を行う場合は医師の指導を必ず受けるようにしましょう。
自身の体調に合わせた無理のない運動が大切
運動量が多い場合は補食をとる、もしくは運動前後のインスリン量を減らすなどの注意も必要になります。
短期的な効果を目指し過度な運動を行うことによって、低血糖や運動後の食事による血糖値の急上昇などを引き起こす可能性があります。
いずれもその人の体調に合わせた適切な運動を行うことが重要なので、糖尿病を患っている、あるいはその疑いがある方は、医師と相談しながら自身に合った運動量を調整していく必要があります。
血糖値の上昇を防ぐ効果的な運動法
この項目では、実際どのような運動療法を実施すると効果が高いのかをポイント毎に紹介します。
運動療法では、週150分かそれ以上、週3回の全身を使った有酸素運動が推奨されています。(文献1)
運動強度はややきつい中等度が良いとされており、20分以上の運動の継続がおすすめです。
また、無酸素運動(レジスタンス運動)については、連続しない日程で週に2~3回の実施がすすめられています。
食後1時間〜3時間で運動をする
運動を行う際は食後1~3時間の間で行うのがおすすめです。
食後は血糖値が一時的に上昇し、健康な人で食後1時間、糖尿病の人で食後2時間半ほどでピークに達し、その後緩やかに下がっていきます。(文献2)
そのため、血糖値を下げるのに最も効果的なタイミングは食後のおよそ1時間~3時間後です。
食後の運動にはウォーキング、ヨガ、エアロビクスなどの有酸素運動がおすすめされています。
筋肉をつける運動を取り入れる
有酸素運動に加え、筋肉をつけるための無酸素運動(レジスタンス運動)を取り入れることで、長期的に見た際に血糖値コントロールに有効であるという効果も出ています。
運動を続けていくと、筋肉の量が少しずつ増えていきます。筋肉はエネルギーを大きく消費するため、筋肉が増えていくと血液中のブドウ糖が筋肉に多く取り込まれるようになります。これにより、血糖値を正常値に保ちやすくなります。
また、筋肉によるエネルギーの消費を基礎代謝と呼び、運動によって筋肉が増えることで基礎代謝量の増加に繋がるため太りにくい体質をつくることができるのです。
負荷が高ければ高いほど効果が報告されています。しかし、急に高負荷の運動を始めると、力みによって血圧が上昇し危険です。運動開始前に医師のチェックを受けましょう。
また、適切なフォームで行うことも重要です。動作中重りをあげる際は息を吐き、重りを下げる際は息を吸うことを心がけましょう。
筋肉はすぐには変化しないため、すぐには効果が実感できないかもしれません。短期的な効果を得られやすいのは有酸素運動、長期的な効果を得られるのは無酸素運動と覚えておきましょう。
有酸素運動と無酸素運動を組み合わせると効果的!
一言で運動といっても様々な内容のものがあり、身体にかかる負荷の大きさもそれぞれ違います。
糖尿病にならないための運動には、深く呼吸しながら行う有酸素運動が効果的といわれています。
有酸素運動にあたるもの
- ウォーキング、歩行(できるだけ速く歩く)
- ジョギング
- ラジオ体操
- エアロビクス
また、有酸素運動とは逆に息をつめて行うものを無酸素運動(レジスタンス運動)と呼びます。
無酸素運動にあたるもの
- 短距離走
- 重い物を持つ
- 筋力トレーニング
無酸素運動では、いきなり高負荷な運動は行わないよう注意が必要です。
無酸素運動はあまりしたことがない人にとって、最初はハードルの高い運動かもしれません。 全身を万遍なく鍛えることが推奨されていますが、時間がない人や自信がないという人には、下半身を鍛えられるスクワットから始めることをおすすめします。
短い時間のウォーキングや、日常動作も効果がある
運動とは、いわゆる「スポーツ」だけを指している訳ではありません。軽いウォーキングや立って行う家事など、身体を使った活動全てが運動です。
ある研究では、一日中座っていた人と比べ、軽いウォーキングや短時間の立ち仕事を頻繁に行っていた人のほうが食後の血糖値が低下していたという結果も出ています。(文献3)
日常の身体を使った活動
- 座っている時間を減らす
- いつもより速く歩く
- こまめに家事をこなす
- 身軽に動く
- 階段を使う
「毎日忙しくて運動する時間がつくれない」「長く運動をしていなかったから不安」という人は、まずは日常生活の中で身体を使う機会を増やしてみましょう。
効果的な、運動と食事の見直し
運動によるエネルギーの消費量は、思ったより多くありません。例えば、体重75㎏の人がウォーキングを10分間行うと、25kcalの消費になります。
しかし、毎日夕食にご飯(並盛り)を2杯食べているところを1杯に減らすと、それだけで250kcal減らすことができます。つまり、糖尿病にならないためには運動習慣だけでなく食生活の見直しを合わせて行うことが重要となるのです。
空腹時に運動すると血糖値が急上昇しやすいため、糖尿病予防には逆効果です。早朝のウォーキングやジョギングは、朝食後かパンやバナナなどを軽く食べた後に行いましょう。
まとめ|糖尿病予防には空腹時を避けた適切なタイミングでの運動が重要
空腹時の運動は、糖尿病の人にとっては悪い影響を及ぼす可能性があります。
激しい運動によって血糖値が下がってしまうだけでなく、空腹時の運動後の食事によって血糖値が急上昇してしまう可能性があります。
また、薬を飲んで治療をしている人は低血糖を引き起こしてしまう危険もあるため、食後1~3時間後の運動を行うよう心がけましょう。
ただし、持病や糖尿病合併症がある人、普段の血糖値が非常に高い人は運動が禁忌事項である場合があるため、スポーツを行う前には必ず事前に主治医の指示を受けてください。
なお、当院「リペアセルクリニック」では再生医療による糖尿病の治療に取り組んでいます。患者様一人ひとりの状態に応じた丁寧な診療を心がけ、血糖値や肝機能の管理をサポートしています。
再生医療について詳しく知りたい方は、合わせて以下をご覧ください。

糖尿病のお悩みに対する新しい治療法があります。
参考文献
(文献1)
日本糖尿病学会. 糖尿病診療ガイドライン2024「第4章 運動療法」, 日本糖尿病学会, 2024年.
https://www.jds.or.jp/uploads/files/publications/gl2024/04_1.pdf(最終アクセス:2025年3月25日)
(文献2)
糖尿病ネットワーク.「尿と糖尿病:尿検査でわかること」
https://dm-net.co.jp/urine/2010/05/0202.php(最終アクセス:2025年3月25日)
(文献3)
Buffey, A. J., et al. (2022). The Acute Effects of Interrupting Prolonged Sitting Time in Adults with Standing and Light-Intensity Walking on Biomarkers of Cardiometabolic Health: A Systematic Review and Meta-analysis. Sports Medicine, 52(7), pp.1765-1787.
https://link.springer.com/article/10.1007/s40279-022-01649-4 (最終アクセス:2025年3月25日)