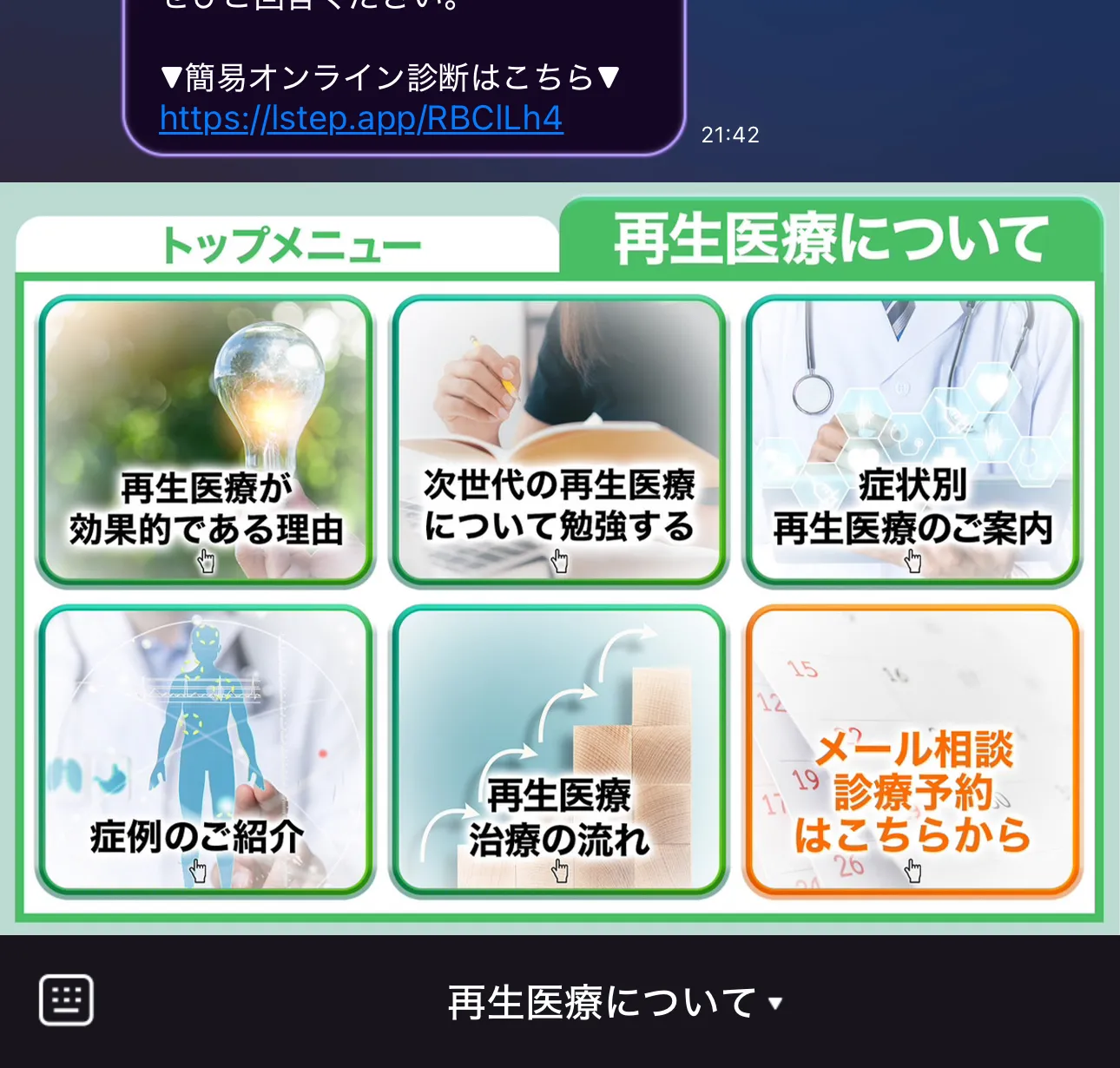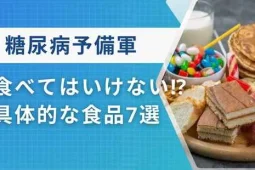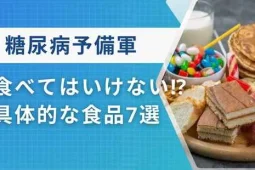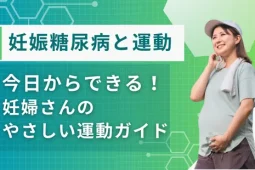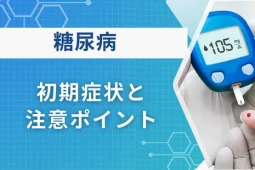- 糖尿病
- 内科疾患
食事の間隔を3時間以上あけると糖尿病を予防できる?継続の工夫を紹介
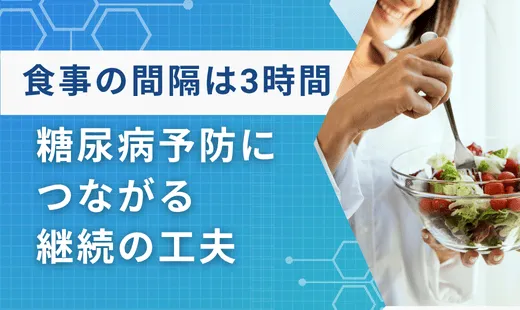
2023年(令和5年)の調査によると糖尿病の治療を受けている方はおよそ550万人、予備軍も含めるとおよそ2000万人に血糖値の異常が見られると考えられています。(文献1)
糖尿病は医薬品を用いて治療すると思われがちですが、食事療法や運動療法では十分に血糖値をコントロールできない際に、初めて治療薬の投与が検討されます。
毎日の食事は血糖値に大きな影響を与えるため、糖尿病の3大治療のなかでも食事療法はとても大切です。
食事に伴い血糖値が上昇すると膵臓からインスリンが分泌されて血糖値を下げます。
しかし、食事の間隔が短いとインスリンによる血糖降下作用が減弱するため注意が必要です。
本記事では食事の間隔を3時間以上あけるメリットや方法について解説します。糖尿病や血糖値の上昇にお悩みの方は参考にしてください。
目次
食事の間隔を3時間以上あけると糖尿病予防につながる
糖尿病を予防する際に食事の間隔を3時間以上あけると効果的とされます。
4〜5時間あけることが適切なケースもあるなど諸説ありますが、血糖値をコントロールするためには食事の間隔を適度にあける必要があることに違いはありません。
食事の間隔をあける必要性について理解するためには、糖尿病発症のメカニズムについて知っておく必要があります。
糖尿病には遺伝的要因で発症する1型と、生活習慣が深く関わる2型の2種類がありますが、単に糖尿病といった場合は2型を指すケースがほとんどです。
2型の糖尿病を発症するメカニズムは以下のとおりです。
- 加齢や遺伝的要因によりインスリンの分泌量が減少する(インスリン分泌障害)
- 乱れた食習慣や運動不足などが原因でインスリンの作用が減弱する(インスリン抵抗性)
- インスリンの分泌不足にインスリン抵抗性が加わり血糖値が上昇する
- 高血糖状態が慢性化すると糖尿病の発症リスクが増加する
2型の糖尿病はインスリン分泌障害とインスリン抵抗性が合わさって発症するのが特徴です。(文献2)
2型の糖尿病にも遺伝的要因が関わっていますが、予防の観点では食事の間隔をあけて過食を避け、血糖値の急激な上昇を抑止するのがポイントです。
食事の間隔を3時間以上あけると血糖値の急激な上昇を抑えられるため、糖尿病の予防につながります。
間隔を3時間以上あけて食事する際に意識すること
糖尿病の予防目的で食事の間隔を3時間以上あける際は以下の4点を意識しましょう。
- 一口につき20~30回ほど噛み時間をかけて食べる
- 一回の食事量を調節して腹8分目に抑える
- 血糖値を上昇させにくい食物繊維が豊富な食材から食べる
- タンパク質が豊富な食材を積極的に摂る
それぞれについて解説します。
一口につき20~30回ほど噛み時間をかけて食べる
糖尿病の予防目的で食事の間隔を3時間以上あける際は、一口につき20〜30回ほど噛み、時間をかけて食べるよう意識しましょう。
よく噛んでゆっくり食べることには、血糖値の急激な上昇を抑える効果があります。食事を開始してから20分が経過すると、満腹中枢が刺激されて「お腹いっぱい」と感じやすくなるため、食べ過ぎを防げます。
平成21年に行われた国民健康・栄養調査において、BMI25以上の肥満の方は食事にかける時間が短い傾向にあるとわかりました。(文献3)これは、早食いが肥満につながりやすく、血糖値管理の観点からも注意が必要であることを示しています。
ただし、食事に時間をかけ過ぎると胃腸のはたらきが低下するため、1回の食事は90分以内にとどめましょう。
また、血糖値の急激な上昇を抑えるためにはGI値(グリセミック・インデックス)の低い食品を取り入れるのも効果的です。
一回の食事量を調節して腹8分目に抑える
一回の食事量を調節して腹8分目に抑えるのも、糖尿病の予防目的で食事の間隔を3時間以上あける際のポイントです。
江戸時代に刊行された養生訓には「腹八分目に医者いらず」の有名な文言が記載されています。
日本糖尿病学会でも食事指導のポイントに「腹八分目とする」を挙げています。(文献4)
食事の量を調整して満腹状態を避けると、血糖値の急激な上昇を抑えられます。
自分で調節する際は主食(炭水化物)の量を減らし、タンパク質や食物繊維を多く含む副菜を多めに摂取しましょう。
血糖値を上昇させにくい食物繊維が豊富な食材から食べる
糖尿病の予防目的で食事の間隔を3時間以上あける際は、食べる順番も意識して食物繊維が豊富な食材から食べましょう。
糖質を多く含む炭水化物から食べ始めると、血糖値が上昇しやすいため注意が必要です。
食物繊維を多く含む代表的な食品の例は以下のとおりです。
- 穀類:玄米・麦ごはん・胚芽米など
- 豆類:大豆・納豆・おからなど
- いも類:こんにゃく・長いもなど
- 野菜類:ごぼう・セロリ・白菜など
- 茸類:きくらげ・エリンギ・シメジなど
- 海藻類:ワカメ・ヒジキなど
食物繊維を多く含む食品のなかでも歯ごたえがある食品を取り入れると、噛む回数が増えて早食いを避ける結果につながります。
タンパク質が豊富な食材を積極的に摂る
糖尿病の予防目的で食事の間隔を3時間以上あける際は、タンパク質が豊富な食材を積極的に摂るのも大切なポイントの一つです。
タンパク質が豊富な食材を積極的に摂取すると満腹感を得やすいため、食事に伴う血糖値の急激な上昇を避けやすくなります。
タンパク質を多く含む代表的な食品の例は以下のとおりです。
- 肉類:鶏むね肉・ささみ・牛もも肉など
- 魚類:サバ・カツオ・マグロなど
- 大豆製品:豆腐・納豆・枝豆など
- 乳製品:ヨーグルト・チーズ・牛乳など
- 卵類:鶏卵・ウズラの卵など
タンパク質を多く含む食品のなかでも鶏むね肉は歯ごたえとボリュームがあるため、血糖値の急激な上昇を避けたい方におすすめです。
食事の間隔を3時間以上あけることを続けやすくする工夫
食事の間隔を3時間以上あけることを続けやすくする工夫は以下の2つです。
- 食事の内容・時間などを記録する
- 手軽に食べられる低GI・高タンパク食品を軽食にする
それぞれについて解説します。
食事の内容・時間などを記録する
食事の間隔を3時間以上あける習慣を続ける際は、食事の内容・時間などを記録しておきましょう。食事に対する意識を高めると、食事の間隔を3時間以上あけるモチベーションの維持につながります。
朝・昼・晩の3回分の食事を欠かさずに記録するのは大変なので、食べ過ぎる傾向が多く見られる夕食の内容の記録から始めましょう。
食事の量やカロリーなどの詳細を記録しなくても、「何時にどんなものを食べたか」記録するだけでも構いません。食事の内容・時間を記録する際は、間食やアルコールの摂取についても書き漏らさないようにしてください。
間食に甘いものを食べると血糖値が急激に上昇するため、食事の順番を意識する努力が無駄になりかねません。ビールやワイン、日本酒には糖質が多く含まれているため、過剰摂取は糖尿病の発症リスクを高めると覚えておきましょう。
手軽に食べられる低GI・高タンパク食品を軽食にする
食事の間隔を3時間以上あける習慣を続ける際は、手軽に食べられる低GI・高タンパク食品を軽食として取り入れる工夫もあります。
軽食を取り入れると昼食や夕食の前に食欲が急増するのを避け、食べ過ぎおよび血糖値の急激な上昇を抑制する結果が見込めます。
軽食に取り入れるのがおすすめの低GI・高タンパク食品の例は以下のとおりです。
- 大豆製品
- 鶏むね肉
- ヨーグルト
- 鶏卵
- アーモンドなど
低GI・高タンパク食品を軽食として取り入れる際は、通常の3食の量を適宜調整してください。また、ヨーグルトは無糖の商品を、アーモンドは無塩の商品を選ぶのがポイントです。
食事の間隔とともに適度に運動することも糖尿病予防につながる
食事の間隔を3時間あけるとともに、適度な運動に取り組むと糖尿病の予防につながります。
8週間以上の運動療法に関する複数の研究をまとめた分析では、ヘモグロビンA1c(HbA1c:過去1〜2カ月の平均的な血糖値)の有意な改善が報告されています。
以前は血糖値を下げるために1週間あたり150分以上の運動が必要と考えられていましたが、研究が進み1週間に30〜100分の運動でも、時間依存的に血糖値を下げられるとわかってきました。
また、週に2~3回のレジスタンス運動(筋力トレーニングなど)を取り入れるとインスリン抵抗性が改善し、血糖値を改善すると示唆されています。(文献5)
食事の間隔を3時間以上あけて過ごす一日のスケジュール例
食事の間隔を3時間以上あけるためには、スケジュールを立てて規則正しい生活を送る必要があります。
たとえば、以下のスケジュールで食事を摂ると、食間に3時間以上の間隔を設けられます。
- 朝食:7~9時(出勤や登校にあわせる)
- 昼食:12~14時
- 夕食:18~20時
間食(補食)の習慣がある方は昼食の3〜4時間後、夕食の3時間前ほどに摂ると良いでしょう。
昼食を摂るのが遅くなった日は、間食(補食)を抜くなどして急激な血糖値の上昇を避けてください。
また、個人により起床や就寝の時間が異なるため、自分の生活リズムに合わせてスケジュールを調整する必要があります。
食事の間隔を3時間以上あけて過ごす上で注意すること
食事の間隔を3時間以上あけて過ごす際は、以下の4点に注意する必要があります。
- 水分を適切に摂って脱水症状を防ぐ
- 夕食の食べ過ぎ・夜遅く(就寝前)の食事を避ける
- 外食が多い人は不足しがちな野菜・魚・大豆製品を意識して摂る
- 清涼飲料水など多量の糖分を含んだ食品を控える
それぞれについて解説します。
水分を適切に摂って脱水症状を防ぐ
食事の間隔を3時間以上あけて過ごす際は、水分を適切に摂って脱水症状を防ぐことが重要です。
食習慣の見直しに伴い食事制限に対する意識が高くなると、水分の摂取量が減少する傾向にあります。
一度に大量の水分を摂取するのは難しいだけでなく、尿として排出されてしまいます。
身体が一度に吸収できる水分量はおよそ200ミリリットルとされているため、コップ1杯程度の水を以下のタイミングで摂取するのがおすすめです。
- 起床時
- 朝食時
- 外出前
- 昼食時
- 間食時
- 運動前後
- 夕食時
- 入浴前後
- 就寝前
水分摂取量やタイミングには個人差があるため、生活リズムや体重などを考慮して適宜調整してください。
夕食の食べ過ぎ・夜遅く(就寝前)の食事を避ける
食事の間隔を3時間以上あけて過ごす際に意識したいことの一つが、夕食の食べ過ぎや夜遅く(就寝前)の食事を避けることです。
仕事が忙しくて昼食を摂れなかったり、間食の習慣がなかったりすると、空腹にまかせて夕食を大量に食べてしまう傾向にあります。
食事の量が増えると単純に糖質の摂取量が増加するため、血糖値の上昇を招きやすくなります。
夕食後はエネルギー消費量が少ないため、食べ過ぎにより体脂肪が増加すると糖尿病の発症リスクも高くなるため注意が必要です。
夕食を摂取する時間も耐糖能を左右すると知っておきましょう。
静岡県立大学の研究によると、夕食を19時に摂取した場合と比べ、20時以降に摂取した場合は食後の耐糖能(血糖値を正常な範囲に保つ能力)が低下するとわかっています。(文献6)
20時以降に食事を摂ると血糖値が上がりやすく、肥満や糖尿病のリスクが増加するので、食事の間隔とともに気をつけてください。
外食が多い人は不足しがちな野菜・魚・大豆製品を意識して摂る
食事の間隔を3時間以上あけて過ごすのに伴い、外食が多い人は不足しがちな野菜・魚・大豆製品を意識して摂取しましょう。
外食すると肉料理を選びやすく、糖尿病予防に効果が見込める野菜・魚・大豆製品が不足しやすいためです。
糖尿病にならないためには、できるだけ外食の回数を減らした方が良いでしょう。コンビニやスーパーでお弁当を買う場合は、野菜のおかずを1品プラスしてみましょう。
清涼飲料水など多量の糖分を含んだ食品を控える
砂糖がたくさん入っている清涼飲料水をよく飲む人は注意が必要です。清涼飲料水は、カロリーが高い割に得られる満足感が少なく、とくに炭酸飲料は口当たりが癖になりやすく飲み過ぎてしまう傾向があります。
普段飲んでいる清涼飲料水を控えるだけでも一度に100〜200kcalほど抑えられるため、糖尿病予防には効果的です。
食事の間隔は無理しない範囲であけて血糖値を調整しましょう
糖尿病は血糖値が慢性的に高くなる病気で、進行すると合併症を引き起こして四肢の切断が必要となるケースもあります。
糖尿病を予防するためには日々の食習慣を見直し、血糖値の急激な上昇を避ける必要があります。
血糖値の急激な上昇を避けるためにおすすめの方法の一つが、食事の間隔を3時間以上あけることです。食事の間隔を3時間以上あけると血糖値の急激な上昇を抑制し、糖尿病の発症リスクを下げる効果が見込めます。
ただし、食事の間隔をあけるだけでなく栄養バランスの取れた献立を考えたり、適度な運動を取り入れたりするのも重要なポイントです。
当院「リペアセルクリニック」では、糖尿病に対する治療として再生医療を行っています。慢性的な高血糖にお悩みの方はお気軽にご相談ください。

糖尿病のお悩みに対する新しい治療法があります。
食事の間隔に関してよくある質問
食事の間隔に関して以下2つの質問がよく聞かれます。
- 食事の間隔を16時間以上にするのはあけすぎ?
- 朝ごはんと昼ごはんの間隔が短いと太る?
以下でそれぞれお答えします。
食事の間隔を16時間以上にするのはあけすぎ?
食事制限による体重管理の方法の一つとして、16時間ダイエット(プチ断食)が挙げられます。
空腹の時間を長く設けることで脂肪の燃焼を促すのが目的ですが、糖尿病予防の観点からはおすすめできません。食事の間隔があきすぎることで、食後の血糖値が急激に上昇するリスクがあるためです。
また、食事できる時間が8時間に限られているため、1食で摂取する食べ物の量が増加する傾向にあります。
朝ごはんと昼ごはんの間隔が短いと太る?
朝ごはんと昼ご飯の間隔が短いからといって、必ずしも太るわけではありません。
太るか痩せるかを決定するのは摂取したカロリーと、1日の間に消費されるカロリーとのバランスで決まります。
朝ごはんと昼ご飯の間隔が短くても「摂取カロリー < 消費カロリー」のバランスを保てば太りにくいです。
ただ、朝ごはんと昼ご飯の間隔が短いと消化不良を起こしたり、胃の不快感や胃痛を生じたりする可能性があります。
朝食が遅くなったら、可能な範囲で昼食の時間を遅らせるのがおすすめです。
(文献1)
日本生活習慣病予防協会「糖尿病の調査・統計」
https://seikatsusyukanbyo.com/statistics/2025/010845.php(最終アクセス:2025年6月18日)
(文献2)
一般社団法人日本内分泌学会「2型糖尿病」
https://www.j-endo.jp/modules/patient/index.php?content_id=93(最終アクセス:2025年6月18日)
(文献3)
農林水産省「ゆっくり食べる」
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/minna_navi/topics/topics4_02.html(最終アクセス:2025年6月18日)
(文献4)
日本糖尿病学会「糖尿病治療ガイド」
https://www.jds.or.jp/uploads/fckeditor/files/uid000025_67756964655F323031382D323031392E706466.pdf(最終アクセス:2025年6月18日)
(文献5)
日本糖尿病学会「糖尿病診療ガイドライン2024」
https://www.jds.or.jp/uploads/files/publications/gl2024/04_1.pdf(最終アクセス:2025年3月25日)
(文献6)
静岡県立大学「食事間隔の延長による食後血糖悪化の病態生理の解明」
https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/media/US_forum2024_tokubetsu158.pdf(最終アクセス:2025年3月25日)