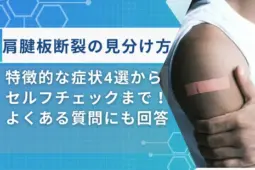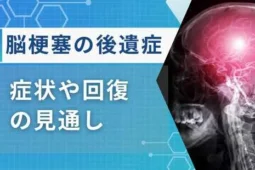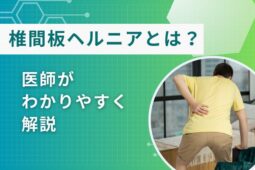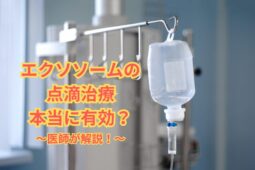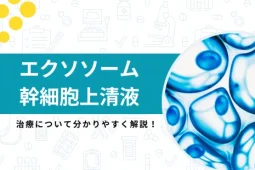- 幹細胞治療
- PRP治療
- 肘関節
- 再生治療
テニス肘の治療に対する再生医療の可能性|メリット・デメリットを解説

テニス肘の痛みは日常生活に影響を与えやすく、長期間にわたって悩まされるケースも少なくありません。
テニス肘の治療法は保存療法・手術療法、そして近年は「再生医療」が選択肢のひとつになっています。
再生医療は、保存療法で改善が見られず、手術は避けたいという方の選択肢となる、患者様自身の細胞を活用する新しい治療法です。
本記事では、テニス肘に対して再生医療を選択する上で知っておきたい、メリット・デメリットをわかりやすく解説します。
テニス肘の治療を検討している方は、参考にしてください。
なお、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療に関する情報の提供と簡易オンライン診断を行っています。ぜひ登録いただき、ご確認ください。
目次
テニス肘の治療の新しい選択肢「再生医療」とは
テニス肘の治療では、保存療法や手術に加え、「再生医療」が新たな選択肢となっています。
再生医療の代表的な方法としては、「幹細胞治療」と「PRP療法」があります。
いずれも、注射や点滴を通じて症状のある部位にアプローチする治療法で、入院や手術を必要とせず、日帰りでの施術が可能です。
以下では、幹細胞治療とPRP療法それぞれの特徴について、詳しく解説します。
細胞の力を利用する幹細胞治療
幹細胞治療とは、患者様自身から採取した幹細胞を用いる再生医療のひとつです。
幹細胞が、さまざまな種類の細胞に変化する「分化能」という能力を活かします。
再生医療は皮膚や筋膜の表面ではなく、関節内や腱付着部などへ静脈点滴または局所注入によってアプローチします。
脂肪由来の幹細胞治療を行う当院「リペアセルクリニック」での治療の流れは以下のとおりです。
1. 初診・問診・血液検査で適合確認
2.局所麻酔下で脂肪の採取(米粒2~3粒ほどの量)
3.細胞培養・加工
4.投与(静脈点滴または局所注入)
5.定期的な経過観察
投与自体は日帰りで対応可能です。
ただし、当院では冷凍保存しない幹細胞を使用しているため、細胞を培養し、投与できる状態にするまで約1カ月を要します。通院頻度は治療内容により異なりますが、およそ月1回程度のペースとなります。
また、幹細胞治療は痛みや組織の損傷が重度である場合に適用されるケースが多く、治療の適応については医師による慎重な判断が求められます。
テニス肘に対するPRP療法の原理
PRP療法とは、患者様自身の血液から血小板を高濃度に抽出し、患部に注射する再生医療のひとつです。
血小板は、ケガをしたときに出血を止めるとともに「成長因子」という物質を放出して組織の修復プロセスを促進します。
PRP療法を行っている当院「リペアセルクリニック」での治療は、以下の手順で進められます。
1.採血
2.採血した血液を遠心分離し、血漿成分を抽出
3.高濃度の血漿成分を患部へ注射
PRP療法は注射によって行われ、入院や手術を必要とせず、施術時間も比較的短いのが特徴です。
また、軽度な症状に対して適応になるケースが多い傾向があります。

手術をしない新しい治療「再生医療」を提供しております。
テニス肘で再生医療を選ぶメリット
再生医療は、肘の腱・靱帯などに負担がかかるテニス肘に対する、身体への負担が少ない治療法として選択肢になっています。
では、どのようなメリットがあるのか、詳しく見ていきましょう。
身体への負担が少ない
再生医療は、身体にかかる負担を抑えられる点がメリットのひとつです。
手術では皮膚を切開し、場合によっては腱や靱帯の再接合・固定、人工物の挿入などを伴うケースがあります。
一方で、再生医療は注射または点滴で細胞や血液成分を投与するため、全身麻酔や長時間の手術を必要とせず、治療当日の身体的な負担を少なくできるのが特徴です。
とくに、早期の職場復帰やスポーツ活動の継続を望む方にとって、有力な選択肢のひとつになっています。
アレルギー反応や合併症のリスクが少ない
再生医療は、患者様本人の細胞を利用するため、免疫拒絶・アレルギー反応が起こるリスクが低い治療法です。
他人の組織を移植する場合と異なり、自己の細胞を使用することで、身体が異物として認識する可能性が極めて低くなります。
また、針を使った注射や点滴が中心で、大きな切開を伴わないため、術中・術後の出血や感染症などのリスクも抑えられます。
入院する必要がない
再生医療では入院を必要とせず、日帰りで治療ができる点も大きなメリットです。
手術を必要とする治療では、術前検査・麻酔・術後管理・痛みや腫れのケア・退院までのフォローが必要です。
一方、再生医療では脂肪採取・血液採取・細胞処理・注入という工程を、比較的短時間で済ませられます。
日帰りまたは短時間の通院で対応できることから、日常生活への影響を抑えられるのです。
仕事や日常生活への影響を心配せずに治療をスタートできるという点は、ライフスタイルを重視する方にとって有力な選択肢となります。
治療後の日常生活への影響が少ない
再生医療を用いたテニス肘の治療では、治療後に日常生活や軽度な動作への制限が手術ほど大きくない点もメリットです。
手術をした場合には、術後の固定・制限・リハビリテーションが長期間に及ぶことがあります。
注射や点滴で治療する再生医療では、治療直後から比較的早期に通常の生活に戻ることが可能です。
また、採取や注入する際のダメージも少ないため、術後の腫れ・痛み・回復期間も短く済みます。
趣味のスポーツや家事・仕事を継続しながら、これまでどおりに過ごしたいというニーズに応えられる治療法なのです。
テニス肘で再生医療を選ぶデメリット
再生医療に限らず、どのような治療にも留意すべき点があります。
ここでは、テニス肘に対して再生医療を検討する際に知っておきたい、主なデメリットについて見ていきましょう。
すべての人に効果があるとは限らない
再生医療の治療を受けたすべての人に明確な改善が現れるとは限りません。
症状の進行度や炎症の範囲、既存の腱や靱帯の損傷状態、年齢や基礎疾患の有無などが治療の影響に関わります。
さらに、再生医療は個々の細胞の状態に依存するため、冷凍しておらず質の良い細胞などでなければ、期待される組織修復のプロセスが十分に働かないケースもあります。
したがって、医師による詳細な診察や検査をもとに、適応や治療目的を慎重に確認することが大切です。
施術できるクリニックが限られる
再生医療は、専門的な知識と技術、厚生労働省への届出が必要とされる高度な医療行為です。
一般的な整形外科や接骨院などでは取り扱っていないケースが多く、施術を受けられる医療機関は限られています。
とくに、自己脂肪由来の幹細胞治療は、脂肪の採取・細胞の培養・加工・管理など、厳密な手続きと設備が求められるため、実施できるクリニックはごく一部なのです。
また、医療機関によって対応できる症状や、治療法の内容が異なる場合もあります。
治療を受けられないケースがある
再生医療は、すべての患者に適用できるわけではありません。
たとえば、すでに肘の関節に人工関節を挿入している場合には適用不可となっています。
また、以下のケースも安全性の観点から治療が見送られる場合があります。
- 重度の全身疾患がある方
- 感染症の有無が確認された方
- 妊娠中や授乳中の方
- 自己免疫疾患のある方
ただし、適応については医療機関ごとに異なる基準が設けられているため、事前に治療の可否や制限事項を確認しましょう。
再生医療が適応となる主な症状|テニス肘・ゴルフ肘について
再生医療では、おもに以下の症状が適応となります。
- 半月板損傷:膝の関節内にある軟骨組織が切れたり、裂けたりする状態
- 膝靭帯損傷:膝を安定させる靭帯が伸びたり、部分的に切れたりして不安定になるケガ
- 肘内側上顆炎(ゴルフ肘):肘の内側に痛みが出る、繰り返しの動作で起こる炎症
- 肘外側上顆炎(テニス肘):肘の外側に痛みが出る、前腕の使い過ぎによる障害
- 手首の靭帯損傷:手首の靭帯が伸びるなど部分的に断裂し、痛みや不安定感が生じる状態
- TFCC損傷:手首の小指側にある軟骨や靭帯が損傷し、回す動作で痛みが出る状態
- 足底腱膜炎:かかとの骨から足の裏にかけての腱に炎症が起き、歩くと痛みが出る症状
- 肩腱板損傷:肩を動かす筋肉や腱が損傷し、腕を上げにくくなったり痛みが出る状態
- 膝蓋腱炎(ジャンパー膝):膝の皿の下の腱に炎症が起き、跳んだり走ったりで痛む症状
- オスグッド・シュラッター病:成長期に膝の下が出っ張って痛くなるスポーツ障害です。
- 肉離れ(筋断裂):筋肉が強く伸ばされた際に、部分的に切れて痛みや腫れが起こる症状
- アキレス腱炎:かかとの上あたりのアキレス腱に炎症が起こり、歩行や運動時に痛む症状
- 足首靭帯損傷:足首の捻挫によって靭帯が損傷し、腫れや不安定感が生じる状態
- 腱鞘炎:指や手首を使いすぎることで腱の通り道に炎症が起き、動かすと痛む状態
以下では、テニス肘とゴルフ肘について詳しく解説します。
テニス肘(上腕骨外側上顆炎)
テニス肘は、前腕の伸筋群に繰り返しの負荷がかかることで、肘の外側にある腱の付着部に炎症や微細な損傷が生じる疾患です。
とくに、テニスのバックハンド動作で痛みが出やすいため、通称として広くテニス肘と呼ばれています。
実際には、タオルを絞る・ペットボトルのフタを開けるといった動作やパソコン操作、調理など、スポーツに限らず日常のシーンで痛みが現れるのが特徴です。
発症は、加齢による腱の変性が見られる中高年層に多く、悪化すると安静時にも痛みが続く場合があります。
軽度であれば保存療法が中心ですが、長期にわたって痛みが続く場合には、再生医療も治療の選択肢のひとつです。
ゴルフ肘(上腕骨内側上顆炎)
ゴルフ肘は、肘の内側に痛みが出る疾患です。
ゴルフのスイング動作で痛むため「ゴルフ肘」と呼ばれていますが、実際にはスポーツに限らず、手首を内側に曲げる・物を握る・ロープを引く・ドアノブをひねるといった動作でも痛みが誘発されます。
肘の上腕骨内側の骨の出っ張り「上顆(じょうか)」に繰り返しの負荷がかかり、腱に微細な損傷や炎症が起こるのが原因です。
主に、手作業を行う職業やスポーツ選手、家事を担う方にも多く見られる障害であり、放置すると慢性化するケースもあります。
保存療法で改善しない場合には、再生医療の適応が検討されます。

スポーツ外傷は⼿術しなくても治療できる時代です。
まとめ|再生医療でテニス肘の痛みを治療しよう
テニス肘は、日常の動作やスポーツの繰り返しによって肘の腱に負担がかかり、痛みを生じる疾患です。
保存療法などで改善が見られない場合、再生医療が選択肢になります。
再生医療は身体への負担を軽減し、手術を避けたい方や日常生活への影響をできるだけ抑えたい方の治療法のひとつです。
テニス肘は、早期の対応が痛みの悪化や長期化を防ぐ鍵になります。
医師と相談しながら、自分の症状に合った治療法を見つけていきましょう。
なお、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、テニス肘の治療に用いられている再生医療に関する情報の提供と簡易オンライン診断を実施しています。
肘の痛みでお悩みなら、ぜひご登録ください。
\無料オンライン診断実施中!/