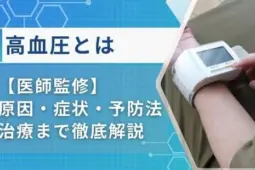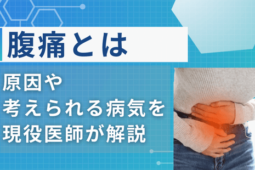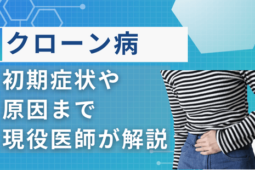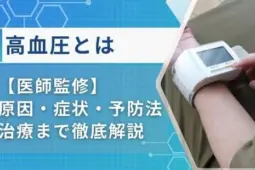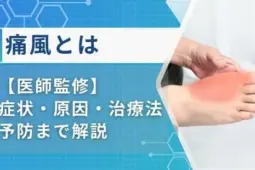- 内科疾患
- 内科疾患、その他
腎臓機能と高血圧を改善する方法|悪影響を及ぼす理由も現役医師が解説
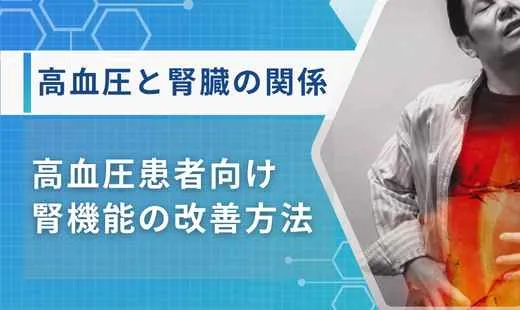
「高血圧だと腎臓に影響するって聞いたけど、血圧の高さはどう改善すればいいの?」
「そもそも両者にはどんな関係性があるのか知りたい」
このような疑問をお持ちの方も多いでしょう。
結論、高血圧の場合、腎臓に悪影響を及ぼします。血圧が高いと腎臓に負担がかかり腎機能が低下するほか、腎炎や慢性腎臓病などの病気を発症するリスクも高まります。
腎機能を健康な状態に保つには、高血圧を改善するための取り組みを日頃から継続することが大切です。
本記事では、腎臓と高血圧の関係や血圧の高さを改善する方法を解説します。高血圧患者が発症しやすい慢性腎臓病についても紹介しているので、参考にしてみてください。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
「高血圧と関連のある腎臓病」について気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
【基礎知識】腎臓と高血圧の関係
高血圧は、脳卒中や心筋梗塞といった命に関わる怖い病気を引き起こすことをご存じの方は多いかもしれません。
高血圧はそれだけでなく、腎臓にも負担を与え、徐々に腎臓の機能を低下させていきます。
この章では、高血圧と腎臓の働きについて解説した上で、高血圧が腎臓に与える影響を詳しく説明します。
高血圧とは
高血圧とは、一般的に「最高血圧が140mmHg以上もしくは最低血圧が90mmHg以上、またはその両方」である状態を指します。
血圧は変動しやすいため一時的にこの値を上回ることはよくあり、その場合は問題とはなりません。
腎臓の働き
腎臓は、尿を作る働きがあり、老廃物や余分な塩分を尿として体外に排出してくれます。尿の量を調整する機能もあり、体内の水分量を適切な状態に保ちます。
また、ホルモンを分泌し、血圧の調整を図るのも腎臓の重要な役割です。そのほかにも血液を作るホルモンも分泌しており、貧血にならないように体をサポートしています。
高血圧が腎臓に与える影響
高血圧の状態が長期間続くと、腎臓に負担を与え、腎機能の低下を引き起こします。
腎臓の機能が低下すると、腎炎(腎臓の炎症)を発症しやすくなります。また、慢性的な機能障害を引き起こし、慢性腎臓病と診断される方も少なくありません。
腎臓から血圧への逆の影響もあります。腎臓は血圧を調整するホルモンを分泌する働きがあるため、腎臓の機能が低下すると高血圧になりやすいです。
このように、腎臓と高血圧は密接な関係にあり、互いに影響し合って悪循環を招くことがあります。
高血圧患者が発症しやすい慢性腎臓病について
ここでは、高血圧患者が発症しやすい慢性腎臓病について、さらに詳しく解説します。
慢性腎臓病とは、腎機能の障害が慢性的に続いている状態です。
具体的には、機能異常による腎障害が3カ月以上持続または糸球体濾過量(glomerular filtration rate:GFR)の数値が60mL/min/1.73m²未満に低下した状態が3カ月持続している方を指します。(文献1)
健康な方の糸球体濾過量は100mL/min/1.73m²程度ですので、慢性腎臓病の方では正常値の60%ほどまで機能が低下している状態です。
国内に1330万人の慢性腎臓病患者が存在すると推定されています。これは成人の約8人に1人の割合であり、どなたでも発症しうる身近な疾患です。(文献2)
慢性腎臓病の原因
慢性腎臓病の原因にはさまざまなものがありますが、とくに高血圧や脂質異常症、糖尿病といった生活習慣病と深く関係しています。
また、加齢による腎機能低下も大きな原因の1つです。
|
慢性腎臓病の症状
慢性腎臓病の初期には自覚症状がないことが多いですが、進行すると息切れや倦怠感、むくみといった症状が現れます。
|
このような症状がみられた場合、腎臓が正常に機能していない可能性があるため治療が必要になります。
慢性腎臓病の治療
残念ながら慢性腎臓病で徐々に低下してしまった腎機能を完全に元に戻す治療法はありません。
慢性腎臓病と診断された場合に行う治療には大きく分けて、進行を抑える治療、そして悪化した腎機能を人工的に維持する治療の2つになります。
|
治療方法 |
治療内容 |
|---|---|
|
投薬治療 |
進行を抑える治療 慢性腎臓病の原因となった生活習慣病に対する投薬治療になります。 具体的には、高血圧をお持ちの方であれば降圧薬の内服が一般的です。 |
|
腎代替療法 |
腎機能を人工的に維持する治療 腎代替療法(血液透析や腹膜透析など)と呼ばれる治療になります。 先ほど紹介したような息切れや倦怠感、むくみといった症状を伴う場合にこのような治療が必要になる可能性があります。 |
高血圧患者が腎臓の機能を改善する方法
高血圧患者が腎臓の機能を改善させるには、日頃の生活習慣や、血圧の状態を適切に管理することが大切です。
具体的な改善策は主に以下の5つです。
- 食生活を見直す
- 禁煙する
- 糖尿病の治療を進める
- 血圧計測で目標値内にコントロールする
- 健康診断を受ける
順番に見ていきましょう。
食生活を見直す
高血圧を予防するために最も大切なことは、バランスの取れた食生活を送ることです。
日々の食事では炭水化物、たんぱく質、脂質といった三大栄養素が大部分を占めており、現代の日本人は特に、炭水化物や脂質を摂りすぎる傾向にあります。
このような食生活を続けてしまうと、血圧が上昇し、腎臓に負担がかかります。さらに、高血圧を防ぐためには、塩分を控えた食事も大切です。高血圧や慢性腎臓病を予防するための適切な塩分量は1日当たり6g未満とされています。
ところが、厚生労働省の調査報告書によると日本人が1日に摂取している塩分量の平均値は9.8gです。(文献3)平均すると1日当たり3.8gの減塩が必要となります。
禁煙する
喫煙は血圧を上げる要因となります。たばこに含まれる成分が血管の収縮や柔軟性の低下を引き起こすためです。
そのため、腎機能の改善を図るには、禁煙をして高血圧にならないようにする意識が大切です。
以下の方法が禁煙に役立ちます。
- 禁煙外来を受診する
- ニコチンパッチやガムを使う
無理のないペースで、たばこの本数を少しずつ減らしていきましょう。
糖尿病の治療を進める
高血圧と糖尿病は併発しやすく、国内にいる糖尿病合併高血圧患者は約90万人です。実際には、糖尿病患者の半数以上は高血圧を併発しています。(文献4)
糖尿病を発症している方は、糖尿病の治療に専念することで高血圧の改善につながり、ひいては腎臓機能の改善も期待できます。
糖尿病の主な治療は、糖質の量や血糖値の上昇をコントロールする食事療法と、インスリンを注射で投与する薬物療法です。
そのほかにも再生医療の選択肢があります。再生医療は患者様ご自身の細胞を活用した治療方法で、当院では脂肪由来の幹細胞を投与する治療を提供しています。
メール相談、オンラインカウンセリングを承っておりますので、詳しい治療方法を知りたい方はお気軽にお問い合わせください。
血圧計測で目標値内にコントロールする
血圧は家庭用の血圧計で簡単にチェックできるため、日ごろから計測する習慣を付けましょう。
日々血圧を意識しつつ、生活習慣の改善だけで下がりきらない場合には内科のある病院を受診してください。
降圧薬を服用しながら適切な値にコントロールする必要があります。
健康診断を受ける
慢性腎臓病を早期発見するには、定期的に健康診断を受けることが大切です。
慢性腎臓病の初期段階では、腎機能の低下を生じていても自覚症状がみられない場合がほとんどです。
そのため、早期発見のためには健康診断の血液検査で血清クレアチニン値や血中尿素窒素など、腎臓の機能に関わる項目をチェックしましょう。
これらの項目が異常と判定された場合には慢性腎臓病の可能性がありますので、早めに内科を受診し、早期の検査をおすすめします。
腎臓機能と高血圧の改善策を知って日々の過ごし方を見直そう
血圧と腎臓は密接な関係にあるため、それぞれの状態を良好に保つ意識が健康維持に繋がります。
高血圧は日頃の食生活の改善、喫煙習慣、運動習慣、定期的な血圧チェックにより、早期発見と適切な対策が可能です。
本記事で紹介した改善策を参考に、腎機能の向上を目指しましょう。
\無料オンライン診断実施中!/
腎臓と高血圧の改善に関するよくある質問
腎不全と高血圧に関連のあるレニンとはなんですか?
レニンは、血圧を上げる働きのあるホルモンを作るために必要な酵素です。つまり、レニンの分泌量が増えると、高血圧になりやすいです。
高血圧の状態が長期間続くと、腎機能が著しく低下し、正常に機能しなくなる腎不全に進行する可能性があります。
高血圧患者が腎臓を検査する方法は?
高血圧患者の腎臓状態をチェックする代表的な検査は以下のとおりです。
|
検査の種類 |
内容 |
|---|---|
|
尿検査 |
尿に含まれる成分を検査 たんぱく質や血液などが混入し、異常が認められると腎機能低下の可能性があります |
|
血液検査 |
クレアチニン(老廃物の一種)の濃度を検査 クレアチニン値の濃度が高いと腎臓の機能低下が疑われます |
|
画像検査 |
腎臓の形・大きさを画像で検査 腎臓の萎縮や腫瘍が確認できます |
|
腎生検 |
腎臓の組織を採取する検査 尿検査・血液検査・画像検査では判断困難な場合に正確に診断します |
検査は状態の進行具合や医師の判断によって選択されます。
低血圧の場合も腎臓に負担がかかりますか?
低血圧の状態が長く続くと、体内に酸素や栄養が行き届かなくなり腎臓にも負担を与えます。
参考文献
(文献1)
エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023|東京医学者 日本腎臓学会編集
(文献2)
エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2018|東京医学者 日本腎臓学会編集
(文献3)
令和5年国民健康・栄養調査結果の概要|厚生労働省