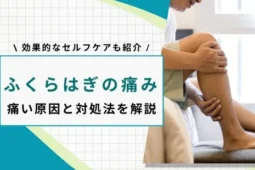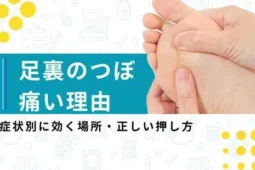- 足部、その他疾患
- 足部
下垂足のリハビリ方法を医師が解説|治し方もあわせて紹介

「足先がうまく持ち上がらず、歩くたびに引っかかる」
「下垂足の症状が長引いて辛い」
つま先が引っかかりやすくなり、歩行に支障をきたすことが特徴です。早く症状を改善したいと思っても、効果的なリハビリ法がわからず悩む方も少なくありません。
本記事では、下垂足のリハビリ方法と合わせて以下についても解説します。
- 下垂足のリハビリにおける注意点
- 下垂足のリハビリ以外での治し方
- 下垂足のリハビリでよくある質問
下垂足は正しい方法でリハビリを継続することで、症状の改善が期待できます。下垂足に悩んでいる方は、ぜひ最後までお読みください。
下垂足のリハビリ方法
| リハビリ方法 | 目的 | 方法例 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 足首・足指の運動 | 足関節や足趾の可動域を広げ、柔軟性と神経の働きを促進する | 足首の上下運動(背屈・底屈)、足指のグーパー運動 | 違和感がある場合は無理せず、小さな動きから始める |
| 筋力トレーニング | 足首を持ち上げる筋肉(前脛骨筋など)を強化する | チューブを使った足首の背屈運動、かかと上げ運動 | 正しいフォームを意識し、回数よりも一つひとつの動作を丁寧に行う |
| ストレッチ | 筋肉の緊張を和らげ、血行促進と柔軟性向上を図る | ふくらはぎ(腓腹筋・ヒラメ筋)のストレッチ、足の甲の伸展 | 反動をつけず、ゆっくりと呼吸を止めずに行う |
下垂足の改善には、筋肉と神経の機能回復を目指すリハビリが欠かせません。複数の運動をバランスよく取り入れるのが大切です。
- 足首・足指の運動
- 筋力トレーニング
- ストレッチ
リハビリを実施する場合は、自己流ではなく、医師の指導のもと行いましょう。
以下の記事では、下垂足の原因や治らないときの対処法を詳しく解説しています。
足首・足指の運動
| 種類 | 目的 | やり方(手順) | 回数目安 |
|---|---|---|---|
| 足首の背屈運動 | 足首を持ち上げる筋力の強化 | 椅子に座り、つま先をすね側に引き寄せて数秒キープ | 10回 |
| 足首の底屈運動 | ふくらはぎの筋力強化 | 椅子に座り、つま先を下に伸ばして数秒キープ | 10回 |
| 足首の回旋運動 | 足関節の柔軟性向上・血流促進 | 椅子に座り、足首を左右にゆっくり大きく回す | 各方向10回 |
| 足指の運動 | 足指の筋力とバランス感覚の改善 | 足指をグーパーしたり、タオルを足指で掴んで持ち上げる | 各動作10回 |
(文献1)
足首や足指を意識して動かすことは、下垂足リハビリの基本です。足首をゆっくりと上下させたり、足指を握ったり開いたりする運動は、関節の硬直を防ぎます。
足首や足指の運動を正しく行うことで、筋肉への神経伝達を促します。違和感があればすぐに中止し、医師に相談してください。
筋力トレーニング
| 種類 | 目的 | やり方(手順) | 回数目安 |
|---|---|---|---|
| タオルギャザー | 足指の筋力強化、細かな動きの改善 | 床にタオルを置き、足指でたぐり寄せる | 10回程度 |
| チューブトレーニング | 足首の背屈・底屈筋の強化 | セラバンドを足にかけ、足首を上下に動かす | 各方向10回程度 |
| カーフレイズ | ふくらはぎ・足首周囲の筋力強化 | つま先立ちになり、かかとを上下にゆっくり動かす | 10回程度 |
(文献2)
下垂足では、足を持ち上げる筋肉の力が低下しているため、筋力トレーニングを継続的に行う必要があります。とくに前脛骨筋や足指を動かす筋肉の運動は、歩行を安定させるのに不可欠です。
無理をすると、悪化する可能性があるため、負荷をかけすぎずに回数を増やすのがポイントです。
ストレッチ
| ストレッチ名 | 方法 | ポイント |
|---|---|---|
| ふくらはぎのストレッチ | 壁に手をつき、片足を後ろに引いてかかとを床につけたまま伸ばす | かかとは床につけたまま行う |
| アキレス腱のストレッチ | タオルを足裏にかけて両手で手前に引き、アキレス腱をゆっくり伸ばす | ゆっくりと引きすぎないよう注意 |
下垂足では筋肉が硬くなり、柔軟性が低下することで歩行のバランスが乱れやすくなります。
柔軟性の低下などを防ぐには、無理のない範囲でストレッチを続けることが大切です。代表的な方法には、壁を使ったふくらはぎのストレッチや、タオルを使ったアキレス腱のストレッチがあります。
動作中に反動をつけたり無理に引き伸ばしたりするのは逆効果になるため、ゆっくりと呼吸をしながら行いましょう。
下垂足のリハビリにおける注意点
リハビリは適切な方法で実践しないと効果を得られないだけでなく、かえって状態を悪化させる可能性があります。
リハビリにおける注意点は以下の6つです。
- 医師の診断・指示のもと行う
- 無理のない範囲で行う
- 継続して行う
- 転倒に注意する
- 装具は正しく着用する
- 日常生活に気を付ける
医師の診断・指示のもと行う
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原因の多様性 | 下垂足は神経障害、外傷、脳疾患など原因がさまざまで、リハビリ法も異なる |
| 自己判断のリスク | 誤ったリハビリにより、症状の悪化や回復の遅れを招く可能性がある |
| 医師の役割 | 医師は原因や症状の重さ、全身状態を考慮し、リハビリ計画を立てる |
| 実施時の注意点 | リハビリ開始前に医師の診断を受け、内容・頻度・負荷量などを指示に従って実施する |
(文献2)
下垂足の原因は腰や神経、脳の病気などさまざまであり、それぞれに適したリハビリ方法が異なります。
自己判断で始めると症状を悪化させるリスクがあるため、必ず医師の診断と指示に基づいて行いましょう。
無理のない範囲で行う
リハビリは無理をすると、かえって悪化する恐れがあります。強い違和感が出たときに我慢して続けると、炎症や筋肉の損傷を招き、回復が遅れます。
体調や症状の変化に応じて、運動量や頻度を調整するのも大切です。地道な継続が、少しずつ機能を取り戻すことにつながります。
継続して行う
下垂足のリハビリは、短期間で改善が見込めるものではありません。神経や筋肉の回復には時間がかかるため、地道な継続が重要です。
調子がよく感じる日でも無理はせず、必要以上の負荷はかけず、少しずつ取り組むようにしましょう。
転倒に注意する
下垂足の方はつま先が持ち上がりにくくなるため、ちょっとした段差でも転倒しやすくなります。転倒を防止するために、リハビリは段差や物がないことを確認してから実施します。
転倒によって骨折やさらなる神経障害が起きるリスクもあるため、無理のない範囲で取り組みましょう。
装具は正しく着用する
| 装具を着用する際の注意点 | 装具を正しく装着するべき理由 | ポイント |
|---|---|---|
| 装具は正しい方法で装着する | 誤った装着はリハビリ効果を妨げ、皮膚トラブルの原因になる | 医師や義肢装具士の指導に従って装着 |
| 装着時に皮膚の状態を確認する | 擦れやかぶれ、発赤が起こることがある | 違和感があれば装着を中止し相談 |
| 装具の自己判断による調整は行わない | 個人差により適正な位置や角度が異なるため、身体への負担やトラブルの原因となるおそれがあり | 必ず専門家の判断を仰ぐ |
| 装具は定期的なメンテナンスする | 装具の劣化や不衛生が、機能低下や皮膚トラブルを引き起こすことがある | 使用後は清潔に保ち、定期的に点検・交換 |
下垂足では、足首を安定させて歩行を助ける装具(足関節装具など)の使用が推奨されます。ただし、正しく装着しなければ、十分な効果が得られない可能性があります。
誤った装着により、皮膚トラブルや姿勢の乱れを招くこともあります。装具の選定や装着は、医師の指示に従い、不調を感じた際は速やかに相談しましょう。
日常生活に気を付ける
リハビリだけでなく、日常生活での足の使い方を意識するのも大切です。無理に走ろうとしたり、階段を上り下りしようとすると、転倒してしまい、症状が悪化する可能性があります。
また、長時間立ち続けたり無理な姿勢をとったりするのは避け、足は無理に使いすぎず、こまめに休憩を取りましょう。
下垂足のリハビリ以外での治し方
| 治療法 | 内容の概要 | 特徴 |
|---|---|---|
| 物理療法 | 電気刺激や温熱療法などで筋肉や神経を刺激 | 筋力維持や血流改善に有効。違和感の緩和も期待される |
| 薬剤療法 | ビタミンB12や消炎鎮痛薬などを使用 | 神経の修復や炎症を抑える効果がある |
| 手術療法 | 神経の圧迫除去や腱移行術などを行う | 重度の神経障害や回復困難な場合に選択される |
| 再生医療 | 幹細胞やPRP療法などで神経・組織の再生を促す | 新しい治療法で、組織修復を目的とする |
他の治療法を試す際は、必ず医師に相談しましょう。リハビリと併用して行われる治療法は以下の4つです。
- 物理療法
- 薬剤療法
- 手術療法
- 再生医療
リハビリ以外の治療法について解説します。
物理療法
| 効果 | 詳細 |
|---|---|
| 神経の刺激 | 電気刺激を与えることで、麻痺した神経や筋肉の働きをサポート |
| 筋肉の活性化 | 電気刺激で筋肉を動かし、筋力低下や萎縮の予防に役立つ |
| 血行促進 | 温熱やマッサージによって筋肉がほぐれ、血流が良くなり回復しやすくなる |
| 違和感の軽減 | 神経や筋肉の緊張を和らげることで、違和感の緩和が期待できる |
(文献3)
物理療法は、神経や筋肉に刺激を与えることで、血流や機能の回復を促す治療法です。主な方法としては、電気刺激療法や温熱療法などが用いられます。
リハビリとの併用で治癒効果の向上が期待できる一方、症状や持病の兼ね合いで行えない可能性もあるため、医師に相談した上で実施されます。また、自己流のマッサージや温熱療法は症状を悪化させる恐れがあるため、行わないようにしましょう。
薬剤療法
| 薬の種類 | 主な役割・効果 | 注意点 |
|---|---|---|
| ビタミンB群製剤 | 神経の機能を維持・回復を助ける(B1・B12など) | 副作用は少ないが、継続的な服用が必要 |
| 抗炎症薬(NSAIDsなど) | 神経の炎症を抑え、違和感や腫れを軽減 | 胃腸障害・腎機能障害のリスクがあるため長期使用に注意 |
| 鎮痛薬 | 神経痛やしびれなどの不快な症状を和らげる | 眠気・めまいの副作用が出ることがある |
| 神経賦活薬 | しびれ・麻痺などの神経症状を改善 | 効果に個人差があり、医師の判断に基づく処方が必要 |
薬剤療法では、下垂足の原因が神経の炎症や障害にある場合に行われます。神経の働きを助ける薬やビタミン製剤などを服用し、改善に向けて取り組みます。
薬剤はあくまでも補助的な役割であり、リハビリと並行した使用が大切です。薬は自己判断で調整せず、必ず医師の指示に従って服用しましょう。
手術療法
| 手術の種類 | 主な目的・効果 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 神経剥離術 | 圧迫されている神経の周囲組織を取り除き、神経の通り道を確保する | 違和感や麻痺の原因を直接除去できる | 手術リスク(感染・出血)あり |
| 神経縫合・移植術 | 断裂した神経をつなぐ、または別部位の神経を移植して再生を促す | 神経再生が期待でき、運動・感覚の改善に役立つ | 回復に時間がかかる |
| 腱移行術 | 正常な腱を移動させ、麻痺した筋肉の代用とする | 足首の動きを補い、歩行機能が改善されやすい | 術後にリハビリが必要 |
手術療法は、神経の圧迫や断裂などが原因である場合に検討されます。手術療法では、原因を直接的に治癒できる一方、感染症や術後にリハビリが必要になる可能性があります。
また、回復には時間がかかるため、慎重な判断と医師の説明を踏まえた選択が重要です。
再生医療
再生医療は、損傷した神経や筋肉の再生を目的としています。下垂足の原因となる神経障害の根本的な改善が目指せる可能性があり、手術を必要としないことから、感染症や出血を起こすリスクがありません。
再生医療は限られた医療機関でしか受けられないため、事前に実施施設を調べ、自分の症状が適応となるかを確認しましょう。
以下では、再生医療について解説しています。
リハビリで改善しない下垂足は医療機関を受診しよう
リハビリを続けても改善しない場合は、早めに医療機関を受診しましょう。下垂足は原因によって治療法が異なり、脳卒中など重大な病気が隠れていることもあります。
「リペアセルクリニック」では、リハビリで改善しない下垂足に対して、再生医療を活用し、傷ついた神経に回復を促します。
下垂足の症状にお悩みの方は、「メール相談」もしくは「オンラインカウンセリング」にて、当院へお気軽にご相談ください。
\まずは当院にお問い合わせください/
下垂足のリハビリでよくある質問
リハビリはどのくらいの期間続ける必要がありますか?
下垂足のリハビリ期間には個人差があります。症状の原因や重症度、年齢や体力などによって回復までの期間は大きく異なります。
一概にいつまでに治ると断言はできません。リハビリのスケジュールや目標設定については、医師の診断を受けた上で段階的に進めることが大切です。
リハビリ中に違和感があった場合はどうすれば良いですか?
リハビリ中に違和感やしびれなどが出た場合は、無理に続けず、すぐに中止して医療機関へ相談してください。違和感を抱えたままリハビリを継続すると、症状を悪化させる原因になりかねません。
自己判断せず、原因を確認しリハビリ内容を見直すことが大切です。
下垂足でも仕事は続けられますか
仕事の継続は、症状の程度と仕事内容によって異なります。デスクワーク中心であれば、無理な姿勢、長時間の座位は控えましょう。
立ち仕事がある場合は、医師と職場の両方に相談しましょう。
参考文献
辻慎太郎,安部惠子.「足底および足趾運動を活用したウォーミングアップの有効性」, pp.1-9, 発行年(2022)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsehs/67/4/67_199/_pdf/-char/ja?utm_source=chatgpt.com(最終アクセス:2025年4月13日)
Zacharia Isaac,(2023). Rehabilitation for Other Disorders. MSD ManualProfessional Version
https://www.msdmanuals.com/professional/special-subjects/rehabilitation/rehabilitation-for-other-disorders (Accessed: 2025-04-13)
小林 将生ほか.「腰椎椎間板ヘルニアにより下垂足を呈した症例に対する電気刺激を併用した自転車エルゴメーターの有効性」『理学療法科学』, pp.1-4,
https://www.jstage.jst.go.jp/article/rika/31/3/31_489/_pdf (Accessed: 2025-04-13)
Kyle L. McCormick, et al. (2024). Surgical Management of Foot Drop.Orthopedic Reviews
https://orthopedicreviews.openmedicalpublishing.org/article/120047-surgical-management-of-foot-drop?utm_source=chatgpt.com (Accessed: 2025-04-13)
Stella Stevoska, et al. (2021).Tendon transfer in foot drop: a systematic review.PMC Pud Central
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9925604/?utm_source=chatgpt.com (Accessed: 2025-04-13)