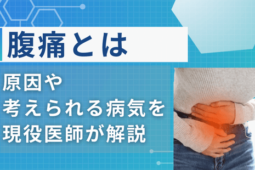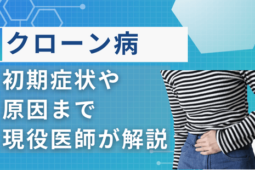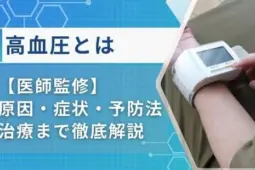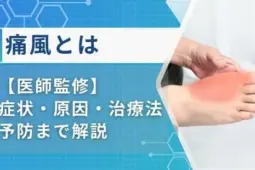- 内科疾患
- 内科疾患、その他
貧血の症状とは|疲れやめまいは貧血のサイン?原因と対策を医師が解説

「最近疲れやすい」
「立ちくらみやめまいが増えた」
そんな体調の変化を、年齢や忙しさのせいにしていませんか。
貧血は女性や子どもに多いイメージがありますが、実際には年代や性別を問わず、誰にでも起こりうる身近な不調です。初期のうちは症状が軽く、「なんとなく不調」という形で見過ごされやすいのも特徴です。
しかし、貧血を放置すると、日常生活の質が下がるだけでなく、背景に別の病気が隠れているケースもあります。早めに症状に気づき、原因を知ることが大切です。
本記事では、貧血でよく見られる症状や原因、対処の考え方について、医師の視点からわかりやすく解説します。
自分の体調を見直すきっかけとして、ぜひ参考にしてください。
また、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。貧血について気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
貧血の症状チェックリスト
もしかして貧血かも?と感じたときに確認できる、症状チェックリストを紹介します。
貧血の症状は「なんとなく体調が悪い」「いつもより疲れやすい」といった軽い不調から始まることが多く、見過ごされやすいのが特徴です。
まずは、日常生活の中で気づきやすいサインと、自分では気づきにくいサインに分けて確認してみましょう。
日常で気づきやすい貧血のサイン
次のような症状がある場合は、貧血の可能性が考えられます。
- 少し動いただけで疲れやすく、だるさが続いている
- 階段を上ると息切れする、朝起きるのがつらい
- めまいや立ちくらみを感じることがある
- 動悸がする、脈が速く感じることがある
- 胸が苦しくなり、深呼吸したくなることが増えた
- 集中力が続かず、ぼーっとすることが多い
- 頭痛が増えたように感じる
- 手足が冷えやすく、食欲が落ちている
- イライラしやすくなり、気分が不安定になりやすい
日常動作や体調の変化として現れやすいため、「疲れているだけ」と思い込まないよう注意が必要です。
自分では気づきにくい貧血のサイン
見た目や体の変化として現れる症状も、貧血のサインの一つです。
- 顔色や唇の色が薄く、「顔色が悪い」と言われる
- 爪が白っぽい、割れやすい、薄くなった
- まぶたの裏が白っぽく見える
- 肌がくすんで見える
- 髪が抜けやすくなった
- 氷を無性に食べたくなることがある
- 月経量が多い、偏食が続いている
- 胃腸の不調がある、貧血につながる薬を服用している
これらは自分では見逃しやすく、周囲に指摘されて気づくケースも少なくありません。
上記のチェックリストの症状に複数該当する場合は、貧血の可能性が考えられます。
ただし、このチェックリストはあくまで目安であり、医学的な診断に代わるものではありません。
該当項目が少なくても体調に不安がある場合や、症状が続いている場合は、自己判断せずに医療機関を受診しましょう。
貧血の症状【重症度別】
貧血の症状は、体内の酸素不足の程度によって現れ方が変わります。
ここでは、初期・中程度・重度の3段階に分けて、代表的な症状と注意点を解説します。
初期の貧血症状
初期の貧血では、体が酸素不足に適応しようとするため、症状は比較的軽く、「体調不良かな?」と見過ごされやすいのが特徴です。
| 症状 | 説明 |
|---|---|
| 疲れやすい | 酸素を運ぶヘモグロビンが不足し、筋肉や臓器に十分な酸素が届かないため、少しの動作でも疲労を感じるようになる。 |
| 集中力の低下 | 脳への酸素供給が不足することで、注意力や思考力が鈍りやすくなる。 |
| 顔色が悪くなる(青白くなる) | 血液の赤みが減るため、肌の色が青白く見えるようになる。 |
| まぶたの裏が白くなっている |
血液中の赤血球の減少により、通常は赤いはずの結膜が白っぽくなる。 |
この段階で休養を取り、食事内容を見直すことで改善する場合もあります。
症状が改善しない、悪化する場合は疾患の可能性があるため、軽視せずに医療機関を受診してください。
中程度の貧血症状
中程度になると、体の代償機能だけでは酸素不足を補えなくなり、日常生活に支障が出始めます。
| 症状 | 説明 |
|---|---|
| 動悸や息切れ | 酸素不足を補うために心臓が過剰に働き、心拍数が増加。軽い動作でも息切れしやすくなる。 |
| めまい、立ちくらみ | 脳への酸素供給が不足するため、姿勢を変えると一時的に脳が酸欠状態になり、ふらつきが起きる。 |
| 頭痛 | 酸素不足が脳の血管を刺激することで、締めつけられるような頭痛が起きることがある。 |
| 爪の変化 | 鉄不足により、爪が反り返る(スプーン状爪)・割れやすくなる・白くなるなどの変化が起こる。 |
| 吐き気 | 胃腸の働きが低下し、消化不良や胃もたれ、軽い吐き気を感じるようになることがある。 |
階段の上り下りや少し早歩きしただけで息切れを感じるようになったら要注意です。
この段階では、医療機関の受診を検討しましょう。
重度の貧血症状
重度の貧血では、生命維持に必要な臓器への酸素供給が著しく不足し、緊急性の高い症状が現れます。
| 症状 | 説明 |
|---|---|
| 失神 | 重度の酸素不足により、脳への血流が一時的に途絶え、意識を失うことがある。 |
| 胸の痛み | 酸素不足で心筋への負担が増し、狭心症のような症状を引き起こすことがある。 |
| 異常な食欲(氷が食べたくなる、など) | 鉄欠乏性貧血に特有の「異食症(ピカ症)」の一種。氷や土、紙など栄養にならないものを無性に食べたくなる。 |
| 赤色平滑舌(ハンター舌炎) | 鉄分不足によって舌乳頭が萎縮し、舌の表面が平らでツルツルになる。味覚障害などを伴うこともある。 |
この段階では入院治療が必要になる場合も多く、放置すると生命に関わる危険があります。
上記の症状が現れた場合は、速やかに医療機関を受診してください。
貧血の主な原因
貧血は「鉄分が足りないだけ」で起こるわけではありません。
食事内容や出血の有無、病気や薬の影響など、いくつかの原因が関係して起こることがあります。
以下の表に、主な原因とそれぞれの概要をまとめました。
| 原因 | 概要 |
|---|---|
| 鉄分不足 | 食事の偏りや吸収障害により、赤血球をつくる材料である鉄分が不足して起こる。最も多い原因。 |
| 体内での出血 | 月経過多、消化管出血、けがなどによる持続的な出血により、血液が失われて貧血になる。 |
| 慢性疾患 | がん、腎臓病、炎症性疾患などの慢性疾患があると、赤血球の産生が抑制されて貧血が起こりやすくなる。 |
| 造血機能の低下 | 骨髄の病気やビタミンB12不足などにより、赤血球をつくる働きそのものが弱まり、貧血を引き起こす。 |
原因がひとつの場合もあれば、複数が重なっているケースもあるため、症状が続く場合は原因を整理して考えることが大切です。
貧血の原因や対処法については、以下の記事でも詳しく解説しているのでご覧ください。
食事からの栄養不足
貧血の原因として最も多いのが、食事からの栄養不足です。
赤血球やヘモグロビンを作るためには、鉄分だけでなく、たんぱく質やビタミン類も必要です。とくに鉄分が不足すると、十分なヘモグロビンが作られず、体中に酸素を運ぶ力が低下します。
また、たんぱく質が不足すると赤血球そのものが作られにくくなり、ビタミンCが不足すると鉄の吸収効率が下がります。
偏食、食事量が少ない、ダイエット中、胃腸の不調で栄養が吸収されにくい場合などは、栄養不足による貧血が起こりやすくなるのです。
出血による鉄の喪失
体の中で出血が続いている場合も、貧血の大きな原因になります。出血によって血液と一緒に鉄分が失われるため、体内の鉄が不足してしまうのです。
女性では、月経量が多い「過多月経」によって慢性的な鉄不足になるケースが少なくありません。また、痔や胃潰瘍、大腸ポリープなどによる消化管からの出血は、自覚がないまま進行することもあります。
出血が続く状態では、いくら食事で鉄分を補っても追いつかないことがあるため、原因となる出血の有無を確認することが重要です。
病気や薬の影響
特定の病気や薬の影響によって、貧血が起こることもあります。
腎臓病では、赤血球を作る指令を出すホルモン(エリスロポエチン)が不足し、貧血になりやすくなるとされています。
また、がんや慢性炎症、自己免疫疾患があると、体の中で赤血球の産生が抑えられたり、鉄がうまく使われなくなるケースもあり、その結果、鉄分が足りていても貧血の症状が出ることがあるのです。
さらに、一部の薬剤によって造血機能が低下したり、消化管出血が起こりやすくなる場合もあります。
このような場合は、自己判断で対処せず、医師による評価と治療が必要です。
年代・性別で異なる貧血の特徴
貧血の症状や起こりやすい原因は、年代や性別によって異なります。
同じ「貧血」でも背景が違うため、自分の立場に合った注意点を知っておくことが大切です。
女性に多い貧血の症状と注意点
女性は月経や妊娠といった体の変化により、男性よりも貧血になりやすい傾向があります。
一般財団法人 女性労働協会によると、日本人女性の約40%が「鉄欠乏性貧血」または「かくれ貧血(潜在性鉄欠乏)」の状態にあり、とくに月経のある20〜40代では65%に上るとされています。(文献1)
自覚症状が少ないまま進行することもあるため、日常的な体調変化に注意が必要です。
月経による貧血(過多月経・生理中のめまい など)
月経のたびに血液とともに鉄分が失われるため、月経量が多い方は慢性的な鉄不足に陥りやすくなります。
生理中や生理前後に、めまい・立ちくらみ・強いだるさを感じる場合は、貧血が関係している可能性があります。
妊娠中・産後の貧血(妊婦・産後ママでよくある症状)
妊娠中は血液量が増える一方、胎児の成長に多くの鉄分を使うため貧血になりやすい時期です。産後も出産による出血や育児による栄養不足が重なり、貧血が続くことがあります。
重度の貧血を放置すると、低体重児や死産のリスクが高まると報告されているため、定期的な検査と早めの対処が重要です。
子宮筋腫など婦人科系疾患に伴う貧血
子宮筋腫や子宮内膜症などの婦人科疾患があると、過多月経によって慢性的な出血が続くことがあります。
その結果、鉄分が不足し、貧血を繰り返すケースも少なくありません。月経量が明らかに多い、年々症状がつらくなっている場合は、婦人科での相談が必要です。
成長期の子どもの貧血
成長期の子どもは、骨や筋肉が急速に発達するため血液量が増えるのにあわせて、多くの鉄分が必要となります。
食事から十分な鉄分を摂取できないと、赤血球がうまく作れず貧血を起こすケースがあるため注意が必要です。
さらに、部活動やスポーツで大量の汗をかくと鉄分が失われ、尿からも排出されやすくなります。加えて、激しい運動により足裏に繰り返し強い衝撃が加わると、赤血球が壊れる「運動性溶血」が起こるケースにも要注意です。
高齢者の貧血
高齢者の貧血は、鉄不足だけでなく慢性疾患や薬の影響など多様な要因が関わってきます。
鉄やビタミン不足に加え、腎臓病や炎症性疾患などの持病があると、造血機能が低下しやすくなるため注意しなければなりません。
さらに、高齢者の典型的な「顔色の悪さ」や「めまい」ではなく、基礎疾患の悪化として症状が現れるケースもあります。また、意識障害や呼吸困難、歩行障害、食欲不振などが見られる場合もあり、加齢のせいと自己判断して放置するのは大変危険です。
男性の貧血が疑われるときに注意したいポイント
男性は女性に比べると貧血の発症率は低いとされていますが、発症した際には注意が必要です。
男性の貧血の背景には、胃や十二指腸潰瘍、胃がん、大腸ポリープ、大腸がんなど、消化管からの出血が隠れているケースがあります。
とくに、便の色が黒っぽい、赤褐色が混じるといった変化がある場合は、消化管出血の可能性を疑うべきです。重大な病気が背景にあることもあるため、貧血の症状があれば医療機関で原因を特定しましょう。
貧血症状の対処法
貧血の症状が出たときは、まず体を休めて様子を見ることが大切です。
「日本臨床検査医学会」によると、成人男性13.0g/dl未満、成人女性と小児は12.0g/dl未満、高齢者は11.0g/dl未満が貧血とされています。(文献2)
自己判断で放置したり、誤った対処をしたりすると、症状が悪化することもあるのです。
ここでは、その場でできる対処法と、市販薬やサプリを使う際の注意点について解説します。
その場でできる対処法
めまいや立ちくらみ、動悸などの貧血症状を感じたときは、無理に動かず安全な姿勢をとることが最優先です。
1.まず、可能であればその場に座るか横になり、頭を低くして安静にしましょう。
2.衣服をゆるめ、深呼吸をして体を落ち着かせることも大切です。
3.急に立ち上がると症状が悪化しやすいため、回復するまではゆっくり行動してください。
4.水分不足があると症状が強く出ることもあるため、意識がはっきりしていれば、少量ずつ水分を補給します。
5.ただし、吐き気が強い場合や意識がぼんやりしている場合は無理に飲まないよう注意しましょう。
これらはあくまで一時的な応急対応です。
症状が繰り返し起こる、長引く、強くなる場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
市販薬やサプリを使う前に知っておきたいこと
貧血対策として、鉄分サプリや市販薬を検討する方も多いですが、原因を確認せずに使用するのは注意が必要です。
貧血には、鉄欠乏性貧血以外にも、病気や出血、薬の影響などさまざまな原因があります。鉄分が原因でない貧血の場合、サプリを飲んでも改善しないだけでなく、体に負担をかけることもあります。
また、鉄剤は胃の不快感、便秘、吐き気などの副作用が出ることもあるため、注意が必要です。
自己判断で長期間使用せず、症状が続く場合は血液検査を受けたうえで、医師の指示に従いましょう。
とくに、
- めまいや動悸が強い
- 数値を指摘されたことがある
- 月経過多や出血が続いている
- 男性や高齢者で貧血を指摘された
といった場合は、サプリに頼らず医療機関で原因を確認してください。
貧血の症状が出た時の受診目安
貧血は軽い不調として見過ごされがちですが、症状の出方や続く期間によっては、早めの受診が必要なケースもあります。
「様子を見てよい状態」と「医療機関での確認が必要な状態」を知っておくことが大切です。
受診が必要な症状・タイミング
次のような症状がある場合は、自己判断せずに医療機関を受診しましょう。
- めまいや立ちくらみが頻繁に起こり、日常生活に支障が出ている
- 動悸や息切れがあり、少し動いただけでも苦しくなる
- 強いだるさや疲労感が続き、休んでも回復しない
- 意識が遠のく、失神したことがある
- 胸の痛みや息苦しさを感じる
- 便が黒っぽい、血が混じるなど出血を疑う症状がある
- 月経量が明らかに多い、期間が長くなっている
- 健康診断で貧血を指摘され、再検査を勧められた
また、症状が軽くても数週間以上続いている場合や、以前より悪化していると感じる場合も受診の目安になります。
貧血の背景に、消化管出血や婦人科疾患、慢性疾患などが隠れていることもあるため注意が必要です。
何科を受診すべきか
貧血が疑われる場合、まずは内科を受診するのが一般的です。血液検査を行い、貧血の有無や重症度、原因の手がかりを確認します。
症状や背景によっては、以下の診療科が案内されます。
- 婦人科:月経過多、不正出血、妊娠・産後の貧血が疑われる場合
- 消化器内科:黒色便、血便、胃痛など消化管出血が疑われる場合
- 腎臓内科・血液内科:慢性疾患や原因不明の貧血が続く場合
どの科を受診すべきか迷う場合でも、まずは内科で相談すれば、必要に応じて適切な診療科を紹介してもらえます。
「この程度で受診していいのかな」と悩む段階でも、早めに相談してください。
\無料オンライン診断実施中!/
貧血の治し方|原因に合わせた治療とセルフケア
貧血の治療は、「なぜ貧血が起きているのか」という原因に合わせて行うことが大切です。
主な治療の柱は、食事療法・薬物療法・原因となる病気の治療の3つです。
症状の程度や体の状態によって、これらを組み合わせながら改善を目指します。
食事療法(鉄・たんぱく質・ビタミンCを意識した食べ方)
貧血の改善で基本となるのが、毎日の食事の見直しです。とくに鉄欠乏性貧血では、鉄分を効率よく摂ることが重要になります。
鉄分は、赤血球やヘモグロビンをつくる材料です。
鉄の吸収を高めるために、ビタミンCや、造血に関わるビタミンB12、良質なたんぱく質も一緒に摂ることが勧められます。
- 鉄分:レバー、赤身の肉魚介類、大豆製品、海藻類、緑黄色野菜
- ビタミンC:果物、野菜、いも類
- ビタミンB12:肉、魚、卵、乳製品
- たんぱく質:肉、魚、大豆製品、卵など
偏った食事を続けると、改善までに時間がかかるため、無理のない範囲でバランスを整えていくことが大切です。
貧血に良い食べ物をもっと知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
薬物療法(内服・注射・点滴)
食事だけでは改善が難しい場合や、貧血が中等度以上の場合には、薬による治療が行われます。
鉄欠乏性貧血では、まず鉄剤の内服が選ばれることが一般的です。代表的な薬には、フェロミア錠やリオナ錠などがあります。
ただし、鉄剤には吐き気や胃の不快感といった副作用が生じることがあります。内服が続けられない場合や、早急に鉄を補充する必要がある場合には、注射や点滴による治療に切り替えることも可能です。
また、腎臓の病気が原因の「腎性貧血」では、赤血球をつくる働きを助ける薬(ESA製剤)が使われることもあります。薬の選択や変更は、必ず医師の判断のもとで行いましょう。
貧血の点滴については、以下の記事も参考にしてください。
原因となる病気の治療
貧血は単独で起きているように見えても、背後には消化器系や婦人科系の病気による出血が隠れているおそれがあります。
胃潰瘍や大腸ポリープ、子宮筋腫、子宮内膜症などが代表的な疾患で、いずれも早期の治療が欠かせません。
たとえば、
- 胃潰瘍・大腸ポリープ・大腸がんなどの消化管疾患
- 子宮筋腫・子宮内膜症などの婦人科疾患
- 慢性腎臓病やリウマチなどの慢性疾患
こうした病気が原因の場合、鉄分を補うだけでは根本的な改善にはなりません。
原因となる病気を見つけ、適切な治療を行うことが再発防止につながります。
貧血の原因疾患については、以下の記事でも詳しく解説しています。
日常生活でできる予防・再発予防
貧血は、一度改善しても生活習慣によって再発することがあります。
そのため、治療と並行して、日常生活の見直しも大切です。
- 無理なダイエットや極端な食事制限を避ける
- 規則正しい食事を心がける
- 過度な飲酒やカフェインの摂りすぎに注意する
- 十分な睡眠と休息をとる
また、月経量が多い方や、妊娠・出産を控えている方は、定期的な血液検査で状態を確認することも予防につながります。
貧血を放置するとどうなる?
貧血は「ただの疲れ」や「体調不良」として見過ごされがちですが、放置すると深刻な健康リスクにつながるため要注意です。
貧血は血液中の赤血球やヘモグロビンが減り、体内に十分な酸素が行き渡らない状態であり、酸素不足を補おうと体は無理に働き続けます。
たとえば、心臓は酸素を全身に送ろうと拍動を早め、心臓に大きな負担がかかりますが、その状態が続くと心不全などの重大な疾患を引き起こすおそれもあるのです。
また、酸素や栄養が十分に届かないと体の回復力や抵抗力も低下し、風邪をひきやすくなったり、感染症にかかりやすくなったりもします。
さらに、頭痛・めまい・息切れ・集中力の低下といった症状が慢性化し、日常生活に支障が出るようになる点も見逃せません。
このように、貧血は放置すると症状の悪化や生活の質の低下にくわえ、命に関わる合併症につながる危険があります。
貧血の症状がある場合は、早めに医療機関を受診することが大切です。
貧血が与える仕事・家事・勉強への影響
貧血が続くと、脳や筋肉への酸素供給が不足し、次のような影響が出やすくなります。
- 集中力が続かず、仕事や勉強の効率が落ちる
- 少し動いただけで疲れやすく、家事が負担に感じる
- めまいや立ちくらみで外出や通勤が不安になる
- 頭がぼんやりして判断力が鈍る
このような状態が続くと、「やる気が出ない」「年齢のせい」と誤解されやすく、本人も不調に慣れてしまうことがあります。
しかし、原因が貧血であれば、適切な治療や対策で改善が期待できるでしょう。
貧血に隠れている病気(胃潰瘍・子宮筋腫・がん など)の可能性
貧血はそれ自体が病気というより、体の中で起きている異常の結果として現れる症状である場合も少なくありません。
とくに注意したいのが、次のようなケースです。
- 胃潰瘍や大腸ポリープ、大腸がんなどによる消化管からの出血
- 子宮筋腫や子宮内膜症などによる慢性的な出血
- がんや慢性炎症、腎臓病などによる造血機能の低下
これらの病気は、初期には自覚症状が乏しく、「貧血だけ」が最初のサインになることもあります。
貧血を繰り返している、治療しても改善しないといった場合は、背景に病気が隠れていないかを確認することが重要です。
まとめ|何となく不調を放置せず早めに相談しよう
貧血は「疲れやすい」「めまいがする」「だるさが続く」といった日常でもよくある不調から始まることが多い症状です。
そのため、忙しさや年齢のせいだと思い込み、見過ごされてしまうケースも少なくありません。
しかし、貧血を放置すると仕事や家事、勉強のパフォーマンスが低下するだけでなく、心臓への負担が増えたり、体の回復力や免疫力が落ちたりするおそれがあります。
また、胃潰瘍や子宮筋腫、がんなど、別の病気が隠れているサインとして貧血が現れることもあります。
応急的な対処で一時的に症状を和らげることはできても、根本的な改善には原因の特定と適切な治療が不可欠です。
症状が気になる場合や健康診断で指摘を受けた際には、早めに医療機関で検査を受けましょう。
当院「リペアセルクリニック」では、公式LINEにて再生医療に関する情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
登録してぜひお気軽にご利用ください。
\無料オンライン診断実施中!/
貧血の症状に関するよくある質問
貧血になりやすい人の特徴は何ですか?
貧血になりやすい人の特徴としては、女性・過度なダイエットをしている方・偏食の方が挙げられます。
女性は月経や妊娠・出産、授乳など、鉄分を失う機会が多いため、鉄欠乏性貧血になりやすいのです。
また、過度なダイエットをしている方や偏食の方も、栄養バランスが乱れると必要な栄養素が不足し、結果として貧血を起こす可能性が高くなります。
一方、慢性疾患や造血機能低下が原因の貧血の場合は、年齢や性別に関係なく発症するため、目立った特徴は見られません。
貧血の症状と低血圧・低血糖の違いはありますか?
貧血・低血圧・低血糖は、いずれも「めまい」「ふらつき」「だるさ」など似た症状が出るため、区別がつきにくいことがあります。
しかし、原因と体の中で起きていることはそれぞれ異なります。
まず貧血は、血液中の赤血球やヘモグロビンが不足し、全身に十分な酸素が運ばれない状態です。そのため、疲れやすさや息切れ、動悸、顔色の悪さなどが出やすくなります。
一方、低血圧は、血圧が低いために脳への血流が一時的に減少し、立ちくらみやふらつきが起こる状態です。長時間立っていた後や急に立ち上がったときに症状が出やすい傾向があります。
また、低血糖は、血液中のブドウ糖が不足することで、冷や汗、手の震え、強い空腹感、動悸などが現れます。食事を抜いた後や、糖尿病の治療中に起こることが多いです。
このように原因が異なるため、症状だけで判断するのは難しいといえます。
自己判断せず、症状が続く場合は医療機関を受診し、血液検査などで原因を確認しましょう。
貧血はどのくらいで治りますか?
貧血が治るまでの期間は、原因や重症度、治療方法によって異なります。
鉄欠乏性貧血の場合、鉄剤の内服や食事改善を始めると、早い方では2〜4週間ほどで自覚症状が軽くなることがあります。
ただし、体内の鉄を十分に補うには、3〜6カ月程度の治療継続が必要とされます。
一方で、出血が続いている場合や、病気が原因となっている貧血では、原因疾患の治療を行わないと改善しません。この場合、治療期間はさらに長くなることもあります。
また、症状が良くなったからといって自己判断で治療を中止すると、再発しやすい点にも注意が必要です。
医師の指示に従い、定期的な血液検査で数値を確認しながら治療を続けることが、回復への近道となります。