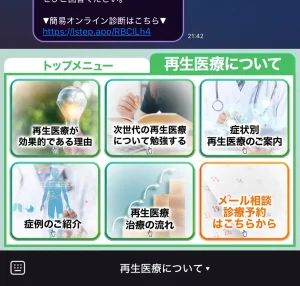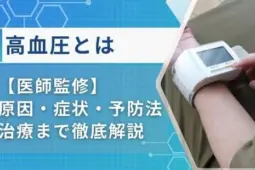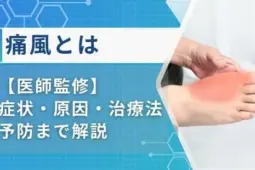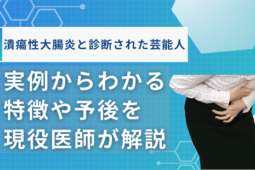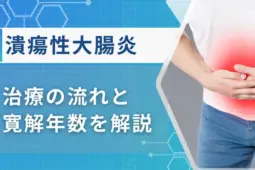- 内科疾患
- 内科疾患、その他
尿酸値が高いとなぜ痛風になる?基準値から治療法まで解説!

健康診断で「尿酸値が高い」と指摘され、不安に感じていませんか?
「痛風になったらどうしよう」「日常生活で何に気を付ければ良いの?」といったお悩みを持つ方もいらっしゃることでしょう。
尿酸値が7.0mg/dLを超えると、痛風のリスクが高まるだけでなく、さまざまな生活習慣病にもつながる可能性があります。
ですが、ご自身の尿酸値の状態を正しく理解し、適切な対策を行うことで、健康な毎日を送ることは十分に可能です。
本記事では、尿酸値の基準値や高くなる原因、そして具体的な治療法について、わかりやすく解説します。
なお、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
尿酸値や痛風について気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
尿酸値が高いと痛風発作のリスクが上昇!
尿酸値が高い状態、いわゆる「高尿酸血症」は、痛風発作を引き起こす要因です。
健康診断などで尿酸値の高さを指摘されたものの、自覚症状がないため放置してしまう方も少なくありません。
しかし、尿酸値が高い状態が続くと、ある日突然、足の指の付け根などに激しい痛みが走る痛風発作が起こる可能性があります。
ご自身の尿酸値がどのくらい危険な状態なのか、正しく理解しましょう。
8.0mg/dLは危険?尿酸値の診断結果を見てみよう
結論、尿酸値8.0mg/dLは注意が必要な状態です。
血液中の尿酸値が7.0mg/dLを超えると、高尿酸血症と診断され、合併症がある場合は8.0mg/dLを越えると治療が検討されます。(文献1)
この状態は、血液中に溶けきれなくなった尿酸が結晶化し、関節などに蓄積しやすくなることを意味します。
尿酸の結晶が関節に溜まると、痛風発作と呼ばれる激しい痛みを引き起こしてしまいますので、以下の表で、ご自身の尿酸値がどのレベルに該当するか確認してみましょう。
| 尿酸値(mg/dL) | 評価 | 状態 |
|---|---|---|
| 7.0以下 | 正常値 | とくに問題ありませんが、生活習慣には注意しましょう。 |
| 7.1~7.9 | 要注意 | 高尿酸血症の状態です。生活習慣の見直しが必要です。 |
| 8.0~8.9 | 危険 | 痛風発作のリスクが高い状態です。専門医への相談をおすすめします。 |
| 9.0以上 | 非常に危険 | いつ痛風発作が起きてもおかしくない状態です。直ちに医療機関を受診してください。 |
尿酸値が高い状態は、痛風だけでなく、腎臓の機能低下や尿路結石、さらには心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる病気のリスクも高めることが知られています。
尿酸値が高いことによる体への具体的な影響については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
尿酸値の基準値|痛風になりやすいライン
尿酸値の基準値は、一般的に7.0mg/dL以下とされています。この数値を超えると「高尿酸血症」と診断され、痛風やその他の生活習慣病のリスクが高まります。
尿酸値が9.0mg/dLを超えると、痛風発作が起こる可能性が非常に高くなりますが、尿酸値が7.0mg/dLを超えたからといって、すぐに痛風になるわけではありません。
高尿酸血症の状態が長く続くことで、徐々に尿酸の結晶が関節に蓄積し、ある日突然痛風発作として症状が現れます。
そのため、自覚症状がなくても健康診断で尿酸値の高さを指摘された場合は、早期に生活習慣の改善に取り組むことが重要です。
男女別|尿酸値の基準値
尿酸値の基準値は、男女で若干異なります。
一般的に、男性の方が女性よりも尿酸値が高くなる傾向があります。
| 性別 | 基準値(mg/dL) |
|---|---|
| 男性 | 3.7~7.8 |
| 女性 | 2.6~5.5 |
(文献4)
男性の尿酸値が女性より高い理由は、男性ホルモンに尿酸の排泄を抑える働きがあるためです。
一方、女性ホルモン(エストロゲン)には、腎臓からの尿酸の排泄を促す働きがあります。そのため、女性は男性に比べて尿酸値が低く痛風になりにくいとされています。(文献5)
しかし、注意が必要なのは閉経後の女性です。閉経を迎えると女性ホルモンの分泌が減少し、尿酸値が上昇しやすくなります。
その結果、閉経後の女性は痛風のリスクが高まるため、女性も食生活や運動習慣に気を配ることが大切です。
年代別|尿酸値の基準値
尿酸値に、年代別の明確な基準値は設けられていません。しかし、年齢を重ねるにつれて尿酸値は上昇する傾向にあります。これは加齢に伴う腎機能の低下が影響していると考えられています。
腎臓は尿酸を体外へ排出する重要な役割を担っているため、その機能が低下すると、体内に尿酸が溜まりやすくなるのです。
実際に、日本の国民健康・栄養調査によると、高齢になるほど血清尿酸値の増加が報告されています。(文献5)
とくに、40代以降の男性や閉経後の女性は、尿酸値が高くなりやすい傾向があるため、定期的な健康診断でご自身の数値を把握し、生活習慣を見直しましょう。
若い世代であっても、食生活の乱れや運動不足、ストレスなどにより尿酸値が高くなるケースも増えていますので、油断は禁物です。
尿酸値が高くなる原因
尿酸値が高くなる主な原因としては、以下のようなものが挙げられます。
- プリン体の過剰摂取
- 尿酸の排泄低下(腎機能低下)
- 飲酒
- 肥満・メタボリックシンドローム
- ストレスや過度な運動
- 遺伝的要因
尿酸は、私たちの体内で「プリン体」という物質が分解されて作られる老廃物です。通常であれば、尿酸は腎臓から尿と一緒に排泄され、体内の量は一定に保たれています。
尿酸が過剰に作られたり、うまく排泄されなくなり、血液中の尿酸値が上昇する原因について解説します。
プリン体の過剰摂取
尿酸の元となるプリン体は、細胞の核に含まれる成分で、私たちの体内でも生成されますが、食事から摂取されるものも少なくありません。
とくに、レバーや魚卵、干物など、プリン体を多く含む食品を過剰に摂取すると、体内で作られる尿酸の量が増え、尿酸値が上昇する原因となります。
一般的に、食品100gあたりに含まれるプリン体が200mg以上のものはプリン体の多い食品とされています。(文献1)
日常的にこれらの食品を好んで食べている方は、注意が必要です。
以下に、プリン体を多く含む食品の例をまとめましたので、ご自身の食生活を振り返ってみてください。
| 食品カテゴリ |
食品カテゴリ |
プリン体含有量(mg/100g) |
|---|---|---|
| 肉類 | 豚レバー | 284.8 |
| 鶏レバー | 312.2 | |
| 牛レバー | 219.8 | |
| 魚介類 | マイワシ干物 | 305.7 |
| 大正エビ | 273.2 | |
| イサキ白子 | 305.5 | |
| アンコウ肝 | 399.2 | |
| 魚卵 | イクラ | 15.7 |
| スジコ | 2.9 | |
| その他 | 干し椎茸 | 379.5 |
| ビール酵母 | 2995.7 |
ただし、プリン体の摂取を極端に制限する必要はありません。大切なのは、バランスの取れた食事を心がけ、プリン体の多い食品は控えめにすることです。
プリン体と尿酸値の関係については、こちらの記事も参考にしてください。
\無料オンライン診断実施中!/
尿酸の排泄低下(腎機能低下)
体内の尿酸は、約70%が腎臓から尿として排泄されます。(文献1)
そのため、腎臓の機能が低下すると、尿酸を十分に排泄できなくなり、体内に蓄積して尿酸値が上昇します。
腎機能が低下する原因はさまざまですが、加齢のほか、糖尿病や高血圧といった生活習慣病が大きく関わっています。
これらの病気は、腎臓の血管にダメージを与え、徐々に腎機能を悪化させてしまうのです。
また、一部の降圧薬や利尿薬なども、尿酸の排泄を妨げることがあります。
現在、なんらかの薬を服用している方で尿酸値が高い場合は、一度かかりつけの医師に相談してみることをお勧めします。
腎機能の低下は自覚症状が現れにくいため、定期的な健康診断で腎臓の状態をチェックすることが非常に重要です。
飲酒
アルコールは、尿酸値を上げる大きな要因の一つです。
その理由は、主に3つあります。
| 理由 | 説明 |
|---|---|
| アルコールが尿酸値を上げる |
アルコールが肝臓で分解される際に、尿酸の元となるプリン体が生成され、体内の尿酸量が増加します。 |
| アルコールが尿酸の排泄を妨げる |
アルコールは腎臓からの尿酸排泄を抑制します。 |
| 利尿作用による脱水 |
アルコールの利尿作用により体内の水分が失われ、血液が濃縮されることで一時的に尿酸値が上昇します。 |
お酒の種類に関わらず、アルコールの摂取量が多いほど尿酸値は上がりやすくなります。
休肝日を設けるなど、適度な飲酒を心がけることが大切です。
肥満・メタボリックシンドローム
肥満、とくに内臓脂肪が多いメタボリックシンドロームの状態は、尿酸値を上昇させることがわかっています。
内臓脂肪からは、インスリンの働きを悪くする物質が分泌され、インスリンの働きが悪くなると、体は血糖値を下げるためにより多くのインスリンを分泌しようとします。
この血液中のインスリンが過剰になった状態(高インスリン血症)が、腎臓での尿酸の排泄を妨げ、結果的に尿酸値を上げてしまうのです。
また、肥満の方は、過食や運動不足の傾向があり、それ自体が尿酸値を上げる原因にもなります。
肥満を解消し、適正体重を維持することは、尿酸値のコントロールにおいて非常に重要です。
BMI(肥満度を表す体格指数)が25以上の方は、まずは減量から始めてみましょう。
BMIの計算方法:体重(kg) ÷ {身長(m) × 身長(m)}
ストレスや過度な運動
意外に思われるかもしれませんが、生活習慣全般の乱れによるストレスや激しい運動も尿酸値を上げる一因となることが示唆されています。
また、短距離走や筋力トレーニングといった、息が上がるほどの激しい運動(無酸素運動)を行うと、体内でエネルギーが大量に消費されます。
このとき、エネルギーの燃えカスとしてプリン体が多く作られ、結果として尿酸値が一時的に上昇します。
ですが、もちろん健康維持のために運動は欠かせません。
ウォーキングやジョギング、水泳といった、軽く汗ばむ程度の有酸素運動であれば、肥満の解消にもつながり、尿酸値の改善に効果的です。
ご自身の体力に合わせて、無理のない範囲で運動を続けましょう。
遺伝的要因
生活習慣に気をつけていても、尿酸値が高くなってしまう場合があります。
その背景には、遺伝的な要因が隠れていることもあります。
尿酸を体内で作る能力や、腎臓から排泄する能力には個人差があり、これらは遺伝によってある程度決まると考えられています。
実際に、家族に痛風の患者様がいる方は、そうでない方に比べて痛風になりやすいとされています。(文献1)
ご自身の体質を理解し、人一倍、食生活や運動習慣に気をつけることが重要です。
食事と痛風の関係については、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。
\無料オンライン診断実施中!/
痛風と高尿酸値の治療法
尿酸値が高いと指摘された場合、どのような治療法があるのでしょうか。
高尿酸血症や痛風の治療の基本は、生活習慣の改善です。
具体的には、「食事療法」「運動療法」「薬物療法」の3つが柱となります。
- 食事療法:プリン体を含む食品を控え、バランスの良い食事を心がける。
- 運動療法:有酸素運動を中心に肥満の改善を目指す。
- 薬物療法:生活習慣の改善で効果が不十分、または痛風発作の既往がある場合に尿酸降下薬を使用。
食事療法では、プリン体を多く含む食品を控え、バランスの取れた食事を心がけることが基本です。
また、水分を十分に摂取し、尿の量を増やすことで、尿酸の排泄を促せます。
運動療法では、ウォーキングなどの有酸素運動を中心に、肥満の解消を目指します。
これらの生活習慣の改善だけでは尿酸値が十分に下がらない場合や、すでに痛風発作を起こしたことがある場合には、尿酸値を下げる薬(尿酸降下薬)を用いた薬物療法が行われます。
治療法の詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
【関連記事】
痛風治療と生活習慣の見直してみる?!今すぐ始める具体的ステップ
尿酸値を下げて腎臓の健康を守る!今すぐ始めたい痛風・腎臓病予防の生活習慣
まとめ|尿酸値が高いときは放置せず早めに医療機関へ!
尿酸値が7.0mg/dLを超える高尿酸血症は、痛風発作のリスクを高めるだけでなく、腎機能低下や尿路結石、心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる病気の危険性も上昇させます。
とくに尿酸値8.0mg/dL以上の方や、痛風発作の既往がある方は、早急な対応が必要です。自覚症状がないからといって放置せず、健康診断で異常を指摘された場合は、専門の医療機関を受診しましょう。
食事療法や運動療法といった生活習慣の改善は、尿酸値をコントロールする基本です。高尿酸血症は腎機能の低下や動脈硬化のリスクを高め、放置すると全身の健康に影響を及ぼします。
痛風発作による関節の痛みだけでなく、高尿酸血症に伴う生活習慣病は、ひざや股関節など他の関節疾患のリスクも高めることが知られています。
当院「リペアセルクリニック」では、変形性ひざ関節症や股関節症など、加齢や生活習慣によって生じる関節疾患に対して再生医療を提供しています。
膝や股関節の痛みでお悩みの方は、当院の公式LINEで発信している再生医療の情報をご確認してください。
尿酸値と痛風に関するよくある質問
尿酸値が高いと必ず痛風になりますか?
尿酸値が高い「高尿酸血症」の状態であっても、必ずしも全員が痛風になるわけではありません。
痛風発作を起こすのは、高尿酸血症の方の一部です。
しかし、尿酸値が高い状態が長く続くほど、また、数値が高ければ高いほど、痛風発作のリスクは確実に上昇します。
自覚症状がないからといって安心せず、尿酸値が高いと指摘されたら、将来の痛風発作を予防するために、生活習慣の改善に取り組むことが大切です。
尿酸値は下がっても再び上がることはありますか?
あります。食事療法や薬物療法によって一度尿酸値が下がっても、治療を中断したり、生活習慣が元に戻ってしまったりすると、再び尿酸値は上昇します。
薬物療法は、高血圧の薬と同様に、継続して服用することで尿酸値をコントロールするものです。
自己判断で薬をやめてしまうと、尿酸値が再上昇し、痛風発作を繰り返す原因となります。
医師の指示に従い、根気強く治療を続けることが重要です。
尿酸値が高いと痛風以外にも病気のリスクはありますか?
高尿酸血症の方は、痛風以外の病気リスクもあります。
血液中に溶けきれなくなった尿酸の結晶は、関節だけでなく、腎臓や尿路にも蓄積します。
腎臓に蓄積すると腎機能が低下する「痛風腎」に、尿路に蓄積すると激しい痛みを伴う「尿路結石」になることがあります。
さらに、高尿酸血症は、高血圧や脂質異常症、糖尿病といった生活習慣病を合併しやすく、心筋梗塞や脳卒中など、命に関わる動脈硬化性疾患のリスクを高めることも明らかになっています。(文献1)
参考文献
(文献1)
高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン 第3版|日本痛風・尿酸核酸学会
(文献2)
高尿酸血症・痛風の診断と治療|日本内科学会雑誌
(文献3)
共用基準範囲に関するガイドライン|公益社団法人 日本臨床検査標準協議会
(文献4)
Analysis of a Japanese Health Insurance Database|Journal of Clinical Medicine
(文献5)
国民健康・栄養調査結果|厚生労働省