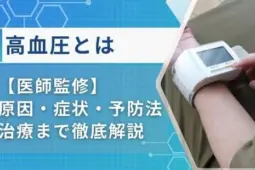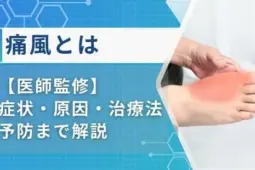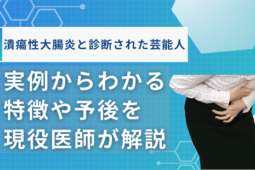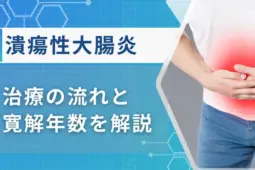- 内科疾患
- 内科疾患、その他
高い尿酸値とは?基準値の目安・原因・合併症のリスクを現役医師が解説
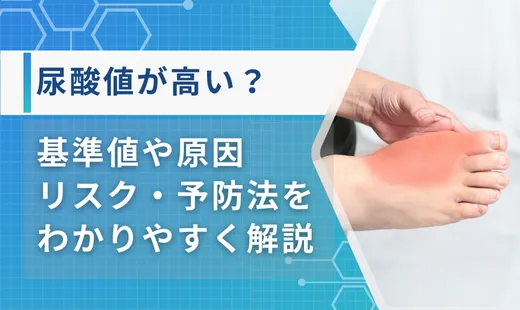
「尿酸値が高いと言われたら、何をすれば良いの?」
「そもそも尿酸値が高くなる原因ってなに?」
このような悩みを抱える方は少なくありません。
尿酸値が高い状態を放置すると、痛風や腎臓病のリスクが高まります。(文献1)
しかし、正しい知識と対策を身につければ、尿酸値はコントロール可能です。
本記事では、高尿酸値の基準や原因、合併症のリスク、効果的な予防法をわかりやすく解説します。生活習慣を見直し尿酸値を下げて、健康な体を目指しましょう。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
高い尿酸値について気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
高い尿酸値とは
尿酸値の正常範囲と、高尿酸血症と診断される基準は以下のとおりです。(文献2)
- 尿酸値の正常範囲(4.0〜7.0mg/dL)
- 高尿酸血症の診断基準(7.0mg/dL以上)
それぞれの診断基準について詳しく解説します。
尿酸値の正常範囲(4.0〜7.0mg/dL)
尿酸値は血液検査で測定され、正常範囲は4.0〜7.0mg/dLです。(文献3)
尿酸は、プリン体の代謝によって生成される老廃物で、通常は尿として排出されます。
しかし、食生活や生活習慣の影響で過剰に生成されたり、排出が滞ったりすると血液中の尿酸濃度が上昇します。
とくに、7.0mg/dLに近い場合は生活習慣の見直しが必要です。
高尿酸血症の診断基準(7.0mg/dL以上)
尿酸値が7.0mg/dLを超えた値は、高尿酸血症と診断される数値です。(文献2)
尿酸値が高い状態が続くと、血液中の尿酸が結晶化し、関節や腎臓に悪影響を及ぼす可能性があります。
とくに、痛風のリスクが高まり、足の親指の付け根などに突然激しい痛みが生じるケースもあります。
また、高尿酸血症は、自覚症状がほとんどないケースもあるため、気づいたときには合併症が進行しているケースも少なくありません。
健康診断で尿酸値が基準を超えていたら、食事や運動習慣の見直しを行い、医療機関を受診して医師に相談しましょう。
尿酸値が高くなる原因
尿酸値が上昇する主な原因は、以下のとおりです。
- プリン体が多い食材・飲み物を摂取している
- 腎臓の機能が低下している
- 遺伝や体質が影響している
いずれの場合も血中尿酸濃度が上がり、痛風や腎機能障害のリスクが高まります。
それぞれの原因を詳しく解説します。
プリン体が多い食材・飲み物を摂取している
尿酸は、プリン体が分解される際に発生する老廃物です。
プリン体は肉類や魚介類に多く含まれ、レバー・干物・ビールの摂取が多いと尿酸値が上がりやすくなります。(文献1)
そのため、高尿酸値を防ぐには、プリン体の多い食品を控えることが重要です。
腎臓の機能が低下している
尿酸は腎臓を通じて尿として排出されます。しかし、腎機能が低下すると排出が滞り、血液中の尿酸濃度が上昇します。(文献4)
また、水分不足や過度なアルコール摂取は腎臓の働きを悪化させ、尿酸の排出を妨げる要因です。
そのため、尿酸をスムーズに排出するには、こまめな水分補給が欠かせません。
目安として1日2リットル程度の水を飲むと、尿の量が増え、尿酸が排出されやすくなります。(文献2)
遺伝や体質が影響している
尿酸値や痛風の発症には、体質や遺伝的要因が関与しています。
尿酸の生成や排泄を担う酵素やタンパク質は遺伝子で決まり、特定の遺伝子変異があると体内に尿酸が蓄積しやすくなります。
米国の大規模研究でも、遺伝的要因が尿酸値に与える影響は男性の場合は23.8%、女性の場合は40.3%関与すると示されています。(文献5)
そのため家族に高尿酸血症や痛風の既往がある場合は、生活習慣の見直しと定期的な検査で早期発見・予防に努めることが重要です。
尿酸値が高い食べ物・飲み物一覧
尿酸値を上げる食品の成分として以下の3つがあります。(文献6)
- プリン体
- フルクトース(果糖)
- アルコール
これらが多く含まれる食べ物や飲み物を摂取すると尿酸値が高くなります。
プリン体含有量が300mg以上(100gあたり)の食べ物は以下のとおりです。(文献2)
- 鶏レバー
- 干物(マイワシ)
- 白子
- あんこう
- 太刀魚
プリン体は魚類に多く含まれる傾向があります。
プリン体が多い飲み物は以下の表のとおりです。(文献7)
|
飲料名 |
プリン体含有量(100mlあたり) |
|---|---|
|
ビール |
約5〜7mg |
|
発泡酒 |
約3〜4mg |
|
地ビール |
約7〜17mg |
ワインやウィスキーなどの他のアルコール飲料は、プリン体含有量が約0.5mg(100mlあたり)と少ない値です。しかし、アルコール自体が尿酸を上げるため飲み過ぎには気をつけてください。
高い尿酸値を下げる食べ物・飲み物一覧
尿酸値を下げる食品の成分は以下のとおりです。(文献6)
- タンパク質(乳製品)
- ビタミンC
- ポリフェノール
- フラボノイド(植物由来の有機化合物)
- 食物繊維
これらが多く含まれる食べ物や飲み物を摂取すると尿酸値を下げる効果が期待できます。プリン体含有量が50mg以下(100gあたり)の食品は以下の表のとおりです。(文献2)
- 野菜類全般
- 米
- 卵
- 乳製品
- 豆類
- きのこ類
- 豆腐
プリン体が低い食品をバランスよく取り入れて、尿酸値を上げない食事を心がけましょう。
また、尿酸値を下げる飲み物としてよく注目されるのがコーヒーです。(文献8)
実際に、コーヒーの摂取が尿酸値を下げる可能性を示す研究がある一方で、反対に尿酸値を上昇させる結果を示す報告もあります。
そのため、コーヒーを飲む際は、体質や摂取量によって影響が異なる可能性があると考え、飲み過ぎには気をつけてください。
高い尿酸値の方が発症しやすい合併症4選
尿酸値が高い状態を放置すると、体内で尿酸が結晶化し、さまざまな合併症を引き起こします。
合併症の主な症状とリスクは以下の表のとおりです。(文献4)
|
合併症 |
主な症状 |
リスク |
|---|---|---|
|
痛風 |
関節の激しい痛み・腫れ |
生活の質の低下 |
|
腎機能障害 |
むくみ・倦怠感・尿量の変化 |
腎不全のリスク |
|
動脈硬化症 |
血管の狭窄・高血圧 |
心筋梗塞・脳卒中のリスク |
|
尿路結石 |
突然の激しい痛み・血尿 |
尿路閉塞・感染症のリスク |
これらの合併症は放置すると悪化し、日常生活に支障をきたす可能性があります。
初期段階では自覚症状が少ないため、定期的な健康診断と早めの対策が重要です。
それぞれの合併症について詳しく解説します。
痛風
尿酸値が高い状態が続くと、血液中の尿酸が結晶化し、関節に沈着して痛風を引き起こします。(文献4)
とくに、足の親指の付け根に激しい痛みが生じるのが特徴です。
痛風発作は突然起こり、数日間歩くのが困難になるほどの強い痛みが続く場合もあります。
発作を防ぐには、日常的に尿酸値をコントロールするのが重要です。
腎機能障害
尿酸値の高い状態が続くと腎臓に負担がかかり、腎機能が低下する可能性があります。(文献4)
尿酸が尿路に結晶として沈着すると、尿の流れを妨げるトラブルが起こりやすくなるため、腎臓結石や腎不全の原因になるケースもあります。
腎機能障害は初期段階では自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに進行する場合がほとんどです。
水分を十分に摂って尿量を増やし、腎臓への負担を減らしましょう。
動脈硬化症
高尿酸値は血管に悪影響を及ぼし、動脈硬化のリスクを高めます。(文献2)
動脈硬化が進行すると血管が狭くなり、心筋梗塞や脳梗塞のリスクも上昇するとされています。
食事では塩分や脂質を控え、適度な運動を習慣化して血流を促進しましょう。
また、ストレスは血管を収縮させる要因となるため、リラックスする時間を持つことも大切です。
尿路結石
尿酸が体内に溜まりやすくなると、腎臓から膀胱の間で結晶化し、尿路結石を引き起こすケースがあります。(文献1)
尿路結石は排尿時の痛みや血尿、頻尿などの症状を伴い、進行すると感染症の原因になる場合もあります。
尿路結石を予防するには、尿酸値を下げる治療に加えてこまめな水分補給が重要です。
アルコールや糖分の多い飲み物を控え、水を多く飲むことで尿の量が増え、尿酸の結晶化を防ぎやすくなります。
高い尿酸値を下げる方法
尿酸値が高い状態を放置すると、痛風や腎機能障害などの合併症を引き起こすリスクが高まります。
しかし、生活習慣を改善すれば尿酸値をコントロールし、リスクを軽減できます。
尿酸値を下げるために有効な対策は主に以下の3つです。
- 食事療法|アルコール制限や水分摂取
- 運動療法|有酸素運動やストレス対策
- 薬物療法|尿酸の産生を抑える薬と排出を促す薬
それぞれ詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
食事療法|アルコール制限や水分摂取
食事は、野菜や海藻など尿酸値が低い食品を意識してバランスよく取り入れましょう。
さらに、ゆっくりよく噛んで食べることで過食を防ぎ、消化機能の改善にもつながります。
アルコールは尿酸値を上昇させる主な要因の1つです。とくに、ビールはプリン体を多く含むため、摂取量が増えると尿酸が生成されやすくなります。
アルコール自体も尿酸の排出を妨げ、尿酸値をさらに押し上げます。(文献9)そのため、尿酸値を下げるにはアルコール摂取量を減らすことが重要です。
また、水分不足は尿酸の排出を妨げて尿酸値を上げる原因となります。
1日2リットル程度の水分補給を意識すると排出がスムーズになり、尿酸値の管理に役立ちます。
運動療法|有酸素運動やストレス対策
ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は代謝を高め、尿酸の排出を促進します。
しかし、激しい運動は尿酸値を上げる可能性があるため注意が必要です。(文献2)
1回30分程度の軽い運動を週3回以上取り入れることが望ましく、無理なく習慣化すると健康維持につながります。
さらに、リフレッシュや休養の時間を意識的に取り入れ、日常的にストレスを発散する習慣を持つことが安定した尿酸値の維持に役立ちます。
薬物療法|尿酸の産生を抑える薬と排出を促す薬
薬物療法は合併症のリスクが高い場合に用いられ、尿酸の産生を抑える薬と排出を促す薬の2つに分けられます。
治療目標は、尿酸値を6.0mg/dL以下に維持することです。(文献10)
高尿酸血症を放置すると、さらなる病気を引き起こす可能性があるため、薬による管理が重要です。
服薬は必ず医師の指示に従って行います。
高い尿酸値は放置せず原因を理解して予防しよう
尿酸値が高い状態を放置すると、痛風や腎機能障害などの合併症を引き起こすリスクが高まります。
日々の生活にできることから少しずつ取り入れることで、尿酸値を管理し合併症のリスクを減らせます。
プリン体の多い食品やアルコールの摂取を控え、水分をしっかり摂るなどを基本に、有酸素運動や適正体重の維持、ストレス管理を意識しましょう。
尿酸値を上げない食生活や飲み物などを相談したい、また痛風の症状や治療方法について相談したい方は、当院リペアセルクリニックのメール相談もしくはオンラインカウンセリングにてご相談ください。
高い尿酸値に関するよくある質問
コーヒーは尿酸値を下げる効果はありますか?
米国の研究結果ではコーヒーを摂取したことで尿酸値が下がる結果が出た報告があります。(文献8)
一方で、反対の結果を示す研究もあり、コーヒーにおける尿酸値への影響は明確ではありません。
コーヒーと尿酸値の関係について、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。
女性の尿酸値が高い原因は?
女性の尿酸値が高くなる原因は、尿酸値を多く含む食品を摂取する生活習慣と閉経による女性ホルモンの変化です。
閉経後の女性は、尿酸値を下げる働きがあるエストロゲン(女性ホルモン)が減少するため、尿酸値が高くなります。
さらに詳しい内容を以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
参考文献
(文献1)
高尿酸血症/痛風|日本生活習慣病予防協会
(文献2)
高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン第3版2022年追補版|日本痛風・尿酸核酸学会
(文献3)
痛風発作を起こす前に-尿酸値が高いといわれたら-|日本医師会
(文献4)
アルコールと高尿酸血症・痛風|厚生労働省
(文献5)
Evaluation of the diet wide contribution to serum urate levels: meta-analysis of population based cohorts|BMJ
(文献6)
食品に含まれるプ リン体について|J-STAGE
(文献7)
魚介類50gあたりの脂質とプリン体の関係|厚生労働省
(文献8)
Is coffee consumption associated with a lower risk of hyperuricaemia or gout? A systematic review and meta-analysis|PMC
(文献9)
アルコールが尿酸代謝に悪い理由|J-STAGE