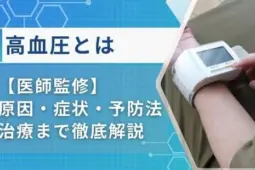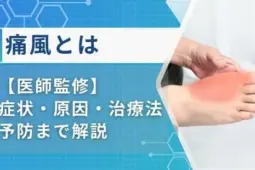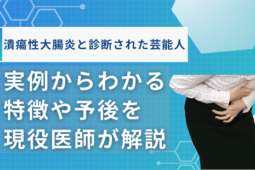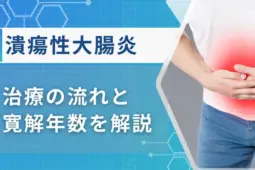- 内科疾患
- 内科疾患、その他
痛風の食事療法とは?|尿酸値を下げる食材と予防習慣を紹介【医師監修】
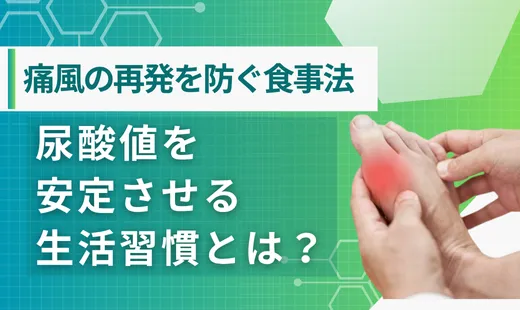
痛風の予防や再発防止には、日々の食事内容が大きく関係しています。
プリン体を多く含む食品やアルコールの摂りすぎは尿酸値を上昇させ、痛風の発作を引き起こす原因となります。
しかし、食事を少し見直すだけで、尿酸値を安定させて痛風を予防・改善することが可能です。
本記事では、痛風と食事の関係についての解説と、プリン体を減らす食習慣や無理なく続けられる食事法を紹介します。
薬に頼りすぎず、食生活から体を整えたい方は、ぜひ参考にしてください。
また、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
痛風について気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
痛風と食事の深い関係|尿酸値を左右するのは毎日の食生活
痛風は、毎日の生活習慣が大きく影響する病気です。
とくに、食事は尿酸値の変動に深く関わっているため、日々の食生活を整えることが痛風の予防や改善につながります。
ここでは、日々の食事がどのように痛風の発症や悪化に関わっているのか解説します。
痛風は「尿酸」が関係する生活習慣病の一つ
痛風は、血中の尿酸が増え、関節内に結晶ができて炎症を起こす「代謝異常による関節炎」の一種で、とくに足の親指など末端部に強い痛みが生じるのが特徴です。
尿酸は、食事から摂取した「プリン体」という成分が体内で分解されてできる老廃物の一つで、本来は尿として体外に排出されます。
しかし、プリン体を多く含む食品を摂りすぎたり、水分不足で排出が追いつかなくなったりすると、尿酸が血液中にたまりやすくなります。
これは「高尿酸血症」と呼ばれる状態で、放置すると関節に尿酸結晶が沈着し、激しい痛みを伴う痛風発作を引き起こします。
乱れた食習慣は痛風を悪化させる最大の要因
痛風を悪化させる要因には、日常的な「食習慣の乱れ」が大きく関係しています。
たとえば、脂っこい食事やアルコールの摂りすぎ、水分不足、不規則な食事時間などは、尿酸の生成や排出バランスを乱します。
とくにアルコールは、体内で尿酸を増やすだけでなく、腎臓からの排出を妨げるため、痛風発作の引き金になりやすいとされています。
また、食事を抜いたり、極端なダイエットも、代謝バランスを崩し尿酸値を上昇させる要因です。
無理な制限をするよりも、日々の食事を少しずつ整えることが、痛風の予防につながります。
プリン体の摂りすぎが尿酸値を上げる理由
尿酸は、体内でプリン体が分解されることで生成されます。
プリン体自体はエネルギー代謝に欠かせない成分ですが、摂りすぎるとその分だけ尿酸が過剰に生成され、血液中の尿酸値が上昇します。
プリン体を多く含む食事を頻繁に摂ると、尿酸が増加しやすく、関節内に結晶として蓄積しやすくなり、痛風発作の原因となります。(文献1)
痛風を発症している場合は、プリン体を含む食品の摂取量を意識したバランスの良い食事を心がけましょう。
痛風の食事で避けるべき食品・飲み物
日々の食事は健康を支える基本ですが、知らないうちに痛風を悪化させる食習慣が身についている場合もあります。
痛風を悪化させないためには、尿酸をためやすい食べ物や飲み物を理解しておくことが重要です。
ここでは、痛風の悪化を防ぐために控えたい食品や飲み物の種類について詳しくみていきましょう。
プリン体を多く含む食品
プリン体は体内で尿酸に分解されるため、摂りすぎると血液中の尿酸値を上昇させます。
とくに、肉類・魚卵・レバーなどの内臓類・乾物類などに多く含まれており、過剰摂取は痛風発作の引き金になります。
以下の表は、食品100g中のプリン体含有量の一例です。
【食品100g中のプリン体含有量】(文献2)
| 食品名 | プリン体含有量(mg/100g) |
|---|---|
| 鶏レバー マイワシ(干物) タラ・ふぐ(白子) あんこう(肝酒蒸し) 健康食品(DNA/RNAなど) |
約300mg~ |
| 豚・牛レバー カツオ マイワシ マアジ・サンマ(干物) エビ |
約200~300mg |
| 肉類(豚・牛・鶏)の多くの部位 魚類 ブロッコリースプラウト ほうれんそう(芽) |
約100~200mg |
| 肉類(豚・牛・羊)の一部 魚類の一部 カリフラワー ほうれんそう(葉) |
約50~100mg |
※数値は一般的な成分表をもとにしたおおよその目安です。
上記の数値を目安に、プリン体の摂りすぎを防ぐよう意識しましょう。
アルコールの過剰摂取は要注意
アルコールは、体内で尿酸を増やすだけでなく、腎臓からの尿酸の排出を妨げる働きもあります。
とくにビールや日本酒はプリン体を多く含み、日常的に飲みすぎると尿酸値が上昇しやすくなります。
一方、焼酎・ウイスキーなどの蒸留酒はプリン体が少ないものの、アルコールそのものが尿酸の排出を阻害するため、過剰摂取は禁物です。
飲酒をする場合は、週に2日以上の休肝日を設けたり、水や炭酸水などで割って飲むことがポイントです。
飲み方を少し工夫するだけでも、痛風発作のリスクを抑えることができます。
外食・コンビニで避けたいメニュー例
外食やコンビニ食品は手軽で便利な反面、脂質や塩分、プリン体が多く含まれているものが多い傾向があります。
なかでも唐揚げ・ハンバーグ・ラーメン・カレーライスなどは、肉類や油を多く使用しており、尿酸値を上げやすい代表的なメニューです。
また、丼ものやセットメニューも炭水化物や動物性たんぱく質が多く、バランスを崩しやすくなります。
外食の際は、野菜や海藻の小鉢を追加する、主菜を魚や豆腐料理に置き換えるなど、少しの工夫で栄養バランスを整えられます。
コンビニ食品では、サラダ・ゆで卵・おにぎり(鮭や梅など)を選ぶなど、無理なく続けられる工夫を意識しましょう。
糖質・果糖の多い飲み物にも注意
清涼飲料水やフルーツジュース、エナジードリンクなどに含まれる「果糖」は、体内で分解される際に尿酸を生成します。
そのため、糖分の多い飲み物を頻繁に摂ると、知らず知らずのうちに尿酸値を上げてしまう可能性があります。
また、スポーツドリンクや加糖コーヒー、缶入りの紅茶飲料なども注意が必要です。
どうしても甘い飲み物が欲しいときは、果汁100%ジュースを少量に抑える、ノンカロリー飲料を選ぶなど、上手にコントロールしていきましょう。
尿酸を下げる効果が期待できる食材
痛風の改善には、尿酸値を上げにくい食材を選び、体の代謝をサポートすることが大切です。
とくに野菜や果物、乳製品には、尿酸をため込みにくくしたり、炎症をやわらげる働きを持つ成分が含まれています。
ここでは、尿酸値のコントロールに役立つ食材と、その栄養成分の特徴を紹介します。
フルーツ|バナナ・さくらんぼ・ベリー系
果物の中でも、バナナやさくらんぼ、ブルーベリーなどのベリー系はカリウムを豊富に含んでおり、体内の塩分バランスを整えて尿酸の排出を促します。
さらに、さくらんぼやベリー類に含まれるアントシアニンには抗酸化作用があり、炎症を和らげる働きが期待できます。
ただし、果物でもブドウやマンゴーなどの果糖が多いものは、尿酸を増やす可能性があるため、1日1〜2皿を目安に適量を守って摂取することが大切です。
野菜|トマト・玉ねぎ
トマトや玉ねぎには、尿酸値を安定させる効果が期待できる成分が含まれています。
トマトに多いリコピンには抗酸化作用があり、炎症や血流の悪化を防ぐことで体内環境を整えます。
また、玉ねぎに含まれるケルセチンは、尿酸の生成を抑える作用を持つとされており、動物性食品と組み合わせることでよりバランスの良い食事になります。
日々の食卓では、サラダやスープ、炒め物に取り入れるなど、無理なく続けられる形で摂ることを意識しましょう。
きのこ類|しめじ・しいたけ・えのき
きのこ類はプリン体が比較的少なく、安心して摂取できる食材です。
なかでも、しめじ・しいたけ・えのきなどは食物繊維が豊富で、腸内環境を整えると同時に尿酸の排出もサポートします。
また、カロリーが低いため、食べすぎによる体重増加を防ぐ効果も期待できます。
炒め物や味噌汁、鍋料理など、日常のメニューに取り入れやすいのも魅力です。
肉や魚の代わりに一部をきのこに置き換えると、プリン体を抑えつつ満足感のある食事ができます。
乳製品|低脂肪ヨーグルト・低脂肪牛乳
低脂肪のヨーグルトや牛乳には、カゼインやラクトアルブミンなどのたんぱく質が含まれており、尿酸の排出を促す働きがあるとされています。
さらに、乳製品はプリン体をほとんど含まないため、痛風の方でも安心して摂れる食品です。
カルシウムの補給にもつながり、骨や筋肉の健康維持にも役立ちます。
毎日の習慣として、朝食や間食に低脂肪ヨーグルトを取り入れるなど、無理なく続けられる方法を意識すると良いでしょう。
痛風の予防・改善に役立つ栄養素と食事のポイント
痛風の予防・改善には、プリン体を控えるだけでなく、尿酸の排出を促す栄養素を意識的に取り入れることも大切です。
また、日々の食事の組み合わせや水分摂取の工夫からでも、尿酸値の安定をサポートできます。
ここでは、尿酸値を下げる効果が期待できる栄養素と、食事で無理なく摂取するポイントについて解説します。
尿酸の排出を助ける栄養素
尿酸の排出を促すためには、体内の代謝を整える栄養素を積極的に摂ることが大切です。
なかでもカリウム・ビタミンC・マグネシウムは、痛風の予防や再発防止を支える栄養素で、次のような効果が期待できます。
以下のように表にまとめました。
| 栄養素 | 効果・特徴 |
|---|---|
|
カリウム |
・体内の塩分バランスを整え、尿の排出を促して尿酸を体外に排出しやすくする ・野菜・果物・海藻類に豊富に含まれる |
| ビタミンC | ・尿酸値を下げる作用があるとされている ・果物やブロッコリー・ピーマンなどに多く含まれる |
| マグネシウム | ・細胞のエネルギー代謝を助け、腎臓の働きをサポートする ・ナッツ類・大豆製品・全粒穀物に多く含まれる |
上記の栄養素を日常的に摂取すると、体の中で尿酸をためにくくする習慣をつくることができます。
プリン体の少ない食材を使って主菜・副菜を組み合わせる
痛風を予防するためには、食材の組み合わせ方も重要です。
たとえば、次のようなプリン体が少ない食材を中心とした主菜・副菜の組み合わせは、満足感を保ちながら尿酸の上昇を防ぐことができます。
|
【おすすめの食材組み合わせ例】
|
また調理方法も、揚げ物よりも茹でる・蒸す・焼くなどの方法を選ぶとさらに効果的です。
こまめな水分摂取で尿酸を排出
尿酸は尿として体外に排出されるため、水分摂取が欠かせません。水分が不足すると尿量が減り、尿酸が体にたまりやすくなります。
そのため、1日あたり1.5〜2リットルを目安に、こまめな水分摂取が大切です。飲み物は、水・麦茶・炭酸水などのカフェインや糖分を含まないものがおすすめです。
起床時・食事中・入浴後など、少しずつ分けて飲むと、体に負担をかけずに尿酸の排出を促せます。
とくに痛風を繰り返している方は、「喉が渇いたと感じる前に飲む」習慣を意識しましょう。
\無料オンライン診断実施中!/
尿酸値を安定させるための1日の理想的な食事メニュー(献立)
食材の選び方や食べるタイミングを少し意識するだけでも、尿酸値の安定や発作の予防につながります。
ここでは、尿酸値を安定させるための理想的なメニュー例を朝・昼・夜・間食のタイミング別に紹介します。
朝食
朝食は、寝ている間に低下した代謝を整え、尿酸の排出をスムーズにするために欠かせません。
おすすめは、和食スタイルで栄養バランスを整えることです。
【メニュー例】
|
納豆は、植物性たんぱく質が豊富でプリン体が少なく、痛風対策に適しています。
また、朝の一杯の水や牛乳で尿酸排出を促すとより効果的です。
昼食
昼食が外食やコンビニ食品が多い場合でも、選び方次第で尿酸値の上昇を抑える工夫ができます。
揚げ物や肉中心のメニューを避け、バランスの取れた定食を選びましょう。
【メニュー例】
| 場所 | おすすめメニュー |
|---|---|
| 外食 | そば+野菜+豆腐 |
| 定食 | 焼き魚定食(冷奴付き) |
| コンビニ | おにぎり(鮭・梅)+サラダ+味噌汁 |
夕食
夕食は一日の疲れを癒す時間ですが、食べすぎやアルコールの飲みすぎは尿酸値を上げる原因になります。
肉や魚は控えめにし、野菜や海藻・豆腐でかさ増しするなど、食事のボリュームを抑えつつ、満足感を両立する工夫が大切です。
【メニュー例】
|
間食・飲み物
間食や飲み物の選び方も、尿酸コントロールに大きく関係します。
糖分を多く含むお菓子や清涼飲料水は尿酸を上げやすいため控えましょう。
【おすすめ食品・飲み物】
|
水分は1日1.5〜2リットルを目安に、こまめに摂るようにしましょう。
痛風の再発を防ぐために見直したい食習慣と生活リズム
痛風は一度発症すると、再発を繰り返しやすい傾向があります。
再発を繰り返さないためには、日々の生活リズムや飲酒習慣を整え、尿酸値の安定を維持することが大切です。
ここでは、痛風の再発を防ぐために見直したい食習慣と生活のポイントを紹介します。
1日3食をバランスよく摂る
食事を抜いたり、まとめて摂ると、体内の代謝バランスが崩れ、尿酸値が急上昇しやすくなります。
とくに、空腹状態が長く続いたあとに高たんぱく・高脂質の食事をとると、尿酸の生成が一気に増える可能性があります。
1日3食を規則正しく摂ることで、血糖値と尿酸値の変動を安定させることができます。
朝食・昼食・夕食をなるべく同じ時間にとり、間食を上手に活用しながらエネルギーを分散させましょう。
アルコール休肝日を週2日以上設ける
毎日のように飲酒していると、肝臓や腎臓への負担が蓄積し、痛風の再発リスクが高まります。
痛風の再発を防ぐためには、週に2日以上の休肝日を設けて肝臓を休ませることが大切です。
どうしても飲酒をする場合は、焼酎やウイスキーなどの蒸留酒を選び、水や炭酸水で割るなど、飲み方を工夫して負担を減らすようにしましょう。
食べる順番を意識する
同じ食事内容でも、食べる順番によって体への影響が変わります。
とくに、野菜やきのこ類などの食物繊維を最初に食べる「ベジファースト」は、血糖値の上昇をゆるやかにし、尿酸の過剰生成を防ぐ効果が期待できます。
ベジファーストを意識して食事する際は、野菜→たんぱく質(肉・魚・豆腐など)→ごはんやパンの順に食べるようにしましょう。
この食べ方は満腹感を得やすく、食べすぎの防止にもつながります。
塩分や脂質の摂りすぎに注意する
塩分や脂質を摂りすぎると、腎臓や肝臓に負担がかかり、尿酸を排出する力が弱まります。
加工食品や外食メニューには塩分や脂質が多く含まれているため、味付けを控えめにする工夫が重要です。
調理の際は、出汁やレモン汁・香味野菜などを活用して風味で満足感を出すとよいでしょう。
また、脂質は揚げ物ではなく、オリーブオイルや青魚などの良質な脂を少量取り入れるのがおすすめです。
痛風の新しい選択肢「再生医療」という考え方
痛風の管理には尿酸値のコントロールが重要です。
食事でのプリン体制限に加えて、再生医療による治療も選択肢の一つとなる場合があります。
再生医療では、自己の幹細胞を採取・培養して点滴にて投与します。
幹細胞が持つ、他の細胞に変化する「分化能」という能力を活用する治療法です。
以下は糖尿病に対する当院の症例です。治療前の尿酸値は8.1mg/dL、治療後は3.1mg/dLでした。
詳しい治療の経過については、以下の症例記事をご参照ください。
まとめ|食事と生活習慣の改善で痛風は予防・改善できる
痛風は、食事内容や生活リズムの見直しによって予防・改善が十分に可能な病気です。
プリン体を多く含む食品やアルコールの摂取を控え、野菜や乳製品など尿酸の排出を助ける食材を積極的に取り入れることで、再発を防ぎやすくなります。
また、1日3食をバランスよく摂ることや、十分な水分補給、適度な運動など、日常の小さな習慣も尿酸値の安定に大きく関わります。
もし食事や生活を見直しても痛みが続く場合は、医師や専門機関へ相談し、適切な治療を受けましょう。
痛風と上手に付き合っていくには、自分の体と向き合いながら、無理のない範囲で生活を整えることが大切です。
痛風の食事治療に関するよくある質問
痛風でもコーヒーやアルコールを飲んでも問題ありませんか?
痛風でも適量であれば、コーヒーの摂取は問題ありません。
一般的に推奨されるコーヒーの摂取量は1日3〜4杯(カフェイン摂取量400mg未満)が目安とされています。
ただし、痛風の重症度や体質によってはカフェインの影響を受けやすい場合もあるため、体調を見ながら調整することが大切です。
一方、アルコールは尿酸値を上昇させる要因となるため注意が必要です。
尿酸値への影響を最低限にするため、以下の摂取量を目安に、週2日以上の休肝日を設けて節度ある飲酒を心がけましょう。
- 日本酒1合
- ビール350mL~500mL(販売元によって異なる)
- ウイスキー60mL
- ワイン148mL まで
尿酸値を下げる食品の一覧はありますか?
株式会社三和化学研究所が公開している「プリン体の摂りすぎに注意!」では、食品に含まれるプリン体の一覧表が掲載されています。(文献2)
また、野菜や豆類、きのこ類、海藻類は低カロリーで、尿酸の排泄を促す食物繊維を多く含みます。
これらの食品には尿をアルカリ性に傾ける働きがあり、尿酸が尿に溶けやすくなることで、尿酸結石の予防にも役立ちます。
より具体的な食事管理については、医師や管理栄養士に相談することをおすすめします。
痛風のときに肉を食べても大丈夫ですか?
肉に含まれるたんぱく質は、体の修復に欠かせない栄養素のため、摂取量と頻度を調整すれば問題ありません。
たとえば、鶏むね肉・ささみ・豚もも肉などを選び、1食あたり80〜100g程度を目安にすると良いでしょう。
また、炒める・揚げるよりも「茹でる・蒸す」など脂質を落とす調理法を選ぶと、体への負担を減らせます。
肉だけでなく豆腐や魚、野菜などを組み合わせて栄養バランスを整えることが再発予防につながります。
参考文献