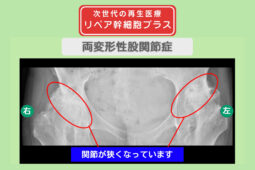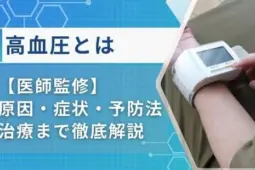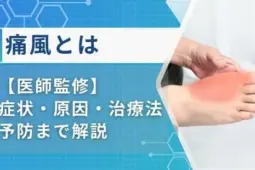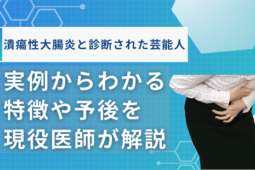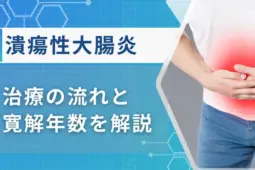- 内科疾患
- 内科疾患、その他
- その他、整形外科疾患
医療ボトックスとは|効果や打ち続けるリスクを現役医師が解説

「医療ボトックスの効果を知りたい」
「医療ボトックスを打ち続けると、どうなるのか心配」
医療ボトックスを検討しているものの、「副作用が心配」「一度始めたらやめられなくなるのでは」と不安を感じていませんか。ボトックス治療は主に医療目的で使用され、症状の緩和や生活の質の向上に効果が期待できます。
一方で、「続けるうちに効きにくくなる」「中止すると症状が戻り悪化する」といった情報に不安を感じる方も少なくありません。正しい知識を持ち、自分に合った治療かどうか、慎重に判断しましょう。
本記事では、現役医師が医療ボトックスについて詳しく解説します。
- 医療ボトックスの効果
- 医療ボトックスを打ち続けるとどうなるのか
- 医療ボトックスをやめるとどうなるのか
- 医療ボトックスの副作用
- 医療ボトックスの治療期間
本記事の最後には、医療ボトックスに関するよくある相談について回答していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
医療ボトックスとは
医療ボトックスは、ボツリヌス菌由来のタンパク質(ボツリヌス・トキシン)を少量注射し、筋肉の過剰な緊張や動きを一時的に抑える治療法です。
主に痙攣、筋肉のこわばり、多汗症、顎関節症、歯ぎしりなどの症状改善や機能回復を目的として用いられ、美容目的とは異なり、症状によっては健康保険の適用もあります。
効果は通常、注射後1〜2週間で現れ、1〜2カ月でピークに達します。その後、3〜6カ月ほど持続し、徐々に効果が薄れていきます。効果を維持するには、3〜6カ月ごとに注射を継続するのが一般的です。効果の持続期間や治療間隔には個人差があるため、実施前に医師への相談が不可欠です。
以下の記事では、脳梗塞に対してのボトックス効果について詳しく解説しています。
医療ボトックスの効果
| 期待できる効果 | 詳細 |
|---|---|
| 筋肉の過剰な緊張や痙縮の緩和 | 神経伝達の遮断による筋肉の収縮抑制 |
| 眼瞼けいれん・片側顔面けいれんの改善 | けいれんを起こす筋肉の動きの抑制 |
| 多汗症の治療 | 発汗を促す神経信号の遮断による汗の抑制 |
| 顎関節症や歯ぎしりの緩和 | 咬筋の過活動抑制による顎や歯への負担軽減 |
医療ボトックスは、過剰に働く筋肉や神経の異常な伝達を一時的に抑えることで、症状を緩和する治療法です。もともとは眼瞼けいれんや斜視などの神経疾患に対して開発されましたが、現在では痙縮、顔面けいれん、多汗症、顎関節症、歯ぎしりなど、幅広い症状に対して効果が認められています。
注射により筋肉や汗腺の働きを抑え、日常生活への支障を軽減することが期待されます。効果は3〜6カ月程度持続します。効果や持続期間には個人差があるため、医師と相談の上で継続的に治療することが重要です。
筋肉の過剰な緊張や痙縮の緩和
| 適応疾患 | 症状の特徴 | ボトックスの作用 | 期待される効果 |
|---|---|---|---|
| 痙性斜頸 | 首の筋肉が勝手に収縮し、頭が傾く・ねじれる状態 | 異常な筋肉の動きを抑制 | 姿勢の改善、違和感や不快感の軽減 |
| 脳性麻痺による運動障害 | 手足の筋肉がこわばり、動かしにくくなる状態 | 筋肉の緊張を和らげ、動きをスムーズにする | 関節の可動域改善、歩行や手の動作の向上 |
脳卒中、脳性まひ、脊髄損傷などの後遺症では、筋肉がこわばり、思うように動かせなくなる痙縮(けいしゅく)と呼ばれる症状が現れることがあります。医療ボトックスは、過剰に収縮している筋肉への信号を一時的にブロックすることで筋肉の緊張を緩和する治療法です。
この作用により、関節の動かしやすさが改善し、日常動作がスムーズになるケースもあります。リハビリの効率が高まり、より効果的な訓練が可能となるのも利点のひとつです。また、強い筋緊張によって起こる違和感や変形、皮膚トラブルを防ぐ効果も期待されています。
このような症状に対するボトックスの効果は3〜4カ月ほど続き、時間の経過とともに効果が薄れ、徐々に元の状態に戻ることがあります。
再発を防ぐには、症状に応じて定期的な注射を検討することが大切です。適切なタイミングと用量で継続することで、生活の質の向上が見込めます。
眼瞼けいれん・片側顔面けいれんの改善
| 疾患名 | 症状の特徴 | ボトックスの作用 | 期待される効果 |
|---|---|---|---|
| 眼瞼けいれん | まぶたのけいれん、勝手に閉じてしまう状態 | 眼輪筋の異常収縮の抑制 | まぶたの開けやすさの改善、けいれんの軽減 |
| 片側顔面けいれん | 顔の片側の筋肉のピクピクとした不随意な動き | 顔面筋の過剰な緊張やけいれんの抑制 | 表情のゆがみの軽減、不快感の改善 |
眼瞼けいれんは、まぶたが無意識にピクピク動いたり、強く閉じてしまう症状で、まぶしさや目の疲れ、視界の遮りを引き起こすことがあります。片側顔面けいれんは、顔の片側にけいれんが生じ、笑ったり話したりすると症状が強まるのが特徴です。いずれも筋肉の異常な収縮が原因とされ、医療ボトックスは有効な治療法です。
けいれんを起こしている筋肉にボトックスを注射することで、神経から筋肉への信号を一時的に抑え、不随意な動きを一定期間抑える効果があります。
効果は注射後2〜5日で現れ始め、2〜4週間で最大となり、2〜4カ月持続します。症状や筋肉の反応を見ながら、定期的に治療を行うことで、日常生活の不便を大きく軽減できる可能性があります。
多汗症の治療
医療ボトックスは、多汗症の原因となる神経の働きを一時的に抑え、汗の分泌を軽減する治療法です。脇や手のひらなど汗が気になる部位に注射することで、2〜3日後から効果が現れます。
効果は通常4〜9カ月続くため、再発時には定期的な治療が必要です。手術とは異なり、傷跡が残らず日常生活への影響もほとんどありません。発汗を抑えることで、日常の不快感や精神的なストレスの軽減に大きく役立ちます。
顎関節症や歯ぎしりの緩和
| 症状・効果 | ボトックス治療の作用 |
|---|---|
| 顎関節症の緩和 | 咬筋の緊張を抑制し、顎関節への負担軽減。違和感や開口障害、クリック音の改善 |
| 歯ぎしり・食いしばりの軽減 | 無意識の歯ぎしり・食いしばりの減少。歯や顎関節へのダメージ予防 |
| 歯の摩耗や補綴物の破損予防 | 噛む力の抑制による歯のすり減りや詰め物・被せ物の破損リスク低減 |
| 顔の輪郭の変化 | 咬筋のボリューム減少によるエラ張りの改善。フェイスラインのすっきり感 |
| 効果の持続 | 効果は通常3~6カ月持続。時間経過とともに徐々に元の状態へ戻る。定期的な再注射で効果維持 |
| 治療の特徴 | 治療時間は短く、ダウンタイムほとんどなし。個人差あり |
顎関節症や歯ぎしり(ブラキシズム)は、睡眠中の強い食いしばりや日中の無意識な筋緊張によって、顎やこめかみの違和感、咬筋の発達、歯のすり減りなどを引き起こす症状です。
これらに対して医療ボトックスを用いることで、噛む筋肉である咬筋の過剰な収縮を一時的に抑え、食いしばりや歯ぎしりの頻度や強さを軽減できます。
咬筋の緊張が緩和されることで、顎の違和感や開口障害が改善し、歯や関節への負担も軽減します。効果は3~6カ月程度持続し、筋緊張の軽減によりフェイスラインがすっきりする場合もあります。
治療を受ける際は、目的や副作用を十分に理解し、医師と相談しながら進めることが重要です。
医療ボトックスを打ち続けるとどうなる?
| 打ち続けると起こりうるリスク | 詳細 |
|---|---|
| 効果の変化と抗体形成のリスク | 抗体の産生により薬剤が効きにくくなる可能性 |
| 表情の変化や筋力低下の可能性 | 周囲の筋肉への影響による違和感や動きの制限 |
| 効果の減弱と元の状態への回帰 | 薬の効果が切れることで症状が再発する可能性 |
| 副作用のリスク | 内出血・違和感・頭痛・倦怠感などが現れる可能性 |
医療ボトックスは効果の持続期間が限られているため、症状のコントロールには定期的な注射が必要です。ただし、長期間の治療に対して効果が薄れたり副作用が蓄積されたりすることに不安を感じる方も少なくありません。
実際には、ボトックスは時間とともに体外に排出されるため、成分が身体に蓄積することはありません。ただし、稀に抗体による効果の減弱、または表情の変化・筋力低下などの副作用が起こる可能性があります。そのため、治療は医師と相談の上、適切な間隔と投与量で行うことが求められます。
効果の変化と抗体形成のリスク
医療ボトックスは、筋肉の動きを一時的に抑えることで、しわやエラ張り、食いしばりなどの改善に用いられます。効果は通常3〜6カ月持続し、薬剤が分解されると徐々に筋肉の動きが戻るのが特徴です。継続的に適切な間隔(目安は3カ月以上)で治療を受けることで、効果が期待できます。筋肉が萎縮することで1回ごとの効果が長く続く場合もあります。
短期間に頻繁な注射を繰り返すと、ボトックスに対する抗体ができて効果が弱まるため、自己判断で注射の間隔を詰めるのは避け、必ず医師の指示に従うことが大切です。また、効果の変化には筋肉の状態や生活習慣も関係するため、定期的に診察を受け、治療間隔や投与量を調整しながら無理のない継続治療を行いましょう。
表情の変化や筋力低下の可能性
ボトックスは、筋肉の動きを一時的に抑えることでしわやたるみを改善しますが、同じ部位に繰り返し注射を行うと、表情筋の動きが制限されやすくなります。笑顔が不自然に見えたり、表情が乏しく感じられたりするのは、筋肉が長期間動かないことで徐々に萎縮し、筋力が落ちるためです。
また、咬筋などの大きな筋肉に繰り返し注射をすると、フェイスラインがすっきりする一方で、噛む力が弱くなるといった筋力低下も起こる可能性があります。額や目元などの部位では、表情のバリエーションが減ることもあります。
ボトックスの効果は3~6カ月程度持続し、回数を重ねることで効果が長く続く傾向がありますが、治療の頻度が高すぎると、副作用や表情の不自然さが目立ちやすくなります。そのため、3〜4カ月以上の間隔を空けることが、自然な表情と筋力を保つためには、重要です。
無理に回数を増やすのではなく、医師と相談の上、適切な量とタイミングで治療を継続することが、健康的で自然な仕上がりを保つポイントです。
効果の減弱と元の状態への回帰
医療ボトックスの効果は通常3〜4カ月程度持続し、時間とともに徐々に消失します。治療を中止すると、抑えられていた筋肉の活動が回復し、もともとの症状が元に戻る可能性があります。
たとえば、痙縮やけいれん、多汗症、食いしばり・歯ぎしりなどが再び現れることがあります。これは、薬の効果が切れて神経と筋肉の伝達が元に戻るためです。中には、再開後すぐに十分な効果が得られにくいケースもありますが、多くは再投与によって症状が再び緩和されます。
一方で、治療を中断しても症状が軽度のまま維持される場合もあるため、無理に継続せず一度経過を観察する選択も可能です。症状の戻り方には個人差があるため、医師と相談しながら、症状の経過に応じて柔軟に治療方針を決めていくことが大切です。
副作用のリスク
| 副作用の種類 | 内容と注意点 |
|---|---|
| 注射部位の腫れ・内出血・むくみ | 針を刺すことで一時的に現れる反応。通常は数日〜1週間で自然に消失 |
| アレルギー反応 | 発疹、赤み、かゆみ、息苦しさなど。ごく稀に発症し、早めの医師相談が必要 |
| 表情の違和感・筋力低下 | 筋肉の動きが抑制されることで起こる違和感や噛む力の低下。過剰投与でリスク増加 |
| 左右差や皮膚のたるみ | 筋肉の使い方の偏りや注射の入り方による影響。個人差あり |
| 頭痛・めまい・吐き気 | 一部の方に起こる全身症状。多くは軽度かつ一時的 |
| 嚥下障害・呼吸困難 | 首や咽頭周囲への注射、大量投与でごく稀に報告される重篤な副作用 |
医療ボトックスには、副作用のリスクがあります。注射部位に腫れや内出血、赤み、軽い違和感が出ることがありますが、これらは一時的で自然におさまることがほとんどです。まれに、隣接する筋肉に薬剤が拡がることで、意図しない筋力低下や表情の変化が起こることもあります。
また、ボトックスに対してアレルギー反応を示す人もごく少数ながら存在し、息苦しさや発疹などが現れる場合もあります。副作用の有無や治療前後の体調変化に気づいた際は、速やかに医療機関へ相談することが大切です。
医療ボトックスをやめるとどうなる?
| やめると起こりうる症状 | 詳細 |
|---|---|
| もとに戻る可能性がある | 抑えられていた症状の再発 |
| 見た目の変化に対する違和感 | シワや輪郭の戻りによる印象の変化 |
| 筋肉の活動が再開する | けいれんや緊張など筋肉の動きの再出現 |
医療ボトックスを中止すると、薬の効果が切れるのに伴い、神経と筋肉の伝達が徐々に元の状態へ戻ります。その結果、けいれんや痙縮、過度な発汗、歯ぎしりなど、これまで抑えられていた症状が再発する可能性があります。
ただし、症状が悪化するというよりは、治療前の状態に戻ると考えるのが一般的です。症状の戻り方や強さには個人差があり、すぐに再発する場合もあれば、一定期間は落ち着いた状態が続くこともあります。また、長期間治療を継続していた方ほど、効果が切れた際に見た目や感覚の変化に強い違和感を感じることがあります。
治療を継続するか中止するかは、症状の経過や日常生活への影響を踏まえ、医師と相談しながら柔軟に判断することが大切です。
もとに戻る可能性がある
ボトックスは、筋肉にA型ボツリヌストキシンを注射し、神経と筋肉の伝達を一時的に遮断することで、筋肉の動きを抑え、しわ・エラ張り・食いしばりなどの症状を軽減する治療です。
ただし、効果は一時的で、通常3〜6カ月程度で薬剤が分解され、神経伝達が回復します。すると筋肉が再び動き始め、治療前の状態に戻る可能性が高くなります。
元に戻る現象は、ボトックスが筋肉を破壊するのではなく、動きを一時的に抑える仕組みであるためです。たとえばエラボトックスを中止すると、咬筋が再び発達し、エラ張りや食いしばりが戻ることがあります。治療を中止しても症状が悪化したり、老化が進むことはありません。
また、長期間(数年〜十数年)ボトックスを継続したごく一部のケースでは、筋肉の動きが弱まる廃用性萎縮に似た状態が起こることがありますが、非常に稀です。多くの場合は中止により自然回復します。継続治療を希望する場合は、症状や目的に応じて医師と相談し、適切なタイミングと頻度での治療が推奨されます。
見た目の変化に対する違和感
医療ボトックスの効果は3〜6カ月ほどで徐々に消失し、筋肉の動きが元に戻ります。それに伴い、しわやエラの張り、フェイスラインなどが治療前の状態に近づいていきます。
これはボトックスの効果が自然に切れた結果であり、異常ではありません。治療中の若々しく整った見た目に慣れていると、効果が切れて元の状態に戻ったときに老けた印象や疲れた印象を受けやすくなります。見た目が悪化したわけではなく、治療前の状態に戻っただけです。
また、長期間ボトックスを続けていた場合は、筋肉の動きが抑えられていた分、効果が切れたときに違和感を強く感じやすくなります。こうした見た目の変化は副作用ではなく、心理的なギャップによるものです。治療を中止する際は、あらかじめ医師と相談し、必要に応じて他の治療を検討することで、違和感を抑えながら自然な変化に対応できます。
筋肉の活動が再開する
医療ボトックスの効果は一時的で、3〜6カ月ほどで神経と筋肉のつながりが回復し、抑えられていた筋肉の活動が再開します。これは、神経から筋肉への信号をブロックするボトックスの作用が切れ、神経枝が再生するためです。
筋肉の動きが戻ると、けいれんや痙縮、歯ぎしりなどの症状が再び現れることがありますが、これは自然な反応であり異常ではありません。もともと症状が強かった人では、変化に違和感や不安を覚えることもあります。
ボトックスは筋肉を壊す薬ではないため、基本的に機能は元に戻ります。ただし、長期間にわたる連続使用では、まれに筋肉が使われにくくなり、萎縮が見られることもあります。再治療が必要かどうかは、症状や生活への影響を見ながら判断し、医師と相談の上で治療方針を決めることが大切です。
医療ボトックスの副作用
| 副作用 | 詳細 |
|---|---|
| 局所的な副作用 | 注射部位の腫れ・赤み・内出血・違和感など |
| 筋力低下や動作の制限 | 力が入りにくい・動かしづらい感覚の一時的出現 |
| 全身的な副作用 | 頭痛・倦怠感・吐き気・まれにアレルギー反応など |
医療ボトックスは高い治療効果が期待できる一方で、副作用の可能性もあります。多くは軽度かつ一時的なもので、注射部位の腫れ、赤み、内出血、違和感などが見られますが、通常は数日以内に自然に改善します。
注射する部位や筋肉の範囲によっては、表情が不自然に感じられたり、噛みにくさ、飲み込みにくさが出ることもあります。さらに、非常にまれではありますが、アレルギー反応、全身のだるさ、頭痛、吐き気などが起こるケースもあるため注意が必要です。これらの症状が現れた場合は、早めに医師へ相談することで適切に対応できます。
また、以下のような方にはボトックス治療は推奨されません。(文献1)
- 神経筋接合部の障害(例:重症筋無力症)を持つ方
- 妊娠中または授乳中の女性(影響が十分に明らかになっていないため)
副作用への理解を深め、体調や持病に応じて医師と十分に相談しながら治療を進めることが、医療ボトックスの活用につながります。
局所的な副作用
| 副作用の種類 | 主な原因 | 詳細 |
|---|---|---|
| 腫れ・内出血 | 注射針の刺激・血管損傷・身体の反応 | 注射時の物理的刺激による反応。多くは軽度で数日以内に自然に消退する |
| 刺激・違和感 | 皮膚や筋肉への刺激・注入圧 | 注射直後に生じやすい一時的な感覚。数時間から数日で改善 |
| 赤み・かゆみ・発疹 | アレルギー反応や炎症反応 | ごく稀に発生する。軽度で短期間の経過が多い |
| 副作用の対策 | 技術・衛生管理・事前の体調確認 | 適切な治療とリスク管理で副作用の頻度や重症化を最小限に抑えることが可能 |
医療ボトックスの局所的な副作用は、注射による物理的な刺激や体の自然な防御反応が原因で起こることがほとんどです。腫れ、内出血、違和感などは一時的な症状であり、通常は数日以内に自然に治まります。まれにかゆみや発疹、赤みが見られることもありますが、これらも軽度で、アレルギー反応としてはごく稀なケースです。
副作用を最小限に抑えるには、施術者の技術や衛生管理、アレルギー歴の確認が不可欠です。副作用が長引く場合や不安を感じた際は、早めに医師へ相談することが重要です。
筋力低下や動作の制限
ボトックスによる筋力低下や動作の制限は、神経から筋肉への信号が一時的に遮断されることで起こります。これは、しわを目立たなくするために筋肉の動きを抑える作用によるものです。
その結果、注射部位の筋肉に力が入りにくくなることがあります。ただし、これらの反応は一時的であり、時間の経過とともに自然に回復します。
これらは薬の効果が持続する2~4カ月間の一時的な変化です。ただし、左右差や違和感が強い場合は、早急に医療機関を受診しましょう。
全身的な副作用
| 副作用の種類 | 原因・仕組み | 特徴・注意点 |
|---|---|---|
| 頭痛 | 神経伝達の変化・炎症反応・筋緊張バランスの乱れ | 多くは軽度で一時的。数日以内に自然に軽快 |
| アレルギー反応 | ボツリヌストキシンや添加物への免疫反応 | 発疹、かゆみ、腫れ。稀にアナフィラキシーなどの重篤反応 |
| 呼吸困難・嚥下困難 | 薬剤の過量・全身への広がり・基礎疾患の影響 | 重症筋無力症や呼吸器疾患のある方はとくに注意。異常を感じたら早期受診が必要 |
| 倦怠感・だるさ | 神経や筋肉への作用による一時的な全身的影響 | 軽度で自然に回復することが多い |
| 心臓への影響 | ごく稀に報告される自律神経系や循環器系への影響 | 不整脈や心不全の既往がある方は慎重な判断が必要 |
医療ボトックスは主に局所に作用する治療ですが、ごく稀に全身的な副作用が現れることがあります。頭痛や倦怠感は比較的よく見られますが、多くは軽度で数日以内に自然に改善します。
稀にアレルギー反応として発疹やかゆみが出ることがあり、重症の場合はアナフィラキシーを起こす可能性もあるため注意が必要です。また、薬剤が広がることで呼吸や嚥下に関わる筋肉に作用し、呼吸困難や全身の筋力低下を引き起こすことがあります。
とくに、神経筋疾患や呼吸器疾患のある方には慎重な対応が求められます。症状が強く現れたり長引いたりする場合は、速やかに医師へ相談してください。
医療ボトックスの治療期間
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 効果発現時期 | 注射後2週間ほどで効果出現。1〜2カ月目にピーク |
| 効果持続期間 | 通常3〜4カ月持続。その後徐々に消失 |
| 治療間隔・頻度 | 3〜4カ月ごとに年数回の注射が一般的 |
| 抗体形成リスク | 過度な頻度での投与は抗体形成による効果減弱リスク増加 |
| 治療の目的 | 一時的な症状改善。根本治癒目的ではない |
| 治療計画の調整 | 症状や目的、個人差に応じて調整。医師との継続的な相談が不可欠 |
(文献2)
医療ボトックスの効果は、注射後2週間ほどで現れ始め、1〜2カ月目に効果のピークを迎えます。効果は通常3〜4カ月持続し、その後徐々に消失します。症状の改善を継続したい場合は、3〜4カ月ごとに年数回の注射を繰り返すことが一般的です。ボトックスはあくまで一時的な治療であり、根本治癒を目的とするものではありません。効果を持続させるには、長期的な治療と定期的な経過観察が必要です。
治療間隔や期間は、症状や目的、個人差に応じて調整されます。無理のない治療計画を立てるためにも、医師との継続的な相談が重要です。
医療ボトックスで改善しない症状に再生医療という新たな選択肢
医療ボトックスは多くの神経筋疾患や過活動による症状に対して効果が期待できますが、すべての症状に適応するわけではありません。
たとえば、筋肉の損傷が進んでいる場合や、神経に重度の障害がある場合には、ボトックス単独では十分な改善が得られないことがあります。こうしたケースで注目されているのが再生医療です。
再生医療は、自己の幹細胞などを用いて損傷した組織や神経の修復を目指す治療法です。ボトックスでは改善が難しい症状に対して、新たな選択肢として注目されています。ただし、すべての症状が再生医療で改善するわけではなく、治療の適応や効果は症状によって異なります。
医療ボトックスに関するお悩みは、当院「リペアセルクリニック」へご相談ください。当院では、医療ボトックスに関するご相談に対応しており、症状やご希望に応じて再生医療のご提案も可能です。
ご質問やご相談は、「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」で受け付けておりますので、お気軽にお申し付けください。
\無料オンライン診断実施中!/
医療ボトックスに関するよくある相談
医療ボトックスに関しての相談はどの診療科へするべきでしょうか?
医療ボトックスは、適応となる症状や疾患によって相談先の診療科が異なります。対応する診療科は以下を参考に受診ください。
| 主な症状・疾患 | 対応する診療科 |
|---|---|
| 顔面けいれん・眼瞼けいれん | 神経内科、脳神経外科 |
| 手足の痙縮(脳卒中後など) | リハビリテーション科、整形外科 |
| 多汗症(腋窩・手のひら・足の裏など) | 皮膚科、形成外科、耳鼻咽喉科 |
| 咬筋の緊張・食いしばり・歯ぎしり | 歯科口腔外科、矯正歯科 |
| 美容目的(表情じわ、エラ張りなど) | 美容皮膚科、美容外科 |
ボトックス治療を実施しているかどうかは医療機関によって異なるため、事前にホームページや電話で確認するとスムーズです。
医療ボトックスの治療を受ける前に確認すべきポイントはありますか?
医療ボトックスの治療を受ける前に以下の7点をしっかり確認しましょう。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 1.信頼できる医療機関か | 症例数、製剤の種類、衛生管理、アフターケア体制を確認する |
| 2.カウンセリングの内容 | 希望や不安を伝え、リスクや副作用の説明をしっかり受ける |
| 3.持病や服薬の申告 | 神経筋疾患、重い心疾患、肝障害がある場合は治療できないことがある |
| 4.妊娠・授乳の有無 | 妊娠中・授乳中・妊娠希望の方は治療を避ける |
| 5.当日の体調管理 | 発熱や不調がある日は治療を延期する |
| 6.薬や飲酒の管理 | 飲酒は控える。抗凝固薬や一部の薬は事前に医師へ申告する |
| 7.治療前の準備 | 顔のバランスや筋肉の状態を医師が確認してから注射を行う |
上記以外にも不安な点がある場合は、医師に事前に相談することが大切です。
医療費控除は適用されますか?
医療ボトックスが医療費控除の対象となるかどうかは、治療目的か美容目的かによって判断されます。医療費控除の対象となるケースとしては、歯ぎしり、食いしばり、顎関節症、多汗症など、医師の診断に基づく治療目的のボトックスは、医療費控除の対象です。確定申告時に、診断書や治療内容が記載された領収書を提出することで、控除を受けられます。
一方、医療費控除の対象外となるケースは、小顔やしわ取り、ガミースマイル改善など、美容を目的とした治療は医療費控除の対象にはなりません。また、医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が一定額(通常10万円)を超えた場合、その超過分が控除されます。
治療目的であることを証明できるよう、診断書や領収書は必ず保管しておきましょう。
参考資料
アッヴィ合同会社 アラガン・エステティックス「医療用医薬品 : ボトックスビスタ」 KEGG データベース, 2025年3月
https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00056431(最終アクセス:2025年06月16日)
医療法人社団永生会「ボツリヌス(ボトックス)療法」医療法人社団永生会
https://www.eisei.or.jp/clinic/eiseiclinic-gairai/botulinum/(最終アクセス:2025年06月16日)