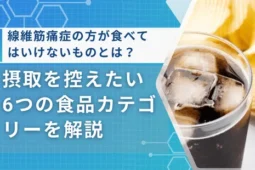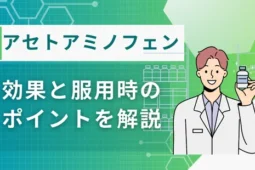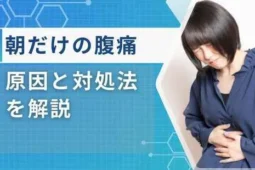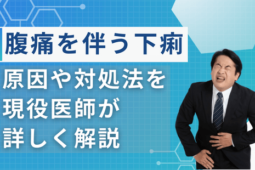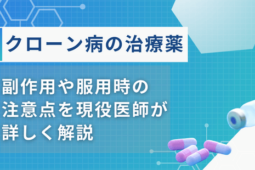- 内科疾患
- 内科疾患、その他
貧血の数値でわかる重症度|症状・入院目安・治療の判断ポイント
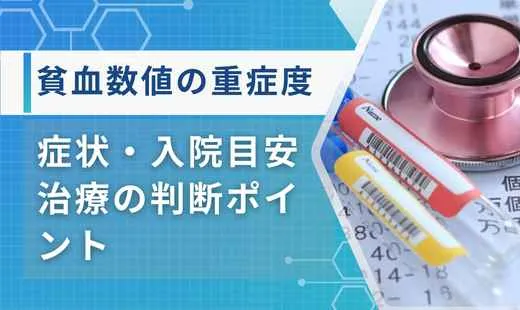
健康診断で「貧血の疑い」と言われた、あるいは血液検査の結果を見ても「どの数値が貧血を示しているのか」「自分の数値は正常なのか」分からずに不安を感じていませんか?
普段から疲れやすさやめまいを感じていて、貧血ではないかと気になっている方も多くいらっしゃいます。
この記事では、貧血に関わる血液検査の数値の見方や基準値をわかりやすく解説します。数値の見方を理解し、ご自身の状況を把握しましょう。
なお、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しています。再生医療について詳しく知りたい方は、公式LINEにご登録ください。
貧血の数値でわかる重症度
血液検査で貧血かどうかを調べるときに最も重要な項目が「ヘモグロビン」です。健康診断の結果表では以下のように表記されています。
- Hb
- HGB
- 血色素量
- ヘモグロビン
どの表記でも同じ検査値を指しており、この数値を見ることで貧血の有無や重症度を判断できます。
世界保健機関(WHO)が定義しているヘモグロビン濃度の基準は、次の通りです。
| 対象者 | 貧血なし | 軽度貧血 | 中等度貧血 | 重度貧血 |
|---|---|---|---|---|
| 6~59ヶ月の小児 | 11.0 g/dL以上 | 10.0~10.9 g/dL | 7.0~9.9 g/dL | 7.0 g/dL未満 |
| 5~11歳の小児 | 11.5 g/dL以上 | 11.0~11.4 g/dL | 8.0~10.9 g/dL | 8.0 g/dL未満 |
| 12~14歳の小児 | 12.0 g/dL以上 | 11.0~11.9 g/dL | 8.0~10.9 g/dL | 8.0 g/dL未満 |
| 非妊娠女性(15歳以上) | 12.0 g/dL以上 | 11.0~11.9 g/dL | 8.0~10.9 g/dL | 8.0 g/dL未満 |
| 妊娠女性 | 11.0 g/dL以上 | 10.0~10.9 g/dL | 7.0~9.9 g/dL | 7.0 g/dL未満 |
| 男性(15歳以上) | 13.0 g/dL以上 | 11.0~12.9 g/dL | 8.0~10.9 g/dL | 8.0 g/dL未満 |
(文献1)
上記のWHO基準に加えて、ヘモグロビン値ごとの症状の現れ方や治療の必要性は以下が目安です。
| ヘモグロビン値 | 主な症状・体への影響 |
|---|---|
| 11〜12 g/dL | ほとんど自覚症状なし |
| 9〜10 g/dL | 頭痛・だるさ・肩こり・動悸や息切れ |
| 7〜8 g/dL | 治療として輸血が必要になることがある |
| 6 g/dL以下 | 息切れや息苦しさなど心不全の症状が現れることが多い |
数値や症状はあくまで目安であり、年齢や持病の有無によって症状の現れ方は変わります。気になる場合は医師に相談しましょう。
血液検査における数値|貧血の基準値
健康診断や血液検査の結果を見ても、数字の意味がわからず不安を抱く方は多いのではないでしょうか。
ヘモグロビンの他にも、ヘマトクリットなどの基準値と意味を理解できれば、自分の数値がどの範囲にあるかを判断しやすくなります。
この項目では、各検査項目の数値の見方と貧血との関係について詳しく解説します。
血色素量(ヘモグロビン:Hb)
ヘモグロビンは赤血球に含まれる鉄分を持つタンパク質で、体内で酸素を運ぶ重要な役割を担っています。血液検査でヘモグロビン値を確認すれば、貧血のリスクや体への影響を判断できます。
| 対象 | 基準値 |
|---|---|
| 15歳以上の男性 | 13g/dL未満 |
| 15歳以上の女性 | 12g/dL未満 |
(文献1)
症状がなくても数値が少しずつ下がっている場合は注意が必要です。
ヘマトクリット(Ht)
ヘマトクリットは、血液の中で赤血球がどのくらいの割合を占めているかを示す数値です。血液の中には主に赤血球が含まれているため、ヘマトクリットを見ると赤血球がどのくらいあるかがわかります。
年齢や性別によって基準値が異なりますが、数値の目安は以下のとおりです。
| 対象 | 基準値 |
|---|---|
| 男性 | 40.7~50.1% |
| 女性 | 35.1~44.4% |
(文献2)
ヘマトクリット値は月経による鉄分の損失や、男性ホルモンによる赤血球産生の違いがあるため、女性の方が男性よりもやや低い傾向にあるのが一般的です。
ヘマトクリット値が低下していると、赤血球が不足していることを示し、貧血の可能性があります。また、数値が高いときは脱水や多血症など、赤血球が相対的に増えている状態が考えられます。
赤血球数(RBC)
赤血球数(RBC)は、血液の中にどれくらい赤血球があるかを示す検査値です。赤血球は体のすみずみに酸素を運ぶ役割を持っているため、不足すると体に影響が出やすく、多すぎてもリスクがあります。
赤血球数の基準値の目安は以下のとおりです。
| 対象 | 基準値 |
|---|---|
| 男性 | 435~555×10⁶/μl |
| 女性 | 386~492×10⁶/μl |
(文献2)
男性の方が女性よりも数値が高めになるのは、男性ホルモンが赤血球を作る働きを活発にする点や、女性は月経で鉄分を失いやすい点が関係しています。
赤血球数が低いと、酸素を運ぶ力が不足している状態で、貧血の可能性があります。そのため、鉄分の不足や出血の有無もあわせて調べることが大切です。
また、基準値を超えて赤血球数が多い場合は、多血症が考えられます。とくに喫煙者や高地に住んでいる方は高めに出やすい傾向があります。生活習慣や体調を見直し、必要に応じて精密検査を受けましょう。
MCV(平均赤血球容積)
MCVは赤血球1個あたりの大きさを示す検査値で、貧血の種類や原因を判断する手がかりになります。
MCVの基準値の目安は、以下の通りです。
| 対象 | 基準値 |
|---|---|
| 男性・女性 | 83.6〜98.2fl |
(文献2)
MCVの数値が低い場合は赤血球が小さく、鉄が不足している可能性があります。鉄剤の補充などで数値の改善が期待できます。
一方、MCVの数値が高い場合は赤血球が大きく、ビタミンB12や葉酸不足が主な原因です。必要に応じて栄養補給や治療が検討されます。
MCVの数値は単独ではなく、他の血液検査と組み合わせて判断するのが重要です。数値の傾向を把握すれば、貧血の種類や必要な対応を見極めやすくなります。
MCH / MCHC(赤血球中のヘモグロビン量・濃度)
MCH(平均赤血球ヘモグロビン量)とMCHC(平均赤血球ヘモグロビン濃度)は、赤血球1個あたりに含まれるヘモグロビンの量と濃度を示す検査値で、貧血のタイプや原因を把握する手がかりになります。
MCHとMCHCの数値の目安は以下のとおりです。
| MCH(平均赤血球ヘモグロビン量) | MCHC(平均赤血球ヘモグロビン濃度) |
|---|---|
| 男性・女性:27.5~33.2pg | 男性・女性:31.7~35.3g/dL |
(文献2)
MCHとMCHCの数値が低い場合、赤血球1個に含まれるヘモグロビンが少ないことを意味し、鉄欠乏性貧血や慢性疾患による貧血が疑われます。
また、MCHとMCHCの数値が高いときは赤血球中のヘモグロビンが濃く、脱水や血液疾患が関係している場合があります。
MCH・MCHCは、赤血球1個あたりの酸素運搬能力を知る手がかりです。数値の変化は疲れやすさや息切れなどの症状として現れることがあります。
フェリチン(貯蔵鉄)
フェリチンは体内に鉄分を貯蔵するタンパク質で、主に肝臓や骨髄などに存在します。
血中のフェリチン値は体内の鉄分の貯蔵量を反映するため、鉄欠乏や鉄過剰の診断において重要な指標です。
フェリチンの基準値範囲は以下のとおりです。
| 対象 | 基準値 |
|---|---|
| 男性 | 25~280 ng/ml |
| 女性 | 10~120 ng/ml |
(文献2)
ヘモグロビン値が正常でも、フェリチン値が低い場合は隠れ貧血や鉄欠乏の可能性があります。体内の鉄分が少なくなっている状態で、早めの対策が重要です。
一方、フェリチン値が高い場合は白血病や肝臓障害、感染症などが関係している可能性があります。
フェリチン値は、貧血リスクの判断材料だけでなく生活習慣の見直しにも役立ちます。
血清鉄(Fe)
血清鉄(Fe)は、血液中に存在する鉄分の量を示す検査値です。血中の鉄分は主にトランスフェリンと呼ばれるタンパク質と結合して体内を運ばれ、鉄分の利用状況を把握する手がかりになります。
血清鉄の基準範囲は、以下の通りです。
| 対象 | 基準値 |
|---|---|
| 男性・女性 | 40〜188μg/dL |
(文献2)
血清鉄値が低い場合は鉄欠乏性貧血の可能性があり、逆に高い場合は急性肝炎や急性白血病などが関係しているときがあります。
また、炎症性疾患や感染症で血清鉄が低下する場合があるため、ほかの検査値も踏まえて総合的に判断する必要があります。
【貧血のタイプ別】数値の見方
貧血にはいくつかのタイプがあり、それぞれ特徴的な数値の傾向があります。自分の血液検査の結果と照らし合わせることで、どのタイプの貧血の可能性があるかを把握しやすくなります。
各タイプの特徴的な数値や注意点を一つずつみていきましょう。
鉄欠乏性貧血の特徴
鉄欠乏性貧血では、血液検査で特徴的な数値の変化が現れます。
主な傾向は以下の通りです。
- ヘモグロビン(Hb):低下
- 平均赤血球容積(MCV):低下
- 平均赤血球ヘモグロビン量(MCH):低下
- フェリチン(貯蔵鉄):低下
- 総鉄結合能(TIBC):上昇
上記の数値パターンは、鉄不足によって赤血球が小さく色が薄い状態になることを示しています。フェリチンの低下は体内の鉄貯蔵量の枯渇を、総鉄結合能(TIBC)の上昇は体が鉄分を取り込もうとしている状態です。
血液検査の数値を総合的に見ることで、鉄欠乏性貧血のリスクや体への影響を判断する目安になります。
隠れ貧血(潜在性鉄欠乏)
隠れ貧血は、一般的な血液検査では見つかりにくい貧血の前段階で、ヘモグロビン値が正常範囲内でも、体内の鉄貯蔵量が不足している状態を指します。
自覚症状がほとんどないことも多く、見過ごされやすいため注意が必要です。
主な数値の傾向は以下の通りです。
- Hb(ヘモグロビン):正常範囲内
- フェリチン(貯蔵鉄):低下
フェリチン値が低い場合、体内の鉄分が枯渇し始めており、将来的に貧血へ進行する恐れがあります。とくに、女性は月経による鉄分損失があるため、男性よりも注意深い観察が必要です。
定期的にフェリチン値をチェックしておくと、自覚症状が出る前の早期段階で鉄欠乏を発見でき、食事やサプリでの補給など適切な対策につなげられます。
悪性貧血(ビタミンB12欠乏)の特徴
ビタミンB12欠乏による悪性貧血では以下の特徴が見られます。
- ヘモグロビン(Hb):低下
- 平均赤血球容積(MCV):上昇
- 葉酸:低下
- ビタミンB12:低下
ビタミンB12や葉酸は赤血球の正常な形成に必要な栄養素で、不足すると赤血球が大きくなるのが特徴です。
血液検査の数値が上記に当てはまる方は、赤血球の形成に関わる栄養が不足している可能性があります。
必要に応じて医師に相談し、適切な治療を受けたり生活習慣の見直しをしたりしましょう。
慢性疾患に伴う貧血の特徴
慢性疾患に伴う貧血は、次のような基礎疾患が原因となることがあります。
- 感染症
- 悪性腫瘍
- 関節リウマチ
- 心不全
- 腎疾患
主に、慢性的な炎症によって鉄分がうまく利用されず、赤血球が作られにくくなる傾向にあります。血液検査ではフェリチンが正常から高値を示すことが多く、体内に鉄分はあるものの、ヘモグロビンの合成に使われにくい状態を反映しています。
根本的な改善には、原因となる疾患の治療が重要で、単純な鉄剤補充だけでは十分な効果が得られにくいことが特徴です。
血液検査の数値を総合的に見ながら、医師と相談して適切な対応を検討しましょう。
貧血の数値改善法
貧血の数値改善法は主に以下の2つです。
- 鉄剤内服・注射での治療
- 生活習慣の見直し
血液検査で貧血が疑われても、原因や程度は人によって異なります。改善のためには、医師の診断にもとづいた治療と日常生活での工夫の両方が重要です。
鉄剤内服・注射での治療
鉄欠乏性貧血と診断された場合、基本となる治療は鉄剤による補充です。一般的には内服薬が用いられますが、症状や数値によって注射が選ばれるケースも見られます。
副作用としては、便秘・下痢・吐き気・胃の不快感などがみられることがあります。
治療の優先度や検査の必要性を含め、自分の状態に合った方法を選ぶことが大切です。
生活習慣の見直し
軽い貧血の場合は、毎日の食事や生活の工夫で良くなる場合があります。
具体的なポイントは、下記の通りです。
- 食事:鉄分を多く含む食品を普段の食事に取り入れる。ビタミンCやたんぱく質を一緒に摂取すると鉄分の吸収が良くなる。
- 飲み物の工夫:食事中のコーヒーや緑茶、清涼飲料水は鉄分の吸収を妨げるため食事の前後は控えると効果的
- 睡眠と休養:夜更かしを避ける、休日にしっかり体を休めるなど体の回復を意識する
鉄分は、どのように組み合わせて食べるかで吸収率が変わります。赤身肉やレバーなどの動物性食品には鉄分が多く含まれているので、積極的に摂取しましょう。
一方、コーヒーや緑茶に含まれるタンニンや、清涼飲料水や加工食品に添加されることが多いリン酸塩は、鉄分の吸収を妨害する要因になるので注意が必要です。
さらに、睡眠不足はホルモンや自律神経のバランスを乱し、血液をつくる働きを妨げることがあります。夜更かしを避け十分な睡眠をとることは、貧血改善の基盤となります。
小さな工夫を積み重ねることで、数値改善につながる可能性があります。無理のないところから始めてみましょう。
貧血の受診目安
健康診断で貧血を指摘されたら、症状がなくても内科や婦人科を受診しましょう。必要に応じて、治療が推奨される場合もあります。
高齢の方では、年齢のせいと見過ごされやすい軽いめまいや疲れやすさが、実は進行した貧血のサインとなっている場合があります。
血液検査の数値は目安のひとつにすぎず、体調の変化やライフステージによって必要な対応は変わります。
数値にとらわれず、違和感を覚えたら早めに医師へ相談しましょう。
貧血と数値の関係性を理解して適切に対処しよう
血液検査の数値を確認することで、貧血の程度や必要な対処法を把握できます。
数値を見る際のポイントは、以下の通りです。
- ヘモグロビンや赤血球数が基準値よりどのくらい下がっているか把握する
- 鉄分の貯蔵量(フェリチン)を把握する
- 症状がなくても再検査や医師相談が必要な場合がある
上記を把握しておくことで、自分に必要な行動を選べます。
軽い疲れやめまい、息切れもサインになることがあるので、数値だけでなく体調の変化にも注意しましょう。
健康管理では、貧血だけでなく様々な体の不調に早めに気づくことが大切です。
当院「リペアセルクリニック」のLINEでは、関節の痛みや脳梗塞、糖尿病など再生医療に関する情報をお届けしています。貧血の治療は対象外ですが、幅広い健康管理の参考として、ぜひご登録ください。
\無料オンライン診断実施中!/
参考文献