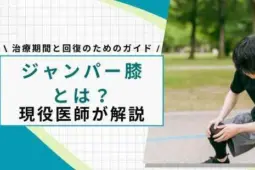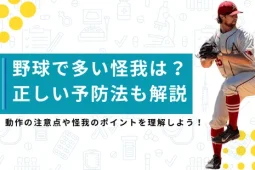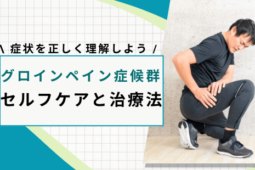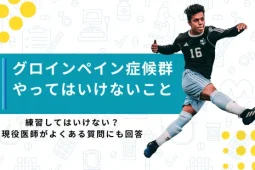- 下肢(足の障害)
- スポーツ外傷
かかとの痛み、実は疲労骨折かも?初期症状や治療法を解説
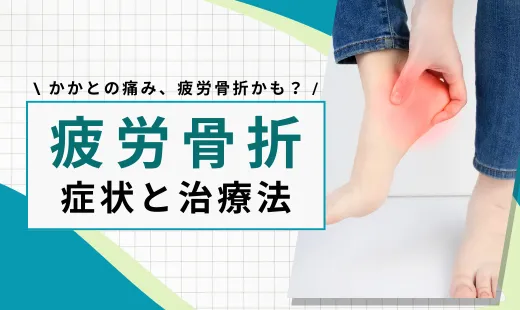
「歩くとかかとが痛い」「原因はわからないがかかとが痛む」
その症状は、かかとの疲労骨折かもしれません。
疲労骨折は中足骨や足首などで起きやすいというイメージを持っている人もいるでしょう。
中足骨、足首周辺と比べると少ないケースではありますが、かかとも疲労骨折を起こすことはあるため注意が必要です。
この記事ではかかとの疲労骨折について解説します。
通常の骨折との違いや治療にかかる期間、予防対策についても紹介しています。原因不明のかかとの痛みに悩まされている人は、参考にしてください。
目次
かかとの疲労骨折とは?通常の骨折との違い
疲労骨折とは、長時間の運動など負荷が継続的に骨に加わることで起こる骨折です。
ジャンプすることが多いスポーツや、長時間の立ち仕事など、足を酷使する状況が長時間ある人がなりやすいとされています。
通常の骨折との大きな違いは、痛みの原因が明確にあるかどうかです。
通常の骨折は、「着地に失敗してかかとを強打した」「事故などでかかとを強打した」など、強い衝撃が加わったことで起こる「外傷性骨折」の場合がほとんどです。
対して疲労骨折はダメージの蓄積によって発生します。
そのため、徐々に患部の痛みが強まっていく場合もあり、すぐに気付けなかったという例も少なくありません。
かかとの疲労骨折の特徴的な症状
かかとの疲労骨折の主な症状は以下の通りです。
- かかとに圧をかけると強い痛みが起こる
- かかと付近の腫れや熱感、あざができることもある
- 歩行が困難になる
また、かかとの骨折が原因で合併症や後遺症を引き起こす可能性もあります。
合併症では、骨折による強い腫れが周辺の血管を圧迫し、血流障害を起こすコンパートメント症候群が発生することがあります。ただし、かかとの疲労骨折でこの合併症が起こることは極めてまれです。
骨折による変形や可動域の低下といった後遺症が見られることも少なくありません。
合併症や後遺症を防ぐためには早期の治療が最善です。自己診断で決めつけず、まず医師に相談しましょう。
疲労骨折を起こしやすい人の特徴
疲労骨折を起こしやすい人の特徴は以下の通りです。
- スポーツをしている。
- 仕事や日常生活でずっと立っていること、歩くことが多い。
- 成長期や更年期などで骨がもろくなっている。
- 栄養バランスが乱れている。
- 靴底が薄い靴を履いている。
特にかかとは固い床、地面への着地時に負荷がかかることが多いと言われています。
ジャンプすることが多いバスケットボールやバレーボールなどの種目は注意が必要です。
また、蹴り上げる動作の多い陸上競技やヒールを履いて行うダンス競技もかかとへの負担が大きいとされています。
かかとの疲労骨折の診断および治療
かかとの疲労骨折は適切な診断と治療が重要です。
疲労骨折は通常の骨折とは異なり、蓄積されたダメージによって起こるため、診断には専門的な検査が必要になることがあります。
治療では安静を基本として、症状に応じて松葉杖やテーピングなどを用いて患部への負担を軽減します。完治には医師の指導に従った段階的な治療とリハビリが欠かせません。
この項目ではかかとの疲労骨折の診断方法や完治するまでの治療法について解説します。
疲労骨折の検査・診断方法
疲労骨折の場合、早期の検査ではレントゲンで骨折線が見えないケースが多いです。
そのため、CT検査やMRI検査を行い患部の状況を確認します。MRI検査では、レントゲン上では見えなかった骨周辺の炎症などによって判断が可能です。
発症後2~3週間経つと、骨折線が見えてくることがあります。
かかとの疲労骨折の治療法
かかとの疲労骨折の治療は安静が基本です。軽傷なら1〜1.5か月、重症なら2〜3か月の安静期間が必要で、スポーツは原則禁止となります。
重い荷物を持つことは控え、ケガをしている足での歩行もなるべく避けてください。症状に応じて松葉杖やテーピングを用います。
テーピングは症状緩和と再発防止に効果的ですが、間違った方法では骨の癒合不良や症状悪化を招くため、必ず医師の指導のもとで行ってください。
定期的な通院で治癒状況を確認し、段階的なリハビリも早期完治に有効です。完治後もリハビリを続け、再発防止に努めましょう。
自己判断でのスポーツ再開は危険なため、医師の判断を最優先とし、些細なことでも相談してください。
かかとの疲労骨折を防ぐためにすべきこと
疲労骨折を防ぐためには、まず継続的な負荷を軽減するのが有効です。
- 休息をしっかりとる
- 普段使用する靴を見直す
- 栄養バランスを整える
これらの予防法について詳しく見ていきましょう。
休息をしっかりとる
例えば、スポーツをしている人は練習量の調節からはじめてください。
アスリートは練習のしすぎによって疲労骨折を起こしてしまうことが多いです。
適度に休憩時間をとる、運動後のストレッチやマッサージを行うなど、運動以外のケアにも目を向けましょう。
普段使用する靴を見直す
運動時の靴を変えることで疲労骨折のリスクが軽減される可能性もあります。
靴底がすり減って薄くなっているとクッション性が失われ、踏み込んだ際のダメージが直接骨に届いてしまいます。
また、外側だけすり減っているなど、靴の形自体が変形してしまうと姿勢の崩れの原因にもなり余分な負荷がかかってしまうこともあります。靴の定期的なメンテナンスは非常に重要です。
栄養バランスを整える
骨の強度を保つために食事の栄養バランスを整えることも大切です。カルシウム、ビタミンDなどが骨を強くします。
カルシウムは以下の食品に多く含まれています。
- 乳製品や大豆製品
- にぼしなどの小魚
ビタミンDが多く含まれている食品は以下の通りです。
- 魚介類
- きのこ類
普段の食事に意識的に取り入れ、骨折しない体づくりを心がけましょう。
まとめ|かかとでも疲労骨折は発生する!長引く痛みはすぐに専門の医師へ相談を
かかとの疲労骨折は継続的に負荷がかかることで発生します。
例えば、ジャンプをするスポーツや地面を踏み込むスポーツを長くやっている人や長時間歩く、立ったままの仕事をしている人は注意が必要です。
かかとの疲労骨折の完治には1か月〜3か月ほどかかります。治療期間は重い荷物を持たない、歩行時になるべく患部に負担をかけないことが必要です。
症状の度合いによってはテーピングなども行いましょう。テーピングは症状の緩和だけでなく再発の予防にも効果的です。
かかとの疲労骨折を予防するためには継続的な負荷を軽減することが重要です。
スポーツをしている人は練習量を調整し、十分な休息をとることを心がけて下さい。
また、休息以外にも骨を強くするための栄養管理や、靴のメンテナンスも疲労骨折の予防に効果があります。
疲労骨折は蓄積されたダメージによって起こるため、自分では気づきづらいケガのひとつです。
かかとの痛みが長引く場合は疲労骨折の可能性も踏まえ、まずは医療機関を受診しましょう。
\無料相談受付中/
かかとの疲労骨折に関してよくある質問
かかとの疲労骨折ではどんな痛みが起きる?
かかとの疲労骨折の特徴的な痛みとして、
- かかとに圧をかけると強い痛みが起こる。
- 足と足首が大きく腫れ上がり、あざができることもある。
- 歩行が困難。
などが挙げられます。
かかとの疲労骨折は全治何カ月?
症状の重さにもよりますが、おおよそ1か月~3か月ほどで完治します。
治療にかかる期間や治療期間の制限などは重症度で変わるため、医師に相談しましょう。
かかとの疲労骨折は、合併症や、変形、神経障害などの後遺症が残ることがあります。骨が完全に癒合するまで必ず通院を続けてください。
かかとが疲労骨折した状態でも歩ける?
かかとが疲労骨折を起こした場合、歩くことはできますが健常時のように歩くことは非常に困難です。
歩いた際にかかとに負荷がかかり、強い痛みを感じる可能性があります。
重症の場合は松葉杖を使用し、患部への負担を軽減するようにしましょう。