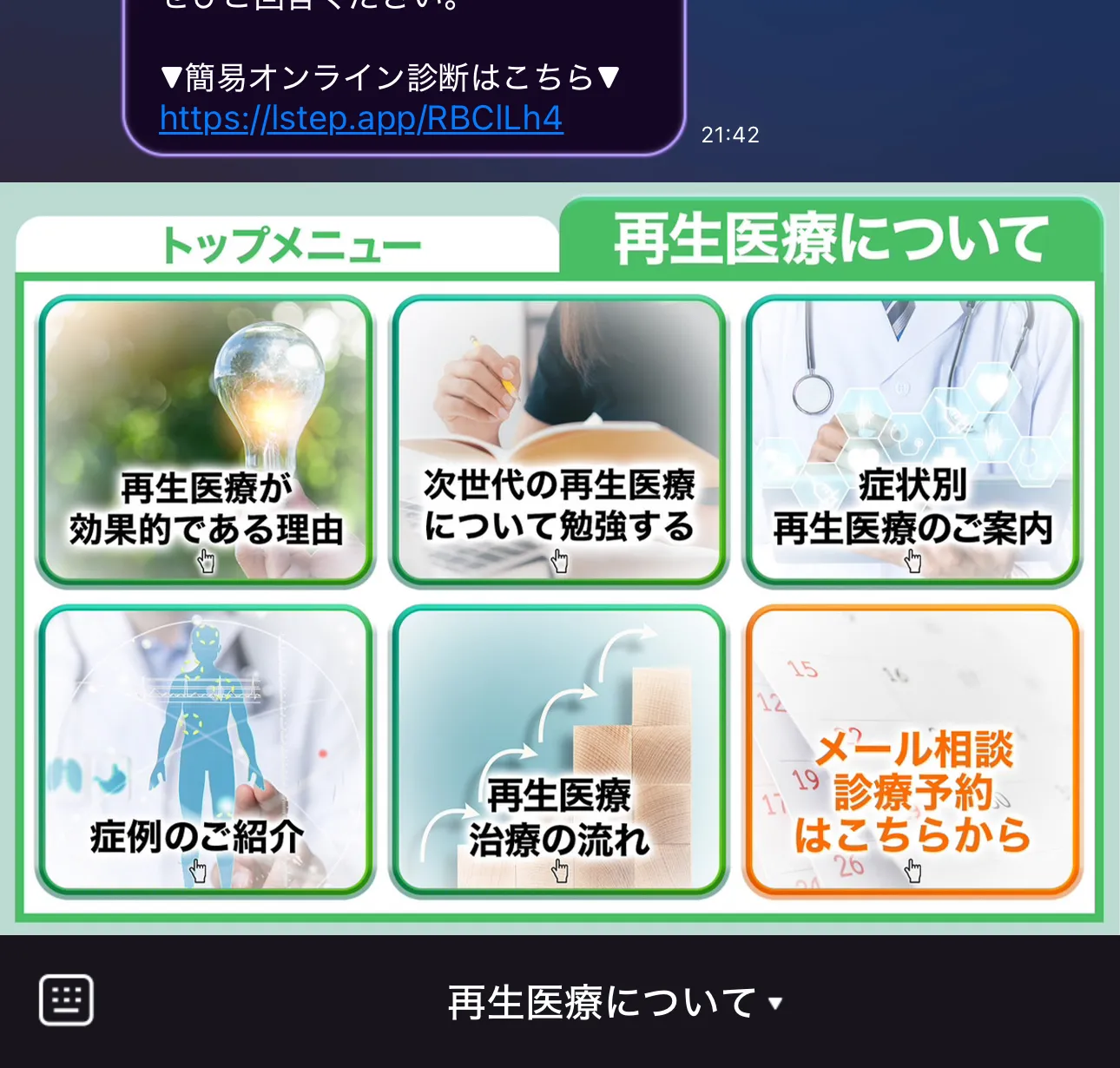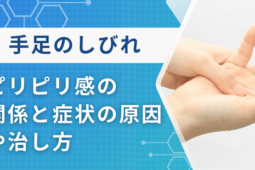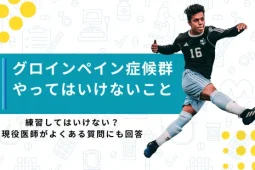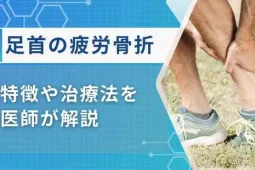- 足部、その他疾患
- 下肢(足の障害)
- 足部
- スポーツ外傷
捻挫の重症度をチェックする方法!病院に行くべきか判断する基準も解説

足首や手首をひねった際に「痛みはあるけど病院に行った方が良いのかな?」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。
「軽い捻挫だろう」と放置されやすいですが、捻挫が癖になったり関節炎になるリスクがあるため、症状に合わせて適切な治療を受けることが重要です。
しかし、捻挫は自己判断が難しいケースも多く「実は捻挫ではなく靭帯が断裂していた」という場合も少なくありません。
本記事では、捻挫した部位別に重症度をチェックする方法や病院に行く判断基準について解説します。
また、リペアセルクリニックではご自身の治癒力を活用して早期復帰をサポートする「再生医療」を提供しており、捻挫症状の改善が認められた症例を公式LINEで配信中です。
つらい痛みから解放されるための一歩を踏み出すために、ぜひ 参考にしてください。
\公式LINEでは再生医療に関する情報や症例を公開中!/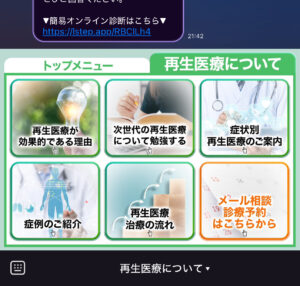
▼LINE限定の再生医療に関する情報は以下からご覧ください
目次
【部位別】捻挫の重症度をチェックする方法
捻挫とは、転倒時や段差を踏み外したときなどに、関節に負荷がかかって起こるけがのことです。関節まわりの靱帯や腱、軟骨などを損傷している状態を指します。
軽度の場合はギプスやサポーターで損傷した部位を固定することで治療できますが、重症の場合は手術が必要になるケースもあります。そのため、捻挫をした初期段階で重症度を正しく診断し、早期に適切な治療をおこなうことが大切です。
本章では、捻挫の重症度を以下3つの部位別に解説します。
- 足首の捻挫の場合
- 手首の捻挫の場合
- 指の捻挫(突き指)の場合
自分の捻挫をセルフチェックする際の参考になれば幸いです。また、捻挫を早く治す方法について調べている方は、以下の記事もご覧ください。
足首の捻挫の場合
足首を捻挫した場合は、「Ottawa Ankle Rule(以下、オタワ アンクル ルール)」をもとにセルフチェックを行いましょう。
オタワ アンクル ルールは5つの項目で構成されており、該当する項目が1つでもあれば骨折の可能性があると判断します。
※圧痛:皮膚に圧力(押すなど)を与えた際に痛みを感じること
もし該当する項目がある場合、早めに整形外科を受診し、レントゲンなど詳しい検査を受けることをおすすめします。
また、該当の項目がなくても足首の違和感や痛み、腫れが続いている場合は早めに受診しましょう。
「病院に行く時間がない」という方は、ぜひ当院(リペアセルクリニック)にお電話ください!
また、当院の公式LINEでは、患者さまの細胞を活用し早期改善を目指せる「再生医療」に関する情報を配信しています。
スポーツ外傷に対する症例も公開しているため、ぜひ参考にしてください。
手首の捻挫の場合
手首の捻挫では、動かしたときの違和感や痛み、熱の有無などによって重症度をチェックできます。
以下の表はあくまでセルフチェックとして利用し、症状が続く場合は整形外科を受診しましょう。
|
チェック項目 |
手首の捻挫の重症度 |
|
曲げ伸ばし、ひねるなどの動作をすると痛み・違和感がある |
軽度 |
|
負傷したカ所が腫れており、少しでも動かすと痛み・違和感がある |
中度 |
|
負傷したカ所を動かさなくても痛みがある。あるいは熱を持っている |
重度(骨折の疑いあり) |
手首の捻挫は、骨折と見分けるのが難しいケースも多くあります。
1週間以上痛みが引かない場合は整形外科を受診し、レントゲンなどの検査を受けることをおすすめします。
指の捻挫(突き指)の場合
指の捻挫(突き指)をした場合、以下の表をもとに重症度をセルフチェックしてみましょう。
|
チェック項目 |
指の捻挫の重症度 |
|
・痛み、違和感がある ・腫れている ・曲げ伸ばしは可能 |
軽度 |
|
・炎症(痛みや腫れ)が一週間以上続く ・曲げ伸ばしが困難 ・指が変形しているように見える |
中度から重度 (腱の損傷や骨折、靱帯損傷の疑いあり) |
指の捻挫は、軽度であれば1週間程度で炎症がおさまることが多いですが、症状がある場合は念のため病院に行くことをおすすめします。
整形外科を受診し、レントゲンなどの詳しい検査を受けましょう。
突き指と指の骨折、靱帯損傷について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしていただけると幸いです。
捻挫を放置するリスク
捻挫を治療せず放置した場合、以下のリスクが考えられます。
- 捻挫を繰り返しやすくなる
- 痛みが長引く
- 機能障害が残る(例:関節の可動域が狭くなる) など
たとえ軽い捻挫であっても、保存療法など適切な治療をしなかった場合、靱帯が伸びた状態で固定されてしまいます。靱帯が伸び、関節が緩んでいる状態で負荷をかけると、同じ部位の捻挫を繰り返したり、痛みが長引いたりするリスクが高まるでしょう。
また、捻挫した部分が不安定になり、歩行や運動時のパフォーマンスへの影響も考えられます。骨折や変形につながる可能性もあるため、捻挫をした場合は早い段階で保存療法をはじめとする治療をおこないましょう。
捻挫と見分けにくい3つのけが
捻挫と見分けることが難しいけがは、以下の3つが挙げられます。
- 脱臼
- 骨折
- 関節軟骨損傷
捻挫の痛みが続く場合は、本章で紹介した外傷の可能性を考慮し、病院での受診を検討しましょう。
脱臼
脱臼とは、靱帯などの組織が損傷し、関節が外れてしまっている状態を指します。一方、捻挫は靱帯が傷ついてるものの、関節部分は外れておらず、安定性を保っている状態です。
脱臼の治療では「整復」もしくは「固定」を実施します。それぞれの治療法の詳細は以下のとおりです。
|
治療法 |
内容 |
|
整復 |
皮膚の上から、もしくは手術により、ずれた骨を元の位置に戻す |
|
固定 |
ギプス等の器具を装着して脱臼した部位を正しい位置で固定する |
部位や重症度によって差はありますが、脱臼の治療期間は、一般的には1カ月前後です。
骨折
捻挫した部位の変形や内出血、強い腫れがみられる場合、骨折をしている可能性があります。骨折の場合は、脱臼と同様「整復」もしくは「固定」をおこないます。
体重をかけることで悪化するリスクもあるため、捻挫か骨折か判断できないときは早めに整形外科を受診しましょう。
関節軟骨損傷
捻挫の痛みや違和感が長期的に継続する場合、関節軟骨損傷が疑われます。
関節軟骨損傷とは、関節の骨端表面にある組織が損傷している状態です。放置すると変形性関節症を引き起こすリスクもあるため、早めに適切な治療をおこなう必要があります。
関節軟骨損傷の場合、ギプスでの固定で治療するのが一般的です。ただし慢性化した場合は手術が必要になるケースもあります。
捻挫の痛みが続く場合は「軽度だから大丈夫」と放置せず、早めに医療機関を受診しましょう。
まとめ|捻挫の重症度をチェックして病院に行くべきか正しく判断しよう
捻挫の重症度をチェックする方法は、捻挫の部位によって異なります。捻挫だと思っていたけがを放置すると、変形性関節症などの病気につながる可能性が高くなります。
痛み・違和感が長期間続く場合や、部位を動かせないほどの炎症が起こっている場合は、早めに整形外科を受診しましょう。
当院「リペアセルクリニック」では、捻挫などの外傷に対する再生医療や幹細胞治療をおこなっています。
一般的に捻挫の治療では、3〜4週間の固定後、2〜3カ月間のリハビリをおこないます。しかし固定治療によって関節が固まると、リハビリがそれ以上長期化するケースも少なくありません。
再生医療を実施すれば、固定期間・リハビリ期間を短縮し、より早期に社会復帰できる可能性が高まります。捻挫の治療法やリハビリの長期化を懸念している方は、ぜひ一度「リペアセルクリニック」へご相談いただければ幸いです。
また、当院の公式LINEでは、患者さまの細胞を活用し早期改善を目指せる「再生医療」に関する情報を配信しています。
スポーツ外傷に対する症例も公開しているため、ぜひ参考にしてください。
捻挫の重症度チェックについてよくある質問
捻挫をした場合、どうしたら良いですか?
まずは痛みの部位を確認して、体重をかけられるか確認しましょう。
痛みの部位は上記のチェックリストを参考にして、「くるぶしの内側」「くるぶしの外側」「かかとの外側」「足背から内側」にかけて押して確認します。押して痛みがある場合や、体重をかけられない場合には、病院受診をお勧めします。
また、捻挫の初期対応として知っておきたいのが、受傷の初期、急性期と言われる時点での対応をまとめた「POLICE」です。
POLICE
- Protection(保護)
- Optimal Loading(最適な負荷)
- Ice(冷却)
- Compression(圧迫)
- Elevation(挙上)
※拳上とは
捻挫した患部を心臓より高い位置に保つことで内出血による腫れを防ぐためです。
急性期の傷害対処法は、一般的に受傷後48~72時間以内にPOLICEによる処置を行うことが基本となります。
しかし、急性期を過ぎても患部が腫れている、触ると熱を持っているなどの場合は、引き続き「POLICE」処置を継続し、病院を受診することをおすすめします。
急性期には負荷をかけられないので、怪我をした直後は包帯で圧迫してアイシングを行い、足を挙上しておくようにしましょう。冷感湿布による冷却も、炎症の鎮静に効果的です。
捻挫は、どの程度の期間で治りますか?
軽度の靭帯損傷で、手術が必要ない場合には足関節をシーネやギプスで最低3週間の固定が推奨されており、長い場合には6週間程度固定を行うこともあります。また、スポーツの復帰時期については症状経過によります。
一般的には痛みがなくなった後からサポーターをして、ウォーキング、ジョギングなどの軽いスポーツから復帰し、徐々に元の競技へ復帰とします。
その間にチューブやタオルを使って足関節周囲筋を鍛えておき、必要であれば予防のためのリハビリも行う場合があります。
病院でのアドバイスに従いましょう。
捻挫後、時間が経過したが、痛みが残っている場合はどうしたら良いですか?
捻挫による靭帯損傷は重症度により3段階に分類されます。
このうち最も重症な「靭帯の完全断裂」では手術も検討されますし、治療が適切に行われなかった場合には足関節の不安定性を生じてしまいます。
また、捻挫と思っていても、距骨という骨の軟骨が損傷してしまっていることもあります。
このように、痛みが残っている場合には、足関節の不安定性や軟骨損傷の有無など、原因を詳しく調べる必要があるため早めの病院受診が大切です。
病院を受診する場合は何科を受診すれば良いですか?
捻挫した場合は、整形外科を受診しましょう。