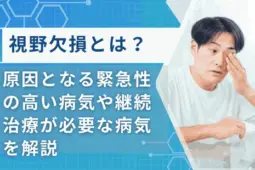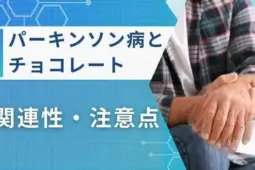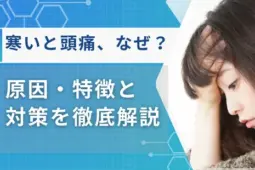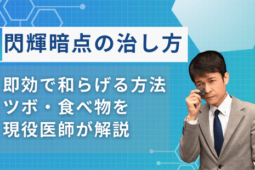- 頭部、その他疾患
パーキンソン病にバナナは良くない?気を付けたい食事とおすすめの食べもの5選
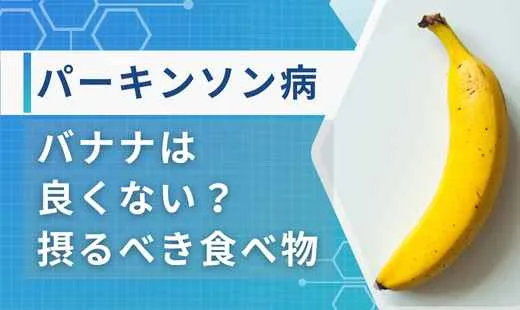
パーキンソン病の人にバナナは良くない、という話を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。
実は、バナナは摂取するタイミングや量によっては、パーキンソン病の症状の改善を妨げてしまう可能性があるのです。
この記事ではパーキンソン病の人にとってバナナが良くないと言われている理由を解説します。
バナナ以外に気を付けるべき食事のほか、治療中とるべき食事についても紹介しているので、治療中の人やその家族の人はぜひ参考にしてみてください。
目次
パーキンソン病の薬とバナナの同時服用は注意!
パーキンソン病の人がバナナを食べてはいけないと言われている理由は、バナナに含まれるビタミンB6が大きく関係しています。
このビタミンB6は、パーキンソン病の人が治療で用いる薬の効果を弱めてしまう危険性があります。
パーキンソン病は脳内のドパミン神経細胞が減少することが原因で、手足の震え、身体が動かしづらい、転倒しやすくなってしまうという症状が出る病気です。
そのため、パーキンソン病の治療では「L-ドパ」というドパミンの前駆物質(体内で酵素の作用によりドパミンに変わる物質)として働く薬を用います。
バナナに含まれるビタミンB6は、L-ドパが脳に届く前に体内でドパミンに変えてしまうため、脳に届くL-ドパの量が減ってしまうのです。(文献1)
しかし、現在では薬内にL-ドパの分解を防ぐ成分を配合していることも多いため、過剰摂取をしなければそこまで神経質になる必要はありません。
パーキンソン病でバナナ以外にも気を付けたい食事
パーキンソン病の方は、バナナ以外にも注意が必要な食事があります。
しかしいずれも過剰な摂取を控え食事のタイミングに気を付けていれば、食事が原因でパーキンソン病が悪化することはありません。
大量摂取に気を付けるべき食事やそれぞれの注意点について紹介します。
ビタミンB6
ビタミンB6は、大量摂取をするとL-ドパの吸収を妨げる可能性があります。
ビタミンB6はバナナのほか、アボカド、にんにく、かつお、鶏レバーに多く含まれています。
しかし、近年の研究でビタミンB6は50mg以上摂取しなければ影響はないという報告もあります。(文献1)
L-ドパには分解を防ぐ成分も入っているため、摂取する量やタイミングに気を付ければ、あまり大きな影響もないといえます。
ビタミン剤などのサプリメントは使用時に医師に相談しましょう。
投薬直後の高たんぱく食
投薬直後の高たんぱく食は、ビタミンB6同様L-ドパの吸収を妨げる可能性があるため注意が必要です。
たんぱく質自体は筋肉をつくる栄養として重要なものであり、パーキンソン病の人も積極的に摂るべきです。
タイミングや量を調整すれば問題ないため、医師に相談しながら食事を組み立ててみてください。
パーキンソン病診療ガイドラインによれば、朝・昼に摂取するたんぱく量を減らし、夕飯時に高たんぱくの食事を行う「蛋白再配分療法」は効果が高いという報告もありました。(文献2)
食べにくい固形食品
パーキンソン病は末期になると咽頭周りの筋肉が動きづらくなり、嚥下障害を併発することがあります。
そのため、飲みこみづらい食べ物や、かみ砕くのに時間がかかる固い食品は避けるべきです。
食事の際はゆっくりよく噛むことを心がけましょう。
パーキンソン病の人がとったほうがいい食べ物
パーキンソン病は身体への影響が大きい病気です。
必要な栄養をしっかり摂り丈夫な身体をつくることが、症状の緩和にもつながります。
この項目では必要な栄養と、その栄養が多く含まれる食べ物を紹介します。
食物繊維が豊富な食事
パーキンソン病の人は便秘になりやすいため、お通じをよくするために食物繊維が豊富な食事をとることが望ましいです。
食物繊維には水溶性食物繊維と不溶性食物繊維があります。どちらか一方に偏らず、バランス良く摂取しましょう。
食物繊維が多く含まれている食品
- 干ししいたけ(不溶性)
- きのこ類(不溶性)
- キャベツ(不溶性)
- りんご、キウイなどのフルーツ(水溶性)
- わかめ、ひじきなどの海藻類(水溶性)
など
水分
パーキンソン病の人は水分不足に陥りやすいと言われています。
パーキンソン病の症状である発汗異常や便秘、嚥下障害により水分をうまく飲み込めなくなってしまうことが原因です。
そのため、普通の人よりも多く水分をとることが推奨されています。
1日1500ml~2000mlの摂取が望ましいです。
たんぱく質
パーキンソン病を患うと、筋肉や関節が動きづらくなり、身体を思うように動かせなくなってしまいます。
末期になると寝たきりになってしまう人や、車いす生活を余儀なくされる人もいます。
要介護の生活を防ぐためには、筋肉量を落とさないことが重要です。
たんぱく質は筋肉をつくる非常に重要な栄養素です。
ただし、薬物治療をしている人は、たんぱく質を摂取するタイミングに注意してください。投薬直後に高たんぱくな食事をすると薬の効果を弱めてしまう可能性があります。
たんぱく質が多く含まれる食品
- 鶏肉、豚肉をはじめとする肉類
- 魚介類
- 大豆製品
- チーズなどの乳製品
など
ビタミンD・カルシウム
パーキンソン病患者は身体動作の困難さが原因で体重減少、骨粗しょう症のリスクも高まることがわかっています。
重症度が上がるほど骨密度は低下してしまうため、骨を作る上で欠かせないカルシウム、ビタミンDは積極的に摂りましょう。
カルシウムが多い食べ物
- 牛乳
- チーズ
- 小松菜
- しらす干し
- 豆腐
- 干しえび
など
ビタミンDが多い食べ物
- 鮭(焼き)
- サンマ(焼き)
- しらす干し
- 卵
- 干ししいたけ
など
しらす干しはカルシウム、ビタミンDどちらも一度に摂れます。
抗酸化物質
パーキンソン病の原因であるドパミン神経細胞の減少には、酸化ストレスが関連しているといわれています。(文献2)
抗酸化物質は酸化ストレスを抑制する効果があるため、ドパミン神経細胞の減少を防ぐ効果が期待できます。
抗酸化作用のある主な栄養はビタミンA、ビタミンC、ビタミンE、ポリフェノール、ミネラルなどです。
抗酸化物質を多く含む食べ物
- パプリカ、ブロッコリー、トマト、ほうれん草などの緑黄色野菜
- いちご、ブルーベリーなどのベリー類
- アーモンドなどのナッツ類
- 緑茶
- 赤ワイン
など
パーキンソン病に対する再生医療について
パーキンソン病の症状を緩和する治療法には、再生医療という選択肢があります。
再生医療とは、「幹細胞」という治癒力が高く、培養が可能な細胞を用いて損傷した患部を治療する方法です。
2025年、京都大学の研究チームがiPS細胞から作製したドパミン神経細胞を脳に移植する治験を実施しました。その結果、7名のうち6名の人がドパミンが脳内で生み出されており、筋肉のこわばりなどの症状も改善されたといいます。
再生医療を用いることで失われた神経細胞を補うことが期待されており、進行性で治療が難しいとされてきたパーキンソン病に対して、新たな希望をもたらしています。
パーキンソン病の症状にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
\無料相談受付中/
まとめ|パーキンソン病では食事内容と薬の相互作用に注意!医師に相談のもと食事管理をしよう
パーキンソン病の人にとってバナナが良くないと言われている理由は、バナナに含まれるビタミンB6が、薬を体内で分解してしまい効果を弱めてしまうためです。
しかし、近年では薬の研究も進み、分解を防ぐ成分も配合しています。ビタミンB6を投薬の直後に摂らない、大量摂取しないという注意をしていれば、特に大きな問題はありません。
ビタミンB6のほか、投薬直後の高たんぱくな食事も薬を分解する危険性があるため控えましょう。
一方、過剰な栄養制限はパーキンソン病を重症化させる原因にもなります。丈夫な身体づくりはパーキンソン病の症状緩和に有効です。
便秘に効果のある食物繊維、筋肉をつくるたんぱく質、骨を丈夫にするカルシウムやビタミンDのほか、たくさんの水分を摂ることを心がけましょう。
パーキンソン病の症状にお悩みの方は、再生医療による治療もご検討ください。
当院「リペアセルクリニック」では、お客様の症状・状況にあわせたご提案をしております。お気軽にご相談ください。
参考文献
(文献1)
佐藤陽子ほか.「レボドパの薬効に影響を与えるビタミンB6摂取量に関する系統的レビュー」『食品衛生学雑誌』58(6), pp.257-266, 2017年
https://www.jstage.jst.go.jp/article/shokueishi/58/6/58_268/_pdf(最終アクセス:2025年6月24日)
(文献2)
日本神経学会「パーキンソン病診療ガイドライン2018」p215
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_27.pdf(最終アクセス:2025年6月24日)