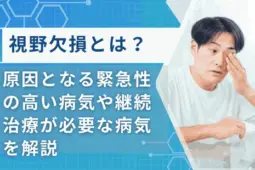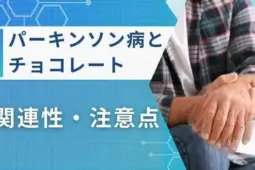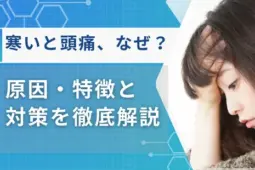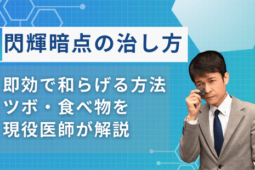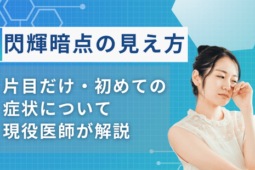- 頭部
- 頭部、その他疾患
パーキンソン病の初期・進行期の症状|診断・原因・治療法を解説

手足の震えや動作の遅れ、歩行のしづらさなどは「年齢のせいかも」と見過ごされがちな症状ですが、実はパーキンソン病が原因かもしれません。
進行性の神経疾患であるパーキンソン病は、早期の気づきと適切な対処が大切です。
予防や進行を遅らせるためにも、正しい知識を身につけておきましょう。
本記事では、パーキンソン病の原因や症状、診断・治療の選択肢まで、患者や家族が知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。
なお、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、パーキンソン病の治療で研究が進められている再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施していますので、ぜひご登録ください。
目次
パーキンソン病とは
パーキンソン病は、脳内のドパミンを産生する神経細胞が減少して発症する神経変性疾患です。
主に以下のような運動症状(体の動きに関わる症状)があります。
- 手足の震え
- 筋肉のこわばり
- 動作の遅れ
- 姿勢のバランス障害
中高年に多く見られる疾患ですが、40歳未満で発症する若年性パーキンソン病も存在するため、若い人でも油断できません。
なお、パーキンソン病は厚生労働省により「指定難病」に分類されています。
指定難病とは、原因不明で治療法が確立していない長期療養が必要な疾患のうち、医療費助成の対象とされるものを指します。
パーキンソン病の初期症状・進行期症状
パーキンソン病は進行性の神経疾患であり、症状は段階的に変化していきます。
初期には、以下のような軽微な兆候が見られるのが特徴です。
- 片側の手足に震えが現れる
- 歩行時の腕の振りが小さくなる
- 動作が遅くなる
- 表情が乏しくなる
- 字が小さくなる
上記の症状は加齢による変化と区別がつきにくく、見過ごされてしまう場合がある点に注意が必要です。
やがて進行すると、以下のような症状が目立ってきます。
- 姿勢の不安定性による転倒
- 筋肉のこわばり
- 歩行障害(すくみ足、小刻み歩行)
- 嚥下障害(えんげしょうがい)や言語障害
- 自律神経症状(便秘、起立性低血圧など)
- 認知機能の低下や幻覚
進行期には日常生活に大きな支障をきたすようになり、介助が必要となるケースも少なくありません。
早期発見と適切な治療が、症状の進行を遅らせる鍵となります。
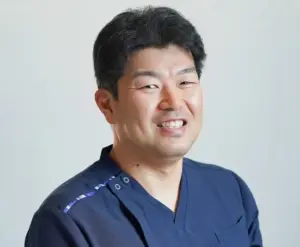
パーキンソン病の初期症状や進行度別の症状については、以下の記事でも解説しているので参考にしてみてください。
パーキンソン病の原因
パーキンソン病は、中脳にある「黒質」と呼ばれる部位の神経細胞が減少し、神経伝達物質であるドパミンの分泌が低下することで発症します。
ドパミンは、脳内で運動を円滑に調整する役割を担っており、不足すると手足の震えや動作の遅れなどの運動障害が現れるのが特徴です。
しかしながら、黒質の神経細胞がなぜ壊れてしまうのか、その根本的な原因はいまだ明らかにされていません。
遺伝的要因や加齢、環境因子(農薬や重金属など)が関与する可能性が示唆されていますが、決定的な因果関係は解明されていないのが現状です。
したがって、パーキンソン病の予防法や根治療法の確立には、さらなる研究が必要とされています。
パーキンソン病の診断
パーキンソン病の診断では、特徴的な運動症状の確認に加え、複数の補助的検査を組み合わせます。
ここでは、代表的な検査法を見ていきましょう。
血液検査
パーキンソン病は血液検査の結果だけで診断できないものの、甲状腺機能異常や肝機能障害など、類似の症状が現れる他疾患の除外診断に有効です。
また、特定の医薬品の副作用としてパーキンソン病に似た症状が現れる「薬物性パーキンソニズム」の原因となる、代謝異常や感染症の評価にも用いられています。
全身状態を把握し、安全な治療方針を立てるためにも欠かせない検査のひとつです。
MIBG心筋シンチグラフィー検査
MIBG(メタヨードベンジルグアニジン)心筋シンチグラフィーは、自律神経機能の低下を評価する画像検査です。
MIBGとは放射性医薬品で、心臓の交感神経系の機能を調べるために使われています。
パーキンソン病においては、心筋へのMIBG取り込みが低下する傾向がある点を利用する方法ですが、あくまで補助手段として有用な検査です。
また、脳の神経細胞にできる異常なたんぱく質の塊が神経を壊すことで発症する「レビー小体型認知症」との鑑別や、診断の裏づけとしても用いられています。
DATスキャン
DATスキャンは、脳内で運動を調整する役割を持つ「ドパミン神経」がどの程度機能しているか、画像として映し出す検査です。
「核医学検査」とも呼ばれ、微量の放射性薬剤を体内に注射し、薬剤が脳内のどこにどのくらい集まるかを特殊なカメラで調べます。
とくに調べるのは、運動制御に重要な部位「線条体(せんじょうたい)」にある「ドパミントランスポーター」というたんぱく質です。
ドパミントランスポーターの数が減っていると、ドパミン神経が減少していると判断されます。
パーキンソン病ではドパミン神経が少なくなっているため、DATスキャンでその変化を捉えることが可能です。
手の震えが見られる「本態性振戦(ほんたいせいしんせん)」など、他の病気との区別にも役立ち、より正確な診断につながります。
頭部CT・MRI検査
頭部CTやMRIは主に、脳出血や脳腫瘍、脳梗塞など他の神経疾患による症状との区別に用いられます。
パーキンソン病では、これらの検査で明確な異常が見られないケースが多いものの、進行した症例では黒質の萎縮などが確認される場合もあるため、鑑別診断としても不可欠な検査です。
脳血流スペクト検査
脳血流スペクト検査は、脳の各領域の血流状態を評価する検査方法です。
パーキンソン病では特定の部位に血流低下が見られる場合があり、進行度の把握や認知機能障害との関連性を確認するための補助的な検査として行われています。
また、レビー小体型認知症など、他の神経疾患との鑑別にも用いられています。
パーキンソン病の治療法
パーキンソン病の治療は、ドパミンの不足によって生じる症状を改善し、日常生活の質を維持することが目的です。
現在のところ根治療法は存在しておらず、主に薬物療法によって神経伝達のバランスを整えることが基本となります。
治療内容は、病状の進行や症状の現れ方に応じて段階的に見直されていきますが、薬でのコントロールが難しくなる進行期には、手術療法やデバイス補助療法も選択肢のひとつです。
個々の症状に合わせた適切な治療計画の立案が、長期的な病状管理には不可欠となります。
薬の種類
パーキンソン病の薬物療法では、ドパミンの補充・模倣・維持を目的とした複数の薬が使われます。
以下に主な薬剤をまとめました。
| 薬の種類 | 主な役割 | 特徴 |
|---|---|---|
| レボドパ製剤 | 脳内でドパミンに変換される | 最も効果的で広く使用される第一選択薬 |
| ドパミンアゴニスト | ドパミンのように働く | 効果はやや穏やかだが作用時間が長い |
| MAO-B阻害薬 | ドパミンの分解を抑える | 他の薬との併用で効果を補強する |
| COMT阻害薬 | レボドパの効果持続時間を延長する | 薬効の「切れ」を緩和 |
| 抗コリン薬 | アセチルコリンの作用を抑制する | 震えに効果があるが副作用に注意 |
| アマンタジン | ドパミン放出を促進する | 初期症状やジスキネジアに効果がある |
薬剤は単独または組み合わせて使用され、患者の年齢、症状の程度、副作用リスクなどを考慮して処方されます。
手術療法
パーキンソン病では、内服薬による治療で十分な効果が得られなくなった場合、手術療法やデバイス補助療法が検討されます。
代表的な手術法が、脳深部刺激療法です。
脳の視床下核などの特定部位に電極を埋め込み、電気刺激を加えて異常な神経活動を抑制し、手の震えや動作の遅れなどの症状を改善します。
また、胃に設けた小さな穴にチューブを通し、薬を直接小腸に送り続けて薬の効果を安定させるレボドパ持続経腸投与療法も治療法のひとつです。
体内の薬の濃度を一定に保ち、薬の効き目が突然切れる「オン・オフ現象」の改善を目指します。
以下の記事では、パーキンソン病に対する先進医療や研究について紹介しているので、参考にしてみてください。
パーキンソン病における「再生医療」という選択肢
パーキンソン病の研究分野では、iPS細胞(人工多能性幹細胞)を用いた再生医療の開発が進められています。
iPS細胞にはさまざまな種類の細胞に変化できる「分化能」があり、細胞からドパミン神経前駆細胞を作り出して移植する臨床研究が行われているのです。(文献1)
また、遺伝子を脳に注入することで、パーキンソン病の症状を改善する方法も試みられています。(文献2)
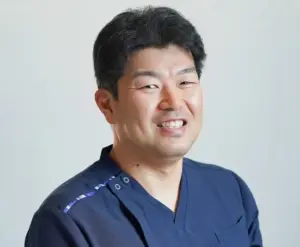
再生医療について詳しくは、以下をご覧ください。

手術をしない新しい治療「再生医療」を提供しております。
パーキンソン病の予防法
パーキンソン病は原因が完全には解明されておらず、確実な予防法は確立されていません。
ただし、以下のような生活習慣が発症のリスク低減につながる可能性があります。
- 定期的な運動やウォーキングなどの身体活動
- バランスの取れた食生活
- 十分な睡眠やストレスの軽減
上記のような生活習慣がパーキンソン病の発症を防げると断定されてはいませんが、健康維持の観点からも意識的に取り入れることが推奨されます。
健康的な生活を続けていくためにも、適度な運動やバランスの取れた食生活、十分な睡眠を心がけていきましょう。
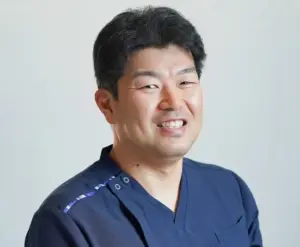
まとめ|パーキンソン病は適切な対処で進行を遅らせよう
パーキンソン病は進行性の神経疾患ですが、早期の診断と適切な治療、生活管理によって症状の進行を遅らせることは不可能ではありません。
現在では薬物療法が中心ではあるものの、運動や食生活、睡眠などの生活習慣や予防も含めて重要な要素です。
病気と上手に向き合い、医療機関との連携も欠かさずに生活の質を高めていきましょう。
なお、当院「リペアセルクリニック」では、パーキンソン病など神経の病気でも研究が進められている再生医療を行っております。
また、公式LINEでは再生医療に関する情報を提供するとともに、簡易オンライン診断をご利用いただけますので、お気軽にご登録ください。
\無料オンライン診断実施中!/
パーキンソン病に関するよくある質問
パーキンソン病が治った人はいますか?
現在の医療では、パーキンソン病を根本的に治す治療法は存在していません。
主な治療は症状の進行を抑えたり、生活の質を維持したりする対症療法です。
ドパミン神経細胞の減少を完全に回復させる方法は、現段階で確立されていない点に留意しておきましょう。
コーヒーはパーキンソン病の進行に影響しますか?
一部の研究では、カフェインを含むコーヒーの摂取がパーキンソン病の発症リスクを下げる可能性があるとしています。
ただし、進行を遅らせる効果が医学的に証明されているわけではありません。
予防や治療の手段として推奨されているわけでもないため、健康に配慮した上で適切な量を摂取すると良いでしょう。
コーヒー摂取の一般的な健康への影響については、以下の記事でも詳しく解説しています。
パーキンソン病になりやすい性格は?
パーキンソン病の患者には、以下のような性格の傾向があるとされています。
- 几帳面で細かいことにこだわる
- 変化を好まず、新しいことに慣れにくい
ただし、これらの性格が直接的な原因になるとの確証があるわけではなく、あくまで統計的な傾向にすぎません。
パーキンソン病にかかった有名人はいますか?
国内外には、パーキンソン病を公表した著名人がいます。
海外では俳優のマイケル・J・フォックスやボクサーのモハメド・アリ、日本ではみのもんたさんのほか、故・岡本太郎氏や作家の三浦綾子氏などが挙げられます。
病気と向き合いながら活動を続けた方もいるので、パーキンソン病患者の励みになっているといえるでしょう。
パーキンソン病の寿命はどのくらいですか?
パーキンソン病は進行性の病気ですが、生命予後が悪いわけではありません。
統計的には、平均寿命は一般の人と比べて2〜3年程度短くなるとされています。
適切な治療やリハビリテーションにより、発症から10年以上にわたって自立した生活を送ることも可能です。(文献3)
パーキンソン病は何科を受診すれば良いですか?
パーキンソン病の診療は、神経内科または脳神経内科が担当します。
専門的な診断や治療が必要となるため、最初は地域の医療機関やかかりつけ医に相談し、必要に応じて専門医を紹介してもらいましょう。
(文献1)
Phase I/II trial of iPS-cell-derived dopaminergic cells for Parkinson’s disease|Nature
(文献2)
パーキンソン病の病態理解と治療の最前線|J-STAGE(日本内科学会雑誌)
(文献3)
6 パーキンソン病|厚生労働省