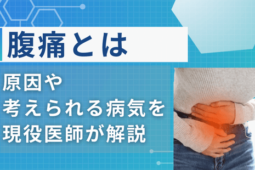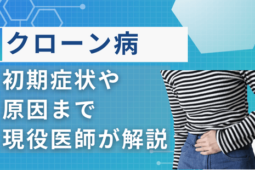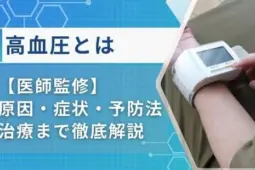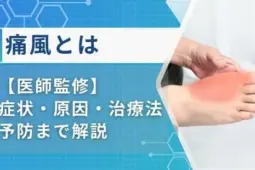- 内科疾患
- 内科疾患、その他
脂質異常症と高脂血症の違いを医師が解説!治療法・予防法

「健康診断で脂質の数値を指摘されたけれど、脂質異常症と高脂血症って何が違うの?」「放っておくとどうなるのだろう」と、健康診断の結果を見て不安を感じた方も多いのではないでしょうか。
脂質異常症と高脂血症は、よく混同されがちな言葉ですが、近年、医療の現場では「脂質異常症」が正式な病名として使われています。
脂質異常症は、自覚症状がないまま動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳卒中など命に関わる病気を引き起こす可能性があるため注意が必要です。
本記事では、脂質異常症と高脂血症の違いから原因や基準値、予防・治療法、そして再生医療まで解説します。
当院「リペアセルクリニック」では、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。脂質異常症に関連する「しびれ」などの症状についてお悩みの方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
脂質異常症と高脂血症の違い【結論:同じ病態の旧称と新称】
脂質異常症と高脂血症は基本的に同じ病態を指しますが、現在では「脂質異常症」が正式な診断名で、「高脂血症」は古い呼び方です。
かつては、血液中のコレステロールや中性脂肪が基準値より高い状態を総称して「高脂血症」と呼んでいました。
しかし、研究が進むにつれて、脂質の中でも「HDLコレステロール(善玉)」のように、基準値より「低い」状態が体に悪影響を及ぼす脂質があることがわかってきました。(文献1)
このような脂質の異常を包括的に捉えるべく、2007年に日本動脈硬化学会が診断名を変更し、脂質の量が基準値から外れた状態をすべて含める形で「脂質異常症」という名称が使われるようになったのです。
【比較表】脂質異常症と高脂血症の診断範囲の違い
現在の正式な診断名である「脂質異常症」は、以前使われていた「高脂血症」よりも、より広い異常を対象としています。
以下の表では、脂質異常症と高脂血症の違いを整理しました。
| 脂質の種類 | 脂質異常症 (現在の診断名) |
高脂血症(以前の考え方) |
|---|---|---|
| HDLコレステロール (善玉) |
低いことが問題 | (基準に含まず) |
| LDLコレステロール (悪玉) |
高いことが問題 | 高いことが問題 |
| トリグリセライド (中性脂肪) |
高いことが問題 | 高いことが問題 |
このように、悪玉コレステロールや中性脂肪の増加に加え、善玉コレステロールの減少も含む状態を脂質異常症と呼びます。
より広い範囲の異常を的確に捉えるべく、高脂血症から脂質異常症へ診断名が変更されたわけです。
なぜ「高脂血症」から「脂質異常症」に名称変更されたのか
診断名が「高脂血症」から「脂質異常症」へ変更された理由は、病態の理解が進み、名称が実態と合わなくなったのが理由です。
以前は、LDLコレステロールや中性脂肪が基準より高い状態のみを問題とする「高脂血症」という名称が一般的でした。しかしその後の研究により、HDLコレステロールが基準より低い状態も、動脈硬化性疾患の重大なリスク因子であることが判明したのです。
したがって、「高脂血症」という表現では、「脂質が高い状態」のみが問題とされているような誤解を招く恐れがありました。このような背景を受け、2007年に日本動脈硬化学会は診断名を「脂質異常症」へと変更したわけです。
現在では、脂質値が高い場合だけでなく、低い場合も含めた異常として明確に捉えられるようになり、より適切な疾患管理と予防の啓発が可能になっています。
脂質異常症(高脂血症)の種類|基準値の違い・主な原因
脂質異常症は、血液中の脂質値が基準範囲から外れることで診断され、血液検査によって主に以下3つのタイプに分類されます。
- 高LDLコレステロール血症
- 低HDLコレステロール血症
- 高トリグリセライド血症(中性脂肪)
ここでは、それぞれの特徴と日本動脈硬化学会が定めている診断基準値を解説します。
ご自身の健康診断の結果と見比べながら、どのタイプに当てはまる可能性があるのかを確認してみましょう。
高LDLコレステロール血症
高LDLコレステロール血症とは、血液中のLDLコレステロール(いわゆる悪玉コレステロール)が基準値を超えて多くなった状態を指します。
LDLコレステロールが増加すると、血管の内壁に入り込み「プラーク」と呼ばれる塊を形成し、動脈硬化を進行させるため注意しなければなりません。プラークが破れると、心筋梗塞や脳梗塞といった重大な疾患を引き起こす危険が高まるのです。
診断の基準は、空腹時の血液検査でLDLコレステロール値が140mg/dL以上とされています。(文献2)
主な原因は、肉の脂身やバターなど動物性脂肪の摂りすぎや慢性的な運動不足、さらには遺伝的な体質などが挙げられます。
低HDLコレステロール血症
低HDLコレステロール血症は、血管内の余分なコレステロールを回収し、肝臓に戻す役割をもつHDLコレステロール(善玉)が基準より少ない状態です。
HDLコレステロールが不足すると、血管内にコレステロールが蓄積しやすくなり、動脈硬化の進行を抑えにくくなります。
診断基準は、空腹時の採血でHDLコレステロール値が40mg/dL未満の場合です。(文献2)
喫煙習慣、運動不足、内臓脂肪型肥満といった生活習慣が主な要因とされており、生活習慣の改善が治療の基本になります。
高トリグリセライド血症(中性脂肪)
高トリグリセライド血症は、血液中の中性脂肪「トリグリセライド」が基準を上回る状態を指します。
中性脂肪は体のエネルギー源ですが、過剰に蓄積されると内臓脂肪として蓄えられ、動脈硬化のリスクを大きく高める要因となるため注意が必要です。
診断基準では、空腹時の血液検査においてトリグリセライド値が150mg/dL以上が異常とされます。(文献2)
白米やパンなど糖質の多い食事や過度の飲酒、過食、運動不足などが主な原因であり、バランスの取れた食事と生活習慣の見直しが重要です。
脂質異常症を放置するリスクとは?動脈硬化と関連疾患
脂質異常症を「症状がないから問題ない」と軽視することは、重大な疾患につながる危険な行為です。
脂質異常症は、進行しても自覚症状がほとんど現れないため、「サイレントキラー」とも呼ばれています。血管内にコレステロールが沈着し、プラークと呼ばれる塊を形成して血管を狭くする「動脈硬化」という血管の老化現象を静かに進行させているのです。
プラークが破れると血栓ができ、血流が遮断されて命に関わる疾患を引き起こす恐れがあります。
脂質異常症を放置した結果、動脈硬化を原因として発症する主な疾患には以下のようなものがあります。
| 影響を受ける場所 | 主な病名 |
|---|---|
| 心臓 | 狭心症、心筋梗塞 |
| 脳 | 脳梗塞、脳出血 |
| 足の血管 | 閉塞性動脈硬化症(痛み、しびれ) |
| 腎臓の血管 | 腎機能の低下 |
これらの疾患は、発症すると命に関わるだけでなく、日常生活にも大きな支障を及ぼします。
健康診断で脂質異常症が指摘された場合は、身体からの重要な警告として真摯に受け止め、早期に生活習慣の改善や対策を始めることが大切です。
脂質異常症(高脂血症)の治療法
脂質異常症の治療において最も重要な目的は、単に検査値を下げるのではなく、動脈硬化の進行を抑制し、将来的な心筋梗塞や脳卒中の予防につなげることです。
治療の基本は、病態の根本にある生活習慣の改善であり、以下の3つのアプローチが柱となります。(文献3)
- 食事療法
- 運動療法
- 薬物療法
まずは食事や運動の改善から開始し、それでも脂質値のコントロールが困難な場合や動脈硬化のリスクが高いと判断される場合には、薬物療法の併用が推奨されます。
では、以下で詳しく見ていきましょう。
食事療法|コレステロールを下げる脂質異常症(高脂血症)に良い食べ物
脂質異常症の管理では、日々の食事内容の見直しが治療の基本です。バランスの取れた食習慣で、血中脂質の改善と動脈硬化の予防につなげていきましょう。
以下では、控えるべき食品と積極的に摂取したい食品の例を挙げましたので、参考にしてみてください。
【控えるべき食品】
- 肉の脂身やバターなどに多い飽和脂肪酸
- マーガリンや加工食品に含まれるトランス脂肪酸
- 精製された糖質(ご飯、パン、菓子類)
- アルコール類
飽和脂肪酸とトランス脂肪酸はLDLコレステロール(悪玉)の増加を促進し、過剰な糖質とアルコールは中性脂肪の上昇に関係するため注意が必要です。
【積極的に摂取したい食品】
- 野菜、海藻、きのこ類に豊富な食物繊維
- 青魚やオリーブオイルに多く含まれる不飽和脂肪酸
水溶性食物繊維はコレステロールの吸収を抑制し、不飽和脂肪酸は血中脂質のバランスを整える作用があります。無理なく食習慣を改善するためにも、まずは1日1食からの見直しを意識してみましょう。
運動療法|脂質異常症の改善に効果的な運動
運動療法は、食事療法と並んで脂質異常症の改善に欠かせない要素です。有酸素運動には、HDLコレステロール(善玉)の増加とトリグリセライド(中性脂肪)を減少させる効果があります。
以下のように、手軽に始められる運動がおすすめです。
- ウォーキング
- 軽いジョギング
- 水泳や自転車などの有酸素運動
「ややきつい」と感じる強度で、1回30分以上、週に3日以上を目標にしましょう。
忙しい場合は、10分×3回でも同等の効果が期待できます。たとえば、「一駅分を歩く」「エレベーターではなく階段を使う」など、日常の中に自然な形で運動を取り入れることから始めましょう。(文献5)
なお、心臓病や膝関節に既往症がある方は、運動を開始する前に必ず医師の指導を受けてください。
薬物療法|脂質を下げる薬の種類と作用
食事療法や運動療法を継続しても脂質の数値が基準値まで改善しない、あるいは心筋梗塞などの動脈硬化性疾患のリスクが高いと医師が判断した場合には、薬物療法が検討されます。(文献4)
ただし、薬物療法は生活習慣の改善を補助する手段であり、心筋梗塞の既往がある方や糖尿病を合併している方を除き、治療の主軸ではありません。自己判断での服薬中止や調整は避け、必ず医師の指示に従いましょう。
脂質異常症の治療で使用される主な薬剤には、以下の種類があります。
| 薬の種類 | 作用の概要 |
|---|---|
| スタチン系薬剤 | 肝臓でのコレステロール合成を抑える、最も基本的な薬です。 |
| フィブラート系薬剤 | 肝臓での中性脂肪の合成を抑え、分解を促します。 |
| EPA・DHA製剤 | 青魚の油の成分で、中性脂肪の合成を穏やかに抑えます。 |
| 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬(エゼチミブ) | 小腸でのコレステロールの吸収を妨げます。 |
なお、いずれの薬剤にも副作用の可能性があり、筋肉の痛み、脱力感、肝機能の異常などが見られるケースがあります。薬を服用している間に体調の変化を感じた場合には、速やかに主治医に相談しましょう。
脂質異常症の薬については、以下の記事で詳しく解説しておりますので、気になる方は参考にしてみてください。
脂質異常症(高脂血症)の予防法|今日からできる生活習慣の改善
脂質異常症は、将来的な動脈硬化や心筋梗塞、脳卒中のリスクを高める疾患ですが、発症の多くは日々の生活習慣と密接に関連しています。
とくに、偏った食事や運動不足、喫煙、肥満といった要因は血中脂質の異常を引き起こしやすく、早期からの対策が必要です。
ここでは、今日から始められる4つの具体的な改善策を紹介します。
食事を管理する
脂質異常症の予防には、毎日の食事内容の見直しが欠かせません。
過剰なカロリーや飽和脂肪酸、トランス脂肪酸の摂取は、LDLコレステロールや中性脂肪を増加させ、動脈硬化のリスクを高めます。
また、糖質やアルコールの摂りすぎも中性脂肪の上昇につながるため、控えめにしましょう。
なかでも、以下の5点が重要です。
- カロリー摂取量を適正に保つ
- 飽和脂肪酸(肉の脂身、バターなど)を控える
- トランス脂肪酸(マーガリン、加工食品など)を避ける
- 甘いもの・炭水化物の過剰摂取を控える
- アルコール摂取を減らす
さらに、野菜や海藻、青魚などを積極的に取り入れると、コレステロール吸収の抑制や脂質バランスの改善が期待できます。
身体活動・運動に取り組む
運動不足は、HDLコレステロールの低下や中性脂肪の上昇につながり、脂質異常症の進行要因となるため要注意です。
有酸素運動には、脂質代謝を改善し、心血管疾患のリスクを下げる効果が認められています。ウォーキングや軽いジョギング、水泳などの有酸素運動を「ややきつい」と感じる強度を目安に行いましょう
さらに、運動の「質」と「量」をより明確に把握するための指標として、「メッツ(METs)」が役立ちます。メッツは、身体活動の強度を数値化した単位で、安静時のエネルギー消費量を「1メッツ」と定義し、それに対して何倍のエネルギーを消費するかを表します。
たとえば、普通の歩行は約3メッツ、軽いジョギングは約6メッツとされており、活動の強度を客観的に評価する際に有用です。
厚生労働省のガイドライン(2023年案)では、生活習慣病予防のために「週23メッツ・時以上」の身体活動を推奨しています。(文献5)これには、3メッツの活動を週に約8時間、または6メッツの活動を週に約4時間などが該当します。
無理なく減量する
過体重や肥満は、LDLコレステロールや中性脂肪の増加、HDLコレステロールの低下に直結するリスク因子です。
しかし、急激な減量や過度な食事制限は健康を損なう恐れがあるため、無理のないペースでの減量が推奨されます。
実際、無糖尿病の肥満者40人を対象にしたランダム化比較試験では、体重のわずか5%の減少で肝臓や脂肪組織、筋肉のインスリン感受性が大きく改善し、心血管疾患のリスク因子が良好な方向に変化したと報告されています。(文献8)
体重を少し減らすだけでも、脂質代謝に良い影響をもたらす可能性があるため、適切な食事制限と定期的な運動を組み合わせて無理なく体重を管理しましょう。(文献6)
禁煙する
喫煙は、HDLコレステロールを低下させる要因の一つであり、脂質異常症の悪化や動脈硬化の進行に関与します。たとえタバコの本数が少なくても、血管内皮機能に与えるダメージは大きく、予防の観点から禁煙は不可欠です。
各国の合計45本の研究を対象とした大規模なメタ解析では、禁煙によってHDLコレステロールが平均0.06 mmol/L(約2.3 mg/dL)上昇することが確認されました。(文献7)
禁煙は単に肺への負担を減らすだけでなく、脂質代謝の改善にも明確な効果が期待できます。禁煙は、脂質異常症の予防・治療において欠かせない取り組みです。
まとめ|脂質異常症(高脂血症)は早期発見と継続的な対策が重要
脂質異常症は、LDLコレステロール(悪玉)の上昇だけでなく、HDLコレステロール(善玉)の低下や中性脂肪の増加など、血中脂質の広範な異常を指す病態です。
放置すると、血管の老化が静かに進行し、動脈硬化を通じて心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる疾患を引き起こすリスクが高まります。
脂質異常症は「サイレントキラー」とも呼ばれ、自覚症状がほとんど現れないまま進行する点に注意が必要です。症状がなくても年に1回は健康診断を受け、自分の脂質値を把握しましょう。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、さまざまな治療に応用されている再生医療に関する情報の提供と簡易オンライン診断を行っています。ぜひご登録いただき、ご利用ください。
\無料オンライン診断実施中!/
脂質異常症(高脂血症)に関するよくある質問
略語の「dL」と「hl」とは何ですか?
「dL」はデシリットル(deciliter)の略です。
1dLは100mLに相当し、血液検査ではコレステロールや中性脂肪などの濃度を「mg/dL(ミリグラム・パー・デシリットル)」で表しています。
一方、「hl」は「hyperlipemia(高脂血症)」の略で、血中脂質の異常(現在の脂質異常症)を指す医療現場での略語です。日本の診断名としては、2007年以降「脂質異常症」という名称が公式に用いられています。
脂質異常症と高コレステロール血症の違いは?
脂質異常症は、LDLコレステロールが高い状態だけでなく、HDLコレステロールが低い状態や中性脂肪が高い状態も含めた総称です。
一方、高コレステロール血症はコレステロールやLDLコレステロールが高い状態を指す名称で、脂質異常症のうち「コレステロール値の高値」に焦点を当てています。
2007年の動脈硬化性疾患予防ガイドラインの改訂で「高脂血症」は「脂質異常症」に名称変更され、より幅広い脂質異常を包括する定義となりました。
脂質異常症(高脂血症)と糖尿病の関係は?
脂質異常症と糖尿病は、いずれも動脈硬化のリスク因子です。両者が合併するとその影響は相乗的になり、動脈硬化の進行がさらに加速します。
糖尿病患者はインスリン抵抗性の影響で中性脂肪が増え、HDLコレステロールが低下しやすくなるため、両疾患の管理を連携して行うことが重要です。
参考文献
(文献1)
脂質異常症(高脂血症)|日本医師会 健康の森
(文献2)
動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版|日本動脈硬化学会
(文献3)
脂質異常症|厚生労働省 e-ヘルスネット
(文献4)
脂質異常症治療のエッセンス|日本医師会編
(文献5)
健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023|厚生労働省
(文献6)
Effects of Moderate and Subsequent Progressive Weight Loss on Metabolic Function and Adipose Tissue Biology in Humans with Obesity|PubMed
(文献7)
The effect of quitting smoking on HDL-cholesterol – a review based on within-subject changes|Biomarker Research
(文献8)
In obese patients, 5 percent weight loss has significant health benefits|WashU Medicine(Washington University School of Medicine in St. Louis)