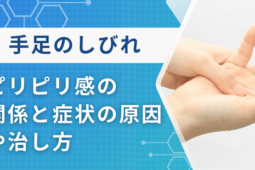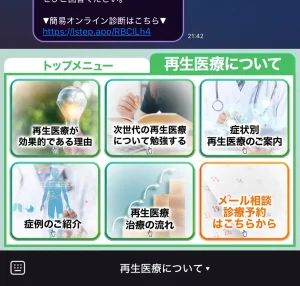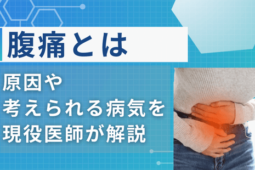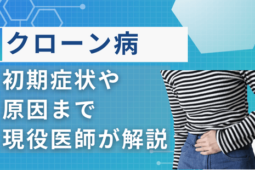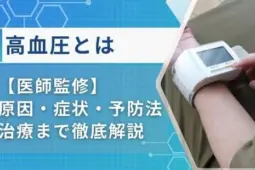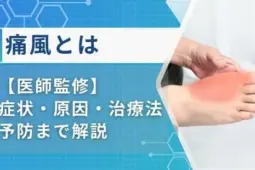- 内科疾患
- 内科疾患、その他
手足がしびれる症状は脂質異常症の危険サイン?動脈硬化を防ぐ治療
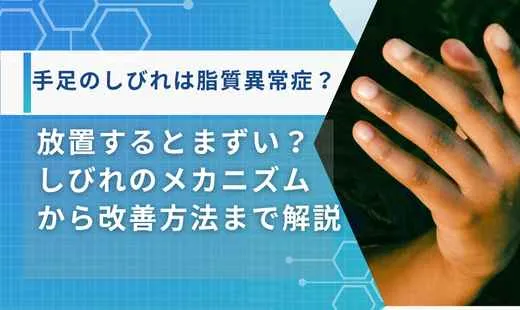
「健康診断で脂質異常症を指摘されたけれど、とくに症状もないし……」
「最近、手足がしびれることがある。もしかして何かの病気と関係があるのかな?」
このように、健康診断の結果や気になっている手足のしびれに関して、不安に思われている方もいらっしゃることでしょう。
実は、脂質異常症そのものが直接「しびれ」を引き起こすことは、あまりありません。
しかし、だからといって安心はできません。
脂質異常症を放置していると、動脈硬化や糖尿病といった深刻な病気につながり、それが原因でしびれが現れることがあるのです。
本記事では、脂質異常症がどのようにして手足のしびれに関わるのか、そのメカニズムを専門医が詳しく解説します。
あわせて、ご自身でできる生活習慣の改善方法についてもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
脂質異常症が関連する「しびれ」のお悩みを今すぐ解消したい・再生医療に興味がある方は、当院「リペアセルクリニック」の電話相談までお問い合わせください。
目次
脂質異常症でしびれる?基礎知識から症状まで専門医が解説
脂質異常症と診断されても、多くの場合、自覚症状がないため軽く考えてしまうかもしれません。
しかし、この病気は静かに進行し、重大な合併症を引き起こす可能性があります。
まずは脂質異常症とはどのような病気なのか、そしてなぜ「しびれ」と結びつけて考えられがちなのか、基本的な知識から確認していきましょう。
脂質異常症の定義と種類
脂質異常症とは、血液の中に含まれる脂質、具体的には「悪玉」と呼ばれるLDLコレステロールや中性脂肪(トリグリセライド)が基準値より多い状態や、「善玉」と呼ばれるHDLコレステロールが基準値より少ない状態を指します。
血液中の脂質は、細胞膜やホルモンの材料になるなど、体にとって不可欠なものですが、そのバランスが崩れることが問題なのです。
主な種類は以下の3つのタイプに分けられます。(文献1)
| 脂質異常症のタイプ | 説明 |
|---|---|
| 高LDLコレステロール血症 | 「悪玉」コレステロールが多い状態。増えすぎると血管の壁にたまり、動脈硬化の原因になります。 |
|
低HDLコレステロール血症 |
「善玉」コレステロールが少ない状態。善玉コレステロールは余分なコレステロールを回収する働きがあるため、少ないと動脈硬化が進みやすくなります。 |
| 高トリグリセライド血症 | 中性脂肪が多い状態。これも動脈硬化の要因となるほか、急性膵炎のリスクを高めることがあります。 |
これらの診断基準となる具体的な数値は、健康診断の結果などで確認できます。
ご自身の数値を把握し、どのタイプに当てはまるかを知ることが大切です。
なぜ「しびれ」が直接的な症状ではないのか?
「脂質異常症が原因で手足がしびれる」と考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、結論からいうと、脂質異常症そのものが神経に直接作用して「しびれ」を引き起こすことは、ほとんどありません。
では、なぜ「しびれ」と脂質異常症が結びつけて考えられるのでしょうか。
その背景には、脂質異常症が引き起こす動脈硬化が大きく関係しています。
動脈硬化によって血管が硬く、狭くなると、手足の末端まで十分な血液が届きにくくなります。
この血流の悪化が、結果として神経に栄養や酸素を十分に供給できなくなり、しびれが感じられることがあるのです。
つまり、「脂質異常症→動脈硬化→血流障害→しびれ」という流れで症状が現れることはありますが、「脂質異常症 → しびれ」という直接的な関係ではないことを理解することが重要です。
そのため、「しびれ」を感じる場合、その裏には単なる血行不良だけでなく、脂質異常症がもたらす血管の深刻な変化が隠れている可能性を考える必要があります。
脂質異常症の一般的な自覚症状
脂質異常症が「サイレントキラー(静かなる殺し屋)」と呼ばれる最大の理由は、病気がかなり進行するまで、ほとんど自覚できる症状が現れない点にあります。
痛みやかゆみ、倦怠感のようなわかりやすいサインがないため、健康診断で数値を指摘されても、つい放置してしまいがちです。
しかし、症状がないからといって、体の中で問題が起きていないわけではありません。
水面下で動脈硬化が静かに進行し、ある日突然、心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる病気を引き起こすリスクをはらんでいます。
まれに、脂質異常症が重症化した場合や、遺伝的な要因が強い家族性高コレステロール血症などでは、特徴的な身体的サインが現れることがあります。
黄色腫(おうしょくしゅ): コレステロールが皮膚の下にたまってできる、黄色いできものや膨らみです。目のまぶたや、肘、膝、お尻などに見られることがあります。
アキレス腱黄色腫(けんおうしょくしゅ): アキレス腱が太く、硬くなります。これもコレステロールが沈着することによって起こります。
これらの症状は、脂質異常症がかなり進行しているサインかもしれません。
しかし、このような症状が現れる前に、定期的な健康診断で血液の数値をチェックし、異常があれば早期に対策を始めることがなによりも重要です。
脂質異常症がしびれの症状を引き起こすメカニズム
脂質異常症自体がしびれの原因になることは稀ですが、放置すると引き起こされるさまざまな合併症が、間接的に「しびれ」の症状をもたらすことがあります。
ここでは、その代表的なメカニズムを3つの観点から詳しく解説します。
ご自身の「しびれ」が、どのような体の変化によって起きているのかを理解する手がかりにしてください。
動脈硬化による血流障害としびれの関係
脂質異常症の最も深刻な影響の一つが、動脈硬化を促進してしまうことです。
動脈硬化とは、血管が弾力性を失い、硬く、もろくなってしまう状態を指します。
血液中に増えすぎた悪玉コレステロール(LDL)は、血管の内壁に入り込んで酸化され、プラークと呼ばれるお粥のような塊を形成します。
このプラークが血管の内側を狭くし、血液の流れを妨げるのです。
とくに、手や足の先にあるような細い血管(末梢血管)では、この影響が顕著に現れます。
動脈硬化によって血流が悪くなると、末梢の神経細胞に必要な酸素や栄養が十分に行き渡らなくなります。
その結果、神経が正常に機能できなくなり、「ジンジンする」「ピリピリする」といった「しびれ」や、足先が冷たく感じるといった症状が現れます。
さらに動脈硬化が進行すると、閉塞性動脈硬化症(ASO)という病気に至ることもあります。
この病気では、歩くと足が痛くなり、休むと楽になる特徴的な症状(間歇性跛行)が現れ、重症化すると足の組織が壊死してしまう危険性もあります。
糖尿病性神経障害としびれの関係
脂質異常症と糖尿病は、生活習慣の乱れという共通の土台を持つため、非常に密接な関係にあり、併発しやすいことが知られています。(文献2)
脂質異常症を放置していると、インスリンの働きが悪くなるインスリン抵抗性という状態を引き起こし、糖尿病の発症リスクを高める可能性があります。
そして、糖尿病の三大合併症の一つとして知られるのが糖尿病性神経障害です。
これは、糖尿病による高血糖の状態が長く続くことで、全身の神経、とくに手足の末梢神経がダメージを受ける病気です。
高血糖は、以下の2つのメカニズムで神経障害を引き起こし、しびれの原因となります。
神経細胞への直接的なダメージ:血液中の過剰な糖が、神経細胞内で代謝される過程でソルビトールという物質に変わり、これが神経細胞内に蓄積して神経の働きを妨げます。
神経への血流障害:高血糖は、神経に栄養を送る細い血管の動脈硬化も促進します。これにより血流が悪化し、神経細胞が酸欠・栄養不足に陥り、機能が低下します。
この糖尿病性神経障害によるしびれは、多くの場合、足の裏や指先から始まり、徐々に体の中心に向かって広がっていく特徴があります。
\無料オンライン診断実施中!/
その他の合併症としびれの関係
動脈硬化や糖尿病のほかにも、脂質異常症が関与すると、しびれを引き起こす可能性のある病気が存在します。
例えば、甲状腺機能低下症もその一つです。
甲状腺ホルモンは全身の代謝をコントロールする重要なホルモンですが、このホルモンの分泌が低下すると、脂質代謝にも異常が生じ、脂質異常症を悪化させることがあります。
同時に、甲状腺機能低下症では、体のむくみ(粘液水腫)が神経を圧迫したり、神経そのものの働きが鈍くなることで、しびれや感覚の低下といった症状が現れることがあります。
また、肝臓は脂質代謝の中心的な役割を担う臓器です。
そのため、脂肪肝や肝硬変など、肝機能に障害が生じると脂質異常症を招きやすくなります。
肝機能の低下が進行すると、体内の毒素が十分に処理されなくなり、神経に悪影響を及ぼしてしびれを感じることもあります。
このように、脂質異常症は単独の問題ではなく、体のさまざまな機能と関連しあっています。
そのためしびれの症状がある場合は、こうした他の病気が隠れていないか多角的に原因を探ることが大切です。
\無料相談受付中/
脂質異常症改善のための生活習慣の見直しと実践方法
脂質異常症の治療の基本は生活習慣の改善です。
日々の少しの心がけが、血液中の脂質のバランスを整え、将来の大きな病気を防ぐことにつながります。
ここでは、すぐに始められる実践的な方法を3つの柱に分けてご紹介します。
忙しい毎日の中でも無理なく続けられるヒントを見つけて、健康な体を取り戻しましょう。
食生活の改善ポイント
脂質異常症を改善するための第一歩は、毎日の食事を見直すことです。
とくに意識したいのは、摂取する「油の種類」と「食物繊維」です。
まず、「控えるべき油」と「積極的に摂りたい油」を知りましょう。(文献3)
| 油の種類 | 解説 |
|---|---|
| 控えるべき油 |
飽和脂肪酸:肉の脂身、バター、ラード、生クリームなどに多く含まれます。悪玉コレステロール(LDL)を増やす原因。 トランス脂肪酸:マーガリン、ショートニングなどを使用するお菓子やパン、揚げ物などに含まれます。悪玉コレステロールを増やし、善玉コレステロール(HDL)を減らす原因。 |
| 積極的に摂りたい油 | 不飽和脂肪酸:青魚(サバ、イワシ、アジなど)に含まれるEPAやDHA、オリーブオイルやナッツ類に含まれるオレイン酸などが代表的です。これらは中性脂肪を減らしたり、悪玉コレステロールを減らしたりする働きが期待できます。 |
次に、コレステロールの吸収を穏やかにする「食物繊維」を十分に摂ることが大切です。
| 食物繊維 | 解説 |
|---|---|
| 水溶性食物繊維 | 海藻、きのこ、こんにゃく、大麦などに豊富です。腸内でコレステロールの吸収を妨げる働きがあります。 |
| 不溶性食物繊維 | 野菜、豆類、きのこ類に多く含まれます。便通を促し、腸内環境を整えます。 |
まずは、食事の最初に野菜や海藻のサラダ、きのこのスープなどを一品加えることから始めてみてはいかがでしょうか。
\無料オンライン診断実施中!/
効果的な運動習慣の取り入れ方
食事改善と並行した定期的な運動は、脂質異常症の改善に効果的です。中性脂肪を減らし、善玉コレステロール(HDL)を増やす直接的な効果が期待できます。
特に推奨されるのは、ウォーキングや水泳、サイクリングなどの有酸素運動です。
体脂肪をエネルギーとして燃焼し、脂質代謝を改善します。少し汗ばむ強度で1回30分以上が目標です。
まずは階段の利用や一駅分のウォーキングなど、日常で体を動かす機会を増やしましょう。
有酸素運動に筋力トレーニングを組み合わせると、さらに効果が高まります。筋肉量増加により基礎代謝が上がり、エネルギー消費しやすい体質になります。
無理のない範囲で週3回以上が理想です。(文献4)
禁煙・節酒の重要性
食事や運動と同じくらい、あるいはそれ以上に脂質異常症の改善と合併症予防に重要なのが、禁煙と節酒です。(文献5)
禁煙について
タバコの有害物質は血管内壁を傷つけ、動脈硬化を促進します。また善玉コレステロール(HDL)を減らし、悪玉コレステロール(LDL)を酸化させて血管壁への蓄積を促します。
脂質異常症患者の喫煙は動脈硬化リスクを著しく高めるため、自力での禁煙が困難な場合は禁煙外来の利用を検討しましょう。
節酒について
過度の飲酒は肝臓での中性脂肪合成を促進し、高トリグリセライド血症の直接の原因となります。
高カロリーなおつまみも脂質異常症を悪化させるため、食べすぎには注意が必要です。
厚生労働省が示す適度な飲酒量は1日あたり純アルコール約20gです。これはビール中瓶1本、日本酒1合、ワイングラス1杯弱に相当します。
飲まない日を設けて、肝臓を休ませるのも大切です。
脂質異常症の症状|しびれへの再生医療のアプローチ
脂質異常症が進行し、動脈硬化によって手足の血流が悪化して「しびれ」などの症状が現れた場合、生活習慣の改善や薬物療法と並行して、新たな治療の選択肢が検討されることがあります。
その一つが「再生医療」という治療法です。
再生医療は、患者様自身の幹細胞や血液を使う治療法で、入院や手術を伴わないのが特徴です。
当院「リペアセルクリニック」では、幹細胞を用いた再生医療を提供しております。
公式LINEでは、再生医療に関する情報発信や簡易オンライン診断を実施しているので、ぜひご登録ください。
脂質異常症の症状でしびれを感じたら医療機関へ
今回は、手足のしびれと脂質異常症の関係について解説しました。
脂質異常症そのものが直接「しびれ」を引き起こすことはまれである一方、放置すると動脈硬化や糖尿病といった合併症につながり、結果として「しびれ」が現れる可能性があります。
このように自覚症状がないまま進行することが多いため、健康診断での数値チェックと、症状が出る前からの生活習慣の改善が非常に重要です。
もし、あなたが健康診断で脂質異常症を指摘されており、かつ手足のしびれにお悩みであれば、それは体からの危険信号かもしれません。
自己判断で放置せず、なるべく早く専門の医療機関を受診して原因を調べてもらいましょう。しびれの症状は、時として重篤な病気のサインである可能性もあります。
なお、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療に関する情報発信や簡易オンライン診断を実施しています。お悩みの症状がある方は、ぜひ一度ご登録ください。
参考文献
(文献1)
動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版|日本動脈硬化学会
(文献2)
糖尿病診療ガイドライン2024|日本糖尿病学会
(文献3)
日本人の食事摂取基準2020年版|厚生労働省