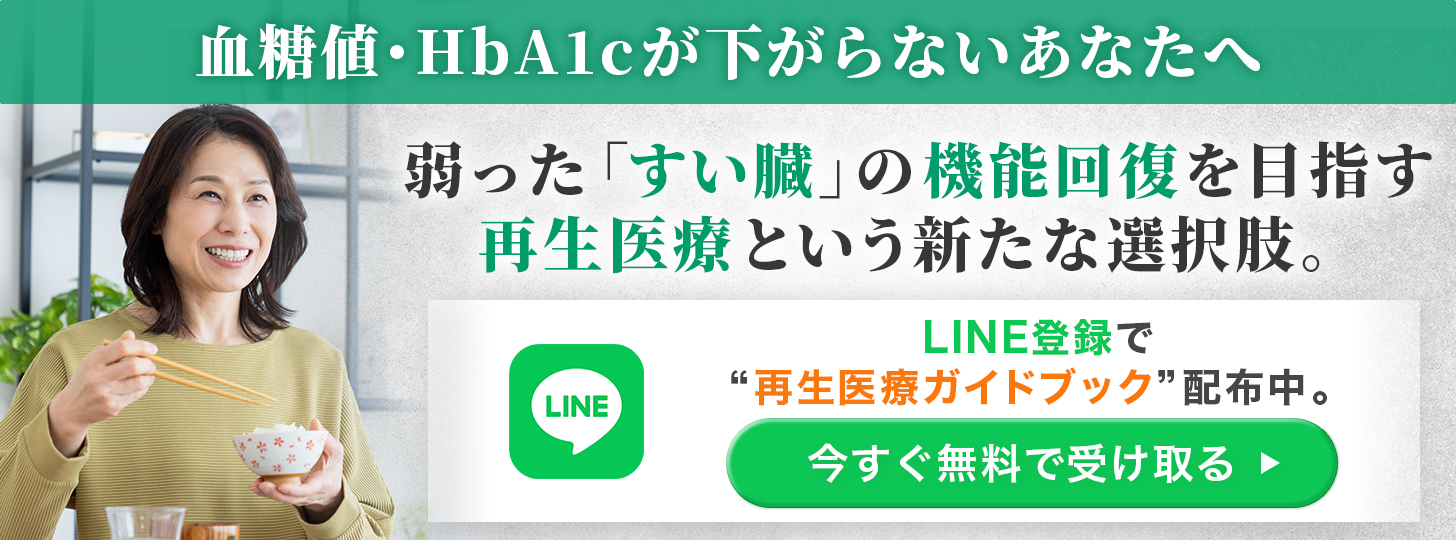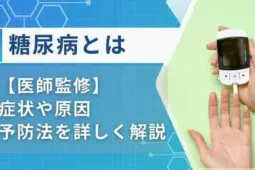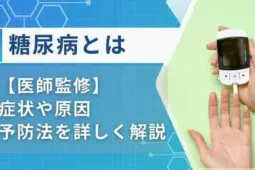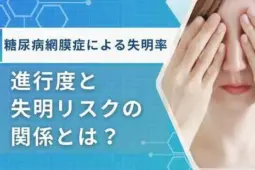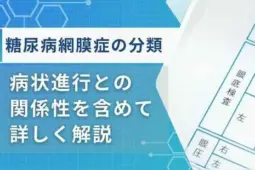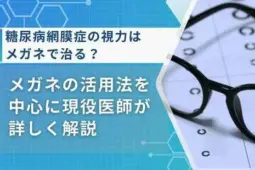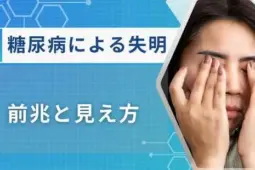- 糖尿病
- 内科疾患
妊娠糖尿病が胎児や母体に与える影響について解説|治療・予防法も紹介

妊娠中には、いろいろと気を付けなければならないことがあります。妊娠糖尿病もその1つです。
もしも、妊娠中に母親が糖尿病になったら、生まれてくる子ども(胎児)や母体にどういった影響があるのか不安になるかと思います。
この記事では、妊娠中に診断される妊娠糖尿病の胎児への影響と、その治療法・予防法について詳しく解説します。また、妊娠糖尿病が母体に与える影響や産後の注意点についても触れていきます。
目次
妊娠糖尿病の胎児への影響
妊娠糖尿病は胎児にさまざまな悪影響を及ぼす危険性が指摘されています。
また妊娠中だけでなく、出産後の子どもに合併症が出てしまう可能性があります。
本項目では妊娠、出産など各時期に起こる可能性のある危険性を紹介します。
さまざまな合併症を引き起こす可能性が高まる
妊娠中に高血糖状態が続くとお腹のなかの胎児も高血糖になり、以下のような合併症を引き起こすことがあります。
- 子宮内胎児死亡
- 新生児低血糖
- 巨大児
- 低出生体重児
- 多血症
- 特発性呼吸促拍症候群
- 頭蓋内出血
- 鎖骨骨折
- 頭血腫
- 上腕神経麻痺など
これらの合併症を予防するためには、妊娠中の血糖値を適切にコントロールすることが重要です。
妊娠中期以降には子宮内胎児死亡の可能性が増加
妊娠糖尿病を患った場合、妊娠32週ごろから突然子宮内胎児死亡を起こすことがあります。36週以降はその頻度が上昇するため、適宜検査を行い、問題がある場合入院処置が必要です。
難産になる可能性が上がる
妊娠糖尿病は難産のリスクも上がることが分かっています。 巨大児や奇形児といった合併症を引き起こした場合、出産時に頭が出た後肩がひっかかってしまい、うまく産道を通れない「肩甲難産」を起こすリスクが高くなります。
また、妊娠糖尿病による母体の高血圧、臓器障害などから、帝王切開分娩の発生率も上がってしまいます。
出産後の子どもへの影響
妊娠糖尿病中は血糖値が高い状態が続き、体内をめぐるブドウ糖の量が増えてしまいます。その結果胎児にもブドウ糖がめぐり、血糖値が上がります。 早い段階で治療に臨めば影響も少なく済みますが、妊娠糖尿病のまま放置してしまうと胎児も高血糖がつづいてしまいます。
血糖値が高いまま生まれた子どもは将来的にメタボリックシンドロームになりやすいという報告も上がっています。生活習慣病、動脈硬化などが発症しやすくなってしまう危険性があるため注意が必要です。
妊娠糖尿病とは?
妊娠糖尿病とは、妊娠中にはじめて発見または発症した糖代謝異常のことを指します。
「明らかに糖尿病である」と妊娠中に診断された場合は厳密には妊娠糖尿病とは呼ばず、「妊娠中の明らかな糖尿病」として区別されます。また、妊娠前に発症している糖尿病は「糖尿病合併妊娠」と呼ばれます。
妊娠糖尿病の原因
妊娠すると胎盤から分泌されるホルモンの影響でインスリン抵抗性が強くなってしまいます。インスリンは血糖値を正常にコントロールする働きを担っているため、インスリン抵抗性が上がり働きが弱くなると、血糖値が上がりやすくなります。
妊娠糖尿病を発症すると、母体だけでなくお腹のなかの胎児も高血糖になるため、さまざまな合併症を発症する危険性が高まってしまいます。
妊娠糖尿病の診断方法と診断基準
妊娠糖尿病は、スクリーニング検査と75gブドウ糖負荷試験の2段階の検査で判断します。
スクリーニング検査
妊娠糖尿病のスクリーニング検査はすべての妊婦を対象に妊娠初期と中期に行う検査で、妊娠糖尿病の可能性がある人を抽出する目的で行われます。
妊娠初期の随時血糖値の基準は検査施設によって95mg/dlまたは100mg/dlと異なります。また、妊娠中期の随時血糖値の基準は100mg/dl、50gブドウ糖負荷試験の基準は140mg/dlとなります。
妊娠糖尿病スクリーニング検査で陽性と判断された方は次で説明する75gブドウ糖負荷試験に進みます。
日本産科婦人科学会が推奨している妊娠糖尿病スクリーニング検査
妊娠初期:随時血糖値
妊娠中期:随時血糖値あるいは50gブドウ糖負荷試験
75gブドウ糖負荷試験
妊娠糖尿病スクリーニング検査で陽性が出た場合、75gブドウ糖負荷試験を行います。75gブドウ糖負荷試験では、以下の基準を1つでも満たした場合に妊娠糖尿病と診断されます。
試験基準
空腹時血糖値 ≧92mg/dl
1時間後の血糖値≧180mg/dl
2時間後の血糖値 ≧153mg/dl
妊娠糖尿病の治療
妊娠糖尿病と診断されたら、「血糖値コントロール」に取り組まねばなりません。ただし、妊娠中は運動療法を行うことが難しいため、主として「食事療法」と「薬物療法」を行うことになります。
食事療法で注意すべき点
妊娠糖尿病の治療は食事療法で血糖コントロールを行うことが基本になります。
妊娠中は食後高血糖を起こしやすい傾向がありますが、一方で長時間の空腹状態ではインスリン不足により体内でケトン体が作られ、糖尿病ケトアシドーシスを引き起こすリスクが高まります。特に妊娠中は体調の変化が激しいため、規則正しい食事が大切です。
薬物療法で注意すべき点
食事療法を行っても血糖値のコントロールがうまくいかない場合は薬物療法を行います。
妊娠中の薬物療法では経口血糖降下薬ではなく、インスリン治療を行うことになります。
通常のインスリン療法では血糖値コントロールがうまくいかないという場合はインスリンの基礎量や追加量を補充する方法を取ることがあります。これを強化インスリン療法(インスリンの頻回注射療法やインスリン持続皮下注入療法のこと)といいます。
妊娠糖尿病を早期発見・予防するには
妊娠糖尿病を予防できれば、母体や胎児への影響を減らすことにつながります。
そのためには、まず妊娠糖尿病にかかりやすい人の体質や、悪影響を与える生活習慣を理解しておくことが重要です。 以下で妊娠糖尿病の早期発見、予防に必要な項目を詳しく解説します。
妊娠糖尿病にかかりやすい人の特徴を理解する
以下の体質を持つ人は妊娠糖尿病にかかりやすいと言われています。
- 肥満
- 家族に糖尿病の人がいる
- 35歳以上の妊娠
- 尿糖の陽性が続く
- 羊水過多
- 原因不明の流産、早産、死産の経験がある人
- 妊娠高血圧症候群の人、もしくは既往歴がある人
もしいずれかの項目に該当しているようであれば注意が必要です。妊娠糖尿病を予防するためには、下の項目を参考に生活習慣の見直しを行う必要があります。
生活習慣の見直し
妊娠中はインスリンの分泌量が増えるため、空腹状態をなるべく作らないことが大切です。空腹を感じた場合は、野菜や豆類、鶏のささみなど良質のたんぱく質を摂るようにしましょう。
また、食事は食べる順番も大切です。野菜から食べ始め、汁物、メイン、炭水化物という順番で食べることで血糖値の急激な上昇を防ぐことができます。
妊娠糖尿病は通常の糖尿病と同様に、生活習慣だけでなく遺伝的要素も関係するといわれています。そのため上記で紹介したような方法を取り入れたにも関わらず妊娠糖尿病を発症したという場合も、あまりストレスに感じる必要はありません。
食事以外には適度な運動も大切です。血流を改善するウォーキングやヨガ、エアロビクスなどの有酸素運動が適切です。しかし、過度な運動はむしろ逆効果になる可能性もあるため、医師の許可を得て行いましょう。
定期健診の受診
妊娠糖尿病は早期発見が大事な病気です。胎児に影響が及ばないよう定期的に妊婦検診を行いましょう。
定期健診を行うことは、正しい生活習慣の維持にも有効です。
出産後、妊娠糖尿病の影響
出産後は急速にインスリン必要量が減少します。そのため、薬物療法を行っている人はインスリンの量を血糖値に合わせて調整する必要があります。 また、妊娠糖尿病患者の方は、正常な妊婦と比べて将来糖尿病を発症する頻度は41~62%だといわれています。(文献1)
産後6~12週間後にブドウ糖負荷試験を受け、妊娠糖尿病が治っているか確認し、その後も定期的に検査を受けることが重要になります。 産後に正常値に戻った人でも、最低でも3年間は産後のフォローアップが必要です。
授乳中の食事は妊娠前の摂取エネルギーから約450kcal程度増やすことを目安にしましょう。これは授乳のための付加エネルギーですので、授乳が終われば元の摂取エネルギーに戻す必要があります。
また、妊娠糖尿病を発症した人がそのままメタボリックシンドロームを起こす例もあります。上記で紹介した治療や予防を行いながら、産後も注意していく必要があります。
まとめ|妊娠糖尿病が胎児や母体に与える影響について解説|治療・予防法も紹介
妊娠前や妊娠中に糖尿病と診断されたときの対処法と母体や胎児への影響について説明しました。
妊娠糖尿病は、妊娠中に発症する糖代謝異常であり、母体や胎児にさまざまな影響を及ぼします。発症すると母体だけでなく、胎児にも影響をおよぼします。また、妊娠中は運動療法が困難なうえ、使用できる薬が限定されるため、治療は慎重に行う必要があります。
妊娠糖尿病は、妊娠中だけでなく出産時、出産後にもさまざまなリスクを引き起こす可能性が高い病気です。
予防のためにも妊娠中の食事や体調管理は特に気を使い、正しい生活習慣を心がけましょう。また、定期的な検査や医師との相談が大切です。
妊娠糖尿病と診断されたら、まずは食事療法や薬物療法を行いましょう。特に妊娠中は運動療法が難しいため、食事やインスリン治療が主な方法となります。
また、糖尿病患者が妊娠を望む場合は血糖コントロールに努め、医師と相談しながら計画的に妊娠することも重要です。妊娠糖尿病にかかりやすい人の特徴についてもまとめていますので、妊娠前に確認することをおすすめします。
妊娠糖尿病患者は産後の糖尿病発症率が高いため、産後も定期的に検査を受けましょう。
当院「リペアセルクリニック」では糖尿病に対する治療として、再生医療を行っております。 幹細胞による再生医療は、血糖値や肝機能値の改善にアプローチします。
再生医療について詳しく知りたい方は、当院「リペアセルクリニック」へお気軽にご相談ください。

糖尿病のお悩みに対する新しい治療法があります。
参考文献
(文献1)
平松 祐司. 「妊娠糖尿病」 岡山医学会雑誌, 2011年, 123(3), pp. 243-245.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/joma/119/1/119_1_79/_pdf
(最終アクセス:2025年3月25日)