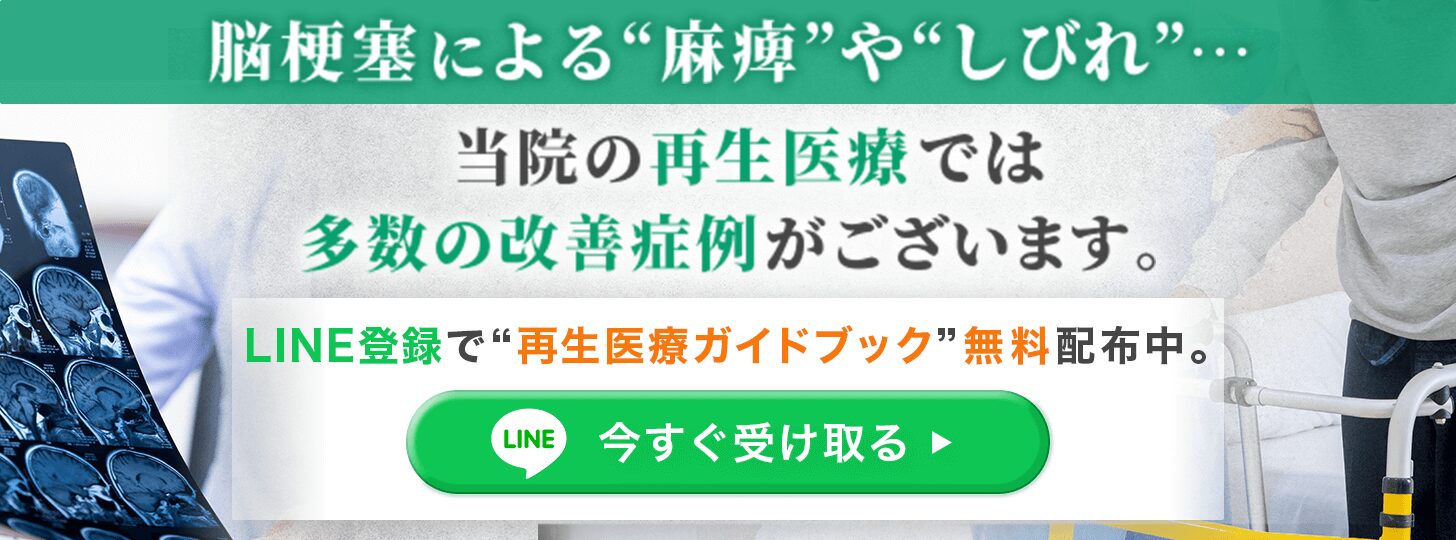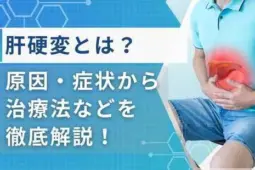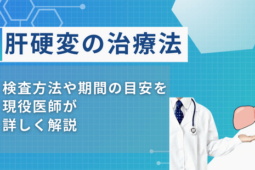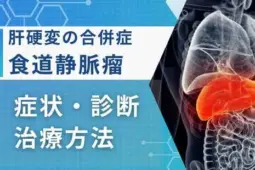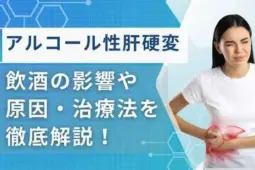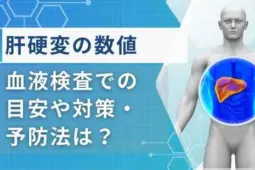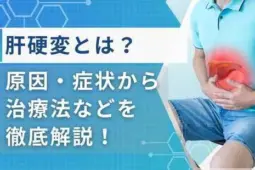- 脳梗塞
- 肝疾患
- 内科疾患
肝硬変の食事で気をつけることは?食べてはいけないものやおすすめ献立を医師が解説

肝硬変と診断を受けてから、どのような食事をとったら良いのかお悩みではないでしょうか。
医師から食事指導を受けたものの、具体的にどの食品をどの程度制限すれば良いのか、また、美味しい食事を楽しめるのか不安に感じている方もいるでしょう。
肝硬変の方は、健康な人に比べて食事の制限が多くなります。しかし、栄養バランスを意識してメニューを工夫すると、治療中でも美味しく食事を楽しみながら、必要な栄養を摂取できるでしょう。
本記事では、肝硬変の食事で気をつけるべきポイントとおすすめの献立を紹介します。
ぜひこの記事を参考に、無理なく続けられる食事の工夫を行い、健康を守るための食生活を取り入れていきましょう。
\肝硬変に対する再生医療/
肝硬変を放置すると肝機能が徐々に低下して腹水や黄疸、肝性脳症、消化管出血、肝がんなどの重い合併症を引き起こし、最終的には肝不全や肝移植が必要となる可能性があります。
そのため食事療法を含めた日常管理は重要ですが、食事や薬物療法だけでは肝機能の低下を十分に食い止められないケースもあるのが現実です。
このような場合、従来の治療に加えて、肝臓そのものの修復力にアプローチする治療法として、再生医療が注目されています。
再生医療とは患者さまご自身の脂肪由来幹細胞を用いて、損傷や炎症を受けた肝組織の修復・再生を促し、肝機能の改善や病状進行の抑制を目指す治療法です。
【こんな方は再生医療をご検討ください】
- 食事療法や生活習慣の改善を続けているが、肝機能の数値が改善しない
- 将来的な悪化や合併症が不安
- 肝硬変による入院や日常生活への影響をできるだけ避けたい
>>再生医療専門の「リペアセルクリニック」に無料相談する
「このまま食事療法だけで大丈夫なのか不安」「進行してしまった肝硬変でも、今からできることを知りたい」といったお悩みをお持ちの方は、当院(リペアセルクリニック)の無料カウンセリングをご利用ください。
また、おすすめの食材や再生医療・治療の考え方については、動画でも詳しく解説しています。
目次
肝硬変の人が気をつけるべき食事|食べてはいけないもの3選
肝硬変の人が控えるべき食品は以下の3つです。
これらの摂取を控えて、日々の食生活に気を配りましょう。肝硬変の方は、普段から肝臓への負担を減らす意識を持つことが大切です。
肝硬変の原因や治療法については、以下の記事が参考になります。
塩分が多い食事
腹水やむくみがある肝硬変の人は塩分摂取量の目安として、1日5〜7gに抑えることが推奨されます。(文献1)
腹水とは、お腹の中にタンパク質を含んだ液が大量に貯留した状態です。(文献2)
肝臓の機能が低下すると、血液中のアルブミンが減少し、水分が血管外へ漏れ出して腹水やむくみが生じます。塩分を摂りすぎると体内の水分がさらに増え、症状を悪化させる要因となります。そのため、肝硬変の人は塩分を控えることが重要です。
とくに以下のような食品は塩分が多いため、注意が必要です。(文献3)
- インスタント食品(カップめんやインスタントラーメンなど)
- 梅干し
- 漬物
塩分を適切にコントロールし、腹水やむくみの悪化予防に努めましょう。
肝硬変の腹水の予後や治療方法を知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
刺激物・硬い食品
肝硬変の患者は、食道静脈瘤のリスクがあるため、刺激物や硬い食品の摂取を控えることが重要です。(文献4)
食道静脈瘤とは、門脈圧亢進症(肝臓に流れ込む門脈の血圧が高くなる状態)によって生じる食道の血管のこぶであり、破裂すると大量出血を引き起こす可能性があります。(文献5)
食道は食べ物の通り道になっているため、その表面上にある膨らんだ血管に尖ったものや硬いものが当たると、破裂する可能性があるため注意が必要です。
たとえば、せんべいや小魚のおやつ、ナッツ、骨のある魚、フランスパンなどは硬いので適しません。また、香辛料の多いカレーやコーヒーも刺激が強いため控えた方が良いでしょう。
逆に好ましい食品は、茶碗蒸しや麺類(うどんやそうめんなど)、お米、プリン、ヨーグルトなどの消化しやすい柔らかい食べ物です。調理する際には柔らかく仕上げるように工夫してみてください。
高タンパクな食事
肝硬変の方は、タンパク質の過剰摂取に注意が必要です。
基本的に、肝硬変の方は健康な方よりもタンパク質を多めに摂取することが推奨されています。推奨されるタンパク質の1日摂取量は以下のとおりです。(文献8)(文献9)
|
対象 |
推奨されるタンパク質の1日摂取量目安 |
|---|---|
|
健康な方 |
男性:約0.95~1.0g/kg 女性:約0.93~0.99g/kg |
|
肝硬変の方(蛋白不耐症がない場合) |
1.0〜1.5g/kg |
タンパク質が不足すると栄養状態の悪化につながるため、過不足がない摂取量を心がける必要があります。
ただし、肝硬変の方は摂取のしすぎにも注意が必要です。
タンパク質は体に必要な栄養素ですが、消化・分解される過程で毒素のひとつ「アンモニア」を発生させます。健康な肝臓であれば無毒化されますが、肝機能が低下すると処理が追いつかず、体内にアンモニアが蓄積してしまいます。
血液中のアンモニア濃度が上昇し、脳にまで達すると神経症状を引き起こす「肝性脳症」の原因になります。
そのため、タンパク質の過剰摂取には注意が必要です。(文献6)とくに動物性タンパク質の摂りすぎには注意しましょう。
以下のような食品はタンパク質を多く含むため、摂取量を調整することをおすすめします。(文献7)
- 卵類
- 豚肉類
- 乳製品
肝硬変と同様、肝臓に中性脂肪が溜まる「脂肪肝」も食事の見直しが大切です。脂肪肝の食事の注意点を知りたい方は、以下のコラムも参考にしてください。
肝硬変の食事でおすすめの献立例
肝硬変では栄養バランスを整えつつ、肝臓に負担をかけない食事を摂ることが重要です。塩分やタンパク質を控えながらも、必要な栄養素を効率よく摂取できる献立を紹介します。
【朝食】
- パン
- 野菜スープ
- 果物・サラダ
- カフェオレ
野菜や果物を取り入れることでビタミンや食物繊維が摂取でき、腸内環境を整えられます。腸内環境を整えるとアンモニアの産生を抑制できるため肝硬変の方におすすめです。肝性脳症を合併している方は、カフェオレに入れる牛乳の量を少なめにしましょう。
【昼食】
- うどん
- 果物
- ヨーグルト
消化が良いうどんを主食にすることで消化管への刺激を抑え、食道静脈瘤のリスクを低減できます。そのため、うどんのような柔らかい食材がおすすめです。塩分を控えるため、うどんのつゆは薄味にして出汁を活用すると良いでしょう。
【夕食】
- ごはん
- 豆腐ハンバーグ
- 根菜汁
- 生野菜
主菜に植物性タンパク質を含む豆腐ハンバーグを取り入れると、食物繊維を多く摂取でき、アンモニアの蓄積を抑えられます。(文献10)主菜はなるべく、動物性タンパク質の代わりに植物性タンパク質を用いると良いでしょう。
合併症がある場合は、医師と相談しながら食事内容を調整しましょう。
肝硬変の食事療法の注意点
肝硬変の患者は、食事の摂り方にも注意が必要です。栄養素や食品に加え、以下の食事の取り方をするよう意識しましょう。
- 1日3回規則正しく食べる
- 高タンパク食や高カロリー食は避ける
- 満腹まで食べない(腹八分目を意識する)
- よく噛んで食べる
- 食べてからすぐにお風呂に入らない
- 深夜には高脂肪食品の摂取を避ける
これらの食事のポイントも意識すると、肝硬変の悪化防止につながります。今まで注意していなかった方は、今日から気をつけましょう。
肝硬変では食事の見直しに合わせて、専門医の治療をしっかり受けることが大切です。肝硬変の治療について詳しく知りたい方は、以下のコラムも参考にしてください。
まとめ|肝硬変は食事を工夫して悪化を防ごう
肝硬変では肝機能が低下している分、食事内容や摂取方法に注意しなければなりません。普段の食事内容の工夫が合併症を予防することにつながります。
合併症を改善・予防する上で食事療法は非常に重要です。医師や栄養士とも相談しながら、ご自身のライフスタイルに合った食事の工夫を行ってみてください。
一方で、「食事や生活習慣を改善しても数値が思うように良くならない」「肝硬変の進行や将来のことが不安」という方は、再生医療も選択肢の一つになります。
当院(リペアセルクリニック)では、肝臓疾患に対する治療の選択肢として、自己脂肪由来幹細胞を用いた再生医療を行っています。
【こんな方は再生医療をご検討ください】
- 食事療法や生活習慣の改善を続けているが、肝機能の数値が改善しない
- 将来的な悪化や合併症が不安
- 肝硬変による入院や日常生活への影響をできるだけ避けたい
>>再生医療専門の「リペアセルクリニック」に無料相談する
将来に向けて、選択肢を知っておきたいという方はぜひ、一度ご相談ください。
肝硬変の食事についてよくある質問
肝硬変の食事で生ものは食べられますか?
肝硬変の方は、生ものの摂取は控えましょう。
肝硬変は肝機能が低下している状態です。そのため、解毒能力が弱まり、食中毒のリスクが高まります。健康な人なら食品に含まれる細菌やウイルスは肝臓で解毒されますが、肝硬変の方はこの機能が低下し、感染症にかかりやすくなるのです。
とくに、生の魚介類には「ビブリオ・バルニフィカス」と呼ばれる細菌が含まれることがあり、重篤な感染症を引き起こす可能性があります。(文献11)
お寿司や刺身などの生魚は避けて、加熱調理した食品を摂取するようにしましょう。
肝硬変で食事がとれないときの対処法はありますか?
肝硬変の患者が食事をとれない場合は、栄養不足を防ぐために以下のような対策を取りましょう。
- 消化の良い食品を摂取する(お粥、スープ、豆腐、ヨーグルトなど)
- 少量ずつ複数回に分けて食べる(1日5~6回程度に分ける)
- 食欲が低下した場合は栄養補助食品を活用する
- 医師の処方に基づきBCAA(分岐鎖アミノ酸)製剤を取り入れる
食事から十分な栄養を摂れない場合、医師の指導のもとで栄養補助食品を活用するのもひとつの手です。エネルギーが補給できるドリンクタイプの栄養補助食品を取り入れると、食欲がなくても無理なく栄養を摂取できるでしょう。

肝臓疾患のお悩みに対する新しい治療法があります。
参考文献
(文献1)
日本消化器病学会・日本肝臓学会「肝硬変診療ガイドライン 2020(改訂第 3 版)」2020年発行
https://www.jsge.or.jp/committees/guideline/guideline/pdf/kankouhen2020_re.pdf
(最終アクセス:2025年3月26日)
(文献2)
MSDマニュアル「腹水」, MSDマニュアル家庭版,2023年1月
https://www.msdmanuals.com/ja-jp/home/04-%E8%82%9D%E8%87%93%E3%81%A8%E8%83%86%E5%9A%A2%E3%81%AE%E7%97%85%E6%B0%97/%E8%82%9D%E7%96%BE%E6%82%A3%E3%81%AE%E7%97%87%E7%8A%B6%E3%81%A8%E5%BE%B4%E5%80%99/%E8%85%B9%E6%B0%B4
(最終アクセス:2025年3月26日)
(文献3)
消費者庁「栄養成分表示を使って、あなたも食塩摂取量を減らせる」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/food_labeling_cms206_20191126_09.pdf
(最終アクセス:2025年3月26日)
(文献4)
MSDマニュアル「肝硬変」, MSDマニュアルプロフェッショナル版,2022年1月
https://www.msdmanuals.com/ja-jp/professional/02-%E8%82%9D%E8%83%86%E9%81%93%E7%96%BE%E6%82%A3/%E7%B7%9A%E7%B6%AD%E5%8C%96%E3%81%A8%E8%82%9D%E7%A1%AC%E5%A4%89/%E8%82%9D%E7%A1%AC%E5%A4%89L
(最終アクセス:2025年3月26日)
(文献5)
MSDマニュアル「静脈瘤」, MSDマニュアルプロフェッショナル版,2023年5月
https://www.msdmanuals.com/ja-jp/professional/01-%E6%B6%88%E5%8C%96%E7%AE%A1%E7%96%BE%E6%82%A3/%E6%B6%88%E5%8C%96%E7%AE%A1%E5%87%BA%E8%A1%80/%E9%9D%99%E8%84%88%E7%98%A4
(最終アクセス:2025年3月26日)
(文献6)
MSDマニュアル「肝性脳症」, MSDマニュアル家庭版,2023年1月
https://www.msdmanuals.com/ja-jp/home/04-%E8%82%9D%E8%87%93%E3%81%A8%E8%83%86%E5%9A%A2%E3%81%AE%E7%97%85%E6%B0%97/%E8%82%9D%E7%96%BE%E6%82%A3%E3%81%AE%E7%97%87%E7%8A%B6%E3%81%A8%E5%BE%B4%E5%80%99/%E8%82%9D%E6%80%A7%E8%84%B3%E7%97%87
(最終アクセス:2025年3月26日)
(文献7)
文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」から出典,2023年発行
https://fooddb.mext.go.jp/index.pl
(最終アクセス:2025年3月26日)
(文献8)
厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020 年版)」2019年12月発行,
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf
(最終アクセス:2025年3月26日)
(文献9)
日本消化器病学会・日本肝臓学会「追補内容のお知らせ 『肝硬変診療ガイドライン』(2020 年 11 月)」2022 年 3 月 18 日更新,https://www.jsh.or.jp/lib/files/medical/guidelines/jsh_guidlines/kankouhen2020_AR_v2.pdf?utm_source=chatgpt.com
(最終アクセス:2025年3月26日)
(文献10)
渡辺 明治.「9.肝硬変合併症とその対策3)肝性脳症」『日本内科学会雑誌』80巻(10号), p1625-p1630 1991年発行
https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika1913/80/10/80_10_1625/_pdf
(最終アクセス:2025年3月26日)
(文献11)
厚生労働省「ビブリオ・バルニフィカスに関するQ&A」食品の安全に関するQ&A, 2016年11月9日
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/qa/060531-1.html#top
(最終アクセス:2025年3月26日)