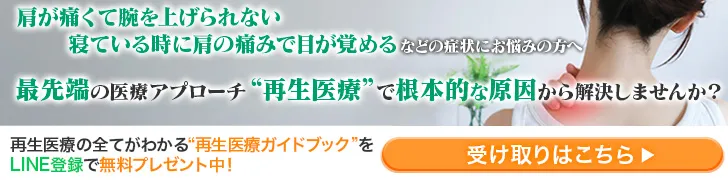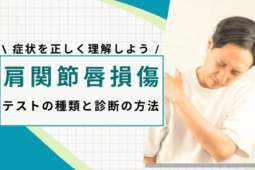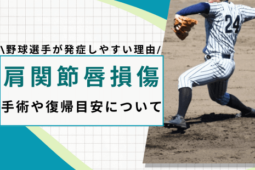- 肩関節、その他疾患
- 肩関節
ひどい肩こりはなぜ起こる?セルフケアから専門治療まで医師が解説

「マッサージを受けても、すぐに肩こりがぶり返す」「痛みがひどくて仕事に集中できない」とお悩みではありませんか。
ひどい肩こりは、単なる疲労ではなく、姿勢や生活習慣、ストレスなど複数の要因が重なって起こる場合が多いです。そのため、原因を正しく理解し、ご自身に合った対処法を選ぶことが改善への近道です。
本記事では、ひどい肩こりが起こる原因から、自宅でできるセルフケア、医療機関での治療選択肢まで詳しく解説します。つらい肩こりを根本から改善するために、ぜひ参考にしてください。
なお、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
肩こりでお悩みの方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
ひどい肩こりが起こる原因
ひどい肩こりを改善するためには、まず原因を知ることが重要です。原因がわかれば、効果的な対処法を選びやすくなります。
肩こりの主な原因は、以下の5つです。
それぞれ詳しく解説します。
長時間の同じ姿勢による筋緊張
デスクワークやスマートフォンの操作など、同じ姿勢を長時間続けると、首や肩の筋肉が緊張し続けます。筋肉が緊張した状態が続くと血流が悪化し、疲労物質や老廃物がたまりやすくなります。
その結果、筋肉が硬くなり、こりや痛みが生じるのです。
とくに、肩甲骨周囲の筋肉が動かない状態が続くと、肩全体の動きが制限され、肩こりが慢性化しやすくなります。1時間に1回は席を立ち、肩を回すなどの軽い動作を取り入れることが大切です。
猫背やストレートネックによる負担
猫背やストレートネック(首のカーブが失われた状態)は、首や肩の筋肉に大きな負担をかけ、肩こりの原因となります。
成人の頭の重さは約4〜6kgあります。正しい姿勢であれば、背骨全体で支えられますが、頭が前に出た姿勢では、首や肩の筋肉だけで頭を支えなければなりません。
結果的に筋肉の緊張が常態化し、慢性的な肩こりにつながります。日頃から正しい姿勢を意識することが、肩こり予防の基本です。
運動不足による血行不良
運動不足になると筋肉量が低下し、血液を送り出すポンプ機能が弱まります。血行が悪いと筋肉が固まって痛みが出やすくなるため、肩こりが慢性化しやすくなります。
ウォーキングや軽いストレッチなど、日常的な体を動かす習慣が、肩こり予防に効果的です。
冷えによる筋肉のこわばり
体が冷えると血管が収縮し、血流が低下します。血流が悪くなると筋肉に酸素や栄養が行き届かなくなり、筋肉がこわばりやすくなります。
とくに、冷房の効いた室内で長時間過ごす方や、冬場に肩や首を露出する服装をしている方は、肩こりが悪化しやすいです。
冷えを感じやすい方は、「カーディガンやストールで肩を温める」「入浴で体を温める」などの対策が有効です。
ストレスと自律神経の乱れ
精神的なストレスは、自律神経のバランスを乱し、筋肉の緊張を高めます。交感神経(体を活動・緊張状態にする神経)が優位な状態が続くと、肩や首の筋肉に力が入りやすくなり、肩こりが悪化しやすくなります。
ストレスが原因の肩こりは、マッサージだけでは改善しにくい場合があります。十分な睡眠やリラックスできる時間を確保し、ストレスを溜め込まない工夫を心がけましょう。
【簡易診断】ひどい肩こりの重症度をチェック
肩こりの症状は人によって異なります。以下の表で、ご自身の症状の重症度を確認してみましょう。
| 重症度 | 主な症状 | 該当する症状例 | 推奨される対処法 |
|---|---|---|---|
| 軽度 | ・肩の張り ・軽い疲労感 |
・デスクワーク後に肩が重い ・もみほぐすと楽になる |
セルフケア(ストレッチ・マッサージ)で改善可能 |
| 中度 | ・持続的なこり ・動かしにくさ |
・朝起きても肩が重い ・首を回すと痛みがある ・頭痛を伴う |
セルフケアと生活習慣改善を推奨。改善しなければ医療機関受診を検討 |
| 重度 | ・強い痛み ・日常生活への支障 |
・痛みで眠れない ・腕にしびれがある ・吐き気を伴う |
医療機関での受診を検討すべき |
軽度であればセルフケアで改善が期待できますが、中度以上の症状が続く場合は、早めに医療機関への受診を検討しましょう。
\無料オンライン診断実施中!/
ひどい肩こりを改善するためのセルフケア
軽度から中度の肩こりであれば、セルフケアで症状の改善が期待できます。ここでは、自宅で実践できる4つのセルフケア方法を紹介します。
それぞれ詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
マッサージ療法
セルフマッサージは、筋肉の緊張を和らげ、血流を改善する目的で行います。
肩こりに効果的なセルフマッサージの方法は、以下のとおりです。
- 右手で左肩の筋肉(僧帽筋)を軽くつかむ
- 痛気持ち良い程度の力で、ゆっくりともみほぐす
- 首の付け根から肩先に向かって、少しずつ位置をずらしながら行う
- 30秒〜1分ほど続けたら、反対側も同様に行う
なお、強く押しすぎると筋肉を傷める可能性があるため、「痛気持ち良い程度」の力加減を意識しましょう。
また、マッサージはあくまで一時的な対処です。根本的な改善を目指したいのであれば、姿勢の見直しや運動習慣の改善を心がけましょう。
運動療法(ストレッチ)
肩や肩甲骨まわりを動かすストレッチは、血流改善と筋肉の柔軟性向上に効果が期待できます。
具体的な肩甲骨まわりのストレッチ方法は、以下を参考にしてください。
- 両肩を前後に大きく回す
- 両手を肩に当てて、円を描くように動かす
- 肩をすくめた後、ストンと落とす
ストレッチは日々の継続が重要です。また、入浴後など「体が温まっているタイミング」で行うと効果的です。
ただし、痛みが強い場合は無理をせず、症状が落ち着いてから行ってください。
温熱療法
肩周りを温めると血管が拡張し、血流が改善されます。血流が良くなると、筋肉に酸素や栄養が届きやすくなり、こわばりが緩和されます。
温熱療法の方法は、以下のとおりです。
| 方法 | やり方 | ポイント |
|---|---|---|
| 入浴 | 38〜40℃程度のお湯に15〜20分つかる | 肩までしっかり浸かる |
| 蒸しタオル | 濡らしたタオルを電子レンジで1分ほど温め、肩に当てる | やけどに注意し、心地良い温かさで使用 |
| 温熱シート | 市販の温熱シートを肩に貼る | 長時間の使用は低温やけどに注意 |
ただし、肩に熱感や腫れがある場合は、炎症が起きている可能性があります。その場合は温めずに冷やし、医療機関を受診してください。
生活習慣の改善
肩こりの根本的な改善には、日常生活の見直しが欠かせません。以下の表を参考に、改善策を試してみてください。
| 改善項目 | 具体的な対策 |
|---|---|
| 姿勢 | ・デスクワーク時はモニターの高さを目線に合わせる ・椅子に深く座る |
| 作業環境 | 1時間に1回は席を立ち、軽いストレッチを行う |
| 睡眠 | 7〜8時間の睡眠を確保し、自分に合った高さの枕を使用する |
| 運動 | ウォーキングや軽い体操など、日常的に体を動かす習慣をつける |
なお、セルフケアを続けても改善しない場合は、別の原因が隠れている可能性があります。2週間以上症状が続く場合は、医療機関への受診を検討しましょう。
ひどい肩こりが改善しない場合の治療選択肢
セルフケアを続けても改善しない場合は、医療機関での治療が検討されます。ここでは、医療機関での代表的な治療法を2つ紹介します。
それぞれの治療法を詳しく解説します。
薬物療法
薬物療法は、痛みや筋肉の緊張を和らげる目的で行われます。医療機関では、症状に応じて以下のような薬が処方されます。
| 薬の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 非ステロイド性消炎薬 (NSAIDs) |
いわゆる「痛み止め」で、とくに急性期の痛みに効果がある。飲み薬、湿布、坐薬などがある |
| 筋弛緩薬 (きんしかんやく) |
筋肉のこわばりを抑える薬。NSAIDsと一緒に処方されることが多い |
| ビタミンB製剤 | 神経の修復を助ける目的で処方される |
| 血流改善薬 | 血流を改善し、筋肉への酸素や栄養の供給を促す |
(文献1)
なお、薬物療法は症状を和らげる対症療法であり、根本的な原因を解決するものではありません。医師の指示に従い、適切に使用することが大切です。
注射療法
肩こりの症状が強い場合や、セルフケアで改善しない場合は、神経ブロック注射が検討されるケースがあります。(文献1)
神経ブロック注射は、肩こりの原因と考えられる箇所の神経やその周辺に、麻酔薬やステロイドホルモンを注射する治療法です。
痛みやこりを一時的に和らげ、「痛み→筋肉の緊張→血行不良→さらなる痛み」という肩こりの悪循環を断ち切る効果が期待できます。
ただし、注射療法はすべての肩こりに適応されるわけではありません。医師の診察を受け、症状に応じて適切な治療法が選択されます。
ひどい肩こりは別の病気が関係していることもある
セルフケアや一般的な治療で肩こりが改善しない場合、筋肉以外の問題が原因となっている可能性があります。
「肩こりの背景に隠れていることがある疾患」には、以下のようなものがあります。
| 疾患名 | 特徴 |
|---|---|
| 頚椎椎間板ヘルニア (けいついついかんばん) |
首の椎間板が飛び出し、神経を圧迫する。腕のしびれや痛みを伴うことがある |
| 頚椎症性神経根症 (けいついしょうせいしんけいこんしょう) |
加齢により頚椎が変形し、神経を圧迫する。肩から腕にかけての痛みやしびれが特徴 |
| 四十肩・五十肩 (肩関節周囲炎) |
肩関節の炎症により、動かすと強い痛みが生じる。腕が上がらなくなることもある |
このような疾患が原因の場合、セルフケアや対症療法だけでは十分な改善が難しいことがあります。そのため、医療機関を受診し、精密な検査を受けることが大切です。
なお、当院「リペアセルクリニック」では、手術をしない選択肢として「再生医療」を提供しています。再生医療とは、患者様ご自身の細胞が持つ「組織を修復する働き」を利用した治療法です。
肩こりが長期間改善しない方や、上記のような疾患と診断された方は、再生医療も選択肢の一つとして検討してみてください。
また、以下の記事では「頚椎椎間板ヘルニア」の症例を紹介しています。ぜひ参考にしてください。
まとめ|ひどい肩こりは原因に合った治し方を選ぶことが重要
本記事では、ひどい肩こりの原因から、セルフケア、医療機関での治療選択肢まで解説しました。
ひどい肩こりの原因は、姿勢や運動不足、ストレスなど人によって異なります。まずはセルフケアで改善を試み、それでも症状が続く場合は医療機関への受診を検討しましょう。
ご自身の症状や原因に合った対処法を選ぶことが、肩こり改善への近道です。
なお、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療に関する情報の提供や簡易オンライン診断を行っております。
肩こりでお悩みの方は、ぜひご登録ください。
\無料オンライン診断実施中!/
ひどい肩こりに関するよくある質問
ひどい肩こりはマッサージだけで治る?
マッサージは筋肉の緊張を和らげ、一時的に症状を軽減する効果があります。ただ、姿勢や生活習慣が改善されなければ、肩こりは再発しやすいです。
マッサージはあくまで対症療法の一つです。根本的な改善には姿勢の見直しや運動習慣の改善、場合によっては医療機関での治療が必要になることもあります。
なかなか治らない肩こりにお悩みの方は、医療機関への受診を検討してみてください。
ひどい肩こりで頭痛や吐き気がある場合は病院に行くべき?
頭痛や吐き気を伴う肩こりは、筋肉の緊張だけでなく、神経の圧迫や血行不良が関係している可能性があります。
とくに、以下のような症状がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
- 頭痛が頻繁に起こる、または強くなっている
- 吐き気やめまいを伴う
- 腕や手にしびれがある
- 市販薬を飲んでも改善しない
放置すると症状が悪化する可能性があるため、自己判断せず専門医への相談をおすすめします。
ひどい肩こりは何科を受診すればいい?
肩こりの受診先は、症状によって異なります。受診先の判断に迷った際は、以下の表を参考にしてください。
| 症状 | 受診すべき診療科 |
|---|---|
| 肩や首のこり・痛み | 整形外科 |
| 頭痛やめまいを伴う | 整形外科または神経内科 |
| ストレスや不眠が原因と思われる | 心療内科 |
迷った場合は、まずは整形外科への受診をおすすめします。整形外科では、レントゲンやMRIなどの検査で骨や筋肉の状態を確認し、適切な治療法を提案してもらえます。
参考文献