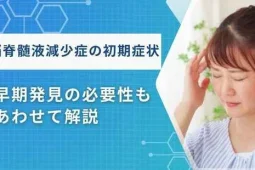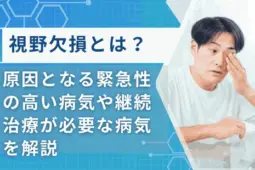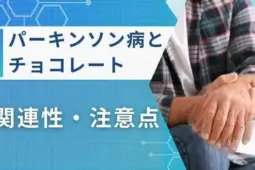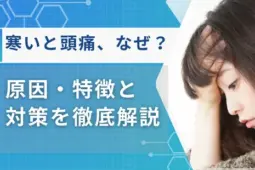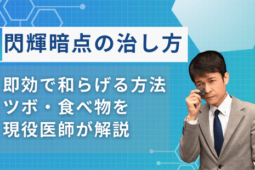- 頭部
- 頭部、その他疾患
脳脊髄液減少症のセルフチェック方法を紹介|治療方法もあわせて解説
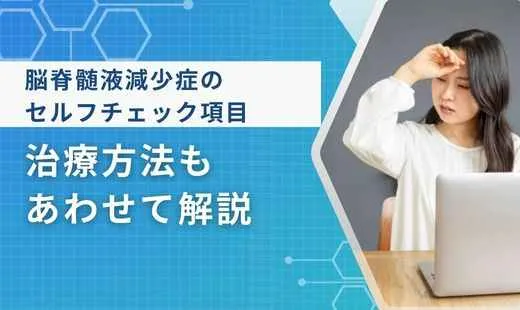
「めまいや頭痛が続いている」
「貧血が原因だと思っていたが、血液検査では異常なしだった」
「異常がないのに、なぜめまいや頭痛が続いているのだろう?」
このような不安や疑問をお持ちの方も多いでしょう。原因不明のめまいや頭痛などが続くときには、脳脊髄液減少症の可能性があります。
本記事では脳脊髄液減少症のセルフチェック項目や、病気の概要、治療法について解説します。
症状が続く不安を軽減するために、ぜひ最後までご覧ください。
目次
脳脊髄液減少症のセルフチェック方法
この章では、脳脊髄液減少症のセルフチェック項目を表にまとめました。
| セルフチェック項目 | 詳細 |
|---|---|
| 主な症状 |
|
| その他の症状 |
|
| 症状の現れ方 | 座ったり起き上がったりしてから3時間以内に症状が出現・悪化しやすい |
起立性頭痛とは、立ち上がったときや座っているときなどに強くなる頭痛のことです。
当てはまる項目が多く、過去に病院で「異常なし」と診断された方は、脳脊髄液減少症を発症している可能性があります。
脳脊髄液減少症の症状について詳しく知りたい方は、以下の記事をあわせてご覧ください。
そもそも脳脊髄液減少症とは
脳脊髄液減少症とは、脳脊髄液が常に、もしくは断続的に漏れ出してしまう疾患です。(文献1)脳脊髄液の役割は、脳と脊髄を守ることです。
脳脊髄液が漏れ出て量が減ると、頭痛や首の痛み、めまい、耳鳴り、見え方の異常、体のだるさなど、さまざまな症状が現れます。
脳脊髄液減少症は、以下の2種類に分けられます。
- 症候性:病気やけがが原因で発症する
- 特発性:発症の原因が不明である
発症しやすい年齢は40歳前後であり、女性に多い疾患です。
脳脊髄液減少症は現在も研究が進められており、診断基準や治療法は確立されていません。(文献2)
脳脊髄液減少症に症状が似ている疾患
脳脊髄液減少症に症状が似ている疾患としては、以下のようなものがあげられます。(文献2)
- 慢性頭痛
- 頸椎症
- 頚椎椎間板ヘルニア
- むち打ち症
- うつ病
脳脊髄液減少症は正確な診断基準が確立されていないため、別の疾患名で診断されてきたケースも少なくありません。もしくは、異常なしと診断された方も多い状況です。
原因がわからずに症状が続いたため、苦しんできた方も多いことが想定されます。
以下の記事では、脳脊髄液減少症と症状が似ている、むち打ち症について詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
脳脊髄液減少症の治療方法【セルフチェック該当者向け】
この章では、セルフチェックにおいて脳脊髄液減少症の可能性が高かった方に向けて、治療方法を詳しく解説します。
保存的治療
保存的治療では、水分補給と安静が必要です。1~2週間程度は、追加摂取1日1000~2000mlの水分を摂り、安静にして過ごしましょう。(文献3)脳脊髄液の減少を止める効果が期待できます。
水分補給に関しては、入院やもしくは通院により、医療機関で点滴を受けるケースもあります。
水分補給時に経口補水液が効果的という説もありますが、科学的な根拠は提示されていません。
ブラッドパッチ
ブラッドパッチとは、自分の血液を髄液が漏れ出ている部分に注入する治療法で、平成28年度から保険適用されました。
注入量は漏れ出ている部分によって異なります。腰椎(腰の背骨)で20〜40ml、胸椎(胸の背骨)で15~20ml、頚椎(首の背骨)で10~15mlです。
ブラッドパッチ治療後は1週間程度の安静が望ましく、同じ場所に再度治療する場合は、3か月以上の経過観察期間を設けることが望ましいとされています。(文献1)
硬膜外生理食塩水注入療法
腰椎からカテーテルを挿入して、生理食塩水を48~72時間持続的に注入する治療法で、注入のペースは1時間につき20ml程度です。(文献2)
生理食塩水のみ注入する方法に加えて、ブラッドパッチのときに、生理食塩水を35〜50ml程度注入する方法もあります。
セルフチェックで脳脊髄液減少症を疑う際は医療機関を受診しよう
セルフチェックで当てはまる症状が多かった方や、症状があるにもかかわらず、異常なし、もしくは原因不明と診断された方は脳脊髄液減少症の可能性があります。
脳脊髄液減少症は、研究段階の疾患であるため、診断・治療できる医療機関が限られていますが、出来る限り早い受診をおすすめします。
お住まいの都道府県庁ホームページ内に、脳脊髄液減少症に関する情報が記載されていることも多いため、受診を検討される方は、検索してみましょう。
リペアセルクリニックでは、メール相談やオンラインカウンセリングを実施しています。脳脊髄液減少症と思われる症状でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
\まずは当院にお問い合わせください/
脳脊髄液減少症に関するよくある質問
脳脊髄液減少症は何科を受診すると良いでしょうか?
脳脊髄液減少症に対応している主な診療科は、以下のとおりです。
- 脳神経外科
- 脳神経内科
- 神経内科
- 整形外科
- 麻酔科
ただし、「治療まで可能」、「相談・検査のみ」など医療機関によって対応が異なります。治療においても、ブラッドパッチ対応可能なところと、不可能なところにわかれます。
多くの都道府県ホームページでは、脳脊髄液減少症の医療機関に関する情報を公開しているので、検索してみましょう。
脳脊髄液減少症と起立性調節障害の違いは何ですか?
起立性調節障害とは、交感神経や副交感神経のバランスの乱れによりさまざまな症状が起こる疾患で、小学校高学年から高校生の方に多く見られます。(文献4)
めまいや頭痛、立ちくらみといった症状は脳脊髄液減少症と共通していますが、脳脊髄液減少症の原因は、文字どおり脳脊髄液の減少です。そのため両者は、原因や治療法に違いがあります。
脳脊髄液減少症は難病指定されていますか?
2025年(令和7年)4月1日の時点で、国の指定難病は348種類存在しますが、脳脊髄液減少症は含まれていません。(文献5)
脳脊髄液減少症に関しては、2007年度(平成19年度)から厚生労働科学研究費補助金、2015年度(平成27年度)からは日本医療研究開発機構(AMED)において、研究が実施されています。(文献6)
脳脊髄液減少症は、さらなる研究および難病指定が求められる疾患といえるでしょう。
参考文献
(文献1) 脳脊髄液減少症研究会ガイドライン作成委員会「脳脊髄液減少症ガイドライン2007」2007年
http://www.npo-aswp.org/data/2007-0330.pdf
(最終アクセス:2025年4月18日)
(文献2) 松本英之,宇川 義一.「脳脊髄液減少症」『日本内科学会雑誌』100(4), pp.1076-1083, 2011年
https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/100/4/100_1076/_pdf
(最終アクセス:2025年4月18日)
(文献3) 兵庫県神河町「脳脊髄液減少症をご存知ですか?」https://www.town.kamikawa.hyogo.jp/cmsfiles/contents/0000000/507/nouekizui.pdf
(最終アクセス:2025年4月18日)
(文献4) 一般社団法人 起立性調節障害改善協会「脳脊髄液減少症と起立性調節障害の違いを解説-どちらに該当するかセルフチェック」一般社団法人 起立性調節障害改善協会ホームページ, 2024年2月25日
https://odod.or.jp/kiritsusei-tohaod-6279/
(最終アクセス:2025年4月18日)
(文献5) 厚生労働省「指定難病の概要、診断基準等、臨床調査個人票(告示番号1~348)※令和7年4月1日より適用」厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53881.html
(最終アクセス:2025年4月18日)
(文献6) 厚生労働省「脳脊髄液減少症について」厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/nanbyo/100402-1.html
(最終アクセス:2025年4月18日)