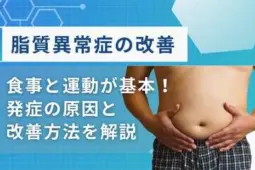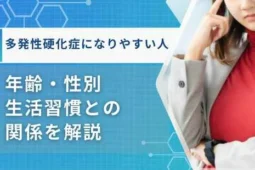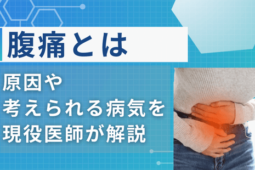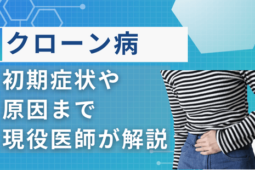- 内科疾患
- 内科疾患、その他
【医師監修】脂質異常症で食べてはいけないもの一覧|食べたほうがいい食材も紹介
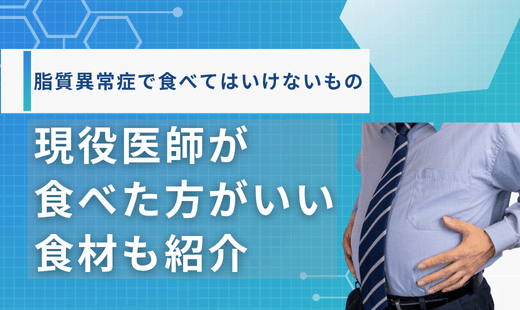
「コレステロールが高い」
「中性脂肪が多い」
健康診断で指摘されたものの、どの食品を避ければ良いかわからず、食生活の改善に悩む方も多いでしょう。脂質異常症は、放置すれば動脈硬化や心筋梗塞などの重大な病気につながるリスクがあります。
脂質異常症と診断されたら、まずは食生活の見直しが不可欠です。本記事では現役医師が、脂質異常症で食べてはいけないものを一覧で紹介します。
記事の最後には、脂質異常症の食事に関するよくある質問についてもまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
脂質異常症に関連する「しびれ」などの症状についてお悩みの方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
脂質異常症で食べてはいけないもの一覧
| 食品の種類 | 具体的な食品例 | 控える理由・ポイント |
|---|---|---|
| 肉類(脂身の多い肉・加工肉) | 牛・豚のバラ肉、鶏皮、ベーコン、ソーセージ、ハム | 飽和脂肪酸が多く、悪玉コレステロール(LDL)を増やし、動脈硬化のリスクを高める |
| 乳製品(全脂ヨーグルト・生クリーム・バター) | 全脂ヨーグルト、生クリーム、バター、チーズ | 飽和脂肪酸やコレステロールが多く、血中脂質を悪化させやすい |
| 油脂類(マーガリン・ショートニング・揚げ物) | マーガリン、ショートニング、フライドポテト、唐揚げ | トランス脂肪酸や飽和脂肪酸が多く、LDL増加・HDL減少の原因になる |
| 菓子類(スナック菓子・洋菓子) | スナック菓子、ケーキ、ドーナツ、クッキー、チョコレート | 脂質・糖分・トランス脂肪酸が多く、中性脂肪やコレステロールを増やす |
| 精製された炭水化物や糖分の多い食品 | 白米、白パン、砂糖菓子、清涼飲料水 | 血糖値や中性脂肪を上げやすく、脂質異常症の管理に不向き |
| インスタント食品や外食メニュー | ラーメン、ファストフード、カップ麺、ピザ | 脂質・塩分・糖分が多く、トランス脂肪酸やカロリー過多になりやすい |
脂質異常症と診断された場合、食事を見直すことが不可欠です。その中でもとくに、飽和脂肪酸・トランス脂肪酸・コレステロール・糖質を多く含む食品は、血中脂質を悪化させる原因になります。
具体的には、脂身の多い肉や加工肉、乳製品、トランス脂肪酸を含む油脂類、菓子類、精製された炭水化物、インスタント食品などの摂取を控える必要があります。
以下の記事でも、脂質異常症で食べてはいけないものについて解説しています。
【関連記事】
【一覧】脂肪肝を改善できる食事は?食べてはいけないものも【医師監修】
糖尿病予備軍が「食べてはいけないもの」7選|血糖値を安定させる「大根」がおすすめな理由
肉類(脂身の多い肉・加工肉)
| ポイント | 内容 | 健康への影響・推奨 |
|---|---|---|
| 飽和脂肪酸が多い | 脂身の多い牛肉・豚肉、ソーセージ、ベーコンなど | LDLコレステロール上昇→動脈硬化・心臓病・脳卒中リスク増。摂取は1日の総カロリーの6%以下推奨 |
| 加工肉のリスク | ベーコン、ハム、ソーセージなど | トランス脂肪酸・塩分も多く、悪玉コレステロール増・善玉減、血圧上昇・心血管リスク増 |
| 脂質量が重要 | 脂身の多い部位(赤身・白身問わず)、鶏皮付き肉など | 飽和脂肪酸が多いとLDL上昇。肉の種類より脂質量に注意 |
| 代替タンパク質 | 青魚、大豆製品、ナッツ類など | 植物性・魚由来のタンパク質や不飽和脂肪酸でLDL低下が期待できる |
飽和脂肪酸は豚バラ肉や牛バラ肉、ベーコン、ソーセージなどの脂肪分の多い肉類や加工肉に多く含まれ、肝臓のLDL受容体の働きを抑制し、血中LDLコレステロール値の上昇を引き起こします。その結果、動脈硬化や心筋梗塞、脳卒中などのリスクが高まるとされています。
米国心臓協会は、飽和脂肪酸の摂取を総エネルギー比6%以下に制限するよう推奨しています。(文献1)
また加工肉にはトランス脂肪酸と塩分が多く含まれており、トランス脂肪酸はLDLを増やしてHDLを減少させ、塩分は高血圧を招き心血管リスクを上昇させる要因です。肉については、赤身か白身かよりも脂身の量が重要であり、鶏皮も脂質が多いため注意が必要です。
そのため、魚(とくに青魚)や豆類、ナッツ類などの不飽和脂肪酸を含む食品に切り替えることで、LDL低下が期待できます。
乳製品(全脂ヨーグルト・生クリーム・バター)
| 理由・ポイント | 具体例 | 詳細 |
|---|---|---|
| 飽和脂肪酸が多い | 全脂ヨーグルト、生クリーム、バター | LDLコレステロール上昇リスク。低脂肪・無脂肪タイプの選択推奨 |
| 製品による影響の違い | バター、生クリーム、全脂ヨーグルト、チーズ | バター・生クリームは控えめ。ヨーグルト・チーズは無糖・低脂肪タイプを選択 |
| 飽和脂肪酸の過剰摂取回避 | 乳製品全般 | 食事全体で飽和脂肪酸を抑え、心血管リスク低減 |
| 食べ方の工夫 | バター・生クリーム・ヨーグルト・チーズ | たまの使用や低脂肪・ノンファット製品への置き換え |
全脂ヨーグルトやバターに多く含まれる飽和脂肪酸は、肝臓のLDL受容体の働きを抑制し、結果的にLDLコレステロール値を上昇させます。
米国心臓協会は、飽和脂肪酸摂取の総カロリーを6%以下に抑えることを推奨しており、生クリームやバターの過剰摂取による健康リスクを軽減すると報告されています。(文献1)
ただし、全脂ヨーグルトやチーズは種類によっては悪影響が少ないとされており、必ずしも避ける必要はありません。まずは低脂肪または無脂肪の製品を選ぶのがおすすめです。(文献2)
TLC(治療的生活習慣改善)プランでは、飽和脂肪酸と総コレステロールを制限することで動脈硬化や心血管疾患のリスク低下が示されており、とくに乳製品は飽和脂肪酸の主要な供給源であるため注意が必要です。
ヨーグルトや牛乳を取り入れる場合は、低脂肪または無脂肪タイプを選ぶことで脂質を抑えつつ、カルシウムやタンパク質をしっかり補えます。
油脂類(マーガリン・ショートニング・揚げ物)
| 理由・ポイント | 具体例 | 健康への影響・注意点 |
|---|---|---|
| トランス脂肪酸の含有 | マーガリン、ショートニング | LDL(悪玉)コレステロール上昇、HDL(善玉)コレステロール低下、動脈硬化・心血管疾患リスク増。摂取は総エネルギーの1%未満推奨 |
| 揚げ物の油の問題 | フライ、ドーナツなど | 油の繰り返し加熱でトランス脂肪酸が増加する。脂質摂取量も多くなりやすい |
| 飽和脂肪酸の多さ | 揚げ物、加工油脂 | 飽和脂肪酸がLDLコレステロールを上げ、心血管リスクを高める |
| 日本人の摂取状況 | パン、洋菓子、揚げ物 | 平均摂取量は少ないが、頻繁に食べる人は注意が必要 |
マーガリンやショートニングには、部分水素化された油に由来するトランス脂肪酸が含まれており、LDL(悪玉)コレステロールを上昇させるだけでなく、HDL(善玉)コレステロールを低下させるため、動脈硬化や心血管疾患リスクの要因となります。
一般社団法人日本動脈硬化学会も冠動脈疾患のリスク因子として、トランス脂肪酸の摂取を総エネルギーの1%未満に抑えることを推奨しています。(文献3)
揚げ物は、油を繰り返し加熱することでトランス脂肪酸が増え、衣が油を多く吸収するため、脂質の摂取量が過剰になりやすい食品です。また、加工油脂や揚げ油には飽和脂肪酸も含まれており、LDLの上昇を促します。
日本人の平均的なトランス脂肪酸摂取量は総エネルギーの約0.3%と、WHOの1%未満という基準を十分に下回っていますが、パン類・洋菓子・揚げ物を頻繁に摂取する方では、1%を超えるケースも報告されており、注意が必要とされています。(文献4)
脂質異常症管理においては、調理油の種類や使用頻度、調理方法に注意し、トランス脂肪酸と飽和脂肪酸の摂取を控えることが重要です。たとえば、蒸す・焼くなど油を控えた調理法への切り替えが推奨されます。
菓子類(スナック菓子・洋菓子)
スナック菓子や洋菓子には、トランス脂肪酸や飽和脂肪酸、精製された糖分が多く含まれています。これらは悪玉(LDL)コレステロールや中性脂肪を増やし、善玉(HDL)コレステロールを減らすため、脂質異常症や動脈硬化、心疾患のリスクを高めます。
また、菓子類は高カロリーで肥満の原因にもなりやすく、生活習慣病が悪化する要因の1つです。間食には果物や無糖ヨーグルト、ナッツなどを選び、成分表示でトランス脂肪酸を確認する習慣が数値改善と病気予防に役立ちます。
精製された炭水化物や糖分の多い食品(白米、白パン、砂糖菓子)
| 項目 | 内容 | 健康への影響・注意点 |
|---|---|---|
| 控える理由 | 精製炭水化物は中性脂肪を上げやすく、HDL(善玉)コレステロールを下げやすい | 肥満、動脈硬化、心血管疾患リスク増加 |
| 不足しやすい栄養素 | 食物繊維、ビタミンB群、ミネラル | 栄養バランスの乱れ、コレステロール排泄促進効果の減少 |
| 控えたい食品 | 白米、白パン、砂糖菓子、精白麺、菓子パン | 高GI・高糖質食品 |
| おすすめ食品 | 玄米、全粒粉パン、雑穀ご飯 | 食物繊維・ビタミン・ミネラルが豊富、コレステロール排泄促進 |
| 注意点 | 糖質を極端に減らさず、バランス良く摂取 | 炭水化物エネルギー比率は50~55%が目安 |
白米や白パン、砂糖を多く含む菓子や飲料などの精製された炭水化物は、血糖値を急上昇させやすく、中性脂肪の増加やHDL(善玉)コレステロールの低下を引き起こします。その結果、脂質異常症が悪化し、動脈硬化や心血管疾患のリスクが高まります。また、これらの食品は食物繊維やビタミン・ミネラルが不足しやすく、栄養バランスも崩れがちです。
日本循環器協会も、精製されていない穀類への切り替えを推奨しており、玄米などはコレステロール排泄を促進する効果も報告されています。ただし、糖質の極端な制限は、近年の研究では死亡リスクの上昇とも関連していると報告されています。そのため、日本人では炭水化物の摂取比率は総エネルギーの50~55%が望ましいです。(文献4)
主食を選ぶ際は、玄米や全粒粉パンなどの未精製穀類を取り入れ、食物繊維とともにバランスよく摂ることが大切です。
インスタント食品や外食メニュー(ラーメン・ファストフード)
インスタント食品やファストフードは、飽和脂肪酸・トランス脂肪酸・塩分・カロリーが多く含まれており、脂質異常症の悪化に直結します。インスタントラーメンや揚げ物は、LDL(悪玉)コレステロールや中性脂肪を増やし、HDL(善玉)を減らす原因になります。
また、日本国内の研究では、牛丼のようなファストフードを12週間継続摂取した結果、血圧の上昇や血中脂質の変動が確認されており、健康リスクの高さが指摘されています。(文献5)
どうしても外食が必要なときは、揚げ物や濃い味付けを避け、野菜の多い定食などを選び、脂質・塩分・カロリーを抑える意識を持つことが大切です。
脂質異常症で食べたほうがいい食材一覧
| 食材グループ | 具体例 | 期待できる効果・ポイント |
|---|---|---|
| 青魚や魚介類 | さば、いわし、さんま、さけ、まぐろ | EPA・DHAの摂取で中性脂肪低下、悪玉コレステロール抑制、動脈硬化予防 |
| 野菜・海藻・きのこ類 | ほうれん草、ブロッコリー、わかめ、ひじき、しいたけ、えのき | 食物繊維が豊富でコレステロール吸収抑制、血糖値安定、ビタミン・ミネラル補給 |
| 大豆製品 | 豆腐、納豆、豆乳、みそ、おから | 植物性タンパク質とイソフラボンで血中脂質改善、動脈硬化予防 |
| 良質な油脂 | オリーブオイル、えごま油、アマニ油 | 不飽和脂肪酸が多く、悪玉コレステロール低下、心血管リスク低減 |
| 玄米・全粒粉パンなど低GI食品 | 玄米、雑穀米、全粒粉パン、そば | 食物繊維・ビタミン・ミネラルが豊富、血糖値の急上昇を防ぎ中性脂肪抑制 |
脂質異常症の改善には、避ける食品だけでなく、積極的に摂りたい食材を意識するのも重要です。血中脂質のバランスを整える栄養素を含む食品を選ぶことで、無理なく健康的な食生活を続けやすくなります。
以下の記事では、食事以外にも脂質異常症を改善する方法を解説しています。
青魚や魚介類(EPA・DHAを含む)
| 項目 | 内容 | 期待できる効果・ポイント |
|---|---|---|
| EPA・DHAの作用 | 青魚に多いオメガ-3系脂肪酸 | 中性脂肪(TG)を減らし、脂質バランスを改善 |
| 抗炎症作用 | 血管の炎症抑制 | 動脈硬化予防、心筋梗塞や脳卒中リスク低減 |
| 血液サラサラ効果 | EPAが血小板凝集を抑制 | 血栓予防、心血管トラブル予防 |
| 摂取目安 | サバ、イワシ、アジ、サンマなどを週2〜3回 | 焼き魚・煮魚など揚げない調理法がおすすめ |
(文献5)
青魚に多く含まれるEPAやDHA(オメガ-3系脂肪酸)は、血液中の中性脂肪を減らし、脂質バランスを整える働きがあります。EPAには血管の炎症を抑える作用があり、動脈硬化や心筋梗塞、脳卒中の予防にも効果が期待されています。
また、血小板の凝集を抑えることで血液をサラサラに保ち、血栓の予防にもつながります。青魚(サバ、イワシ、アジ、サンマなど)は、週2〜3回を目安に取り入れると効果的です。DHAは生活習慣病だけでなく、目の健康にも良いとされています。(文献6)
調理法は煮魚や焼き魚など、揚げない方法がおすすめです。揚げない調理法で仕上げることで、余分な脂を避けつつEPA・DHAを効率よく摂取できます。
野菜・海藻・きのこ類(食物繊維が豊富)
| 項目 | 内容 | 期待できる効果・ポイント |
|---|---|---|
| コレステロール吸収抑制 | 水溶性食物繊維(海藻、果物、麦類) | LDLコレステロール低下、胆汁酸の排出促進 |
| 不要な脂質排出 | 食物繊維全般 | 余分な脂質の便排出、脂質異常症の改善 |
| 腸内環境改善 | 不溶性食物繊維(ごぼう、きのこ、豆類、根菜) | 便通促進、腸内環境の正常化 |
| 摂取バランス | 水溶性:不溶性=1:2が理想 | 野菜・きのこ・海藻の組み合わせ推奨 |
| 摂取目安 | 男性18~64歳22g以上、女性18~74歳18g以上/日 | 日本人の食事摂取基準2025年版準拠 |
食物繊維は、コレステロールや中性脂肪の吸収を抑え、余分な脂質の排出や便通の改善に役立つため、脂質異常症の改善に重要です。とくに水溶性食物繊維はLDL(悪玉)コレステロールの低下に効果的で、不溶性食物繊維は腸の動きを活発にし便通を促進します。
野菜・海藻・きのこ類を組み合わせることで、水溶性と不溶性を1:2のバランスで摂ることができ、どちらも効率よく補えます。日本人の食事摂取基準(2025年版)では、男性18~29歳・75歳以上は1日20g以上、30~64歳は22g以上、65~74歳は21g以上、女性18~74歳は18g以上、75歳以上は17g以上が目標量です。(文献6)
調理時は油の使いすぎに注意し、蒸し物や煮物を中心に取り入れることが、無理なく脂質コントロールにつながります。
大豆製品(豆腐・納豆・豆乳など)
大豆製品は植物性タンパク質を豊富に含み、飽和脂肪酸が少ないため、脂質異常症に適した食品とされています。豆腐・納豆・豆乳は調理が簡便で、日常の食事に取り入れやすい点も特徴です。大豆イソフラボンや大豆タンパク質には、LDL(悪玉)コレステロールを低下させる効果が臨床試験で確認されています。(文献7)
さらに、植物ステロールや食物繊維の作用により、腸管からのコレステロール吸収も抑制されます。納豆は発酵によって栄養価が高まり、健康効果がさらに期待できます。肉類の代替として大豆製品を取り入れることで、飽和脂肪酸の摂取を減らしつつ、良質なタンパク質とバランスの取れた栄養補給が可能となり、脂質異常症の改善や予防に有用です。
良質な油脂(オリーブオイル・えごま油)
オリーブオイルやえごま油などの良質な油脂は、脂質異常症の方にとって非常に有効な食材です。これらの油に多く含まれる不飽和脂肪酸は、血液中の脂質バランスを整える働きがあります。
オリーブオイルの主成分であるオレイン酸は、悪玉(LDL)コレステロールを下げ、善玉(HDL)コレステロールにはほとんど影響を与えません。えごま油に豊富なα-リノレン酸は、中性脂肪を減らし、血液をサラサラに保つ効果や血栓予防作用が期待できます。
動物性脂肪やトランス脂肪酸を多く含む油の代わりに、これらの良質な油に置き換えることで、動脈硬化や心疾患のリスクを下げられます。ただし、どんな油でも摂りすぎはカロリー過多の原因となるため、適量を守ることが大切です。炒め物やサラダに上手に取り入れ、脂質の「質」を意識した食生活を心がけましょう。
玄米・全粒粉パンなどの低GI食品
| ポイント | 内容 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 血糖値の急上昇抑制 | 低GI食品(玄米・全粒粉パン) | 中性脂肪の増加防止、脂質異常症の改善 |
| 食物繊維が豊富 | 白米・白パンより多い食物繊維 | LDLコレステロール低下、腸内環境の改善 |
| 満腹感の持続 | 噛む回数が増え消化がゆっくり | 過食・間食の予防、体重管理 |
| 糖尿病・肥満予防 | 低GI・高食物繊維の特性 | 生活習慣病全体のリスク低減 |
低GI食品は血糖値の急上昇を抑え、インスリンの過剰分泌を防ぐことで肝臓での中性脂肪の合成を抑制し、脂質異常症の改善に役立ちます。玄米や全粒粉パンに多く含まれる食物繊維は、胆汁酸と結合してLDLコレステロールを下げる効果があり、全粒穀物の摂取によるLDLコレステロール低下も期待できます。
粒子が粗いため噛む回数が増え、満腹感が持続しやすく、過食や間食の抑制にもつながり、低GIかつ高食物繊維の食事は肥満や糖尿病のリスクを下げ、脂質異常症だけでなく生活習慣病全体の予防にも有効です。主食に玄米や全粒粉パン、雑穀ごはんを取り入れることで、血液の脂質バランスと健康維持が期待できます。
今日から始められる食事の見直しポイント
| 見直しポイント | 詳細 |
|---|---|
| 食事の量やバランスを考慮する | 適正なエネルギー量の把握、主食・主菜・副菜の組み合わせ、さまざまな食材の選択、食物繊維の積極的摂取 |
| 調理法を見直す | 油の使用量の制限、揚げ物や脂質の多い料理の頻度を減らす、蒸し物・煮物・焼き物の活用、調理油の種類の工夫 |
| 外食での食事選びを工夫する | 主食・主菜・副菜が揃うメニューの選択、野菜や魚料理の優先、油や塩分の多い料理の回避、量の調整 |
脂質異常症の改善には、特定の食品を取り入れるだけでなく、日々の食事全体を見直すことが重要です。どのくらい食べるか、どのように調理するか、外食では何を選ぶかといった基本的なポイントを意識し、食事の量やバランス、調理法の工夫が実践的な改善につながります。
無理のない範囲で生活を見直すことが、脂質コントロールと健康維持の第一歩です。ただし、自己判断で行うのではなく、医師の指導のもとで進めることが大切です。
食事の量やバランスを考慮する
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 適切なエネルギー摂取で肥満と脂質異常を防ぐ | 摂取エネルギーの適正管理、体重増加防止、BMIの安定化、脂質異常症悪化の予防 |
| バランスの良い食事が血中脂質を改善する | 和食パターン(ご飯・魚・野菜・大豆)による血中脂質改善と動脈硬化予防 |
| バランス配分(主食・主菜・副菜)が習慣化を後押し | 野菜・果物と全粒穀物を皿の半分に、残りをタンパク質源にする食事習慣による血中脂質・体重管理支援 |
| 過食やムラ食を防ぎ、脂質バランスを保てる | 一定量の食事と均等なバランスによる間食・過食防止、血糖・中性脂肪の安定化 |
(文献8)
脂質異常症の予防・改善には、摂取エネルギーを抑えつつ、栄養バランスの良い食事を心がけることが重要です。主食・主菜・副菜をそろえた一汁三菜のような食事スタイルは、自然と食べすぎを防ぎ、満足感を得やすくなります。
米国農務省によると、野菜や果物、全粒穀物を皿の半分に、残りをタンパク質源とする食事習慣が、血中脂質の改善や体重管理に効果的とされています。たとえば、白米を玄米に替える、肉の代わりに魚や大豆製品を取り入れるといった工夫が、過剰な脂質やカロリーの摂取を防ぎ、栄養バランスを整える助けになります。
日々の食事で、量の調整と食材の組み合わせを意識することが、脂質異常症の改善への一歩となります。
調理法を見直す
| 見直しポイント | 内容 |
|---|---|
| 脂質の摂取量を抑えられる | 油を多く使う揚げ物や炒め物を控える |
| 余分な脂を減らせる | 焼く・茹でることで脂が自然に落ちる |
| トランス脂肪酸や酸化を防げる | 高温加熱を避け、健康リスクを軽減 |
| カロリー摂取の抑制・肥満予防につながる | 油を使わない分、全体のカロリーが減る |
| 取り入れやすい工夫 | 揚げ物を蒸す・茹でる・焼くに切替える |
脂質異常症の改善には、毎日の調理法を見直すのが効果的です。揚げ物や炒め物は脂質やカロリーの摂取量が増える原因となりますが、蒸す・茹でる・焼く調理法なら、油の使用を抑えることで、脂質やカロリーの摂取量も自然に減らせます。
また、余分な脂が落ちるためコレステロールの管理にも役立ちます。家庭でもすぐに取り入れられる実践的な方法です。
外食での食事選びを工夫する
外食は脂質や塩分が多くなりやすく、脂質異常症を悪化させる原因となります。揚げ物や脂っこい料理は避け、焼き魚や蒸し料理、野菜が多く含まれる定食を選ぶことで、栄養バランスが整いやすくなります。
主食・主菜・副菜・汁物がそろった定食は、食物繊維が豊富で、LDLコレステロールの抑制にも効果的です。野菜や汁物を先に食べる、栄養成分表示を参考にするなどの工夫も有効です。
ラーメンのスープを残す、丼物より定食を選ぶ、腹八分目を意識するなど、外食でも脂質を抑える工夫を重ねることで、脂質異常症の予防・改善につながります。
脂質異常症における食べていけないものを控えてバランスの良い食事を心がけよう
脂質異常症と診断された方は、まず「避けるべき食品」を知り、日々の食事を見直すことが大切です。飽和脂肪酸やトランス脂肪酸を含む食品を減らし、青魚や野菜、食物繊維が豊富な食品を積極的に取り入れることで、脂質バランスの正常化に貢献します。
また、調理法や食事の量にも気を配ることで、日常生活の中で無理なくコントロールできます。一人で改善が難しいと感じる場合は、医師や管理栄養士への相談も選択肢のひとつです。
脂質異常症と密接に関係する糖尿病にお悩みの方は、当院「リペアセルクリニック」へご相談ください。糖尿病はインスリンをつくる細胞の働きが弱くなることで起こります。再生医療はその細胞を補い、機能を回復させることで、根本的な治療につながると期待されています。
ご質問やご相談は、「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」で受け付けておりますので、お気軽にお申し付けください。
\無料オンライン診断実施中!/
脂質異常症の食事に関するよくある質問
脂質異常症で食べても良いお菓子はありますか?
脂質異常症の方でもお菓子を楽しむことはできますが、脂質やカロリーが少ないものを選び、量に注意しましょう。羊羹や寒天、高カカオチョコ、あたりめなどがおすすめです。
成分表示を確認し、個包装を活用すると食べすぎ防止にもなります。洋菓子やスナック類は控えめにしましょう。
食事制限はいつまで続ければいいですか?
脂質異常症では、まず3〜6カ月間、食事や運動など生活習慣の改善を行い、血液検査で効果を確認します。数値が改善しても再発しやすいため、食事管理は継続が必要です。薬を始めた場合も、医師の指示に従って続けましょう。
脂質異常症は食事以外に気を付けることはありますか?
脂質異常症の改善には、食事に加えて生活習慣全体の見直しが重要です。有酸素運動(ウォーキングやジョギングなど)を1日30分以上、週3回以上行うことで、HDL(善玉)コレステロールを増やし、中性脂肪を減らす効果があります。
さらに、禁煙や節酒、適正体重の維持、定期的な検査も大切です。必要に応じて医師の指導で薬を併用するケースもあります。
以下の記事では、脂質異常症の薬物療法について詳しく解説しています。
参考文献
Saturated Fat|American Heart Association
Is It Okay to Eat Butter If You Have High Cholesterol? A Cardiologist Settles the Debate|EatingWell
Cumulative Meta‐Analysis of the Soy Effect Over Time|AHA|ASA Journals
厚労省が「日本人の食事摂取基準(2020年版)」を公表 脂質異常症と高齢者のフレイルに対策 よりきめ細かな食事指導が必要に|保健指導リソースガイド