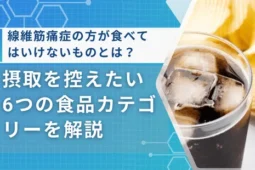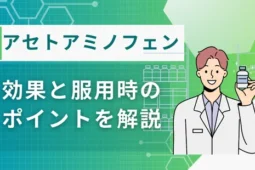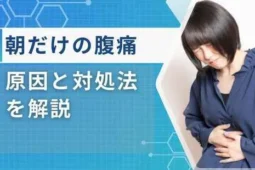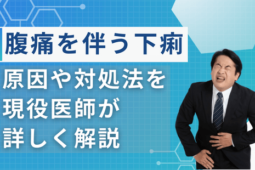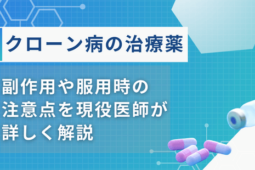- 内科疾患
- 内科疾患、その他
脂質異常症の改善は食事と運動が基本|発症の原因と改善方法・おすすめの食事を解説
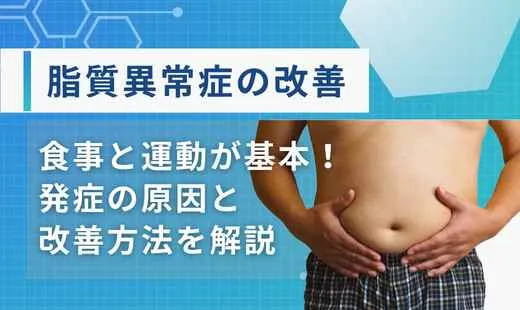
健康診断で脂質異常症と指摘され、「どう改善すればいいの?」と不安を感じていませんか。
放置すると動脈硬化や心筋梗塞につながることがあるため、早めの対策が大切です。脂質異常症の改善には、食事・運動・飲み物選びなど、日々の生活習慣を見直すことが効果的とされています。
本記事では、脂質異常症を改善するための食事や運動方法、日常に取り入れやすいお茶の選び方について解説します。
脂質異常症は放置すると動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞などにつながることがあり、これらの疾患には再生医療による治療の選択肢もあります。
気になる症状がある方は、ぜひ一度当院「リペアセルクリニック」の公式LINEにご登録ください。
目次
脂質異常症の改善には食事と運動が重要
脂質異常症は、血液中のLDLコレステロールや中性脂肪が高い、またはHDLコレステロールが低い状態を指します。
以前は「高脂血症」と呼ばれていましたが、脂質が高いだけでなく低い場合も健康に影響することから、現在は「脂質異常症」という名称が使われています。(文献1)健康診断では今も「高脂血症」という表現を見ることがあり、両者は同じ概念です。
この脂質異常症を改善するためには、日々の食事と運動を整えることが基本になります。脂質の摂りすぎや運動不足が続くと数値が上がりやすいため、食事の選び方を意識したり、軽い運動を習慣にしたりすることが大切です。
無理なく続けられる工夫を取り入れることで、改善につながりやすくなります。
【関連記事】
【医師監修】脂質異常症の診断基準|総コレステロールなど各数値の正常値と治療法を解説
脂質異常症と高脂血症の違いを医師が解説!
脂質異常症を改善する食事のポイント
脂質異常症の改善には、食事内容を整えることがとても重要です。
脂質の摂り方や食品の選び方によって、LDLコレステロールや中性脂肪の数値は大きく変わります。控えたい食品と積極的に摂りたい食品を意識することで、日常の食事でも無理なく改善につなげることができます。
とくに、脂質の質、食物繊維の量、調理方法を見直すことがポイントです。毎日の食事から少しずつ改善していきましょう。
控えたい食べ物(飽和脂肪酸・糖質・揚げ物)
脂質異常症の改善には、飽和脂肪酸や糖質の摂りすぎに注意する必要があります。
これらを多く含む食品は、LDLコレステロールや中性脂肪が高くなりやすいため、量や頻度を控えることが大切です。
【控えめにしたい食品例】
| 項目 | 代表的な食品 | 理由 |
|---|---|---|
| 飽和脂肪酸が多い食品 | バター、ラード、脂身の多い肉、ソーセージ、クロワッサン | LDLコレステロールが上がりやすい |
| 糖質の摂りすぎにつながる食品 | 白米、パン、麺類、菓子類、甘い飲み物 | 中性脂肪が増えやすい |
| 揚げ物・油が多い料理 | フライドポテト、唐揚げ、天ぷら、とんかつ | 調理過程で脂質が増加する |
【控える際のポイント】
- 完全に避ける必要はなく、「量」と「頻度」を調整する
- 揚げ物は週に数回ではなく、週1回程度に抑える
- 肉は脂身の少ない部位や鶏むね・ささみなどに置き換える
- 主食(白米・パン)の量を調整し、食物繊維の多い副菜を増やす
積極的に摂りたい食べ物(食物繊維/EPA・DHA)
脂質異常症の改善には、LDLコレステロールの吸収を抑える食品や、中性脂肪を下げる働きのある食品を積極的に取り入れることが大切です。とくに食物繊維とEPA・DHAは食事改善の中心となる成分です。
【積極的に取り入れたい食品例】
| 項目 | 代表的な食品 | 期待できる働き |
|---|---|---|
| 食物繊維を多く含む食品 | 玄米・雑穀、海藻、きのこ類、野菜、豆類 | 食後の血中脂質の上昇を抑えやすい |
| EPA・DHAを多く含む魚 | さば、さんま、いわし、鮭、まぐろ | 中性脂肪を下げる働きがある |
| 良質な脂質を含む食品 | オリーブオイル、アボカド、ナッツ類 | 飽和脂肪酸の置き換えに適している |
【取り入れる際のポイント】
- 野菜や海藻類は「毎食」取り入れるのが理想
- 魚(とくに青魚)は週2~3回を目安に食卓へ
- 調理の油は、バターやラードよりオリーブオイルを優先
- ナッツは食べすぎると脂質が増えるため1日10〜20g程度にとどめる
脂質異常症改善の献立例
脂質異常症の改善には、「脂質を減らす」よりも質の良い脂質を選ぶ・食物繊維を増やす・糖質を摂りすぎないことが大切です。
以下は、日常に取り入れやすい献立例です。
朝食例(糖質控えめ+食物繊維アップ)
- オートミール+無脂肪ヨーグルト+ベリー類→食物繊維・ポリフェノールが豊富でLDL対策に◎
- ゆで卵/卵焼き(油少なめ)→良質なたんぱく質で満腹感が続く
昼食例(脂質控えめ・野菜たっぷり)
- サバの味噌煮/サバ缶アレンジ→EPA・DHAで中性脂肪対策に◎
- 玄米ごはん/雑穀米→食物繊維が多く血糖急上昇を予防
- 具だくさん味噌汁(豆腐・わかめ・野菜)→満腹感アップ&カロリー調整
夕食例(低脂質・高タンパク・食物繊維)
- 鶏むね肉のグリル/豆腐ハンバーグ→脂質が少なくたんぱく質をしっかり補給
- ひじき・切り干し大根・ほうれん草おひたし→不溶性+水溶性食物繊維でコレステロールにアプローチ
間食のおすすめ(どうしても食べたい時)
- ナッツ(無塩・小袋で量を調整)
- 高カカオチョコレート(1日10g程度)
- こんにゃくゼリー、ヨーグルト
献立を考えるときは、主菜の脂質量を抑えつつ、野菜や海藻・大豆など食物繊維の多い副菜をしっかり組み合わせることが大切です。
また、魚や鶏肉などのたんぱく質を適度に取り入れ、油を使わない調理法を選ぶことで、無理なく脂質バランスを整えやすくなります。
脂質異常症を改善するための正しい運動方法
脂質異常症の改善には、生活の中で継続できる運動が大切です。
運動習慣を身につけることで中性脂肪が減り、HDL(善玉)コレステロールが増えやすくなります。また、脂肪の蓄積を防ぎ、動脈硬化の予防にも役立ちます。
ここでは、脂質異常症の改善に効果的な運動と、続けるためのポイントを紹介します。
有酸素運動
有酸素運動は、中性脂肪を減らし、HDLコレステロールを増やすために効果的な運動です。
軽く息が弾む程度の強度で続けることで、体内の脂肪エネルギーが優先的に使われます。
| 種類 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| ウォーキング | 1日30分を目安に、やや早歩きで歩く | 無理のないペースで継続する |
| ジョギング | 会話できる程度のペースで走る | 走りすぎない、足の痛みに注意 |
| 水泳 | 水中での負荷により効率的に脂肪燃焼 | 冷えすぎないよう休憩を挟む |
| サイクリング | 平坦な道を軽快にこぐ程度 | 交通状況に注意する |
継続が何より大切です。
週150分以上(1日30分程度)を目安に、できる範囲から始めてみましょう。(文献2)
筋力トレーニング(レジスタンス運動)
筋力トレーニングは、基礎代謝を高め、脂質のコントロールを助けます。
とくに大きな筋肉を鍛えることで消費エネルギーが増え、脂質をためにくい身体づくりにつながります。
| 種類 | 詳細 | 注意点 |
|---|---|---|
| スクワット | 下半身の大きな筋肉を重点的に鍛える | 無理のない回数で、膝に痛みがある場合は控える |
| 腕立て伏せ | 胸・腕・肩など広い範囲を鍛える | フォームを意識し、膝つきで調整OK |
| 腹筋運動 | 体幹を鍛え姿勢改善にも役立つ | 急な動作を避け、ゆっくりと行う |
筋トレは週2〜3回を目安に行い、休息を挟みながら続けることがポイントです。
日常生活での身体活動量を増やす
特別な運動をしなくても、普段の生活の中で体を動かすだけでも効果は得られます。
| 行動 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 階段を使う | エレベーターやエスカレーターをなるべく使わない | 膝の痛みがある日は無理しない |
| こまめに歩く | 一駅前で降りる、買い物は歩いて行く | 暑い日は熱中症に注意 |
| 家事・庭仕事 | 掃除・洗濯・草むしりなども立派な運動 | 疲れすぎないよう休憩をはさむ |
| 長時間座らない | 30~60分ごとに立ち上がって動く | 姿勢を変えるだけでもOK |
日々のちょっとした活動で中性脂肪が減り、脂肪が燃えやすい体質になります。
運動以外の活動を意識し、座っている時間を減らし、デスクワークやテレビの合間に立ち上がって身体を動かす習慣をつけましょう。歩数計アプリで目標を設定したり、何かのついでに動く工夫をすると、無理なく続けやすくなります。
日常生活の中で意識的に体を動かすことが、血中脂質の改善と健康維持につながります。
脂質異常症の改善に役立つおすすめの飲み物
脂質異常症の改善には、日常的に飲むお茶や飲料に含まれる成分も役立ちます。
とくにカテキンやポリフェノールは、脂質の吸収や酸化に関わる働きがあり、食事と合わせて取り入れることで健康的な脂質バランスの維持に役立ちます。
無理なく続けられる飲み物を選びながら、生活習慣全体とあわせて取り入れることが大切です。
カテキン(緑茶)
カテキンは緑茶に多く含まれる成分で、脂質代謝をサポートする働きがあります。
| カテキンの働き | 詳細 |
|---|---|
| 食事由来のコレステロール吸収を抑える | 食事と一緒に飲むことで、コレステロールが体内へ吸収される量を穏やかにする |
| 脂肪の分解・燃焼をサポート | 脂肪をエネルギーに変える酵素の働きを助ける |
| 抗酸化作用で血管を守る | LDLが酸化するのを抑え、動脈硬化を予防する働きが知られている |
カテキンが多い飲み物
- 煎茶
- 抹茶
- カテキン高含有タイプの特定保健用食品(トクホ)
毎日続けられる飲み方を選び、食事・運動と合わせて取り入れることが大切です。
ポリフェノール(烏龍茶・紅茶)
ポリフェノールは、種類ごとに働きが異なり、飲み物によって品質や量が変わります。
抗酸化作用を持つため、血管の健康維持に役立つとされています。
| 含まれる成分 | 主な働き | 飲み物の例 |
|---|---|---|
| 重合ポリフェノール | 脂肪の吸収を抑える、代謝をサポート | プーアール茶 |
| ウーロン茶ポリフェノール | 食事の脂肪の吸収を穏やかにする | ウーロン茶 |
| ゲニポシド酸など | 血圧や血管の健康を保つ働きが知られている | 杜仲茶 |
| 没食子酸・カテキン・タンニン | LDLの酸化を抑える抗酸化作用 | 紅茶、プーアール茶 |
日ごとに違う種類のお茶を取り入れると、さまざまなポリフェノールが摂れます。
カフェインが気になる場合は、午後以降はノンカフェインのお茶に切り替えてください。
トマトジュース(中性脂肪)
トマトに含まれるリコピンは抗酸化作用があり、中性脂肪の管理にも役立つとされています。
期待される働き
- リコピンの抗酸化作用で血管の健康を保つ
- 食事と一緒に飲むと血中脂質に関わる働きが期待できる
飲み方の目安
- 無塩タイプのトマトジュースを1日コップ1杯程度
- 朝食や夕食のタイミングに取り入れると続けやすい
脂質異常症が改善しない原因と対処方法
脂質異常症は、食事や運動を意識していても、なかなか数値が改善しないケースがあります。続かない生活習慣や隠れた要因が関係していることも多く、原因を把握することが改善への第一歩です。
この章では、改善しない理由と、今日から取り入れられる対処方法を解説します。
やせ型でも脂質異常症(高脂血症)が起こる理由
「痩せているのに脂質異常症と言われた」という方は少なくありません。
やせ型でも以下の理由で脂質異常が起こることがあります。
- 遺伝的体質
家族性脂質異常症(FH)など、遺伝によってLDLが高くなることがある - 筋肉量が少ない
基礎代謝が低く、脂質代謝がうまく働かない - 食事内容の偏り
炭水化物中心、脂質の質が悪い、たんぱく質不足 - 隠れ肥満(内臓脂肪型肥満)
見た目は細くても中性脂肪が高くなるケース
やせ型の脂質異常症は生活習慣の見直しとあわせて、必要に応じて医療機関に相談してください。
サプリ・特保は補助として扱う
脂質異常症の改善には、まず食事・運動などの生活習慣が土台になります。
サプリメントや特定保健用食品(トクホ)は、その土台を支える「補助的な役割」として考えることが大切です。たとえば、EPA・DHAのサプリや、コレステロールの吸収を抑えるトクホのお茶などは、日々の食事だけでは不足しがちな成分を補う点で役立つ場合があります。
しかし、それだけで数値が大きく改善するわけではなく、食べすぎ・飲みすぎ・運動不足が続くと効果を実感しにくくなります。
医師の治療方針や体調に合わせて適切に取り入れながら、あくまで生活習慣の改善を中心に続けていくことが重要です。
継続期間と再受診の目安
脂質異常症の改善には、生活習慣を整えてから結果が数値に反映されるまでに時間がかかります。
一般的に、食事や運動の見直しを始めてから効果が現れ始めるのは1〜3カ月程度とされており、健康診断でも通常は数カ月単位で経過を確認します。自己管理を続けても改善が見られない場合や、数値が大きく変動した場合は、早めに医療機関を受診して原因を見直すことが重要です。
また、家族性脂質異常症の可能性がある人や、更年期・基礎疾患が背景にある人は、自分の判断で放置せず、定期的な受診を習慣づけることで、より適切な治療やアドバイスを受けられます。
まとめ|自分にできる改善を続けて無理なく数値を整えましょう
脂質異常症は、すぐに数値が変わるものではありませんが、食事や運動といった普段の生活を少しずつ整えていくことで、確実に改善へ近づけます。
完璧を目指す必要はなく、自分が続けられる範囲で習慣を積み重ねることが大切です。外食や忙しい日があっても気にしすぎず、できる日からまた整えていけば大丈夫です。
もし数値が思うように下がらない場合は、早めに医療機関へ相談し、必要に応じて治療や検査を受けることで安心につながります。
自分の体と向き合いながら、無理のない改善を続けていきましょう。
脂質異常症の改善におけるよくある質問
改善にかかる期間は?
脂質異常症の数値が改善するまでの期間は、食事や運動をどれだけ継続できるかによって大きく変わります。
早い方では1〜2カ月で中性脂肪の低下が見られることがありますが、LDLコレステロールの改善には3カ月以上かかることも珍しくありません。
とくに食事療法や有酸素運動は毎日の積み重ねが重要で、短期間で劇的に変わるわけではありません。焦らず続けながら、定期的に血液検査で変化を確認することが大切です。
外食時にどう工夫する?
外食では脂質の多いメニューを選びやすくなるため、注文の仕方を少し工夫するだけで改善につながります。揚げ物を避け、焼く・蒸す・ゆでる調理法の料理を選ぶと脂質を抑えられます。
丼ものや麺類など炭水化物中心になりやすいメニューは控えめにし、野菜や海藻、きのこ類がしっかり入った副菜を追加するのがおすすめです。外食では味付けが濃くなりやすいため、ドレッシングやソースを別添えにして量を調整すると、余分な脂質と糖質を避けられます。
更年期や家族性は改善できる?
更年期では女性ホルモンの変化によりLDLコレステロールが上がりやすくなりますが、食事改善や運動習慣の見直しによって数値が整うことは十分にあります。とはいえ、変化が大きい時期のため、早めに医師へ相談しながら対策を進めることが安心です。
一方、家族性脂質異常症(FH)の場合は遺伝的な要因で数値が高くなりやすく、生活習慣だけで十分に改善できないケースもあります。(文献2)
早期に専門的な評価を受け、必要に応じて薬物療法を取り入れながら総合的に管理することが重要です。
(文献1)
脂質異常症診療のQ&A|一般社団法人日本動脈硬化学会
(文献2)
脂質異常症|日本循環器協会