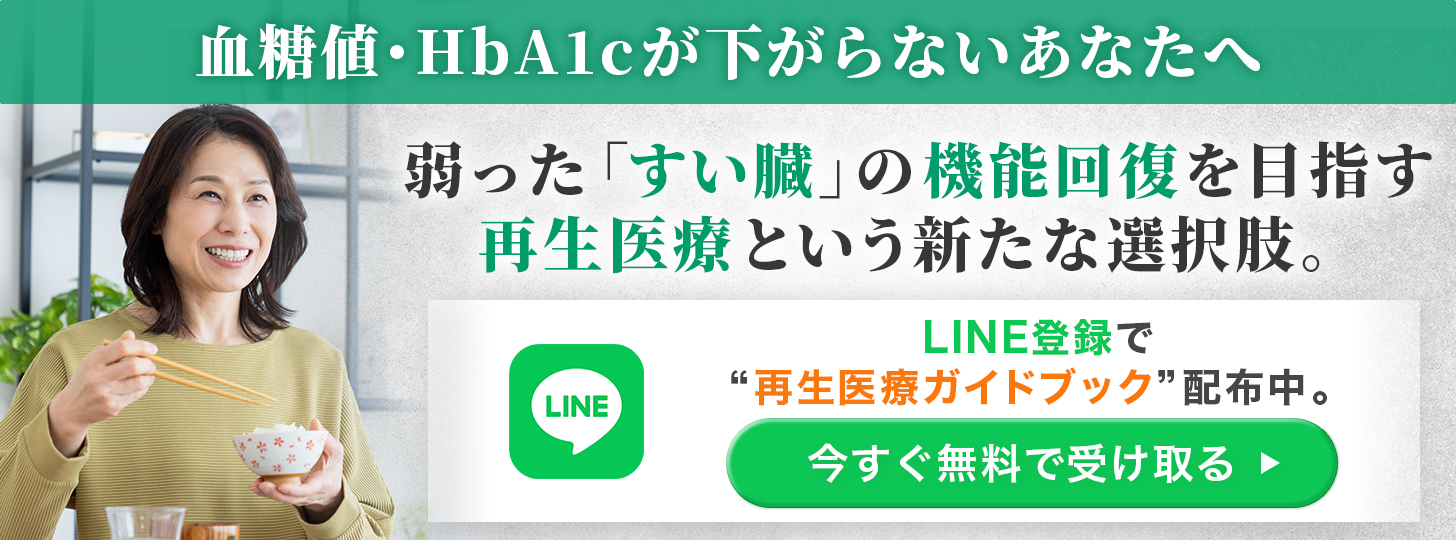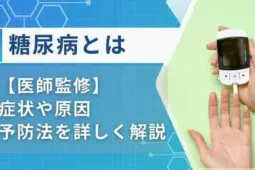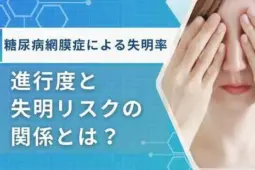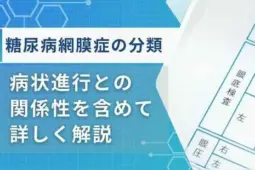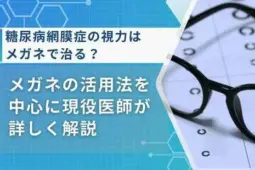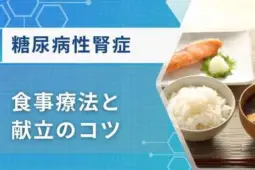- 糖尿病
- 内科疾患
糖尿病による失明の前兆を医師が解説【見え方に要注意】
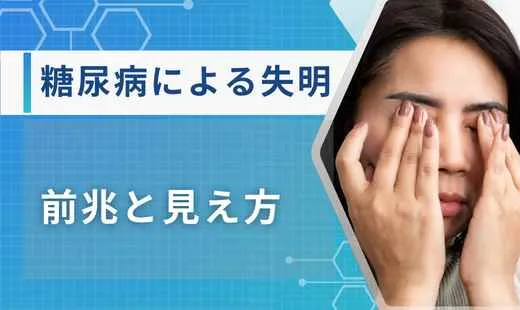
糖尿病は症状が進行していくと、失明といった重大な合併症を発症する場合があります。しかも痛みなく進行するため、前兆に気づくことが視力を守るためには必要です。
本記事では、糖尿病で失明を招く具体的な前兆サイン、進行の仕組み、予防法や治療法まで専門的にわかりやすく解説します。糖尿病の失明が気になる方は、ぜひ参考にしてください。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
糖尿病について気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
糖尿病による失明の前兆症状
糖尿病は血糖値が高い状態が続くことで全身の血管を傷つけ、目の奥にある網膜の血管も傷つけられます。これにより「糖尿病網膜症」を発症し、進行すると失明につながることもあります。初期は自覚症状が少なく気づきにくいですが、以下のようなサインが現れたら注意が必要です。
| かすみ目・視界のぼやけ | 網膜の血流が悪化し、ピントが合いにくくなる |
| 暗い所で見えにくい | 網膜の細胞がうまく働かず、薄暗い場所で視界が悪くなる |
| 飛蚊症や黒い点が増えた | 硝子体出血や網膜剥離の兆候で、視界に糸くずや黒い点が浮かぶように見える |
| 視野が欠ける・ゆがむ | 網膜や黄斑部のむくみ、出血などで、見える範囲が狭くなったり歪んで見えることがある |
| 急激な視力低下 | 網膜剥離や大きな出血など、失明に直結する深刻な状態 |
糖尿病網膜症の症状を放置すると、進行して回復が難しくなる場合があります。少しでも「おかしいな」と感じたら早めに眼科を受診し、専門的な検査を受けましょう。
【失明の前兆】糖尿病網膜症の進行と症状
糖尿病網膜症は血糖値が高い状態が続くことで網膜の血管が障害され、段階的に進行します。初期から末期にかけて症状も変化し、最終的には失明のリスクが高まります。
初期|単純糖尿病網膜症
糖尿病網膜症の初期段階は「単純糖尿病網膜症」と呼ばれ、自覚症状がほとんどないのが特徴です。自分では見え方に変化を感じにくいため、気づかないまま進行してしまいます。
初期の症状は以下のとおりです。
- 点状出血
- 硬性白斑
- 網膜浮腫
網膜内の細い血管が高血糖の影響で傷つき、血液や脂質が漏れ出すことで起こります。網膜浮腫によるむくみが進むと視力への影響が出ることもあります。初期段階では血糖値を適切に管理し、食事療法や運動療法、薬物療法を徹底すれば進行を防ぐことが可能です。
眼科での定期的な検査により、わずかな変化を早期に発見し、適切な治療を行うことが大切です。
中期|増殖前糖尿病網膜症
増殖前糖尿病網膜症は糖尿病網膜症の中期段階で、血管障害が進み、より深刻な変化が現れます。多くの場合、この段階でも自覚症状はほとんどなく、異変を感じることはまれです。
中期の症状は以下のとおりです。
- 軟性白斑
- 網膜内細小血管異常
軟性白斑は網膜の酸素不足を示すサインで、網膜内細小血管異常は血流が阻害されていることを意味します。進行を抑える治療としては、レーザー光凝固で異常血管を封じ込めたり、抗VEGF薬注射やステロイド注射でむくみを軽減したりします。
進行を防ぐためには、血糖管理を継続し、眼科での定期検診を受けることが不可欠です。
末期|増殖糖尿病網膜症
糖尿病網膜症がさらに進行し末期になると「増殖糖尿病網膜症」と呼ばれ、失明の危険性が非常に高くなります。高血糖により網膜が酸素不足になると、新生血管が異常に増殖し、さまざまな深刻な合併症を引き起こします。
末期の症状は以下のとおりです。
- 硝子体出血
- 新生血管の増殖
- 急激な視力低下
- 牽引性網膜剥離
新生血管は非常にもろく破綻しやすいため、硝子体出血により視界が急に真っ暗になることもあります。瘢痕組織が網膜を引っ張り牽引性網膜剥離を起こすと、急速な視力喪失が生じます。
治療にはレーザー治療(汎網膜光凝固術)や硝子体手術などが必要です。進行を防ぐには、早期の診断と治療、血糖管理、そして眼科での定期的なフォローが不可欠です。視力を守るため、少しでも異変を感じたらすぐに受診しましょう。
【前兆症状を防ぐ】糖尿病で失明しないための予防法
糖尿病による失明を防ぐためには、毎日の管理と定期的な検査が欠かせません。以下のポイントを意識して予防に取り組みましょう。
- 血糖コントロール:血糖値を適切に管理し、網膜へのダメージを防ぐ
- 血圧・脂質管理:高血圧や脂質異常症を改善し、血管障害を予防する
- 有酸素運動:ウォーキングなどを習慣にし、血糖値や血圧を安定させる
- 食事の管理:バランスの良い食事でカロリー・糖質をコントロールする
- 定期的な眼底検査:自覚症状がなくても早期発見のために検査を欠かさない
日々意識して実践すると、糖尿病網膜症の進行を抑え、失明のリスクを大きく減らせます。医師や管理栄養士と相談しながら、自分に合った計画を立て、無理なく続けることが大切です。
失明の前兆段階で適用される糖尿病網膜症の治療法
糖尿病網膜症は進行度に応じてさまざまな治療法があります。失明リスクが高まる前兆段階で適切な治療を受ければ、糖尿病網膜症の進行を抑えることが期待できます。以下は主な治療法です。
- 血糖コントロール
- レーザー光凝固術
- 硝子体手術
- 抗VEGF療法
- 再生医療
血糖コントロール
糖尿病網膜症の進行を防ぐためのもっとも基本的な治療は、血糖コントロールです。血糖値が高い状態が続くと、網膜の血管が傷つき、病変が進行しやすくなります。糖尿病治療ではインスリン療法や内服薬を活用し、血糖値を適正範囲に維持することを目指します。食事療法や運動療法を組み合わせ、血糖変動の抑制が非常に大切です。
生活習慣の見直しも欠かせません。バランスの良い食事、適度な運動、規則正しい生活を続ければ全身の血管障害を予防できます。医師や栄養士と相談しながら無理なく継続しましょう。
定期的な血液検査や通院を通じて経過をしっかり管理すれば、合併症の早期発見や治療につながります。ご自身の健康状態を理解し、専門医と二人三脚で取り組むことが大切です。
レーザー光凝固術
レーザー光凝固術は、糖尿病網膜症の進行を抑えるための標準的な治療法です。網膜が酸素不足になると、異常な新生血管が増殖しやすくなり、出血や網膜剥離を引き起こす危険性が高まります。レーザー光凝固術では網膜の虚血部分にレーザーを照射し、組織を凝固させることで酸素需要を抑え、新生血管の発生を予防します。
レーザー光凝固術により、視力低下の進行を抑えられます。ただし、レーザー治療は進行を完全に止めるものではなく、血糖コントロールや定期検診と組み合わせて総合的に管理する必要があります。
早期発見と適切なタイミングでの治療が、視力を守るための大切なポイントです。治療の際は専門医が丁寧に説明を行い、患者様の不安を取り除きながら進めます。
硝子体手術
硝子体手術は、進行した糖尿病網膜症による重篤な合併症に対する治療法です。網膜剥離や硝子体出血が発生した場合、レーザー光凝固術だけでは十分な効果が得られなかった場合に実施されます。
手術では、目の中にある濁った硝子体を除去し、出血や瘢痕を取り除いた上で、網膜を正しい位置に再付着させる処置を行います。急激な視力低下を改善し、さらなる失明を防ぐことを目指します。術後のケアや経過観察も重要になるため、定期的な受診は必要です。
手術の適応やタイミングは患者様一人ひとりの眼の状態に合わせて慎重に判断します。不安な点や疑問があれば担当医に相談してみましょう。
抗VEGF療法
抗VEGF療法は、糖尿病網膜症によって生じる黄斑浮腫を抑制するための治療法です。VEGF(血管内皮増殖因子)は新生血管の増殖を促進し、血管の透過性を高めて黄斑部にむくみを生じさせます。抗VEGF薬を眼内に注射するとVEGFの働きを抑えられるため、むくみが軽減でき視力の維持につながります。
治療は一度で終わるものではなく、症状に応じて繰り返しの注射が必要な場合も多いです。黄斑浮腫は視力低下の大きな原因となるため、早期治療が非常に重要です。眼科専門医が患者様の眼の状態を詳しく評価し、適切な治療計画を立てながら進めます。
再生医療
糖尿病網膜症に対する新たな治療アプローチの一環として、再生医療があります。患者様ご自身の脂肪組織から採取した細胞を培養し、身体に戻す治療法です。当院では再生医療に関する情報や現状をご説明し、患者様に合った治療をご案内しています。
ご関心のある方は、まずはお気軽にご相談ください。ご不明点や不安な点についても丁寧にお話をさせていただきます。
\無料相談受付中/
糖尿病による失明を防ぐためにも前兆を見逃さず早期に医療機関を受診しよう
糖尿病網膜症は初期には自覚症状がほとんどなく進行し、気づいたときには重度になっていることも珍しくありません。失明を防ぐには、血糖値のコントロールをしっかり行った上で、内科での定期受診の継続が必要です。目の状態を把握するために眼科の定期受診も欠かせません。視界のかすみやぼやけ、見え方の違和感など、わずかな前兆を見逃さないようにしましょう。
「気になる症状があるけれど受診して良いのかな」と迷わずに、早めに専門医を受診すれば、進行を抑える治療につなげることが可能です。当院でも、糖尿病と目の健康に関する再生医療についてのご相談を受け付けておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
\無料相談受付中/

糖尿病のお悩みに対する新しい治療法があります。
糖尿病による失明の前兆についてよくある質問
糖尿病網膜症は痛みがなくても進行しますか?
糖尿病網膜症は網膜の血管が傷つき変化していく病気ですが、網膜には痛覚がないため、進行していても痛みを感じることはありません。そのため患者様自身が異変に気づかず、病気がかなり進行してから初めて自覚症状が出るケースも多いのが特徴です。
ただし、飛蚊症(視界に黒い点や糸くずが見える)、視野の一部が欠ける、ゆがんで見えるなど、痛みの代わりに現れる前兆症状が出る場合もあります。症状を見逃さず、少しでも見え方に異変を感じたら早めに眼科を受診しましょう。定期的な検査での早期発見が失明を防ぐポイントです。
糖尿病は血糖値が下がればよくなりますか?
糖尿病網膜症は、血糖値が高い状態が続くことで網膜の血管にダメージを与え、進行していく病気です。血糖値を下げることで傷んだ血管を元に戻すことはできませんが、進行を抑えることは可能です。
血糖コントロールをしっかり行えば、新たな血管障害を防ぎ、既存の病変の悪化を抑えられます。内科での治療を継続し、食事療法や運動療法を取り入れることが重要です。網膜症の進行度に応じた眼科での治療や定期検査を併用し、視力を守るための総合的な管理をしましょう。