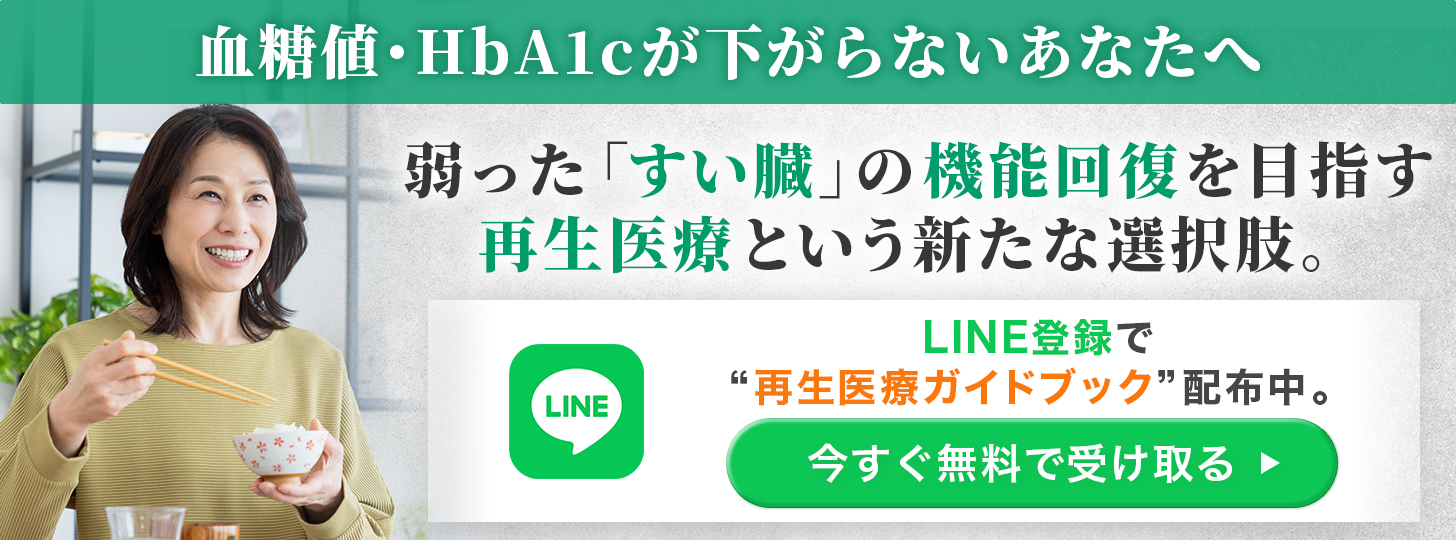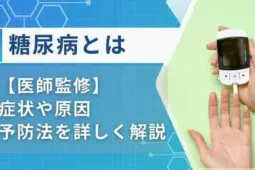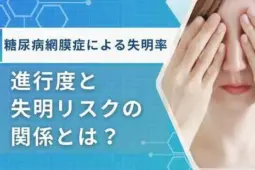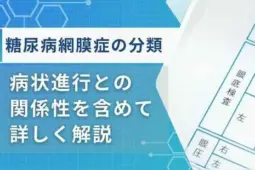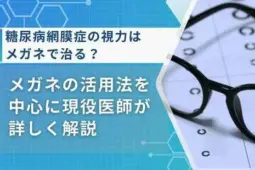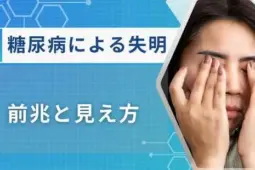- 糖尿病
- 内科疾患
糖尿病網膜症は治るのか|治療方法とあわせて現役医師が解説
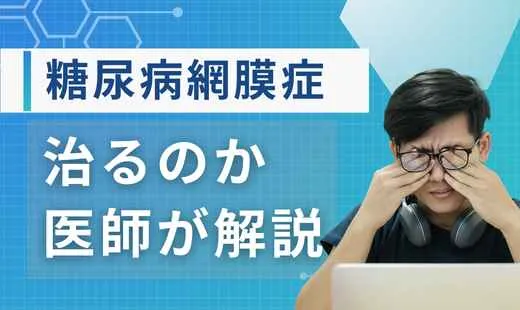
「糖尿病の治療を続けて数年たつが、最近目がかすむようになった」
「糖尿病網膜症があるのではないか」
「糖尿病網膜症は治るのだろうか」
糖尿病治療中の方で、このような状況になっている方も多いことでしょう。
糖尿病網膜症は合併症の1つで、進行すると視力低下や失明のリスクがあります。
完全に治すことは難しい状況ですが、早期発見早期治療により、進行を抑えることは可能です。
本記事では、糖尿病網膜症の治療について解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
糖尿病網膜症の完治は難しいが進行の抑制は可能
糖尿病網膜症は、糖尿病による高血糖が長期間続くことで、目の網膜にある細い血管が損傷を受ける合併症の一つです。
出血やむくみ、さらには異常な新生血管の増殖を引き起こし、視力低下や最悪の場合は失明に至るケースもあります。
また、進行しても自覚症状の乏しいケースが少なくありません。
一度低下した視力を完全に回復させるのは難しいものの、定期的な眼科検診と早期の治療によって進行を食い止め、視力を保つことは可能です。
糖尿病にかかっているのであれば、糖尿病網膜症のリスクを常に意識し、適切に管理するよう心がけていきましょう。
糖尿病が原因の失明に関しては、以下の記事でも詳しく解説しているので参考にしてください。
糖尿病網膜症の治療方法
糖尿病網膜症の治療は、進行の度合いや症状に応じてさまざまな選択肢があります。とくに初期段階では、適切な治療によって視力低下の抑制や合併症の予防が可能です。
ここでは、糖尿病網膜症の主な治療方法について解説します。
レーザー光凝固術
レーザー光凝固術(ひかりぎょうこじゅつ)とは、糖尿病網膜症の進行を抑えるために行われる治療法です。
新生血管の発生予防や退縮、黄斑のむくみ抑制を目指す治療で、主に以下の3種類があります。
- 直接光凝固
- 格子状網膜光凝固
- 汎網膜凝固
直接光凝固は、新生血管や毛細血管瘤の病変そのものにレーザーを当て焼き固める方法です。出血や浮腫の進行を止めたり、新たな出血を予防したりするために利用されます。
格子状網膜光凝固は、網膜のむくみに対して格子状にレーザーを照射する方法です。むくんだ部分の水分を吸収させて黄斑の腫れを軽減したり、視力低下の進行を抑えたりなどに効果が期待できます。
汎網膜凝固は、網膜全体にレーザーを施すことで新生血管の発生を抑制するのが特徴です。酸素不足によってできる新生血管の減少・抑制を目的としています。
抗VEGF治療
抗VEGF治療は、黄斑のむくみや新生血管の発生に関与するVEGF(血管内皮増殖因子)の作用を抑制する治療法です。抗VEGF薬を眼球内に注射し、視力低下やモノのゆがみといった症状の抑制を目指します。
注射は外来で短時間で終了し、初回の注射後は経過を観察しながら追加治療が行われるのが一般的です。
ただし、硝子体注射の傷口から細菌が入り込むと「眼内炎」という感染症を起こすリスクがあります。
頻度はまれではあるものの、重篤な視力障害を引き起こす可能性があるため、硝子体注射前後の抗生剤点眼や消毒などを行う必要があります。
硝子体手術
硝子体手術は糖尿病網膜症が進行し、網膜剥離や硝子体出血が生じた際に行われる外科的治療法です。
硝子体とは水晶体と網膜の間にある透明な組織で、コラーゲン繊維と水から構成されています。
手術によって出血や混濁を起こした硝子体を取り除き、視力の回復や網膜の機能維持を目指します。
レーザー治療が無効だったケースや、重度の合併症がある場合に適応されるのが一般的です。
広く利用されている手術方法ですが、顕微鏡下での細かい操作が必要など高度なレベルの手術となるほか、合併症が起こるケースがあります。
糖尿病網膜症の分類
糖尿病網膜症は進行度に応じていくつかの段階に分類されており、治療方針や予後の見通しも段階ごとに異なります。
初期にはほとんど自覚症状がない場合が多いものの、進行すると視力の低下や失明の危険性も高まるため、各段階の特徴を正しく理解しておきましょう。
ここでは、糖尿病網膜症の代表的な3つの分類について解説します。
単純糖尿病網膜症
単純糖尿病網膜症は、網膜の毛細血管が高血糖の影響でもろくなり、小さな出血や毛細血管瘤が生じる初期段階の病態です。
血管からタンパク質や脂肪が漏れ出し、硬性白斑(白い斑点)として網膜に沈着するケースもあります。
また、自覚症状はほとんどなく、気づかないうちに進行するケースも少なくありません。
ただし、血糖コントロールを適切に行えば、症状の進行を防ぐことが可能な段階です。
詳しい網膜の状態を調べるべく眼底の血管造影検査を行う場合もありますが、進行を防ぐためには早期発見と生活習慣の見直しが重要となります。
増殖前糖尿病網膜症
増殖前糖尿病網膜症は毛細血管の障害が進行し、広範囲にわたって血流が途絶える状態です。
網膜に酸素や栄養が届かなくなると体が新たな血管を作ろうと反応しますが、この過程で神経のむくみや静脈の拡張が生じます。
視界のかすみやぼやけといった自覚症状が現れる場合もありますが、無症状のケースも少なくありません。
治療方法は、網膜光凝固術を採用するのが一般的です。
増殖糖尿病網膜症
増殖糖尿病網膜症は、糖尿病網膜症が進行したもっとも重症な段階です。
新生血管が網膜や硝子体に向かって伸びてきますが、新生血管は非常にもろく、破れると硝子体出血を引き起こす恐れがあります。
結果、飛蚊症や急激な視力低下が生じるケースがあるほか、網膜表面に「増殖膜」と呼ばれる膜ができて網膜剥離を引き起こす場合もあります。
また、年齢が若いほど進行が早いとされており、注意しなければなりません。
糖尿病網膜症が進行した段階では手術が必要となりますが、手術が成功しても視力が日常生活に支障がないレベルまで回復しないことがあります。
視力を保つために必要な自己管理
糖尿病網膜症による視力低下を防ぐためには医療機関での治療だけでなく、日常生活における自己管理が重要な役割を果たします。
血糖・血圧・脂質のコントロールに加えて定期的に眼科を受診し、重症化の予防と早期発見につなげていくことが大切です。
では、視力を維持するために実践すべき自己管理のポイントを詳しく見ていきましょう。
血糖・血圧・脂質の管理を徹底する
糖尿病網膜症の発症や進行を抑えるには、血糖・血圧・脂質の3つの項目をバランスよく管理することが重要です。
とくに、血糖コントロールの目安であるヘモグロビンA1cを7%未満に保つように推奨されています。
また、高血圧はとくに収縮期血圧との関連が深く、進行リスクを高める因子です。
さらに、脂質異常症の適切な治療も網膜症の進行抑制に良好な影響を与えるとされています。
血糖値だけでなく、血圧や脂質の管理にも注力しながら視力を保つように自己管理を徹底しましょう。(文献1)
定期的に眼科を受診する
糖尿病網膜症の早期発見と進行防止には、定期的な眼科受診が欠かせません。
2型糖尿病患者の約30%は、診断時すでに網膜症を発症しているという報告があり、耐糖能異常の段階でも網膜症が認められる場合があります。
したがって、2型糖尿病と診断されたら直ちに眼科を受診することが重要ですが、受診頻度としては以下が目安です。
- 網膜症がない場合:年1回
- 単純網膜症:6カ月ごと
- 増殖前糖尿病網膜症:2カ月ごと
- 増殖期糖尿病網膜症:月1回の検査
(文献2)
ただし、上記はあくまで目安です。
患者によって病態や症状は異なるため、実際の受診頻度は眼科医の判断に従いましょう。
まとめ|糖尿病網膜症のポイントは早期発見と継続治療
糖尿病網膜症は、重症化すると視力の著しい低下や失明を招く恐れのある重大な合併症です。しかしながら、早期に発見し適切な治療を行えば、進行を抑えながら視力を保つ効果が期待できます。
糖尿病と診断された段階から定期的に眼科を受診し、状態を継続的に管理していくことが重要です。
また、血糖値に加えて血圧や脂質のコントロールも、進行予防において欠かせません。日々の生活習慣を見直しながら、継続的な治療と管理を徹底していきましょう。
リペアセルクリニックでは、糖尿病に対する再生医療にも対応しています。
公式LINEでは、無料オンライン診断を実施しているので、糖尿病でお悩みの方は一度ご相談ください。
\無料オンライン診断実施中!/
糖尿病網膜症に関するよくある質問
糖尿病患者の失明率はどのくらいですか?
公益社団法人日本眼科医会によれば、糖尿病網膜症が重症化して失明に至る、あるいは失明の危機にある糖尿病患者は全体の約20%と報告されています。(文献3)
糖尿病における眼の合併症がいかに深刻であるかを示しており、失明を防ぐためには血糖・血圧・脂質の適切な管理と、定期的な眼科受診による早期発見と治療が重要です。
糖尿病網膜症は失明原因の何位ですか?
2019年に岡山大学学術研究院が行った全国調査によると、糖尿病網膜症は視覚障害の原因として第3位に位置づけられています。(文献4)
なお、第1位は緑内障、第2位は網膜色素変性症です。
視覚障害と失明は完全に同義ではありませんが、糖尿病網膜症は視力障害や失明と密接に関連します。
進行を防ぐためには早期発見と継続的な治療が重要であり、定期的な眼科受診が欠かせません。
参考文献
(文献1)
一般社団法人日本糖尿病学会「高齢者糖尿病の血糖コントロール目標について」
https://www.jds.or.jp/modules/important/index.php?content_id=66 (最終アクセス:2025年6月23日)
(文献2)
日本糖尿病眼学会診療ガイドライン委員会「糖尿病網膜症診療ガイドライン(第1 版)」
https://www.nichigan.or.jp/Portals/0/resources/member/guideline/diabetic_retinopathy.pdf (最終アクセス:2025年6月23日)
(文献3)
公益社団法人日本眼科医会「糖尿病で失明しないために」
https://www.gankaikai.or.jp/health/35/index.html (最終アクセス:2025年6月23日)
(文献4)
岡山大学「視覚障害の原因疾患の全国調査:第1位の緑内障の割合が40%超〜2018年の視覚障害認定基準改正の影響が判明〜」
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id1082.html?utm_source=chatgpt.com (最終アクセス:2025年6月23日)