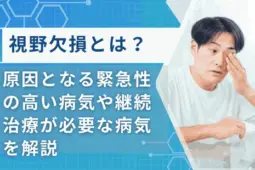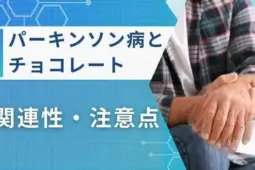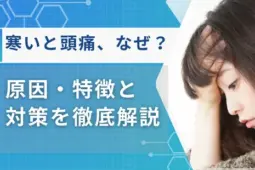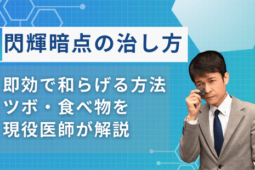- 頭部
- 頭部、その他疾患
- その他、整形外科疾患
失調性歩行とは|歩き方の特徴や原因・リハビリ方法を現役医師が解説
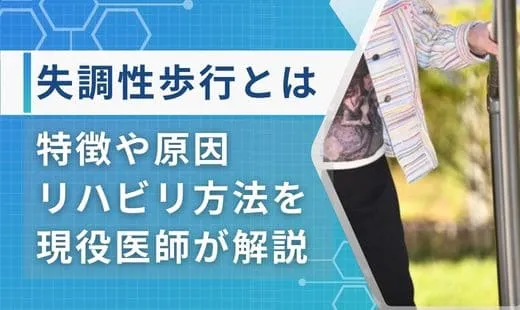
「失調性歩行って何?」「ふらつく歩き方は治るの?」「どんな病気が関係しているの?」
このような疑問をお持ちではありませんか。
医師から「失調性歩行」と言われたものの、詳しい説明がなく不安を感じている方もいるかもしれません。
失調性歩行とは、バランスがとりにくく、まっすぐ歩けなくなる歩行障害のひとつです。
本記事では、失調性歩行の症状や原因、リハビリによる改善の可能性について解説します。
診断後の不安を少しでも和らげるヒントとして、参考にしていただけたら幸いです。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
失調性歩行について気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
失調性歩行の特徴は「歩くときのふらつき」
失調性歩行とは、体のバランスをうまく保てず、ふらつきながら歩く状態を指します。
症状のあらわれ方にはいくつかのタイプがあり、それぞれ特徴が異なります。
ふらふら揺れながら歩く
体のバランスを保つのが難しくなり、左右にふらふらと揺れながら歩くのが特徴です。(文献1)
一見すると酔っているように見えるため、「酩酊歩行」とも呼ばれます。
歩いている途中で急に向きを変えようとすると、動きがぎこちなくなり、強くふらつくこともあります。(文献2)
足を大きく広げて歩く
歩くときに足を大きく開いて進むのも、失調性歩行の典型的なパターンです。(文献1)
重心を安定させようとする無意識の反応で、転ばないように下半身を広く使って支えようとするのです。
このとき、ひざを伸ばしたまま大きく踏み出すような歩き方になりやすく、本来のように膝を柔らかく曲げて歩く動きが見られなくなります。
階段の上り下りが難しくなるのも、このようなバランスの崩れが関係しています。(文献2)
\無料オンライン診断実施中!/
失調性歩行を引き起こす主な原因
失調性歩行にはいくつかのタイプがあり、それぞれ背景にある病気や障害が異なります。
歩行障害の詳しい種類や原因は、こちらの記事でも詳しく紹介しているため、合わせてご覧ください。
小脳の障害|脊髄小脳変性症・小脳出血など
小脳は体の動きをスムーズにし、バランスをとる役割をもっています。
ここに障害があると、歩くときに体が左右に揺れ、足がもつれるなどの症状が現れます。
代表的な病気は、脊髄小脳変性症、小脳出血、多発性硬化症などです。(文献3)
脊髄の障害|脊髄腫瘍・脊髄空洞症など
脊髄は背骨の中を通る神経の束で、脳からの指令を体に伝える通り道です。
この部分に異常があると、足の動きや位置の感覚がうまく伝わらなくなり、歩き方がぎこちなくなります。
脊髄腫瘍や脊髄空洞症などが関係していることがあります。(文献4)
前庭の障害|メニエール病・前庭神経炎など
前庭とは、耳の奥にあるバランスを感じ取る器官です。
ここがうまく働かなくなると、立っているときや歩いているときにぐらぐらする感覚が続きます。
メニエール病、前庭神経炎、感染性髄膜炎などが代表的です。(文献4)
大脳の障害|多発性脳梗塞など
大脳は、動きの「司令塔」として働く部分です。
脳内の前頭葉、頭頂葉といった部位に異常があると、筋力に問題がなくても体のバランスが崩れたような歩き方になることがあります。(文献4)
小脳の障害に似た症状が見られることがあり、原因の特定が難しいケースがあることも大脳の障害の特徴です。
また、明らかな麻痺がなくても歩行が不安定になることもあるため、脳全体の状態を丁寧に確認する必要があります。(文献4)
これらの病気は、早めに気づいて対応することが大切です。
失調性歩行には専門的なリハビリが効果的
失調性歩行の症状がみられた場合、原因となる障害に合わせたリハビリをすることで、歩行の安定を目指せます。
協調運動を助ける「フレンケル体操」
フレンケル体操は、目で見ながらゆっくりと体を動かすリハビリ方法です。
手足を「どう動かすか」を意識しながら反復練習をして、バランス感覚や動きの調整力を取り戻す目的があります。
たとえば、以下のような動作をします。
- 椅子に座って床に置いた目印をなぞるように足を動かす
- 仰向けになり、片脚のかかとを床につけたまま、かかとをゆっくり滑らせるようにしながら膝を曲げ伸ばす
- 床に平行線を引き、その上を歩く
シンプルな動作を自分の目で確認しながら繰り返します。
特別な器具は不要で、ベッドや椅子があれば始められるため、自宅でも取り入れやすい訓練のひとつです。
感覚のずれを補う「重りや包帯」
失調性歩行では、手足の動きと感覚がうまく一致しないことがあります。
自分では足をまっすぐ出したつもりでも、実際にはずれていたり、力を入れすぎてしまったりするのです。
こうした「感覚のずれ」を補う方法として、手足に軽い重りや包帯をつけるリハビリがあります。
重さや圧迫感があることで、手足の位置や動きを意識しやすくなり、「動きすぎ」「力の入れすぎ」といったミスを防ぎやすくなるのです。
重りや包帯の量は状態に合わせて調整でき、歩く・立つ・座るなど、基本動作の安定にもつながります。
体幹の安定性を高める「筋力トレーニング」
筋力や体力が落ちていると、バランスをとる力も弱くなり、ふらつきや転倒のリスクが高まります。
そのため、失調性歩行のリハビリでは筋力をつけることも大切です。
筋力トレーニングには、筋力向上に加えて筋肉の協調性やリズミカルな動作を改善する効果も期待できます。
また、柔軟体操を取り入れて、関節のこわばりを防ぐことも行います。
無理なく体を支える力をつけていくことで、転倒予防や日常生活の自立にもつながるため、継続がカギになるでしょう。
失調性歩行の改善を目指すなら医療機関を受診しよう
失調性歩行には、小脳や脊髄、大脳、耳のバランス器官など、さまざまな原因が関係しています。
原因によって対処法も異なるため、医療機関での検査やリハビリが大切です。
歩き方に違和感があるときや、家族に「おかしい」と言われたときは、迷わず専門の医師に相談してください。
リペアセルクリニックでは「メール相談」や「オンラインカウンセリング」も行っています。
失調性歩行でお悩みの方は当院へお気軽にご相談ください。
\無料相談受付中/
失調性歩行に関するよくある質問
失調性歩行はリハビリで改善しますか?
失調性歩行の改善は、原因となる病気や障害によって異なります。
ただし、フレンケル体操や筋トレなどのリハビリを継続することで、歩行が安定し、日常生活の質も向上する可能性があります。
専門の病院を受診し、医師やリハビリスタッフの指導を受けながら継続していきましょう。
小脳が原因の失調性歩行は治りますか?
小脳性の失調は、根本的な治療が難しいこともありますが、リハビリや再生医療などによって歩行の質が改善する可能性があります。
早めに医療機関で相談し、状態に合った対応を始めることが大切です。
小脳梗塞の後遺症の治療や予後については、こちらの記事で詳しく紹介しているため、合わせてご覧ください。
参考文献