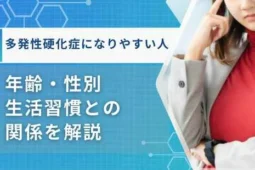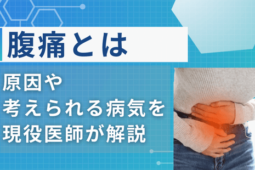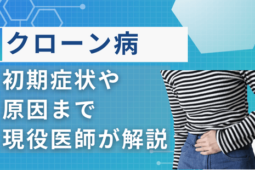- 内科疾患
- 内科疾患、その他
バージャー病とは|初期症状・原因・治療法など現役医師がわかりやすく解説
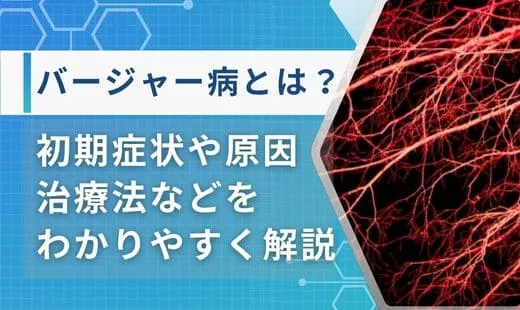
「足先が冷える」「しびれが続く」といった症状が気になっていませんか。
その不調は、ただの疲労や年齢のせいではなく、「バージャー病」という血管の病気が関係している可能性があります。
バージャー病とは、主に手足の血管が詰まり、進行すると壊死や切断のリスクもある深刻な疾患です。
本記事では、「バージャー病」について、気になる初期症状や原因、治療法を医師がわかりやすく解説します。
ぜひ本記事を参考にご自身の症状と照らし合わせ、バージャー病の可能性がないかどうかを確認してみてください。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
バージャー病について気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
バージャー病とは手足の血管が詰まりやすくなる難病
バージャー病とは、正式名称は「閉塞性血栓性血管炎」で、手足の血管が詰まりやすくなる指定難病の一つです。発症には喫煙が深く関係しており、特に「若年層で喫煙歴のある男性」に多いと報告されています。(文献1) (文献2)
主に手足の動脈や静脈に炎症が起こることで血管が詰まり、手足の冷えやしびれ・痛みなどの症状があらわれます。死亡率はきわめて低いものの、進行すると皮膚潰瘍や組織の壊死を引き起こし、手足の切断に至るケースもあるため注意が必要です。
また、国内の患者数は2012年時点で約7,000人と推定されており、生活の質(QOL)を守るためにも、早期発見と禁煙を含めた適切な治療が大切です。(文献1)
\無料オンライン診断実施中!/
【進行度別】バージャー病にみられる症状
バージャー病の症状は、病気の進行とともに変化し、初期段階から末期にかけて段階的に悪化することがあります。本章では、進行度に応じてみられる主な症状を順を追って解説します。
重症化を防ぐためにも、早期に異変に気づき、適切な対処を心がけましょう。
なお、バージャー病にみられる「血栓性静脈炎」については、以下の記事にて詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
初期症状|手足のしびれが多い
バージャー病の初期症状として多く見られるのが、手足のしびれや冷えです。
これらの症状は、末梢血管の炎症により血流が悪化し、組織への酸素・栄養供給が不足することで起こります。
また、皮膚が青白く変色するチアノーゼが見られることもあります。冷たいものに触れたときや寒い場所にいるときに血行が一時的に悪化し、皮膚の色が青白く変化する現象です。その後じんじんとした痛みを感じることもあります。
これらの症状はいずれも血行不良のサインであり、放置すると進行する可能性があるため早めの対処が重要です。
進行した症状|運動時の足の違和感・潰瘍があらわれることも
バージャー病が進行すると、初期症状に加えて、見た目にもわかるような症状があらわれることがあります。代表的な症状は以下のとおりです。
|
症状 |
説明 |
|---|---|
|
間欠性跛行(かんけつせいはこう) |
一定距離を歩くと足が痛くなり、休むと痛みが和らぐ |
|
手足の潰瘍 |
皮膚が赤黒く変色し、表面がただれて見えることが多く、悪臭を伴う場合もある |
ただし、バージャー病の症状があらわれる順番は個人差があり、人によっては最初から指先をはじめとする部位に潰瘍ができるケースもあります。手足の違和感や見た目の変化が気になる場合は、早めに受診するようにしましょう。
バージャー病と同様、間欠性跛行がみられることが多い病気に「閉塞性動脈硬化症」があります。詳細はこちらの記事でも解説していますので、気になる方はあわせてご覧ください。
末期状態|壊死による切断リスクがある
バージャー病が末期状態にまで進行すると、潰瘍が広がり、最終的には壊死(組織死)が起こるようになります。
壊死とは、血流が完全に途絶えることで酸素や栄養が届かなくなり、組織が死んでしまう状態です。壊死した部位は黒く変色して冷たくなり、感覚がなくなることも多く見られます。
さらに壊死が進行すると感染症を併発しやすくなり、生命に危険が及ぶ可能性が高まります。そのため、壊死の部位を取り除くために患部の手足を切断せざるを得ないケースもあるのです。
手足の切断は、生活の質を著しく低下させるため、末期に至る前の早期発見と治療が大切です。
バージャー病の原因の多くは「喫煙習慣」
バージャー病の最大の危険因子は、喫煙習慣です。
タバコに含まれるニコチンをはじめとする有害物質が、血管の細胞に直接ダメージを与え、炎症を引き起こしやすくなります。さらに血小板が集まりやすくなるため、血の塊ができやすくなります。
特に、手足の末梢にある細い血管でこの作用が強く働き、血流が阻害されるため、初期段階では手足に症状があらわれやすくなるのです。
そのため、バージャー病と診断された場合、禁煙が最も重要な治療法の一つとなります。
バージャー病の治療法
医療機関で行われるバージャー病の治療法は、主に以下の4つです。
- 禁煙
- 薬物療法
- 運動療法
- 手術(重症の場合)
治療法をあらかじめ知っておくことで、医師との相談がスムーズになり、自分に合った治療を選ぶ際の参考になります。本章を参考に、それぞれの治療内容について理解を深めてみてください。
禁煙
喫煙は、バージャー病の大きな要因とされており、多くの場合で喫煙者に対しては禁煙を勧められます。禁煙によりバージャー病の進行抑制や再発リスクの低減などが期待されています。
ただし、自力での禁煙が難しい方も少なくありません。そのような場合は、医療機関による禁煙支援を活用するのも有効です。主な支援内容には、以下のようなものがあります。(文献3)
- ニコチン依存度のチェック
- 呼気の測定
- ニコチンパッチやニコチンガムなどを使った薬物療法
- 専門スタッフによる禁煙指導
これらの支援を受けることで、禁煙の成功率を高めることができます。禁煙に不安を感じる方は、ひとりで抱え込まず、このような支援を積極的に活用してみましょう。
薬物療法
手足しびれや冷えが認められる場合は血行不良が疑われるため、抗血小板薬(血液をサラサラにする薬)が処方されることがあります。(文献4) これにより、血のかたまりの形成を抑えて血管の詰まりを予防し、手足の冷えやしびれといった症状の緩和につながるのです。
状態によっては、血管拡張薬や血流改善薬などが用いられることもありますが、これらの薬は病状や体質に応じて医師が判断します。自己判断せず、早めに医療機関を受診しましょう。
運動療法
間欠性跛行の症状がある場合、薬物療法に加え、医師や理学療法士の指示の下で運動療法が行われることがあります。なかでも代表的なのが「トレッドミル療法」です。(文献4)
トレッドミル(電動式の歩行マシン)を使用し、一定の速度で歩行を行い、痛みが出た時点で休憩をはさむというサイクルを繰り返し行います。これにより血流改善や歩行能力の向上が期待できるのです。
ただし、潰瘍や壊死がある場合は、運動により症状を悪化させるおそれもあります。必ず専門医の指導のもとで行うようにしましょう。
重症例は手術を行う
薬物療法や禁煙だけでは改善が見られない場合や症状が進行する場合には「血行再建術」と呼ばれる手術が行われることがあります。「血行再建術」は詰まった血管の代わりに人工血管や自身の血管を用いて迂回路(バイパス)を作り、血流を回復させる治療法です。
また、血行再建術が困難な場合や手指に限局した潰瘍がある場合は「交感神経節切除」が行われることもあります。
一方で、これらの従来治療では十分な効果が得られない症例も少なくありません。そのような中で注目されているのが、細胞や組織の再生能力を活かした「再生医療」です。
再生医療では、自身の細胞を活用して血管や組織の再生を図る治療を行います。
当院「リペアセルクリニック」では、この再生医療を取り入れた治療を行っております。メール相談やオンラインカウンセリングを通じて無料のご相談も可能です。
バージャー病の治療方針に悩まれている方は、どうぞお気軽に当院までご相談ください。
\無料相談受付中/
バージャー病の進行を防ぐ生活習慣・日常の注意点
バージャー病の進行を防ぐためには、治療と並行して日常生活でのセルフケアも大切です。日常生活の主な注意点は以下の3つです。
- 受動喫煙を避ける
- 手足を冷やさない
- 生活習慣の治療を適切に管理する
この章を参考に、今日からできる予防習慣を少しずつ取り入れていきましょう。
たばこの煙を避ける
喫煙は、バージャー病の発症リスクを高めます。自分自身が禁煙するのはもちろんのこと、喫煙していない方も周囲の環境に注意を払うことが大切です。タバコの煙には、喫煙者が直接吸い込む「主流煙」だけでなく、周囲に拡散される「副流煙」にも多くの有害物質が含まれています。
家庭や職場などに喫煙者がいる場合は、分煙環境を整える、喫煙スペースに近づかないなど、受動喫煙を避ける対策を講じましょう。
手足を冷やさない
バージャー病では末梢の血流が悪くなるため、特に冷えに注意が必要です。
特に寒い季節や冷房の効いた室内では、知らないうちに血流が悪化しやすくなります。以下のような工夫で、手足を温かく保ちましょう。
- 靴下や手袋を重ねて着用する
- 就寝前に湯船でしっかり温まる
- 外出時は手足の露出を避ける服装を選ぶ
手足の冷えは、バージャー病の症状悪化に直結するため、日頃から意識的に温める習慣を持つことが大切です。
なお「冷えていないのに手足が冷たく感じる」場合の対処法は、こちらの記事でも詳しく解説しています。あわせて参考にしてみてください。
生活習慣病の治療を適切に受ける
糖尿病・高血圧・高脂血症といった生活習慣病は、いずれも末梢血流の悪化を進める要因となります。
糖尿病は血管にダメージを与え、高血圧や高脂血症は動脈硬化を進行させます。これらの病気を治療せずに放置すると、バージャー病の進行を早めたり、合併症を引き起こしたりするリスクが高まります。
そのため、生活習慣病の治療中の方は、医師の指導のもとで食事や運動などの生活習慣を見直し、必要に応じて薬を正しく服用することが大切です。
また、生活習慣病は初期には自覚症状がないことも多いため、症状がなくても年に1回程度の定期的な健康診断を受けるようにしましょう。
バージャー病は早期発見と禁煙が進行抑制のカギ
バージャー病は、手足の血管が詰まる進行性の難病であり、主な原因は喫煙とされています。初期には足のしびれや冷えといった症状から始まり、最悪の場合には手足の切断に至ることもあるため、早期対応が重要です。
バージャー病の予防や進行抑制には、禁煙と早期発見が不可欠です。本記事を参考にし、気になる症状がある場合は、速やかに専門医の診察・治療を受けましょう。
当院「リペアセルクリニック」では、もともと人体にある幹細胞を用いた再生医療による治療を行っております。メール相談やオンラインカウンセリングを通じて無料相談も受付中です。
バージャー病の治療方針に悩まれている方は、お気軽に当院までご相談ください。
\無料オンライン診断実施中!/
バージャー病に関してよくある質問
閉塞性動脈硬化症(ASO)との違いは?
バージャー病と閉塞性動脈硬化症(ASO)には、以下のような違いがあります。(文献4)(文献5)
|
バージャー病 |
閉塞性動脈硬化症(ASO) |
|
|---|---|---|
|
主な発症年齢 |
若年層(特に喫煙者) |
高齢者が中心 |
|
最大のリスク要因 |
喫煙 (生活習慣病も影響することあり) |
動脈硬化(糖尿病・高血圧・高脂血症などの生活習慣病) |
|
影響が出やすい血管の場所 |
手足の細い血管に断続的に発生 |
比較的太い血管に広範囲に発生 |
|
血管の状態 |
血管壁が炎症を起こして閉塞 |
血管壁が硬化し閉塞 |
鑑別には、年齢、喫煙歴、他の生活習慣病の有無などが用いられます。
バージャー病は何科で見てもらえるの?
バージャー病の症状が疑われる場合は、血管外科、循環器内科、または膠原病内科での診療が可能です。
お住まいの地域に血管外科や循環器内科がない場合や、どの科を受診すべきか迷うときは、まずはかかりつけ医や総合診療科を受診することをおすすめします。
いずれの場合も、不安な症状がある場合は早めに医療機関を受診し、必要に応じて専門医の診察を受けることが大切です。
参考文献